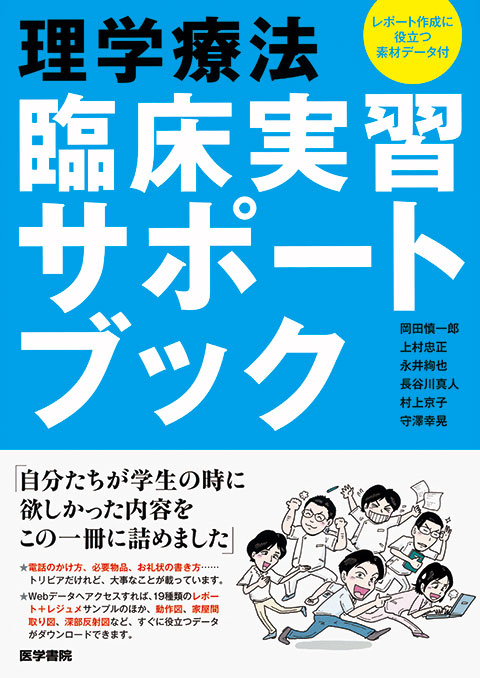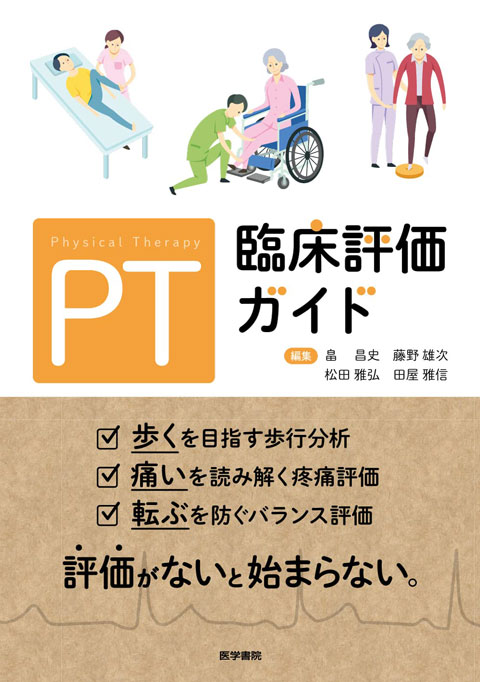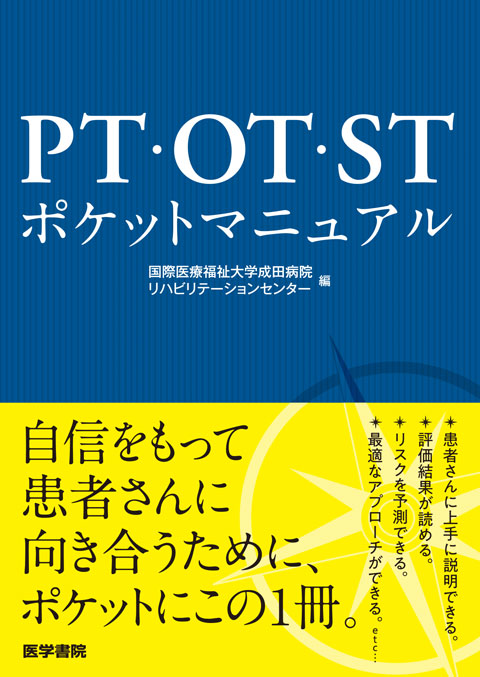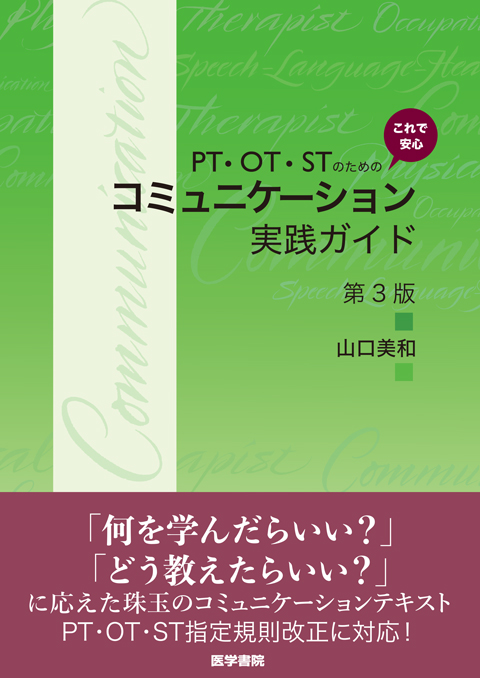理学療法 臨床実習サポートブック
レポート作成に役立つ素材データ付
理学療法士を目指す学生の臨地実習をトータルにサポートするガイドブック
もっと見る
学生が苦戦する臨床実習でフル活用できる実習の手引書。実習の流れを概観した後、デイリーやレポートを書くためのノウハウを、経験者ならではの視点でアドバイスする。お礼状の書き方をはじめ、コミュニケーションのコツや危機克服Q&Aも役に立つ。作成者のアドバイス付のレポート19種類、そして「歩行図」「動作図」「姿勢図」「反射図」もコピーが可能な形式でWebからアクセス可能。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
- サポート情報
序文
開く
ちょっと長いまえがき 後輩の皆さんへ届けたいもの(岡田慎一郎)
理学療法士の臨床実習を経験した人が集まると、みんな口をそろえて「とにかくきつかった」と言います。当時の体験がよみがえり、まるで戦友のように実習話で盛り上がります。
この本は、実習を客観的に見ることができるようになった私たち先輩の立場から、理学療法士の実習をいかに乗り切るかについて、戦略的・効率的なノウハウを紹介しようと試みる企画です。
●実習の本来の目的に戻ろう
連日徹夜も当たり前、と言われる理学療法士の臨床実習ですが、実習中はレポート、日誌など、“書き物”に意識が集中してしまい、目の前の患者さんが二の次になってしまいがちです。本来、実習とは「患者さんと向き合い、リハビリを考察しつつ、実際に動く体験をする」のが目的だと思います。徹夜することで患者さんへのリハビリがより良いものになるのなら徹夜もアリだと思いますが、寝ていなければ正常な判断力を失い、実習ならではの体験に集中できなくなってしまいます。それでは本末転倒です。
実習は、学校にもよりますが、3年生で1回、4年生で2回、最長2か月弱というスケジュールで行われるものです。そんな長丁場なのですから、徹夜ばかりしてそれを誇るような悪しき習慣はなくなるべきだと思っています。
●備えあれば
では、なぜ学生さんが徹夜のような状況に追い込まれるのかというと、それは「探し物」「調べ物」に膨大な時間がかかっていること、そして、いろいろな予備知識、“備え”が不足したまま実習の場に赴いているためではないかと思います。
“備え”というのは、具体的な「物」もそうですし、「人としてのマナー」や「精神的な準備」も含みますし、「情報」も備えの1つですね。例えば「実習ではこんなことが要求されますよ。それはこういう意味なんですよ」といったことがわかって臨むのと知らないで臨むのとでは、実習の質が違ってきます。
準備がちょっと不足していたがために、本来持っている自分の長所、可能性が発揮できず、不全感をかかえたまま実習が終わってしまうのは残念すぎます。どうせ判定されるのならば、自分が持っているものをちゃんと出して、やれるだけやったと思える内容で評価を受けたいものです。
そこで、この本には私たちが自分の実習期間のことをできるだけ細かく思い出しながら、「もしあの時“これ”があったら自分は助かったろうな」「“これ”をしていたらもう少し楽だっただろうな」と思う“もの”と“こと”を網羅していくことにしました。
●私たちもいろんな体験をしました
人は視野狭窄に陥った時に、鬱になったり、もうダメだと思い込んだりします。例えば、4年生での最後の実習、これで落ちたら……と思うと、追い詰められてどんどんおかしな思考になっていきます。
この本の著者6人も、それぞれ実習ではいろんな経験をしました。そんな経験を紹介していますので、読んでもらえば、「ああ自分だけじゃないんだ」「この人よりはマシだ」と思えたりして、視野が少し広がるかもしれません。
僕自身も紆余曲折ありました。人生スムーズに来たわけではありません。実習のために1年留年もしました。そうしたことも含めていろんなことが自分の肥やしになって今につながっていると思っています(留年したって命が取られるわけじゃあないですし!)。
●仕事の場は医療施設に限らない
著者6人は今では理学療法士の資格を持ち、いろいろな職場で働いています。
6人のうち、一貫して病院や施設に勤務しているのは半数。あとの3人は、「え? 理学療法士でそんな仕事もあるの?」というような、一風変わった働き方を経験しています(6章でそれを紹介しています)。僕のようなどこにも所属しない自由業だとルーチンワークは少なく、日々違った場所に出向き、日々の仕事を自分で作り出していくような生活ですが、人との出会いがたくさんあり、飽きるということがありません。
何が言いたいのかというと、「理学療法士の職場は病院や施設だけではない」ということなのです。もし「病院や施設しかないんだ」と思い込んで実習に臨むと、病院や施設があなたにとって働きたい環境に思えなかった場合に、資格を取るモチベーションが保ちにくくなってしまいますよね。だから理学療法士の資格を取ると想像以上に仕事にいろいろな幅が生まれる、ということも、この本では紹介していきたいと思っています。
もちろん病院や施設を職場にしていない僕を含めた2人も、自分の活動のベースに理学療法士の学校で習ったことや、資格を取るうえで勉強したことがいい経験になっている事実には変わりありません。そして普段はあまり意識していませんが、「自分は理学療法士という資格を持っている」ということが、自分の仕事を説明する際や、何かを思考する際の拠りどころになっています。
●これが評価表だ!
さて、ここでちょっと話は飛ぶように思うかもしれませんが、実習の成績表である「臨床実習評価表」を紹介したいと思います。
なぜこれを冒頭で紹介するかというと、実習のゴール、つまり「こういう評価項目に沿って実習をやっているのですよ」ということを、実習前に知っておいたほうがいいと思うからです。このゴールを知りながら実習を行うのと、知らずにやみくもに行うのとでは、実習中の思考法や動き方が違ってくると思うのです。
臨床実習評価表は、日本理学療法士協会発行の『臨床実習教育の手引き 第5版』で目安が示されているのですが、それをもとに学校ごとに作成しているので、目標項目や評価者が記入する欄の形式などは学校によって違います。ただこの手引きには、次の「3つの領域」を踏まえて評価表の目標項目を設定するよう記されていますので、評価する際の骨子は同じになると言えます。
目標項目とすべき「3つの領域」は次のようになっています。
さて、それでは臨床実習評価表がどんなものなのかを見てみましょう。
最初は、現在病院で理学療法士として働く守澤幸晃さんが作成してくれたものです。彼は現在、実習生を受け入れる立場になっている人なので、複数の学校の臨床実習評価表から平均的なものと思われるものを作成してくれました。
臨床実習評価表の例 (本サイトでは省略)
守澤さんと上村さんの臨床実習評価表、いかがでしたか(私なんかはいまだにこれを見ると妙な汗が出てきますが)。
学校によって、評価表にはバリエーションがあるということがわかりましたね。守澤さんが示してくれた評価表のコメント欄からは、臨床実習指導者がどういう観点で学生を見て、どういう思いを抱きながら指導しているかが読み取れると思います。また、上村さんの1回目の評価表からは、実習1回目の辛口なコメントと、しかしその裏にある臨床実習指導者の思いを感じることができると思います。そして上村さんが奮起し、2回目に「良」の総合判定をもらえたことがなにより読者の皆さんの希望になるんじゃないかと思い、上村さんの評価表は1回目も2回目も紹介させていただいたというわけです。
こんなふうに、この本では、できるだけ実習のリアルな現実に迫りながらアドバイスを盛り込んでいきたいと思っています。この本のなかに、あなたが実習を乗り切るために1つでも参考になるものが見つかったなら、そして少しでも助けになる部分があったなら、著者の1人としてこんなに嬉しいことはありません。
理学療法士の臨床実習を経験した人が集まると、みんな口をそろえて「とにかくきつかった」と言います。当時の体験がよみがえり、まるで戦友のように実習話で盛り上がります。
この本は、実習を客観的に見ることができるようになった私たち先輩の立場から、理学療法士の実習をいかに乗り切るかについて、戦略的・効率的なノウハウを紹介しようと試みる企画です。
●実習の本来の目的に戻ろう
連日徹夜も当たり前、と言われる理学療法士の臨床実習ですが、実習中はレポート、日誌など、“書き物”に意識が集中してしまい、目の前の患者さんが二の次になってしまいがちです。本来、実習とは「患者さんと向き合い、リハビリを考察しつつ、実際に動く体験をする」のが目的だと思います。徹夜することで患者さんへのリハビリがより良いものになるのなら徹夜もアリだと思いますが、寝ていなければ正常な判断力を失い、実習ならではの体験に集中できなくなってしまいます。それでは本末転倒です。
実習は、学校にもよりますが、3年生で1回、4年生で2回、最長2か月弱というスケジュールで行われるものです。そんな長丁場なのですから、徹夜ばかりしてそれを誇るような悪しき習慣はなくなるべきだと思っています。
●備えあれば
では、なぜ学生さんが徹夜のような状況に追い込まれるのかというと、それは「探し物」「調べ物」に膨大な時間がかかっていること、そして、いろいろな予備知識、“備え”が不足したまま実習の場に赴いているためではないかと思います。
“備え”というのは、具体的な「物」もそうですし、「人としてのマナー」や「精神的な準備」も含みますし、「情報」も備えの1つですね。例えば「実習ではこんなことが要求されますよ。それはこういう意味なんですよ」といったことがわかって臨むのと知らないで臨むのとでは、実習の質が違ってきます。
準備がちょっと不足していたがために、本来持っている自分の長所、可能性が発揮できず、不全感をかかえたまま実習が終わってしまうのは残念すぎます。どうせ判定されるのならば、自分が持っているものをちゃんと出して、やれるだけやったと思える内容で評価を受けたいものです。
そこで、この本には私たちが自分の実習期間のことをできるだけ細かく思い出しながら、「もしあの時“これ”があったら自分は助かったろうな」「“これ”をしていたらもう少し楽だっただろうな」と思う“もの”と“こと”を網羅していくことにしました。
●私たちもいろんな体験をしました
人は視野狭窄に陥った時に、鬱になったり、もうダメだと思い込んだりします。例えば、4年生での最後の実習、これで落ちたら……と思うと、追い詰められてどんどんおかしな思考になっていきます。
この本の著者6人も、それぞれ実習ではいろんな経験をしました。そんな経験を紹介していますので、読んでもらえば、「ああ自分だけじゃないんだ」「この人よりはマシだ」と思えたりして、視野が少し広がるかもしれません。
僕自身も紆余曲折ありました。人生スムーズに来たわけではありません。実習のために1年留年もしました。そうしたことも含めていろんなことが自分の肥やしになって今につながっていると思っています(留年したって命が取られるわけじゃあないですし!)。
●仕事の場は医療施設に限らない
著者6人は今では理学療法士の資格を持ち、いろいろな職場で働いています。
6人のうち、一貫して病院や施設に勤務しているのは半数。あとの3人は、「え? 理学療法士でそんな仕事もあるの?」というような、一風変わった働き方を経験しています(6章でそれを紹介しています)。僕のようなどこにも所属しない自由業だとルーチンワークは少なく、日々違った場所に出向き、日々の仕事を自分で作り出していくような生活ですが、人との出会いがたくさんあり、飽きるということがありません。
何が言いたいのかというと、「理学療法士の職場は病院や施設だけではない」ということなのです。もし「病院や施設しかないんだ」と思い込んで実習に臨むと、病院や施設があなたにとって働きたい環境に思えなかった場合に、資格を取るモチベーションが保ちにくくなってしまいますよね。だから理学療法士の資格を取ると想像以上に仕事にいろいろな幅が生まれる、ということも、この本では紹介していきたいと思っています。
もちろん病院や施設を職場にしていない僕を含めた2人も、自分の活動のベースに理学療法士の学校で習ったことや、資格を取るうえで勉強したことがいい経験になっている事実には変わりありません。そして普段はあまり意識していませんが、「自分は理学療法士という資格を持っている」ということが、自分の仕事を説明する際や、何かを思考する際の拠りどころになっています。
●これが評価表だ!
さて、ここでちょっと話は飛ぶように思うかもしれませんが、実習の成績表である「臨床実習評価表」を紹介したいと思います。
なぜこれを冒頭で紹介するかというと、実習のゴール、つまり「こういう評価項目に沿って実習をやっているのですよ」ということを、実習前に知っておいたほうがいいと思うからです。このゴールを知りながら実習を行うのと、知らずにやみくもに行うのとでは、実習中の思考法や動き方が違ってくると思うのです。
臨床実習評価表は、日本理学療法士協会発行の『臨床実習教育の手引き 第5版』で目安が示されているのですが、それをもとに学校ごとに作成しているので、目標項目や評価者が記入する欄の形式などは学校によって違います。ただこの手引きには、次の「3つの領域」を踏まえて評価表の目標項目を設定するよう記されていますので、評価する際の骨子は同じになると言えます。
目標項目とすべき「3つの領域」は次のようになっています。
| 領域1: | 理学療法に対する「知識」を理解し、それを利用して「問題解決」できる能力(=認知領域) |
| 領域2: | 理学療法の「技術」を模倣、吸収し、その技術を高める能力(=精神運動領域) |
| 領域3: | 理学療法士の仕事や役割を理解したうえで、それに対して取るべき「態度」や行動を起こす能力(=情意領域) |
さて、それでは臨床実習評価表がどんなものなのかを見てみましょう。
最初は、現在病院で理学療法士として働く守澤幸晃さんが作成してくれたものです。彼は現在、実習生を受け入れる立場になっている人なので、複数の学校の臨床実習評価表から平均的なものと思われるものを作成してくれました。
臨床実習評価表の例 (本サイトでは省略)
守澤さんと上村さんの臨床実習評価表、いかがでしたか(私なんかはいまだにこれを見ると妙な汗が出てきますが)。
学校によって、評価表にはバリエーションがあるということがわかりましたね。守澤さんが示してくれた評価表のコメント欄からは、臨床実習指導者がどういう観点で学生を見て、どういう思いを抱きながら指導しているかが読み取れると思います。また、上村さんの1回目の評価表からは、実習1回目の辛口なコメントと、しかしその裏にある臨床実習指導者の思いを感じることができると思います。そして上村さんが奮起し、2回目に「良」の総合判定をもらえたことがなにより読者の皆さんの希望になるんじゃないかと思い、上村さんの評価表は1回目も2回目も紹介させていただいたというわけです。
こんなふうに、この本では、できるだけ実習のリアルな現実に迫りながらアドバイスを盛り込んでいきたいと思っています。この本のなかに、あなたが実習を乗り切るために1つでも参考になるものが見つかったなら、そして少しでも助けになる部分があったなら、著者の1人としてこんなに嬉しいことはありません。
目次
開く
ちょっと長いまえがき 後輩の皆さんへ届けたいもの
[コラム] 理学療法士の学校を選ぶ際に見るべきポイントは?
第1章 実習全体の流れを紹介します
1.実習前に実習指導者へ電話をかけます
2.実習前に準備すべき物と事
3.実習が始まったら
4.(気が早いですが)お礼状はいつ出すのか。お礼状の書き方
[コラム] 先輩たちが学生に望むもの、最上位は「一般常識」です
第2章 デイリーノート、デイリーアクションシート(ポートフォリオ方式)の書き方
1.デイリーノートの書き方
2.デイリーアクションシート(ポートフォリオ方式)の書き方
[コラム] ポートフォリオが採用されるようになった背景とメリット
第3章 症例レポート(ケースレポート)を書くための準備とノウハウ
1.症例レポートとは何か。どのように書けばいいのか
2.「統合と解釈」の考え方
3.症例レポート作成を助ける便利なノウハウ
●薬剤の調べ方
●論文の探し方
●エビデンスが見つかりやすい日本理学療法士学会の診療ガイドライン
●家族構成・相関図の描き方
●動作・姿勢の描き方
(1)起居・移動動作 (2)反射検査
(3)背臥位から立位に至るまでの代表的な動作
(4)歩行動作 (5)臥位とその応用姿勢
●デジタルカメラによる撮影方法
[コラム] レポートに行き詰まったら、「患者さんの求めている目標」に立ち返りましょう
[コラム] KJ法を使うことがあります
[コラム] たくさん本は持っていきましたが……
[コラム] 論文はあくまで、自分の結論を導くための「素材」です
第4章 住環境情報と整備の考え方
1.「住環境」情報の活かし方
2.「家屋調査報告書」の例を紹介します
3.疾患別・障害別にみた住環境整備の考え方
●脳血管障害の場合
●関節リウマチの場合
●骨折の場合
●パーキンソン病の場合
●脊髄損傷の場合
●頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷の場合
[コラム] 自助具について
第5章 先輩たちが書いた症例レポート+レジュメ
ご案内
右大腿骨転子部骨折によりγ-nailを施行した90歳代の女性
左変形性膝関節症を呈し、左人工膝関節置換術が施された症例
第6章 コミュニケーションのコツ、お悩みQ&A、就職先など
1.臨床実習指導者とのコミュニケーションを円滑にするコツ
2.どう考えたらいい? 実習中のあんなこと、こんなことQ&A
3.理学療法士の就職先はいろいろあります
●一般病院
●介護老人保健施設
●介護付き有料老人ホーム、通所介護(デイサービス)
●個人事業主
●所属せずに自由業─講演、執筆、企業アドバイザー、その他いろいろ
●就職先いろいろ─私の経験から
[コラム] 雑談力はとても重要/上手にストレスマネジメントを/
飲みニケーション & 食べニケーションの楽しみ方
[コラム] 臨床実習指導者を経験した私が今思うこと
[コラム] 実習は、臨床実習指導者も成長する機会です
おわりに
危機別便利索引
実習あるあるマンガ
[コラム] 理学療法士の学校を選ぶ際に見るべきポイントは?
第1章 実習全体の流れを紹介します
1.実習前に実習指導者へ電話をかけます
2.実習前に準備すべき物と事
3.実習が始まったら
4.(気が早いですが)お礼状はいつ出すのか。お礼状の書き方
[コラム] 先輩たちが学生に望むもの、最上位は「一般常識」です
第2章 デイリーノート、デイリーアクションシート(ポートフォリオ方式)の書き方
1.デイリーノートの書き方
2.デイリーアクションシート(ポートフォリオ方式)の書き方
[コラム] ポートフォリオが採用されるようになった背景とメリット
第3章 症例レポート(ケースレポート)を書くための準備とノウハウ
1.症例レポートとは何か。どのように書けばいいのか
2.「統合と解釈」の考え方
3.症例レポート作成を助ける便利なノウハウ
●薬剤の調べ方
●論文の探し方
●エビデンスが見つかりやすい日本理学療法士学会の診療ガイドライン
●家族構成・相関図の描き方
●動作・姿勢の描き方
(1)起居・移動動作 (2)反射検査
(3)背臥位から立位に至るまでの代表的な動作
(4)歩行動作 (5)臥位とその応用姿勢
●デジタルカメラによる撮影方法
[コラム] レポートに行き詰まったら、「患者さんの求めている目標」に立ち返りましょう
[コラム] KJ法を使うことがあります
[コラム] たくさん本は持っていきましたが……
[コラム] 論文はあくまで、自分の結論を導くための「素材」です
第4章 住環境情報と整備の考え方
1.「住環境」情報の活かし方
2.「家屋調査報告書」の例を紹介します
3.疾患別・障害別にみた住環境整備の考え方
●脳血管障害の場合
●関節リウマチの場合
●骨折の場合
●パーキンソン病の場合
●脊髄損傷の場合
●頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷の場合
[コラム] 自助具について
第5章 先輩たちが書いた症例レポート+レジュメ
ご案内
右大腿骨転子部骨折によりγ-nailを施行した90歳代の女性
左変形性膝関節症を呈し、左人工膝関節置換術が施された症例
第6章 コミュニケーションのコツ、お悩みQ&A、就職先など
1.臨床実習指導者とのコミュニケーションを円滑にするコツ
2.どう考えたらいい? 実習中のあんなこと、こんなことQ&A
3.理学療法士の就職先はいろいろあります
●一般病院
●介護老人保健施設
●介護付き有料老人ホーム、通所介護(デイサービス)
●個人事業主
●所属せずに自由業─講演、執筆、企業アドバイザー、その他いろいろ
●就職先いろいろ─私の経験から
[コラム] 雑談力はとても重要/上手にストレスマネジメントを/
飲みニケーション & 食べニケーションの楽しみ方
[コラム] 臨床実習指導者を経験した私が今思うこと
[コラム] 実習は、臨床実習指導者も成長する機会です
おわりに
危機別便利索引
実習あるあるマンガ
| 雪の日に… 実録!ある日の実習密着24時間 花は咲く 書かなくていい…? バイザーの仕事はオレの仕事?! 覚悟の実習生 遅刻防止のコツ 寝ない演技で乗り切れ! 涙のインスタントラーメン 連休中に遊びに行ったら… ものまね卒業試験 別れのベルは突然に | 感涙の刺しゅうハンカチ 孫に似ているので オレ流のカウントダウン だんじり指令 屋号って何? 方言コミュニケーション モテる実習生はツライよ?! 思わず号泣 頑張る力 逆境に咲く恋の花 北の国から 気分はもう戦友 |
書評
開く
先輩の経験や思いが詰まった待望の一冊
書評者: 前野 竜太郎 (常葉大准教授・理学療法学)
「自分たちが学生の時に欲しかった内容をこの一冊に詰めました」という言葉が,この書籍の帯に記されている。この本のコンセプトはまさにここにある。臨床実習という,学生にとっての最難関科目において,生きるか死ぬかの苦労をされた先輩の経験や思いが詰まった,現役の学生さんや社会人学生さん向けの待望の一冊と言える。
この本は,実習生なら必ず1週間前に行わないといけない臨床実習指導者への連絡や,実習に向けての必要物品の確認から始まり,バイザーおよびスタッフとのコミュニケーションの取り方,デイリーノートの書き方,わからない臨床上の疑問への対応,そしてレポートの作成方法,発表レジュメの作成方法,最後に実習終了後のお礼状の書き方まで,学生が施設で実習を始めようとするとき,「どうしよう,わからない!」と不安になることへ,できる限り応えようとしている労作である。
ただし,ここまで懇切丁寧に書かれた一冊をもってしても,臨床実習は甘くはないのが現実である。その原因は,病院・施設ごとに評価治療の基準の細部に独自性があり,その異なる基準の中に,外部から実習生として入り,短い時間で適応していかないといけないからである。よって,臨床実習を進める上で一番問題になるのは,多くの場合,実習生と,バイザーを中心とした医療スタッフとのコミュニケーションである。これは,バイザーがいかに感じているか,そしてそれを実習生の側が感じとることができるか,という,なかなか説明が難しい感性の問題でもある。その辺りの感性の世界の一端も,この本では,漫画も含めてわかりやすく紹介されている。
臨床実習の本質は,医療の世界,ひいては理学療法の世界に入るために必ず身につけないといけない儀式・儀礼をいかに理解し,適応し,加えて行動に移すか,にある。独特な医療文化をくぐり抜けることなしに,一足飛びに医療人,そして理学療法士になるのは不可能である。もし学生さんたちが,医療系の「社会人」というものがどんなものか知りたいのであれば,この医療の世界独特の通過儀礼を知ることが必須である。
社会人学生を含め学生にとって大切なのは,それまで学んできたこと,自らのこだわりや自我といったものを,いったんカッコにくくって脇に置き,指導者に従ってみることである。それが実習をうまく運ぶ一番の近道なのかもしれない。臨床実習は,終わってみれば,ほんの通過点にすぎない。これで人生が全て決まるわけではないし,生死が決まるわけでもない。もしさまざまなよしなしごとで,理不尽を感じ,疑問に思ったことがあったとしても,バイザーに合わせて頭の中で上手に整理し,対応できればそれが一番であろう。まずは,常に何かを学ぼうとする意欲と,日々の誠実な対応を忘れないよう心がけよう。そうして苦闘する日々の中で,思わぬところでこの労作が支えてくれるかもしれない。この本をひもといたとき,何かがひらめいてくるかもしれない,そんな一冊である。
最後に。臨床実習指導者の皆さま,この書籍をぜひ参照いただき,日々誠実に学ぼうとしている実習生を,時には優しい大きな背中で見守ってあげてください。皆さんの学生時代を思い出しつつ。
実習に不安な学生や悩む指導者には,必見の一冊
書評者: 藤井 顕 (藤リハビリテーション学院副学院長)
私はこの本を,理学療法士を養成する学校の立場で読んだ。
理学療法士養成課程では,総単位の2割前後を臨床実習が占めている。学生は実習地において3~4週間の短期実習,8~10週間の長期実習に臨み,評価または治療を中心にさまざまな形で臨床実習を展開する。
本書は,理学療法士をめざす学生のガイドブックとして,臨床実習をフルにサポートする内容である。著者たちが臨床実習で苦労した自分たち自身の経験を踏まえて,「学生のときにこれが欲しかった」と思うあらゆる情報やアドバイスを網羅している。
どのような内容なのか,いくつか例を挙げよう。
実習には荷物として何をどれだけ準備し,持っていけばよいかということは学校でもオリエンテーションを行うが,この本ではそれがさらに学生目線で一段深く生活に根ざしてアドバイスされており,イラストも使ってあるので学生はリアルにイメージできるだろう。
また,「実習指導者への電話のかけ方フローチャート」や「お礼状の書き方」もサンプル付きで紹介されている。学校のカリキュラムではこうしたことの指導まではとても手が回らない状況があるので,社会的対応に不慣れな学生には一つのサンプルとして示す価値があるだろう。
「デイリーノート」「デイリーアクションシート」「症例レポート」の実例が掲載されているが,この本には要所要所に,その作成者ならではの“生のコメント”が挟み込まれている。それにより学生は,実習指導者からどのような指導があったのか,またどのように考えて切り抜けたのか,という裏話を知ることができる。こういったエピソードは学生が実際に難局を切り抜けようという場面で助けになるだろう。
また,レポート作成に便利な動作図・反射図のデータがWebからダウンロードできる付録が付いている点も注目される。この付録を使いこなすことができれば省力化と時間の節約になるのではないかと思う。これは本書の冒頭で著者が書くように,実習というのは書き物ばかりに集中するのではなく,患者さんと向き合い,リハビリを考察しつつ,実際に動く体験をするためのもの,という考えに基づく付録だと理解する。
最終章では,先輩から後輩へのアドバイスとして,コミュニケーションのこつ・お悩みQ&A,また就職先として,理学療法士の資格を取った後,病院・その他多方面で活躍する著者らの活動の場が紹介されている。
この本を最後まで読み終えて,私が感じたのは“学生が納得できる実習を経験できるように”との著者らの切なる願いだった。マンガも使ってあるのでこの本は一見すると軽い本に思えるかもしれないが,読み進めてみれば,学生を相当実際的に助けるであろう内容の濃い一冊だとわかる。理学療法士の本は高額なものが多いなか,抑えた値段設定も学生には嬉しいはずだ。
書評者: 前野 竜太郎 (常葉大准教授・理学療法学)
「自分たちが学生の時に欲しかった内容をこの一冊に詰めました」という言葉が,この書籍の帯に記されている。この本のコンセプトはまさにここにある。臨床実習という,学生にとっての最難関科目において,生きるか死ぬかの苦労をされた先輩の経験や思いが詰まった,現役の学生さんや社会人学生さん向けの待望の一冊と言える。
この本は,実習生なら必ず1週間前に行わないといけない臨床実習指導者への連絡や,実習に向けての必要物品の確認から始まり,バイザーおよびスタッフとのコミュニケーションの取り方,デイリーノートの書き方,わからない臨床上の疑問への対応,そしてレポートの作成方法,発表レジュメの作成方法,最後に実習終了後のお礼状の書き方まで,学生が施設で実習を始めようとするとき,「どうしよう,わからない!」と不安になることへ,できる限り応えようとしている労作である。
ただし,ここまで懇切丁寧に書かれた一冊をもってしても,臨床実習は甘くはないのが現実である。その原因は,病院・施設ごとに評価治療の基準の細部に独自性があり,その異なる基準の中に,外部から実習生として入り,短い時間で適応していかないといけないからである。よって,臨床実習を進める上で一番問題になるのは,多くの場合,実習生と,バイザーを中心とした医療スタッフとのコミュニケーションである。これは,バイザーがいかに感じているか,そしてそれを実習生の側が感じとることができるか,という,なかなか説明が難しい感性の問題でもある。その辺りの感性の世界の一端も,この本では,漫画も含めてわかりやすく紹介されている。
臨床実習の本質は,医療の世界,ひいては理学療法の世界に入るために必ず身につけないといけない儀式・儀礼をいかに理解し,適応し,加えて行動に移すか,にある。独特な医療文化をくぐり抜けることなしに,一足飛びに医療人,そして理学療法士になるのは不可能である。もし学生さんたちが,医療系の「社会人」というものがどんなものか知りたいのであれば,この医療の世界独特の通過儀礼を知ることが必須である。
社会人学生を含め学生にとって大切なのは,それまで学んできたこと,自らのこだわりや自我といったものを,いったんカッコにくくって脇に置き,指導者に従ってみることである。それが実習をうまく運ぶ一番の近道なのかもしれない。臨床実習は,終わってみれば,ほんの通過点にすぎない。これで人生が全て決まるわけではないし,生死が決まるわけでもない。もしさまざまなよしなしごとで,理不尽を感じ,疑問に思ったことがあったとしても,バイザーに合わせて頭の中で上手に整理し,対応できればそれが一番であろう。まずは,常に何かを学ぼうとする意欲と,日々の誠実な対応を忘れないよう心がけよう。そうして苦闘する日々の中で,思わぬところでこの労作が支えてくれるかもしれない。この本をひもといたとき,何かがひらめいてくるかもしれない,そんな一冊である。
最後に。臨床実習指導者の皆さま,この書籍をぜひ参照いただき,日々誠実に学ぼうとしている実習生を,時には優しい大きな背中で見守ってあげてください。皆さんの学生時代を思い出しつつ。
実習に不安な学生や悩む指導者には,必見の一冊
書評者: 藤井 顕 (藤リハビリテーション学院副学院長)
私はこの本を,理学療法士を養成する学校の立場で読んだ。
理学療法士養成課程では,総単位の2割前後を臨床実習が占めている。学生は実習地において3~4週間の短期実習,8~10週間の長期実習に臨み,評価または治療を中心にさまざまな形で臨床実習を展開する。
本書は,理学療法士をめざす学生のガイドブックとして,臨床実習をフルにサポートする内容である。著者たちが臨床実習で苦労した自分たち自身の経験を踏まえて,「学生のときにこれが欲しかった」と思うあらゆる情報やアドバイスを網羅している。
どのような内容なのか,いくつか例を挙げよう。
実習には荷物として何をどれだけ準備し,持っていけばよいかということは学校でもオリエンテーションを行うが,この本ではそれがさらに学生目線で一段深く生活に根ざしてアドバイスされており,イラストも使ってあるので学生はリアルにイメージできるだろう。
また,「実習指導者への電話のかけ方フローチャート」や「お礼状の書き方」もサンプル付きで紹介されている。学校のカリキュラムではこうしたことの指導まではとても手が回らない状況があるので,社会的対応に不慣れな学生には一つのサンプルとして示す価値があるだろう。
「デイリーノート」「デイリーアクションシート」「症例レポート」の実例が掲載されているが,この本には要所要所に,その作成者ならではの“生のコメント”が挟み込まれている。それにより学生は,実習指導者からどのような指導があったのか,またどのように考えて切り抜けたのか,という裏話を知ることができる。こういったエピソードは学生が実際に難局を切り抜けようという場面で助けになるだろう。
また,レポート作成に便利な動作図・反射図のデータがWebからダウンロードできる付録が付いている点も注目される。この付録を使いこなすことができれば省力化と時間の節約になるのではないかと思う。これは本書の冒頭で著者が書くように,実習というのは書き物ばかりに集中するのではなく,患者さんと向き合い,リハビリを考察しつつ,実際に動く体験をするためのもの,という考えに基づく付録だと理解する。
最終章では,先輩から後輩へのアドバイスとして,コミュニケーションのこつ・お悩みQ&A,また就職先として,理学療法士の資格を取った後,病院・その他多方面で活躍する著者らの活動の場が紹介されている。
この本を最後まで読み終えて,私が感じたのは“学生が納得できる実習を経験できるように”との著者らの切なる願いだった。マンガも使ってあるのでこの本は一見すると軽い本に思えるかもしれないが,読み進めてみれば,学生を相当実際的に助けるであろう内容の濃い一冊だとわかる。理学療法士の本は高額なものが多いなか,抑えた値段設定も学生には嬉しいはずだ。