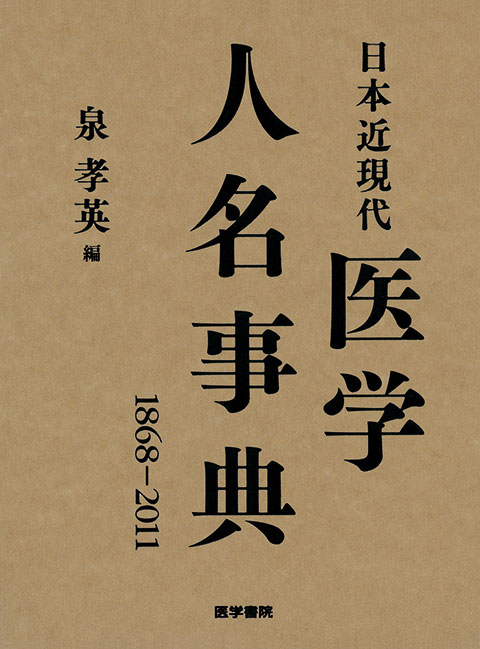日本近現代医学人名事典
【1868-2011】
わが国の医学・医療の礎を築いた故人の業績を集大成
もっと見る
明治・大正・昭和・平成の140年間余(1868~2011年)において、わが国の医学・医療の発展に貢献した3,762名(故人)の業績を整理・収載した人名事典。医師、看護師、薬剤師、療法士、検査技師など医療専門職を中心に、著名な患者、社会事業家、出版人など周辺領域で尽力したひとびとも選定した。付録に関連年表・書名索引(全10,055タイトル)を収載。
| 編 | 泉 孝英 |
|---|---|
| 発行 | 2012年12月判型:A5頁:810 |
| ISBN | 978-4-260-00589-0 |
| 定価 | 13,200円 (本体12,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 序文
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
・本事典が第26回矢数医史学賞を受賞!
2014年5月31日、第26回矢数医史学賞授賞式が、第115回日本医史学会総会・学術総会(福岡県太宰府市。理事長=小曽戸洋)にて開催され、泉孝英氏(京都大学名誉教授)の 『日本近現代医学人名事典 【1868-2011】』(医学書院)が選ばれました。同賞は故・矢数道明氏寄贈の基金により設けられ、医学の歴史研究上で優れた業績に対し授与されています。
・一版社団法人 日本医史学会の賞について
・『週刊医学界新聞』 関連記事(第3084号 2014年07月14日)
・『週刊医学界新聞』〔寄稿〕近代医学の145年(泉孝英)(第3008号 2012年12月24日)で取り上げられている長与専斎(1838-1902年)、早石実蔵(1882-1977年)、花房秀三郎(1928-2009年)の本書本文を立ち読みでご覧になれます。
序文
開く
序
本事典は、わが国において西洋医学が公式に採用された慶応4/明治元(1868)年3月から平成23(2011)年末までの約145年間において、わが国の医学・医療に携わり、物故された人物3762名についての記録集である。具体的な記載項目については凡例を参照されたい。
刊行を企画した理由は、医学・医療にかぎらず、すべての人々の仕事は先人の仕事の上に成り立っているとの前提からである。したがって、先人の生き方、考えたこと、成果を記載しておくことは、後世のひとびとが次の仕事を考えるときに、大きな参考になるものであることに疑いを挟む余地はない。
まずお断り、お詫びしておくべきことを記しておきたい。
本事典の編集は、基本的には編者の個人的作業であるので、この期間の中で本書に収載すべきでありながら、掲載されていない人物が少なくはないこと、また正確さに欠ける記載があり得ることを、編者として少なからず懸念していることである。読者、関係各位からの更なる情報提供に期待したい。しかるべき時期の増補・改訂版において、加筆・訂正を行うことを目指している。
本事典の名称は『日本近現代医学人名事典』であり、医学・医療領域を網羅する人名事典たることを志して準備を進めてきた。しかし、平成24年現在の時点において“医学・医療”を広義に捉えるとすれば、看護学・生物学・歯学・薬学・リハビリテーション学、さらに福祉等の領域をも含めるべきであるが、本事典においては、それらの十分な記載が行われたとは判断していない。これまた、各位からの情報提供をお願いしたいところである。
なお編集開始当時には、物故者であるか否かを問わずに編集作業を進めてきた。しかし、さまざまの検討を重ねた結果、記載人物は物故者に限定することとした。資料・情報を提供いただいた各位に陳謝する。
ここで本事典の背景となる基礎事項として、明治元年以来今日まで、わが国における医学・医療のたどった道について、編者なりにまとめた概略を記しておきたい。この約145年間を、大きくは「明治・大正・昭和戦前期」「昭和戦後期」そして「平成期」の3つの時期に区分されると考えている。
明治・大正・昭和戦前期[明治元(1868)年~昭和20(1945)年]
ドイツ医学の公式採用(明治3年)以来、わが国は多数のドイツ人教師を招聘して、主として東京大学、その前身校において医学教育が行われた。卒業生は、全国各地の医学校に赴任してドイツ医学の普及を図った(参考 吉良枝郎『明治期におけるドイツ医学の受容と普及』、平成22年)。また、明治期を通じて900余名が留学のため渡独している。驚くべきこととして、文部省留学生に代表される公費留学生が250名程度であったのに、650名を超す多数の私費留学生が渡独している。わが国がドイツ医学をいかに熱心に受容しようとしたかがうかがえる。
この時代、ドイツで学んだ技法を駆使して、わが国で数多くの優れた研究が行われた。西欧においては細菌学勃興の時期である。病原菌発見の歴史は、明治6(1873)年のハンセン(ノルウェー)による「らい菌」の発見に始まり、明治15(1882)年にはコッホ(ドイツ)によって結核菌の発見が行われている。わが国においても、ペスト菌の発見(北里柴三郎 明治27年)、赤痢菌の発見(志賀潔 明治30年)が行われている。細菌学の領域だけではない。明治43年に藤浪鑑と稲本亀五郎による移植可能なニワトリ肉腫(藤浪肉腫)の発見、大正4年には山極勝三郎と市川厚一によるタールを用いた人工発癌における世界初の成功などが報告されている。いずれも、がん研究の歴史においてきわめて重要な成果であり、特に、山極・市川の仕事がなぜノーベル生理学・医学賞を受賞できなかったのかについての議論は、今なお続いている。このように、明治・大正期のわが国における医学研究は世界的にも注目された研究が少なくない。まさに、医学にとっても『坂の上の雲』(司馬遼太郎 昭和43年)の時代であった。
一方、医療の面をみれば、明治7年の「医制」発布以来、近代的医療制度の確立が図られたが、この時期はなお、わが国が伝染病(感染症)対策に終始した時代であった。明治初期・中期は、コレラ、赤痢、腸チフスなどの急性伝染病の時代と言える。明治12年のコレラ大流行では、罹患数16万2637人、死者数10万5786人もの驚くべき数字が記録されている。政府は明治9年の天然痘予防規則以来、海港虎列刺病伝染予防規則(明治12年)、伝染病予防規則(明治13年)などの法令を制定して対策に躍起となったが、その制圧には程遠い状況であった。また、慢性伝染病である結核、ハンセン病の制圧を目指しての立法が行われたのは、それぞれ明治も末期の37年、40年に至ってのことである。
この時期、伝染病対策が遅々として進まなかった理由としては、抗菌薬が未開発であったことが挙げられるが、より基本的には、この時期、絶えず起こった戦乱・戦争――慶応4年の戊辰戦争以来、台湾出兵、西南の役、日清戦争、北清事変、日露戦争、シベリア出兵、済南事件、満州事変、日中戦争、そして昭和16年の大東亜戦争――のために多大の軍事費を要し、民生費は乏しく、上下水道といった急性伝染病の防疫上、最低限必要な環境整備すらできなかったことがある。しかし、われわれ日本人が特に好戦的であったわけではない。問題は、明治の開国以来の人口の急増による財政面での圧迫であった。明治3年から昭和15年までの70年間に、日本人はほぼ倍増した。明治元年には、早くも米国(ハワイ・本土)移民が始まり、明治41年にはブラジル移民が始まったが、いずれも相手国から門戸を閉ざされることになり、昭和7年には最後の移民地としての満州移民が開始された流れがある。このなかで、日清、日露戦争の勝利を受けて、わが国は台湾(明治28年)、朝鮮(明治43年)の外地経営に乗り出さざるを得なかった不幸な歴史がある。
昭和20年8月、日本の敗戦を迎えて、内地人口7200万人の国土に、軍人・一般邦人を含めて510万人が加わった。食糧難・住宅難・交通難のなかで、引揚者からのコレラ、発疹チフスなどの急性伝染病の国内への侵入・流行が懸念されたが、10月に厚生省は臨時防疫局を設置して、伝染病に対する水際作戦を展開し、大きな被害を出さないという見事な成果を挙げている。当時の防疫関係者、厚生技官の労苦は、わが国の医療史に明記されておくべきことである。
また、この時代の前後、重要な施策が行われている。「日本医療団」の発足(昭和17年6月)と病院・療養所の国有化政策である。戦時下という状況のなかで強行されたことであるが、「医療国営化・公営化」は、戦時体制の一つとしてではなく、医療の社会化・社会保障としての医療を考える上で、避けて通れない検討課題である。現在、欧州の国民皆保険の国々は、原則、公営医療である。少なくとも、病院は公営である。日本医療団は、米占領軍の意向を受けて昭和22年11月に解散した。そのわずか13年5か月後には、「国民皆保険」である。日本医療団が温存できておれば、現在の医療の混乱も少しは防げたかもしれないと思うと残念なことである。
昭和戦後期[昭和20(1945)年~昭和64(1989)年]
医療史の上でみれば、死因第1位だった結核に代わり、脳血管疾患が死因第1位となった昭和26年から戦後期が始まることになる。昭和戦前期と較べて最も大きな変化は、医学の面では「ドイツ医学から米国医学」への転換であり、医療面では「国民皆保険」の実現(昭和36年)がある。
なぜ、「ドイツ医学から米国医学」であったのか。一つの要因は、二度にわたる世界大戦でいずれもドイツが敗北を喫し、特に第二次世界大戦後、東西に分割されたことによるその国力低下がある。しかし、より大きなことは、昭和24年に開始されたガリオア留学生、28年からのフルブライト留学生として、多数の日本人研究者・医師が米国に向かい、その帰国者によって米国医学が急速にわが国に普及したことである。
ペニシリン、ストレプトマイシンをはじめとする抗菌薬のわが国への導入とその開発・普及によって、伝染病(感染症)は激減した。しかし、抗菌薬だけが感染症を制圧したわけではない。生活環境(居住、大気、上下水道、栄養)、労働環境(職場環境、労働時間の減少)の改善・向上の果たした役割もきわめて大きい。加えて、最大の要因は「国民皆保険化」に代表される医療環境(医療施設、医療機器、薬剤)の整備・充実である。このような戦後の国民生活の向上・環境の改善は、わが国の経済成長、特に昭和30年から48年まで続いた高度経済成長に支えられたことであった。また戦後は、戦争が一度もない国となり、戦前に比較して軍事費が激減したことは、民生費、社会保障費の確保をももたらしたことは、銘記して強調されねばならないことである。
明治初年、国民の平均寿命は男女とも30歳程度であった。そして、大東亜戦争前の昭和15年になっても男46・9歳、女50・0歳の状況であったが、戦後、急速な延びをみせ、平成元年には男75・9歳、女81・8歳に延長した。
感染症に代わって浮上してきたのは、「成人病(脳卒中、がん、心臓病)・生活習慣病」である。昭和32年から開始された成人病対策は、平成8年には“生活習慣病”と名称が変更され、国家的レベルで対策が講じられるようになった。
一方、戦後の医学研究の動向をみると、米国医学の導入にあまりにも忙しく、「日本人は、学問であれ宗教であれ、外国で生まれたものをわが国に移植して自分のものとし、文化を作り上げてきた。必然的に外国産を尊重し、それを持ち込んだ個人をも尊敬した。加えて、外国で生まれたばかりのものを重要だと判断した。このような傾向は日本民族に深く染み付いた歴史的な体質になっているのではなかろうか」(小高健『日本近代医学史』、平成23年)との指摘を否定できない状況にあったことは事実である。“Nature”“Cell”両誌に追悼文(いずれも2009年4月)の掲載された花房秀三郎の「がん遺伝子の先駆的研究」(昭和38~52年)、利根川進の「多様な抗体を生成する遺伝的原理の解明」(昭和62年ノーベル生理学・医学賞)は、いずれも外国で生まれた業績である。
平成期[平成元(1989)年~]
現在に至るこの期を代表する象徴的なできごとは、「介護保険」の実施(平成12年)である。医療から介護への転換である。理由は、世界の文明国家に例をみない速度で進展した「人口の高齢化」にある。平成23年の老年人口(65歳以上)は2975万人、全人口の23・3%で、なかでも75歳以上の後期高齢者は1471万人、全人口の11・5%に達している。
なぜ、高齢者は増加したのか。病気による死亡が減少したためである。その理由は二つある。一つは生活環境(居住、大気、上下水道、栄養)、労働環境(職場、労働時間)のさらなる改善・向上による病気自体の減少である。もう一つは医療環境(施設、機器、薬剤)の改良による治療の向上である。
「成人病・生活習慣病」対策の成果として、平成期になっての病気の減少は目覚ましいものがある。脳卒中、虚血性心疾患は激減している。がんにおいても、肺がんのように増加しているものもあるが、全体としてみれば、近年の減少傾向は明らかである。
長寿自体は大変結構なことである。問題は医療・介護費、さらには生計費の負担を、わが国の社会が支えられるかである。現状、後期高齢者の医療・介護に用いられている経費は約18兆円であり、今後のさらなる増額は必至である。その増加を支えるためには、当然、経済活動の活性化が必要である。同時に「適切な医療・介護、妥当な医療・介護費」を目指しての検討が必要である。後期高齢者医療だけの問題ではない。わが国の医療全体として、英国・北欧の社会保障型国家に比較すると、国民1人あたりの年間受診回数は3~5倍、医師1人あたりの年間診療回数は3~8倍、病床数(人口あたり)は4~5倍、平均在院日数は2~3倍、人口あたりのCT台数は4~13倍、MRI台数は3~7倍、透析患者数は4倍の状況である。これらの数字だけをもって過剰医療というわけではないが、日本の医療水準の高さを示すことではない。
なお、本書の編集作業も大詰めに近くなった10月8日、大きな朗報がもたらされた。山中伸弥教授(京大)のノーベル賞受賞である。わが国で生まれた仕事に対する初の生理学・医学賞である。その業績である「iPS細胞の開発」(2006/平成18年)は、共同受賞者のジョン・ガードン卿の「クローンオタマジャクシ作製」(1962/昭和37年)の延長線上の成果であり、冒頭で記した「人々の仕事は先人の仕事の上に成り立っていること」を改めて感じさせられた快挙であった。授賞理由は「成熟細胞が初期化され、多能性をもつことの発見」。まさに生理学賞に値する偉業である。山中教授への次なる大きな期待は、iPS細胞の臨床応用・実用化である。巨大な壁への挑戦ではあるが、山中教授の二度目の栄誉を期待したい。
わが国の医学史・医療史をめぐってのこのような記載が適切かどうかの議論は別としても、本書に記載された多数の有名・無名の人物が生きてきた道を、それぞれの時代と照合してみるとき、さまざまな思いに駆られるのは編者だけではあるまいと思われる。
最後に、謝辞を記させていただきたい。
本書の記載内容は、別記のようなきわめて多数の刊行物(書籍、雑誌、新聞等)と公開されている各種データベースを参考にさせていただいた。なかでも大正10年創刊以来、91年の歴史をもつ『日本医事新報』、また『大日本博士録』(井関九郎編、発展社、大正10年~昭和5年)に拠るところが大きい。特に謝意を記載しておきたい。
情報提供をいただいたご遺族・ご親族、調査に利用させていただいた国立国会図書館、編者の地元にある京都府立図書館、京都府立医科大学図書館、京都大学医学部図書館をはじめ、全国各地の図書館・資料館・史料館、ならびに編者・編集部からの問合せにご回答・ご協力いただいた各大学・教室・医局、病院その他の関係者に厚くお礼申し上げたい。
また、大学停年退官後14年間、編者が本書編纂にあたった日々の暮らしを支えていただいた公益財団法人京都健康管理研究会・中央診療所の職員各位、また滋賀文化短期大学(現 びわこ学院大学短期大学部)、神戸薬科大学、同志社女子大学等の関係各位に感謝する。また、平成18年以来、厳しい出版不況の情勢下において本書刊行の意義を理解いただいた医学書院の七尾清編集長、7年に及んだ編集期間を通じて諸方面の連絡役・窓口を担当していただいた編集者青木大祐、ならびに制作部黒田清、梅津善嗣の諸氏に深謝する。膨大な情報の処理に尽くされた三美印刷株式会社の諸氏とデザインを担当された町口覚・景兄弟に感謝する。
本書が、わが国の医学・医療のさまざまの領域において、あゆみを進めるときの道標の一つになり、さらには、方向性を考えていくよすがとなることが、編者の願いである。
平成24年12月
泉 孝英
本事典は、わが国において西洋医学が公式に採用された慶応4/明治元(1868)年3月から平成23(2011)年末までの約145年間において、わが国の医学・医療に携わり、物故された人物3762名についての記録集である。具体的な記載項目については凡例を参照されたい。
刊行を企画した理由は、医学・医療にかぎらず、すべての人々の仕事は先人の仕事の上に成り立っているとの前提からである。したがって、先人の生き方、考えたこと、成果を記載しておくことは、後世のひとびとが次の仕事を考えるときに、大きな参考になるものであることに疑いを挟む余地はない。
まずお断り、お詫びしておくべきことを記しておきたい。
本事典の編集は、基本的には編者の個人的作業であるので、この期間の中で本書に収載すべきでありながら、掲載されていない人物が少なくはないこと、また正確さに欠ける記載があり得ることを、編者として少なからず懸念していることである。読者、関係各位からの更なる情報提供に期待したい。しかるべき時期の増補・改訂版において、加筆・訂正を行うことを目指している。
本事典の名称は『日本近現代医学人名事典』であり、医学・医療領域を網羅する人名事典たることを志して準備を進めてきた。しかし、平成24年現在の時点において“医学・医療”を広義に捉えるとすれば、看護学・生物学・歯学・薬学・リハビリテーション学、さらに福祉等の領域をも含めるべきであるが、本事典においては、それらの十分な記載が行われたとは判断していない。これまた、各位からの情報提供をお願いしたいところである。
なお編集開始当時には、物故者であるか否かを問わずに編集作業を進めてきた。しかし、さまざまの検討を重ねた結果、記載人物は物故者に限定することとした。資料・情報を提供いただいた各位に陳謝する。
ここで本事典の背景となる基礎事項として、明治元年以来今日まで、わが国における医学・医療のたどった道について、編者なりにまとめた概略を記しておきたい。この約145年間を、大きくは「明治・大正・昭和戦前期」「昭和戦後期」そして「平成期」の3つの時期に区分されると考えている。
明治・大正・昭和戦前期[明治元(1868)年~昭和20(1945)年]
ドイツ医学の公式採用(明治3年)以来、わが国は多数のドイツ人教師を招聘して、主として東京大学、その前身校において医学教育が行われた。卒業生は、全国各地の医学校に赴任してドイツ医学の普及を図った(参考 吉良枝郎『明治期におけるドイツ医学の受容と普及』、平成22年)。また、明治期を通じて900余名が留学のため渡独している。驚くべきこととして、文部省留学生に代表される公費留学生が250名程度であったのに、650名を超す多数の私費留学生が渡独している。わが国がドイツ医学をいかに熱心に受容しようとしたかがうかがえる。
この時代、ドイツで学んだ技法を駆使して、わが国で数多くの優れた研究が行われた。西欧においては細菌学勃興の時期である。病原菌発見の歴史は、明治6(1873)年のハンセン(ノルウェー)による「らい菌」の発見に始まり、明治15(1882)年にはコッホ(ドイツ)によって結核菌の発見が行われている。わが国においても、ペスト菌の発見(北里柴三郎 明治27年)、赤痢菌の発見(志賀潔 明治30年)が行われている。細菌学の領域だけではない。明治43年に藤浪鑑と稲本亀五郎による移植可能なニワトリ肉腫(藤浪肉腫)の発見、大正4年には山極勝三郎と市川厚一によるタールを用いた人工発癌における世界初の成功などが報告されている。いずれも、がん研究の歴史においてきわめて重要な成果であり、特に、山極・市川の仕事がなぜノーベル生理学・医学賞を受賞できなかったのかについての議論は、今なお続いている。このように、明治・大正期のわが国における医学研究は世界的にも注目された研究が少なくない。まさに、医学にとっても『坂の上の雲』(司馬遼太郎 昭和43年)の時代であった。
一方、医療の面をみれば、明治7年の「医制」発布以来、近代的医療制度の確立が図られたが、この時期はなお、わが国が伝染病(感染症)対策に終始した時代であった。明治初期・中期は、コレラ、赤痢、腸チフスなどの急性伝染病の時代と言える。明治12年のコレラ大流行では、罹患数16万2637人、死者数10万5786人もの驚くべき数字が記録されている。政府は明治9年の天然痘予防規則以来、海港虎列刺病伝染予防規則(明治12年)、伝染病予防規則(明治13年)などの法令を制定して対策に躍起となったが、その制圧には程遠い状況であった。また、慢性伝染病である結核、ハンセン病の制圧を目指しての立法が行われたのは、それぞれ明治も末期の37年、40年に至ってのことである。
この時期、伝染病対策が遅々として進まなかった理由としては、抗菌薬が未開発であったことが挙げられるが、より基本的には、この時期、絶えず起こった戦乱・戦争――慶応4年の戊辰戦争以来、台湾出兵、西南の役、日清戦争、北清事変、日露戦争、シベリア出兵、済南事件、満州事変、日中戦争、そして昭和16年の大東亜戦争――のために多大の軍事費を要し、民生費は乏しく、上下水道といった急性伝染病の防疫上、最低限必要な環境整備すらできなかったことがある。しかし、われわれ日本人が特に好戦的であったわけではない。問題は、明治の開国以来の人口の急増による財政面での圧迫であった。明治3年から昭和15年までの70年間に、日本人はほぼ倍増した。明治元年には、早くも米国(ハワイ・本土)移民が始まり、明治41年にはブラジル移民が始まったが、いずれも相手国から門戸を閉ざされることになり、昭和7年には最後の移民地としての満州移民が開始された流れがある。このなかで、日清、日露戦争の勝利を受けて、わが国は台湾(明治28年)、朝鮮(明治43年)の外地経営に乗り出さざるを得なかった不幸な歴史がある。
昭和20年8月、日本の敗戦を迎えて、内地人口7200万人の国土に、軍人・一般邦人を含めて510万人が加わった。食糧難・住宅難・交通難のなかで、引揚者からのコレラ、発疹チフスなどの急性伝染病の国内への侵入・流行が懸念されたが、10月に厚生省は臨時防疫局を設置して、伝染病に対する水際作戦を展開し、大きな被害を出さないという見事な成果を挙げている。当時の防疫関係者、厚生技官の労苦は、わが国の医療史に明記されておくべきことである。
また、この時代の前後、重要な施策が行われている。「日本医療団」の発足(昭和17年6月)と病院・療養所の国有化政策である。戦時下という状況のなかで強行されたことであるが、「医療国営化・公営化」は、戦時体制の一つとしてではなく、医療の社会化・社会保障としての医療を考える上で、避けて通れない検討課題である。現在、欧州の国民皆保険の国々は、原則、公営医療である。少なくとも、病院は公営である。日本医療団は、米占領軍の意向を受けて昭和22年11月に解散した。そのわずか13年5か月後には、「国民皆保険」である。日本医療団が温存できておれば、現在の医療の混乱も少しは防げたかもしれないと思うと残念なことである。
昭和戦後期[昭和20(1945)年~昭和64(1989)年]
医療史の上でみれば、死因第1位だった結核に代わり、脳血管疾患が死因第1位となった昭和26年から戦後期が始まることになる。昭和戦前期と較べて最も大きな変化は、医学の面では「ドイツ医学から米国医学」への転換であり、医療面では「国民皆保険」の実現(昭和36年)がある。
なぜ、「ドイツ医学から米国医学」であったのか。一つの要因は、二度にわたる世界大戦でいずれもドイツが敗北を喫し、特に第二次世界大戦後、東西に分割されたことによるその国力低下がある。しかし、より大きなことは、昭和24年に開始されたガリオア留学生、28年からのフルブライト留学生として、多数の日本人研究者・医師が米国に向かい、その帰国者によって米国医学が急速にわが国に普及したことである。
ペニシリン、ストレプトマイシンをはじめとする抗菌薬のわが国への導入とその開発・普及によって、伝染病(感染症)は激減した。しかし、抗菌薬だけが感染症を制圧したわけではない。生活環境(居住、大気、上下水道、栄養)、労働環境(職場環境、労働時間の減少)の改善・向上の果たした役割もきわめて大きい。加えて、最大の要因は「国民皆保険化」に代表される医療環境(医療施設、医療機器、薬剤)の整備・充実である。このような戦後の国民生活の向上・環境の改善は、わが国の経済成長、特に昭和30年から48年まで続いた高度経済成長に支えられたことであった。また戦後は、戦争が一度もない国となり、戦前に比較して軍事費が激減したことは、民生費、社会保障費の確保をももたらしたことは、銘記して強調されねばならないことである。
明治初年、国民の平均寿命は男女とも30歳程度であった。そして、大東亜戦争前の昭和15年になっても男46・9歳、女50・0歳の状況であったが、戦後、急速な延びをみせ、平成元年には男75・9歳、女81・8歳に延長した。
感染症に代わって浮上してきたのは、「成人病(脳卒中、がん、心臓病)・生活習慣病」である。昭和32年から開始された成人病対策は、平成8年には“生活習慣病”と名称が変更され、国家的レベルで対策が講じられるようになった。
一方、戦後の医学研究の動向をみると、米国医学の導入にあまりにも忙しく、「日本人は、学問であれ宗教であれ、外国で生まれたものをわが国に移植して自分のものとし、文化を作り上げてきた。必然的に外国産を尊重し、それを持ち込んだ個人をも尊敬した。加えて、外国で生まれたばかりのものを重要だと判断した。このような傾向は日本民族に深く染み付いた歴史的な体質になっているのではなかろうか」(小高健『日本近代医学史』、平成23年)との指摘を否定できない状況にあったことは事実である。“Nature”“Cell”両誌に追悼文(いずれも2009年4月)の掲載された花房秀三郎の「がん遺伝子の先駆的研究」(昭和38~52年)、利根川進の「多様な抗体を生成する遺伝的原理の解明」(昭和62年ノーベル生理学・医学賞)は、いずれも外国で生まれた業績である。
平成期[平成元(1989)年~]
現在に至るこの期を代表する象徴的なできごとは、「介護保険」の実施(平成12年)である。医療から介護への転換である。理由は、世界の文明国家に例をみない速度で進展した「人口の高齢化」にある。平成23年の老年人口(65歳以上)は2975万人、全人口の23・3%で、なかでも75歳以上の後期高齢者は1471万人、全人口の11・5%に達している。
なぜ、高齢者は増加したのか。病気による死亡が減少したためである。その理由は二つある。一つは生活環境(居住、大気、上下水道、栄養)、労働環境(職場、労働時間)のさらなる改善・向上による病気自体の減少である。もう一つは医療環境(施設、機器、薬剤)の改良による治療の向上である。
「成人病・生活習慣病」対策の成果として、平成期になっての病気の減少は目覚ましいものがある。脳卒中、虚血性心疾患は激減している。がんにおいても、肺がんのように増加しているものもあるが、全体としてみれば、近年の減少傾向は明らかである。
長寿自体は大変結構なことである。問題は医療・介護費、さらには生計費の負担を、わが国の社会が支えられるかである。現状、後期高齢者の医療・介護に用いられている経費は約18兆円であり、今後のさらなる増額は必至である。その増加を支えるためには、当然、経済活動の活性化が必要である。同時に「適切な医療・介護、妥当な医療・介護費」を目指しての検討が必要である。後期高齢者医療だけの問題ではない。わが国の医療全体として、英国・北欧の社会保障型国家に比較すると、国民1人あたりの年間受診回数は3~5倍、医師1人あたりの年間診療回数は3~8倍、病床数(人口あたり)は4~5倍、平均在院日数は2~3倍、人口あたりのCT台数は4~13倍、MRI台数は3~7倍、透析患者数は4倍の状況である。これらの数字だけをもって過剰医療というわけではないが、日本の医療水準の高さを示すことではない。
なお、本書の編集作業も大詰めに近くなった10月8日、大きな朗報がもたらされた。山中伸弥教授(京大)のノーベル賞受賞である。わが国で生まれた仕事に対する初の生理学・医学賞である。その業績である「iPS細胞の開発」(2006/平成18年)は、共同受賞者のジョン・ガードン卿の「クローンオタマジャクシ作製」(1962/昭和37年)の延長線上の成果であり、冒頭で記した「人々の仕事は先人の仕事の上に成り立っていること」を改めて感じさせられた快挙であった。授賞理由は「成熟細胞が初期化され、多能性をもつことの発見」。まさに生理学賞に値する偉業である。山中教授への次なる大きな期待は、iPS細胞の臨床応用・実用化である。巨大な壁への挑戦ではあるが、山中教授の二度目の栄誉を期待したい。
わが国の医学史・医療史をめぐってのこのような記載が適切かどうかの議論は別としても、本書に記載された多数の有名・無名の人物が生きてきた道を、それぞれの時代と照合してみるとき、さまざまな思いに駆られるのは編者だけではあるまいと思われる。
最後に、謝辞を記させていただきたい。
本書の記載内容は、別記のようなきわめて多数の刊行物(書籍、雑誌、新聞等)と公開されている各種データベースを参考にさせていただいた。なかでも大正10年創刊以来、91年の歴史をもつ『日本医事新報』、また『大日本博士録』(井関九郎編、発展社、大正10年~昭和5年)に拠るところが大きい。特に謝意を記載しておきたい。
情報提供をいただいたご遺族・ご親族、調査に利用させていただいた国立国会図書館、編者の地元にある京都府立図書館、京都府立医科大学図書館、京都大学医学部図書館をはじめ、全国各地の図書館・資料館・史料館、ならびに編者・編集部からの問合せにご回答・ご協力いただいた各大学・教室・医局、病院その他の関係者に厚くお礼申し上げたい。
また、大学停年退官後14年間、編者が本書編纂にあたった日々の暮らしを支えていただいた公益財団法人京都健康管理研究会・中央診療所の職員各位、また滋賀文化短期大学(現 びわこ学院大学短期大学部)、神戸薬科大学、同志社女子大学等の関係各位に感謝する。また、平成18年以来、厳しい出版不況の情勢下において本書刊行の意義を理解いただいた医学書院の七尾清編集長、7年に及んだ編集期間を通じて諸方面の連絡役・窓口を担当していただいた編集者青木大祐、ならびに制作部黒田清、梅津善嗣の諸氏に深謝する。膨大な情報の処理に尽くされた三美印刷株式会社の諸氏とデザインを担当された町口覚・景兄弟に感謝する。
本書が、わが国の医学・医療のさまざまの領域において、あゆみを進めるときの道標の一つになり、さらには、方向性を考えていくよすがとなることが、編者の願いである。
平成24年12月
泉 孝英
書評
開く
過去から現在までつながる豊かな医学・医療の歴史 (雑誌『助産雑誌』より)
書評者: 湯本 敦子 (獨協医科大学看護学部)
まず,14年という歳月をかけ,お1人で研究を積み重ねて本書を完成された泉孝英氏に賞賛と感謝を申し上げたい。現在の医学・医療は先人たちからの歴史の結実として存在する。この書が刊行されたことで,先人の歩みを知り,今の私たちの仕事を再確認する糸口ができるであろう。
本書には,明治元年から現在にいたる145年間の物故者で,医学・医療に携わった3762名について,各人の生年~没年,出身地,【専門領域】,学歴,職歴,主な業績,著書・関連書籍などが記載されている。記載内容からは,編者が入手し得た資料から丹念に纏められたことがうかがわれる。序文には明治以来今日までの医学・医療の変遷について概略がまとめられ,また付録として資料・年表・書名索引が記載されていることは,歴史背景の理解の助けになる。ただし収載された人物の専門領域ごとの索引がないのが残念であった。
【看護師(助産師)】として掲載されているのは,今西ヨシ,上坂きさ,桶谷そとみ,納村千代,楠本ミサノ,田中志ん,寺島信恵,原田静江,三森孔子,三宅コタミ,【看護師(従軍看護婦,助産師)】として沼本津根などである。
桶谷そとみは「桶谷式乳房管理法」を普及させ,三森孔子は,「お産の学校」を開講しラマーズ法をわが国に普及させた。助産師はもとより母親たちの間にもその名が浸透している人物である。田中志んは,保健文化賞を受賞しており,伝記も出版されている。寺島信恵は「神戸友愛養老院」創設者であり,助産師というよりむしろ社会福祉事業家として名が知られているかもしれない。三宅コタミは緒方助産婦教育所を卒業し,祖母から孫まで5代続く助産師である。原田静江は日本看護協会名誉会員助産師第1号となった人物である。今西ヨシは奈良県第1号の助産師で,今西石産婆看護婦養成所を設立している。上坂きさ,納村千代は福井県,楠本ミサノは広島県の助産師であり,それぞれの地域において活躍した人々である。
本書ではすでに歴史の中で脚光を浴び広く認知されているであろう人物のみならず,編者自身が看護史等の資料から拾い上げた人々の足跡が記されている。編者は,本書が個人的作業による編集であり,収載されるべきでありながら収載されていない人物もいることの断わりを述べているが,例えば,医学を学んだ後産婆になり助産施設を開設,産婆学校を設立した村松志保子などもぜひ掲載してほしい人物の1人である。今後,さらに新たな情報や資料により加筆され,先人たちの豊かな歴史の証となることを期待する。
(『助産雑誌』2013年7月号掲載)
医療関係者の歴史から知る,新しい看護職のあり方 (雑誌『看護管理』より)
書評者: 草刈 淳子 (獨協医科大学大学院特任教授/愛知県立看護大学名誉教授,元学長)
◆厚さ5cmに詰め込まれた,医療関係者の深い歴史
本書の書評を依頼された時,5cmほどもある分厚さを前に,思わず「どなたか別の方に…」という言葉が口をついた。編者の泉孝英氏は,1936(昭和11)年生まれ,1960(昭和35)年京都大学医学部卒とのこと故,筆者とほぼ同年代である。よくもここまで纏められたことと感心した。しかし,読み始めた途端にのめり込んだ。本書は,1868(明治元)年から2011(平成23)年までの145年間に,日本の医学・医療に携わった3762名の方々に関する記録集である。医師,看護職はもちろん,医療に関わられた法律家や行政官も対象となっている。
日本の看護黎明期では,外国人ナースのツルー,ヴェイッチ,その教育を受けて東大病院初の外科看病婦取締となった大関和,いま話題の新島八重など。戦後では,新たに設立された日本看護協会の井上なつえ会長,厚生省看護課初の看護職保良せき課長,さらに1952(昭和27)年に設立された初の看護系大学の高知女子大学の和井兼尾や,その翌年にできた東京大学医学部衛生看護学科初代主任教授の福田邦三,基礎看護学の湯槙ますほか,各地の実践現場で活躍された,今は亡き方々のお名前とその活動歴が収載されている。
◆看護の歴史と医療関連事項を同時に確認
1960(昭和35)年7月に,東大衛生看護学科3期生の筆者が,初めて大卒看護職第1号として厚生省保険局医療課に入省した頃,看護課は廃止されていた。国民皆保険が達成される前年であり,その年の秋には看護職が中心となった病院ストが起こった。日本の保健医療制度が未確立だった時代に看護行政を推進されてきた,当時の医務局医事課看護参事官だった金子光氏ら,直接お世話になった方々の名前に出逢い,懐かしく当時を思い起こした。
こうしてこの人名事典をめくり,おひとりおひとりの功績を拝見すると,これらの方々やそのご父兄が,どれほど我が国の医学・医療の中心で活躍され,立派な仕事をされてきたのかを知り,あらためて超一流の先生方,関係者に育てられた幸せを確認させられた。それと同時に,卒業後は,それぞれ果敢に石ころだらけの道を切り開いてきたとは思うものの,どれほどその期待に応えた活動ができたのかを省み,今後も看護の専門職化と後輩の育成にさらに尽力しなければとの思いを深くした。
本書は人名事典としてだけでなく,文献や資料さらには年表並びに書名の索引も付されている。「社会」として“鳥羽・伏見の戦い”,「医事」として“軍陣病院設立”ほか,「医療行政」「医学」といった項目ごとにその年々に起こった事実が記載されていて,医療史を確認する際にも役立つ。看護の歴史を読みつつ当時の医療関連事項を確認できるのは,多忙な看護職にとっては有り難いことである。温故知新,新しい看護職のあり方が問われる重要な時期にある今,各大学や各県看護協会に本書が備えられ,看護職の方々や学生に活用されることが望まれる。
(『看護管理』2013年6月号掲載)
人から人に伝えられた145年の医療史を紡ぎ,未来へ (雑誌『看護教育』より)
書評者: 芳賀 佐和子 (東京慈恵会医科大学医学部看護学科客員教授)
明治から平成へと移り変わった時代のなかで,医学・医療の進歩は目覚ましいものがあります。そしてそこには先人の業績を引き継ぎ,さらに発展させてきた人々の足跡があります。
最近,精神科医の森田正馬の手になる『根岸病院看護法』について調べています。この本は明治41年に著わされたものです。本の内容は,看護法一般を述べ,そのうえで精神病者の看護の要点が著わされています。わが国最初の精神科看護書は明治34年に榊保三郎の書いた『癩狂院における精神病看護学』であり,その後明治35年に門脇真枝著,片山国嘉閲『精神病看護学』,明治41年に清水耕一著,二宮昌平編,呉秀三,田沢秀四郎閲『新選看護学』があります。
森田正馬は帝国大学を卒業し,明治36年より東京慈恵医院医学専門学校の教員として巣鴨病院で学生に講義をし,明治39年から根岸病院医長として診療に関わり,その2年後に『根岸病院看護法』が書かれたのです。この本を森田正馬が書くにあたって影響を受けたと考えられる人を調べる目的で本事典を見始めました。森田の師呉秀三,青山胤通から始まって,片山国嘉,富士川游,榊俶,榊保三郎,門脇真枝,石田昇,清水耕一,高木兼寛,中村古狭,松村清吾……と調べました。結果は,一人を除いて業績を知ることができました。そのとき,編者が14年間かけて編集された,本書の深淵にふれた思いがしました。事典には生死の年が最初に書かれているので,森田正馬との関係を探るうえで参考になりました。と同時に時代背景が浮かびやすいと感じました。また,人ごとに抽出されている文献は人物像に迫っていく活動のヒントとなり,今,私はいつ果てるともない思索への旅を楽しんでいます。
本書は,「医学」人名事典と銘打たれていますが,「医学・医療」の発展に貢献した3762名(故人)を,医師,看護師,薬剤師,療法士,検査技師など医療職に限らず,社会事業家などからも選定しています。看護の立場から本書をみますと,105名の先人たちが載っていました。これは過去に類例がない規模になっているのではないでしょうか。そこで【看護師】の所だけを抽出して読んでみました。そこには看護が社会のなかでその役割を果たしながら発展している現状に多くの先人の働きがあったことが示され,看護界における歴史の一端を知ることができます。
本書を読み進むうちに,“実は,先人の志を詳らかにして次世代につないでいくのは,読者自身の責務”と語りかけられている思いがします。
最後に,膨大な作業を経て810ページにまとめられた本書は,その過程を包み込み,手に取りやすい重さとすてきな装丁に仕上がっているのも嬉しいことです。
(『看護教育』2013年5月号掲載)
未来に残る医療界の大きな遺産 (雑誌『看護研究』より)
書評者: 川原 由佳里 (日本赤十字看護大学准教授・看護歴史研究室)
ついに,『日本近現代医学人名事典』が医学書院から刊行された。医学,歯学,薬学,看護学などの分野の研究者にとっては待ち望んでいた画期的な基礎資料である。これまで医療分野で活躍した人々を網羅した人名事典は存在せず,出版史上でもすでに絶版となった1950年の『世界医学人名事典』(木下正中著,医学書院)くらいだという。それだけでも本書が公刊された意義は大きい。
全体で810ページの大著であり,明治元年から平成23年末までの約145年間にわたり,医学・医療に携わった3762名もの関係者が記載されている。
それぞれの人物に関する記述は簡潔で読みやすい。医療の各分野を開拓,発展させた医師,看護師に始まり,近代日本の医療福祉に貢献した政治家,行政担当者,事業家,軍医までを含む幅広い分野の人々の歩みが記載されている。氏名,生年月日はもちろん,旧姓,卒業大学,勤務先と役職,研究内容,退職後の活動,著書や共著書名といった内容まで記載されており,必要な情報を得ることができる。また付録の「年表」は,本文中に記載された人々が生きた時代について理解しやすいよう,明治元年からの社会の動きと医療にかかわる出来事が簡潔にまとめられている。あわせて必要な人名に迅速にアクセスすることが可能な索引を駆使すれば,潜在的な能力を十分に活用できる。たいへん秀逸な事典である。
研究者ならもちろんのこと,そうでなくても日本の医療の成り立ちに関心をもつ人ならぜひ1冊手元に置いておきたい。気の向いたときにパラパラと眺めるだけでもよい。今日の医療が実現されるまでに,いかに大勢の人々がこの分野で仕事をされ,貢献されたかに思いを馳せることができる。あるいは人物ごとに,彼らの学び,経験,医療に関する課題への取り組みをじっくりと読むことで,ある人物の意外な経歴を知ったり,他の人との関係がわかったり,時代背景を理解したりする。そうするうちに,過去の人々は現代の私たちにどのようなメッセージを発するだろうか,などと考えはじめる。「歴史とは現在と過去との対話である」と述べたのは歴史学者のE. H. カーであるが,この事典には,過去の人々との対話を促し,私たちもまた歴史的存在であることの自覚をもたらす力が備わっている。
最後に,この事典のすばらしさをもう1つ語らせてもらいたい。編者が序文で述べている「人々の仕事は先人の仕事の上に成り立っている」という言葉の通り,この事典のすみずみに,編者の方の謙虚さが行き渡っている。歴史的事実の正確を期し,必要かつ十分な情報を精選し,しかも華美な修飾は一切ない。その確実かつ謙虚な態度がすばらしい。それは編者が14年もの歳月をかけて編纂したプロセスに裏打ちされているのだろう。この事典は確実に,医学・医療領域における重要な資産の1つとなるであろうし,今後ともぜひ,継続的に増補・改訂を重ねていかれることを願ってやまない。
(『看護研究』2013年4月号掲載)
「歴史もの」がプレゼンスを示した2012年、味わい深い事典が刊行 (雑誌『精神看護』より)
書評者: 鈴木 晃仁 (慶應義塾大学・医学史)
2012年の日本の医学界を振り返ると、山中伸弥教授のノーベル賞受賞という最先端の研究と並んで、「歴史もの」が確かなプレゼンスを示すようになった1年であった。「医学史」の研究はもちろん以前からおこなわれており、優れた書物も出版されていたが、過去からの蓄積と新刊された書物が相まって、ある〈まとまり〉のようなものを示すようになった。医学と医療の現在性、未来志向性と並んで、それが持つ長い歴史が確かな存在感を持つようになったのである。
医学書院から昨年発行された書籍をみても、金川英雄が翻訳し解説を付した呉秀三・樫田五郎『精神病者私宅監置の実況』はベストセラー並みの扱いであるが、これは今から100年ほど前に発行された論文を現代の医療関係者にも無理なく読めるように現代語訳したものである。木村哲也『駐在保健婦の時代 1942-1997』は、激動の戦中から戦後・高度成長期に形成された日本人の健康と日常を、高知県の保健婦の現代史を通じて生き生きと復活させた著作である。翻訳ものでは、ウィリアム・バイナムとヘレン・バイナムの『Medicine 医学を変えた70の発見』は、私も共訳者の1人であるが、医学史の専門家だけでなく多くの人々に訴えるインパクトがある図版を300点以上も掲載したヴィジュアル医学史の決定版である。
これらの2012年の成果は、近年の多彩で多様な医学史の書物と融合して、「医学史」というものを、緩やかだが確かな形で存在感をもつ主題として作り上げてきた。たとえば、2008年に医師の茨木保が執筆して医学書院から発行された『まんが 医学の歴史』、2010年に藤原書店から刊行された主にフランスの歴史学者たちによる豪華な『身体の歴史』全3巻、2012年に歴史学者の青木歳幸が吉川弘文館から刊行した『江戸時代の医学-名医たちの300年』などが、記憶に新しい。これらの仕事に、『看護教育』に連載されている茨木保「ナイチンゲール伝」や、大河ドラマの主人公の山本八重が日清・日露戦争に篤志看護婦として参加する姿も加えることができるだろう。
『日本近現代医学人名事典』は、このような医学史という領域に、伝記的な基礎を与える重要な仕事である。明治元年(1868)から平成23年(2011)までの140年あまりの期間に、医学・医療に携わった人物で、すでに物故された3,762人の記録である。日本の医者が中心であるが、日本やその植民地などで活躍した外国人の医療者や、看護師、薬剤師、医療の社会運動家、医療問題で活躍した患者など、医療という領域を作り上げている多様な領域から選ばれている。それぞれの人物の項目は、国内の医学校や留学などの教育や、大学や病院や教会などの役職の記述を中心にしたものになっており、業績の解説や著作と評伝などの文献的な情報が付け加えられている。医学関連の政治・行政や医学評論だけでなく、医師であると同時に歌人や文学者などとして活躍した個人も採用されている。親戚や婚姻関係などの記述も味わい深い。巻末につけられた「年表」は、明治から平成をカバーする優れた医学年表になっており、自分が生まれた年に何が起きたのかをまず見てみると楽しい。
この書物が多くの医療関係者の本棚に置かれて、医学の歴史が多くの人々に実感されることが望まれる。そうすれば、現在において実用的であり、未来には改善される医療というだけでなく、長い伝統を持つ豊かな営みという〈新しい〉顔を見せることだろう。
(『精神看護』2013年5月号掲載)
日本の近代医学の歴史を語る貴重な資料
書評者: 高久 史麿 (日本医学会長・自治医科大学名誉学長)
今回,医学書院から泉孝英先生の編集による『日本近現代医学人名事典』が刊行された。この事典で紹介されている方々は,2011年末までに死去された医療関係者の方々である。紹介の対象になっているのは医師,医学研究者が大部分であるが,歯科医師,看護師,薬学,体育指導者,宣教師,事業家(製薬業),工学者(衛生工学),社会事業家,厚生行政の方,生物学者など,幅広い業種の方々であり,いずれもわが国の医療の発展に大きく貢献された方々である。本誌に紹介されている方々の年代は誠に長く,1868年から2011年までの143年に及び,その数は3,762名に達している。
本書の「序」にも紹介されているように,1868年はわが国に西洋医学が導入された年であるから,本書は,日本の近代医学・医療に貢献された先達のご経歴とご業績を網羅した“一大人名事典”であるといって過言ではないであろう。
この書評を書くにあたって,私自身が指導を受けた20人近くの恩師の方々の名前を拾い上げてその内容を読んでみたが,その内容の正確さに強い感銘を受けた。なお,この20人の方々の各々のご業績の紹介に関しては,その内容にやや濃淡があるように感じられたが,これだけ多くの方々の紹介であるからこの程度のばらつきはやむを得ないであろうと考えている。
泉孝英先生が胸部の疾患をご専門にされておられたことは,先生が京都大学の教授の時からよく存じ上げていたが,先生がご退官後14年間かけて本書の編集にあたられたことを本書の「序」で知った。医学者としての泉孝英先生しか知らなかった私にとって,大きな驚きであった。あらためて泉先生の本書の編集に対する甚大なご尽力に心からの敬意を表すると同時に,泉先生のご努力が本書を日本の近代医学の歴史を語る貴重な資料にしたと私は考えている。
このような貴重な資料の作成に成功された泉孝英先生ならびに医学書院の方々に衷心からお祝いの言葉を捧げるとともに,1人でも多くの方々に本書を貴重な資料として温存していただきたいという私の願いの言葉をもって,推薦の言葉の締めくくりとしたい。
たぐいまれな,近現代医学の歴史教科書としても優れた書
書評者: 早石 修 (大阪バイオサイエンス研究所名誉所長)
本書は,1868(明治元)年3月に明治政府が欧米医学を公式に採用して以来,2011(平成23)年末までに物故された医療関係者で,特にわが国の医学・医療の発展に貢献された3,762名を選んで,物語風に記録されたユニークな人名事典であります。何分にも膨大な内容であり,私自身,生化学という限られた基礎医学が専攻分野なので,医学・医療全体の問題を議論したり,評価することには必ずしも適任ではありません。それでもまず本書を通読して,最も重要な“人選”が極めて公正で妥当であるという印象を受けました。
次に個々の記載について,個人的に親しかった方々について詳しく調べました。いずれもおおむね正確な情報に基づいており,しかも専門的な記述以外に本人の性格,趣味,交際,家族など私的な紹介も多く,読物としても興味深いものでした。以下,幾人かを収載人物の例として挙げます(敬称略)。
古武弥四郎(本書253ページ)は,「わが国の生化学の開祖」荒木寅三郎(25ページ)の門下で,「わが国の生化学の基礎を築いた」人物です(私にとってはティーチャーというよりメンターというべき方でした)。その講義は極めて難解であったため,学生時代の私は医化学の道を諦め,「わが国におけるウイルス研究の先駆者」谷口腆二(393ページ)の業室研究生にしていただきました。卒後,軍医として出征し終戦後に破壊された大阪の惨状の中に戻って臨床医になるか迷ったとき,改めて基礎医学の道を勧めてくれたのが谷口と,後述する父でした。その後,阪大微生物病研究所(微研)を経て渡米してアメリカ国立健康研究所(NIH)部長となった私を,京大で医化学講座第3代教授内野仙治(92ページ)の後任人事が難航した折,当時の医学部長平沢興(514ページ)が異例の決断をされ,招聘された縁がありました。
1909年の「世界で最初の内因性睡眠物質の発見者」石森国臣(53ページ)は,同時期にアンリ・ピエロンが,ほぼ同じアイデアによる実験から類似の結果を出してフランスで発表し,欧米で著名になったのに対し,日本語雑誌で発表した石森は,世界的には無名のまま近年に至っていたわけです。2009年にはその発見100周年を祝して,私が記念講演をさせていただきました。1つ残念なのは,石森は生理学者であり,その当時の有機化学者との共同研究をされなかったため物質の同定がされていないことでした。1世紀後の私は,「視床下部温度感受性ニューロンを発見」された優秀な生理学者の中山昭雄(450ページ)と共同実験を行なうことによって,プロスタグランジンD2の睡眠誘起作用を生理学の立場からも確認することができました。
驚いたのは,わが父早石実蔵(496ページ)が収載されたことです。父は祖母一人に育てられ18歳で医師免許を取得,臨床医としても研究者としても大変優れた人で,8歳年下の妻光子と共々満95歳の長命で亡くなりましたが,最後まで最新の英文医学誌に目を通す勉強家でした。編者泉孝英博士による解説を医学界新聞(第3008号【寄稿】近代医学の145年)で拝見して,父のように在野で過ごしたため,医学の正史からは忘れられた無名人をも顕彰する趣旨があったことに感銘を受けました。また加うるに,収載人物それぞれの医学・医療に対する貢献を第三者にもわかりやすく解説されるために,膨大な参考文献,資料,年表などを別添されていることも,本書の付加価値を大きく高めています。
本書は,日本はおろか海外にもたぐいまれな,ユニークな近現代医学の歴史教科書としても極めて優れたものであり,編者のライフ・ワークとして高く評価されるべきものと信じます。
事典としての有用性を超えた,読み応えのある書
書評者: 猪飼 周平 (一橋大大学院教授・総合社会科学(比較医療史))
本書は,呼吸器内科を専門とする医学者が14年にわたり,明治期以降日本の近代医学・医療の発展に貢献した3,762名(物故者)の履歴を調べあげた成果である。評者のように,明治期以降の医業関係誌を参照する機会の多い者にとっては,このように便利かつ確度の高いレファレンスが完成したことは,大変喜ばしいことであり,そのありがたみは今後随所で感じられることになるであろう。編者の長年のご苦労に感謝したい。
とはいえ,本書を単に事典として理解するとすれば書評の対象とする必要はないかもしれない。そこで以下では,本書を約800ページの読物と解してその意義を考えてみたい。
まず,本書に掲載されている人物の履歴を見ると,医師が大部分(3,383名)であり,またその大部分が大卒(3,027名)で占められている。戦前において大卒の医師免許の下付数はおよそ1万6,000名であり,その大部分が物故していると考えれば,ざっとみて大卒医師の2割弱の履歴を本書がカバーしていることになる。このように理解すると,本書はどのように読めるだろうか。
なにより,近代医学において戦前の大卒医が選び抜かれたエリートとしての役割を担っていたということである。後世の医学者(編者)の視点から見て,近代医学・医療の発展に貢献したと評価できる大卒医が,大卒医の少なくとも2割近くもいるというのは,いかに大卒医が実質を備えたエリート集団であったかを物語っている。
実際,掲載されているその履歴を読んでみると,大学教員を経ている者が多く,概して大変華々しいものであるといえる。これは,たとえば大正期に初版が刊行された『日本医籍録』(版によっては国立国会図書館の近代デジタルライブラリーで利用できる)と比較するとわかりやすい。
戦前を通じて,医師には,おおまかに言って,上から「大卒,医専卒,試験及第医,従来開業医」という4つの階層があった。『日本医籍録』の場合,試験及第医や従来開業医の掲載が多く,その経歴も,資格取得後比較的早く開業するのが一般的であった。そのような医師たちにとっては,開業地に地盤を形成し,市郡レベルの医師会などで社会的地位を確保してゆくキャリアが成功のパターンであったといえよう。これに対して,本書に掲載されている大卒医たちは,基本的に大学の教員としてのキャリアを経ている者が多い。本書に収載されている医専卒(医学校卒含む)が316名にとどまっていることからも示唆されるように,医専を卒業して教員のキャリアを登った事例は少ない。ここから,戦前日本の医師4階層の中で隔絶した最上位階層として,また他の階層の医師たちとは異なった使命を帯びた存在として大卒医(少なくともその2割)があったことを読み取ることができるだろう。
もちろん,評者のように本書を読むというのは,おそらく一般的な利用法ではないだろう。ただ,読物として読み応えがあることがよい事典の条件の1つであるとするならば,少なくとも評者には,本書は単なる事典としての有用性を超えたよい事典であるといえる。
書評者: 湯本 敦子 (獨協医科大学看護学部)
まず,14年という歳月をかけ,お1人で研究を積み重ねて本書を完成された泉孝英氏に賞賛と感謝を申し上げたい。現在の医学・医療は先人たちからの歴史の結実として存在する。この書が刊行されたことで,先人の歩みを知り,今の私たちの仕事を再確認する糸口ができるであろう。
本書には,明治元年から現在にいたる145年間の物故者で,医学・医療に携わった3762名について,各人の生年~没年,出身地,【専門領域】,学歴,職歴,主な業績,著書・関連書籍などが記載されている。記載内容からは,編者が入手し得た資料から丹念に纏められたことがうかがわれる。序文には明治以来今日までの医学・医療の変遷について概略がまとめられ,また付録として資料・年表・書名索引が記載されていることは,歴史背景の理解の助けになる。ただし収載された人物の専門領域ごとの索引がないのが残念であった。
【看護師(助産師)】として掲載されているのは,今西ヨシ,上坂きさ,桶谷そとみ,納村千代,楠本ミサノ,田中志ん,寺島信恵,原田静江,三森孔子,三宅コタミ,【看護師(従軍看護婦,助産師)】として沼本津根などである。
桶谷そとみは「桶谷式乳房管理法」を普及させ,三森孔子は,「お産の学校」を開講しラマーズ法をわが国に普及させた。助産師はもとより母親たちの間にもその名が浸透している人物である。田中志んは,保健文化賞を受賞しており,伝記も出版されている。寺島信恵は「神戸友愛養老院」創設者であり,助産師というよりむしろ社会福祉事業家として名が知られているかもしれない。三宅コタミは緒方助産婦教育所を卒業し,祖母から孫まで5代続く助産師である。原田静江は日本看護協会名誉会員助産師第1号となった人物である。今西ヨシは奈良県第1号の助産師で,今西石産婆看護婦養成所を設立している。上坂きさ,納村千代は福井県,楠本ミサノは広島県の助産師であり,それぞれの地域において活躍した人々である。
本書ではすでに歴史の中で脚光を浴び広く認知されているであろう人物のみならず,編者自身が看護史等の資料から拾い上げた人々の足跡が記されている。編者は,本書が個人的作業による編集であり,収載されるべきでありながら収載されていない人物もいることの断わりを述べているが,例えば,医学を学んだ後産婆になり助産施設を開設,産婆学校を設立した村松志保子などもぜひ掲載してほしい人物の1人である。今後,さらに新たな情報や資料により加筆され,先人たちの豊かな歴史の証となることを期待する。
(『助産雑誌』2013年7月号掲載)
医療関係者の歴史から知る,新しい看護職のあり方 (雑誌『看護管理』より)
書評者: 草刈 淳子 (獨協医科大学大学院特任教授/愛知県立看護大学名誉教授,元学長)
◆厚さ5cmに詰め込まれた,医療関係者の深い歴史
本書の書評を依頼された時,5cmほどもある分厚さを前に,思わず「どなたか別の方に…」という言葉が口をついた。編者の泉孝英氏は,1936(昭和11)年生まれ,1960(昭和35)年京都大学医学部卒とのこと故,筆者とほぼ同年代である。よくもここまで纏められたことと感心した。しかし,読み始めた途端にのめり込んだ。本書は,1868(明治元)年から2011(平成23)年までの145年間に,日本の医学・医療に携わった3762名の方々に関する記録集である。医師,看護職はもちろん,医療に関わられた法律家や行政官も対象となっている。
日本の看護黎明期では,外国人ナースのツルー,ヴェイッチ,その教育を受けて東大病院初の外科看病婦取締となった大関和,いま話題の新島八重など。戦後では,新たに設立された日本看護協会の井上なつえ会長,厚生省看護課初の看護職保良せき課長,さらに1952(昭和27)年に設立された初の看護系大学の高知女子大学の和井兼尾や,その翌年にできた東京大学医学部衛生看護学科初代主任教授の福田邦三,基礎看護学の湯槙ますほか,各地の実践現場で活躍された,今は亡き方々のお名前とその活動歴が収載されている。
◆看護の歴史と医療関連事項を同時に確認
1960(昭和35)年7月に,東大衛生看護学科3期生の筆者が,初めて大卒看護職第1号として厚生省保険局医療課に入省した頃,看護課は廃止されていた。国民皆保険が達成される前年であり,その年の秋には看護職が中心となった病院ストが起こった。日本の保健医療制度が未確立だった時代に看護行政を推進されてきた,当時の医務局医事課看護参事官だった金子光氏ら,直接お世話になった方々の名前に出逢い,懐かしく当時を思い起こした。
こうしてこの人名事典をめくり,おひとりおひとりの功績を拝見すると,これらの方々やそのご父兄が,どれほど我が国の医学・医療の中心で活躍され,立派な仕事をされてきたのかを知り,あらためて超一流の先生方,関係者に育てられた幸せを確認させられた。それと同時に,卒業後は,それぞれ果敢に石ころだらけの道を切り開いてきたとは思うものの,どれほどその期待に応えた活動ができたのかを省み,今後も看護の専門職化と後輩の育成にさらに尽力しなければとの思いを深くした。
本書は人名事典としてだけでなく,文献や資料さらには年表並びに書名の索引も付されている。「社会」として“鳥羽・伏見の戦い”,「医事」として“軍陣病院設立”ほか,「医療行政」「医学」といった項目ごとにその年々に起こった事実が記載されていて,医療史を確認する際にも役立つ。看護の歴史を読みつつ当時の医療関連事項を確認できるのは,多忙な看護職にとっては有り難いことである。温故知新,新しい看護職のあり方が問われる重要な時期にある今,各大学や各県看護協会に本書が備えられ,看護職の方々や学生に活用されることが望まれる。
(『看護管理』2013年6月号掲載)
人から人に伝えられた145年の医療史を紡ぎ,未来へ (雑誌『看護教育』より)
書評者: 芳賀 佐和子 (東京慈恵会医科大学医学部看護学科客員教授)
明治から平成へと移り変わった時代のなかで,医学・医療の進歩は目覚ましいものがあります。そしてそこには先人の業績を引き継ぎ,さらに発展させてきた人々の足跡があります。
最近,精神科医の森田正馬の手になる『根岸病院看護法』について調べています。この本は明治41年に著わされたものです。本の内容は,看護法一般を述べ,そのうえで精神病者の看護の要点が著わされています。わが国最初の精神科看護書は明治34年に榊保三郎の書いた『癩狂院における精神病看護学』であり,その後明治35年に門脇真枝著,片山国嘉閲『精神病看護学』,明治41年に清水耕一著,二宮昌平編,呉秀三,田沢秀四郎閲『新選看護学』があります。
森田正馬は帝国大学を卒業し,明治36年より東京慈恵医院医学専門学校の教員として巣鴨病院で学生に講義をし,明治39年から根岸病院医長として診療に関わり,その2年後に『根岸病院看護法』が書かれたのです。この本を森田正馬が書くにあたって影響を受けたと考えられる人を調べる目的で本事典を見始めました。森田の師呉秀三,青山胤通から始まって,片山国嘉,富士川游,榊俶,榊保三郎,門脇真枝,石田昇,清水耕一,高木兼寛,中村古狭,松村清吾……と調べました。結果は,一人を除いて業績を知ることができました。そのとき,編者が14年間かけて編集された,本書の深淵にふれた思いがしました。事典には生死の年が最初に書かれているので,森田正馬との関係を探るうえで参考になりました。と同時に時代背景が浮かびやすいと感じました。また,人ごとに抽出されている文献は人物像に迫っていく活動のヒントとなり,今,私はいつ果てるともない思索への旅を楽しんでいます。
本書は,「医学」人名事典と銘打たれていますが,「医学・医療」の発展に貢献した3762名(故人)を,医師,看護師,薬剤師,療法士,検査技師など医療職に限らず,社会事業家などからも選定しています。看護の立場から本書をみますと,105名の先人たちが載っていました。これは過去に類例がない規模になっているのではないでしょうか。そこで【看護師】の所だけを抽出して読んでみました。そこには看護が社会のなかでその役割を果たしながら発展している現状に多くの先人の働きがあったことが示され,看護界における歴史の一端を知ることができます。
本書を読み進むうちに,“実は,先人の志を詳らかにして次世代につないでいくのは,読者自身の責務”と語りかけられている思いがします。
最後に,膨大な作業を経て810ページにまとめられた本書は,その過程を包み込み,手に取りやすい重さとすてきな装丁に仕上がっているのも嬉しいことです。
(『看護教育』2013年5月号掲載)
未来に残る医療界の大きな遺産 (雑誌『看護研究』より)
書評者: 川原 由佳里 (日本赤十字看護大学准教授・看護歴史研究室)
ついに,『日本近現代医学人名事典』が医学書院から刊行された。医学,歯学,薬学,看護学などの分野の研究者にとっては待ち望んでいた画期的な基礎資料である。これまで医療分野で活躍した人々を網羅した人名事典は存在せず,出版史上でもすでに絶版となった1950年の『世界医学人名事典』(木下正中著,医学書院)くらいだという。それだけでも本書が公刊された意義は大きい。
全体で810ページの大著であり,明治元年から平成23年末までの約145年間にわたり,医学・医療に携わった3762名もの関係者が記載されている。
それぞれの人物に関する記述は簡潔で読みやすい。医療の各分野を開拓,発展させた医師,看護師に始まり,近代日本の医療福祉に貢献した政治家,行政担当者,事業家,軍医までを含む幅広い分野の人々の歩みが記載されている。氏名,生年月日はもちろん,旧姓,卒業大学,勤務先と役職,研究内容,退職後の活動,著書や共著書名といった内容まで記載されており,必要な情報を得ることができる。また付録の「年表」は,本文中に記載された人々が生きた時代について理解しやすいよう,明治元年からの社会の動きと医療にかかわる出来事が簡潔にまとめられている。あわせて必要な人名に迅速にアクセスすることが可能な索引を駆使すれば,潜在的な能力を十分に活用できる。たいへん秀逸な事典である。
研究者ならもちろんのこと,そうでなくても日本の医療の成り立ちに関心をもつ人ならぜひ1冊手元に置いておきたい。気の向いたときにパラパラと眺めるだけでもよい。今日の医療が実現されるまでに,いかに大勢の人々がこの分野で仕事をされ,貢献されたかに思いを馳せることができる。あるいは人物ごとに,彼らの学び,経験,医療に関する課題への取り組みをじっくりと読むことで,ある人物の意外な経歴を知ったり,他の人との関係がわかったり,時代背景を理解したりする。そうするうちに,過去の人々は現代の私たちにどのようなメッセージを発するだろうか,などと考えはじめる。「歴史とは現在と過去との対話である」と述べたのは歴史学者のE. H. カーであるが,この事典には,過去の人々との対話を促し,私たちもまた歴史的存在であることの自覚をもたらす力が備わっている。
最後に,この事典のすばらしさをもう1つ語らせてもらいたい。編者が序文で述べている「人々の仕事は先人の仕事の上に成り立っている」という言葉の通り,この事典のすみずみに,編者の方の謙虚さが行き渡っている。歴史的事実の正確を期し,必要かつ十分な情報を精選し,しかも華美な修飾は一切ない。その確実かつ謙虚な態度がすばらしい。それは編者が14年もの歳月をかけて編纂したプロセスに裏打ちされているのだろう。この事典は確実に,医学・医療領域における重要な資産の1つとなるであろうし,今後ともぜひ,継続的に増補・改訂を重ねていかれることを願ってやまない。
(『看護研究』2013年4月号掲載)
「歴史もの」がプレゼンスを示した2012年、味わい深い事典が刊行 (雑誌『精神看護』より)
書評者: 鈴木 晃仁 (慶應義塾大学・医学史)
2012年の日本の医学界を振り返ると、山中伸弥教授のノーベル賞受賞という最先端の研究と並んで、「歴史もの」が確かなプレゼンスを示すようになった1年であった。「医学史」の研究はもちろん以前からおこなわれており、優れた書物も出版されていたが、過去からの蓄積と新刊された書物が相まって、ある〈まとまり〉のようなものを示すようになった。医学と医療の現在性、未来志向性と並んで、それが持つ長い歴史が確かな存在感を持つようになったのである。
医学書院から昨年発行された書籍をみても、金川英雄が翻訳し解説を付した呉秀三・樫田五郎『精神病者私宅監置の実況』はベストセラー並みの扱いであるが、これは今から100年ほど前に発行された論文を現代の医療関係者にも無理なく読めるように現代語訳したものである。木村哲也『駐在保健婦の時代 1942-1997』は、激動の戦中から戦後・高度成長期に形成された日本人の健康と日常を、高知県の保健婦の現代史を通じて生き生きと復活させた著作である。翻訳ものでは、ウィリアム・バイナムとヘレン・バイナムの『Medicine 医学を変えた70の発見』は、私も共訳者の1人であるが、医学史の専門家だけでなく多くの人々に訴えるインパクトがある図版を300点以上も掲載したヴィジュアル医学史の決定版である。
これらの2012年の成果は、近年の多彩で多様な医学史の書物と融合して、「医学史」というものを、緩やかだが確かな形で存在感をもつ主題として作り上げてきた。たとえば、2008年に医師の茨木保が執筆して医学書院から発行された『まんが 医学の歴史』、2010年に藤原書店から刊行された主にフランスの歴史学者たちによる豪華な『身体の歴史』全3巻、2012年に歴史学者の青木歳幸が吉川弘文館から刊行した『江戸時代の医学-名医たちの300年』などが、記憶に新しい。これらの仕事に、『看護教育』に連載されている茨木保「ナイチンゲール伝」や、大河ドラマの主人公の山本八重が日清・日露戦争に篤志看護婦として参加する姿も加えることができるだろう。
『日本近現代医学人名事典』は、このような医学史という領域に、伝記的な基礎を与える重要な仕事である。明治元年(1868)から平成23年(2011)までの140年あまりの期間に、医学・医療に携わった人物で、すでに物故された3,762人の記録である。日本の医者が中心であるが、日本やその植民地などで活躍した外国人の医療者や、看護師、薬剤師、医療の社会運動家、医療問題で活躍した患者など、医療という領域を作り上げている多様な領域から選ばれている。それぞれの人物の項目は、国内の医学校や留学などの教育や、大学や病院や教会などの役職の記述を中心にしたものになっており、業績の解説や著作と評伝などの文献的な情報が付け加えられている。医学関連の政治・行政や医学評論だけでなく、医師であると同時に歌人や文学者などとして活躍した個人も採用されている。親戚や婚姻関係などの記述も味わい深い。巻末につけられた「年表」は、明治から平成をカバーする優れた医学年表になっており、自分が生まれた年に何が起きたのかをまず見てみると楽しい。
この書物が多くの医療関係者の本棚に置かれて、医学の歴史が多くの人々に実感されることが望まれる。そうすれば、現在において実用的であり、未来には改善される医療というだけでなく、長い伝統を持つ豊かな営みという〈新しい〉顔を見せることだろう。
(『精神看護』2013年5月号掲載)
日本の近代医学の歴史を語る貴重な資料
書評者: 高久 史麿 (日本医学会長・自治医科大学名誉学長)
今回,医学書院から泉孝英先生の編集による『日本近現代医学人名事典』が刊行された。この事典で紹介されている方々は,2011年末までに死去された医療関係者の方々である。紹介の対象になっているのは医師,医学研究者が大部分であるが,歯科医師,看護師,薬学,体育指導者,宣教師,事業家(製薬業),工学者(衛生工学),社会事業家,厚生行政の方,生物学者など,幅広い業種の方々であり,いずれもわが国の医療の発展に大きく貢献された方々である。本誌に紹介されている方々の年代は誠に長く,1868年から2011年までの143年に及び,その数は3,762名に達している。
本書の「序」にも紹介されているように,1868年はわが国に西洋医学が導入された年であるから,本書は,日本の近代医学・医療に貢献された先達のご経歴とご業績を網羅した“一大人名事典”であるといって過言ではないであろう。
この書評を書くにあたって,私自身が指導を受けた20人近くの恩師の方々の名前を拾い上げてその内容を読んでみたが,その内容の正確さに強い感銘を受けた。なお,この20人の方々の各々のご業績の紹介に関しては,その内容にやや濃淡があるように感じられたが,これだけ多くの方々の紹介であるからこの程度のばらつきはやむを得ないであろうと考えている。
泉孝英先生が胸部の疾患をご専門にされておられたことは,先生が京都大学の教授の時からよく存じ上げていたが,先生がご退官後14年間かけて本書の編集にあたられたことを本書の「序」で知った。医学者としての泉孝英先生しか知らなかった私にとって,大きな驚きであった。あらためて泉先生の本書の編集に対する甚大なご尽力に心からの敬意を表すると同時に,泉先生のご努力が本書を日本の近代医学の歴史を語る貴重な資料にしたと私は考えている。
このような貴重な資料の作成に成功された泉孝英先生ならびに医学書院の方々に衷心からお祝いの言葉を捧げるとともに,1人でも多くの方々に本書を貴重な資料として温存していただきたいという私の願いの言葉をもって,推薦の言葉の締めくくりとしたい。
たぐいまれな,近現代医学の歴史教科書としても優れた書
書評者: 早石 修 (大阪バイオサイエンス研究所名誉所長)
本書は,1868(明治元)年3月に明治政府が欧米医学を公式に採用して以来,2011(平成23)年末までに物故された医療関係者で,特にわが国の医学・医療の発展に貢献された3,762名を選んで,物語風に記録されたユニークな人名事典であります。何分にも膨大な内容であり,私自身,生化学という限られた基礎医学が専攻分野なので,医学・医療全体の問題を議論したり,評価することには必ずしも適任ではありません。それでもまず本書を通読して,最も重要な“人選”が極めて公正で妥当であるという印象を受けました。
次に個々の記載について,個人的に親しかった方々について詳しく調べました。いずれもおおむね正確な情報に基づいており,しかも専門的な記述以外に本人の性格,趣味,交際,家族など私的な紹介も多く,読物としても興味深いものでした。以下,幾人かを収載人物の例として挙げます(敬称略)。
古武弥四郎(本書253ページ)は,「わが国の生化学の開祖」荒木寅三郎(25ページ)の門下で,「わが国の生化学の基礎を築いた」人物です(私にとってはティーチャーというよりメンターというべき方でした)。その講義は極めて難解であったため,学生時代の私は医化学の道を諦め,「わが国におけるウイルス研究の先駆者」谷口腆二(393ページ)の業室研究生にしていただきました。卒後,軍医として出征し終戦後に破壊された大阪の惨状の中に戻って臨床医になるか迷ったとき,改めて基礎医学の道を勧めてくれたのが谷口と,後述する父でした。その後,阪大微生物病研究所(微研)を経て渡米してアメリカ国立健康研究所(NIH)部長となった私を,京大で医化学講座第3代教授内野仙治(92ページ)の後任人事が難航した折,当時の医学部長平沢興(514ページ)が異例の決断をされ,招聘された縁がありました。
1909年の「世界で最初の内因性睡眠物質の発見者」石森国臣(53ページ)は,同時期にアンリ・ピエロンが,ほぼ同じアイデアによる実験から類似の結果を出してフランスで発表し,欧米で著名になったのに対し,日本語雑誌で発表した石森は,世界的には無名のまま近年に至っていたわけです。2009年にはその発見100周年を祝して,私が記念講演をさせていただきました。1つ残念なのは,石森は生理学者であり,その当時の有機化学者との共同研究をされなかったため物質の同定がされていないことでした。1世紀後の私は,「視床下部温度感受性ニューロンを発見」された優秀な生理学者の中山昭雄(450ページ)と共同実験を行なうことによって,プロスタグランジンD2の睡眠誘起作用を生理学の立場からも確認することができました。
驚いたのは,わが父早石実蔵(496ページ)が収載されたことです。父は祖母一人に育てられ18歳で医師免許を取得,臨床医としても研究者としても大変優れた人で,8歳年下の妻光子と共々満95歳の長命で亡くなりましたが,最後まで最新の英文医学誌に目を通す勉強家でした。編者泉孝英博士による解説を医学界新聞(第3008号【寄稿】近代医学の145年)で拝見して,父のように在野で過ごしたため,医学の正史からは忘れられた無名人をも顕彰する趣旨があったことに感銘を受けました。また加うるに,収載人物それぞれの医学・医療に対する貢献を第三者にもわかりやすく解説されるために,膨大な参考文献,資料,年表などを別添されていることも,本書の付加価値を大きく高めています。
本書は,日本はおろか海外にもたぐいまれな,ユニークな近現代医学の歴史教科書としても極めて優れたものであり,編者のライフ・ワークとして高く評価されるべきものと信じます。
事典としての有用性を超えた,読み応えのある書
書評者: 猪飼 周平 (一橋大大学院教授・総合社会科学(比較医療史))
本書は,呼吸器内科を専門とする医学者が14年にわたり,明治期以降日本の近代医学・医療の発展に貢献した3,762名(物故者)の履歴を調べあげた成果である。評者のように,明治期以降の医業関係誌を参照する機会の多い者にとっては,このように便利かつ確度の高いレファレンスが完成したことは,大変喜ばしいことであり,そのありがたみは今後随所で感じられることになるであろう。編者の長年のご苦労に感謝したい。
とはいえ,本書を単に事典として理解するとすれば書評の対象とする必要はないかもしれない。そこで以下では,本書を約800ページの読物と解してその意義を考えてみたい。
まず,本書に掲載されている人物の履歴を見ると,医師が大部分(3,383名)であり,またその大部分が大卒(3,027名)で占められている。戦前において大卒の医師免許の下付数はおよそ1万6,000名であり,その大部分が物故していると考えれば,ざっとみて大卒医師の2割弱の履歴を本書がカバーしていることになる。このように理解すると,本書はどのように読めるだろうか。
なにより,近代医学において戦前の大卒医が選び抜かれたエリートとしての役割を担っていたということである。後世の医学者(編者)の視点から見て,近代医学・医療の発展に貢献したと評価できる大卒医が,大卒医の少なくとも2割近くもいるというのは,いかに大卒医が実質を備えたエリート集団であったかを物語っている。
実際,掲載されているその履歴を読んでみると,大学教員を経ている者が多く,概して大変華々しいものであるといえる。これは,たとえば大正期に初版が刊行された『日本医籍録』(版によっては国立国会図書館の近代デジタルライブラリーで利用できる)と比較するとわかりやすい。
戦前を通じて,医師には,おおまかに言って,上から「大卒,医専卒,試験及第医,従来開業医」という4つの階層があった。『日本医籍録』の場合,試験及第医や従来開業医の掲載が多く,その経歴も,資格取得後比較的早く開業するのが一般的であった。そのような医師たちにとっては,開業地に地盤を形成し,市郡レベルの医師会などで社会的地位を確保してゆくキャリアが成功のパターンであったといえよう。これに対して,本書に掲載されている大卒医たちは,基本的に大学の教員としてのキャリアを経ている者が多い。本書に収載されている医専卒(医学校卒含む)が316名にとどまっていることからも示唆されるように,医専を卒業して教員のキャリアを登った事例は少ない。ここから,戦前日本の医師4階層の中で隔絶した最上位階層として,また他の階層の医師たちとは異なった使命を帯びた存在として大卒医(少なくともその2割)があったことを読み取ることができるだろう。
もちろん,評者のように本書を読むというのは,おそらく一般的な利用法ではないだろう。ただ,読物として読み応えがあることがよい事典の条件の1つであるとするならば,少なくとも評者には,本書は単なる事典としての有用性を超えたよい事典であるといえる。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。