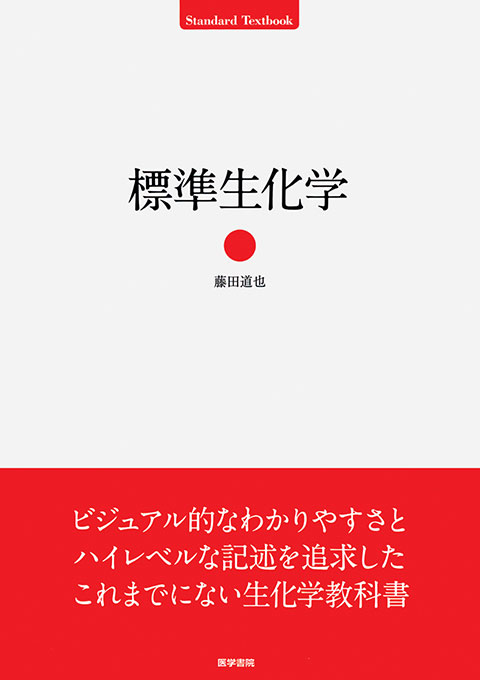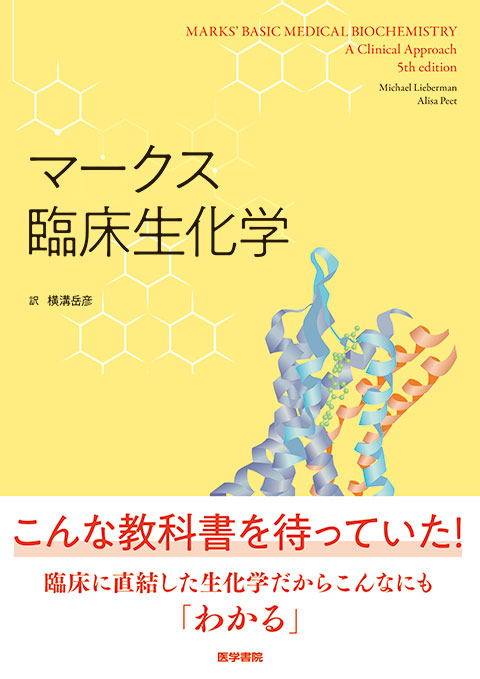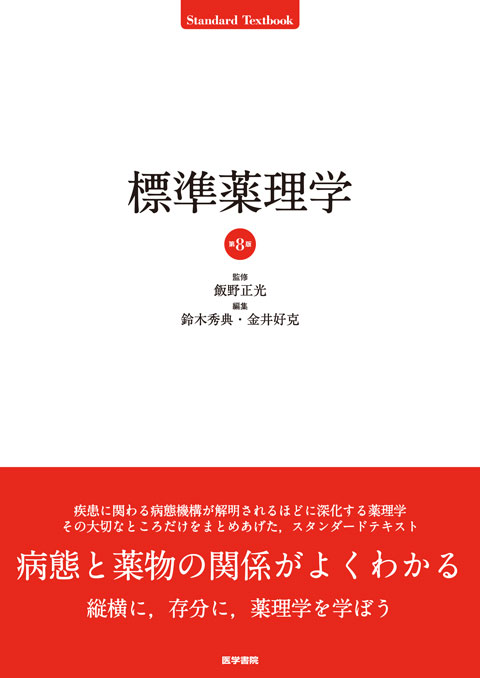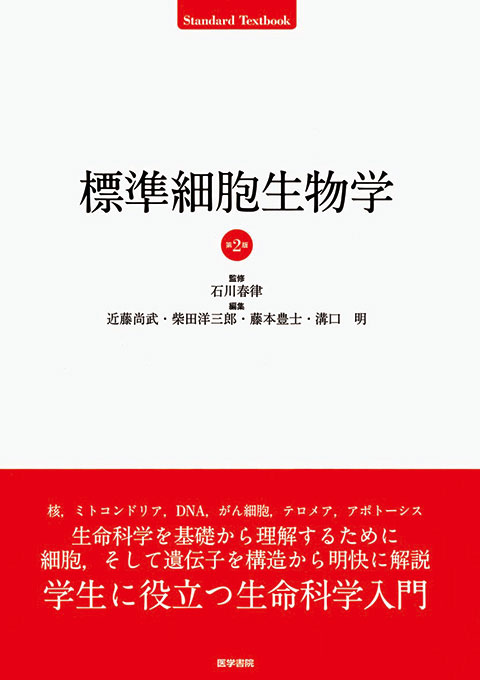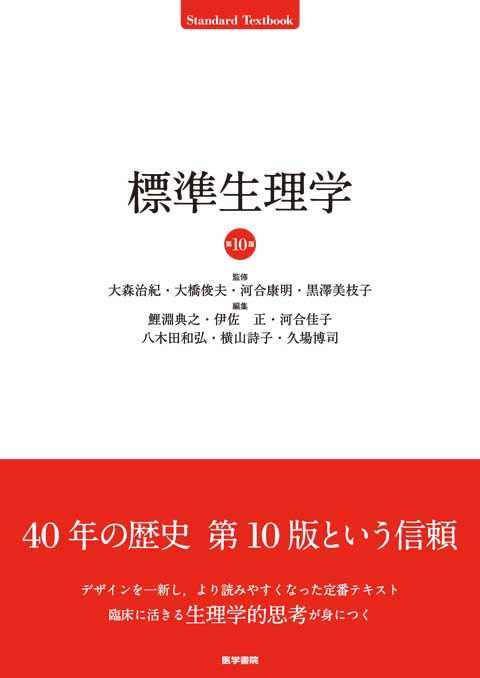標準生化学
生化学への理解を促す工夫に満ちた教科書
もっと見る
生化学の基本的事項からの記述や図の多用など、生化学の教育に長年携わってきた著者の単独執筆だからこそ成しえた工夫に満ちた教科書。生化学において重要な代謝の解説に重きを置く一方、がんの基礎医学の理解のため細胞周期の制御とがん関連タンパク質にも詳細な言及がされるなど、類書を見ないユニークな内容構成。随所で最新の学説も紹介されており、知的好奇心を刺激されながら読み通したくなる1冊。
| ● | 『標準医学シリーズ 医学書院eテキスト版』は「基礎セット」「臨床セット」「基礎+臨床セット」のいずれかをお選びいただくセット商品です。 |
| ● | 各セットは、該当する領域のタイトルをセットにしたもので、すべての標準シリーズがセットになっているわけではございません。 |
更新情報
-
2025.04.23
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
序
なぜ生化学を学ぶことがだいじなのか
われわれのからだは物質(原子・分子)を抜きに語ることはできない。これらの物質が互いに作用し合うことによってはじめて細胞・組織・器官が機能し,さらに個体としての生命活動を営むことが可能になる。人間としての生命活動を最も基本的なレベルで支えているのが物質とそれらの間の反応であることは議論の余地がない。
この人間活動の最も基本的な機構を理解するためにあるのが「生化学」という教科である。生化学はその先端においてなお発達を続けつつも,その大方においてすでに単なる学問の段階を通り過ぎ「生体を理解するための基本的な知識」つまり「医学における常識」として定着している。
この教科を学ぶことで栄養学,分子医学・分子生物学がよりよく理解されるとともに,健康とは何か,病気とは何かという医学の根本問題をその基礎において理解するための確かな道が拓〈ひら〉かれるのである。したがって,医学生は生化学を疎ましく思うことなくこれを学び,生化学的思考を身につけてもらいたい。
本書について
従来,生化学を理解しようとする学生にとって市販の教科書と現実の授業とのギャップが問題だった。教科書の中には主に期末試験の対策のために作られたものを少なしとしなかったからである。それはそれで役に立っていることは間違いがない。しかし,それで事足れりとしていては,せっかく長時間をかけて行われる授業が理解不全に終わってしまうおそれがある。現場の講義(それは現在世界の学界で新しく得られつつある知見の紹介が核になる)の理解を深め,足らざるところを補うことを主眼としてこの教科書が作成された。その点をご理解いただければそれに過ぎる幸いはない。
かといって,本教科書は読者に有機化学や生物科学の知識があることを前提として書かれているのではないことは,始めの数ページをめくっていただければわかるであろう。生化学を理解するのに必要なきわめて初歩的な段階から始めて徐々に程度を上げる方法によっているので,最初から順序を踏んで学んでいただければ全体を理解するのに大きい困難はないはずである。もし読者が理解するのに困難を感じる箇所があるとすれば,それは関連分野の知識がまだ未解決の状態にあるか,または著者の説明の至らなさによるのであって,後者の場合は著者の菲才をお許しいただきたい。
本書では,関連分野の教科書で詳述されている事項については原則的にそれらに委ねる方針を採った。つまり,関連分野の教科書とのオーバーラップによるむだ を避け,生化学の教科書としての独自性を尊重した。そのような観点から,医学の生化学にとって特に重要なテーマについては十分なページ数を割いた。なかでも代謝についてはかなりのページ数を割き,臨床の基礎としての生化学がいかに大事なものであるかを強調した。また,がんの基礎医学の理解に欠くことのできない細胞周期の制御とがん関連タンパク質(遺伝子)についても類書を抜く十分なスペースを当てた。
話の進め方に関してはやさしいものから始め序々にレベルを上げるという方針を採った。その際,全体としてできるだけ本文を簡潔にし,図を多用して理解を得やすくした。
本書は「人体の生化学」であり,とくに断わらない限り物質や反応(代謝)はヒトのそれである。類書ではそこが明確になっていないものがある。植物や微生物に固有の代謝とヒトのそれを区別しないで構成した代謝経路を提示している場合もまれではない。
医学部の授業はただ単に年度末に単位を認定するためのものであってはならない。授業で最先端の研究の息吹に接することが学生を刺激し医学への情熱を掻き立たせるのだという信念に導かれて本書を執筆した。したがって,本書では同時代性を徹底的に追求した。そのため,将来変更される可能性のある仮説をもあえて取り入れた。「先走り過ぎる」あるいは「標準生化学でなく非標準生化学だ」というそしりを受ける覚悟である。しかし,教科書製作者は学生を愚弄してはならないと思う。本書が読者を刺激して更なる知識の探求に向かわせるきっかけとなればこれに過ぎる喜びはない。
執筆に当たっては,藤田がまず本書の第一稿(図表を含む)を作成し,それを執筆協力者に査読していただき,寄せられた意見を取り入れて改変したものを完成稿とした。執筆協力者のご支援に心から感謝するとともに読者のご愛顧とご批判をお願いしたい。最後に,糖鎖の記号表記法についてご教示いただいた大阪大学名誉教授谷口直之氏に感謝する。
2012年6月
藤田 道也
なぜ生化学を学ぶことがだいじなのか
われわれのからだは物質(原子・分子)を抜きに語ることはできない。これらの物質が互いに作用し合うことによってはじめて細胞・組織・器官が機能し,さらに個体としての生命活動を営むことが可能になる。人間としての生命活動を最も基本的なレベルで支えているのが物質とそれらの間の反応であることは議論の余地がない。
この人間活動の最も基本的な機構を理解するためにあるのが「生化学」という教科である。生化学はその先端においてなお発達を続けつつも,その大方においてすでに単なる学問の段階を通り過ぎ「生体を理解するための基本的な知識」つまり「医学における常識」として定着している。
この教科を学ぶことで栄養学,分子医学・分子生物学がよりよく理解されるとともに,健康とは何か,病気とは何かという医学の根本問題をその基礎において理解するための確かな道が拓〈ひら〉かれるのである。したがって,医学生は生化学を疎ましく思うことなくこれを学び,生化学的思考を身につけてもらいたい。
本書について
従来,生化学を理解しようとする学生にとって市販の教科書と現実の授業とのギャップが問題だった。教科書の中には主に期末試験の対策のために作られたものを少なしとしなかったからである。それはそれで役に立っていることは間違いがない。しかし,それで事足れりとしていては,せっかく長時間をかけて行われる授業が理解不全に終わってしまうおそれがある。現場の講義(それは現在世界の学界で新しく得られつつある知見の紹介が核になる)の理解を深め,足らざるところを補うことを主眼としてこの教科書が作成された。その点をご理解いただければそれに過ぎる幸いはない。
かといって,本教科書は読者に有機化学や生物科学の知識があることを前提として書かれているのではないことは,始めの数ページをめくっていただければわかるであろう。生化学を理解するのに必要なきわめて初歩的な段階から始めて徐々に程度を上げる方法によっているので,最初から順序を踏んで学んでいただければ全体を理解するのに大きい困難はないはずである。もし読者が理解するのに困難を感じる箇所があるとすれば,それは関連分野の知識がまだ未解決の状態にあるか,または著者の説明の至らなさによるのであって,後者の場合は著者の菲才をお許しいただきたい。
本書では,関連分野の教科書で詳述されている事項については原則的にそれらに委ねる方針を採った。つまり,関連分野の教科書とのオーバーラップによるむだ を避け,生化学の教科書としての独自性を尊重した。そのような観点から,医学の生化学にとって特に重要なテーマについては十分なページ数を割いた。なかでも代謝についてはかなりのページ数を割き,臨床の基礎としての生化学がいかに大事なものであるかを強調した。また,がんの基礎医学の理解に欠くことのできない細胞周期の制御とがん関連タンパク質(遺伝子)についても類書を抜く十分なスペースを当てた。
話の進め方に関してはやさしいものから始め序々にレベルを上げるという方針を採った。その際,全体としてできるだけ本文を簡潔にし,図を多用して理解を得やすくした。
本書は「人体の生化学」であり,とくに断わらない限り物質や反応(代謝)はヒトのそれである。類書ではそこが明確になっていないものがある。植物や微生物に固有の代謝とヒトのそれを区別しないで構成した代謝経路を提示している場合もまれではない。
医学部の授業はただ単に年度末に単位を認定するためのものであってはならない。授業で最先端の研究の息吹に接することが学生を刺激し医学への情熱を掻き立たせるのだという信念に導かれて本書を執筆した。したがって,本書では同時代性を徹底的に追求した。そのため,将来変更される可能性のある仮説をもあえて取り入れた。「先走り過ぎる」あるいは「標準生化学でなく非標準生化学だ」というそしりを受ける覚悟である。しかし,教科書製作者は学生を愚弄してはならないと思う。本書が読者を刺激して更なる知識の探求に向かわせるきっかけとなればこれに過ぎる喜びはない。
執筆に当たっては,藤田がまず本書の第一稿(図表を含む)を作成し,それを執筆協力者に査読していただき,寄せられた意見を取り入れて改変したものを完成稿とした。執筆協力者のご支援に心から感謝するとともに読者のご愛顧とご批判をお願いしたい。最後に,糖鎖の記号表記法についてご教示いただいた大阪大学名誉教授谷口直之氏に感謝する。
2012年6月
藤田 道也
目次
開く
第1章 生化学から見た人体の作り
I 人体の単位-細胞
1.形質膜(細胞膜)
2.核
3.小胞体
4.ゴルジ装置
5.リソソーム
6.ミトコンドリア
7.ペルオキシソーム
8.細胞骨格
9.サイトゾル
10.細胞の極性
11.細胞間マトリックス
II 器官と組織
1.循環系
2.消化系
3.呼吸系
4.泌尿系
5.内分泌系
6.神経系
第2章 生体の物質的基礎
I 生体を構成する元素とそれらの作る結合
1.生体に多い6元素と量比
2.生体元素の作る結合
II 糖質(糖)
1.糖質の基本構造と性質
2.単糖の構造と性質
3.単糖の誘導体
4.多糖(グリカン)
III 脂質
1.脂質の性質と基本構造
2.脂肪酸
3.単純脂質
4.複合脂質
IV アミノ酸,ペプチド,タンパク質
1.アミノ酸
2.ペプチドとポリペプチド
3.複合タンパク質
V ヌクレオチドと核酸
1.ヌクレオチド
2.核酸
第3章 人体の基本代謝
I 代謝総論
1.異化と同化
2.代謝の調節
3.代謝系のバランス
4.代謝の区画化
5.酵素の本体
6.酵素キネティックス(酵素反応速度論)
7.アロステリック効果
8.誘導適合仮説
9.酵素の分類
10.酵素の命名
II 糖質の分解
1.解糖系への基質の供給
2.解糖
III 脂質の分解(脂肪酸酸化)
1.脂肪酸酸化系への基質の供給
2.脂肪酸の酸化
IV アミノ酸の異化
1.アミノ基転移
2.尿素回路
3.炭素骨格の異化
4.生理活性物質への転化
5.アミノ酸代謝の異常
V ヌクレオチドの異化
1.プリンヌクレオチドの異化
2.ピリミジンヌクレオチドの異化
3.ヌクレオチドのその他の代謝と塩基の回収
VI 共通の終末酸化系-クエン酸回路と呼吸鎖
1.クエン酸回路(TCAサイクル)
2.呼吸鎖(電子伝達系)
VII グルコースの合成
1.糖新生(グルコネオゲネシス)
2.フルクトース,ガラクトースのグルコースへの転化
VIII 脂質の合成
1.脂肪酸の合成
2.グリセロ脂質の合成
3.スフィンゴ脂質の合成
IX 塩基とヌクレオチドの合成
1.プリン塩基とプリンヌクレオチドの合成
2.ピリミジン塩基とピリミジンヌクレオチドの合成
第4章 基本代謝系の相関と統合
I 代謝経路における調節
1.グルコース代謝の調節
2.グリコーゲン代謝の調節
3.脂肪酸とトリアシルグリセロール代謝の調節
II 器官・組織における代謝の統合
1.ホルモンによる代謝の統合
2.受容体シグナリング
III エネルギー代謝の病態-肥満と2型糖尿病
1.肥満
2.インスリン抵抗性
3.2型糖尿病
第5章 遺伝情報の発現と保存
I 遺伝情報の発現
1.転写
2.スプライシング
3.転写のその他の問題-エピジェネシス
4.翻訳
II 遺伝情報の保存と変化
1.DNAの複製
2.DNAの損傷と修復
3.組換え
III 細胞増殖
1.細胞周期とその制御
2.細胞周期制御の異常
第6章 血液と細胞性ストレス
I 血液
1.リポタンパク質
2.凝固と線溶
3.ヘムの合成と分解(ポルフィリン代謝)
II 細胞性ストレス
1.酸化ストレス
2.小胞体ストレス
索引
I 人体の単位-細胞
1.形質膜(細胞膜)
2.核
3.小胞体
4.ゴルジ装置
5.リソソーム
6.ミトコンドリア
7.ペルオキシソーム
8.細胞骨格
9.サイトゾル
10.細胞の極性
11.細胞間マトリックス
II 器官と組織
1.循環系
2.消化系
3.呼吸系
4.泌尿系
5.内分泌系
6.神経系
第2章 生体の物質的基礎
I 生体を構成する元素とそれらの作る結合
1.生体に多い6元素と量比
2.生体元素の作る結合
II 糖質(糖)
1.糖質の基本構造と性質
2.単糖の構造と性質
3.単糖の誘導体
4.多糖(グリカン)
III 脂質
1.脂質の性質と基本構造
2.脂肪酸
3.単純脂質
4.複合脂質
IV アミノ酸,ペプチド,タンパク質
1.アミノ酸
2.ペプチドとポリペプチド
3.複合タンパク質
V ヌクレオチドと核酸
1.ヌクレオチド
2.核酸
第3章 人体の基本代謝
I 代謝総論
1.異化と同化
2.代謝の調節
3.代謝系のバランス
4.代謝の区画化
5.酵素の本体
6.酵素キネティックス(酵素反応速度論)
7.アロステリック効果
8.誘導適合仮説
9.酵素の分類
10.酵素の命名
II 糖質の分解
1.解糖系への基質の供給
2.解糖
III 脂質の分解(脂肪酸酸化)
1.脂肪酸酸化系への基質の供給
2.脂肪酸の酸化
IV アミノ酸の異化
1.アミノ基転移
2.尿素回路
3.炭素骨格の異化
4.生理活性物質への転化
5.アミノ酸代謝の異常
V ヌクレオチドの異化
1.プリンヌクレオチドの異化
2.ピリミジンヌクレオチドの異化
3.ヌクレオチドのその他の代謝と塩基の回収
VI 共通の終末酸化系-クエン酸回路と呼吸鎖
1.クエン酸回路(TCAサイクル)
2.呼吸鎖(電子伝達系)
VII グルコースの合成
1.糖新生(グルコネオゲネシス)
2.フルクトース,ガラクトースのグルコースへの転化
VIII 脂質の合成
1.脂肪酸の合成
2.グリセロ脂質の合成
3.スフィンゴ脂質の合成
IX 塩基とヌクレオチドの合成
1.プリン塩基とプリンヌクレオチドの合成
2.ピリミジン塩基とピリミジンヌクレオチドの合成
第4章 基本代謝系の相関と統合
I 代謝経路における調節
1.グルコース代謝の調節
2.グリコーゲン代謝の調節
3.脂肪酸とトリアシルグリセロール代謝の調節
II 器官・組織における代謝の統合
1.ホルモンによる代謝の統合
2.受容体シグナリング
III エネルギー代謝の病態-肥満と2型糖尿病
1.肥満
2.インスリン抵抗性
3.2型糖尿病
第5章 遺伝情報の発現と保存
I 遺伝情報の発現
1.転写
2.スプライシング
3.転写のその他の問題-エピジェネシス
4.翻訳
II 遺伝情報の保存と変化
1.DNAの複製
2.DNAの損傷と修復
3.組換え
III 細胞増殖
1.細胞周期とその制御
2.細胞周期制御の異常
第6章 血液と細胞性ストレス
I 血液
1.リポタンパク質
2.凝固と線溶
3.ヘムの合成と分解(ポルフィリン代謝)
II 細胞性ストレス
1.酸化ストレス
2.小胞体ストレス
索引
書評
開く
著者の熱い思いが込められた優れた教科書の誕生
書評者: 畑 裕 (東京医歯大教授・病態代謝解析学)
「標準生化学でなく非標準生化学だというそしりを受ける覚悟である」と著者は決意を述べられている。医学書院の標準シリーズといえば,医学生向けの正統的教科書の印象が強い。評者が医学生であった三十年近い昔もその位置付けは確固としていた。そのシリーズに『標準生化学』が装い新たに加わった。白を基本とするすっきりした装丁は,掃き清められた禅寺の白砂にも似て清浄で書店の棚で目を引く。そして,手に取ると,いきなり「非標準生化学」とあって驚かされる。「医学部の授業はただ単に年度末に単位を認定するためのものであってはならない。授業で最先端の研究の息吹に接することが学生を刺激し医学への情熱を掻き立たせるのだという信念に導かれて本書を執筆した」著者「序」には著者の熱い思いがほとばしっている。
一変したのは装丁だけではない。標準シリーズには同著者による『標準分子医化学』があり好評を博していたが,あえて,その前身を捨て去り「これまでにない生化学教科書」として新しく書き起こされている。単独執筆に移行したのは大英断だ。優れた教科書の条件はいろいろ考えられるが,一人の著者が初めから終わりまで書き通している教科書には良書が多い。医学の進歩,情報量の増大により,医学生に伝えるべき内容は複雑多岐になっている。どんなに博学な著者であってもすべてに精通するのは難しい。複数の専門家の参加が求められる。しかし,複数の書き手の介在は,複雑な情報を整理してわかりやすく伝達する上では,ともすると障壁になる。このジレンマを,一人の著者が第一稿をすべて執筆し,その後,二十八名の執筆協力者が査読し修正して完成させるという,コロンブスの卵のように単純で画期的な方法で克服している。長年,生化学領域で活躍されてきた著者だからこそ取り得た方法かもしれないが,今後の教科書を作成する上で大いに参考にすべき手法だ。
さて,そうして出来上がったのが,この『標準生化学』だ。全体300ページ,『標準分子医化学』に比べ,大分,軽量化した。教壇から語りかけるような文体は読みやすく頭に入りやすい。単独執筆の功だ。評者は医学生に「何か一冊,教科書を購入して通読するように。学生時代に読んだ教科書を手元に残しておくと,後日,必ず役に立つ」と勧める。医師として勤務する多忙な日常の中で,あいまいになった専門領域以外の知識を新たにしたいとき,学生時代の教科書は,夜道の提灯,霧の海の灯台のようなよりどころになってくれる。ところが,インターネットから情報を落とせるようになったせいか,教員が親切すぎてプリントやパワーポイントを配布するせいか,最近の医学生は成書を携えない傾向がある。本書は,分量的にも,読みやすさにおいても,価格の面でも,医学生が教科書として手元に置きやすそうだ。
医学生に限らない。本書は一義的には医学生を対象に書かれているようだが,医学生でなくても「最先端の研究の息吹」は「医学への情熱を掻き立てる」はずだ。理学部,薬学部,農学部などの学生も手に取ってほしい。現在の日本では,医学部基礎系教室が医学科出身者を大学院生,スタッフとして集めるのが難しくなっている。この傾向は今後,ますます強まると懸念される。そのときに活躍してほしいのは,医学生以外の関連学部出身者だ。アメリカの医学部のように,医師免許を持たない研究者が半数を占めて指導的な役割を果たすようにならなければ,すそ野の広い医学研究は維持できない。
著者「序」には「『代謝』と『細胞周期の制御』と『がん関連タンパク質』」には「類書を抜く十分なスペースを当てた」ともある。古典教科書的な生化学,分子生物遺伝学の項目は全体の6割にとどまり,残りはがんや代謝にかかわる先端的話題に割かれる個性的な構成になっている。だからといって「標準」でなくて「非標準」とは評者は思わない。「標準」は時代とともに変わる。現代の医学生を対象とする生化学教育では,これが「標準」かもしれない。とはいえ,先端部分を盛り込もうとすれば常時アップ・デートが要求される。「関連分野の教科書とのオーバーラップ」を避ける方針がとられているため,がんや糖尿病以外の疾病との関係の記述は限定されている。単位認定を目的とする学習を批判する著者の本意でないかもしれないが,当世学生気質や共用試験を考慮すると,練習問題を望む声も上がりそうだ。定期的なアップ・デート,関連教科書へのリンク,テキストへの練習問題挿入など,電子書籍を利用した対応策を出版社に講じてほしい。医学史をみると,グーテンベルクの印刷術はベザリウス以後の解剖学の知識普及に大きく影響したとある。電子書籍はグーテンベルク以来の革命だそうだ。歴史は過ぎ去って初めて全体像が見える。変革の最中にいる当事者には立ち位置がわかりづらい。昨日の「非標準」は今日の「標準」ということもある。私たちは医学教育における「標準」が一新される節目に立っているのかもしれない。
書評者: 畑 裕 (東京医歯大教授・病態代謝解析学)
「標準生化学でなく非標準生化学だというそしりを受ける覚悟である」と著者は決意を述べられている。医学書院の標準シリーズといえば,医学生向けの正統的教科書の印象が強い。評者が医学生であった三十年近い昔もその位置付けは確固としていた。そのシリーズに『標準生化学』が装い新たに加わった。白を基本とするすっきりした装丁は,掃き清められた禅寺の白砂にも似て清浄で書店の棚で目を引く。そして,手に取ると,いきなり「非標準生化学」とあって驚かされる。「医学部の授業はただ単に年度末に単位を認定するためのものであってはならない。授業で最先端の研究の息吹に接することが学生を刺激し医学への情熱を掻き立たせるのだという信念に導かれて本書を執筆した」著者「序」には著者の熱い思いがほとばしっている。
一変したのは装丁だけではない。標準シリーズには同著者による『標準分子医化学』があり好評を博していたが,あえて,その前身を捨て去り「これまでにない生化学教科書」として新しく書き起こされている。単独執筆に移行したのは大英断だ。優れた教科書の条件はいろいろ考えられるが,一人の著者が初めから終わりまで書き通している教科書には良書が多い。医学の進歩,情報量の増大により,医学生に伝えるべき内容は複雑多岐になっている。どんなに博学な著者であってもすべてに精通するのは難しい。複数の専門家の参加が求められる。しかし,複数の書き手の介在は,複雑な情報を整理してわかりやすく伝達する上では,ともすると障壁になる。このジレンマを,一人の著者が第一稿をすべて執筆し,その後,二十八名の執筆協力者が査読し修正して完成させるという,コロンブスの卵のように単純で画期的な方法で克服している。長年,生化学領域で活躍されてきた著者だからこそ取り得た方法かもしれないが,今後の教科書を作成する上で大いに参考にすべき手法だ。
さて,そうして出来上がったのが,この『標準生化学』だ。全体300ページ,『標準分子医化学』に比べ,大分,軽量化した。教壇から語りかけるような文体は読みやすく頭に入りやすい。単独執筆の功だ。評者は医学生に「何か一冊,教科書を購入して通読するように。学生時代に読んだ教科書を手元に残しておくと,後日,必ず役に立つ」と勧める。医師として勤務する多忙な日常の中で,あいまいになった専門領域以外の知識を新たにしたいとき,学生時代の教科書は,夜道の提灯,霧の海の灯台のようなよりどころになってくれる。ところが,インターネットから情報を落とせるようになったせいか,教員が親切すぎてプリントやパワーポイントを配布するせいか,最近の医学生は成書を携えない傾向がある。本書は,分量的にも,読みやすさにおいても,価格の面でも,医学生が教科書として手元に置きやすそうだ。
医学生に限らない。本書は一義的には医学生を対象に書かれているようだが,医学生でなくても「最先端の研究の息吹」は「医学への情熱を掻き立てる」はずだ。理学部,薬学部,農学部などの学生も手に取ってほしい。現在の日本では,医学部基礎系教室が医学科出身者を大学院生,スタッフとして集めるのが難しくなっている。この傾向は今後,ますます強まると懸念される。そのときに活躍してほしいのは,医学生以外の関連学部出身者だ。アメリカの医学部のように,医師免許を持たない研究者が半数を占めて指導的な役割を果たすようにならなければ,すそ野の広い医学研究は維持できない。
著者「序」には「『代謝』と『細胞周期の制御』と『がん関連タンパク質』」には「類書を抜く十分なスペースを当てた」ともある。古典教科書的な生化学,分子生物遺伝学の項目は全体の6割にとどまり,残りはがんや代謝にかかわる先端的話題に割かれる個性的な構成になっている。だからといって「標準」でなくて「非標準」とは評者は思わない。「標準」は時代とともに変わる。現代の医学生を対象とする生化学教育では,これが「標準」かもしれない。とはいえ,先端部分を盛り込もうとすれば常時アップ・デートが要求される。「関連分野の教科書とのオーバーラップ」を避ける方針がとられているため,がんや糖尿病以外の疾病との関係の記述は限定されている。単位認定を目的とする学習を批判する著者の本意でないかもしれないが,当世学生気質や共用試験を考慮すると,練習問題を望む声も上がりそうだ。定期的なアップ・デート,関連教科書へのリンク,テキストへの練習問題挿入など,電子書籍を利用した対応策を出版社に講じてほしい。医学史をみると,グーテンベルクの印刷術はベザリウス以後の解剖学の知識普及に大きく影響したとある。電子書籍はグーテンベルク以来の革命だそうだ。歴史は過ぎ去って初めて全体像が見える。変革の最中にいる当事者には立ち位置がわかりづらい。昨日の「非標準」は今日の「標準」ということもある。私たちは医学教育における「標準」が一新される節目に立っているのかもしれない。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。