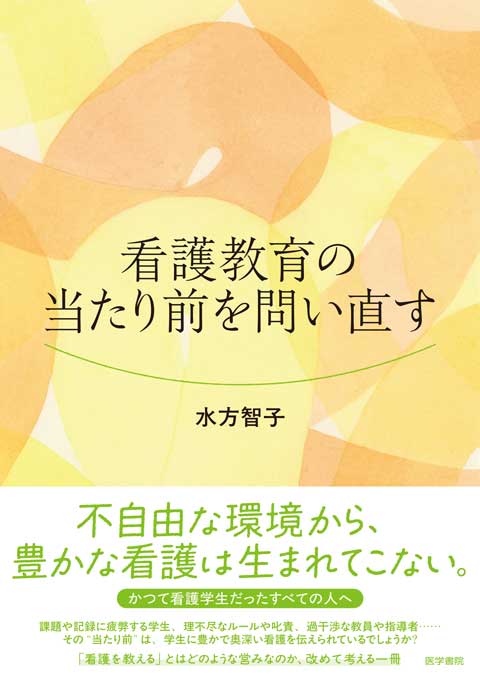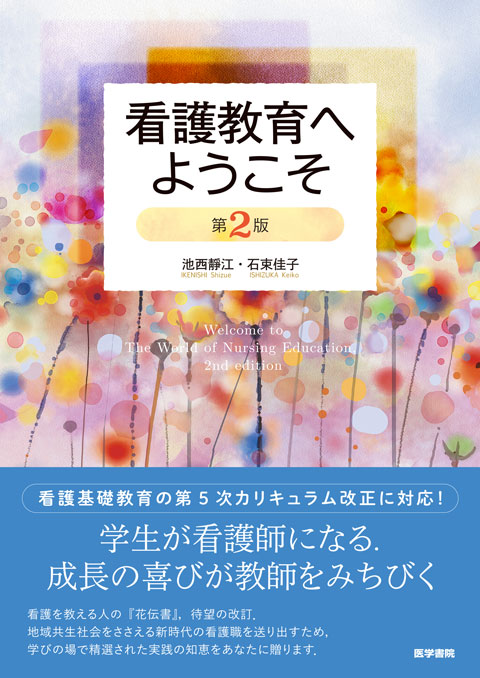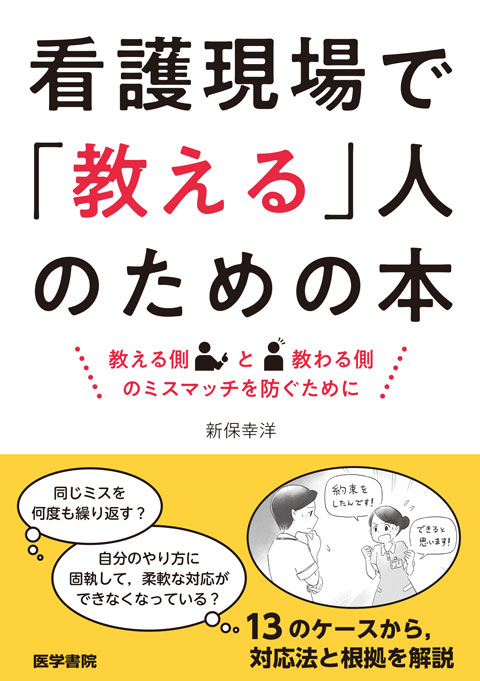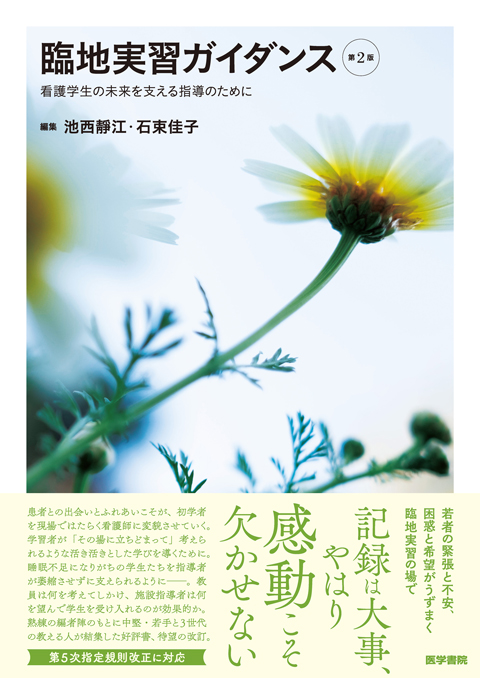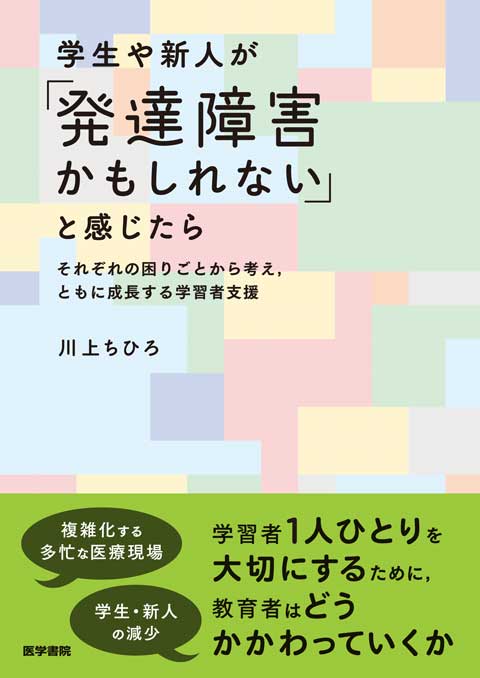看護教育の当たり前を問い直す
悪しき連鎖を “今” 断ち切って、もっとワクワクする看護教育へ
もっと見る
「看護学生に人権はない」「看護学校はパワハラの温床」──そんな言葉を耳にしたことはないだろうか。本書は、看護教育のハラスメント的指導、“べき論”の連鎖に終止符を打つ、覚悟と希望の書。「看護を教える」とはどのような営みなのか、看護も教育も本来の目的に立ち返り、もっと楽しく、ワクワクする看護教育へ。方法論? 否、教育の<本質>を問う、すべての“育てる人”に贈るバイブル。
| 著 | 水方 智子 |
|---|---|
| 発行 | 2025年11月判型:A5頁:224 |
| ISBN | 978-4-260-06238-1 |
| 定価 | 2,640円 (本体2,400円+税) |
更新情報
- 序文
- 目次
序文
開く
はじめに
今、日本社会は大きな変革期を迎えている。そのひとつは、2008年に既にピークとなった人口の急激な減少によるものであり、2030年には高齢化率が30パーセントを超え、2056年には人口が1憶人以下になると試算されている。そのような状況の中、今まで看護基礎教育が主な対象としてきた18歳人口も減少の一途をたどることは目に見えている。
そして、日本では2020年1月から始まった新型コロナウイルス感染症の流行が、医療者の労働環境の過酷さが周知されるきっかけになり、看護師等のエッセンシャルワーカーが人気のない仕事のひとつになってしまった。このような感染症の世界的な流行だけでなく、突発的な豪雨・地震といった自然災害の発生、IT技術の進化による産業構造の転換などにより、世界は急激に変化している。
このように、先行きが不透明で将来が予測困難な状態を「VUCA」と言う。「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の4つの単語の頭文字をとった造語である。VUCAの世界で今後何が起こるか、もはや誰も予測することはできない。
一方で、未だ看護教育では「今まで通り」が蔓延しているようにみえる。「看護教育での当たり前」が学生を追い詰めたり、教員同士の対立につながったりと、VUCAの時代になっても「今まで通り」から抜け出せていないことがあるように思えてならない。もちろん、患者や利用者・学生やスタッフ・教員を大切に運営している学校も多く存在しているが、看護学校でのハラスメントがニュースで報道されることもあり、この悪しき伝統を打破していくには、看護や教育に関わる一人ひとりの看護職の意識改革が必要であると思っている。教員が「教え込み」をしなくても、学生が「辛い思い」をしなくても、看護職になることはできる。
私自身、看護学校を卒業して40年以上、教員や管理者として仕事をしてきた。この間、自分はどうやって看護や教育、管理を学び、患者や学生や教員に関わってきたのかを再考してみたい。「あなたの言うことは理想論」と否定され、多くの失敗を積み重ねながらも周りの人たちに支えてもらう中で、「看護」「教育」「管理」が自分の中で明確になってきたように思う。そして、この経験から得られたものが、誰かの手がかりになることを願っている。このような私に寄り添い、諦めず一緒に歩んでくれた医学書院の番匠遼介氏、新鮮な感覚で私に示唆を与えてくれた福村紗希氏に、この場を借りて心からお礼を申し上げる。
これから看護師を目指す方、またそのご家族の方へ。本書は主に看護教育の厳しい面や問い直しが必要な部分について言及しているため、驚かれる方もいらっしゃるかもしれない。しかし、看護も看護教育も自分を豊かにするものであり、ワクワクするくらい心がときめく、とても奥深く面白い仕事である。そして、やっぱり「看護の道を進んでよかった」と私は思っている。ぜひ、みなさんにも豊かで深い看護の世界のドアを叩いてほしい。
そして、この本は臨床で勤務されている方にもぜひ読んでいただきたい。文中の「学生」を「後輩やスタッフ」に、「教員」を「指導者など看護を教える人」に読み替えていただけると嬉しい。
2025年8月
水方智子
目次
開く
第1部 看護教育を問い直す
1 看護教育とはどのような営みか?
「知情意」から教育を考える
2 「看護学生は課題が多い」は当たり前?
「教えてもらってないので分かりません」
手段が目的化していないか?
3 そもそも「看護」とは、「教育」とは何か
「看護」とは何か
「看護」と「教育」の原基形態
4 「○○してあげる」「あなたのことを想って」は勘違い
「看護」も「教育」も「対象中心」である
過剰援助は看護でも教育でもない
教授錯覚に陥っていないだろうか?
教員は学生の“親〞ではない
5 「看護教育」についての考え方
①「根性」論
②「教えれば、学ぶ」論
③「言えれば、できる」論
④「関係」論
看護教育における学習論の流れ
「管理」も「看護」「教育」と同じ形をしている
第2部 臨地実習指導を問い直す
1 「臨地実習が厳しい」のは当たり前?
「できない」のは「初学者」の特徴である
悪しき教育の連鎖を断ち切ろう
2 臨地実習とは、どのような営みか
経験の浅い指導者がとりがちな「伝授」という方法
実習指導の教材は、看護を教えてくれる「対象」
実習指導には立場の変換能力が必要
臨地実習指導は「事実のつきあわせ」が重要
指導者・教員側の対象像を学生に押しつけない
二者関係から「三者関係」への思考の転換
対象に害を与えようと思う学生はいない
看護や教育の実践を俯瞰するには事例検討が有効
3 実習指導・記録の当たり前を問い直す
学生の看護と病棟の看護は一致しない
臨地実習は教育課程に組みこまれたひとつの「授業」である
再実習をどう捉えるか
看護を「知る」ためには看護を「する」ことが一番
申し送りノートには「学生の成長」を記載しよう
学生の行動計画の事前確認は必要だろうか?
実習記録の赤ペンは必要だろうか
実習記録用紙に「枠」は必要だろうか
臨地実習の本質を見つめ直そう
自分の学習記録としての大学ノート
実習記録を自宅に持ち帰ることは必要だろうか
第3部 看護学生との関わり方を問い直す
1 「厳しい指導」は当たり前?
看護教育に厳しい指導は必要ない
「教えられたように」教えないために、教育観を再構成しよう
2 「学生向けにさまざまなルールを設ける」のは当たり前?
服装や髪色の規定を問い直す
学生が持つ権利を制限しすぎていないだろうか?
学生は時間があれば、勉強するのか
3 そもそも人間は主体的で自立的な存在である
人間は自分の意志で歩き出す
手をかければかけるほど、人は成長しない
学生自身に「困っていただく」ために
教員がみな同じ言動をする必要はない
実習のグループは学生たちで決められる
たくさん褒めれば、本当に人は育つのか?
承認欲求の呪縛から解放されよう
4 看護学校の使命を問い直す
完成された人を育てようとしてはいけない
「やってみる」ことなしに実践知は身につかない
看護学校の目的は学生の国家試験合格?
学校の目標を学生に強要してはならない
看護学校と病院は対等な関係であるべき
学校は病院の下請けではない
「査定」ばかりしていませんか
看護師のキャリアアップを問い直す
5 授業・演習は看護が楽しくなるような言葉で語ろう
授業とは「テキストを教える」ことではない
授業は計画(指導案)通りには進まない
学生が自分のアタマで「のぼり・おり」ができることを意識する
学内と臨床で乖離があるのは当然
看護技術の目的と手段の「往還イメージ」
6 これからの教育課程編成
私の経験から
「学年ごとに学ぶ」を問い直す
第4部 もっと楽しく、ワクワクする看護教育へ
1 教員の自己研鑽
①認識論からの学び──認識を3つの段階で捉える
②認識の「のぼり・おり」とキッカケことば
③人の「表現」と「認識」は同じではない
教員は「看護」と「教育」の両方の学習が必要
自己の実践から学び続けること──俯瞰・省察
自分の授業を公開しよう
2 私が歩んできた道を振り返る
看護職に就いた理由──全員が強い気持ちで看護職を目指すわけではない
看護基礎教育で学んだこと──教員の価値観を学生に押しつけない
看護師経験から学んだこと──看護管理とは「人を自由にさせること」
教員になって学んだこと──自己の実践を振り返ることと仲間がいることの大切さ
看護学校の責任者になって学んだこと──「ピンチ」は教育を飛躍的に発展する「チャンス」
日本看護学校協議会の会長になって学んだこと
3 学校管理の在り方を問い直す
看護職が学校管理者になる
「管理」も自分の経験から学ぶ
教務室ではフラットに
教員を悩ませる学生は「良い学生」である
看護教育も学校管理も「間接的看護」である
保護者対応はどうあるべきか──学生を中心に考える
芸能事務所に学ぶ組織づくり
教員の「売り」と「売り方」を考える
ひとつ上の仕事が意識できるように働きかける
4 看護教育をあなたが変える
自分の授業を変える
思考のトレーニングをする
本質を見つめ直し、教育をアップデートしよう
5 種をまいて仲間をつくろう
否定の否定の法則
爪を研いで時機を待て
6 異端児万歳!
すべては自分の糧になる
呪縛から解放されてもっと自由に! 楽しく!
参考・引用文献
索引