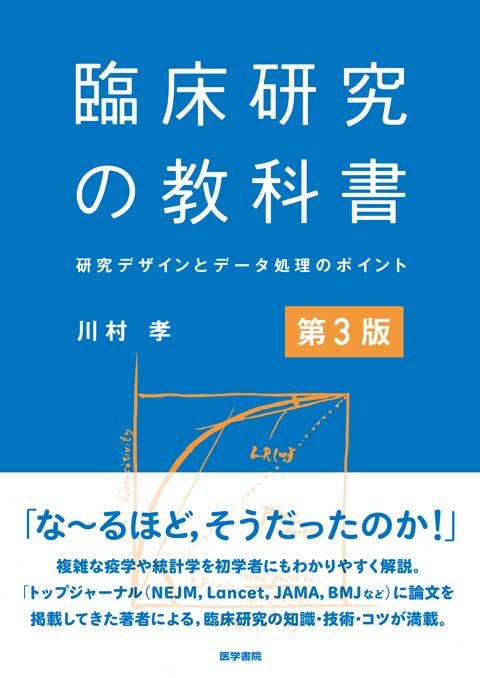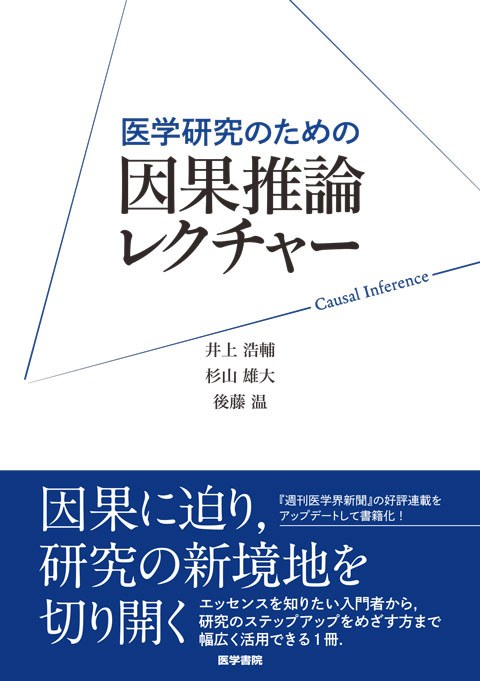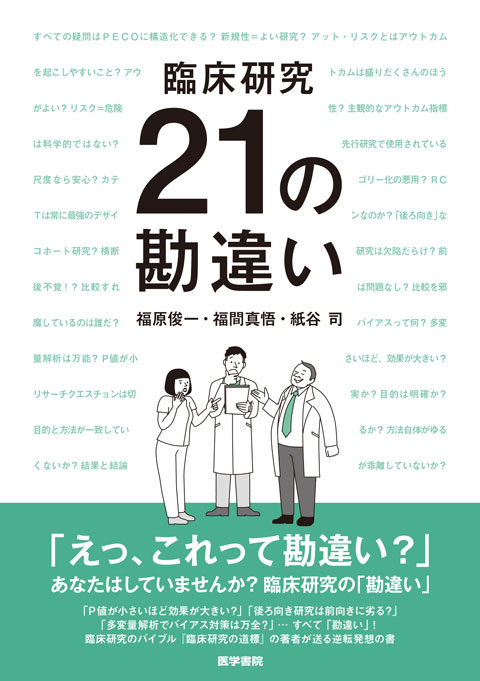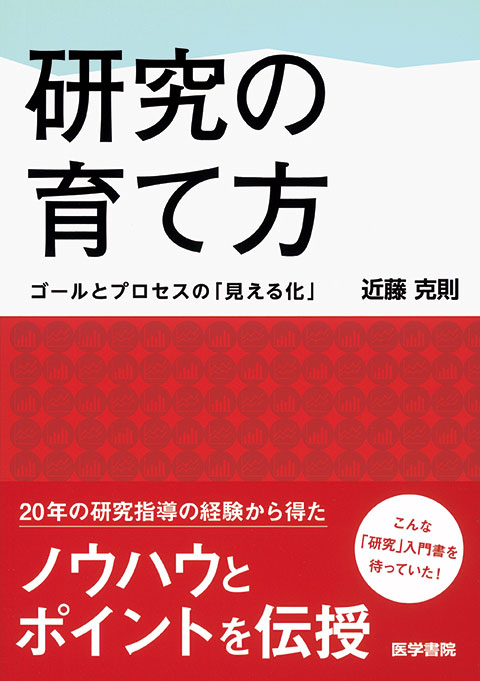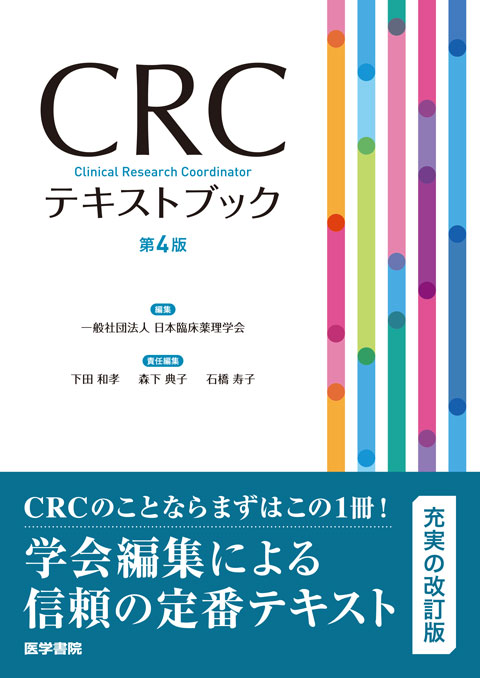臨床研究の教科書 第3版
研究デザインとデータ処理のポイント
な~るほど、そうだったのか! 臨床研究の知識・技術・コツをわかりやすく解説
もっと見る
トップジャーナル(NEJM、Lancet、JAMA、BMJなど)への論文掲載実績を誇る著者が、自身がこれまでに培ってきた臨床研究の知識・技術・コツを惜しみなく注ぎ込んだ定番書。これから臨床研究を始めたい読者に向けて、研究デザイン、データ解析方法、論文の書き方をわかりやすく解説。第3版では、①倫理指針の改正に対応、②調査票の作成を追加、③失敗談をコラム形式で追加し、よりビジュアルな図表を例示しました。
| 著 | 川村 孝 |
|---|---|
| 発行 | 2025年09月判型:B5頁:280 |
| ISBN | 978-4-260-06154-4 |
| 定価 | 4,950円 (本体4,500円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
第3版の序
『臨床研究の教科書』を上梓して9年あまりが経過した.この間に,健康・医療戦略法や臨床研究法があらたに制定され,ビッグデータが国策で整備されるなど,研究の法的環境に大きな変化が生じた.また,方法論の面でも,観察研究で治療の有効性を評価するための傾向スコアやinstrumental variableがごく普通に利用されるようになり,コホートを効率よく用いるケース・コホート研究や世界の知見をもっと大きく束ねるネットワーク・メタアナリシスが普及するなど,研究も進化している.利益相反の管理も含めた研究倫理についてもさらに整備された.
第3版では,上記の諸点について補強するとともに,第2版の記述全体を見直し,初学者が陥りやすいいくつかのピットフォールをQ&Aの形で追加した.それでも「臨床や公衆衛生の現場からエビデンスを発信してもらうために」という目的や,「ちょっと難しいことをわかりやすく」という記述方針に変わりはない.本書が文字通り「教科書」となって,諸兄の研究のお役に立てることを願っている.
私事で恐縮だが,2020年3月に勤務していた京都大学を退職し,長年にわたる組織マネジメントのくびきから逃れた.現在,国立病院機構京都医療センターの臨床研究センターで定期的に臨床研究の指導をしているが,そのほかにもフリーランスの立場で様々な臨床研究を支援している.また現役の一研究者として現在も論文も書いている.
再改訂にあたって,本書(初版・第2版)の読者や私の講義を受講された方々からいただいた意見も反映した.ここに謝意を表したい.
2025年8月吉日
京都大学名誉教授 川村 孝
目次
開く
序章
1. なぜ臨床研究が必要か
2. 足らないエビデンスは自分でつくる
3. プライマリ・ケアの現場でもエビデンスはつくれる
4. 臨床研究の分類
5. 疫学・統計学のセンスを持つ
第1部 研究の立案
1章 研究の構想
1. 臨床上の疑問の定式化
2. 先行研究の成果の確認
2章 研究のデザイン
1. 疫学とは何か
2. 実態を要約する記述疫学研究
3. 予後を調べるコホート研究
4. 原因を遡及する症例対照研究
5. 治療・予防の有効性を検証する介入研究
6. 診断性能を検証する診断研究
7. 研究の趨勢を知る系統的レビュー(メタアナリシスを含む)
8. 医療の効率を評価する費用効果分析
9. ビッグ・データの活用
10. 探査と精査のための質的研究
11. 質問票の作成
3章 倫理的配慮
1. 倫理規範
2. 『人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針』の主な規制点
4章 研究体制の整備
1. 研究の公正な運営に必要な組織
2. 科学研究費などの申請に必要な組織
5章 研究計画書の作成
1. 研究計画書の内容
2. 現場マニュアル
3. 対象者への説明文書および同意書
4. パイロット研究
第2部 研究の運営
6章 研究の運営
1. 事前の準備
2. 研究の開始と維持
3. データの収集
4. 対象者の登録・追跡の終了
7章 研究費の確保と経理
1. 研究費の種類
2. 研究費の経理
第3部 データの整理と解析
8章 データベースの構築
1. データベースの構築
2. バイアスと交絡
9章 統計解析
1. 統計解析の考え方
2. 基本的な統計技法
3. 特定目的・特定デザインの統計技法
4. 生存曲線
5. 交絡を調整する多変量解析
6. 個人の転帰を占う──臨床予測モデル
7. 基準値の作成
8. 観察研究で行う擬似的ランダム化試験
9. サンプル・サイズの算定
10. 不確実さへの対応
第4部 研究成果の公表と活用
10章 論文の執筆
1. 成果公表の義務
2. 論文の構成
3. 図表の描き方
4. 執筆の手順
5. 作文のポイント
6. 日常のトレーニング
7. 投稿と査読対応
8. 臨床現場への還元
第5部 研究の実例とトレーニング
11章 臨床研究の実例
1. 手作り感覚の多施設共同RCT──感冒に対するNSAIDの有効性
2. 少数でも検出力の高いクロスオーバー・デザインのRCT──肩こりに対する鍼治療の有効性
3. 目の前の患者の真実を予測する臨床予測モデル──肺炎における起炎菌の薬剤耐性の予測
4. 経年変化を見る症例対照研究──心電図ST-T異常完成までの血圧の推移
5. 着想次第で面白い結果が出る記述疫学研究──働き盛りの突然死の実態
6. 労力と経費を節約するケース・コホート研究──一般住民におけるアディポネクチンと死亡との関係
12章 京都大学における臨床研究者の養成
文献
索引
Pitfall
1 生存曲線の起点
2 追跡中の事象による分類
3 症例と対照のバックグラウンド
4 診断研究の対象者
5 平均値の怪
6 P 値の有意性を比較
7 多項目の検定
Advanced Knowledge
1 “ない”ことの証明は難しい
2 用量反応関係は過小評価される──誤分類と回帰希釈の問題
3 介入と転帰の繰り返し──急性期医療評価の難しさ
4 RCTのP 値は十分に小さくならない──サンプル・サイズ算定の影響
書評
開く
「自前でやる臨床研究」を現実的に始めるための羅針盤
書評者:三原 弘(札幌医大准教授・総合診療医学/医療人育成センター教育開発研究部門/統合IRセンター)
臨床研究を始めたい――しかし大学院に進む時間もなく,研究資金や人員も限られ,働き方改革の中で残業もままならない。そんな現場医師の切実な声に応えるのが,川村孝氏の『臨床研究の教科書 第3版』である。
著者はNEJM,Lancet,JAMAなどトップジャーナルへの掲載実績を誇り,研究デザインからデータ解析,論文執筆までを体系的に解説する。本書は初版以来,「自分たちで答えを生み出す」現場主導型研究のバイブルとして読み継がれてきた。
今回の第3版では2024年改訂の倫理指針に対応し,調査票作成の章を新設。さらに実際の“失敗談”をコラム形式で多数収録し,思わぬ落とし穴(生存曲線の起点設定や平均値の罠,P値比較の誤用など)を豊富な図表と共に解説する。プライマリ・ケアや日常診療でもエビデンスを創り出せる実例や,費用効果分析,臨床予測モデルまでを網羅した多彩な章立ては,忙しい臨床医にとって大きな支えとなる。
治験は製薬企業が主体であり,臨床医の業務負担は比較的軽い。一方,新薬や高価なデバイスが保険収載されると,海外研究デザインを模した観察研究が各施設で行われ,学会はその成績で盛り上がるが,ブームが去れば継続が難しい。多くの診療ガイドラインでは重要臨床疑問(CQ)を設定して文献検索しても,質の高い研究が見当たらず,前向き研究疑問(FRQ)として公開されることも少なくない。これは論文化を見込める研究課題である一方,先達が論文化できなかった難しさも示しており,自分たちだけで計画・実施するのは容易ではない。
実際,非薬物治療や高価なデバイスを使わない臨床研究は華々しさに欠け,盛り上がりにくい。しかし,コストがかかる割に効果が限定的な薬剤や高額デバイスに対し,コスパ・タイパに優れた介入の有効性を示すことこそ,これからの高価値医療推進に不可欠だ。地域の病院でこそ可能な疫学研究や非薬物治療の臨床研究を活性化し,若手や指導医が大学勤務時は基礎研究,地域勤務時は臨床研究やデータベース研究に取り組む循環を作ることは,地域医療の人材定着や優秀な人材の循環にもつながるだろう。
本書は,そうした「自前でやる臨床研究」を現実的に始めるための羅針盤である。研究の本質を押さえ,働きながらでも負担なく進められる「次世代の臨床研究」の設計図がここにある。仲間と相談しながら小さく始め,自らの現場からエビデンスを創出する。その一歩を踏み出す全ての医療者に,本書を強く薦めたい。
臨床研究の実践知が随所に盛り込まれた「実務で使える教科書」
書評者:椛島 健治(京大大学院教授・皮膚科学)
『臨床研究の教科書』第3版の刊行を心よりお祝い申し上げます。著者の川村孝先生とは,京大医学部の教授の一員として長年ご一緒させていただきました。その中で,常に幅広い知識と鋭い洞察を持って議論に臨まれる先生の姿勢に,私は深い敬意を抱いてまいりました。また,学位審査などを通じても,先生が研究方法論や臨床現場の課題に精通されていることを幾度となく実感してきました。そのような先生が丹念に執筆を続けられ,本書が第3版まで改訂を重ねて刊行されることは,まさに日本の臨床研究教育における大きな財産であり,私自身もこの書評を執筆する機会を頂けたことを大変光栄に存じます。
本書の大きな特徴は,単なる方法論の解説にとどまらず,著者ご自身が積み上げてこられた臨床研究の実践知が随所に盛り込まれている点です。序章では「なぜ臨床研究が必要か」「足らないエビデンスは自分でつくる」といった力強いメッセージが示され,読者が研究を行う動機づけを得られるよう工夫されています。加えて,第1部から第5部にかけて,研究計画の立案,運営,データ解析,成果の公表に至るまで,臨床研究の全過程を一貫して解説している構成は,まさに「実務で使える教科書」と呼ぶにふさわしい内容です。特に,統計解析やビッグデータの活用,倫理的配慮,研究計画書作成の具体的指針などが明確に整理されており,若手研究者にとって羅針盤となるだけでなく,経験豊富な研究者にとっても常に立ち返ることのできる信頼すべき基盤となっています。
今回の第3版では,近年の研究環境の変化に対応するため,傾向スコアやinstrumental variableといった解析手法の発展や,ネットワーク・メタアナリシスの整理,さらに費用対効果分析の章が拡充されています。研究デザインの基礎から実際の臨床研究の実例,さらにはトレーニング方法に至るまで,研究者が直面するあらゆる疑問に応える構成となっており,これから臨床研究を志す医師・大学院生にとって,まさに必携の一冊であると確信します。
とりわけ若手研究者にとって心強いのは,本書が「研究は身近な疑問から出発できる」という姿勢を貫いていることです。現場で遭遇する臨床上の課題をそのまま研究テーマとして発展させる手法が,平易かつ具体的に示されています。これは,研究に大規模な設備や特別な環境が必ずしも必要ではなく,日常診療の中からも国際的に通用する成果が生み出せることを教えてくれるものです。臨床と研究の両立に悩む若い医師たちにとって,本書は大きな励ましとなるはずです。
本書が,多くの研究者に臨床研究の魅力と意義を伝え,次世代の研究者が新しいエビデンスを切り拓く原動力となることを心から願っております。