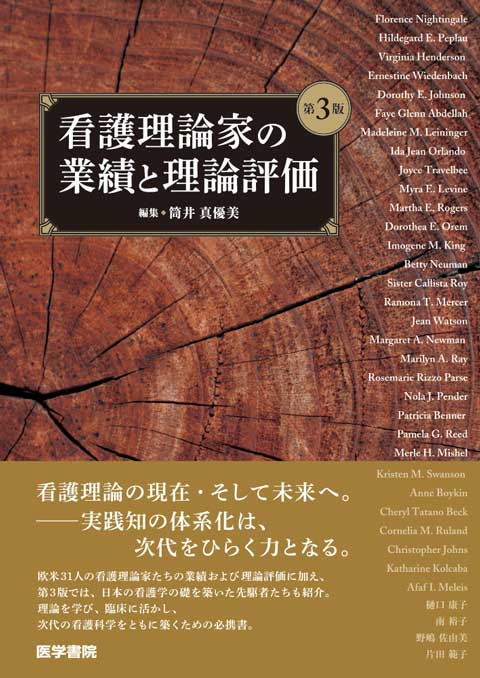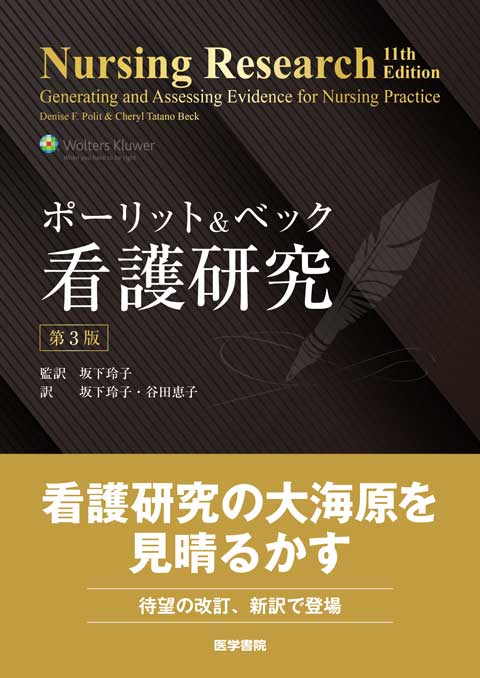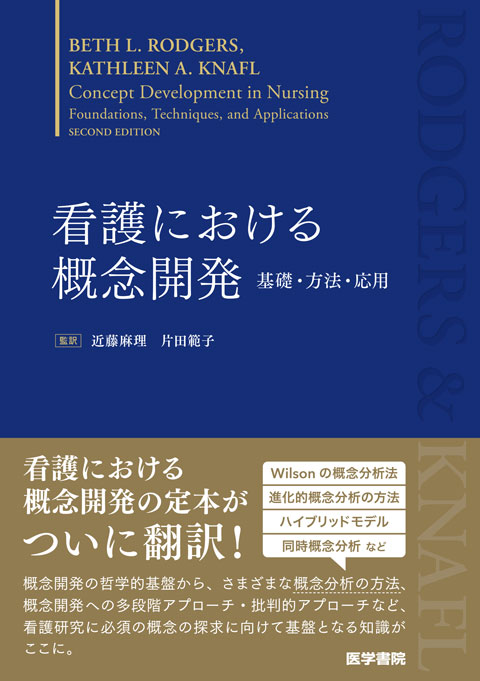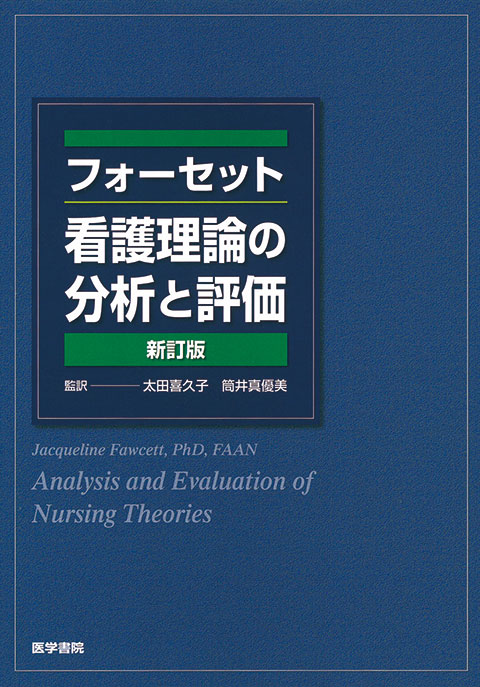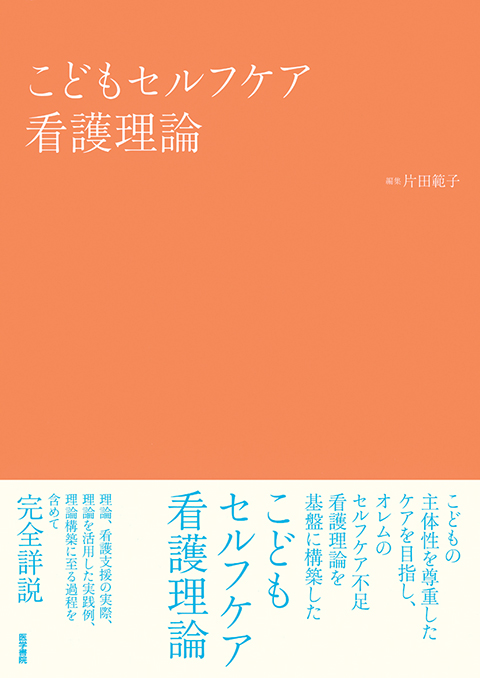看護理論家の業績と理論評価 第3版
看護理論の現在・そして未来へ。── 次代をひらくために実践知の体系化をめざす ──
もっと見る
欧米の31人の看護理論家の業績および理論の紹介、それぞれの理論の評価を解説する待望の第3版。今改訂では、新たに日本の看護学の礎を築いた先駆者たちも紹介。理論を学び、臨床に活かし、次代の看護科学をともに築くための必携書。
| 編集 | 筒井 真優美 |
|---|---|
| 発行 | 2025年11月判型:B5頁:656 |
| ISBN | 978-4-260-06151-3 |
| 定価 | 7,040円 (本体6,400円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第3版 序
本書は,翻訳書ではなく,日本人研究者の手による看護理論に関する著作として,2010年に初版が上梓されました.その背景には,「看護理論を,日本の看護者自身の視点からまとめた書籍を出版したい」との思いがありました.執筆者はいずれも,各理論家に深い理解と関心を持つ方々であり,改めて第3版の刊行に向けて筆をとる意義を強く感じております.
今回,私が担当した各章の改訂は,院生との討議を重ねるなかで鋭い指摘を受け,多くの見直しを行うこととなりました.アメリカではこのような討議や議論の中から,看護理論が練られ,今なお改訂され続けています.日本においても,1979年に看護学修士課程,1988年に博士課程が開設されて以来,看護学の知の発展は着実に進んでいます.
私が看護実践家を対象とした看護理論研修を始めてから,すでに30年近くが経過しました.実践家が病棟で直面する課題に対し,看護理論のエッセンスを活用して,人間の最善の利益を守るプロセスをともに考えてきました.実際に,看護理論を病棟において応用し,臨床に貢献している実践家もいます.看護理論は看護実践のためにあり,理論が知識として活かされてこそ,人々の健康と安寧に資するものとなることを,私自身深く実感しています.
恩師マーサE.ロジャーズは「未来は新しいビジョン,柔軟性,好奇心,創造性,勇気,冒険心,共感,そして優れたユーモアのセンスを,我々に要求する」と語りました.その言葉は,私が多くの大学院生や実践家と向き合う中で,改めて深い意味をもって響いています.
本書の付録にある地図をご覧いただくとわかるのですが,1492年の大陸発見以降,アメリカでは東海岸から西海岸へと開拓が進んだように,看護学も同様に,東海岸を中心に発展してきました.1980年以前に活躍した看護理論家(第II~IV部)の多くが東海岸の都市で生誕・活躍しているのは,都市部に大病院や大学・大学院が早くから設立されていたためです.また,1960年代にはPhD取得者の多くが看護学以外の分野で学位を得ていたことが問題視され,コースワークを有する看護学博士課程の設置が進められました.巻末に収載した年表と地図からは,こうした世界の動向の中,看護学がどのように発展してきたか,その歩みを読み取ることができます.
本書第I部では,看護理論の評価を行ううえで基盤となる知識をまとめています.「第1章 看護学・看護科学の発展」では,看護学の学問体系,看護理論の重要性,看護理論研究者の業績に加え,日本における看護理論の邦訳一覧を示し,先達の理論への熱意を紹介しています.
「第2章 看護理論」では,看護理論を哲学,概念モデルといった不明瞭な分類をせず,「看護理論」として包括的に解説しています.日本では,中範囲理論の教育・活用をうながす流れもありますが,中範囲理論は1980年代半ばから発展しているため,活用するには洗練が必要な理論が多いことがわかります.
「第3章 理論評価と理論開発」では,本書の主軸である理論評価の内容と,理論評価の理解を深めたうえでの理論開発について解説しています.現在,アメリカの多くの大学院では,理論評価・開発がコースワークに組み込まれており,看護理論の創出に貢献しています.今後日本でも,修士課程における理論評価,博士課程での理論開発のコースワークが充実していくことが期待されます.
「第4章 看護理論の歴史」では看護学が発展してきた歩みをたどり,「第5章看護理論と倫理」では,看護学が発展するために看護理論とは不可分である倫理に焦点をあてています.
「第6章 ケアリングの概観」では,看護学・看護科学の中心概念であるケアリングについて取り上げています.第13章レイニンガー,第23章ワトソン,第25章レイ,第28章ベナー,第31章スワンソン,第32章ボイキンといったケアリング理論家と併せてご覧いただければより理解が深まることでしょう.
第II部以降では,初版・第2版と同様に,看護理論家ごとに,理論の出発点となる書籍・論文を「最初の代表的著作」とし,その発表年代順に収載しています.時代区分として,第II部「『看護覚え書』発行~1959年」,第III部「1960~1969年」,第IV部「1970~1979年」,第V部「1980年以降」とし,今回,第3版では新たにコーネリア M.ルーランド(第34章)を取り上げました.
さらに今回新しく設けた第VI部では,日本に看護学博士課程が設置される以前に渡米し,博士号を取得された4人の看護師の方々を紹介しています.日本における看護理論家が少ない理由については,院生や実践家からも多くの問いが寄せられており,その声に応える形で新たに加えました.その狙いについては,第VI部の扉をご参照ください.
看護理論を真に理解するためには,それぞれの理論家の生きた時代や国・地域などをはじめとした文化的背景の理解が不可欠です.巻末には,日本および世界における看護の歩みを示す年表と,理論家の生誕地や主に活躍した都市を記した地図を掲載しています.看護理論を理解し,また今後の看護学の展開を展望する手がかりとしてご活用いただければ幸いです.
最後になりましたが,本書の意図をご理解いただき,多忙のなか真摯にご執筆いただいた先生方に,心より感謝申し上げます.なかには,体調不良をおして加筆・修正にご尽力くださった方もおられます.なお,第16章「マイラ E.レヴァイン」をご執筆いただいた宮脇美保子先生が逝去されましたことをここに記し,謹んでご冥福をお祈りいたします.
医学書院の堀口一明様,南部拓也様,小長谷玲様には,企画当初から発行に至るまで根気強く支えていただきました.また,退社なさった北原拓也様にもさまざまな形で支援していただきました.ありがとうございました.
2025年 トルコ桔梗の咲くころ
編者 筒井真優美
目次
開く
第I部 看護理論の発展と理論評価の基盤となるもの
第1章 看護学・看護科学の発展
第2章 看護理論
第3章 理論の評価と理論開発
第4章 看護理論の歴史
第5章 看護理論と倫理
第6章 ケアリングの概観
第II部 『看護覚え書』発行~1959年
第7章 フローレンス・ナイチンゲール:創はじまりの看護理論
第8章 ヒルデガード E. ペプロウ:看護における人間関係の概念枠組み
第9章 ヴァージニア・ヘンダーソン:人間のニードと看護独自の機能
第10章 アーネスティン・ウィーデンバック:臨床看護における援助技術
第11章 ドロシー E. ジョンソン:ジョンソン行動システムモデル
第III部 1960~1969年
第12章 フェイ・グレン・アブデラ:21の看護問題
第13章 マドレン M. レイニンガー:文化ケアの多様性と普遍性
第14章 アイダ・ジーン・オーランド:看護過程の教育訓練
第15章 ジョイス・トラベルビー:人間対人間の看護
第16章 マイラ E. レヴァイン:保存モデル
第IV部 1970~1979年
第17章 マーサ E. ロジャーズ:ユニタリ・ヒューマン・ビーイングズの科学(Science of Unitary Human Beings)
第18章 ドロセア E. オレム:セルフケア不足看護理論
第19章 アイモジン M. キング:目標達成理論
第20章 ベティ・ニューマン:ベティ・ニューマン・システムモデル
第21章 シスター・カリスタ・ロイ:人と環境の統合を創る能力(適応)
第22章 ラモナ T. マーサー:母親役割移行過程理論(Becoming a Mother)
第23章 ジーン・ワトソン:ユニタリ・ケアリング・サイエンス(Unitary Caring Science)
第24章 マーガレット A. ニューマン:拡張する意識としての健康の理論(Health as Expanding Consciousness:HEC)
第25章 マリリン A. レイ:ビューロクラティック・ケアリング理論
第V部 1980年以降
第26章 ローズマリー・リゾ・パースィ:人間生成(humanbecoming)理論
第27章 ノラ J. ペンダー:ヘルスプロモーション・モデル
第28章 パトリシア・ベナー:看護実践の明示化(articulation)から看護学教育法のたゆまぬ探求
第29章 パメラ G. リード:セルフ・トランセンデンス
第30章 マール H. ミシェル:不確かさ理論
第31章 クリステン M. スワンソン:ケアリング中範囲理論
第32章 アン・ボイキン:ケアリングとしての看護
第33章 シェリル・タタノ・ベック:産後うつ病理論
第34章 コーネリア M. ルーランド:ピースフル・エンド・オブ・ライフ理論
第35章 クリストファー・ジョーンズ:リフレクティブ,ナラティブ
第36章 キャサリン・コルカバ:コンフォート理論
第37章 アフアフI. メレイス:移行理論
第VI部 日本の看護学の先駆者たち
第38章 樋口 康子:看護学を日本の学問に
第39章 南 裕子:実践科学としての看護学の探究
第40章 野嶋 佐由美:家族看護学の発展に向けてのキャリアの歩み
第41章 片田 範子:「こどもセルフケア看護理論」の成り立ち
付録
年表:日本・世界の出来事と看護の理論化の流れ
地図:看護理論家の生誕地・活躍した都市
索引