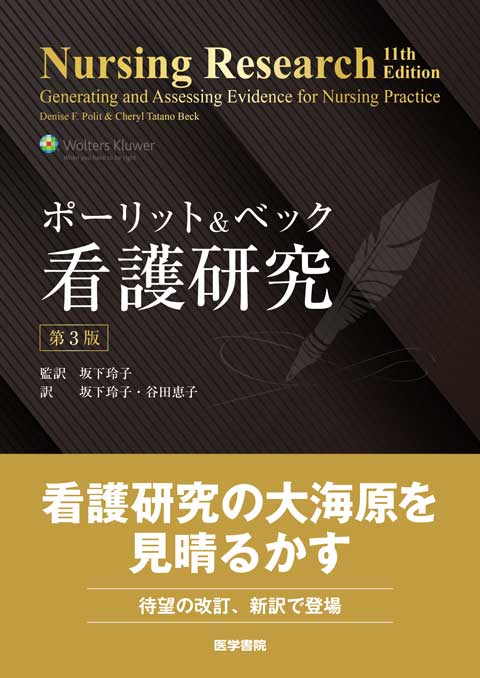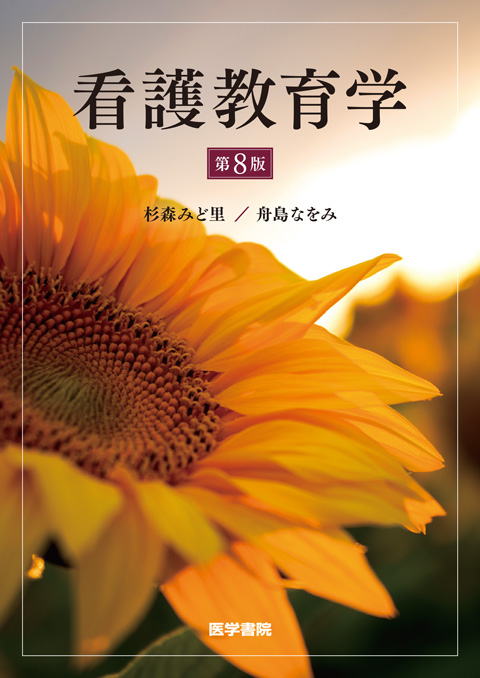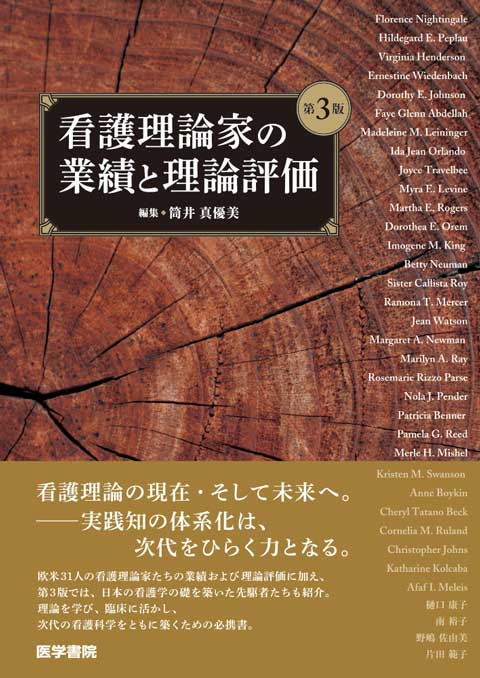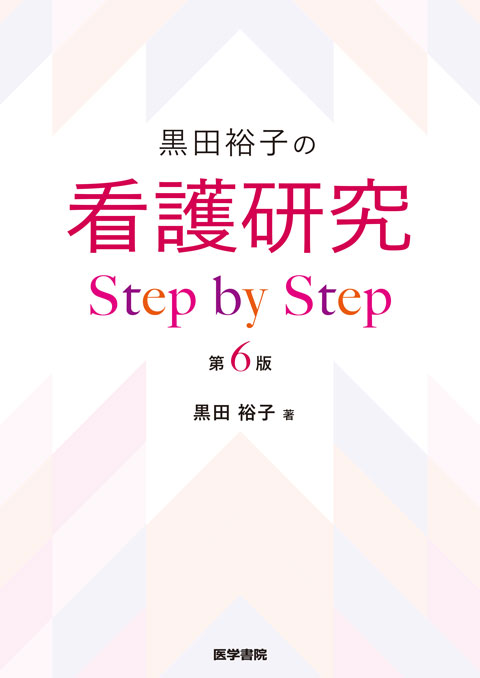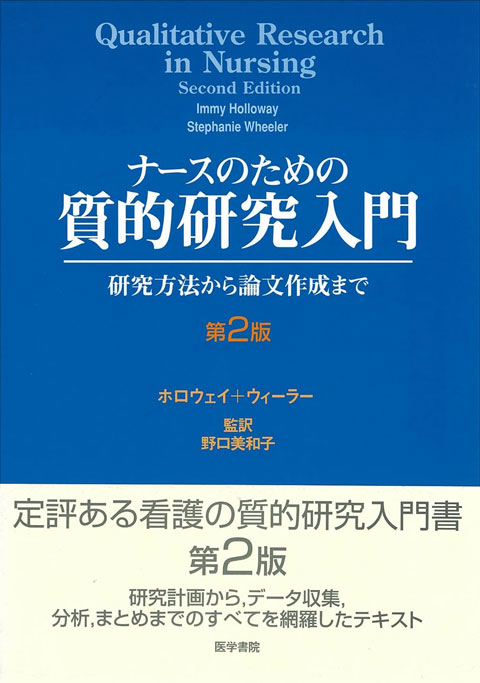ポーリット & ベック 看護研究 第3版
「新訳」で生まれ変わる看護研究の羅針盤
もっと見る
初学者にとって、看護研究の全容を掴まんとすることは、果てしない大海原に漕ぎ出すに等しい困難がある。航海を可能とする羅針盤のように、本書は看護研究に臨む皆さんの道標となるだろう。明瞭な「新訳」により、さらに可読性が増した本書は、これまで以上に多くの読者の支えとなることは間違いない。
| 著 | D. F. ポーリット / C. T. ベック |
|---|---|
| 監訳 | 坂下 玲子 |
| 訳 | 坂下 玲子 / 谷田 恵子 |
| 発行 | 2025年03月判型:B5頁:840 |
| ISBN | 978-4-260-05706-6 |
| 定価 | 10,780円 (本体9,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
第3版 監訳者序
Denise F. Polit とBernadette P. Hunglerによる『Nursing Research:Principles and Methods』は,1978年に出版され,著者がHunglerからCheryl T. Beckに代わって以来,「ポーリットとベックの看護研究」「黒本」という呼び名で,多くの看護研究者や大学院生,教員に愛され,読み継がれてきた。それは,彼らの本が,医療に関する研究法を広く網羅しているだけに留まらず,ひとえに,看護学と看護実践の向上を目指してきたからである。すなわち,「真に人間中心のケアを実現し,人々のWell-beingを推進するために看護研究は,どのような貢献を果たしうるか」という探究が,本書の根底に一貫して流れていると考える。科学的推論を保証するために,研究の厳密性は追求しなければならない。ゆえに最新の知見を導入し,内的妥当性を高め,厳密にデザインされた研究法を構築する必要がある。しかし一方で,厳密な研究デザインでも証明できることは限られており,それを重んじるあまり,複雑な看護現象を単純化し,外的妥当性や実現可能性を犠牲にしてはならない。
すべての看護研究は,看護実践の向上とその先にある人々のWell-beingに捧げられるべきである。
この原則を忘れては,研究活動そのものが意味のないものになってしまう。さまざまな要因が絡み合う看護現象をどのように捉え,看護介入をどのように導き,その効果をどう評価し改善していくか──そのような問いに,本書は答えてくれる。
世界中の読者から圧倒的な支持を得て看護研究を牽引してきた本書は,初版から書き続けてきたPolitが2021年に他界し,両氏により版を重ねることは叶わなくなった。最新の原書第12版の著者はJane M. FlanaganとBeckに代わったが,タイトルは『Polit & Beck's Nursing Research』となっており,Politの名が残されている。果てしない看護現象の大海を照らし,看護学の科学性を高め導いてくれた灯台を失ったようで寂しいが,Politが手掛けた最後の版(第11版)の翻訳という大役を仰せつかり,一語,一語,そのメッセージを読み解かせていただけたことを光栄に思う。
日本語版は本書が第3版となる。前回は原書第7版(2009)の翻訳であったので,時代の変化とともに,内容はかなり進化している。大きな特徴として,次の3点が挙げられる。
まず,エビデンスに基づく実践Evidence-Based Practice(EBP)が軸となり,本書全体が,「看護のためのエビデンスをどのように構築し活用するか」という視点で構成されている。特に,新しく追加された質改善(第12章),量的研究結果の臨床的解釈(第21章),実践への適用可能性(第31章)に関する内容は,現実世界を変えるための研究に向けたヒントを提供してくれる。
次に,ますます重要性の高まる質的研究の解説が前版からさらに充実していることに加え,ミックス・メソッド研究やシステマティックレビューなどの方法論も新たに章立てされており,幅広い研究法を俯瞰しつつ,包括的に学ぶことができる。時代の潮流に沿ってデジタルデータをはじめとする新しいデータの収集法や,ビッグデータを用いた研究手法が追加されているのも魅力的である。加えて前版と同様,多様な研究例がそのヒントとともに紹介されている点は,抽象的な研究法の理解を促すとともに,具体的な研究を計画する際に大いに参考になる。
最後に,看護研究を志す人には是非,「第6章 理論的枠組み」を読んでいただきたい。すべての研究が理論や概念モデルに基づいている必要はないとはいえ,何を対象に,何を明らかにしようとしているのかという研究の概念枠組みは明確にすべきであり,それが研究の質を大きく左右する。この章は,そのことの重要性を教えてくれる。
看護学は人と人との関わりの中で実践される学問である。その現場においては,常に新しい課題が生まれ続ける。日々看護学を探究し,そしてこれからの看護学を担う多くの方々が,本書を通じて実りある研究活動を実現し,人々により良いケアが届けられることを願う。最後に,看護研究の礎ともいえる稀有な書をつくりあげたPolitとBeckの両博士に,深い敬意を捧げる。
2025年3月
坂下玲子
目次
開く
第I部 看護研究とエビデンスに基づく実践の基礎
第1章 エビデンスに基づく実践のための看護研究への誘い
第2章 エビデンスに基づく看護:研究エビデンスから実践を導く
第3章 質的研究と量的研究の重要な概念とステップ
第II部 看護におけるエビデンス生成のための概念化と研究計画
第4章 研究問題,リサーチクエスチョン,仮説
第5章 文献レビュー:エビデンスの探索と批判的評価
第6章 理論的枠組み
第7章 看護研究における倫理
第8章 看護研究の計画
第III部 看護のエビデンスを創出する量的研究のデザインと実施
第9章 量的研究デザイン
第10章 量的研究における厳密性と妥当性
第11章 量的研究のさまざまなタイプ
第12章 質改善と改善科学
第13章 量的研究における標本抽出
第14章 量的研究におけるデータ収集
第15章 測定とデータの質
第16章 自己報告尺度の開発と検証
第17章 記述統計
第18章 推測統計
第19章 多変量統計
第20章 量的データ分析のプロセス
第21章 臨床的意義と量的結果の解釈
第IV部 看護におけるエビデンス生成のための質的研究の設計と実施
第22章 質的研究のデザインとアプローチ
第23章 質的研究における標本抽出
第24章 質的研究におけるデータ収集
第25章 質的データ分析
第26章 質的研究における信憑性と厳密性
第V部 看護におけるエビデンス生成のためのミックス・メソッド研究の設計と実施
第27章 ミックス・メソッド研究の基本
第28章 ミックス・メソッド研究を用いた複雑な看護介入方法の開発
第29章 ミックス・メソッドを用いた介入の実行可能性研究とパイロット・スタディ
第VI部 看護の実践のためのエビデンスの確立
第30章 研究エビデンスのシステマティックレビュー
第31章 適用可能性,一般化可能性,関連性:実践に基づくエビデンスに向けて
第32章 エビデンスの普及:研究の知見の報告
第33章 エビデンスを生み出す研究計画書の執筆
付録A:確率分布の統計表
付録B:統計記号一覧
用語集
索引
書評
開く
看護学の進化と社会背景を反映した唯一無二の看護研究入門書
書評者:大久保 暢子(聖路加国際大大学院教授・ニューロサイエンス看護学)
評者が大学院修士課程に在籍していた頃,「看護研究とは何ぞや」を学んだのがDenise F. PolitとBernadette P. Hunglerによる『Nursing Research:Principles and Methods』(3rd ed)の訳本初版(1994)であった。当時,大学院生の間では「黒本」と呼称し,いつもカバンに入れ持ち歩いていたものである。看護研究の入門書といえども,非常に厳格な文章表現と研究用語の適確な使用,具体的な説明文が掲載されており,浅く広くの入門書とは一線を画し,本書一冊で看護研究の一通りを深く広く学べる唯一無二の書籍であった。この書籍が今回,訳本第3版として出版された。
第3版は,原書第11版を訳しているが,これまでの訳本初版・第2版と異なる点は,2つの章の追加と各章の大幅改訂である。看護の進化と社会背景を敏感に反映し,時代に即した内容とすべく追章と改訂に至ったと推測する。質改善(Quality Improvement:QI)と改善科学(Improvement Science),研究エビデンスの適用可能性に関する研究手法が新章として追加された。QIは,これまで研究とみなされない状況が続き,各医療施設における限局した質改善の結果としてのみ評価されてきた。しかし改善プロジェクトを開発し評価する方法と枠組みが提示されるようになり,エビデンスに基づく質改善として改善科学の学問と評されるようになった。国内外で看護の博士課程としてDNP(Doctor of Nursing Practice)コースが誕生したのもこれに大きく関係しているといえるだろう。また,Evidenced Based Practice(EBP)は,厳格にコントロールされた研究から得た平均的な結果によるエビデンスであることから,実世界での個別性のある患者が除外され,現場での適用可能性に疑問や懸念が出始めているのも事実である。この疑問を解決するための研究手法を本書がわかりやすく掲載している。QIや改善科学,適用可能性を新章として取り上げている本書は,非常に読みごたえがあり,時代を反映した研究手法として学ぶ価値が大きい。大幅に改訂した各章においても,最新のシステマティックレビューの方法,質的データの分析方法に多くの頁を割いており,刻々と変化する看護の研究手法について,コンピューターによるデータ分析にも触れながらわかりやすく説明がなされている。
本書を拝読し,上記のように説明してみると,やはり痛感するのは,「看護学の進化と社会背景を反映した唯一無二の看護研究入門書」ということである。看護研究を専門的に学ぼうとしている看護系の大学院生に必見であると同時に,久しく看護研究の基本を学ぶ機会を得ていない看護教員や看護学研究者にも新知見を得ながら看護研究を復習できる書籍といってよいだろう。評者自身も非常に学ぶことが多く,書評の機会に感謝したい。