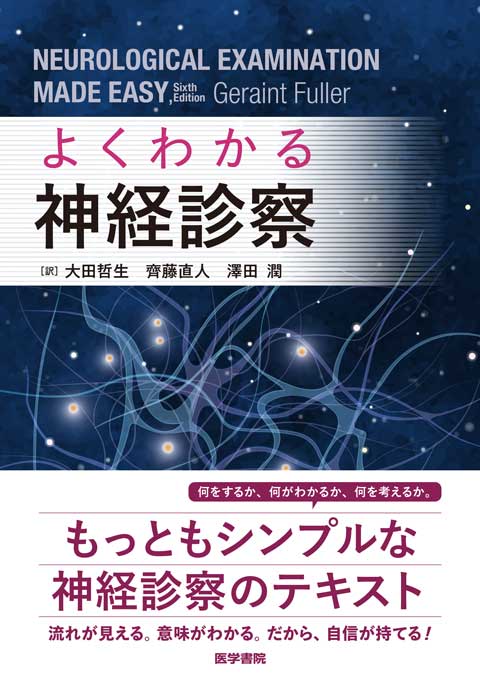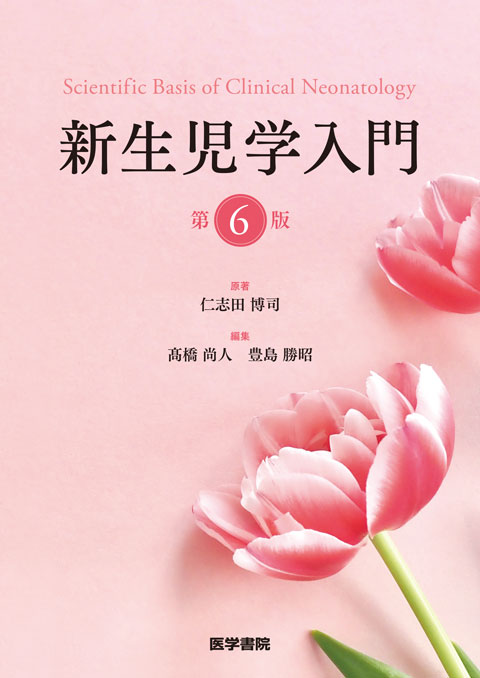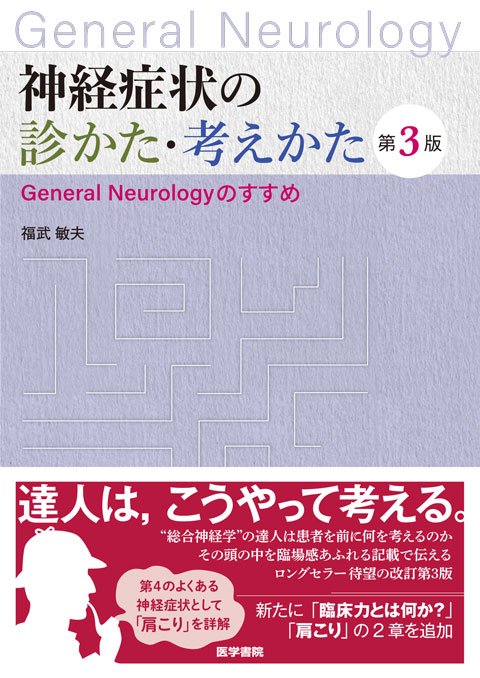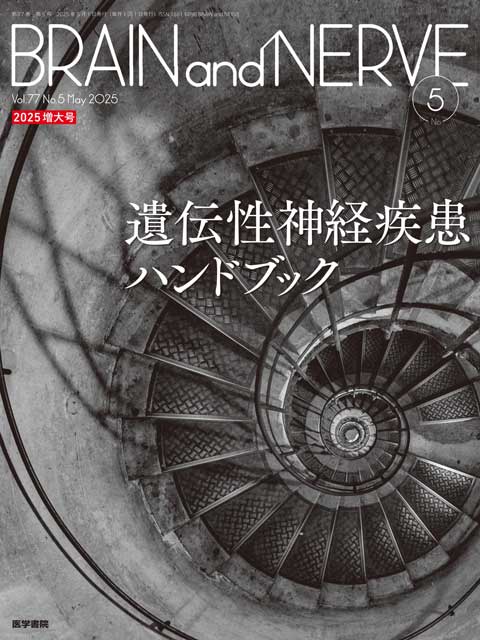ケースカンファレンスから学ぶ 新生児神経の診かた[Web動画付]
実際の症例カンファレンスとWeb動画を通して、新生児の神経について深く学べる1冊
もっと見る
国立成育医療研究センターで実際に開催されている神経内科と新生児科の症例カンファレンスを通して、新生児の神経について深く学べる。大きくは総論と各論の2パートから成り、各論では13個のCASEによって神経内科医と新生児科医の考え方を追体験できる。また知識を補完するコラムも満載。付録Web動画では、実際の神経所見や診察手技の様子を視聴しながら「新生児の神経を診る」ことへの理解がより進む1冊。
| 監修 | 阿部 裕一 / 伊藤 裕司 |
|---|---|
| 編集 | 国立成育医療研究センター 神経内科・新生児科 |
| 発行 | 2025年10月判型:B5頁:216 |
| ISBN | 978-4-260-06016-5 |
| 定価 | 8,800円 (本体8,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
序文
開く
推薦の序/序
推薦の序
1950年のわが国の新生児死亡率と乳児死亡率は27.4と60.1(1,000出生対)であった.当時は低出生体重児や新生児仮死への医療的介入が限定的であった.その後,新生児集中治療室の整備が始まり,保育器,人工呼吸器,サーファクタント製剤,高頻度振動換気法,一酸化窒素吸入療法が導入され,呼吸・肺高血圧管理を中心とする新生児蘇生法が体系化され,地域周産期母子医療センターが1996年から全国に整備されて母体や新生児の搬送ネットワークが機能するようになった.その結果,わが国の2024年の新生児死亡率と乳児死亡率はそれぞれ0.8と1.8と世界最低となり,死亡原因のほとんどが児の先天的問題に起因する.さらに,出生時体重が1,000g未満の児の生存率も9割以上となった.わが国では在胎22~23週の児も救命対象とし,出生時体重が500g台の児も生存しうる.なお,わが国の2,500g未満で出生する児は2023年には全出生の9.65%を占め,OECD(経済協力開発機構)34か国中もっとも高い.
低出生体重児や疾患を有する新生児・乳児の生存率が改善した現在,救命された新生児や乳児の神経学的評価の重要性が近年,特に高まっている.その主な理由は以下のとおりである.在胎週が短く出生時体重の低い児は長期的な中枢神経障害(脳性麻痺,精神遅滞,視力障害,聴力障害など)のリスクが高い.そのような児においても神経発達の可塑性があるため,中枢神経異常の早期発見と理学療法や感覚刺激プログラムなどの早期リハビリテーションにて予後の改善が期待される.さらに,中枢神経障害の重症化予防や軽減が児と御家族のwell-beingに寄与する.
本書は,新生児・乳児の神経の診かたをできるだけ平易かつ具体的に解説することを目指して出版された.新生児・乳児の神経所見の取り方や得られた所見や検査結果から推定される病巣の組み立て方が,総論と症例にて具体的に丁寧に示されており,読者が容易に理解できるように工夫されている.本書は,国立成育医療研究センター神経内科と新生児科の専門医と若手医師が参加して毎月実施している合同カンファレンスの実例をもとに作成されている.特に実際の神経診察をQRコードにて動画として視聴できることも本書の大きな特徴の1つである.
新生児・乳児医療においても救命のみが目的の時代は過ぎ去った.本書には児が有する様々な困難を克服し,医療を通じて児と家族の biopsychosocial well-beingを目指す小児神経科医と新生児科医の心意気が感じられる.小児神経科医と新生児科医はもちろん,関係する多くの方に御一読いただけることを願う.
2025年9月
国立成育医療研究センター 理事長
五十嵐 隆
序
「神経を診る」.この言葉に身構えてしまう新生児科医は少なくはないでしょう.私自身も,脳波や神経診察は苦手,呼吸や循環がわかれば何とかなると言い訳をして「神経」から逃げていましたが,実際にはNICUでも外来でも,新生児科医でいる限りは「神経」と日々向き合わなければなりません.
本書は,国立成育医療研究センターにおける新生児科と神経内科との協働の記録です.神経内科医によるNICU回診は2014年に始まり,月に1回,ベッドサイドでの診察とディスカッションが行われてきました.しかし,コロナ禍のために2020年からは,神経内科医の診察を事前録画し,それをオンラインで供覧する新形式へと移行することになりました.この新形式には思いのほか利点が多く,新生児科医にとっては,神経内科医が編集して言語化した神経所見や診察手技を繰り返し視聴できるため,職人技のような神経内科医の診察技術や思考過程への理解を深めるのに役立ちました.神経内科医にとっても,診察動画を見返してポイントを絞って編集することは,自身の臨床力を洗練するための絶好の教材であり,新生児科医・神経内科医の双方にとって実りある学習機会となっていました.ケアや面会の時間を気にせずじっくり議論でき,小さな疑問を気軽に話題にできたことも有益でした.このようななかで,このカンファレンスを書籍化すれば,多くの新生児医療従事者にも役立つのではないかという声が自然と上がりました.
本書は「新生児神経学についての完成された知識を伝える成書」ではありません.実在症例を前に新生児科医と神経内科医が建設的に意見を交わしたプロセスを読者に追体験してもらうことで,「新生児の神経を診る」ことへの向き合い方,考え方,悩み方を共有したいという思いで編まれた一冊です.執筆者のなかには現在は他施設で活躍している者もいますが,それぞれが“成育”の新生児科や神経内科の一員であった時期に実際に関わった症例を担当して執筆しました.まさに両科の総力を結集させた一冊と言えるでしょう.本書が,新生児医療に携わるすべての方にとって,「神経」への苦手意識を振り払うきっかけとなり,臨床に新たな視点と手応えをもたらすことを願っています.
末筆ながら,診療情報や診察動画の利用を快諾してくださった患者さんおよびご家族の方々に,心から感謝を申し上げます.皆さまのご理解とご協力がなければ,本書の刊行は実現し得ませんでした.また,構想の初期段階から本企画を丁寧に育ててくださった医学書院の塩田高明さんにも,この場をお借りして深謝いたします.
私自身が専攻医だった10年前にこの本があったなら──そんな思いを込めて,本書を世に送り出したいと思います.
2025年9月
甘利昭一郎
目次
開く
総論
1 新生児の神経学
2 0歳児の発達
3 新生児神経診察でわかること・わからないこと
4 基本的な症候の診察法
症例検討
1 出血後水頭症,脳室拡大傾向のある生後3か月(修正39週)の児
2 出血後水頭症,頭蓋内圧亢進所見のある生後3か月(修正41週)の児
3 双胎間輸血症候群の受血児で,FLP後に大脳の破壊性病変を合併した児
4 典型的な経過をたどった重症新生児仮死の正期産児
5 重症新生児仮死で出生し,筋緊張低下を認める生後1か月(修正39週)の児
6 両上肢のミオクローヌス,肝障害,血小板減少を認める生後3週の児
7 息こらえ発作を繰り返す,13トリソミーの生後1か月の児
8 順調な経過の18トリソミーの生後2か月の児
9 未診断の先天異常症候群の生後3か月の児
10 多関節拘縮のある生後2か月の児
11 繰り返す無呼吸発作と,筋緊張低下を認める正期産児
12 脊髄髄膜瘤の児
13 早期新生児期発症の難治性てんかんの児
索引
COLUMN
新生児の神経学の歴史
超早産児と頭蓋内病変
出血後水頭症の治療と侵襲のジレンマ
HIE,PWML,PVLの画像所見(超音波,MRIなど)
双胎間輸血症候群
重症新生児仮死,低酸素性虚血性脳症と低体温療法
神経学的予後推定の原則
ビリルビン脳症
脳性麻痺のお子さんのフォローアップ
18トリソミー──手術や治療に関するジレンマ
息こらえ
新生児脳梗塞
新生児の神経学的評価スケール
書評
開く
新生児医療に携わる全ての医療者にとって,大きな助けとなる一冊
書評者:早川 昌弘(医療法人社団葵鐘会小児科・顧問)
新生児医療の目標は救命にとどまらず,児の長期予後を改善することであり,その意味で新生児神経は極めて重要な分野である。しかし,多くの新生児科医にとって新生児神経は難解で,苦手意識を抱くことも少なくない。その理由として,病態や責任病巣がわかりにくく,診察から得られる神経学的所見が限られることが挙げられる。
このたび刊行された,国立成育医療研究センター神経内科・新生児科の先生方による『ケースカンファレンスから学ぶ 新生児神経の診かた』は,新生児神経の基礎から診察のTipsまでを丁寧にまとめた一冊であり,理解を深める上で大変有用である。
本書は「総論」と「症例検討」の二部構成である。総論では,新生児の神経学,0歳児の発達,新生児神経診察でわかること・わからないこと,基本的症候の診察法,と根幹となる内容が体系的に整理されている。特に,新生児の神経学(成人・小児・新生児の神経学の同じところ,違うところ,新生児の神経学で出てくる独特な概念),新生児神経診察でわかること・わからないことの解説は,新生児神経を理解する上で極めて重要である。
症例検討では,成育医療研究センターで定期的に行われているケースカンファレンスが紙上で再現され,13例が提示されている。新生児科から神経内科への対診依頼に始まり,神経内科医による診察,詳細な神経学的所見,病巣推定,鑑別診断へと進む構成で,思考過程が明確に示されている。
また鑑別の考え方として,大脳から脊髄,筋に至る構造図を用いて,推定される主病巣,症状や所見との対応,関連が考えられる他部位が整理されており,病態理解が非常に容易になる。さらに合同カンファレンスでは,新生児科医からの質問に神経内科医が詳細に回答し,合同カンファレンスの後日談として,その後の追加検査や確定診断,経過が簡潔にまとめられている。家族向けの病状説明資料も掲載され,実際の説明を具体的にイメージできる。まさに合同カンファレンスをそのまま紙上に再現したような構成であり,読者はその場に参加しているかのような臨場感を得られる。
特筆すべきは,QRコードから児の神経学的症状や診察の実際の動画を視聴できる点である。文章や画像ではとらえにくい動きの特徴が直感的に理解でき,新生児神経の学習に大いに役立つ。また,各コラムでは病態生理だけでなく,治療の実際や臨床上のジレンマなど,教科書にはあまりみられない,臨床ならではの貴重な知見も紹介されている。
本書は,新生児医療に携わる全ての医療者にとって,新生児神経への抵抗感を軽減し,理解を深める上で大きな助けとなる一冊である。初心者だけでなく,新生児専門医にとっても多くの示唆が得られ,本書を読み進めることで新生児神経への理解が一層深まり,ひいては新生児の長期予後の改善にも貢献することであろう。
付録・特典
開く
![ケースカンファレンスから学ぶ 新生児神経の診かた[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1517/6101/9347/115205.jpg)