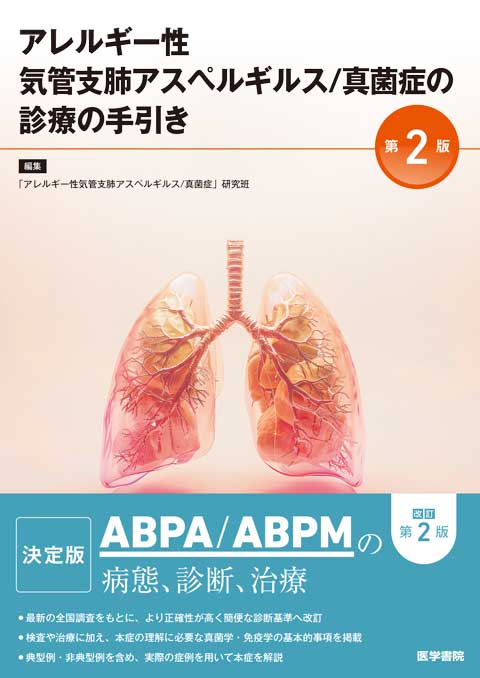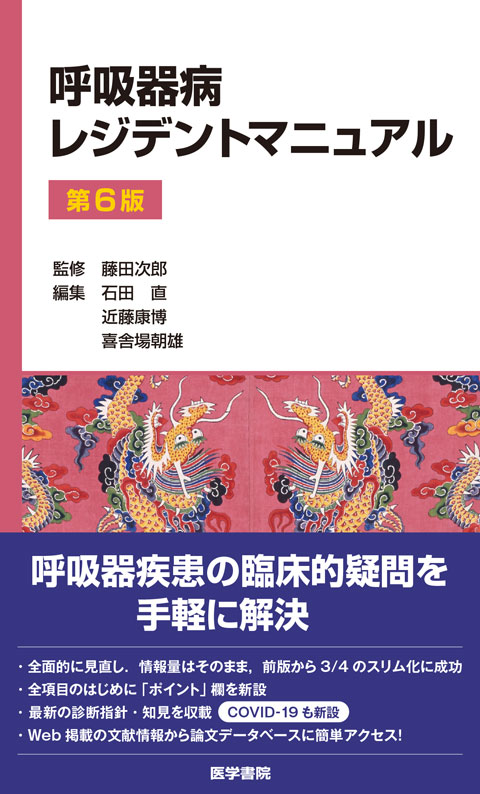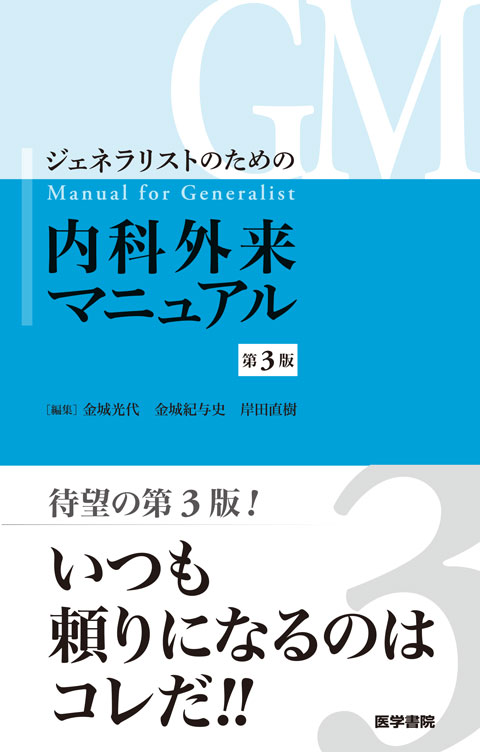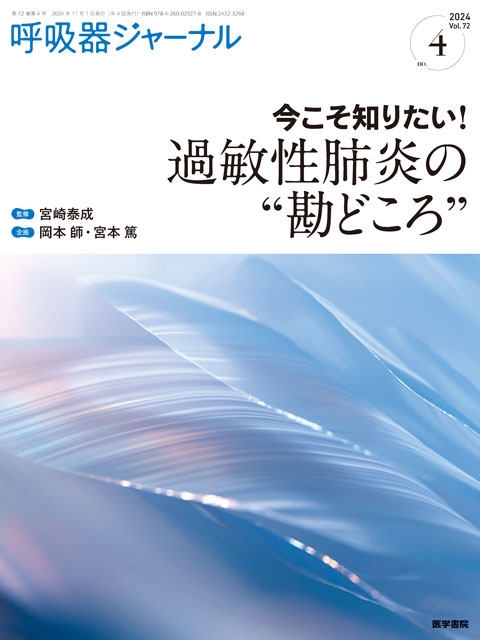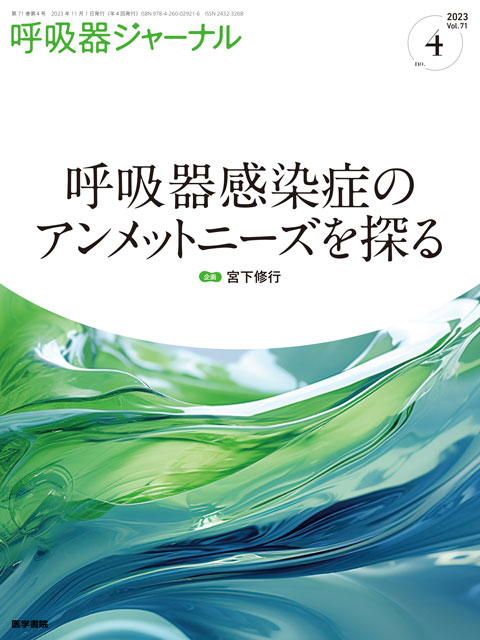アレルギー性気管支肺アスペルギルス/真菌症の診療の手引き 第2版
アレルギー性気管支肺アスペルギルス/真菌症の診断基準・知見をまとめた診療の手引き
もっと見る
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が実施した全国調査をもとに、アレルギー性気管支肺アスペルギルス/真菌症の新しい診断基準と最新の知見をまとめた診療の手引きの第2版。約100施設、500名の症例に基づく明確・詳細な診断基準を掲載。再燃しやすいことが特徴の本症への対策として「空気環境整備」の解説を拡充。新たな章として「症例」を掲載。ABPMの理解を深め、対応力を高めることができる一冊。
| 編集 | 「アレルギー性気管支肺アスペルギルス/ 真菌症」研究班 |
|---|---|
| 発行 | 2025年03月判型:B5頁:280 |
| ISBN | 978-4-260-05714-1 |
| 定価 | 5,940円 (本体5,400円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第2版の序
アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(allergic bronchopulmonary aspergillosis:ABPA),アレルギー性気管支肺真菌症(allergic bronchopulmonary mycosis:ABPM)は,主に成人喘息患者あるいは囊胞性線維症患者の下気道に腐生した真菌(糸状菌)が,I型アレルギー反応とIII型アレルギー反応,好酸球活性化に伴う粘液栓形成を誘発して発症する慢性炎症性気道疾患である.真菌感染症と異なり,菌体は気管支内腔の粘液栓内に限局しており,気道組織への浸潤は認められない.
Aspergillus fumigatus (アスペルギルス・フミガーツス)および他のアスペルギルス属真菌(A. flavus,A. niger,A. oryzae など)で発症することが大半を占め,これらアスペルギルス属真菌によって発症した場合は血清学的にも類似した応答を示すことからABPA と総称することが,2024年の国際医真菌学会(International Society for Human and Animal Mycology:ISHAM)のABPAワーキンググループにおいて確認された.一方,Penicillium (ペニシリウム)属,Schizophyllum commune (スエヒロタケ)などアスペルギルス属以外の糸状菌で発症した場合にABPMと診断する.
臨床的には喘息患者が中高年以降で咳嗽,喀痰,血痰などを呈し発症することが多く,気管支の鋳型状をした粘液栓の喀出は特徴的であるが,無症候で血液検査や胸部画像検査での異常を契機に診断されることもある.末梢血好酸球数の増加や高IgE血症がみられ,真菌特異的IgE/IgG抗体・沈降抗体,真菌に対する即時型/遅延型皮膚反応が陽性となる.画像所見では,移動性の浸潤影,中枢性気管支拡張,中枢気道における気管支内粘液栓,特に傍脊椎筋組織よりも高いCT値を呈する高吸収粘液栓が特徴的である.経口副腎皮質ステロイド薬(以下,ステロイド薬),抗真菌薬による4か月程度の治療が標準であるが,約半数の症例で治療中あるいは治療後に再発する.顕在例以外にも重症喘息などと誤診されている潜在例が多く,放置すれば肺の線維化から呼吸不全に至る.
2013年度に厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業(免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業)の一環として「アレルギー性気管支肺真菌症の診断・治療指針確立のための調査研究」班が設置された当時は,この疾患に関する知見の多くは,環境や背景疾患が大きく異なる南アジア(インドなど)や欧米でのものであり,わが国での体系的検討は行われていなかった.また,当時汎用されていた診断基準の診断感度が低く,診断・治療の遅れにつながっていた.以上の理由から,2019年にわが国の実態に即した診療指針として,研究班の構成員を中心にABPA/ABPMの新しい診断基準や最新の知見をまとめた「アレルギー性気管支肺真菌症の診療の手引き」初版が発刊された.同書で初めて紹介された日本発の診断基準は,その後の検討で感度・特異度の高さが検証されてABPA/ABPM診断精度の向上につながり,国内外で多くの臨床医・研究者によって使用されている.また,海外で複数のランダム化比較試験が実施され,経口ステロイド薬,抗真菌薬による標準治療の効果と限界についても明確となった.しかし,標準治療の成功率の低さ,再発率の高さなど,まだまだ課題は多い.
厚生労働省研究班は2015年度から日本医療研究開発機構(AMED)の免疫アレルギー疾患等実用化研究事業に移行し,2016~2018年度の「アレルギー性気管支肺真菌症の新・診断基準の検証と新規治療開発」研究班,2019~2021年度の「真菌関連アレルギー性気道疾患の発症・増悪予防を目指した体内・体外環境の評価と制御」研究班,そして2022年度からの「真菌関連アレルギー性気道疾患における真菌生態・宿主応答機序の解明と発症・増悪・重症化予防法の開発」研究班(以下,ABPM研究班)として継続中である.
「アレルギー性気管支肺真菌症の診療の手引き」初版を刊行してからの5年間で,ABPA/ABPMについてはわが国で2020年に実施された第2回全国調査などから多くの新しい知見が明らかとなり,さらにISHAMのABPAワーキンググループからも新しいガイドラインが発表され,それまで曖昧であった治療反応性や増悪,寛解なども明確に定義された.改訂第2版においては,これらの最新の知見とともに,ABPA/ABPMを理解するために必要な真菌学,免疫学の基本的事項や,典型的・非典型的な実際の症例までを含めたより包括的な内容となっている.本書によってわが国におけるABPA/ABPM診療がさらによいものとなることを祈念する.
2025年2月
浅野浩一郎
目次
開く
第2版の序
初版の序
略語一覧
第1章 環境・病原真菌と宿主免疫応答
1 真菌の生物学
A 真菌の分類
B 真菌の構造
C 真菌のライフサイクル
D 真菌の病原因子
2 体内および環境内真菌
A 体内および環境内真菌叢
B 体内真菌
C 環境真菌
1) 屋内真菌
a) 屋内浮遊真菌濃度構成の機構
b) 居住環境中の真菌のサンプリング
c) 屋内真菌の実態
2) エアコン内真菌の実態
3) 屋外真菌
3 真菌に対する宿主免疫応答
A 感染防御免疫応答
B 2型免疫応答
C 好酸球
4 真菌に対するIgE感作と関連病態
A 日本人一般集団における真菌IgE
B 患者集団における真菌IgE
C 真菌IgE陽性率の地域差
D 真菌IgEと種々のアレルギー病態
E 真菌IgEと喘息重症化
第2章 ABPA/ABPMの病態
1 基礎疾患
2 真菌の定着
3 真菌アレルギー
4 気管支内の好酸球性粘液栓形成
第3章 ABPA/ABPMの原因真菌
1 原因真菌の特性
2 原因真菌種に関するこれまでの報告
A わが国におけるABPA/ABPMの原因真菌
B ABPA/ABPMの原因真菌判定における問題点
3 代表的な原因菌種
A Aspergillus fumigatus (アスペルギルス・フミガーツス)
B その他のアスペルギルス属
C Schizophyllum commune (スエヒロタケ)
第4章 ABPA/ABPMの疫学
1 アスペルギルス・フミガーツス感作率
2 ABPA有病率
第5章 ABPA/ABPMの診断
1 ABPAの臨床像
A 基礎疾患
B 性別・発症年齢
C 臨床症状
D ABPAフェノタイプ,臨床コンポーネント
2 ABPMの臨床像
A 原因真菌
B ABPMの臨床像と診断
C スエヒロタケABPM
3 血液生化学検査
A 末梢血好酸球数
B 血清総IgE値
C その他
4 血清診断法
A 特異的IgE抗体検査
B 沈降抗体/特異的IgG抗体検査
5 画像所見
A ABPA/ABPMにみられる画像所見
B 鑑別診断
6 呼吸機能検査
A スパイロメトリー
B 呼気NO(FeNO)
7 真菌培養・同定法
A ABPA/ABPMにおける喀痰培養の意義
B ABPA/ABPM疑診例における培養法
C 菌種同定の方法
D VOCによるスエヒロタケのスクリーニング法
E 菌を保存しておきたい場合
8 気管支鏡検査
A ABPA/ABPMの診断基準と気管支鏡
B 気管支鏡検査の意義
C 気管支鏡検査所見
9 病理
A ABPA/ABPMにおける粘液栓の意義
B ABPA/ABPMにおける好酸球性粘液栓の病理像
C ABPA/ABPMにおける好酸球性粘液栓の細胞診所見
D 鑑別
10 従来のABPA/ABPM診断基準
A 従来の診断基準
B 従来のABPA/ABPM診断基準の問題点
11 新しいABPA/ABPM診断基準
A ISHAM2013診断基準改訂版
B ISHAM2024診断基準
C わが国のABPA/ABPM臨床診断基準
D わが国のABPA/ABPM臨床診断基準各項目の解説
E わが国のABPA/ABPM臨床診断基準の検証
第6章 ABPA/ABPMの類縁疾患・合併症
1 真菌感作喘息
A 喘息における真菌感作の疫学
B 真菌感作と喘息の難治化
C 真菌感作重症喘息
D 真菌感作喘息の治療
2 慢性肺アスペルギルス症
A 慢性肺アスペルギルス症の分類と診断
B ABPAと慢性肺アスペルギルス症合併の病態生理
C ABPAと慢性肺アスペルギルス症合併の実際
D 第1回全国調査(2013年)におけるABPMと慢性肺アスペルギルス症の合併症例
E ABPAと慢性肺アスペルギルス症合併の治療
3 アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎
A 疾患の概要
B AFRSの診断
C AFRSの治療
D 今後の課題
4 慢性下気道感染症
A ABPA/ABPMと緑膿菌
B ABPA/ABPMと非結核性抗酸菌
5 気管支拡張症
A 気管支拡張症の原因疾患
B 気管支拡張症とアスペルギルス関連疾患
第7章 ABPA/ABPMの予後
1 臨床病期
A 臨床病期
B 放射線画像学的な分類
2 臨床的寛解
A 臨床的寛解の定義
B 臨床寛解失敗リスク
3 増悪・長期予後
A 増悪の定義169
B 増悪の頻度とその要因
C 長期予後
第8章 ABPA/ABPMの治療
1 治療総論
2 経口副腎皮質ステロイド薬
3 抗真菌薬
A ABPAに対する抗真菌薬の位置づけ
B ABPAに対する抗真菌薬の投与期間
C ABPAに対する抗真菌薬投与の副作用
D ABPMに対する抗真菌薬の位置づけ
4 抗体医薬
A ABPA/ABPMの標準治療と分子標的治療薬の意義
B 投与に至る背景
C ABPA/ABPMに対する抗体医薬治療の現状と今後の展望
5 マクロライド系抗菌薬
A 慢性下気道感染症を伴うABPA/ABPMに対するマクロライド系抗菌薬
B ABPA/ABPMに対するマクロライド系抗菌薬の可能性
第9章 環境整備
1 居住環境
A 居住環境の真菌による健康への影響について
B 居住環境の真菌量を低減させるアプローチ
2 空調機器
A 居住空間における空調機器の役割
B 室内真菌汚染について
C 空調機器の清掃方法
D エアコン清掃の効果
E ABPA/ABPM患者居宅におけるエアコン保守管理に関する推奨
第10章 症例
1 典型的なABPA(急性期)
2 典型的なABPA(進行期)
3 スエヒロタケによる喘息非合併ABPM
4 経過中に原因真菌が変化したABPM
5 糸状菌特異的IgE陰性で原因真菌不明なABPM
6 ABPAの気管支拡張病変に慢性肺アスペルギルス症を合併した1例
7 経口ステロイド薬投与中にABPAを発症し,抗真菌薬で治療を行った慢性肺アスペルギルス症例
8 肺非結核性抗酸菌症で治療中にABPAを発症し,抗IL-4受容体抗体で粘液栓が消失した症例
9 粘液栓による呼吸不全が急速に進行し,ECMOで救命しえたスエヒロタケABPM
10 環境因子曝露によって増悪したABPA/ABPM
11 粘液栓除去により自然軽快したABPA
12 抗体医薬(抗IL-4受容体α鎖抗体)で治療したABPA
13 抗体医薬(抗IL-5受容体α鎖抗体)で治療したABPA
索引