内科学 第5版
リハビリテーションに必須の内科学の知識をアップデート!
もっと見る
超高齢社会の現在、内科的疾患を併存するリハビリテーション対象者は多く、対象となる疾患も広がってきている。理学療法士、作業療法士は内科学を必須の知識として学び、常に新しい情報にも触れておく必要がある。本書は、PT/OTに必要な内科学の知識をコンパクトにまとめた定番のテキスト。第5版はカリキュラム改訂に伴って、リハビリテーションに必要な薬の知識についての記述を追加した。
| シリーズ | 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野 |
|---|---|
| 編集 | 前田 眞治 |
| 発行 | 2024年10月判型:B5頁:416 |
| ISBN | 978-4-260-05608-3 |
| 定価 | 6,600円 (本体6,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第5版 序
本書の初版が2000年に出版されてから25年,1/4世紀が経過した.この間,医療の発展は著しく,内科学も医療機器の進歩に加えて,AI(人工知能:Artificial Intelligence)診断学の発展,遠隔診療・治療の普及,血管内治療や分子標的治療,遺伝子学的治療などの進展に伴い,変革の時代の中にいる.
2019年12月に発生した新型コロナウイルス感染症は世界中で猛威をふるい,理学療法士・作業療法士の養成校の講義なども対面で行うことができず,リモートで行われたこともあった.コロナ禍の中でリハビリテーションが必要な高齢者や障害者は外出の制限を受け,自宅内に留まることも多くなり,社会活動は大幅に制約されることとなった.
近年,リハビリテーションの対象者は,呼吸リハビリテーション,心臓リハビリテーション,腎臓リハビリテーション,悪性腫瘍のリハビリテーションなどの領域にも広がってきており,内科的知識は患者の状態を理解するのに必要不可欠となっている.また,第2次世界大戦後のベビーブーム世代が2025年には後期高齢者になり,リハビリテーション対象者のほとんどが何らかの内科的疾患を合併していることが想定される.このため,内科的管理なしにリハビリテーションを安全・円滑に行うことは困難である.
理学療法士・作業療法士などのリハビリテーション専門職が内科的知識を身につけることは,日常臨床の中で対象者に自身の状態を内科的な観点からも的確に把握してもらっているという心理的な安心感を与え,患者-医療者間の良好なコミュニケーションや信頼関係の構築に大きく寄与することになる.
本書の内容は理学療法士・作業療法士国家試験出題基準に準拠して書かれているが,国家試験の範疇にとどまらず,広範な内科学の知識が網羅されており,臨床の現場でもすぐに役立つ豊富な情報が得られる内容であると自負している.
初めて内科学を学ぶ人が理解しやすく親しみやすい内科書であることを念頭に,内科学とはどのようなものであるかに触れ,診察のしかたや症状のとらえかた,症候学,検査法などを最初の部分で解説している.その後に,臓器別・系統別に疾患の病態生理・症状・治療法などを最新の知見を含めて記述した.
本書の最大の特徴は,実際にリハビリテーション医療に従事して,常に対象者の内科学的管理も行いながら医療を実践しているリハビリテーション専門医が執筆している点であり,リハビリテーションに必要な内科学という視点に立って必須の知識を的確に網羅している点にある.
第5版も,熱意をもってリハビリテーション関連専門職の育成に心血を注いでおられる山形県立保健医療大学の上月正博教授,熊本保健科学大学の飯山準一教授に引き続き執筆いただいた.本書をとおして,理学療法士・作業療法士などの専門職が内科学的知識をもち,最良のリハビリテーション医療を行うために貢献することを期待する.
2024年9月
編者 前田眞治
目次
開く
序説 理学療法士・作業療法士にとって内科学を学ぶ意義
1 内科学とは
A 内科学の概念
B 内科学とリハビリテーション
2 内科的診断と治療の実際
A 診断・鑑別診断の進め方
B カルテの書き方
C 診察法
D 臨床検査
E 内科的治療
F 理学療法・作業療法との関連事項
3 症候学
A 発熱
B 全身倦怠感
C 食欲不振・食思不振
D 悪心・嘔吐
E 易感染性
F 意識障害
G めまい
H 浮腫・むくみ
I レイノー現象
J 頭痛
K リンパ節腫脹
L ショック
M 理学療法・作業療法との関連事項
4 循環器疾患
A 循環器系の解剖と生理
B 循環器疾患の主要な症候
C 循環器疾患の診断法
D 循環器疾患各論
E 心臓リハビリテーション
F 理学療法・作業療法との関連事項
5 呼吸器疾患
A 肺の解剖と生理
B 呼吸器疾患の症候とその病態生理
C 臨床検査所見
D 呼吸器疾患各論
E 呼吸リハビリテーション
F 理学療法・作業療法との関連事項
6 消化管疾患
A 消化管の解剖と生理
B 消化管疾患の症候とその病態生理
C 消化管疾患の検査法
D 消化管疾患各論
E 理学療法・作業療法との関連事項
7 肝胆膵疾患
A 肝臓
B 胆道系
C 膵臓
D 腹膜
E 肝胆膵疾患の検査・診断法
F 肝胆疾患各論
G 膵疾患各論
H 腹壁・腹膜疾患各論
I 理学療法・作業療法との関連事項
8 血液・造血器疾患
A 血液の成分と生理
B 造血と血液細胞の分化
C 血液疾患の主要な症候
D 血液の検査法
E 血液疾患各論
F 理学療法・作業療法との関連事項
9 代謝性疾患
A 代謝調節の仕組み
B 代謝性疾患各論
C 理学療法・作業療法との関連事項
10 内分泌疾患
A 内分泌総論
B 内分泌腺とホルモンの解剖・生理
C 内分泌検査法
D 内分泌疾患各論
E 理学療法・作業療法との関連事項
11 腎・泌尿器疾患
A 腎臓の解剖と生理
B 腎疾患の症候とその病態生理
C 腎・尿路系疾患の検査
D 腎・泌尿器疾患各論
E 電解質代謝の異常
F 腎臓リハビリテーション
G 理学療法・作業療法との関連事項
12 アレルギー疾患,膠原病と類縁疾患,免疫不全症
A 免疫系の働き
B アレルギー疾患
C 膠原病
D リウマチ性疾患
E 免疫不全症
F 理学療法・作業療法との関連事項
13 感染症
A 感染症総論
B 感染症各論
C 理学療法・作業療法との関連事項
14 リハビリテーションに必要な栄養学
A 栄養,栄養素
B 食物の消化吸収と代謝
C 体内で合成できない栄養素
D 必要栄養量の決定
E 栄養評価・診断と栄養サポート
F 代替栄養法
G 理学療法・作業療法との関連事項
付録 救命救急の知識
A リハビリテーションで必要な救急処置
B 具体的な救急救命処置
C 窒息時の対応
付録 リハビリテーションで必要な薬剤の知識
A 薬の種類と効き方
〔表〕 主な薬剤の作用・適応と注意点
索引
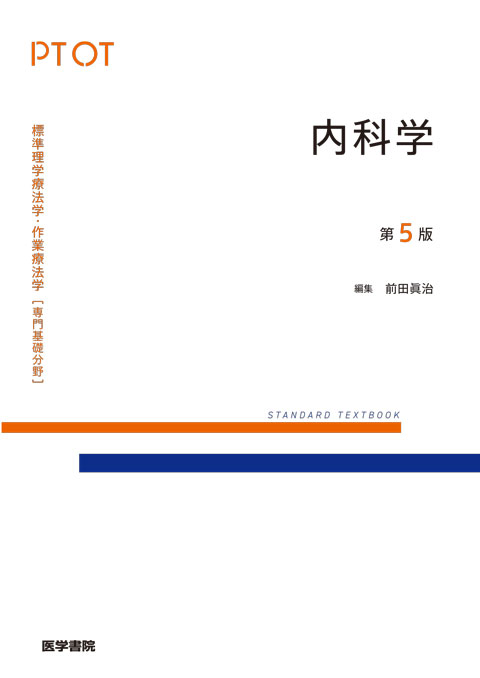
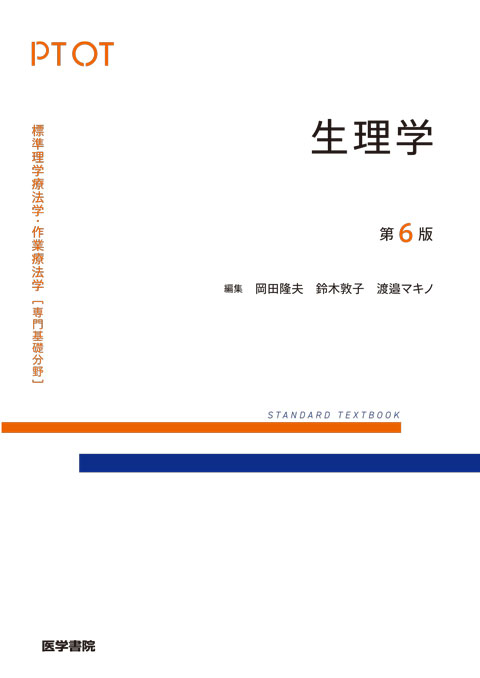
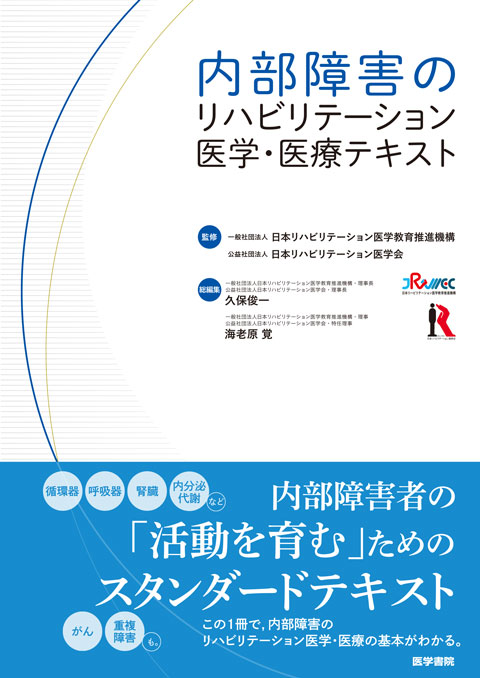
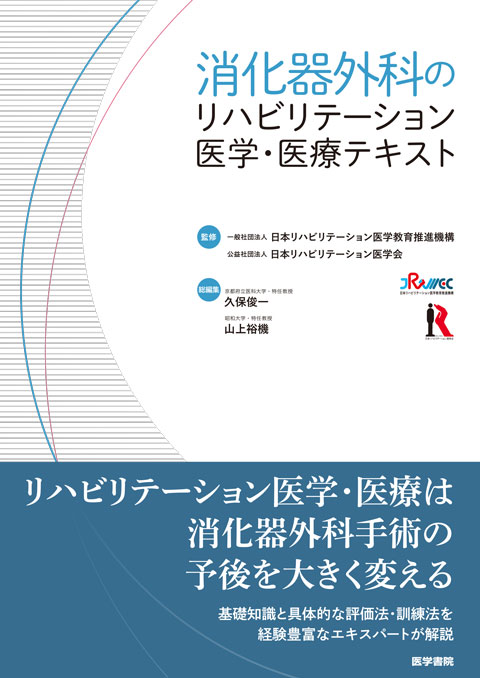
![新臨床内科学 [ポケット判] 第10版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1316/0458/6749/93095.jpg)