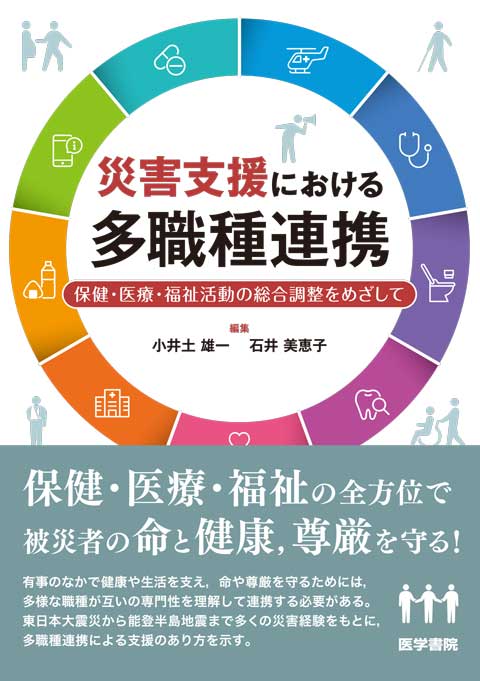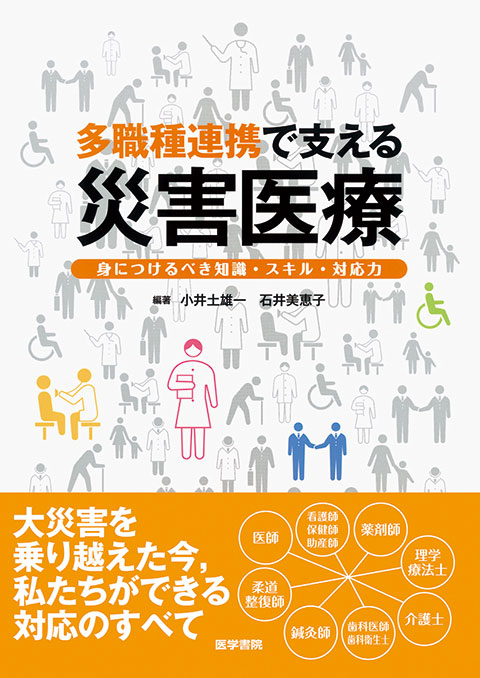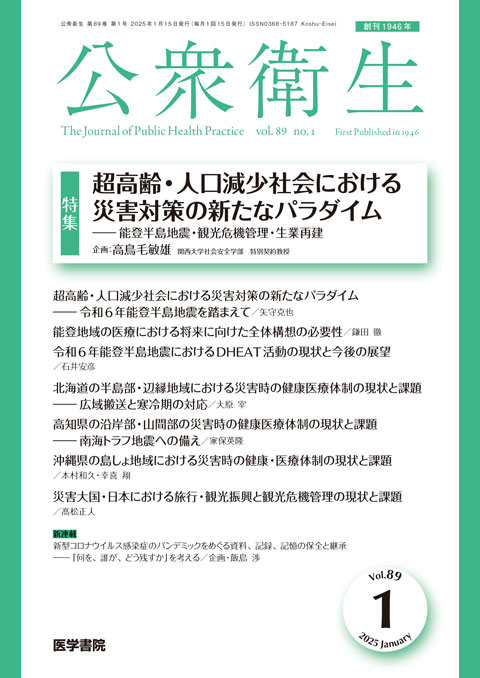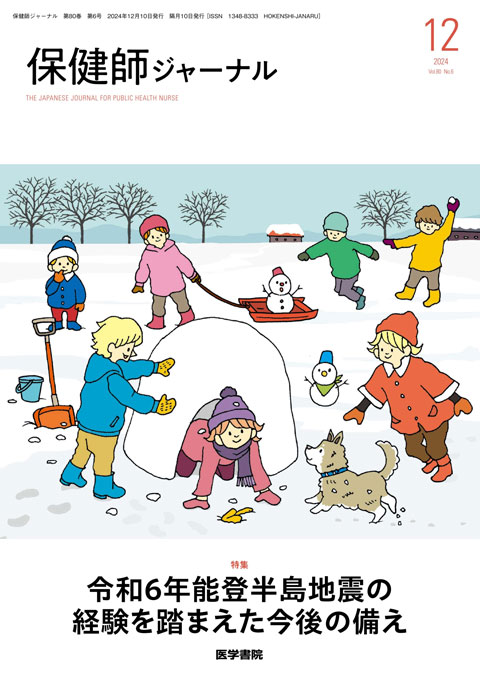災害支援における多職種連携
保健・医療・福祉活動の総合調整をめざして
災害支援をもっと進化させるために伝えたい連携とは、被災者を守るとは
もっと見る
地震や異常気象により毎年のように災害が発生している。COVID-19も災害と考えられた。次はどこが被災するかわからない。医療従事者は災害時の支援・受援を知っておく必要がある。重要な概念は2つ、多様な職種との連携と被災者の人権尊重。本書は令和6年能登半島地震も踏まえ、14チームと13団体の強みを紹介し、多職種連携とともに人権憲章やジェンダーの問題などあらゆる災害支援のあり方について伝える。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
2017年2月に本書の前書である『多職種連携で支える災害医療──身につけるべき知識・スキル・対応力』を上梓してから8年が経った。前書は,東日本大震災の教訓から,様々な医療従事者や職種が連携し急性期から災害対応に関わることが必須であり,特に災害関連死は,医師・看護師を中心とする医療チームだけでは防ぐことができず,急性期から慢性期まで多職種連携で被災者,とりわけ災害時要配慮者にきめ細かく支援することが必要であるという強い思いで発刊した。前書では災害医療に関わる多様な職種に関して,それぞれの災害医療における役割を述べた。
一方,この8年間でいくつもの災害を経験し,多職種連携の重要性は誰もが認める事項となり,実災害で実践されるようになった。本書の目的は,実災害での経験を交えて,いかに多職種連携を実践するかを示すことにある。多職種連携の実践の第一歩はお互いを知ることである。お互いを知らなければ連携できないからである。そして,情報を共有し,同じ指揮系統のなかで活動することが求められる。
そこで,本書では,各支援組織がどのような体制をもち,どのような指揮系統のもとで,どのように情報を共有し,どのような活動ができるのか,さらに実災害ではどのように多職種連携を行ってきたのかを紹介する。お互いを知り連携し補完し合うことにより相乗効果が発揮され,より質の高い支援が可能になる。本書がお互い顔の見える関係づくりの一助になり,目的・目標を共有して同じ方向を向き,方略を共有することができれば幸いである。
また,この8年間で厚生労働省の災害対応指針も変わった。平成28(2016)年熊本地震において現場レベルで保健師チームと医療チームの乖離が課題として残り,この教訓に基づき,保健と医療の一元化(連携・総合調整)のための保健医療調整本部の設置が指示された。医療チームという呼称も保健医療活動チームに変更され,すべての保健医療に関わるチームを含めることとし,関係機関との連絡および情報連携を行うための窓口を設置することとした。
この新しい体制はその後,昨今の気象災害により多くの福祉・介護施設が甚大な被害を受け,また令和3(2021)年防災基本計画に災害派遣福祉チームの整備が追加されたため,保健医療福祉調整本部となった。これにより保健・医療・福祉に関するチームは総合調整されることとなり,まさに国においてもこの8年間で災害対応は多職種連携が必要であるという舵取りがなされたことになる。
しかしながら,保健と医療と福祉はそもそも縦割りであり,「言うは易く行うは難し」である。そのような状況下で起こったのが令和6(2024)年能登半島地震である。この地震においては,DMATはもちろんのこと,JMATやAMATをはじめ各組織・機関より過去最大のチームが派遣され,DHEAT,DWATなどのチームも初めての本格的な活動となった。様々な職能団体による多職種連携が行われ,保健・医療・福祉の連携・総合調整が初めて行われた。本書では,その経験から保健医療福祉の一元化ができたかについても触れる。
また,災害関連死だけでなく,避難所等の環境による健康被害やメンタルヘルスにおいて,さらには新興感染症(新型コロナウイルス感染症)対応においても多職種連携により支援活動が実践されていることを記している。さらに,国際災害支援では当たり前となっている人道憲章やジェンダーの問題についても取り上げた。
我が国は災害多発国である。日本に住んでいる限り災害から逃れることはできない。特に最近は地震だけでなく気象災害が毎年のように起きており,異常気象を考えるとさらに増加することが予想される。医療従事者の誰もが,支援する側,受援する側含めて,いつ自分が矢面に立たされるかわからない。その意味で,すべての医療従事者は災害医療を学ぶ必要があり,多職種連携の重要性を理解し,被災者の命や生活,尊厳を守るという意識を身につけたい。平時の備えとして,各医療施設などでも本書を参考に教育や研修をしてもらいたい。また,多くの職種の方々に幅広く読まれ,個々の対応能力の向上,そして多職種連携に益することを願う。
2025年元旦
編者 小井土雄一・石井美恵子
目次
開く
第1章 災害支援において多職種連携がなぜ必要か
1) 過去の震災で整備されてきた日本の災害医療体制
2) 災害時に保健・医療・福祉の連携が必要とされた背景
3) 保健医療福祉の一元化には多職種連携が必要
4) 災害関連死を防ぐ多職種連携と地域連携BCP
5) 人道支援を支える原則とその重要性
第2章 災害時の保健医療活動体制を知ろう
1 保健医療福祉調整本部とは
A 保健医療福祉調整本部の役割・機能
B 保健医療福祉調整本部の運営,構成員・組織体制
C 多職種連携を支える本部活動の実際
Column 行政の役割
2 災害医療コーディネーター
1) 災害医療コーディネーターの出現まで
2) 災害医療コーディネート体制モデル
3) 災害医療コーディネートチーム
4) 保健,医療,福祉三分野の調整の必要性
5) 災害医療コーディネーターの養成と委嘱の状況
6) 災害時小児周産期リエゾンの活動
第3章 多職種連携とはどういうことか
第4章 災害時に活動する支援チームや各職種の役割・機能を知ろう
1 災害時に活動する支援・派遣チーム
A 災害派遣医療チーム(DMAT)
B 災害派遣精神医療チーム(DPAT)
C 災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)
D 保健師等支援チーム
E 日本医師会災害医療チーム(JMAT)
F 日本赤十字社の救護班
G 国立病院機構医療班
H 全日本病院協会災害時医療支援活動班(AMAT)
I 日本災害歯科支援チーム(JDAT)
J 薬剤師支援チーム
K 災害支援ナース
L 日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)
M 日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)
N 災害派遣福祉チーム(DWAT/DCAT)と災害福祉支援ネットワーク
2 各学会・団体等の活動
A 日本災害医学会──災害医療コーディネーションサポートチーム
B 災害時感染制御支援チーム(DICT)
C 日本透析医会──透析医療における災害対策
D 日本糖尿病学会:糖尿病医療支援チーム(DiaMAT)
E 日本神経学会災害支援ネットワーク:重症神経難病患者支援
F 日本産科婦人科学会
G 日本小児科学会
H 避難所・避難生活学会
I 日本老年医学会:高齢者災害医療支援
J 日本プライマリ・ケア連合学会(PCAT)
K 災害派遣柔道整復チーム(DJAT)
L 災害支援鍼灸マッサージ合同委員会(DSAM)
第5章 救護所・病院・避難所における多職種連携の実際
1 救護所における取り組み
2 病院支援における取り組み
3 避難所における取り組み
4 福祉避難所における取り組み
5 災害とジェンダー:避難生活における困難と必要な支援
第6章 災害支援の様々な場面における多職種連携
1 メンタルヘルスにおける多職種連携
A 被災者のメンタルヘルス
B 救援者のメンタルヘルス
2 災害関連死と健康二次被害を防ぐ多職種連携
A 防ぎえた災害死
B 災害関連死
C 避難所の生活環境と健康被害
第7章 感染症パンデミックにおける多職種連携
第8章 国際災害支援における多職種連携
1 国際災害のスタンダード
2 我が国の国際EMT受援計画
3 避難所の国際基準としてのスフィア基準:被災者の人権を多職種連携で守る
索引
書評
開く
専門分化と多職種連携が進む災害支援の今が分かる
書評者:鈴木 良美(東京医科大学看護学部教授)
◆災害支援の体制は日々更新されている
以前,「保健師ジャーナル」の編集委員の任期中に,「令和6年能登半島地震」における保健師の活動を特集テーマに取り上げようと考えたとき,「DHEAT(Disaster Health Emergency Assistance Team)と保健師チームの違いは何だろう?」という素朴な疑問が浮かびました。どちらのチームにも保健師が参加していることは知っていましたが,厚生労働省のウェブサイトなどに掲載されている活動報告を読んでも,その違いや位置づけが分かりにくく,全体像をつかむのに苦労したのです。
そこで,災害時の保健師活動に長年関わってこられた国立保健医療科学院の奥田博子先生にお話を伺い,ようやくその違いを理解することができました。この経験を通して,災害対応の体制そのものが過去の教訓を踏まえて日々更新され,新たなチームも誕生していることを改めて実感しました。奥田先生は,本書『災害支援における多職種連携』の著者のお一人でもあります。
私自身も,東日本大震災の際に岩手県大槌町での全戸訪問に参加した経験があります。しかし,現場に行ったからといって災害支援の仕組みが見えるわけではありません。目の前の住民支援に集中するあまり,自分がどのような仕組みの中で動いているのかを意識する余裕はほとんどありませんでした。
本書は,そうした専門分化が進む災害支援の現場における全体像を教えてくれる一冊です。阪神・淡路大震災から今日に至るまで,災害での教訓を糧に,災害関連死を防ぐためにどのように医療体制が整えられ,さまざまな職種が誕生し,連携が必要となっていったのかを丁寧に解説しています。
さらにDMAT,DPAT,DHEAT,そして保健師チームといった災害支援に関わる各チームや職種の役割・機能,多職種連携の実際が具体的に示されており,実際の活動をイメージしやすい構成です。
◆災害支援の枠組みを俯瞰的に理解する
多職種連携が進む一方で,関係者が増えるほど「誰が何を担っているのか」が見えにくくなるという課題もあります。そうした中で,自分がどのチームの一員として,どのような役割を期待されているのかを知ることは,冷静に行動するための大切な基盤になります。
令和6年能登半島地震では,卒後3年目の本学卒業生が,保健師チームの一員として現地で活動したと話してくれました。災害支援は今や,特別な業務ではなく,保健師の通常業務の延長として定着しつつあるのだと実感しています。しかし一方で,保健師はオールラウンダーであるがゆえに,災害対応に関する専門的知識や支援体制について十分に学ぶ機会は限られているのも事実です。
本書は,そうした保健師にとって,職場に常備しておきたい“辞書”のような存在になるでしょう。現場に携行して活用することもでき,支援の枠組みを俯瞰的に理解するための羅針盤となります。災害支援にすでに関わっている方も,これから関わる可能性のある方も,ぜひ手に取ってほしい一冊です。
(「保健師ジャーナル」 Vol.81 No.4 掲載)
一つの職種,一つの組織では災害には立ち向かえない
書評者:石井 正(東北大病院総合地域医療教育支援部部長)
本書は,近年の災害対応における多職種協働の実践と課題を体系的にまとめた,極めて実践的かつ意義深い一冊である。
私は2011年の東日本大震災において,最大被災地の一つである石巻医療圏で宮城県災害医療コーディネーターとして,支援医療救護班で構成された「石巻圏合同救護チーム」を立ち上げ,地域災害医療の現場指揮に当たった。そのとき痛切に感じたのは「一つの職種,一つの組織では災害には立ち向かえない」という現実であった。すなわち,避難所巡回診療などの医療提供だけでなく避難所の健康支援,仮設住宅への移行,慢性疾患患者のフォロー,福祉的ケア,精神的ケア,そして地域全体の情報調整――被災者の健康を守るためにはこれらの保健福祉領域のサポートは必須なのだが,それを円滑に遂行・調整していくためには看護師,保健師,薬剤師,社会福祉士,行政職,自衛隊,NPO,地元住民といった多様な立場の人々の力が必要だったのである。
本書が優れているのは,第一に,そうした災害支援の実際における「多職種の力」について,読者がイメージしやすいように,支援チーム・職種ごとにその発足経緯を含めて具体的に紹介している点である。中でもDMAT,DPAT,DHEATなどの専門チームの活動や,各種学会の災害支援活動などについて非常にわかりやすく述べられている。第二に,救護所,病院,避難所など災害支援の「場」ごとに多職種連携による支援の取り組みについても述べられている点である。第三に,ジェンダー視点に立った配慮,メンタルヘルス,災害関連死など,災害支援にかかる課題ごとに支援の在り方についても言及をしている点である。本書はこれらのことがよく整理された形で構成されているので,生きた実践書としての役割を十二分に果たしているといえる。
効果的な多職種連携体制を構築するためには,互いの職能の背景や制度,価値観を理解し,橋渡しをすることが求められる。私自身,震災当時,前述のように行政と医療,医療と福祉のあいだをつなぐ役割を担わざるを得なかった。これは,災害時に限らず平時の地域包括ケアの実践にも通じる本質的な視点であり,本書がその重要性を繰り返し強調している点は評価に値する。
また,COVID-19という新たな健康危機における多職種連携の課題と対応が章立てて取り上げられている点も,斬新である。パンデミック下では従来の災害対応の枠組みでは対応しきれない複雑性が顕在化した。本書はそうした新たな局面に対しても,多職種の柔軟な協働と相互理解の重要性を説いている。
災害は必ずまた起こる。そのとき,私たちはよりよい連携のかたちを探求し続けなければならない。その意味でも本書は,災害医療に従事する全ての医療従事者のみならず,現場で迷いながらも人びとのいのちと暮らしを支えようとする支援者たる行政職,教育者,地域福祉に携わる人々にとっても,大きな学びと示唆を与えてくれる書となろう。