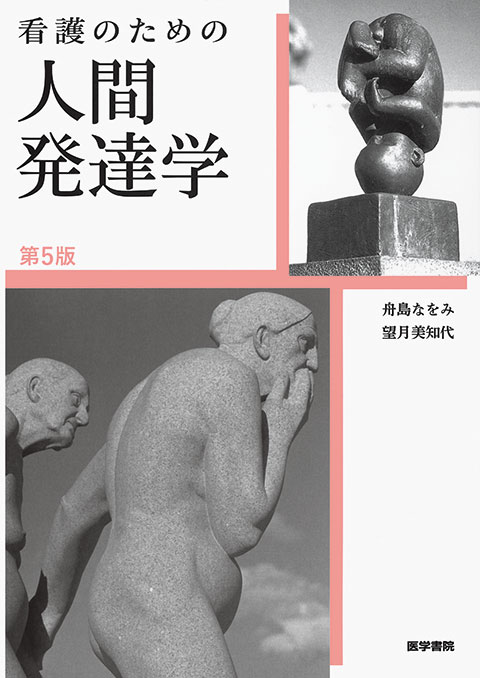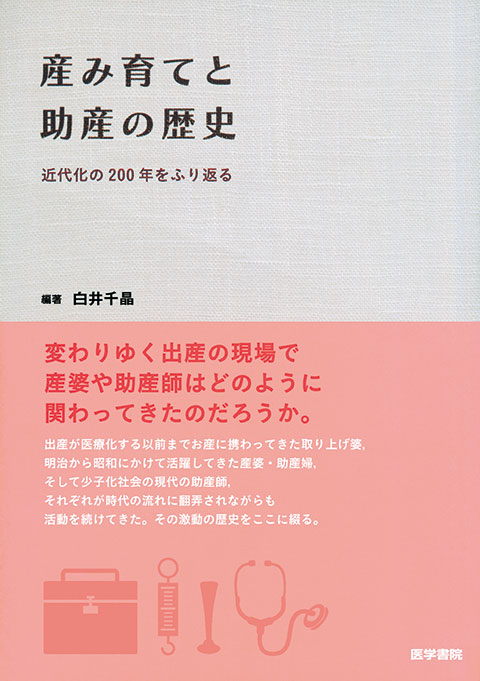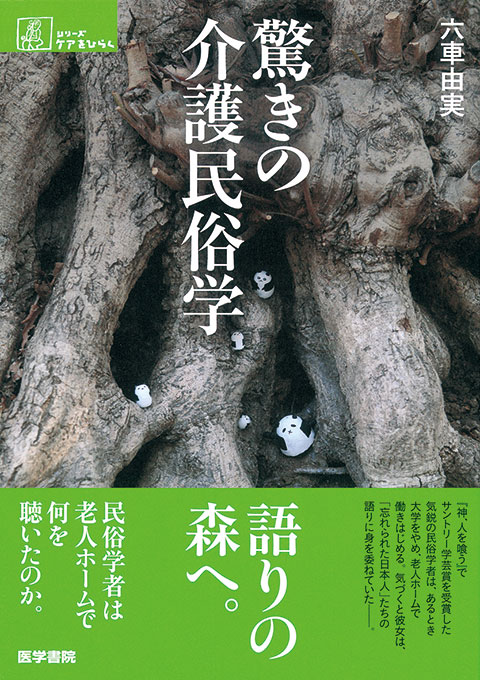文化人類学 [カレッジ版] 第4版
「人間とは何か」を問う。医療・看護領域に向けた文化人類学テキストの決定版!
もっと見る
人間にとって文化とはなにか。文化を見つめることで、人間が見えてくる。身体観、死生観、宗教、世界観など、人を理解するうえで欠かせない「文化」をさまざまな切り口で紹介することで、これまでの概念にとらわれない新たな視界をひらく。いま再びいのちについて考えるための、スタンダードでありながらも新しい文化人類学テキスト。
| 編集 | 波平 恵美子 |
|---|---|
| 発行 | 2021年01月判型:B5頁:244 |
| ISBN | 978-4-260-04220-8 |
| 定価 | 2,530円 (本体2,300円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はしがき
文化人類学は,「人間とは何か」という最も根本的な問いを,「人間にとって文化とは何か」というかたちに置き換えて答えを見出そうとする。そして「文化」を,人間が地球上に現れて以来,生存のために行ってきた多面的な活動とその結果の複合的全体と考えて,その「文化」の普遍性と多様性を具体的に明らかにしようとする。
21世紀に入りすでに20年が過ぎた現在,人間の文化を研究する文化人類学の役割は,以前にもまして,重要になっている。
そのように考える根拠は少なくとも4つある。
1つには,人間が開発した技術,作り出したものの数々,そして歯止めのない欲望は地球の環境を大きく変え,結果として人間の生存を危うくしている。改めて,人間存在とその「文化」の意味を見直し,根本的に改めるべきものを見出す役割である。
2つには,「グローバル化」と称される現象は人間の生存のありようの急速な画一化をもたらし,その多様性を失わせようとしている。20万年以上前に中央東アフリカで生まれて以来,人間は数々の困難を克服しその生存領域を地球規摸に拡大させてきた。それは,ひとえに人間が多様な生き方を発達させたからに他ならない。文化の多様性こそ人間の生き残る道であることを明確にする役割である。
3つには,多数の人の移動と接触が文化の融合だけではなく反目・対立・紛争を生んでいる。そうしたことから,政治的・経済的利害の対立の原因の一端を「文化の違い」とする誤った主張が生まれており,こうした誤った認識を正す役割である。
4つには,2019年末に発現した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックのさなかに現れ,そしてその終息後にも現れるであろう,人間の「文化」の重要な要素を揺るがしかねない大きな変化の研究である。1918年に発現した「スペイン風邪」はともかく,1957年の「アジア風邪」以降いくつかのインフルエンザ・パンデミックが発生したが,COVID-19パンデミックは,それ以前と異なり,真の意味での世界規模での大流行である。その中で,感染予防に採られた最も基本的で重要な予防手段は,「自分以外の人との接触を極力避ける」というものである。生命を感染の危険から守るために,人間が人間であるうえで最も重要な,身体接触を含む人間関係を,一時的であれ,根底から否定することが強調される。また,感染の初期から次第に顕わになってきた,国内,国家間,地域間の格差がある。人の生命が直接関わるがゆえに,感染予防と治療や救命における格差は,強い感情を伴う。このパンデミックのさなかに,そして終焉後の世界を,文化人類学は,痛みを伴いながらも,研究対象にする義務があるだろう。いずれも容易な道ではないが,文化人類学の1世紀半の歴史の中で,現在はその存立意義を示す正念場かもしれない。
本書は7つの章から構成されている。それぞれを簡単に示すと,次のような内容である。
第1章は文化人類学の概要について述べている。第2章は文化人類学の質的研究における位置づけと方法論,その中でもとくにエスノグラフィについて述べている。第3章は,文化が規定する人(個人)についての観念,個人と個人,個人と集団とのつながりを成立させている複雑で巧妙なありようについて,また,家族から国家に至るまでの社会集団について述べている。第4章は「人生儀礼」をはじめとする儀礼が持つ機能と構造,そこで示される時間と空間の分類と認識について述べている。第5章は「宗教」や「信仰」を,文化人類学では一般に考えられているよりはるかに広くとらえて,これらが人間の生存における適応の洗練されたかたちであることを述べ,また,トランスカルチュラル化が進む時代にあって,人びとが築く多様な「世界観」について述べている。第6章は「医療人類学」と呼ばれる分野の概要を示しながら,身体,いのち,健康,病,医療が文化においてどのような位置にあるかについて述べている。第7章は「いのち」あるいは「生命」の意味が,自然科学の影響の広がりの中で拡大していること,一方,誕生と死そして身体において示される人のいのちは,文化的に強く意味づけられていることについて述べている。
「文化人類学」という学問分野の名称は,「社会学」や「心理学」に比べると,現在でもそれほど広く知られていない。しかし,健康科学その他多くの領域で,「フィールドワーク(現地調査)」や「エスノグラフィ」という方法と理論は,その名称も含めて,開発に文化人類学が大きく貢献したことは知られないまま,現在では広く使われている。また,文化人類学が長年にわたり検討を重ね磨いてきた「文化」をはじめとする多くの概念や用語も,文化人類学オリジンであることは知られていないまま広く使われている。喩えれば,作曲者の名前が忘れられたか知られないままに多くの人が長年口ずさむ,イギリスの古謡「グリーンスリーブス」のようなものこそ名曲とされるように,文化人類学が開発した様々な研究手法や概念や理論が,それとは知られずに一般化されてきたことを,文化人類学者は大いに喜ばなければならない。
2020年11月
編者 波平恵美子
目次
開く
第1章 人間と文化
A 文化人類学における文化
①人間であることと文化
②「人種」と民族と文化
③国家と民族と文化
B 文化の諸相
①モノと文化
②分類と文化
C 文化人類学はどのような学問か
①植民地の拡大と文化人類学の誕生
②文化相対主義と文化人類学
③研究方法
④人類学・文化人類学・社会人類学・民族学および隣接分野
D 現代社会と文化人類学の現在
①変化する人間社会と文化人類学の理論
②グローバル化時代の個人と文化
第2章 質的研究とエスノグラフィー
A 質的思考から質的研究へ
①質的思考の基層性
②質的研究とは
B 文化人類学とエスノグラフィー
①質的研究の源流としてのエスノグラフィー
②エスノグラフィーとは
③質的研究の基礎教養としての文化人類学
④エスノグラフィーの展開
C エスノグラフィーを現代にいかす
①「現場」でエスノグラフィーをいかす
②「コロナ後」の世界を想像/創造するために
第3章 個人・家族・家族をこえたつながり
A 個人と社会
①「個人」という概念
②社会における個人
B 家族
①家族のなりたち
②現代社会と家族
C 家族をこえたつながり
①親族
②コミュニティとボランタリー・アソシエーション
③国家
第4章 人生と通過儀礼
A 通過儀礼と境界理論
①通過儀礼とは,なにか
②通過儀礼と境界理論
③自然は本来かたちのないものである
④なぜ節目が危険なのか
B ライフサイクルと境界理論
①人間の一生とライフサイクル
②なぜ誕生や死が危険視されるのか
C 儀礼の構造
①ファン ヘネップと儀礼の構造
②誕生儀礼
③成熟儀礼
④結婚の儀礼
⑤葬式
D 通過儀礼とコミュニタス
①過渡の局面の特徴
②過渡の期間とコミュ二タス
E なぜ通過儀礼を経なければ大人になれないのか
①個人にとってのライフサイクル
②通過儀礼を経なければ,人は「大人」になることはできない
第5章 宗教と世界観
A 文化人類学と「宗教」
①「宗教」を考える
②文化人類学の分析枠組みを通して宗教をみる
B 文化人類学と儀礼研究
①儀礼の定義と分類
②儀礼と「伝統」
C トランスナショナル時代における宗教と世界観
①トランスナショナル化が進む日本
②「宗教と世界観」研究と現代社会
第6章 健康と医療
A 健康と文化
①健康とはなにか
②健康のリスクとレジリアンス
③医療人類学の方法論
B 病気と治療
①病気の認識
②病気の経験
③治療の実践
C 医療の体系
①観念と制度
②医療の体系から医療の実践へ
D 環境と健康
①環境に対する人間の適応
②遺伝的適応と不適応
③文化的適応と不適応
④環境のグローバル化がもたらす健康リスク
第7章 いのちと文化
A 「いのち/生命」の多様性
①「いのち/生命」を定義する試み
②民族誌にみる生命観
B 誕生と死における人のいのち/生命
①いのち/生命が生まれるとき
②人の死──いのち/生命が失われるとき
C いのち/生命と身体
①動く身体と動かない身体──身体の多様な状況とそこにあらわれるいのち/生命観
②身体・人格・いのち/生命
索引
![文化人類学 [カレッジ版] 第4版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6516/0879/6737/107254.jpg)
![心理学 [カレッジ版]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8116/0458/6369/92115.jpg)