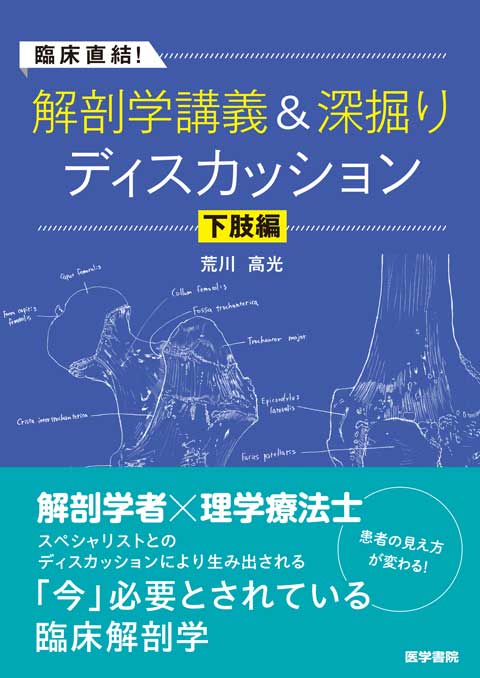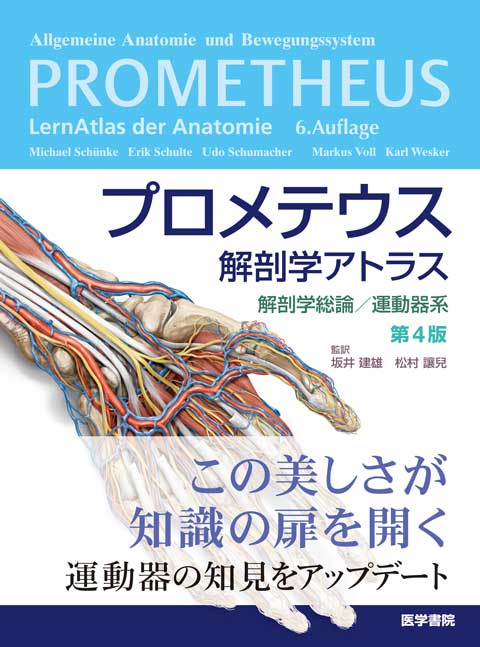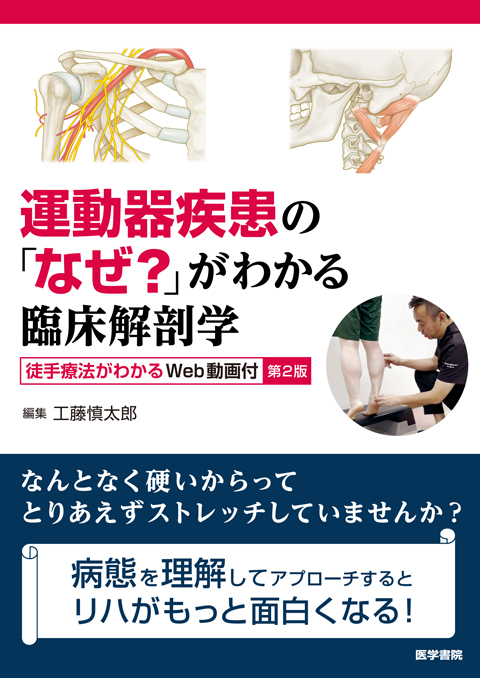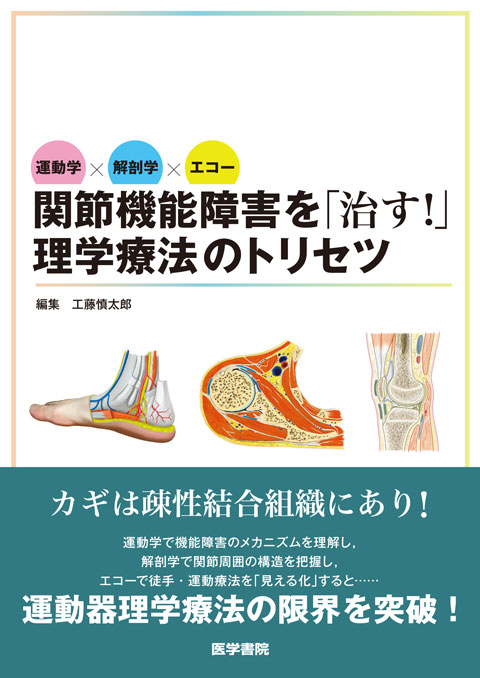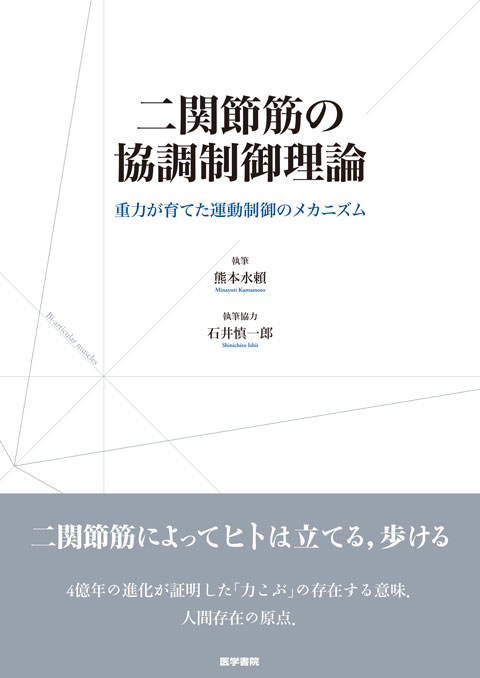臨床直結!解剖学講義&深掘りディスカッション 下肢編
解剖学者×理学療法士 臨床家との対話から生み出される、「今」必要な臨床解剖学
もっと見る
PT界における解剖学エキスパートである荒川先生が、重要ポイントを厳選して講義。運動器理学療法のスペシャリストから鋭い質問がとぶ。臨床で直面する病態やトリガーポイントを深掘りディスカッションで言語化していくなかで、解剖学を臨床に落とし込む過程が見えてきて、患者の見え方が変わる。臨床も解剖学もぞくぞくするほど面白い! このダイナミズムを体感せよ!
| 著 | 荒川 高光 |
|---|---|
| 発行 | 2025年10月判型:B5頁:196 |
| ISBN | 978-4-260-06019-6 |
| 定価 | 5,280円 (本体4,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
解剖学は「観察する」ことから始まり,「理解」に至る学問である──。
本書は,「解剖学を学びたい」という読者に向けた書籍であると同時に,「臨床場面で解剖学がどのように活きるのか」という視点も盛り込んでいる。私は,解剖学を根本から研究する「科学者」としての姿勢を大切にしてきたが,一方で理学療法士として臨床の現場に身を置いてきた。この2つの視点を融合して結実させたのが本書である。
解剖学は,臨床のことをいったん置いて,真正面から向き合う必要がある奥深い学問である。長い歴史がありながら,実際にはいまだに教科書や論文に記されていない未知の部分が多く存在する。有史以来,解剖学は変化し続けてきた。特に近年では,肉眼解剖学の領域においても再発見や再検討が進み,今なお新たな知見が積み重ねられている。では,人体そのものが変化したのかといえば,決してそうではない。変わってきたのは「解剖学」であって,「身体」ではない。実際にご遺体を解剖して観察し,そこから得られる知見こそが臨床に直結する。しかし,この「生きた解剖学」は,既存の教科書とは異なる姿を見せることがある。
初めて解剖学の教科書を読み進めたときに,「臨床で役に立ちそうだ」と実感することは難しい。なぜだろうか。2つの理由が考えられる。
第一に,解剖学は「形態」を対象とする学問であり,臨床医学のためにある内科学や外科学とは性格が異なるという点である。解剖学者は本来,「形態の専門家」であり,臨床家ではない。もちろん,解剖学を学ぶ多くの人々は臨床家であり,臨床に役立てるために解剖学を学ぶ。だが,解剖学を研究・教育する立場において重要なのは,構造を正確に知り,それを適切に言語化し,伝えることである。その「純・形態学者」としての立場こそが,研究者にとっては最も大切であると私は考えている。しかし同時に,そのような「純・形態学者」としての視点だけでは,臨床に直結する感覚とは乖離してしまうことも少なくない。
第二に,解剖学は総論から積み上げていく性質があるため,臨床で重要な局所解剖学に到達する前に,学ぶ意欲が途切れてしまう傾向にある。たとえば「腰痛の原因となりそうな構造を知りたい」と思い立って解剖学を学び始めても,「骨とは」「上皮組織とは」といった総論を学ぶうちに,最初の動機が薄れてしまうのである。
私は,伝統的な解剖学教育の方法に異を唱えるつもりはない。ただ,解剖学をひと通り理解しなければ,臨床家の疑問に十分に応えられないということを強調しておきたい。
この2つの課題を克服するべく,本書では項目ごとに臨床家とのディスカッションを挿入している。私が解説する解剖学が臨床でどのように活かされるのか,臨床家にとって「今」必要とされている解剖学は何かを掘り下げた「深掘りディスカッション」である。これにより,読者は単なる知識の習得にとどまらず,実践に結びつく視点を養うことができるだろう。
本書は,実際の解剖学講義の動画を文字起こししたものがベースとなっている。各章に挿入されている「深掘りディスカッション」は,臨床で活躍されているスペシャリストたちが講義動画を視聴したうえで,私とディスカッションした内容をもとに構成している。講義や対話の雰囲気をできるかぎり残した形で収載している。そのため,一般的な成書に見られるような箇条書きや整理された項目立ては,あまり用いていない。これは「語っていたことの面白さや熱量をそのまま伝えたい」という著者の思いによるものである。読者の皆様にもご理解いただければ幸いである。
また,本書の特色として,総論的内容の「第5章 臨床に活かせる解剖学とは?」をあえて巻末に置いている。まず,臨床に携わるセラピストが知りたい解剖学を提示し,そのうえでその根拠となる総論を必要に応じて参照できるようにした。この順序によって,学び始める段階から「解剖学で何が重要なのか」が見えてくることを意図した。「臨床に直結する形で解剖学を学んでほしい」という,著者の思いによるものである。
本書を手に取ったみなさまには,「形態」に真正面から向き合う楽しさと難しさを存分に味わっていただきたい。そして,構造を深く理解することが,最終的には患者さんのためになる「臨床力」の確かな基盤になることを,心から実感していただきたい。それが著者としての何よりの願いである。
本書の執筆にあたっては,私のもとで学んでくれた学生たちの鋭い質問や,「臨床ではこういう場面で困る」といった臨床家の率直な声が,大きな刺激となった。彼らの探究心と現場感覚が本書の随所に反映されていることを伝えておきたい。また,本書の構想段階から耳を傾け,出版に向けて多くの助言をくださった医学書院の金井真由子氏には深く感謝申し上げたい。
そして何より,静かに見守り,支え続けてくれた家族に,心から感謝の意を表したい。
2025年8月
荒川 高光
目次
開く
第1章 腰部・脊柱──腰痛の原因は腰部の構造にあるのか?
1 腰部・脊柱を構成する骨:脊椎
1 各椎骨には役割がある
2 前弯と後弯の役割は何か?
3 ポイントは「胸椎」を理解すること
4 腰椎の「肋骨突起」とは何か?
2 腰部・脊柱を支える靱帯
1 前縦靱帯
2 後縦靱帯
3 黄色靱帯
3 腰部・脊柱を支える関節
1 椎間関節
2 椎間円板
4 腰部・脊柱を動かす筋
1 脊柱起立筋は本当に「脊柱を起立させる筋」なのだろうか?
2 学名に惑わされるな!
3 横突棘筋の「法則」
5 腰部・脊柱を通る神経
1 腰痛の症状部位の「ずれ」とその範囲
2 殿部の皮神経
3 上殿皮神経分布域の痛みから,何が考えられるか?
4 中殿皮神経分布域の痛みから,何が考えられるか?
5 下殿皮神経分布域の痛みから,何が考えられるか?
6 坐骨神経と「坐骨神経痛」
第2章 股関節──「臼蓋」ってどこ?
1 股関節を構成する骨
1 寛骨は3つの骨からできている
2 閉鎖孔なのに閉鎖していない?
3 どこからどこまでが臼蓋なのか?
2 股関節を支える靱帯・関節包
1 靱帯の中を血管が通るの?
2 連続する構造たち
3 股関節を動かす筋
1 内寛骨筋=腸腰筋なのか?
2 iliocapsularisって何だ?
3 殿筋群
4 回旋筋群=深層六筋なのか?
5 股関節外側の筋群
6 内転筋群
4 股関節を通る神経
1 梨状筋付近の局所解剖
2 髄内釘の影響
第3章 膝関節──「脂肪体」は「脂肪組織」を指すのか?
1 膝関節を構成する骨
1 大腿骨下部の構造
2 不思議な膝蓋骨
3 脛骨
2 膝関節の構造
1 膝関節とは?
2 膝関節の補助装置:関節半月
3 膝関節を支える靱帯
1 「十字」に見えない「十字靱帯」?
2 内側側副靱帯と外側側副靱帯
3 斜膝窩靱帯
4 滑膜ヒダ
5 膝蓋下脂肪体
6 内側・外側膝蓋支帯
7 ALLの発見
4 膝関節を動かす筋
1 膝関節のメインの筋:大腿四頭筋
2 大腿後面の筋
3 ハムストリングスってまとめていいの?
4 鵞足:半腱様筋,縫工筋,薄筋
5 下腿後面の筋
5 膝関節を通る血管
1 内転筋管という長いトンネルを抜けると,そこは膝窩であった
2 膝関節を取り巻く動脈網と膝蓋下脂肪体
6 膝関節を通る神経
1 仙骨神経叢
第4章 足関節・足部──捻挫で損傷するのはどこ?
1 足関節・足部を構成する骨
1 手と同じところ・違うところ
2 足のアーチはどうやって支えているのか?
2 足関節・足部を支える靱帯
1 距腿関節と距骨前脂肪体の関係
2 距骨下関節と足根洞の関係
3 伸筋支帯と足根洞の関係
4 足根洞にある靱帯と筋
5 ショパール関節とリスフラン関節
3 足関節・足部を動かす筋
1 足背の筋
2 足底の筋
3 足部外側の筋
4 足部内側の筋
4 足関節・足部を通る血管
1 前脛骨動脈→足背動脈:どこからが足背動脈?
2 後脛骨動脈→内側・外側足底動脈:足根管と手根管の比較
3 固有底側趾動脈
5 足関節・足部を通る神経
1 伏在神経:足部との関連
2 浅・深腓骨神経:足背の皮神経の個体差
3 腓腹神経:外果後方・下方の枝
4 脛骨神経→内側・外側足底神経:足根管内の臨床
5 固有底側趾神経:変形時に痛む
第5章 臨床に活かせる解剖学とは?
1 関節の構造と靱帯について理解する
1 関節とは?
2 靱帯とは?
2 筋はどこに付着するのか?
1 ミクロからみた筋の付着
2 筋と密性結合組織
3 筋と骨膜
3 腱や付着部の形態を知ろう
1 腱-靱帯-骨膜は連続している
4 組織学を知ることが臨床への近道
1 組織学の概要
2 結合組織とは
5 治療対象は疎性結合組織
1 疼痛と可動域制限のメカニズム
2 末梢神経と血管
3 可動域制限と疼痛が同時に生じるのはなぜか?
6 筋膜ってなんだ?
1 筋膜を示せないのはなぜか?
2 すなわち「筋膜」とは何か?
索引
書評
開く
いったい私たちは臨床で何とどう闘っているのか?
書評者:小野 志操(なか整形外科京都西院リハビリテーションクリニック/理学療法士)
私が理学療法士として臨床で患者さんを診させていただく中で大切にしていることは,解剖学です。それは単に筋の起始・停止を知っているということではなく,軟部組織の構造と隣接組織との関係や付着部の構造を理解しておくということです。
私たち理学療法士は当然のことながら,解剖学的構造破綻を改善することはできません。しかしながら,理学療法により症状を改善させることは可能な場合が少なくありません。「いったい私たちは臨床で何とどう闘っている」のでしょうか?
整形外科疾患をはじめとする患者さんの多くは,「疼痛」と「可動域制限」を主訴として病院やクリニックに来院されます。何が痛いのか? そして,なぜ動かないのか? この疑問を解決するためには,ヒトの身体の構造である解剖の理解が欠かせないわけです。
これまでの解剖学書の多くは,解剖図や写真などが載せられているものの,この解剖の知識をどのように臨床で活用できるのかについては全く記述されていません。それは本書の中でも書かれているように,「解剖学」とは解剖をありのままに研究する「学問」だからに他なりません。
本書を読み進めていくことで,「臨床でどのように解剖学的知識を反映させることができるのか」について考えながら,臨床的解剖学思考を身につけることが可能です。
前述した通り,私は臨床で病態を解釈する上で,解剖学的知識が必須であると考えています。それは,長年の臨床経験に積み重ねや臨床研究を通して,少しずつ身につけてきた思考プロセスです。もし,本書が私の臨床1年目に存在していたら,もっと短い期間で現在の考え方に到達できたに違いないと感じます。
本書は単に解剖図や写真が載せられているのではなく,工藤慎太郎先生をはじめとするスペシャリストの先生方とのディスカッションを通して,「解剖」をどのように「臨床」に反映することができるのかについて考えることが可能となっています。
私個人としては,巻末の「第5章 臨床に活かせる解剖学とは?」に共感する部分が多かったです。臨床において本質的に大切なことがわかりやすく記載されています。「いったい私たちは臨床で何とどう闘うべきなのか?」という疑問を解き明かしてくれます。初学者はもちろん,臨床で活動している全ての療法士に読んでいただきたい一冊です。
“知の化学反応”が臨床を変える「対話型」解剖学書
書評者:黒田 良祐(神戸大大学院整形外科・教授)
本書は,解剖学者と理学療法士が真正面から向き合い,臨床の現場で本当に必要とされる知を磨き上げていく,極めてユニークで刺激的な一冊である。PT界を代表する解剖学エキスパートである荒川高光先生が,膨大な領域から“臨床で使える本質”を抽出して講義し,それに対して工藤慎太郎先生をはじめとした運動器理学療法のスペシャリストたちが,臨床の現場から生まれた鋭い疑問を容赦なく投げかける。
議論の中心には,筋・骨格・神経という構造の理解を,患者の症状や動きと結びつけて再解釈しようとする姿勢がある。トリガーポイントや疼痛発生機序といった,整形外科でも日常的に直面するテーマが深く掘り下げられ,臨床家が抱きがちな「この症状はどこから来ているのか?」という疑問が,対話のなかで徐々に解きほぐされていく。読者はそのプロセスを追体験することで,まるで自らがディスカッションに参加しているかのような臨場感を覚えるだろう。
整形外科医として本書を読むと,その価値は一段と明確になる。私たちが日々向き合う患者の訴えや動作異常は,画像に写る構造の異常だけでは説明できない複雑さを内包している。本書は,そうした“説明しきれない部分”を埋めるための視点を豊富に与えてくれる。筋・筋膜・神経といった要素を「機能的ユニット」としてとらえるアプローチは,触診や動作観察に直結し,診察の精度を高める極めて実践的な思考法である。特に若手医師にとっては,机上の解剖学と臨床所見が一本の線でつながる体験となり,診断プロセスそのものが大きく変わるはずだ。
本書のもう一つの魅力は,専門領域の異なる視点が交わることで生じる“知の化学反応”にある。解剖学者の理論的な視座と,理学療法士の臨床的・運動学的な視座がぶつかり合うことで,双方だけではたどり着けない新たな洞察が生まれていく。その熱量は,本書が単なる解説書ではなく,学際的な創発の場として機能していることを実感させる。
総じて本書は,臨床における解剖学の意味を再定義する一冊である。疾患を「構造の異常」としてとらえるだけでなく,「動きの破綻」として理解する視点を養うことは,今後の運動器診療の質を大きく左右する。本書はその視点を強固に支える教材であり,医師と理学療法士が共通言語をもって患者を理解するための貴重な架け橋となる。臨床解剖学が“今”必要とされる本質を体現した,まさにぞくぞくするほど刺激的な一冊である。
これが解剖学の本なのか?!(でも,おもしろい)
書評者:藤澤 宏幸(東北文化学園大学医療福祉学部長/一般社団法人日本理学療法学会連合理事長)
本書の第一印象は,“読み物として楽しい”である。それでいて解剖学の知識も整理される。しかも,解剖学者の生の声を聴くことができ,「専門家でも知らないことがあるんだ」と,読者は安心して学習を進められる気持ちになれる。
解剖学者の素朴な疑問を反映した各節のタイトルも楽しい。「脊柱起立筋は本当に『脊柱を起立させる筋』なのだろうか?(p.18)」などは,読み手の心を揺さぶるフレーズである。著者いわく,「腸肋筋,棘筋,最長筋の中で,横突起の後方に付着し,上下方向に収縮できるのは最長筋だけであり,それこそが脊柱起立筋といえる」,という。身体運動学を専門とする者からすれば,腸肋筋も左右が同時に求心性収縮すれば,体幹伸展を生じさせるので,重要な脊柱起立筋だと考えるが,解剖学者との見方の違いを知ることができ,それはそれで新鮮で面白い。
所々に出てくる語源も理解を深める手助けになるし,ユーモアも忘れていない。「大転子の語源は,trochanter(転がるもの)がそのまま『転がっている子ども』という意味で『大転子』となっている。Big angel(大天使)と答える学生もたまにいるが,そこに天使はいない(p.50)」などは,解剖学を学ぶ者たちへの愛情が溢れ出ている。
さて,本書の一番の特徴は,著者と運動器理学療法のエキスパートとの対話であろう。超音波画像装置を用いて,生体の内部を観察しながら臨床に取り組んでいる専門家とのやりとりは,解剖学を臨床に活かすための懸け橋になっている。第5章には「臨床に活かせる解剖学」として,そのまとめがしっかりとなされているのもありがたい。加えて,わからないことはわからないとしっかり記載されている点は,学問を究めた者だけが表明できる特権であり,逆に信頼できる。例えば,次のような記載がある。「表層の腰背腱膜から起こる多裂筋もあります。それは椎骨に起始していないので,何と呼称していいのかわからない(p.25)」。心の中で,“ええっ,そうなんですか!!”と叫びたくなる。交わされる会話にすっかり入り込んで,一緒に突っ込みながら読んでいる自分がいるのに気付く。特に,解剖学の知識をベースに,痛みの原因を深掘りしたい人にとって,本書は有益な情報が埋蔵されている宝の山のように感じられるのではないだろうか。
本書が,これまでの解剖学書にはない,非常に刺激的な内容であることは間違いない。そのなかで,著者へ要望するとすれば,比較解剖学的視点であろう。進化論の観点から,他の動物との差異について触れてもらえれば,さらに物語性のある解剖学として読者の心に刻まれるのではないだろうかと期待するものである。
本書は,初学者はもとより,日々悩みながら治療に向き合っている臨床家にこそ,手元に置いてもらいたい一冊である。