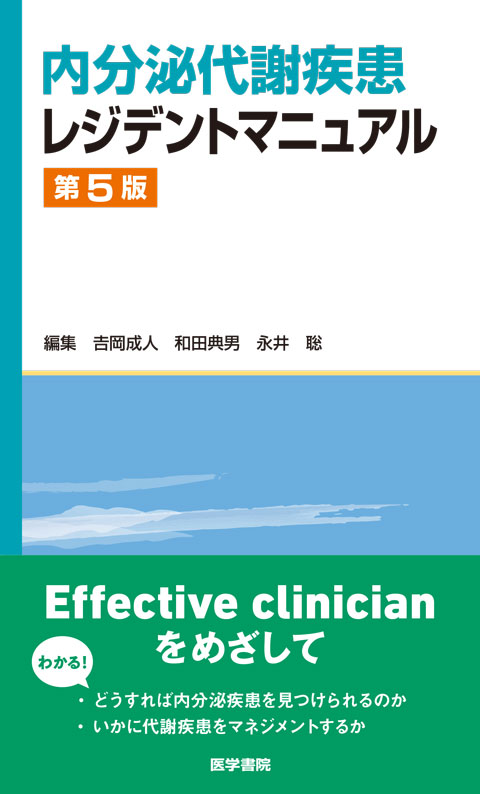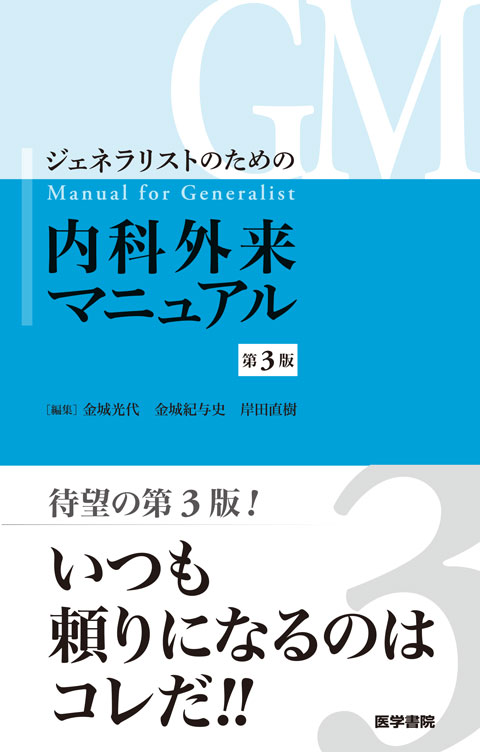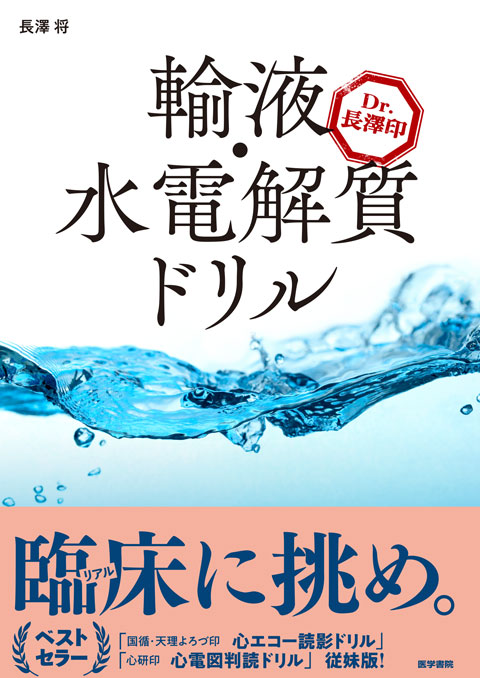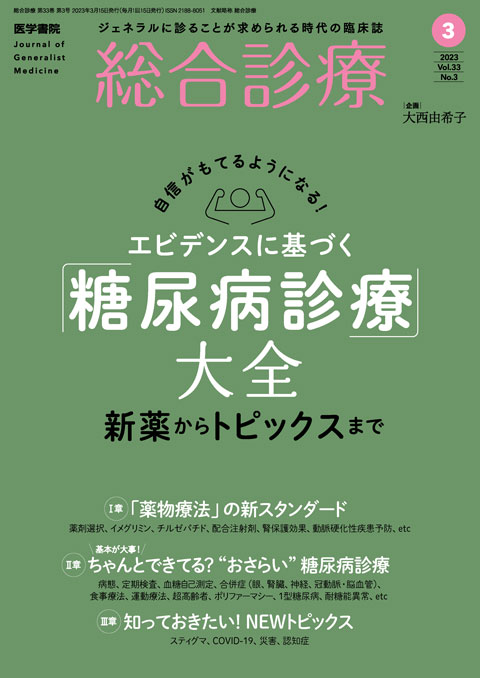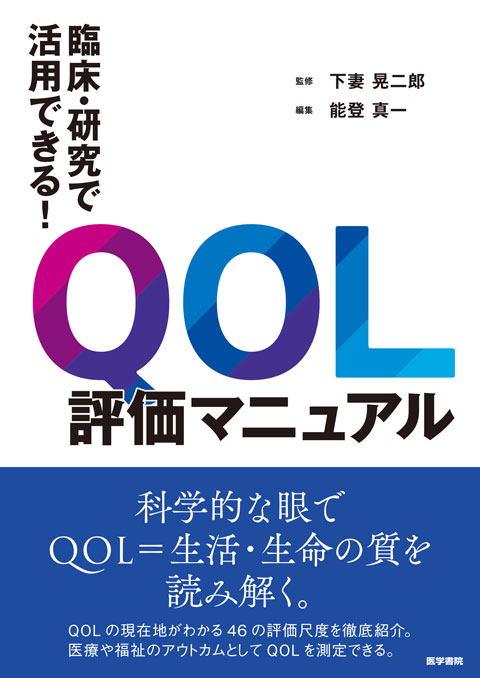内分泌代謝疾患レジデントマニュアル 第5版
Effective clinicianとして内分泌代謝疾患と並走する
もっと見る
数多い内分泌代謝疾患の中でも臨床的に重要な疾患を取り上げて解説する決定版。近年のトピックである免疫チェックポイント阻害薬をはじめとする「薬剤性の内分泌障害」および「電解質異常」については、今回新たに「日常診療のなかの内分泌代謝疾患」章を設けて、スッキリ解説する。各項の最初に、疾患を見逃さないためのチェックリストをまとめ、さらにわかりやすくなった。
| シリーズ | レジデントマニュアル |
|---|---|
| 編集 | 吉岡 成人 / 和田 典男 / 永井 聡 |
| 発行 | 2023年11月判型:B6変頁:432 |
| ISBN | 978-4-260-05272-6 |
| 定価 | 3,740円 (本体3,400円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
第5版の序
2000年に『内分泌代謝疾患レジデントマニュアル』の初版を上梓し,早いもので,四半世紀近くとなり,わたくし自身も医師として40年をこえる時を過ごしました.
40年前の内分泌学は,血中の各種ホルモンをラジオイムノアッセイで測定することがどうにかできるようになった時代です.CTスキャンの画像は粗雑で,小さな下垂体腫瘍は病変部位を特定できませんでした.糖尿病学についてもHbA1の測定が商業化されたばかりで,薬剤もインスリンの動物製剤とSU薬しかなく,網膜症による視力障害や末期腎不全によって透析にいたる患者さんが多くいらっしゃいました.脂質異常症を管理できる薬剤はありませんでした.しかし,いまは内分泌疾患や代謝疾患の多くを的確に診断し,適切な治療を行うことができます.
医学は進歩しましたが,医療の現場において医師と患者さんたちとのコミュニケーションが希薄になったことを実感しています.医師は電子カルテの画面を見て,検査データや画像所見の説明をしますが,患者さんを丁寧に診察し,言葉を交わすことが少なくなりました.
40年前の研修医は病歴の聴取,身体所見の観察が極めて重要であると教えられました.15人程度までは,受け持っている患者さんたちのプレゼンテーションを,検査成績を含めて診療記録を見ずに行うことが当然と受け止められていました.そのため,時間があれば,ベッドサイドに足を運び,患者さんの訴えに耳を傾け,聴診や触診の所見に変化がないかどうかを確認するようにしていました.Phillip A. Tumulty教授が執筆された『The Effective Clinician』という書籍の “臨床医にとっての重要な責務は診断や治療ではない(a clinician is not someone whose prime function is to diagnose or to cure illness,for in many cases,he is not able to accomplish either of these)” という記載に感銘を受けたのはその頃です.臨床医が行うべきことは “management of a sick person” だというのです.病歴,診察所見,検査成績を総合し,深い知識と数多くの臨床の経験をいかし,眼と耳と手と心を駆使して患者さんに誠意をもって語りかけることであるというのです.“effective”な臨床医への道のりは果てしなく遠いものです.
いまだに病む人への十分な対応ができていないわたくしですが,患者さんが不条理な差別や誤解を受け,強い憤りを覚えたことがあります.20年以上も前のことですが,ひとりの1型糖尿病の患者さんから電話がありました.「私,悔しい….市役所の面接で,糖尿病は生活習慣病で自己管理ができない人がなる病気だといわれた.低血糖をひきおこす危険な薬を1日に4回も注射しているなんて信じられない,あんたはきれいな顔をしているから,同じ糖尿病の男を見つけて結婚でもしたらいい…,といわれた」と.その時の憤りを朝日新聞の「声」というオピニオンフォーラムに投稿し,記事を目にした患者さんから「ありがとう,先生」という言葉をいただきましたが,その程度のことしかできない自分自身に不甲斐なさを感じました.
最近になってスティグマ,アドボカシーということが声高に叫ばれています.ごくごく当たり前のことですが,何気なく使っている「ことば」に対しても慎重な姿勢がのぞまれています.今回の改訂にあたっては,本書でも「ことば」に注意し,また多くの若い執筆者を新たに加えて,内容もアップデートするようにしました.書籍が読まれない,売れない時代ではありますが,本書を手にとっていただけると執筆者の内分泌疾患や代謝疾患に対する「思い」が伝わるのではないかと思います.
外界から身を守り,内部の恒常性を維持することでわたしたちは毎日を過ごしています.免疫とホメオスターシスは生命を維持するための重要なメカニズムです.ぜひ,内分泌代謝学を,免疫とホメオスターシスという観点からしっかりと眺めてください.1人ひとりの患者さんたち,1つひとつの検査データがいとおしいものと思われてくると思います.
2023年6月
筆者を代表して
𠮷岡成人
目次
開く
本領域で使用される略語一覧
I章 日常診療のなかの内分泌代謝疾患
1 電解質異常
1.低ナトリウム血症
2.高ナトリウム血症
3.低カリウム血症
4.高カリウム血症
5.低カルシウム血症
6.高カルシウム血症
7.低リン血症
8.高リン血症
9.低マグネシウム血症
10.高マグネシウム血症
2 薬剤と内分泌代謝疾患
1.免疫チェックポイント阻害薬
2.副腎皮質ステロイド薬
3.免疫抑制薬とインターフェロン
4.抗不整脈薬
5.抗精神病薬
II章 内分泌疾患
内分泌疾患を見逃さないために
内分泌機能検査
1 下垂体疾患
下垂体疾患を見逃さないためのチェックリスト
1.下垂体前葉機能低下症
2.先端巨大症,下垂体性巨人症
3.クッシング病
4.プロラクチノーマ
5.バソプレシン分泌低下症(中枢性尿崩症)
6.バソプレシン分泌過剰症
2 甲状腺疾患
甲状腺疾患を見逃さないためのチェックリスト
1.バセドウ(グレーブス)病
2.慢性甲状腺炎(橋本病)
3.甲状腺機能低下症
4.粘液水腫性昏睡
5.亜急性甲状腺炎
6.甲状腺結節
7.甲状腺クリーゼ
3 副腎疾患
副腎疾患を見逃さないためのチェックリスト
1.アジソン病
2.クッシング症候群
3.原発性アルドステロン症
4.褐色細胞腫
5.副腎インシデンタローマ
6.急性副腎不全(副腎クリーゼ)
4 副甲状腺疾患
副甲状腺疾患を見逃さないためのチェックリスト
1.副甲状腺機能低下症
2.原発性副甲状腺機能亢進症
3.悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症
4.高カルシウム血症クリーゼ
5 膵内分泌疾患
膵内分泌疾患を見逃さないためのチェックリスト
1.インスリノーマ
6 性腺疾患
性腺疾患を見逃さないためのチェックリスト
1.男性性腺機能低下症
2.女性性腺機能低下症
III章 糖尿病
高血糖の鑑別のためのチェックリスト
代謝疾患の診療──検査値を診療にフィードバックする
1 糖尿病の診断
2 糖尿病の治療
1.糖尿病を治療するときに考えること──個別化,スティグマへの配慮
2.代謝指標としての血糖マネジメント──低血糖のリスクを勘案して
3.血糖マネジメントに有用な食事と運動
4.2型糖尿病における血糖マネジメント
A 治療のアルゴリズムと経口血糖降下薬の使い方
B 2型糖尿病における注射薬の使い方
5.1型糖尿病における血糖マネジメント
6.糖尿病の合併症と併発症
7.さまざまな病態における糖尿病への対応
A 糖尿病の緊急症
B 低血糖
C 薬物性高血糖
D 薬物性低血糖
E 周術期
F 妊娠糖尿病
IV章 代謝疾患
1 脂質異常症
脂質異常症の鑑別のためのチェックリスト
2 高尿酸血症,痛風
高尿酸血症の鑑別のためのチェックリスト
3 肥満とメタボリックシンドローム
4 骨粗鬆症
索引
書評
開く
領域を超えた臨床能力の底上げに
書評者:大塚 文男(岡山大学術研究院教授・総合内科学)
内分泌代謝領域は,医学生やレジデントにとって,いつも苦手とされる分野の一つである。一方で,私のようにこの領域が学生時代から好きなレジデントも居り,本書のようなマニュアルを読むと今でもワクワクする。内分泌代謝の診療では,医学生・初期研修医から基本領域専攻医では日常診療に潜む内分泌疾患を見逃さないようにいかにアンテナを高くするかがポイントだが,内分泌代謝専攻医にとっては甲状腺疾患・副腎疾患・下垂体疾患・性腺疾患など数々の病態への診断・治療から,常に遭遇している糖尿病診療の実践・応用まで,多くのハードルがあり,すぐに使えるわかりやすいマニュアルが必携といえる。
われわれの教室では,内科・総合診療専攻医と内分泌代謝専攻医の両者が今まさに研さんしており,初学者から専門医までの視点で,教室員で楽しく読ませていただいた。まず全体を眺めるとレジデントが内分泌代謝診療において比較的遭遇しやすい病態がピックアップされており,それぞれの内容が過不足なく簡潔に載っていることに気付く。さらに多岐にわたる疾患でも,それぞれの情報にアクセスしやすい構成となっている。見逃さないためのチェックリスト,内分泌検査の解釈,そして合併症や治療まで,処方例も交えて詳細に記述されていることから,今すぐ知りたいことにたどりつきやすい即戦力となるような工夫がみられる。
さらに読み応えある「症例」や「Side memo」も,ほぼ全てがこの度アップデートされていることに驚く。「症例」には実臨床で遭遇しやすいケースが記載されており,臨床場面を具体的にイメージしながら読み進めることができ,「Side memo」には最新のトピックスもしっかり記載されている。医学生やレジデントが勉強を始めるのにはもちろん,指導する側の知識の整理にも役立つ内容である。この6年間でアップデートされてきた薬剤,診療ガイドライン,スティグマやアドボカシーといった医学的トピックスについても,本マニュアルで触れていることは特筆すべきである。
ITによる用語検索が普及している昨今,初版から数えること四半世紀の長きにわたり本書が改訂され第5版の改訂までに至ったことは,内分泌代謝領域を学ぶ専攻医や若手医師にとって愛され信頼されている証しであろう。初学者向けの入門的な要素と,専門医からベテラン向けの診断・治療のアップデートの両者の視点から,本書はなかなかの優れものである。“レジデント”マニュアルではあるが,鑑別や診断に必要な検査,具体的な処方や経過についても記載され,診療を始めたばかりの研修医からベテラン医師・専門医まで,幅広く使える一冊である。加えて執筆された医師の声も盛り込まれ,マニュアルを超えて読みものとしてもワクワクしながら勉強できる。
本書に記載されていることを吸収していくと,領域を超えた臨床能力の底上げになることは間違いないだろう。レジデントが勉強を始めるのにはもちろん,指導する側の知識の整理にも役立つ本書,ぜひ皆さんの外来・病棟にも置いていただきたい。