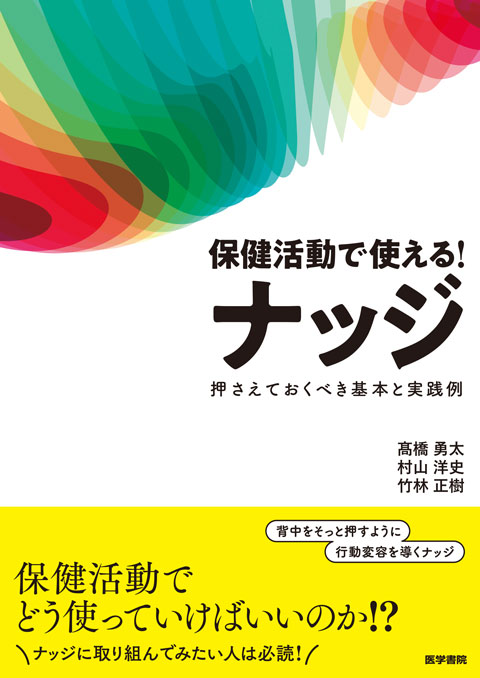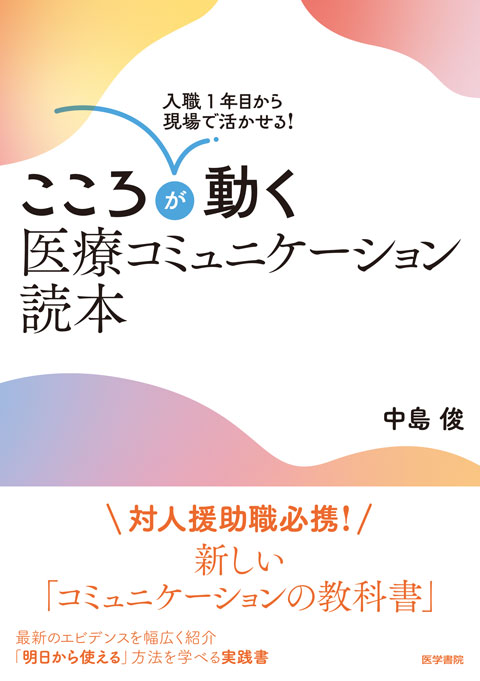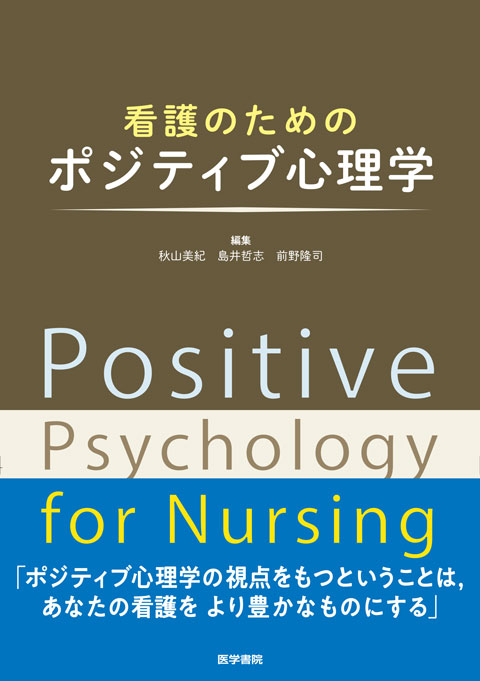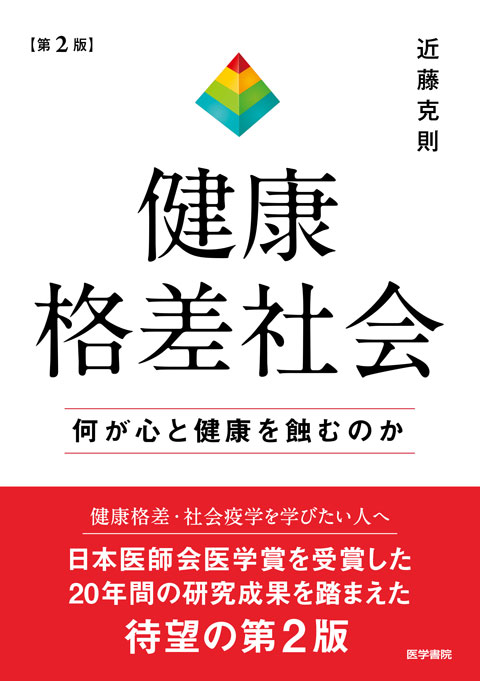保健活動で使える! ナッジ
押さえておくべき基本と実践例
保健活動でナッジに取り組みたい人は必読!その基本とポイントを実践事例とともに解説
もっと見る
人の心理特性に寄り添って、科学的に行動変容を促すアプローチである「ナッジ」。「ナッジ」を保健活動に活用できるように、バイアスやナッジ活用ツールである「EAST」など、押さえておくべきナッジの基本的知識を解説する。さらに、業務や事業にナッジを取り入れる際の具体的な方法やポイントを、保健事業における「ナッジ」の具体的な活用事例の紹介やQ&Aで解説する。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
「閉じこもりの高齢者がサロンに参加するには?」「がん検診の受診者を増やすには?」「健康教室の参加者を増やすには?」──これらは保健活動の中で,誰もが感じたことのある課題ではないでしょうか。
これらの課題の解決策の一つとして,世界的に注目されているのが「ナッジ」です。ナッジとは,人の行動を望ましい方向にそっと後押しする手法で,この理論的な背景にあるのが行動経済学です。
行動経済学は,時に面倒なことを先延ばしにしたり,時に忘れてしまったりする,“ありのままの人”に対して,どうしたら望ましい行動を取ってもらえるのかを研究対象として扱います。ナッジの提唱者,リチャード・セイラーが2017(平成29)年にノーベル経済学賞を受賞したこともあり,ナッジが急激に広まっています。皆様もナッジを耳にする機会が増えたのではないでしょうか。
私がナッジと出会ったのは2018(平成30)年です。ナッジを知れば知るほど保健活動との相性の良さに気付かされました。
保健師は,ゆりかごから墓場までと言われるように,一生のあらゆる場面において,人々の健康に関わります。そして,そのアプローチは,個・集団・地域への支援,施策化などさまざまです。これらの活動に共通するのは,保健活動の重要な柱である「予防」です。予防は一人一人の行動に委ねられていることから,その行動をそっと後押しするナッジを知ることは,予防行動の促進をより効果的に行うことにほかなりません。ナッジは目新しいものばかりでなく,今までも部分的に実践されているものが多くあります。これらの断片的な経験値を科学的にまとめ,実践的なツールとして活用できるところがナッジの特徴です。
本書は,現場の保健師である私(髙橋),公衆衛生学の専門家である村山洋史先生,行動経済学の専門家である竹林正樹先生の三人で執筆しました。私たちの思いは,全国で働く約55,600人の保健師のうち一人でも多くがナッジを知ることで,今よりも良い保健活動ができ,その結果一人でも多くの人が幸せに生活できる社会を実現することです。
本書は保健師向けではありますが,医療・保健・福祉の分野に携わる多様な専門職,そして事務職にも役に立つと信じています。それは,どのような職種であっても,対象は「ありのままの人間」だからです。ナッジはとてもユニークです。そして,ナッジを学ぶことで,人の特性を深く知ることができます。本書を通じて,皆様の日々の仕事が少しでも楽しくなることを願っています。
2023年6月 著者を代表して
髙橋 勇太
目次
開く
はじめに
著者紹介
第1章 なぜ,今ナッジなのか?
そもそもナッジとは?
分かっていてもそれができない人を,後押しする
ナッジで「介入のはしご」がつながる
「介入のはしご」におけるナッジの位置付け
ナッジによる介入のポイント
ナッジ活用のメリット
行動変容へのアプローチの幅が広がる
エビデンスに基づく政策立案とマッチしている
日々の仕事が充実し,楽しくなる
公衆衛生行政におけるナッジの可能性
現場にこそナッジを
第2章 意思決定には癖がある
直感に訴える健康情報
2つの思考モード「直感的で速い思考」と「理性的で遅い思考」
認知バイアスの特性
①損失を嫌う(損失回避バイアス)
②現状維持を好む(現状維持バイアス)
③現在の快楽を重視する(現在バイアス)
④手近なヒントに頼ってしまう(ヒューリスティクス)
⑤大量の情報がベストとは限らない(情報・選択過剰負荷)
⑥今のままが続くと考えてしまう(投影バイアス)
⑦自分に都合の良い情報ばかりを集めてしまう(確証バイアス)
⑧非常時でも正常時と変わらないと考えてしまう(正常性バイアス)
⑨「自分は例外」と楽観視してしまう(楽観性バイアス)
⑩人と同じ行動をしたくなる(同調バイアス)
認知バイアスは必ずしも悪者ではない
認知バイアスを踏まえた介入がナッジ
①シートベルト装着促進のナッジ
②がん検診の勧奨にナッジを活かす
第3章 ナッジを活用するポイントは?
ナッジ実践の枠組み,EAST
Easy(簡単に)
E-1 デフォルト機能を活用する
E-2 面倒な要因を減少させる
E-3 メッセージを単純化する
Attractive(印象的に)
A-1 関心を引く
A-2 動機付け設計を行う
Social(社会的に)
S-1 社会規範を示す
S-2 つながりを活用する
S-3 コミットメントを促す
Timely(タイムリーに)
T-1 タイミングを見極める
T-2 現在バイアスを踏まえる
T-3 事前に対処行動を決めるよう促す
EAST活用の4ステップ
行動プロセスマップで課題や介入のポイントを明確にする
行動プロセスマップの作成で阻害要因に気付く
ナッジを実践する上でのポイント
ナッジは万能ではない
Check(介入の有無別の比較評価)を必ず行う
倫理面に配慮する
第4章 ナッジの実践事例を教えて
実践事例①:特定保健指導案内封筒の開封率向上
実践事例②:ナッジで手指消毒促進
介入と効果測定方法
結果
実践事例③:ナッジメッセージによる高齢期の社会参加活動意向の促進
対象と調査方法
結果
第5章 効果評価はどうしたら良いの?
なぜ効果を評価する必要があるのか
①より良いナッジを考えることができる
②職場や住民にナッジの意義を理解してもらいやすい
③ナッジを継続すべきかを検討できる
評価指標:大事なのは「何を評価するか」
研究デザイン:適切な比較相手を設定する
評価する上でのポイント
代表的な研究デザイン
統計解析:感覚では数値は評価できない
Q&A 評価に関する疑問にお答えします!
アウトカムの設定
研究デザイン
統計解析
実践事例から効果評価の方法を学ぶ
検証方法
結果
担当者のコメント
第6章 弱点を知った上でナッジを使う
ナッジの限界
①ターゲットとする行動によって利き方が違う
②ほかの研究事例と同じ効果が出るとは限らない
③長期的効果までは見込めない可能性がある
改めて,エビデンスは大切
ナッジの失敗事例
ありふれたイラスト
ネガティブな同調効果
メッセージ疲労
思いがけない作用
盛り込み過ぎたナッジ
アイデア偏重
第7章 保健活動におけるナッジの現状と未来
ナッジを巡る世界と日本の動向
ナッジに関する研究の動向
ナッジのポイント
先行研究の検討を入念に
長期的な行動変容の場合は,ほかの介入との組み合わせを
効果評価とそれに見合った設計を
効果的なナッジの実践には対象の理解が重要
ナッジの未来
これからナッジを活用される方々へ
あとがき
索引
コラム
コラム1 YBiTとは
コラム2 システム1の特徴
コラム3 読者からの質問コーナー①
コラム4 よくあるEASTの質問
コラム5 アンケート調査と倫理
コラム6 読者からの質問コーナー②
コラム7 読者からの質問コーナー③
コラム8 ナッジ活用の傾向
コラム9 ナッジを学びたい人へ
事例
事例1 ベジ・ファーストをデフォルトに
事例2 トイレットペーパーホルダーを活用した大腸がん検診の啓発
事例3 英国での大規模な減塩ナッジ
事例4 災害時保健活動での引き継ぎへの活用
事例5 動作指示の明確化で受診率向上
事例6 手書き付箋を付けて,アンケート回答率アップ
事例7 損失回避バイアスに着目した大腸がん検診受診率向上策
事例8 罰則が逆効果だった保育園の遅刻防止
事例9 英国の抗菌薬の過剰処方対策
事例10 禁煙ダービーで禁煙促進
事例11 予約の無断キャンセルを減らした病院
事例12 空港での受動喫煙防止策
事例13 締め切り設定の違いによる先延ばし防止効果
書評
開く
「自然に健康になれる環境づくり」を目指す全ての人に
書評者:近藤 尚己(京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻教授)
健康日本21(第3次)では「自然に健康になれる環境づくりの取り組みを実施し、健康に関心の薄い者を含む幅広い対象に向けた健康づくりを推進する」ことが確認された。この「自然に健康になれる環境づくり」に必須の知識と技術が「ナッジ」と言っていいだろう。
今やビジネスも行政の現場も「ナッジ祭り」の様相を呈しているので、今更「ナッジとは」と解説する必要はないかもしれない。とはいえ、日々の活動の中で「ナッジを十分に活用できています!」と胸を張って答えられる人はどのくらいいるだろうか。また、「EASTやMINDSPACEの意味、ばっちりです!」「健診受診勧奨や効果的な特定保健指導での活用法の事例を知ってます!」と言える人はどれくらいいるだろうか。
これらの問いのうち一つにでも自信を持って「はい」と言えなければ(私も自信はない)、本書はぜひ購入すべき一冊だ。
購入したら、書棚にしまうのではなく、たくさんの付箋をつけて仕事カバンに常に携帯してさまざまな場面でボロボロになるまで使ってほしい。
例えば、来年度の事業の企画会議の場。「第3章 ナッジを活用するポイントは?」や「第4章 ナッジの実践例を教えて」をさっと開いて、EASTに基づきナッジの要素を盛り込めないかを検討してみてほしい。
考案したナッジの取り組みに本当に効果があるのか疑問を持ったら「第6章 弱点を知った上でナッジを使う」を読み返してみるといいだろう。豊富な失敗例とともにナッジの弱点や注意点が示されているので、自身のアイデアの弱点を検討する際に役立つはずだ。
ナッジを活用した事業を考案した後は、「第5章 効果評価はどうしたら良いの?」を読んでほしい。保健事業のPDCAを回すために必須の評価の基本事項や、事業を評価するための具体的な手法が平易な言葉で解説されている。
考案した事業を上司や周囲の仲間に説明する必要がある人は、「第2章 意思決定には癖がある」をさっとおさらいして、ナッジの基盤となっている行動経済学や認知科学の基本事項を確認しておこう。とてもスマートな解説ができるだけでなく、「知恵者」として周囲からの評価が一段階アップすることと思う。
ナッジは「やさしさ」でできている。「わかっちゃいるけどできない」「ついついやってしまう」といった、一見ダメな私たちの行動のクセを正面から受け止めた上で「大丈夫だよ、ありのままに生きていれば自然に健康になれるんだよ」というメッセージを投げかけるのが、ナッジだ。パブリックヘルスは環境づくり。本書を活用する人が増えて、ナッジを存分に活用した、誰もが自然と健康になれるやさしい社会が進んでほしい。
(「保健師ジャーナル」Vol.79 No.6 掲載)