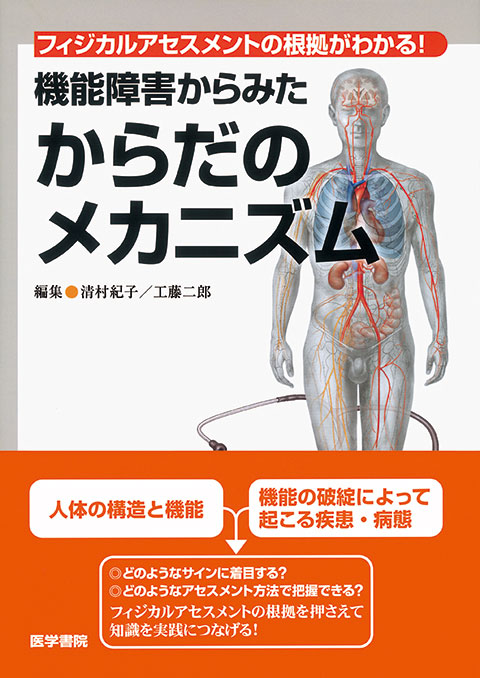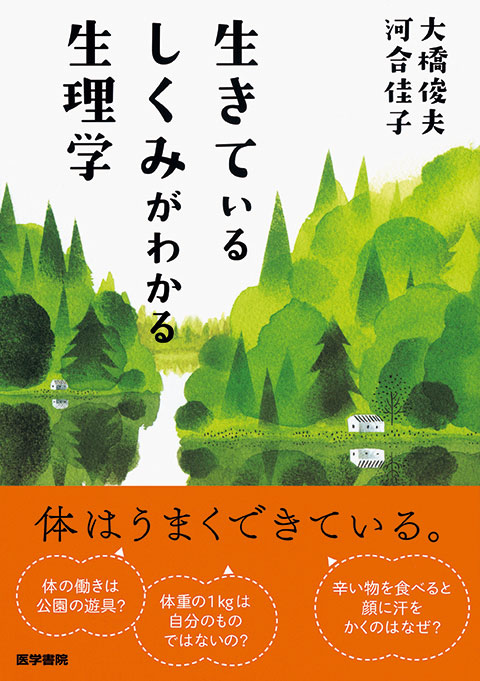疾病のなりたちと回復の促進[2]
病態生理学 第3版
もっと見る
- 本書は、人体の正常な構造と機能を学ぶ「解剖生理学」に対して、その破綻により症状や疾病が引きおこされる経過をしっかりと理解し、臨床に活用するためのテキストです。
- 分かりやすい本文とともに模式図を多用し、正常機能が破綻して異常があらわれるまでの過程が、段階を追って理解できるよう、工夫しました。
- 第1章では、循環障害や炎症など、症状や疾病の病態生理を理解するうえで必要な知識を簡潔にまとめてあります。
- 第2~13章は、生理機能ごとに章立てし、正常機能を簡単に復習したうえで、機能や構造が破綻することによりおこる症状や疾病について解説しています。
- 「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 系統看護学講座-専門基礎分野 |
|---|---|
| 執筆 | 土居 健太郎 |
| 発行 | 2023年02月判型:B5頁:328 |
| ISBN | 978-4-260-05019-7 |
| 定価 | 2,640円 (本体2,400円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はしがき
本書は,患者の健康・命と誰よりも一番関わることになる「看護師」を目指す皆さんに,体の変化に気づき考えるヒントになるように書きました。看護の“看る(みる)”という字は手で見るという意味を持ちます。患者に触れ,観察することで,体の変化を捉えることができ,そしてそのことにより患者はとても安心します。
皆さんは「近代看護の祖」とされるフローレンス=ナイチンゲールをご存じだと思います。ナイチンゲールはクリミア戦争に従軍し,戦争で負傷した軍人を収容する野戦病院で献身的な看護にあたりました。ナイチンゲールが野戦病院に赴任したとき,その病院に収容された傷病兵の死亡率は40%以上だったのです。その中でナイチンゲールは死亡率の高さの原因が,病院の衛生状態のわるさであることに気づき,環境を改善することで,最終的には死亡率が数%まで激減したと言われています。皆さんは,患者にとって最も近くにいる医療者になるのです。患者の肌に触れ,看て,聴いて,その小さな徴候に気づくためには,「正常な状態」と「病気の状態」の2つについて知識を持ち,理解し,今,目の前の患者の体で起こっていることが,どちらであるのかを見極めていく必要があります。この体の変化のスピードは日々変わるものから年余にわたって変わっていくものがあります。それを概念として身につけて,これからの医療の世界で活躍する看護師になってほしいと願っています。
ここで,この本が扱う「病態生理学」について触れたいと思います。皆さんは「病態生理学」を学ぶ前に,専門基礎分野の「解剖生理学」などを習得されていると思います。また専門基礎分野が終われば専門分野の成人看護学を習得されます。この専門基礎分野の知識を礎に専門分野で学ぶ疾患を有機的に理解するための分野が「病態生理学」といえます。これまでにない高度で専門的な医療が展開される中,看護師となる皆さんには豊富な知識と技術に基づき,適切なアセスメントが求められるとともに,新しい状況に対しては,これまで培ってきた経験と知識を駆使して,柔軟に対応する能力が求められます。
2019年12月に中国の武漢で発生した新型コロナウイルスによる感染症は,瞬く間に世界中に流行し,日本には2020年1月に上陸,3月には欧米や中東など世界各地に飛び火しました。そして世界保健機関(WHO)は,パンデミックの状況であると発表しました。私自身も2020年4月から臨床現場で新型コロナウイルス感染症に関わることとなりましたが,当初は対処方法や治療方法などはまったくの手探りの状態でした。このような未知のウイルスに対して最前線で医療にあたってくれたのは,紛れもなく若手の医師たちと看護師の皆さんでした。教科書に載っていない疾患の患者が目の前にいて,症状や徴候がある場合,これをどう解釈するのか。あるいは自分自身に現れる症状や徴候が,新型コロナウイルス感染症と関係するのか,関係ないのか。自分たちの持っている知識と経験から判断していくしかありません。
今では,新型コロナウイルス感染症による味覚異常や嗅覚異常は既知のことですが,当初はよく知られておらず,そのような中で,まずはじめにその症状に気がついたのは,最前線の看護師です。体に起こる変化には未知のものがあるかもしれないため,専門基礎分野の知識と深い理解が必要となってくるわけです。人が病気になったとき,身体機能がどのような状態になっているのか,また異常を起こしている原因はなんなのかといったことが病態生理とよばれ,それを理解することが本書の目的です。看護を行う上で,病態生理を知っていれば,その疾患の患者の身体にどのようなことが起こっているのか,そして今後どのようなことが起こるのかがイメージでき,どのようなケアが必要になるのかがわかります。そのため,病態生理学を深く理解することは,臨床の中の様々な場面で活きてきます。
今回の改訂においては,身体の正常な機能と,それが破綻することによる病態を理解できるように,各器官系統を概説し,とくに臨床現場で多く遭遇する疾患の病態生理についての記載に力を注ぎました。例えば,誤嚥性肺炎は高齢者の死因の上位であり,かつ臨床現場でよく経験する疾患です。そこで,食物の摂取に関わる口腔の働き,嚥下に関する内容を充実させました。また近年,死因として増えている老衰に関しても,老化現象を理解できるように工夫しました。このように本書は,臨床で看護師が必ず直面する患者の病態生理が理解できる教科書を意図しています。さまざまな症状・徴候を呈する患者に対して,科学的知識と経験に基づいた的確な看護を行うことができるように,そしてなにか施すことができなくても,その病態を理解することによって,精神的にも寄り添うことができるように,病態生理学の知識を学んでほしいと願っています。
本書が病態生理学をこれから学ぼうとする看護学生の皆さんや,卒後しばらく経過して新しい知識を吸収したい看護師の方々のお役に立つことを願ってやみません。
2022年11月
土居健太郎
目次
開く
第1章 病態生理学を学ぶための基礎知識
A 正常と病気の状態
B 細胞・組織の障害
C 循環障害
D 感染症
E 腫瘍
F 先天異常と遺伝性疾患
G 老化と死
第2章 皮膚・体温調節のしくみと病態生理
A 皮膚の生体防御のしくみとその障害
B 体温調節のしくみとその障害
第3章 免疫のしくみと病態生理
A 免疫のしくみ
B 免疫反応の低下
C 免疫反応の過剰
第4章 体液調節のしくみと病態生理
A 体液・電解質の調節とその異常
B 酸・塩基平衡のしくみとその異常
第5章 血液のしくみと病態生理
A 骨髄の機能とその障害
B 赤血球の機能とその障害
C 白血球の機能とその障害
D 血小板と出血傾向
第6章 循環のしくみと病態生理
A 心臓のポンプ機能と病態生理
B 血圧調節と末梢循環のしくみと病態生理
第7章 呼吸のしくみと病態生理
A 呼吸器の構造と機能
B 呼吸困難と呼吸不全
C 呼吸器系の防御機構の障害
D 換気の障害
E ガスの拡散障害
F 肺の腫瘍による障害
G 肺循環の障害
H 呼吸調節の障害
第8章 消化・吸収のしくみと病態生理
A 消化管の構造と機能
B 摂食・咀嚼・嚥下の異常
C 消化・吸収における障害
D 肝臓・胆囊の機能とその障害
E 膵臓の機能とその障害
F 腹膜・腹膜腔・腸間膜の機能とその障害
第9章 腎・泌尿器のしくみと病態生理
A 腎臓の構造と機能
B 腎機能の障害
C 泌尿器のしくみと病態生理
第10章 内分泌・代謝のしくみと病態生理
A 内分泌のしくみとその異常
B 糖代謝とその異常
C 脂質代謝とその異常
D 尿酸代謝とその異常
E 骨の代謝とその異常
第11章 生殖のしくみと病態生理
A 女性生殖器の機能とその異常
B 男性生殖器の機能とその異常
第12章 脳・神経,筋のはたらきと病態生理
A 脳・神経,筋の機能
B 脳循環のしくみとその障害
C 髄膜・髄液のはたらきとその障害
D 脳腫瘍
E 脊髄の障害
F 頭痛
G 意識と認知の障害
H 睡眠障害
I 運動制御のしくみとその障害
J 筋収縮のしくみとその障害
第13章 感覚器のはたらきと病態生理
A 視覚器の機能とその異常
B 聴覚器の機能とその異常
C 味覚とその異常
D 嗅覚とその異常
E 皮膚感覚とその異常
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
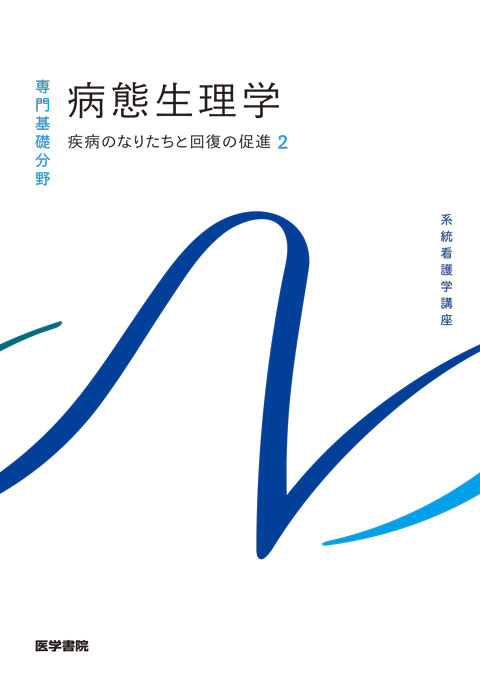
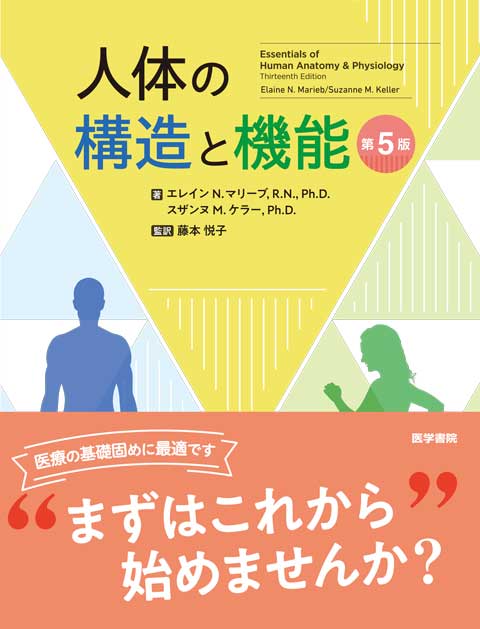
![イラストでまなぶ生理学[Web講義動画付] 第4版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8016/9448/0852/112232.jpg)