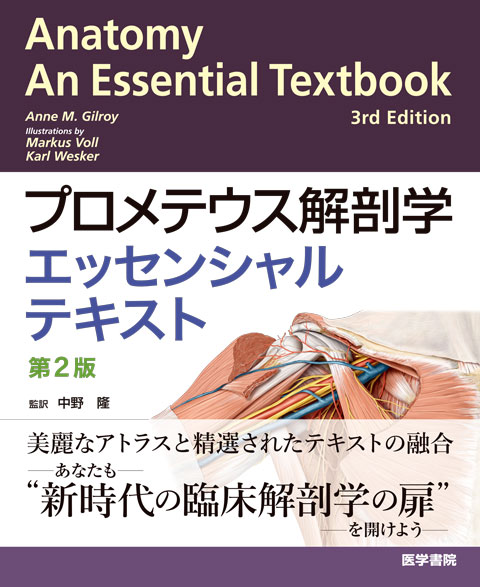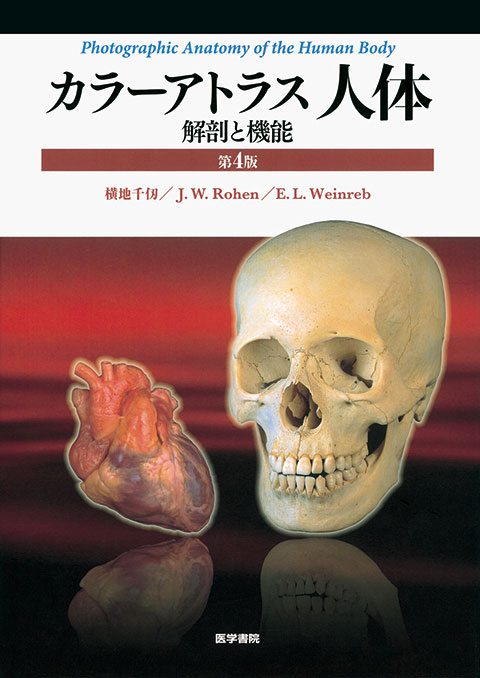人体の構造と機能 第5版
膨大な解剖・生理にはまずこの一冊で筋道を立てよう
もっと見る
解剖と生理を概観し、基礎知識を身につけるのにうってつけの定番書の新版。学習すべき内容を章のはじめに簡潔にまとめ、各節にも『学習目標』を掲げることで、学びやすさ・読みやすさを向上。さらに理解しやすいよう、図版も適宜アップデートされている。膨大な学習分量に圧倒されがちな解剖・生理のまず学んでおきたい基盤を習得するのに、手にとって損はない間違いのない一冊である。
| 著 | エレイン N. マリーブ / スザンヌ M. ケラー |
|---|---|
| 監訳 | 藤本 悦子 |
| 発行 | 2025年03月判型:A4変頁:672 |
| ISBN | 978-4-260-05713-4 |
| 定価 | 5,830円 (本体5,300円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
監訳者まえがき
私は薬学部を卒業しておりますが,神戸大学医学部解剖学講座に所属し,20年あまり医学生への教育に携わって参りました.その後看護師の免許を取得して,今は看護学生への教育に従事するようになっております.実は看護の教育機関に異動したときに途方に暮れたことがあります.それは医学教育では解剖学がおよそ32単位もあったものが,看護教育では一挙に4単位近くにまでに減ってしまったことです.当然,看護に密着した要領の良い解剖生理学教育が強く求められることになりました.そこで,さまざまな教科書にあたり,内容を精査しましたが,残念ながらそのほとんどは医学教育のダイジェスト版でした.これでは解剖生理学は言葉の羅列となり,看護学生には不全感だけが残ります.その結果として,学生は解剖生理学を「最も嫌いな学問」として捉えていることがわかってきました.解剖生理学と看護実践が完全に乖離していることも気がかりでした.
では「看護に密着した」というのはいったいどのようなものか,看護実践の場ではどのようなものが必要なのか? この命題をいつも念頭において教育内容を構築することを試みております.今なお道半ばといったところですが,2014年に日本解剖学会全国学術集会シンポジウムで,「看護学における解剖・生理学教育の現状と課題」というテーマで教育者の方々に問題を投げかけてみました.これに関しては,非常に多くの方から反響があり,大変苦労されていることを見て取ることができました.つまり,解剖生理学はたいていの場合医師が担当していましたが,看護にとって何が重要で,時間配分からどのように内容を取捨選択すればいいかわからなかったのではないかと思います.
そんな折,本書に出合いました.解剖学と生理学がわかりやすく融合し,しかもそれが端的な図譜で説明されていること,生化学や臨床的知見も駆使して書かれていることに驚いたことを覚えております.また言葉の羅列ではなく,物語を読むような説明文も楽しいところです.ただ,それでも時間的には足りないと感じています.看護界でもその指摘があり,先のカリキュラム改正(第5次)では解剖生理学が1単位増やされました.また,私はフィジカルアセスメントも担当しておりますが,フィジカルアセスメントは私が看護学教育を受けたときにはまだなく,新たに創設された看護の教育領域です.幸いなことに多くの時間が割り当てられています.フィジカルアセスメントは決して手順だけを習得するものではなく,解剖生理学の理解に立脚して初めて成り立つものです.つまり解剖生理学として割り当てられた4~5単位の中で教育を完結する必要はなく,臨床への橋渡しという観点から,フィジカルアセスメント教育において解剖生理学の理解をさらに深めることが可能になっていると思います.
解剖生理学の教育は大まかに言って1年次,フィジカルアセスメントは2年次に実施されます.まず,これから始まるすべての看護教育において解剖生理学が基礎にあることを踏まえて,学生の皆さんには本書を用いて1年次にはダイジェスト版ではない人体の構造と機能をしっかりと学習されることを望んでいます.言い換えると,これができれば,次のステップに容易に進むことができ,学習法としては得策だと思います.つまり,あとの学習が楽になるかどうかの分岐点であると考えています.
またフィジカルアセスメントは大学院の専門看護師(CNS)コースでも必修であり,本書はそのような場合にも,なぜそのような方法でアセスメントしていくのか,なんのためにアセスメントするのかといったことを理解するうえで一助になろうかと思います.本書がいろいろな場面で役立つことを願っています.
訳にあたっては,日本解剖学会が編纂した解剖学用語(Nomina Anatomica Japonica 第12版および第13版)を使っています.解剖学用語はどの領域でも共通して使える用語であるからです.またこの用語は実に洗練されており,形(「羽状筋」など)や動き(起始,停止を示す「胸鎖乳突筋」など),はたらき(「括約筋」など)がうまく組み込まれたネーミングとなっている点が卓絶しているところです.ただし,臨床で,ほかの言葉が使われることが多い場合には,その用語も付記しました.
最後に,私を前版で訳者の1人に推薦してくださった故林正健二先生に感謝するとともにご冥福をお祈り申し上げます.さらに,訳やスケジュール管理にご尽力くださいました医学書院の皆様に深く感謝申し上げます.
2025年1月
監訳 藤本 悦子
目次
開く
第1章 人体:概説
1.1 解剖学と生理学の概要
1.2 人体を構成するさまざまなレベルの構造
1.3 生命の維持
1.4 解剖学用語
1.5 ホメオスタシス
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
第2章 基礎化学
2.1 物質やエネルギーの概念
2.2 物質の構成
2.3 分子と化合物
2.4 化学結合と化学反応
2.5 生化学:生命体の化学組成
要約
復習問題
関連職種をのぞいてみよう
第3章 細胞と組織
第1部 細胞
3.1 生命を形作る細胞の基本原理の概要
3.2 一般的な細胞の構造
3.3 細胞の生理学
第2部 身体の組織
3.4 上皮組織
3.5 結合組織
3.6 筋組織
3.7 神経組織
3.8 組織修復(創傷治癒)
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
第4章 皮膚と膜
4.1 人体の膜の分類
4.2 皮膚(外皮系)
4.3 皮膚と膜の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
関連職種をのぞいてみよう
第5章 骨格系
5.1 骨:概観
5.2 軸骨格
5.3 付属肢骨格
5.4 関節
5.5 骨格系の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
関連職種をのぞいてみよう
もっと詳しく見てみよう
第6章 筋系
6.1 筋組織の概要
6.2 骨格筋の顕微鏡解剖学的構造
6.3 骨格筋の活動
6.4 筋の動き,役割,および名称
6.5 骨格筋の肉眼解剖学
6.6 筋系の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
第7章 神経系
7.1 神経系のしくみ
7.2 神経組織:構造と機能
7.3 中枢神経系
7.4 末梢神経系
7.5 神経系の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
第8章 特殊感覚
第1部 眼球と視覚
8.1 眼球の構造
8.2 視覚のしくみ
第2部 耳:聴覚と平衡覚
8.3 耳の構造
8.4 聴覚
8.5 平衡覚
第3部 化学受容:嗅覚と味覚
8.6 匂いの感覚と嗅覚受容器
8.7 味蕾と味覚
第4部 特殊感覚の発生・発達・老化
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
関連職種をのぞいてみよう
第9章 内分泌系
9.1 内分泌系とホルモン機能:概要
9.2 主な内分泌器官
9.3 ほかのホルモン産生組織および器官
9.4 内分泌系の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
第10章 血液
10.1 血液の組成と機能
10.2 止血機構
10.3 血液型と輸血
10.4 血液の発生・発達・老化
要約
復習問題
関連職種をのぞいてみよう
第11章 心臓血管系
11.1 心臓
11.2 血管
11.3 心臓血管系の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
第12章 リンパ系と生体防御
第1部 リンパ系
12.1 リンパ管
12.2 リンパ節
12.3 その他のリンパ器官
第2部 生体防御機構
12.4 自然免疫
12.5 獲得免疫
第3部 リンパ系と免疫の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
第13章 呼吸器系
13.1 呼吸器系の機能解剖
13.2 呼吸生理学
13.3 呼吸器疾患
13.4 呼吸器系の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
第14章 消化器系と体内代謝
第1部 消化器系の解剖学と生理学
14.1 消化器系の解剖学的構造
14.2 消化器系の機能
第2部 栄養と代謝
14.3 栄養
14.4 代謝
第3部 消化器系と代謝の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
第15章 泌尿器系
15.1 腎臓
15.2 尿管,膀胱,尿道
15.3 体液,電解質,酸塩基平衡
15.4 泌尿器系の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
関連職種をのぞいてみよう
第16章 生殖器系
16.1 男性生殖器系の構造
16.2 男性の生殖機能
16.3 女性生殖器系の構造
16.4 女性の生殖機能と周期
16.5 乳腺
16.6 妊娠と胎児の発育
16.7 生殖器系の発生・発達・老化
器官系の協調
要約
復習問題
もっと詳しく見てみよう
付録
付録A 設問の解答
付録B 語根,接頭辞,接尾辞
付録C 元素の周期表
付録D ビタミンとミネラルに関する重要事項
写真提供者一覧
挿図作成者一覧
用語集
索引
和文索引
欧文索引
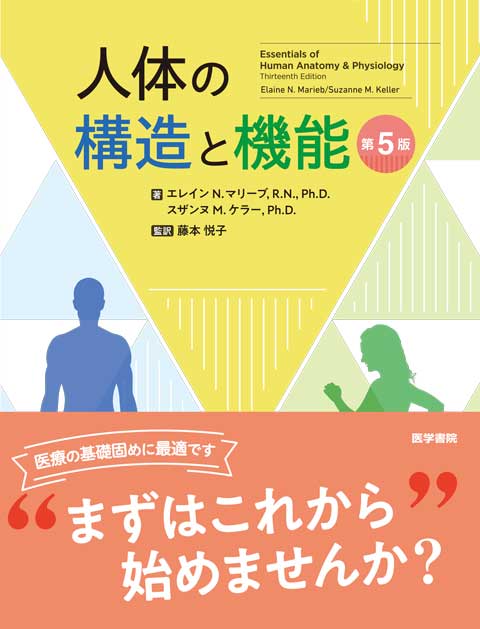
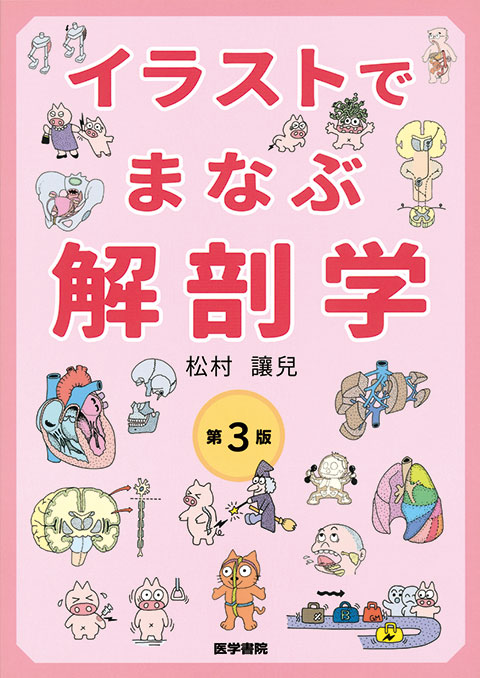
![イラストでまなぶ生理学[Web講義動画付] 第4版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8016/9448/0852/112232.jpg)