MEDICAL LIBRARY 書評特集


聖路加国際病院内科チーフレジデント 編
《評 者》岩田 健太郎(亀田総合病院総合診療・感染症科部長)
その声を聞きながら(内科レジデントの鉄則を読む)
 五感が,記憶を呼び覚ますことがある。試験勉強時に聴きまくった音楽を耳にすると当時の苦痛がじわりとよみがえる。可愛かったあの子と同じ香水の匂いに遭遇すると,ほろ苦い思い出が(かなりビターな思い出が)蘇る。
五感が,記憶を呼び覚ますことがある。試験勉強時に聴きまくった音楽を耳にすると当時の苦痛がじわりとよみがえる。可愛かったあの子と同じ香水の匂いに遭遇すると,ほろ苦い思い出が(かなりビターな思い出が)蘇る。
『内科レジデントの鉄則』を開いた私を刺激したのは視覚ではない。聴覚であった。少なくとも私は,そう感じた。上級医の鋭いあの声(まあ,たいていは怒鳴り声)がよみがえる。「出血性ショックはバイタルサインだ(CBCではない)」「Wheeze=喘息ではない」「頻脈だからといって,やみくもにrate controlをしてはいけない」「心筋梗塞の診断を,トロポニンに頼ってはいけない」「アンモニア=肝性脳症ではない」「麻痺があるからといって脳梗塞とは限らない」……。
雲より高いところに鎮座する偉い指導医のくどくどした説教やレクチャーよりも,頭よりも体,ひたすら走り回る研修医には,年の近い先輩の,こういう箴言こそがなによりありがたい。
経験(そのいくばくかは,おそらく苦い失敗譚)の積み重ねから生まれた数々の箴言。歴史の長い教育病院には必ずこういう言葉たちが蓄積される。本書を読むと,初期研究医のあの喧噪の日々がよみがえる。
3年目のチーフレジデントが初期研修医教育のために作ったこのテキストは,自らの経験と伝統から受け継がれたアフォリズムに満ちている。これだけは知っておいてほしいという強い願いや愛情が込められている。さすがは聖路加のチーフだけあってよく勉強もしている。「なぜFENaがよいのか」の項などは,とても参考になった。
研修医が研修医を教える。屋根瓦方式のもっとも美しい部分を氷結させたのが本書である。その点において,数多い「研修医マニュアル」のエピゴーネンからは決別している。本書を読んだ初期研修医は,新たな先輩医師を得た思いで熟読するとよい。本書を読んだシニアレジデントは,「おれもがんばらにゃ」と魂を鼓舞されるといい。そして指導医は,郷愁に浸りながら読むもよし,黄昏れるにはまだ早いと自らにむち打つのも,またよいであろう。


藤本 卓司 著
《評 者》松村 理司(洛和会音羽病院長)
グラム染色に基づく狭域抗菌薬使用の成果
 2年も前に書評を依頼されていながら,なかなか完読できなかったわけは,私の怠慢についで,個人的な環境の変化にあった。割合大手の病院の院長職への突然の就任は,想定外の激務の日々であった。大所帯の医局人事は,継続させること自体が困難な科も含まれる。民間病院なので,経営問題に大きくのしかかられる。30年間に及ぶ公務員生活を振り返ると,「親方日の丸」の甘さを禁じ得ない。大小の医療事故への対応に昼夜をおかないこともあった。
2年も前に書評を依頼されていながら,なかなか完読できなかったわけは,私の怠慢についで,個人的な環境の変化にあった。割合大手の病院の院長職への突然の就任は,想定外の激務の日々であった。大所帯の医局人事は,継続させること自体が困難な科も含まれる。民間病院なので,経営問題に大きくのしかかられる。30年間に及ぶ公務員生活を振り返ると,「親方日の丸」の甘さを禁じ得ない。大小の医療事故への対応に昼夜をおかないこともあった。
その医療事故だが,最近では,感染症関連のものが多くなっている。当院でも,VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)保菌の集団発生や透析室での急性B型肝炎の多発に襲われたのは,不面目の極みである。本書の著者の藤本卓司先生は,総合内科医や感染症医として現場の研修医や若手医師を惹きつけているだけでなく,院内感染管理医師としても名高い。
そういった背景が,本書にいくつもの麗しい特徴を与えている。第1に,抗菌薬の選択にことのほかうるさい。抗菌域が狭く,副作用が少なく,安い薬を使えとしつこい。第2に,実地臨床の場での大きなツールとしてのグラム染色へのこだわりが中途半端ではない。写真やシェーマが多用され,これでもかといわんばかりであり,先生の執念を感じさせられる。第3に,抗菌薬感受性率について,勤務先の市立堺病院の具体例が取り上げられていることである。「グラム染色に基づく狭域抗菌薬の使用」という良質の原理主義の成果が一望できる。第4に,多数のメモがはさまれており,感染症関連以外のものも多く,いかにも臨床的な薫風が読書のオアシスになっている。第5として,実に読みやすい。箇条書きであるからだけでなく,文章が短く,歯切れがよいからでもある。硬質で,科学的な文体といえる。
新医師臨床研修制度が開始されて3年目に入る。市立堺病院の人気は抜群だが,本書を著された藤本先生の力量にも大きく支えられているのは疑いようがない。地域病院に初期研修医をとられたと嘆く大学人は,先生のこのような実績をまず見習うべきだろう。
なお,9ページの最下段に私とWillis先生への言及がある。1988年とある。懐かしかった。藤本先生が市立舞鶴市民病院へWillis先生の教えを受けるためにはるばるやってきたのは,弱冠卒後4―5年次であり,沖縄県立中部病院における感染症研修への旅の途次だったのがわかる。若き日のあちこちでの武者修行や他流試合が,先生を今日の姿に鍛えあげたように見受けられる。


統合失調症を理解する
彼らの生きる世界と精神科リハビリテーション
広沢 正孝 著
《評 者》高木 俊介(たかぎクリニック(京都市))
精神病理学を広場に開放する書
 統合失調症の人たちの持つ魅力について語る治療者,精神保健福祉関係者は多い。あるいは,その魅力にはまった者がこの道に入る,と言ったほうがいいのかもしれない。著者はおそらく,そのひとりである。それどころか,はまり方にかけては,その道の「第一人者」である。著者を知る者は,それに反対しないであろう。
統合失調症の人たちの持つ魅力について語る治療者,精神保健福祉関係者は多い。あるいは,その魅力にはまった者がこの道に入る,と言ったほうがいいのかもしれない。著者はおそらく,そのひとりである。それどころか,はまり方にかけては,その道の「第一人者」である。著者を知る者は,それに反対しないであろう。
ところで,得てしてその道の第一人者たちは,日々の臨床に埋没していることが多い。しかし,著者は,眺め渡すこと,観照することについても達人である。得てして高踏的で難解を旨とする「達人」が多い中,著者はこれまで平易な語り口で,統合失調症者の人生の機微と,彼らの果たされず埋もれてしまうかもしれない夢について語り続けてきた。その著者が,普段の平易な語り口をそのままに,あの難解な精神病理学のエッセンスを一冊の小さな本にまとめた。
かの難解にして高踏的で鳴らすわが国の精神病理学は,しかし,統合失調症者の理解に関しては世界に類を見ないほどの高い水準に達している。決してないがしろにはできない,精神医学全体の大きな財産なのである。これは,わが国の隔離・収容医療という負の面と,治療者の家族主義的な風土という良心的側面が奇しくも結合した結果であり,歴史の僥倖であった。だから,その成果は今後の統合失調症者の地域生活を少しでも幸福とするために生かされねばならない。そのことは,これまでの隔離・収容主義に対する償いである,と私は思う。
そのためには,統合失調症者の精神病理学が,これまでの難解高踏的な密室の学問ではなく,地域リハビリテーションという広場に気軽にたずさえていけるものにならなくてはならない。この本は,その道を開く第一歩となるだろう。
確かに,統合失調症の人たちの振るまいは,私たちに戸惑いをもたらす不思議なものであることが多い。このことが大きな壁となって,一般社会が彼ら彼女らを受け入れるのを難しくしている。解決として,彼らを変えるのと,私たちが変わるのとの両方向があるが,今の精神医学・医療は,前者にばかり力を入れているようにみえる。これでは,「少数者としての生き方が得意」な彼らも,追いつめられる一方である。著者のまなざしは,その重心を変えて,彼らの生き方を尊重する方向を指している。
統合失調症者は,おそらく,この世ではほとんどまれなほど,「誠意」の通じる人たちである。これが,彼らの最大の魅力であるが,これも精神病理学の目から見ればさまざまな病理が重なった結果ではあろう。しかし,そのことも踏まえた上での私たちの誠意であれば,容易に崩れることのない彼らとの関係の基盤となるだろう。この著書から私はそのことを読み取った。
この本を多くの統合失調症のリハビリテーションにかかわる人たちすべてに薦める。さらに,米国流のDSM診断と生物学的還元主義のみに洗脳されかかっている若い精神科医にぜひとも薦めたい。


《コアテキスト3・4》
疾病の成り立ちと回復の促進
疾病各論[1][2]
下 正宗,前田 環,村田 哲也,森谷 卓也 編
《評 者》森 浩志(阪医大教授・病理学)
活きた用語の使い方を知ることのできる教科書
 コアテキスト・シリーズ『疾病の成り立ちと回復の促進』の第3,4巻(疾病各論)が発刊された。これで医学・医療系臨床教科を学ぶための専門基礎分野の教科書が揃ったわけである。3年前に第1巻『人体の構造と機能』を目にしたときから,使いやすいよい教科書シリーズになりそうだと注目していたが,期待通りの教科書となっている。
コアテキスト・シリーズ『疾病の成り立ちと回復の促進』の第3,4巻(疾病各論)が発刊された。これで医学・医療系臨床教科を学ぶための専門基礎分野の教科書が揃ったわけである。3年前に第1巻『人体の構造と機能』を目にしたときから,使いやすいよい教科書シリーズになりそうだと注目していたが,期待通りの教科書となっている。
これまで,医療系学科/学部の専門基礎分野の講義が非常勤の医学部教員によって行われ,教科書もまた医学部教員によって執筆されることが多いために,解剖学,生理学,医化学,病理学など学問体系ごとの分冊となる傾向があった。シリーズを揃えると重複部分があるため割高な値段であるうえに,執筆者の専門分野のみを記述するセクショナリズムに陥り,読者には不親切な内容の教科書となることが多いのである。
初めて「病気」を学ぶ学生諸君にとっては,正常な人体の機能と構造が,どんな原因でどう変わって病気になり,どんな症状を呈するのか,それらをまとめて教えてくれるのが有り難いはずである。体系立った○○学やXX学の教科書の,それぞれ関連するページから適切な情報を抜き出して,自分なりに知識を組み立てるような自発的学習態度は多くの学生諸君には望めない。一冊の教科書の中で関連事項がコンパクトにまとめられていれば便利である。この教科書はそのために,病理学・細菌学・薬理学・検査/診断学,そして治療方法についても,関連する場面で解説する記述体裁をとっている。
この教科書シリーズは10年前に看護学生を対象に企画されたようである。当時,「看護教育は簡便医学ではなく看護学であるべき」との中央省庁の看護教育基本方針の見直しに従って,臨床看護学に重心を移して,解剖学や生理学の授業内容が簡略化された。ところが医学・医療の進歩に伴って,理解し覚えなければならないことがどんどん増え,看護師国家試験問題も幅広い生命科学の基礎的知識を持たなければ,解けない問題が増えてきた。これは矛盾である。修学年限を延長して基礎医学相当部分に充てる授業時間数を増やす(看護大学化)のは簡単にはゆかない。現実的な解決策は勉強しやすい,読みやすい,よい教科書を作ることである。
この教科書の親切な点は,本文以外に「Word」,「ワンポイント」,「ステップアップ」などが設けられていることである。重要事項に限ったはずのコアテキストとは言いながら,教育熱心な教員(著者)は,あれも知ってほしい,これも教えたいと欲が出るため,どうしても教科書が厚くなる。そうすると読むのが億劫になる。この教科書はその対策として,多くの学生諸君に学んでほしいスタンダードの本文のほか,より発展的な知識を学ぶことのできる「ワンポイント」や「ステップアップ」を用意している。自発性のある学生諸君には親切な企画である。また随所に出てくる「Word」は普通の教科書にはない親切心である。
医療系の専門分野の勉強は実は,専門用語を正確に理解することである。専門用語は症状や病変を定義するもので,くどくどと説明しなくても簡潔に意味が通じる便利さがあるが,あくまでも正確に理解してこそである。その大切さはわかるが,辞書のように専門用語だけを次から次へと羅列されると,うんざりして覚える気がしなくなる。その点,この教科書は初めてその用語が使われる場所で定義が示されるので,活きた言葉の使い方の実例を知ることができる。
この教科書は,当初想定の看護学生だけではなく,コメディカルと呼ばれる医療関連分野の学生諸君にも利用価値が高いといえよう。全ページを精読する必要はなく,各自,その時点で必要な部分だけを読めばよいからである。実は私は医学生の教科書としても通用すると思っている。最近の医学部の授業は医師国家試験の前倒し施行などのために,6年間ではなく5年制になっている。加えて,座って聴く講義は身につかない,グループ討議による自学自習が優れているということになり,講義時間が少なくなった。勢い体系的な知識を提供してくれる教科書を読むよりも,具体的な項目をインターネットで検索して,断片的な情報を継ぎ貼りするような勉強方法になってしまっている。それは医学生向け教科書が分厚すぎるのも原因であろう。
物議を醸すことを承知で言えば,この教科書は看護学生向けにしては欲張りすぎた内容である。むしろ近頃の基礎学力の落ちた医学生に適した教科書であると思われる。これは,医学部と看護学校を含むコメディカルの授業を,試験評価も含めて20年近く担当してきた病理学教員としての実感である。
《コアテキスト3》
B5・頁400・定価3,360円(税5%込)医学書院
《コアテキスト4》
B5・頁448・定価3,465円(税5%込)医学書院


誰もが納得! 胸部X線写真の読み方
高橋 雅士 監訳
《評 者》野間 恵之(天理よろづ相談所病院・放射線科)
胸部単純X線写真を読影するための秘伝本
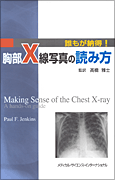 私は教科書には2つのタイプがあると思います。ひとつは読む教科書で,もうひとつが調べる教科書です。本書は典型的な読む教科書で,著者のPaul F. Jenkins氏の長年の経験が凝集されているものです。訳者の高橋先生の言葉を借りると,まさに“秘伝本”であります。英文タイトルに“A hands-on guide”とあるように,著者が読影技術を次へ伝えていきたいという意図が実際の版組みや内部の構成にも表れています。実際に手に持って読むのに最適の大きさで,私も電車の中で読むことが多かったのですが,大変読みやすく感じました。写真も多く簡単に読み進めるのも魅力です。
私は教科書には2つのタイプがあると思います。ひとつは読む教科書で,もうひとつが調べる教科書です。本書は典型的な読む教科書で,著者のPaul F. Jenkins氏の長年の経験が凝集されているものです。訳者の高橋先生の言葉を借りると,まさに“秘伝本”であります。英文タイトルに“A hands-on guide”とあるように,著者が読影技術を次へ伝えていきたいという意図が実際の版組みや内部の構成にも表れています。実際に手に持って読むのに最適の大きさで,私も電車の中で読むことが多かったのですが,大変読みやすく感じました。写真も多く簡単に読み進めるのも魅力です。
私は常々,胸部単純写真の読影力が日本全体で弱くなっていると感じています。近年,CT,MRI,PET,超音波などの技術の進歩によって単純写真の勉強時間がほとんどなくなっていますし,放射線科として胸部単純写真を読まない教育機関も増えています。ときどき“このCT時代に胸部単純写真はいらない”という意見を聞きますが,この発言はまさにそういう人々が臨床をしていないことを物語っていて,語るに落ちると言うべきでしょう。実際の臨床の場では,胸部単純写真は今でも大変重要な位置にあります。これらの状況の中で,本書は,簡便に必要な知識を身につけるにも適した教科書になっています。
一方,著者が英国人内科医であることから,従来,米国の教科書に親しんできたわれわれには,X線診断学の教科書ではありますが,米国と英国の文化の違いを読み取る楽しみもあります。米国のジョークに対して英国のウィットやエスプリといったニュアンスの違いがあり,訳された高橋雅士先生,西本優子先生,牧大介先生のご苦労を垣間見ることもできます。
ともあれ,放射線科に限らず,胸部単純写真を読影する機会のある先生方にはぜひ一読をお勧めしたい本です。
A5変・頁208 定価3,990円(税5%込)MEDSi
URL=http://www.medsi.co.jp/
