MEDICAL LIBRARY 書評特集


栗林 幸夫,佐久間 肇 編
《評 者》高宮 誠(医誠会病院ソフィア健康増進センター顧問/国立循環器病センター客員研究員,元放射線診療部長)
心臓血管疾患の実用的な指南書
 動く器官「心臓」は,常に動かない器官「脳」の診断法の後塵を拝しながら発展してきた。その過程で多列検出器ヘリカルCT(MDCT)とMRIにおいては高速撮影の多様な手法が開発され,時間分解能と空間分解能,S/N比の向上が図られ,動きの激しい細い冠動脈も診断可能になってきた。冠動脈造影を目標に開発された64列MDCTの普及は間近であり,whole heart coronary MRAというような非造影冠動脈画像法が実用域に入りつつある。また,心臓血管疾患の診断アルゴリズムにMDCTとMRI診断法が本格的に組み込まれようとしている。この時期に,本書が出版された意義は大きい。
動く器官「心臓」は,常に動かない器官「脳」の診断法の後塵を拝しながら発展してきた。その過程で多列検出器ヘリカルCT(MDCT)とMRIにおいては高速撮影の多様な手法が開発され,時間分解能と空間分解能,S/N比の向上が図られ,動きの激しい細い冠動脈も診断可能になってきた。冠動脈造影を目標に開発された64列MDCTの普及は間近であり,whole heart coronary MRAというような非造影冠動脈画像法が実用域に入りつつある。また,心臓血管疾患の診断アルゴリズムにMDCTとMRI診断法が本格的に組み込まれようとしている。この時期に,本書が出版された意義は大きい。
編者の栗林氏は電子ビームCTの時代からの心臓血管CTの専門家,佐久間氏は心臓血管MRI一筋の人であり,両氏とも国内外でのこの領域の指導者である。
私が本書を高く評価する点は,個別の専門書として扱われることの多いCTとMRIを並列におき,診断法として確立している部分と両者の診断法の優劣を容易に比較できるように構成されている,参考書としての実用性の高さである。わが国の心臓血管放射線科医はサービス精神のみならず学術的貢献度も高く,『Radiology』や『Radiographics』,『AJR』などに掲載された論文はしばしば学会から顕彰,論評され,実力は世界的な水準にある。執筆者の多くが心臓血管放射線研究会の気鋭のメンバーであり,彼らが各々の得意分野を執筆して内容の充実度を高めている。世界の一流メーカーの技術者たちも執筆し,自社の装置の技術的特徴を述べ合っているのも読み応えがある。日本企業が256列MDCTプロトタイプの実験の結果を記しており,頼もしい開発精神を知ることもできる。
本書で最も紙数を割いているのは心臓画像法であり,特に,最新の冠動脈画像法に重点がおかれ,時代の要請に応えている。冠動脈造影にはそれなりの高速型高性能装置が必要であるが,本書を通読すれば,いずれの施設でも歩留まりのよい冠動脈撮像が可能になるであろう。ステント開存性評価はCTCAの重要な診断目的であるが,この診断能に関する項も参考になることが多い。冠動脈石灰化指数による日本人の冠動脈疾患リスク評価法に関する執筆者の新しい提言も見逃せない。
胸部大動脈瘤におけるAdamkiewicz動脈の位置は血管外科医にとって重要な術前情報であるが,この撮像法を開発したのは本項の執筆者らである。大血管や大動脈分枝,末梢血管疾患では診断目的のカテーテル造影を行う意義はほとんどないことを執筆者らは明確にしている。
本書は,実用的な情報にあふれ,心臓血管系疾患を専門にする医師のみではなく,無侵襲心臓血管画像法の知識は一般の臨床家にとっても絶好の指南書である。また,画像法に携わる診療放射線技師,生理検査技師,ME技師,工業技術者の参考書としても非常に役に立つ本であると思う。


小林 欣夫,園田 信成,森野 禎浩,小谷 順一,前原 晶子,藤井 健一 著
《評 者》南都 伸介(関西労災病院・循環器科部長)
IVUS画像をPCI治療戦略に活かす
 私がPCIをはじめたのは,1980年代の前半です。もっともその時はPCIなどという表現はなく,PTCAでした。本著の序文にあるように,日本でのIVUSの承認が1994年ですので,約10年余はIVUSなしでPCIをしていた時代があったのです。IVUSどころかロータブレータもステントもなく,バルーンカテーテルのみで,今から振り返ればよくやれたなというのが実感です。IVUSが登場したときは,病態解析には役に立つだろうが,IVUSの画像を見てPCIの治療戦略に役立つとは,正直考えもしませんでした。
私がPCIをはじめたのは,1980年代の前半です。もっともその時はPCIなどという表現はなく,PTCAでした。本著の序文にあるように,日本でのIVUSの承認が1994年ですので,約10年余はIVUSなしでPCIをしていた時代があったのです。IVUSどころかロータブレータもステントもなく,バルーンカテーテルのみで,今から振り返ればよくやれたなというのが実感です。IVUSが登場したときは,病態解析には役に立つだろうが,IVUSの画像を見てPCIの治療戦略に役立つとは,正直考えもしませんでした。
今では,IUVSがPCI治療の戦略に大変有用な情報を提供していることは誰も疑わないと思います。スタンフォード大学のFitzgerald先生をして,日本でのSES留置後のステント血栓症が他国と比較して非常に少ないのは,日本はIVUSが保険償還されているので,多くの症例においてPCI時に,IVUSで正確に術前の病変形態の観察がなされ,術後にもステント拡張状態の評価がなされているからだと言わせしめるぐらいです。IVUSがここまで確立したのは日本のインターベンショニストの努力と,本書の執筆者をはじめとした第二世代のインターベンショニストの貢献が高いと思います。
本書を開いてまず気がつくことはIVUS画像とそのイラスト画がすばらしいことです。IVUS画像の中にある重要な所見を大変わかりやすくイラスト画で表現されています。特に,本書の目玉と思われる「基本的なIVUS画像」の章では,PCIでよくお目にかかる,dissection,hematoma,stent,calcified plaque,thrombus,lipid core,fibrous cup,ruptured plaqueなど重要なIVUS像が網羅されています。CAG世代の私には,もう少しCAG像の対比があればとも思いますが,少し欲ばりかもしれません。
また,lumen enlargementのメカニズム,再狭窄のメカニズム,positive and negative remodeling,急性冠症候群のIVUSなど高級な内容も含まれていて,大変興味深く読ませていただきました。
PCIを始めかけた先生や,PCIをしていてIVUS画像をどう戦略に応用していいか迷われている先生にはぜひ読んでいただきたいと思います。いや,序文にあるように,読むより見ていただきたいと言ったほうがよいかもしれません。さらに,「IVUS vs. Angiography-IVUSの有用性を示すエビデンス」や,「Drug-Eluting Stent時代のIVUS」の章などは,インターベンション専門医の先生方にも今までの知識を整理したり,最新情報を取り入れるうえで大変役立つように思います。


《標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野》
老年学
第2版
奈良 勲,鎌倉 矩子 シリーズ監修
大内 尉義 編集
《評 者》荻原 俊男(阪大病院長/阪大大学院教授・老年・腎臓内科学)
医療・介護現場で役立つ老年学のバイブル
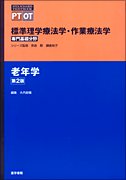 先進国の中でも未曾有の超高齢化社会の到来を控えたわが国において,高齢者の社会を支えているのは税金を納めている納税者だけでなく,実際に高齢者の医療,福祉を支えている家族であり,メディカル・コメディカルスタッフである。
先進国の中でも未曾有の超高齢化社会の到来を控えたわが国において,高齢者の社会を支えているのは税金を納めている納税者だけでなく,実際に高齢者の医療,福祉を支えている家族であり,メディカル・コメディカルスタッフである。
老年医学と聞くと,一般医学の高齢者版に過ぎないという誤った認識が多く見受けられるが,本書を通読すると高齢者の疾病だけでなく,人格から生活スタイルに至るまでの理解が深まり,医療や介護の現場で直ちに役立つ「ポイント」が自ずから身につくような工夫が随所になされている。
本書は国家試験に受かるための「知識」を詰め込むだけでなく,老年学の基本である「全人的に診る」素養を涵養し,その生き様に敬意を払う姿勢を身につけるためにも絶好の読み物でもある。各疾病に関する記述も,各分野の専門家が高齢者に特異的な病態や若年者との違い,見落としがちな症状や兆候などを,詳細に解説している。したがって,授業や実習でバイブルとして携帯し,辞書のような活用も可能であろう。
序説にも記されているが,本書は老年医学だけにとどまらず,基礎老化学,老年社会学,老年精神医学,老年歯科医学の分野も網羅されており,「老年学」のタイトルで総括されているのが最大の特徴である。最近では「アンチ・エイジング」が医療や介護の領域を越えて一大ブームになっているが,健康に老い,寿命を全うしたいというのは,世代を超えた究極の願いである。
基本的には,PT,OTをめざす方の教科書としてまとめられているものの,その内容は医学部生,研修医をはじめ,高齢者にかかわるすべての方に読んでいただきたい幅広いものとなっている。特に高齢者の機能評価ではBarthel IndexやMMSEなど,老年専門医にも日常診療で使いやすい表記で記載されており,私自身も手の届くところに本書を置き,実際に活用させていただいている。また,医療関係者には介護のシステムやリハビリの現状が,介護関連の方には高齢者に特異的な疾患の特徴がわかりやすく記述されており,1人の高齢者をチームで支える時の共通のバイブルとして大いに利用が期待される。
超高齢化社会が円滑に機能していくためには,高齢者自身の自立と理解が必須である。また,高齢者本人のやる気を持続させるには,内在する心身の状態,とりまく社会的環境を総合的に考え,個別に対応することが重要である。マニュアル通りいかないのが高齢者の特徴でもあり,接する側の技量が最も問われるところとなる。
本書をきっかけにして高齢者の心のヒダに潜んだ問題点に気づくことができれば,教科書で学ぶ数倍の貴重な情報が,本人の口から語られることになる。3Kなどと呼ばれがちな高齢者をとりまく環境を宝の山に変えるためにも,読者が老年学のエキスパートとなり,世界一の長寿国を支える担い手としての自負が芽生える一助として,本書が活用されることを願ってやまない。


WM循環器内科コンサルト
池田 宇一 監訳
《評 者》磯部 光章(東医歯大大学院教授・循環制御内科学)
最新知見が散りばめられた研修生活の座右の書
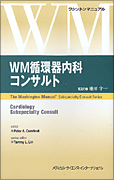 本書は定評ある『ワシントンマニュアル』循環器内科版の翻訳書である。『ワシントンマニュアル』を座右において研修生活を送る医師は少なくない。筆者自身も病棟にあってはこのマニュアルを常に参考にして,少し余裕のある時に「ハリソン」の内科学書をひもとくという勉強の仕方をしていたことを思い出す。
本書は定評ある『ワシントンマニュアル』循環器内科版の翻訳書である。『ワシントンマニュアル』を座右において研修生活を送る医師は少なくない。筆者自身も病棟にあってはこのマニュアルを常に参考にして,少し余裕のある時に「ハリソン」の内科学書をひもとくという勉強の仕方をしていたことを思い出す。
それは,内容の新しさ,必要なことがコンパクトにまとまっていることに加えて,あこがれていたアメリカにおける臨床現場の雰囲気が直接伝わってくるような記述に魅力を覚えたからかもしれない。同じコンセプトで編まれた循環器内科版の訳書が出版されることは,とても喜ばしいことである。
初学者が症例に接しながら勉学をするに際して重要な点の1つは,病態を知り,診断体系における個々の診断プロセスを理解し,治療のコンセプトを知る中で,1人ひとりの患者の診療方針を考えることであろう。極めて安直なマニュアルを参照している研修医も少なくないが,理屈のない要点のみが書かれたマニュアルで勉強した医師には,日進月歩に進化していく医学にキャッチアップし,また千差万別の病態を持った患者の診療方針を他の医療者と対等に議論する能力を獲得することは困難である。
本書は実用書として最新の知見が紹介されているとともに,その理屈や理論が散りばめられた,アカデミズムに貫かれたマニュアルと言ってよい。ACC/AHAのガイドラインが多数紹介されていることも大変便利である。
ただ,翻訳書という制約もある。特に薬物療法においては,本邦で使用できない薬物が原語で多数紹介されており,また投与量にも注意が必要である(ただし訳注として本邦における標準的投与量が記されている)。もう1つ難をあげれば,心電図の見にくさである。本の大きさの制約もあろうが,次回の改訂では工夫していただきたいところである。
これらのことを差し引いても,学生や研修医など初学者にとどまらず臨床の現場で循環器患者を診る医師にぜひ勧めたい画期的なマニュアルである。


矢谷 令子 シリーズ監修
山田 孝 編
《評 者》小林 隆司(神奈川県立保健福祉大助教授・作業療法学)
サイエンスとアートの面から作業療法を研究する
 南カリフォルニア大学のゼムケ教授は,作業療法を万華鏡に喩えた。万華鏡は,基本的には鏡を組み合わせて作った筒で色ガラスなどの小片を見るものである。その構造から考えると,網膜に届く光の信号は,小学校で習った入射角や反射角のような物理学の原則に徹頭徹尾貫かれているはずである。
南カリフォルニア大学のゼムケ教授は,作業療法を万華鏡に喩えた。万華鏡は,基本的には鏡を組み合わせて作った筒で色ガラスなどの小片を見るものである。その構造から考えると,網膜に届く光の信号は,小学校で習った入射角や反射角のような物理学の原則に徹頭徹尾貫かれているはずである。
しかしながら,われわれが体験する万華鏡の最終的な像は数式の理解を超えて美しく,少し動かしただけでさまざまに姿をかえ,2度と同じものはないという儚ささえ感じられる。サイエンスとアートがうまく融合した万華鏡のメタファーは,作業療法を語るにはまさにうってつけだと感銘をおぼえた。
作業療法が(たぶん人間も)サイエンスでありアートであるというなら,作業療法の研究もサイエンスとアートの両面から進められるべきである。そう考えていたら,好適書が医学書院から出版された。それが本書である。本書の特徴はまさに,サイエンスとアートという切り口でさまざまな作業療法研究をカタログ化した点にある。このことによって,研究法の選択に指針が得られる。
例えば,まず実習で受け持ったケースの事例研究をどのようにすすめるか参照した後に,サイエンス的な方向にそれを発展させる場合,シングルシステムデザインや実験的デザインなどが参考になる。アート的な方向なら,記述を分厚くしていくために質的研究やナラティブなどに進むとよい。研究に必要な基礎知識や事例がふんだんに盛り込まれているのも,研究を検討し実行するうえでは大きな助けになる。
さて,本書は教科書の体裁をとっているが,実は臨床家に多く読んでいただきたい本である。本書は,研究は臨床の疑問に答えるために行い,臨床のプロセスは研究のそれと同じであるという理念に貫かれている。つまり,初期評価があり→治療を実施し→再評価により治療効果を検討することは,研究ではベースラインデータを測定し→介入し→アウトカムを示すことにすぎないのである。クリニカルリーズニングにまで踏み込んでいるのは,臨床を支援する研究法という本書の姿勢を顕著に現した部分であろう。
まさに待望の書といえる本書だが,あえて言うなら,項目の重複などが見られる(第1版にはありがち)ので,なるべく早く改訂にとりかかっていただきたい。版を重ねるごとにクオリティがより高まることは間違いない。
なにはともあれ,本書を片手に,図書館で文献を探したり,ラボでアンケートデータと格闘したり,クライエントの物語を傾聴したり,実際に心と体を動かしてみよう。初めて万華鏡を覗いた時の感動にまためぐり合えるから。
B5・頁264 定価3,990円(税5%込)医学書院
