MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


坂本 穆彦 編
《評 者》蔵本 博行(北里大大学院教授・臨床細胞学/北里大名誉教授/日本臨床細胞学会・前理事長)
最新の知見とともに 臨床細胞学を学べる教科書
 臨床細胞学の教科書のベストセラー『細胞診を学ぶ人のために』(編集・坂本穆彦杏林大学病理学教授)が,このたび第4版に改訂された。前回,第3版への改訂は6年前であったと聞くが,この間に細胞診を取り巻く状況は,種々変化してきている。各種癌の取扱い規約の改定や,ガイドラインが新しく制定された。特に乳癌や甲状腺癌の報告様式の取り決めなど細胞診に関係の深いものも含まれている。
臨床細胞学の教科書のベストセラー『細胞診を学ぶ人のために』(編集・坂本穆彦杏林大学病理学教授)が,このたび第4版に改訂された。前回,第3版への改訂は6年前であったと聞くが,この間に細胞診を取り巻く状況は,種々変化してきている。各種癌の取扱い規約の改定や,ガイドラインが新しく制定された。特に乳癌や甲状腺癌の報告様式の取り決めなど細胞診に関係の深いものも含まれている。
これらの変化に迅速に対応できるのは,本書がベストセラーで,多くの知識欲旺盛な読者に愛されてきたからこそであろう。
このように,最新の知識が盛り込まれているのはもちろんであるが,本書の最大の特徴は,初心者であっても,臨床細胞学を基礎からじっくり学べ,かつ臨床細胞学を偏りなく把握できることにある。まず総論的に,細胞の役割,細胞の形態的・機能的特徴が述べられ,細胞像と組織像の対比,さらには病理組織学の基礎的知識が学習できるように構成されている。
各論では,ともすれば著者によって偏りがちになりやすいのであるが,各領域の細胞診をまんべんなく学べるよう配置されているのが大きな特徴である。これは,すべての領域をカバーする病理系の,本邦を代表する細胞診専門家が分担執筆しておられるためであろう。また,共同執筆者の細胞検査士諸氏も癌研有明病院で診断の第一線にあるばかりでなく,教育の担当者として,細胞診の専門家が何を知っているべきか,日々実感しておられるからこそであろう。
近年,大学でも4年間のカリキュラムで学士教育として臨床細胞学が教育されるようになってきた。筆者も北里大学医療衛生学部で細胞検査士コースを担当したが,学生の教科書に対するニーズは高かった。各専門領域の最新の啓蒙書が多い中にあって,本書は,学生が利用するのに最も適切な教科書として数少ない良書であろう。
多数の貴重な症例の写真もさることながら,イラストも多用されている。細胞の特徴を理解するには,まず顕微鏡下の細胞形態を描いてみることであろう。細胞診を学ぶ学徒にとって,このような点も配慮されている本書は親しみやすいのではなかろうか。さらに,この第4版では本文の記載は2色刷となって,一層理解しやすくなった。
本書を,これから臨床細胞学を学び始める熱心な学徒に,通読する優れた教科書として推薦したい。また,細胞診の専門家にも,最新の臨床細胞学の進歩を確認するために,折に触れてひもとく専門書としてお薦めしたい。


四元 秀毅,折津 愈,金澤 實 編
《評 者》井上 洋西(岩手医大教授・第三内科)
代表的な呼吸器疾患の 専門医の思考過程を提示
 医療の質や水準は,医師の診断能力によってまず決定づけられる。
医療の質や水準は,医師の診断能力によってまず決定づけられる。
この診断能力は,本来は学生時代に身に付けられるよう訓練されなければならない。しかし,これまでの日本の医学教育では,講義を通じての知識や技術の理解・修得が優先され,実践的な診断能力の向上は二の次とされることが少なくなかった。これは国公立大学においても同様で,学生時代に客観的・合理的な推量法を教わることはほとんどなかった。
よってわが国では,卒業後に患者さんの協力を前提に,上司の指導を受けながら試行錯誤を重ねて,あるいは独学で診断能力を身につけてきたものといえる。それゆえ,身についた思考法は,上司のやり方や勘をまねた客観性に欠けるものが少なくなかった。
学生の診断能力の欠如は,臨床実習の学生に新患の患者さんの病歴を聴取させてみるとすぐにわかる。頻度の高い疾患でも,鑑別を含めてその疾患を土俵際に追いつめる(臨床診断を行う)能力はほとんど身に付いていないのが一般的といえる。これでは卒後研修必修化の新制度のもとに卒業し医師免許を取得しても,医師として患者さんの前に立たせることはできない。医療の安全上も由々しきことといえる。
しかし欧米,また日本の近隣の東アジアの国々では,すでに何年も前から系統診断学の手法が取り入れられ,個々の知識や技術が有機的に結合しあい,無駄なく合理的に診断に至るための実践的な訓練が,学生時代から行われている。わが国でも,医師国家試験においては,最近になってようやくこのようなproblem solvingの能力を問う問題を増やす傾向に変わりつつあり,国家的なコンセンサスを得て,近い将来医学教育根幹の大きな変革が行われるに違いない。
本書の特色は,特徴ある代表的な呼吸器疾患42症例を通じて,個々の具体的な病歴,身体所見,検査成績を提示し,これらの解決のためのポイントを得た設問を提示し,その合理的な思考過程をその領域において最高峰の実践能力を身につけた専門医が十分議論のうえ提示している。
さらにこの問題形式は,最近の医師国家試験の臨床実地問題の長文問題と同様な形をとっている。この意味でも国家試験を前にした学生が,問題の解決能力を養ううえでも必須の書といえよう。また,研修医や実地医家の診断能力の向上をはかり,また指導医の指導能力に一層の磨きをかけるうえでも,本書が極めて重要な役割を果たすことが期待できる。
この書を読まれた方は,呼吸器の診療が楽しくなるに違いない。よって一読をお勧めしたい。


動画で学ぶ脳卒中のリハビリテーション
[ハイブリッドCD-ROM付]
園田 茂 編
《評 者》岩 テル子(新潟医療福祉大教授・作業療法学)
専門職間の理解も深まる 脳卒中リハの案内書
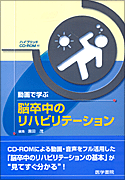 評者の所属する作業療法学科の何人かの学生とともに本書のCD-ROMを見た。4年次の実習を終えた学生は動画の1つひとつに納得し,「そうそう,腕がこんなふうに垂れ下がって動かないのよ」と言い,評価実習直前の3年生は「どうして右手と左手の長さがこんなに違うの」と問う。4年生はあれこれ原因を挙げるが確信が持てないようだ。本文には弛緩性麻痺との記載がある。そこで教師である評者は,「筋がまったく麻痺して動かない患者さんが,3kgもある腕をぶら下げたままこの動画のように立ったり座ったり,場合によっては伝い歩きなどしたら,肩関節はどうなるのか」と問う。4年生は「亜脱臼だ」と口々に言う。かくして評者も学生らも動画につられ,しばし時間を忘れて議論しながら見終わった。本書のCD-ROMでは,目次や索引から見たい項目を即座に,かつ自由に見ることができる。このことも学生をはじめとした若い人の興味を引き付ける要因であろう。
評者の所属する作業療法学科の何人かの学生とともに本書のCD-ROMを見た。4年次の実習を終えた学生は動画の1つひとつに納得し,「そうそう,腕がこんなふうに垂れ下がって動かないのよ」と言い,評価実習直前の3年生は「どうして右手と左手の長さがこんなに違うの」と問う。4年生はあれこれ原因を挙げるが確信が持てないようだ。本文には弛緩性麻痺との記載がある。そこで教師である評者は,「筋がまったく麻痺して動かない患者さんが,3kgもある腕をぶら下げたままこの動画のように立ったり座ったり,場合によっては伝い歩きなどしたら,肩関節はどうなるのか」と問う。4年生は「亜脱臼だ」と口々に言う。かくして評者も学生らも動画につられ,しばし時間を忘れて議論しながら見終わった。本書のCD-ROMでは,目次や索引から見たい項目を即座に,かつ自由に見ることができる。このことも学生をはじめとした若い人の興味を引き付ける要因であろう。
また,言語聴覚学科以外の学生にとって,普段見ることのできない摂食嚥下の評価と治療は特に興味深い。VF検査の場面では作業療法学科の学生は嘆声を上げ,繰り返し見直して誤嚥のメカニズムを理解したようだ。嚥下造影の手順やVF評価法,重症度分類も大変参考になる。このように,本書は脳卒中のリハビリテーションに関わる専門職が互いの仕事を理解するためのよい案内書でもある。
本書は3章から成り,1章の症状・評価と3章の治療の間に運動学習の章がある。障害度に応じた方法を用いて,上達度に応じた訓練量を課し,正常動作を自覚させるフィードバックを繰り返すことが強調され,指導のタイミングも説明されている。全編に優れた臨床家の目が光る。また,脳卒中の回復期リハビリテーションの基本編であると述べられているとおり,臨床での勘所がしっかりと押さえられている。
本書では,CD-ROMの動画に音声がついているのは言語の場面が中心で,ほとんどの動画は説明文と照らし合わせる必要がある。説明文は端的に述べられており,また専門用語が多いので,脳卒中のリハビリテーションの基本的知識が必要であろう。「すべての動画に音声を入れて!」と思わず声が出そうになるが,これは編者である園田氏の密かな企みではないか。90頁という見やすく,かつ手頃な動画付き解説書に読者が引かれ,脳卒中について自主的に深く広く勉強することを期待して編集されたに違いない。そうであれば,その意図は十分達成されている。


矢谷 令子 シリーズ監修
山田 孝 編
《評 者》石井 良和(秋田大教授・作業療法学)
臨床実践を重視 作業療法士をめざす人のために
 この本は『作業療法研究法』というタイトルであるが,単なる研究法(入門)の書ではない。作業療法を過去から現在まで論じており,そして未来へのメッセージを「研究」というキーワードに託して書かれた本である。すでにインターネット上でも高い評価が見受けられる。
この本は『作業療法研究法』というタイトルであるが,単なる研究法(入門)の書ではない。作業療法を過去から現在まで論じており,そして未来へのメッセージを「研究」というキーワードに託して書かれた本である。すでにインターネット上でも高い評価が見受けられる。
作業療法士の臨床的経験の連なりは,作業療法の歴史的縮図のように見える。障害を持つ人のために何か役に立つ仕事に就きたいという素朴で強い思いをいだいて作業療法士になることをめざす段階から,養成校で医学的知識を学び,それを臨床で適用するといういわば科学的思考の実践を試みる段階へ,そして多くのクライエントに出会い,思い通りに治療的プロセスが進むケースや,思うようにならずに困惑してしまうケースなどを経験し,自らの思考と技術が洗練されていく段階とがあるように思われる。
これは,キールホフナーが示したパラダイムシフトによるアメリカ作業療法の歴史と似ている。作業療法の自己相似性があるのかもしれない。
新たなパラダイムを見据えた21世紀の作業療法は,クリニカルリーズニング,エビデンスに基づく実践(EBP),ナラティブに基づく実践(NBP),国際生活機能分類(ICF)といった事柄に関心を寄せざるを得ない状況にある。作業療法士の数が急速に増えてきている現在,作業療法の未来に対する期待と不安が入り交じる。量的な増大が質的変化をもたらすのだろうか。
ヒントは本書の第1章にある「研究は誰が何のためにするものなのか」にありそうに思う。われわれ1人ひとりの臨床と研究のふるまいにあることに気づかれるのではないだろうか。これから作業療法士になる方にはぜひとも一読していただきたい章である。
本書に一貫しているのは「作業療法の専門職としての存在価値は臨床実践にあり」というエリクサの言葉である。また,本書の大きな特徴でもあるアート的手法による研究の解説は,忙しくて研究にまで手が回らないと言われる臨床家の方には臨床現場が情報の宝庫であることに気づかせてくれるであろう。第2章以下では新進気鋭の教育・研究者たちによる,自らの作業療法をベースにした知識と応用が詳細に書き込まれている。
当然のことかもしれないが,個性的な各執筆者の文章がきわめてよく整えられており,それにもまして文章の歯切れのよさに今までにない新鮮さを覚える。編者とのレベルの高いコラボレーションの賜物であろう。教科書として学生だけに持たせるのは「もったいない」とまで言うのは言い過ぎだろうか。


藤田 尚男,石村 和敬 訳
《評 者》高田 邦昭(群馬大大学院教授・生体構造解析学)
わかりやすさに重点を置いた 初学者のための組織学図譜
 Sobottaの組織学図譜第5版(原書第6版)が出た。標本作製法,細胞の光顕像と電顕像,組織学総論,組織学各論,付表,和文・英文索引からなり,いわば組織学をもれなくカバーした従来のオーソドックスな章立てを踏襲している。しかしながら,中を開いてみるとその進化に驚く。今回の改訂では,プラスチック切片を用いた薄い組織切片の明快な写真が要所要所にあって理解を助けている。また,ヒト試料の電顕写真の大幅な採用と,その解説などが大きな変更点である。
Sobottaの組織学図譜第5版(原書第6版)が出た。標本作製法,細胞の光顕像と電顕像,組織学総論,組織学各論,付表,和文・英文索引からなり,いわば組織学をもれなくカバーした従来のオーソドックスな章立てを踏襲している。しかしながら,中を開いてみるとその進化に驚く。今回の改訂では,プラスチック切片を用いた薄い組織切片の明快な写真が要所要所にあって理解を助けている。また,ヒト試料の電顕写真の大幅な採用と,その解説などが大きな変更点である。
従来,この図譜は明快なカラー写真やカラースケッチののった数少ない組織学図譜の1つであった。ページをめくっていると,駆け出しの解剖学教室助手時代に,組織学実習で教えるために,英語版原書(1976年版)を見ながら一生懸命標本を観察した記憶が懐かしくよみがえってきた。同時に,内容がさらにクリアーカットになったのに驚いた。
序に,「この本を利用するわが国の学生が内容をよく理解できることに最大の重点をおいたために,原文とは随分かけ離れた訳になっている」が,「わかりにくい個所はまずないものと自負している」とある。わが国の組織学教科書の文字通りの標準である標準組織学の著者と,息のあった師弟コンビにして初めて自信をもって言えることであろう。実際,訳文は非常によくこなれていて,翻訳であることを意識させない。組織学用語は日本語と英語が併記されていて,現在のカリキュラムにもよく適合している。
この図譜の特徴として,組織の肉眼やマクロ観察による全体像から,詳しい組織や細胞構築をへて電顕での細胞小器官レベルまでシームレスにつながるよう工夫されている点があげられる。低倍率で全体像を見る場面では,無理に低倍率写真を使わないで,綺麗で明快なスケッチを使っている。これは初版から採用されている手法であるが,低倍写真では説明できない点がスケッチによりとても明瞭に示されている。例えば卵巣では,原始卵胞,二次卵胞,グラーフ卵胞,閉鎖卵胞,黄体,白体などが1つの卵巣内に見事に描かれていて,各段階の卵胞の大きさ,配置などが一目で頭に入るようになっている。ページをめくると通常の光学顕微鏡写真とともに,明快な電顕写真があり,適切な解説とともに,この3ページを見るだけで,卵巣の構造と卵胞の成熟過程を理解するよう工夫がされている。
今回の版では,多色刷りの模式図も加わり,さらに理解が深まるであろう。惜しむらくは,この模式図が,従来の図とタッチが違って若干の違和感のある点であるが,カラフルでわかりやすいのは間違いない。
この種の本は,恐竜の進化のように,版を重ねるにつれて,とかく肥大化して自滅することが多いのだが,この本は,付け加えるのではなく,図や説明を入れ替えたり改良したりすることにより,初学者の理解を助けるのに精力が傾けられている。結果として,組織学をはじめて勉強しようという者にとって,間違いのない,熟成していて安心して寄りかかることのできる図譜に成長している。
巻末には,表がまとめて配置してある。これには染色法,組織や細胞の分類や比較,腺や消化管の部位などの似た構造の鑑別診断法などが丁寧にまとめてある。これらの文字のページと図譜のページを往き来することによって,人体の組織構築が文字通り血となり肉となって身につくであろう。
A4・頁280 定価11,550円(税5%込)医学書院
