MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


言語聴覚士のための
言語発達遅滞訓練ガイダンス
佐竹 恒夫,小寺 富子,倉井 成子 編
《評 者》下嶋 哲也(国立身体障害者リハビリテーションセンター・学院 言語聴覚学科)
言語発達遅滞児にかかわる臨床家による臨床家のための本
 言語聴覚士がかかわる対象として,ことばの理解や表現に遅れのある子ども(言語発達遅滞児)は重要な位置を占めている。そして,言語発達遅滞児への言語聴覚士による援助に関する理論と方法論も,これまでにいくつか開発されてきている。
言語聴覚士がかかわる対象として,ことばの理解や表現に遅れのある子ども(言語発達遅滞児)は重要な位置を占めている。そして,言語発達遅滞児への言語聴覚士による援助に関する理論と方法論も,これまでにいくつか開発されてきている。
この本は,言語聴覚士として(編者の先生方が臨床をはじめられた当時はまだ言語聴覚士という公の名はなかったが)長きにわたって継続してきた言語発達遅滞児の臨床の中で,その支援の理論と方法論すなわち〈S-S法〉(正式には,国リハ式〈S-S法〉言語発達遅滞検査法,および訓練法という)を構築してきた編者らと,多くの症例提供をした臨床家による,臨床家のための本である。
臨床家による臨床家のための本たる所以は,まず紹介されている症例がその多様さを確保しながら,〈S-S法〉の理論的枠組みの中に整理されていることである。その理論的枠組みの包括性は,比較的コンパクトにまとめてある序章を読むことによって理解できる。そして以後紹介される症例について,どのような視点でまとめあげられ,評価,訓練立案,再評価されているかということが理解できる。
第一章以降は,症例紹介が〈S-S法〉の理論による症候分類にそってまとめられている。たとえば第一章には「幼児期の一時的な発語の遅れ」が取り上げられ,以降第二章では「ことばの理解ができない子どもの訓練」,第三章では「単語レベルは理解できるが発語のない子どもの訓練」といったようにテーマが設けられ,ほとんどの章で複数の症例が挙げられている。また,難聴との重複障害やAAC(補助拡大コミュニケーション)など,近年その重要性がより高まってきた対象にも積極的に取り組んできた臨床家の足跡をみることができる。
紹介されている各症例は,「その背景となる情報→初期評価→訓練計画の立案→訓練経過→終期評価」という臨床の流れそのものを反映するように段階的にまとめられている。そしてその段階ごとに,「評価のポイント」「訓練のポイント」「解説」などが加筆されている。これらのポイント指摘や解説は,おそらく症例を臨床家どうしで検討する際に議論されたポイントであろう。読んでみると,臨床を実際に行っていくうえで欠かせない視点や評価しておくべきポイント,その後の子どもの状態,経験に基づく臨床の基本的な考え方などが明快な形で,しかも初心者にもわかる程度のていねいさで表現されている。自らの経験を重ねて読んでいくうちに,まるで自分が現在かかわっている症例についてのスーパーバイズを自分が受けているような気持ちにすらなっていく。また,28個におよぶ「コラム」では,これまでの知見から得られた貴重な追跡調査の結果や,少々各論的なもの(例えば文字学習など)が読みやすい長さで書かれており,新しいことを知る喜びを与えてくれる。
最後に,長い臨床歴をもつ臨床家だけが書くことのできる症例が紹介されているのは貴重である。例えば長期経過を追った症例など,1つのグラフを書くのに15年かかるのである。このグラフを見た時に,臨床に必要な知識というにとどまらず,臨床にとって何が大事であるかを学ぶことができたように思う。
この症例集には,1人ひとりのケースに真摯に向き合ってきた多くの臨床家の技術と,臨床にかける思いがたくさん詰まっている。現在言語聴覚士になろうとしている人には理論的枠組みを含めて,具体的症例を通して臨床を理解する手立てとして役立つであろう。また,現在言語聴覚士として言語発達遅滞児にかかわっている人には,予後データと方法論の共有をはじめとして,自らの臨床の質を高める手立てとしてきっと役立つであろう。


内分泌代謝疾患レジデントマニュアル
第2版
吉岡 成人,和田 典男,伊東 智浩 著
《評 者》細井 雅之(大阪市立総合医療センター代謝内分泌内科副部長)
これぞ,シマウマとウマの見分けのできるeffective clinicianへの道!!
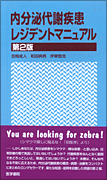 初版の序にある言葉「You are looking for zebra!」「シマウマ探しに陥るな」は,まさにこの本のポリシーです。内分泌をシマウマ(稀な疾患)と思い込みがちなレジデントや上級医,はたまた指導医にも必須マニュアル本です。臨床重視の吉岡先生らしく症例の実例をあげて,いかに内分泌がシマウマでないかを気づかせてくれます。そして第2版の序にあるように,これはeffective clinician「よき臨床医」をめざす吉岡先生のポリシーを感ずる「バイブル」のようなマニュアルです。マニュアルに従いつつ,最終的には患者さん1人ひとりにもどって考える考え方を導いてくれます。バーガー20人分を買いに来たお客さんに「こちらでお召し上がりですか?」と言う店員をつくるようなマニュアル本ではありません。
初版の序にある言葉「You are looking for zebra!」「シマウマ探しに陥るな」は,まさにこの本のポリシーです。内分泌をシマウマ(稀な疾患)と思い込みがちなレジデントや上級医,はたまた指導医にも必須マニュアル本です。臨床重視の吉岡先生らしく症例の実例をあげて,いかに内分泌がシマウマでないかを気づかせてくれます。そして第2版の序にあるように,これはeffective clinician「よき臨床医」をめざす吉岡先生のポリシーを感ずる「バイブル」のようなマニュアルです。マニュアルに従いつつ,最終的には患者さん1人ひとりにもどって考える考え方を導いてくれます。バーガー20人分を買いに来たお客さんに「こちらでお召し上がりですか?」と言う店員をつくるようなマニュアル本ではありません。
最後にある,負荷試験のまとめや,徴候からみた鑑別診断もベッドサイドで必須です。治療内容も現場で迷わぬように,薬剤の商品名と用法,点滴のスピードまで示してあり,そのまま指示簿にも書けるぐらいになっています。
かといってナラティブばかりのマニュアルではなく,大規模スタディの最新のエビデンスと引用文献まで示されています(内科認定医の症例報告の考察にも使えそうです)。ポルフィリン症までカバーされています。
あえて注文をお願いするとすれば,糖尿病の項目で,HOMA-βについて,2型糖尿病患者のインスリン導入についての外来導入方法,インスリン中止可能症例の見分け方,フットケアの項目も次回の改訂ではお願いいたします。
会社の宣伝にのった薬の紹介ではなく,論文のNNT(Number needed to treat)を冷静に分析して最適な治療法を教えてくださる吉岡先生だからこそ,まさに信頼がおけるマニュアルです。スーパーローテーションの研修医には必携してほしいマニュアルです(われわれ指導医も助かります)。


口腔内科学シークレット
Oral Medicine Secrets
Stephen T. Sonis,Robert C. Fazio,Leslie Shu-Tung Fang 編
島原 政司,勝 健一 監訳
《評 者》清水 正嗣(大分大名誉教授・口腔外科学)
歯科医師臨床研修に必要な内容も網羅した実用的名著
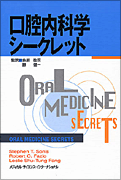 本書の原書“Oral Medicine Secrets”は,米国ハーバード大学口腔内科ほか担当Sonis教授と外科,内科各教授2名,医・歯学両領域専門家3名の合同執筆で2003年出版である。一方,監訳された島原・勝両教授は,医科大学の口腔外科学および内科学の主任教授で,そのもとに各教室の専門スタッフ10名が加わって,本書が2004年秋に完成,出版された。
本書の原書“Oral Medicine Secrets”は,米国ハーバード大学口腔内科ほか担当Sonis教授と外科,内科各教授2名,医・歯学両領域専門家3名の合同執筆で2003年出版である。一方,監訳された島原・勝両教授は,医科大学の口腔外科学および内科学の主任教授で,そのもとに各教室の専門スタッフ10名が加わって,本書が2004年秋に完成,出版された。
本書の特徴は原著者の序文にあるように,本書対象が歯科医師,医師,レジデント,学生たちであり,その内容は近年の歯科臨床の口腔科学全般領域への広がり,患者の高齢化に対応,内科的疾患併存患者の多数化,それへの理解と必要対処の適切な実施を可能にするための成書,広義の教科書である。さらに最近の医療体制がその経済的背景とともに外来診療に重点を置くように求められ,その体制変化にも応えられる内容をもめざしている。
このような著書が求められる事情は日本でもほぼ同様となっており,これに歯・医学部担当者が,その臨床で的確なる対処を求める支持点としての著書が切望されるのは,まさに緊急の課題である。そこでわが国でも,監訳者序文にあるように,2006年から歯科も医科同様の臨床研修義務が法令化され,歯学部新卒業生を中心とする義務研修内容が,質的,量的に高度化,拡大化されると覚悟しなくてはならない現状である。それは当然卒前および卒後教育内容において同様の変化対応が求められる。本書は,かかる重大な変化に対応するに最も相応しく,また,2006年新研修制度実施に合わせて緊急に必要とされる内容を持つものである。それゆえ,本書の監訳・出版が急がれ,担当者全員の通常以上の努力をもって,わずか1年の時間で実行されたものと推察する。本書内容は,内科学全般をカバーし,従来の卒前内科研修では到底カバーされなかった広範領域を取り扱っている。
すなわち,患者評価という内科診断学の総論的項目にはじまり,心血管系疾患,内分泌疾患,妊娠,呼吸器疾患,消化器疾患,血液疾患が細部にわたって取り上げられ,次いで,関節炎,泌尿器生殖器疾患,神経系疾患ほか,歯科・口腔外科に関連深い内科以外の領域疾患も記述されている。口腔疾患に関連しては,感染症,粘膜疾患,腫瘍性疾患,唾液腺疾患,骨疾患など重要領域が多岐にわたって包含されている。最後に症例提示を問題疾患に関連して写真とともに行い,解説されている。合わせて,全体の執筆形式も質問-回答形式として初学者であっても,簡潔に核心を把握できるようにまとめられている。必要参考文献,索引も実用的に添付されて,本書の実用性を高めている。
以上,これらを合わせて,本書は日本において現在まさしく,緊急に求められている歯科臨床,特に卒後の実地研修・教育にすぐ役立つ有用性の高い著書として,広範な歯学・医学臨床の該当修学生,研修生および教育者にぜひ推薦したい実用的名著である。


鑑別診断のための臨床指針
DSM-IV-TRケーススタディ
橋 三郎,染矢 俊幸,塩入 俊樹 訳
《評 者》石郷岡 純(東女医大教授・精神医学)
すべての精神科医が一度は通読すべき1冊
 待望久しかったアメリカ精神医学会によるDSM-IV-TRケーススタディの日本語訳が,このたび出版された。著者はDSM-IV改訂の際の編集委員長であるAllen Frances・デューク大学精神科教授とRuth Rossである。
待望久しかったアメリカ精神医学会によるDSM-IV-TRケーススタディの日本語訳が,このたび出版された。著者はDSM-IV改訂の際の編集委員長であるAllen Frances・デューク大学精神科教授とRuth Rossである。
このケーススタディには74例が収録されており,16章に分かれる各疾患カテゴリーで数例ずつを提示し,症例ごとに鑑別診断を含む診断へのプロセス,および治療方針まで解説するという体裁で構成されている。呈示される症例は適度に教科書的であるがリアリティもあり,解説も抑制の利いた語り口で進められているため受け入れられやすく,操作的診断法がはじまって四半世紀たった今このような診断スタイルがある普遍性に到達し,決して無味乾燥なものではないことを実感できる書物となっている。
本書は読者自らが触れる機会の少ない症例を経験するための症例集ではない。むしろ代表的な症例を通じて生きた診断学を学ぶための1冊である。全国の大学,病院では毎週症例検討会が開かれ,診断,治療について議論が交わされているであろうが,この書物に描かれている症例の呈示法,およびそこから得られる問題点の抽出法,診断へ至る思考プロセスは,そこに集まる臨床医が共通言語として共有すべきひとつのプロトタイプを示していると言えよう。こうした議論がされた後,診断学の歴史や最新の知見など,操作的診断ではカバーできない領域が活発に語られる症例検討会であれば,臨床の力を大いに伸ばすことのできる実りあるものにできるであろう。各施設で議論をリードする立場にある方々には,ぜひ本書で採られているスタイルを参考にしていただければと思う。また,その意味では,これから精神科医として診断学を勉強していくものにとっては,きわめて効率のよい書物でもある。
本書を単なる教科書に終わらせない,興味深い1章が最後に第17章として設けられている。すなわち,操作的であるが故に生じる診断の不確定性,診断する臨床医の目の重要性,情報の量・質の重要性など,診断学の基本に関わる問題点を浮き彫りにする1章であり,それらを考えさせる10例が提示されている。ここでは現在の診断学,操作的診断の限界が症例を通じて赤裸々に描かれているが,一方では,長くこの診断体系の確立に取り組んできた著者らが,ベストではないがベターであると強烈に主張しているようにも見える1章である。操作的診断には,症状からは原因が特定できないという基本的態度と,薬剤性など,明らかに原因があると思われるものは除外するという相反する原則が併存しているが,訳者の橋名誉教授(滋賀医大)が述べているように,新しい知見によっていつの日か今の診断基準が時代遅れになることを,この1章は予言しているように見える。
翻訳は新潟大学の先生方が分担で行い,さらにそれを染矢教授,塩入助教授が修正し,最後に訳者代表の橋名誉教授が全文を校正するという念入りな工程を経て完成されただけに,統一された自然な文体で読みやすいものとなっており,すべての精神科医が一度は通読したい1冊に仕上がっている。


医療と経営の質がわかる人材育成を目指して
進化する病院マネジメント
川渕 孝一 著
《評 者》江藤 かをる(エデュネット協会)
質の高い医療提供を行うためのマネジメントをめざす
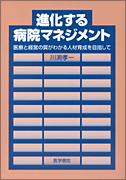 本書は“勢い”を持った本である。この勢いは著者の思いの強さから生まれている。思いとは「病院マネジメントは科学である」ことを理解し,質の高い医療提供を行うためのマネジメントをめざす「日本版ホスピタリスト」を養成したい,というものであると評者は理解する。この強い思いが,本書の勢いを生み出している。
本書は“勢い”を持った本である。この勢いは著者の思いの強さから生まれている。思いとは「病院マネジメントは科学である」ことを理解し,質の高い医療提供を行うためのマネジメントをめざす「日本版ホスピタリスト」を養成したい,というものであると評者は理解する。この強い思いが,本書の勢いを生み出している。
本書は,マネジメントの理論や考え方を一般論として紹介しているのではない。本書の特徴は,企業や病院での成功例や実例を用い,理論を生かした効果的・実践的なマネジメントを読者にわかりやすく説いている点にある。多方面からの統計や調査結果を主張の根拠としている点も高く評価できる。
本書は以下の章から構成されている。
序章:日本版ホスピタリストに求められるリーダーシップ,第1章:外部環境の変化と病院マネジメント-「患者中心の医療」にどう対応するか,第2章:病院経営戦略とバランスト・スコアカード(BSC)-戦略にBSCは有効か,第3章:病院組織-組織はどうすれば活性化するか,第4章:患者のマネジメント-実践的病院マーケティングとは,第5章:人材育成のマネジメント-人はどうすれば動くのか,第6章:内部プロセスのマネジメント-病院をシステムとしてどう捉えるか,第7章:お金のマネジメント-病院をいかにファイナンスすればよいか,第8章:病院のリスクマネジメント。
第2章で登場する「バランスト・スコアカード(BSC)」は戦略的な管理手法として大変有効であると思われるが,著者はBSCを日本の医療にあてはめたのみでなく,実践可能な形にして具体的に読者に紹介している。例えば,第5章の職員の動機づけ,第6章の医薬品・診療材料等の科学的在庫管理方法,待ち時間短縮,電子カルテ導入などには,興味をそそられる内容が多岐にわたって述べられている。
「患者中心」の視点から医療機関のサービス改革に取り組んでいる評者としては,第4章もぜひ多くの医療者に理解していただきたい項目である。
ダメ経営者・ダメ管理者の典型を「KKDH」と呼ぶ。KKDHとはK-勘,K-経験,D-度胸,H-はったり,を指す。理論的な根拠や戦略を伴わないKKDHでは経営や管理に行き詰まる。KKDHに陥らず著者のいう「日本版ホスピタリスト」をめざす方や,何とか現状を変えたいと思っている医療者には,部門を問わずぜひお薦めしたい1冊である。きっと「そうだ,そうだ」と共感する記述やぜひ試してみようと思う箇所に数多く出会えることであろう。
A5・頁376 定価3,150円(税5%込)医学書院
