MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


がんと戦うレジデントに強力な武器となる
がん診療レジデントマニュアル 第3版国立がんセンター内科レジデント 編
《書 評》吉川裕之(筑波大教授・産科婦人科)
妥協なきマニュアル
 「がん診療レジデントマニュアル第3版」を読ませてもらった。第3版であるというのに,これまで書店で目にすることはあったが,内容についてはまったく知らなかった。レジデントマニュアルということで,初心者向きの記載が多いのかと予測していたが,まったく異なるものであった。国立がんセンターのレジデントが執筆し,スタッフがレビューして完成しているためか,レジデントならここまでの知識で十分というような妥協がない。臨床現場で必要でかつ正確な情報を簡潔に記載しており,忙しいレジデントがこれを武器にがんと戦う,まさに実践向きのマニュアルである。EBMを重視した最新の情報は,レジデントのみならず,すべての医師,看護師,薬剤師などにとっても役立つものである。
「がん診療レジデントマニュアル第3版」を読ませてもらった。第3版であるというのに,これまで書店で目にすることはあったが,内容についてはまったく知らなかった。レジデントマニュアルということで,初心者向きの記載が多いのかと予測していたが,まったく異なるものであった。国立がんセンターのレジデントが執筆し,スタッフがレビューして完成しているためか,レジデントならここまでの知識で十分というような妥協がない。臨床現場で必要でかつ正確な情報を簡潔に記載しており,忙しいレジデントがこれを武器にがんと戦う,まさに実践向きのマニュアルである。EBMを重視した最新の情報は,レジデントのみならず,すべての医師,看護師,薬剤師などにとっても役立つものである。
がん診療の基本から最新知識まで
この本は,がん告知とインフォームドコンセント,がん薬物療法の基本概念,臨床試験(第I,II,III相試験などについて詳述)などからはじまり,各臓器別のがん治療について記載したのち,がん性胸膜炎などの治療,感染症対策,がん疼痛治療と緩和医療,骨髄抑制・消化器症状・抗がん剤漏出へのアプローチなど全科共通の必須知識・技術に関して説明している。また,病期分類,組織分類,抗がん剤の保険適応などの他に,臨床試験の倫理規範としてのヘルシンキ宣言,エビデンスレベル,G―CSFに関するASCOガイドライン,血小板輸血に関するASCOガイドライン,RECISTガイドラインなどについてまとまった情報が得られる。遺伝子組み換えモノクローナル抗体,分子標的薬など普通の教科書にまだ記載のない最新情報についてもまとめられている。将来指導者になるべきレジデントが,最も知識欲のある時期に必要かつ十分な情報を得て,がん診療について指導者と真剣に議論を戦わせることを可能にする本として推奨する。また,当然,レジデントに一方的に論破されたくない指導者にも推奨される。
B6変・頁400 定価(本体3,800円+税)医学書院


心・血管系合併症を持つ腎機能障害患者の診療に
腎機能障害患者の循環器病マネジメント島本和明 編
浦 信行,土橋和文 編集協力
《書 評》富野康日己(順天堂大教授・腎臓内科)
23万人を超える 慢性維持透析受療患者
 急性腎不全は,急激な腎機能の低下により生ずるが,適切な緊急透析療法等により可逆性であることが多い。しかし,慢性腎不全では密かに進行することが多く,ついには透析療法が導入される。慢性腎不全にはいろいろな分類があるが,Seldinの分類が一般的である。ほとんど無症状で腎予備能の低下を示すI期から,夜間尿,軽度の高窒素血症・高血圧を示す腎機能不全期(II期),多尿,貧血,中等度の高窒素血症・高血圧,代謝性アシドーシス,高P・低Ca血症を示す腎不全期(III期)へと進行し,尿毒症症状,重症高血圧,浮腫,肺水腫を示す尿毒症期(IV期)に至る。
急性腎不全は,急激な腎機能の低下により生ずるが,適切な緊急透析療法等により可逆性であることが多い。しかし,慢性腎不全では密かに進行することが多く,ついには透析療法が導入される。慢性腎不全にはいろいろな分類があるが,Seldinの分類が一般的である。ほとんど無症状で腎予備能の低下を示すI期から,夜間尿,軽度の高窒素血症・高血圧を示す腎機能不全期(II期),多尿,貧血,中等度の高窒素血症・高血圧,代謝性アシドーシス,高P・低Ca血症を示す腎不全期(III期)へと進行し,尿毒症症状,重症高血圧,浮腫,肺水腫を示す尿毒症期(IV期)に至る。
現在,慢性維持透析療法を受けている患者は,23万人を超えたと報じられている。このような経過の中で腎機能障害の進行を抑制し,不整脈や心不全,心筋梗塞など多くの合併症を予防・治療することは重要な課題である。
専門医にも役立つ実践書
最近,札幌医科大学第2内科・島本和明教授の編集のもと関連病院の先生方が『腎機能障害患者の循環器病マネジメント』を刊行された。島本和明教授は,優れた研究者であると同時に優れた臨床医であり,日頃ご尊敬申し上げている先輩の1人である。夜に開催される研究会でもいつも「お晩でございます」と北海道弁でご挨拶され,道産子の小生はいつも懐かしく伺っている。さて,本書は3部から構成されている。1部では,「病態生理をふまえた患者マネジメント」が述べられているが,中でも腎機能障害例での循環器薬の薬理がコンパクトにまとめられている。他書でもよく述べられるジギタリスや抗不整脈薬の他に最近よく用いられるACE阻害薬,アンジオテンシン受容体拮抗薬などについても排泄経路や透析性がまとめられている。
2部では,「臨床における患者マネジメントの実際」が透析療法を含め述べられている。著者らが実際に経験された症例をもとに疫学,病態,診断,治療へと展開されていくのは大変興味深く読み進めることができる。欲を言えば,薬剤の商品名をもう少し加え,どういった場合に原則としてどのくらいの量を投与すべきか,それでも効果がみられない場合にはどう対処すべきかが述べられていれば,より一層実践的ではないかと感じられた。
3部では,腎機能障害時の検査での注意点や外科的治療,透析患者での心血管系合併症の重要性とその治療などがKey noteとしてまとめられている。特に,腎性貧血をエリスロポエチンなどを用いて改善することが,いかに虚血性疾患イベントの発症を抑えるかという現在最もホットな話題にも触れられている。さらに,本書の特筆すべき点は,付録にある。腎機能不全・透析療法における循環器疾患に対する薬剤の使用量・留意点・副作用とともに,関連団体や企業のホームページ,主たる略語まで述べられているのは,心憎いばかりである。
以上の特長から本書は,腎臓病専門医が心・血管系合併症を有する腎障害患者を診療する際にも大変役に立つ実践書と思われる。
B5・頁232 定価(本体5,200円+税)医学書院


肩の凝らない救急蘇生法の入門書
CPRインストラクターズガイド 第2版小濱啓次 監修
山本保博 編
吉田竜介 編集協力
《書 評》小林国男(帝京大教授・救命救急)
心肺停止患者の救命率向上には 市民への心肺蘇生法教育が重要
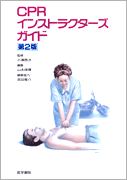 社会全般のシステムが今大きな変革期にあるが,救急医療においても変革が進んでいる。これまでの医療は,医療機関で医師が患者を診るときからはじまるのが通念であったが,搬送を含めた病院前の医療,いわゆるプレホスピタルケアも医療の重要な一環であるとの認識が受け入れられてきた感がある。このような社会の気運が,除細動や気管挿管などの救急救命士の行なう救急救命処置範囲拡大に繋がっているのであろう。しかし,都市部においても救急車が現場に着くには平均6分を要しており,心肺停止患者にはこの間に心肺蘇生法が行なわれないと,救急隊員や医師の努力は報われないことになる。したがって,心肺停止患者の救命率を上げるには,一般市民に対する心肺蘇生法教育がきわめて大切であるといえる。
社会全般のシステムが今大きな変革期にあるが,救急医療においても変革が進んでいる。これまでの医療は,医療機関で医師が患者を診るときからはじまるのが通念であったが,搬送を含めた病院前の医療,いわゆるプレホスピタルケアも医療の重要な一環であるとの認識が受け入れられてきた感がある。このような社会の気運が,除細動や気管挿管などの救急救命士の行なう救急救命処置範囲拡大に繋がっているのであろう。しかし,都市部においても救急車が現場に着くには平均6分を要しており,心肺停止患者にはこの間に心肺蘇生法が行なわれないと,救急隊員や医師の努力は報われないことになる。したがって,心肺停止患者の救命率を上げるには,一般市民に対する心肺蘇生法教育がきわめて大切であるといえる。
好評を博した初版を,米国の 最新ガイドラインに準拠して改変
一般市民に対する心肺蘇生法教育を広めるには,共通の教材を利用するのが効率的であるが,かつては日本医師会,日本赤十字社,消防庁などがそれぞれ独自のカリキュラムとテキストで教育を行なっていた。日本医師会では,救急蘇生法教育検討委員会を組織し,日本救急医学会の協力を得てガイドラインの作成に取り組み,1993年に「救急蘇生法の指針 一般市民のために」を上梓した。日本赤十字社は,「蘇生法講習教本」を基に蘇生法教育を実施していた。その後,2000年に米国心臓協会から,いわゆる「ガイドライン2000」が出されたのを受け,わが国でも関係団体が協力して心肺蘇生の統一した指針を作成することになり,日本救急医療財団に心肺蘇生法委員会が設置され,「救急蘇生法の指針」が改定された。本書の初版「CPRインストラクターズガイド」は,日本医師会,日本赤十字社,消防庁などの当時の教本を集大成して蘇生法指導者用のサブテキストとして1994年に出版されたものである。本書もこの度,「ガイドライン2000」に準拠して改版されたものであるが,基本的に評判の良かった初版の目次構成やイラストを継承している。しかし,心肺蘇生にかかわる内容は「ガイドライン2000」に準拠して改変されているのはもちろんのこと,米国心臓協会(AHA)における心肺蘇生法教育の実際も紹介されている。本書は,表題がCPRとなっているが,心肺蘇生法以外にも止血法,各種外傷・熱傷・中毒等の応急手当,傷病者の管理法や搬送法,一般市民にもわかりやすい解剖・生理の知識など,一般市民が必要とする基本的な事項を網羅している。
本書は,一般市民への心肺蘇生法教育を普及するために有用なテキストであるばかりでなく,医師,看護師,救急救命士など救急医療従事者のための簡便な副読本としても大いに役立つものと思われる。肩の凝らない救急蘇生法の入門書として,ぜひ関係者に一読を薦めたい。
B5・頁136 定価(本体2,000円+税)医学書院
