日本外科学会,日本内科学会 相次いで開催
第96回日本外科学会総会(会長=千葉大教授 磯野可一氏)が4月10-12日に千葉 市の幕張メッセで,また第93回日本内科学会講演会(会頭=東大教授 黒川清氏)が4月11-13日に横浜市 のパシフィコ横浜にて,それぞれ開催された。
日本外科学会では,シンポジウム,ビデオシンポジウム,パネルディスカッション,ワークショッ プ,会長講演,特別講演,海外からの演者を迎えての招待講演,教育講演など,日々進歩する外科領域に とどまらず,外科治療の将来の方向性を模索する基礎や内科学研究の最新の成果も合わせた知見が提示さ れた。
日本内科学会では,約700題の一般演題がすべてポスター形式で発表される一方,講演会場では シンポジウム,特別講演,教育講演,内科セミナー,パネルディスカッションなどが行なわれた。また会 期中に開かれた定期総会では,学会定款の改正が提案され,1925年の社団法人認可以来用いられてきた縦 書きの文章を口語体で横書きとするなどの全面的な変更が了承された。
本号ではそれぞれの学会から話題を拾ってみた(関連記事:第93回日 本内科学会の話題より,第96回日本外科学会の話題より。なお両学会 の話題は次号でも掲載予定)。


第96回日本外科学会
メインテーマ「融和と創造」
 「融和と創造」をメインテーマとした第96回
日本外科学会総会。磯野会長は今回の学会開催にあたって,複雑多岐に分化し高度化した外科学のさらな
る発展のためには,医療全体の研究面・制度面双方における大きな変革の渦の中で続出しているさまざま
な問題点を把握することこそが重要であるとの認識を示した。学会プログラムもその考えを反映し,流行
にとらわれずに医療全体を視野に入れての外科学のさらなる発展の方向を模索するものとなった。
「融和と創造」をメインテーマとした第96回
日本外科学会総会。磯野会長は今回の学会開催にあたって,複雑多岐に分化し高度化した外科学のさらな
る発展のためには,医療全体の研究面・制度面双方における大きな変革の渦の中で続出しているさまざま
な問題点を把握することこそが重要であるとの認識を示した。学会プログラムもその考えを反映し,流行
にとらわれずに医療全体を視野に入れての外科学のさらなる発展の方向を模索するものとなった。
次代を担う外科医養成のために
近年の日本の外科学の特徴としては,QOLを重視し機能温存を目的とした縮小手術への取り組み,早 期診断や手術手技・器械の発達による長期遠隔成績の向上,内視鏡外科手術の普及,診断・治療のための 分子生物学的研究の定着などがあげられる。加えて,医療全体での卒後臨床教育制度改善の流れのなかで, いかにして次代を担う外科医を養成していくかにも大きな関心が持たれている。今回の学会でも,特別シ ンポジウムとして「卒後外科臨床研修のあり方」,展示会場で関連する実演も行なわれた教育講演「外科 医教育のためのバーチャルリアリティーの応用」が行なわれた。また「映像による私の手術手技」, 「3Dハイビジョンで見る手術術式」など,よい医療を提供する原点である外科医が身につけるべき技術 がわかりやすく示された。多角的な視点から捉える
シンポジウムでは幅広い領域から選ばれた演者らによって,外科学を医療全体の視野から見渡した総 合討議が行なわれた。また,すべてのシンポジウムで総合討論の後に特別発言が設定されたのも,多角的 な視点から1つの領域を捉えようという今回の学会の姿勢を示したといえる。シンポジウムのテーマも,消化器癌に対する外科的治療と内科的治療,癌手術や大動脈解離の外 科治療の長期遠隔成績,縮小・拡大手術と補助療法といった,本当に患者のためになる医療の実現をめざ して多様な選択肢の中から適応を見極めていこうというもの。長年に渡って蓄積された自験例や全国の施 設へのアンケート調査も含めた,外科学会ならではの膨大なデータの提示とディスカッションが行なわれ た。
膵十二指腸切除1000例
羽生富士夫氏(東女医大)による特別講演「単一施設における膵十二指腸切除1000例の経験」では, 1995年に東京女子医科大学附属消化器病センター外科において開設(1968年)以来1000例を超えたこの術 式の変遷や長期遠隔成績が発表され,会場の注目を集めた。会長講演は「教室食道外科の過去・現在」。また谷口克氏(千葉大)による特別講演「免疫性制 御系」や,北島政樹氏(慶大)による教育講演「臓器移植と微小循環動態」が行なわれた。
さらに,高度専門化された話題だけでなく,臨床において最も関心の高いテーマによるエデュケー ショナルフォーラムも設けられ,「“common disease”最近の外科手術はどのように変わったか?」,「胸・ 腹腔鏡下手術」が取り上げられた。


第93回日本内科学会
自然との調和をテーマに
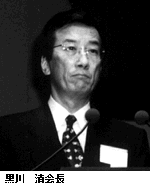 第93回日本内科学会の統一テーマは「自然との
調和を求めて」。「自然の破壊が進む一方で,現代の医療をめぐっては多くの問題がある。人間と他の生
命をめぐる問題などを皆さんと一緒に考えていきたい」(黒川氏)との考えから設定されたもの。会頭演
説「内科医への期待」を行なった黒川氏は,今後の内科医のあり方,医師のあり方について日頃の考えを
率直に訴えた。
第93回日本内科学会の統一テーマは「自然との
調和を求めて」。「自然の破壊が進む一方で,現代の医療をめぐっては多くの問題がある。人間と他の生
命をめぐる問題などを皆さんと一緒に考えていきたい」(黒川氏)との考えから設定されたもの。会頭演
説「内科医への期待」を行なった黒川氏は,今後の内科医のあり方,医師のあり方について日頃の考えを
率直に訴えた。
社会が決める将来の医師像
黒川氏は,「内科のサブスペシャリティ(循環器,消化器など)の専門医であっても,内科全般をか なりのレベルで診療できないと内科医としての責任を果たしているとは言えない」と述べ,「今後は質の 高い均一な研修の成果を国民に保証する必要がある」と提言。内科標榜の問題や,専門医の適正数の予測・ 対策と併せ,日本内科学会の指導的役割への期待を述べた。また,内科医の将来像はすなわち医療の将来像であるとの考えから,将来の医療を規定する要素 として次の「5つのM」を提示し,以下のように解説した。
(1)Market(社会経済):医療が適正にコストエフェクティブに行なわれているかが今後の医療形 態や制度を決めていく要因の1つとなり,臨床判断でもより科学的手法が必要。つまり社会のニーズ,市 場の原理,科学に裏打ちされた判断が求められる。(2)Management(運営):総医療費の増加,老齢化な どのもと,専門医の適正配分,医療費の適正配分,1次~3次の医療機能区分の再構築ができ上がる。 (3)Molecular biology(分子生物学):分子生物学が研究の進歩をリードし,病因・病態の理解,診断・治 療・予防への応用が進む。(4)Microchip/Media(コンピュータの普及と情報社会):国民がより多くの情 報に基づいて医師や病院を選ぶようになる。(5)Moral(医師の倫理,Ethics):技術の進歩に対応し,脳死, 臓器移植,遺伝子診断・治療など,職業人としての倫理とそれに基づく判断,医療行為がますます求めら れ,医師の判断の社会的責任がより厳しく問われる。
黒川氏は最後に,「今後は,従来のような医師による医療の決定ではなく社会が決める医師像・ 医療制度に対し,どこまで医師が責任ある立場として提言し,リーダーシップが取れるかが問われる」と 強調。内科医の持つ臨床と基礎の接点や社会との密接性からみても,日本内科学会のいっそうのリーダー シップの発揮と学会活動の充実が望まれると述べ,講演を結んだ。
最新の情報を解説する教育講演
一方,教育講演としては,「内科診療の進歩」8題と,「最近の話題」8題が行なわれた。「内科診療 の進歩」では,「痛風と高尿酸血症」や「真菌感染症の診断と治療」などについてレクチャーがなされ, このうち「アルツハイマー病診療の最新の進歩」では,中村重信氏(広島大教授)が登壇。他の内科疾患 との合併も稀ではないアルツハイマー病(AD)について,遺伝子診断などの早期診断,予防,知的機能 の改善を図る初期治療などについて語った。また「最近の話題」では,「高血圧の分子生物学的アプローチ」や「遺伝子治療」などがテーマ となり,遺伝子治療については,浅野茂隆氏(東大医科研教授)から,臨床への展開の移行期にある遺伝 子治療の具体的戦略が紹介された。
「最近の話題」ではこの他,狂牛病などで話題となったプリオン病も取り上げられ,立石潤氏 (九大名誉教授)がその概要を講演した。プリオン病は,プリオン蛋白の変異からなる疾病の総称で,遺 伝子異常と感染症の側面を持つ。ヒトの場合の代表的疾患にはクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)やクー ルー病がある。立石氏はプリオン蛋白の特徴やプリオン病の発症機序,予防策などを解説したのち,最近 イギリスで起こった若年性CDJ(従来型は中年期以降に発病)に触れ,新しいタイプのプリオン病と考え られると述べた。
この他学会ではシンポジウムとして「消化器疾患の内視鏡治療」,「糖尿病とその合併症の治療」, 「内科疾患と遺伝子異常」が企画され,多くの参加者を集めた。
