MEDICAL LIBRARY 書評特集


平野 朝雄 編著
《評 者》久保田 紀彦(福井大教授・脳脊髄神経外科)
正常と異常を対比観察 病的所見を解明
 神経病理の入門書である『神経病理を学ぶ人のために』の姉妹版として1980年に初出版された『カラーアトラス神経病理』の第3版が,第2版から18年ぶりに改訂され,出版された。本書は,著者の平野朝雄教授が「まえがき」で述べておられる如く,実物を本から学び取れるように,すべて美しいカラー写真で統一されている。改めて最初からつぶさにカラー写真を観察し,所見の解説を読むと,まるで私が25年前のMontefiore病院の剖検室に戻ったような錯覚を起こした。
神経病理の入門書である『神経病理を学ぶ人のために』の姉妹版として1980年に初出版された『カラーアトラス神経病理』の第3版が,第2版から18年ぶりに改訂され,出版された。本書は,著者の平野朝雄教授が「まえがき」で述べておられる如く,実物を本から学び取れるように,すべて美しいカラー写真で統一されている。改めて最初からつぶさにカラー写真を観察し,所見の解説を読むと,まるで私が25年前のMontefiore病院の剖検室に戻ったような錯覚を起こした。
まず,頭蓋骨,硬膜,脳,脊髄表面の肉眼病理所見から観察し,脳と脊髄の割断面を観察する。肉眼所見と同じ標本の光学顕微鏡所見を対比しながら読むと,実像が明瞭化し,興味が尽きない。通常,教科書は通読するような構成になっているが,本書は常に異なった頁の関連図を読むように工夫されている。著者が最も強調されている如く,正常構造と異常構造の対比が異常所見を探すのに役立つ。そのため,正常の肉眼および顕微鏡所見を詳細に解説している。さらに,サイズを考慮して病的所見を観察できる工夫がなされており,異常所見がわからない場合には,正常所見と比較しながら観察すると大変わかりやすい。
本書の特徴の1つとして,疾患単位がわかりやすく比較できるように工夫されており,類似所見や正反対の病的所見が一瞥できるように配置されている。また,部位別に疾患が記載されており,病変部位と疾患単位の関連がよくわかる。所見の解説には主要所見はもちろん,人工産物と時間的概念が記載されており,所見の奥深さが読み取れる。時間的記載が明確なためか,どの図にも生き生きとした新鮮さがある。すべての生物所見は,ある瞬間を捉えたものであり,その前に何が起こったか,その後に何が起こるのかを想像することが学問の面白さである。特に通常のHE染色での所見には詳細な解説がなされており,僅かな変化も見逃してはならないことを教えている。このような著者の観察力が「平野小体」(図211)の発見をもたらしたのであろうと,いまさらながら敬服する。さらに,HE染色に加え,神経病理で使用される特殊染色や免疫組織染色により所見の実体を詳細に解説している。
脳神経外科医は,腫瘍,血管障害,外傷,感染,奇形などの疾患を扱うことが多く,神経変性疾患には興味が薄い傾向にある。このアトラスを手にとると,神経変性疾患にも興味を起こさせる。最近は,認知症や脊髄疾患を扱う機会が増加しており,本書は日常臨床や学生教育の参考資料になる。巻末には,最新の重要病理所見が追加されている。
著者の鋭い観察力と教育者としての比類なき実力が十分に汲み取れる美しいアトラスである。「学問は無味乾燥で,できれば避けて通りたい」と思う怠惰な精神にこのアトラスが学問への興味を呼び戻してくれる。本書は脳脊髄のCT・MR画像診断を日常業務としている医師にとって,病的所見の解明の優れた手ほどきになる。特に,これから神経病理を学ぼうとされる初心者に『神経病理を学ぶ人のために』の姉妹版として,このアトラスの購読をお薦めする。


ポートフォリオ評価とコーチング手法
臨床研修・臨床実習の成功戦略!
鈴木 敏恵 著
《評 者》武田 裕子(東大助教授・医学教育国際協力研究センター)
学びや成長をもの足りなく感じている研修医・医学生に
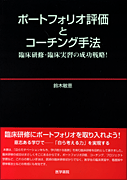 ポートフォリオという単語はもともと,写真やパンフレット,文書などの資料を投げ込んで保存する二つ折りの“紙ばさみ”を指していた。それが次第に,建築家やデザイナーが自らの作品をまとめてファイルし,自分の仕事の成果や実力を示すものという意味で使われるようになった。現在では,学習を刺激しその過程を俯瞰する学習・評価ツールとして,教育の領域で広く用いられている。特に近年,多岐にわたる能力(コンピテンシー)が求められ,内省しつつ成長することが期待される医療者教育に導入されている。ポートフォリオの中身や形式は目的によってさまざまであるが,その意義や効果に関する論文は急増している。
ポートフォリオという単語はもともと,写真やパンフレット,文書などの資料を投げ込んで保存する二つ折りの“紙ばさみ”を指していた。それが次第に,建築家やデザイナーが自らの作品をまとめてファイルし,自分の仕事の成果や実力を示すものという意味で使われるようになった。現在では,学習を刺激しその過程を俯瞰する学習・評価ツールとして,教育の領域で広く用いられている。特に近年,多岐にわたる能力(コンピテンシー)が求められ,内省しつつ成長することが期待される医療者教育に導入されている。ポートフォリオの中身や形式は目的によってさまざまであるが,その意義や効果に関する論文は急増している。
著者が本書のなかで繰り返し述べているように,ポートフォリオが役立つかどうかは,作成する研修医・医学生自身がその意義を理解し,“「やらされている」ではなく「自分の成長につながる」と思えるかどうかが最大の鍵”となる。自分自身を客観的に見つめたり,立ち止まって考える,振り返ることが,医療者にとって不可欠な行為であることに疑いの余地はない。この本は,そのような態度・行動を具体的に言葉で表現し,実行できるようにサポートしてくれる実践的な書である。
しかし必要性を認識することと,行動に移すことの間には,かなり大きな壁が存在する。日記が不得意だと,たとえ1行でも毎日自分の思いや自己評価を書きとめ,さまざまな記録物をファイルしていくのは至難の業に思える。“成長するためには「意志」がいる!”とハッパをかけられても自信がない。そこで本書は後半に,セルフコーチングあるいは指導医によるコーチングや日々の研修におけるフィードバックについて紹介している。例としてあげられた“卒後3年目の医師によるコーチング”は,初期研修医との距離が遠いという印象をもったが,これを指導医の役割と考えるとなるほどと思わされる。また,研修医自身が参加しさまざまな職種を交えての「研修委員会による“オープン評価”」は,多くの研修教育病院の参考になると感じた。
著者の鈴木先生は,“(ローテーションの)区切りに「間」を設けて1人で思考する”こと,しかも“2日程度”と本書で勧められている。ローテーション最終日は,深夜までかかって担当患者の入院経過のサマリーをカルテに記載していた身としては,不可能!と反応してしまったが,医療界以外のところで活動されてきた鈴木先生だからこそ,必要なことを率直に伝えてくださっていると受け止めた。これまでの自分の学びや成長を何となくもの足りないと感じている研修医・医学生のあなたにぜひお薦めしたい1冊である。
病院に熱い眼差しを向け,精力的に教育の分野で活動されている一級建築士の鈴木先生,これからも医学教育への忌憚ないご提言をよろしくお願いいたします。


青野 敏博,苛原 稔 編
《評 者》落合 和徳(慈恵医大教授・産婦人科学)
多様なニーズに応える産婦人科携帯マニュアル
 医療が細分化される一方,全人的医療が求められる昨今である。医学研究は光学顕微鏡から電子顕微鏡へ,やがては遺伝子研究への道筋を辿りながら進んできた。そのおかげで病気の全体像が浮き彫りになり新たな治療法が開発される。マクロの視点からミクロへ,ミクロの視点からマクロへ,これを繰り返しながら医学・医療は進歩していくのだろう。しかし医療現場では病気の全体像を見失わずに,かつ個々の病気の本質をも理解しながら,その場その場での的確な判断と対応が求められる。時間との勝負でもある。産婦人科学においてもしかりである。学問の多様化に伴い,産婦人科の成書とされる書物も枚挙に暇のない状況である。患者さんを目の前にした時にいまさら大きな教科書を紐繙く時間もなければ,教科書的な記述は役に立たないことも少なくない。その時に求められるものは,疑問に即答してくれてなおかつ診療上の指針を与えてくれるものである。徳島大学・青野敏博学長,苛原稔教授編集による『産婦人科ベッドサイドマニュアル』はまさにベッドサイドで役に立つ著書である。
医療が細分化される一方,全人的医療が求められる昨今である。医学研究は光学顕微鏡から電子顕微鏡へ,やがては遺伝子研究への道筋を辿りながら進んできた。そのおかげで病気の全体像が浮き彫りになり新たな治療法が開発される。マクロの視点からミクロへ,ミクロの視点からマクロへ,これを繰り返しながら医学・医療は進歩していくのだろう。しかし医療現場では病気の全体像を見失わずに,かつ個々の病気の本質をも理解しながら,その場その場での的確な判断と対応が求められる。時間との勝負でもある。産婦人科学においてもしかりである。学問の多様化に伴い,産婦人科の成書とされる書物も枚挙に暇のない状況である。患者さんを目の前にした時にいまさら大きな教科書を紐繙く時間もなければ,教科書的な記述は役に立たないことも少なくない。その時に求められるものは,疑問に即答してくれてなおかつ診療上の指針を与えてくれるものである。徳島大学・青野敏博学長,苛原稔教授編集による『産婦人科ベッドサイドマニュアル』はまさにベッドサイドで役に立つ著書である。
産婦人科の研修が初期研修に組み込まれ,短期間ながらも医師として婦人科疾患を持つ患者に接する医師も増えた。『産婦人科ベッドサイドマニュアル』は教科書とは一味違う,臨床上の疑問点,問題点が整理されている。第1版が刊行されたとき,これを手にしてまず思ったことはずっしりとした本だということであった。確かに見てくれよりは重いし,中身も濃い。青野教授(当時)の質実剛健さがそのままマニュアルに凝縮されていた。そしてこのたび内容も新たに,第5版が出版されることになった。1991年に初版が出版されてからすでに15年の歳月が流れている。その間に医学も進歩しまた医療体制も変わった。初期研修の必修化や産婦人科学の細分化,サブスペシャルティーの確立など大きな変化のあった時期である。このようなマニュアルを必要とする人も多様化してきた。しかし初版の読みやすい編集方針を踏襲しながらも,新たな内容が加わった。古き酒袋にスマートに新酒を注ぐ苛原教授の心意気が感じられる。
産婦人科を目指す医師のみならず,初期,後期研修医,第一線の臨床で活躍するプライマリ・ケア医,産婦人科関係のコメディカルスタッフなど,どのレベルのスタッフの要望にも応えられる内容といえよう。ぜひ白衣のポケットに忍ばせていたい1冊である。


小西 文雄 監修
自治医科大学附属大宮医療センター外科 編著
《評 者》志田 晴彦(東京厚生年金病院・外科主任部長)
消化器外科専門医をめざす人の必携書
 古い話だが,私がレジデントの5年間を過ごした1970年代後半から80年代当時は,さまざまな手技を学ぶ際のガイドブックやマニュアルが完備されておらず,上級指導医からの直接指導が主体で,「実践こそが勉強」という考え方が優勢であった。
古い話だが,私がレジデントの5年間を過ごした1970年代後半から80年代当時は,さまざまな手技を学ぶ際のガイドブックやマニュアルが完備されておらず,上級指導医からの直接指導が主体で,「実践こそが勉強」という考え方が優勢であった。
もちろん現在でも技術なしでは何もできないことに変わりはない。しかし往時と違い治療技術や術前術後管理には広い経験やエビデンスに裏付けられた標準的手技があり,これを外れたものはいかに優れたものでも今のレジデントに受けいれられるものではない。
根拠を必要とする情報化時代には多くの知識と技術の標準をコンパクトにまとめたマニュアルが待望される。医学書院からは外科レジデント必携のベストセラー『外科レジデントマニュアル』が発行され,すでに多くの研修医の支持を受けているが,本書は消化器外科医をめざす人のための続編=advanced versionといえよう。この大役をかねてから臨床研修には定評のある自治医大大宮医療センター外科が請け負ったのはまさに適役である。
内容をみると,I .総論とII .各論に分かれ,それぞれに最新情報を取り入れた特徴ある構成になっている。当科のレジデントの意見も参考にして,特に感心したところをあげてみる。I .総論では,2章の「抗生物質使用の原則」が,当然とはいえエビデンスに基づき具体的に丁寧に述べられている。4章の「インフォームド・コンセント」では押さえておくべきポイントがうまくまとめられている。他のレジデントマニュアルにはない項目であり,現在の医療環境を踏まえている点がよい。6章の「全身的合併症と周術期管理」については,採血データの正常値と,逸脱した場合の対応法・目標値などが簡潔に記載されており,項目ごとにまとめられているので使いやすい。II .各論では,癌のガイドラインや規約の記載があり,カンファランスにこれ一冊あれば使い勝手よくプレゼンテーションをこなすことができるであろう。……等々目を引く点は枚挙に暇がない。
このマニュアルが実践向けであることの裏付けは,冒頭に小西教授が述べておられるように実際に自治医大大宮医療センター外科で使っている診療マニュアルに基づいたものであるからこそであり,現場で動き回る若手医師たちの執筆を教授が監修されたものであることも心強い。まさに消化器外科専門医をめざす者が携帯するに最適の書である。
さらには診療・病院運営・学会研究活動などに忙しく,自身のレジデント時代の知識の更新に多くの時間をとれない中堅指導医が,レジデントに「逆指導」を受けることにならないためにもレジデントのみならず「指導医にも必携の書」といえよう。
最後に,Up-to-dateな内容であるだけに,今後の改訂にもたいへんなご苦労があるものと察するが,最新情報を得る日々の努力に怠りない医局の先生方であるだけに,それも杞憂に過ぎないものと信じている。


古川 壽亮,大野 裕,岡本 泰昌,鈴木 伸一 監訳
《評 者》切池 信夫(阪市大大学院教授・神経精神医学)
新しい精神療法CBASPを解説
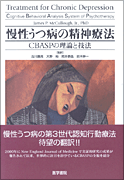 うつ病の治療において,寛解しないうつ病を経験することはまれならずあります。
うつ病の治療において,寛解しないうつ病を経験することはまれならずあります。
この場合,性格の問題にしたり,遷延性や治療抵抗性の難治性うつ病としたりして,薬物療法と支持的精神療法を漫然と続け,楽観的にそのうちよくなる,「明けない夜はない」と思いつつ,治療的ニヒリズムに陥らないようにしながら,気の重い外来治療を継続しがちになります。皆さんもこのようなことを経験したことはないでしょうか。
この本は,このような患者さんに対する治療法の1つとして,McCullough博士が提唱した新しい精神療法を概括した書です。Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy(CBASP:シーバスプ;認知行動分析システム精神療法)と呼ばれ,認知療法と対人関係療法を統合したような治療法ですが,いずれでもありません。今回,この難しい大著を翻訳し,出版された古川先生や大野先生,ならびに諸先生方の努力に敬意を表します。
本書でいう慢性うつ病とは,単極性の気分障害で,2年間以上持続し,その間に症状のない期間が2か月以上続かない状態とされています。そして治療することなしに自然寛解に達することはあまりなく,寛解しても再発することが多いといわれています。そして経過のパターンから,(1)思春期に発症して2年間以上続く軽度から中等度の気分変調性障害,(2)重複うつ病(エピソード間に回復を伴わない反復性大うつ病で,気分変調症に重複),(3)エピソード間に回復を伴わない反復性大うつ病,(4)2年間以上続く慢性大うつ病,(5)重複うつ病と慢性大うつ病の重複,の5タイプに分類されています。
この治療法は人生早期の対人関係の学習が,現在の対人関係に不適応的に働き,自己主張できず受身的,服従的,無力で苦渋に満ちた人生状況を,現在の治療者-患者関係の中で自己主張的な態度に修正していくことにより,自信にあふれ,うつ気分から解放された状況に変化させていくこととされています。
この本は,大きく3部に分かれています。第1部ではCBASPと慢性うつ病患者の精神病理と題して,慢性うつ病の定義,精神病理,経過などが記載されています。第2部ではCBASPの方法と手順と題して,実際の手技が記載されています。その内容は,治らない,変わらないとあきらめている患者に対して,変化への動機づけをしてそれを強化する戦略,状況分析,状況分析の修正段階,治療者-患者関係の中で過去の対人関係を修正していくこと,治療効果の判定などが具体的に述べられています。第3部ではCBASPの歴史と題して,CBASPの開発されてきた経緯,認知療法と対人関係療法との違いなどが記載されています。
この本を読む場合,第1部の4章「経過のパターン,併存症,心理学的特徴」を読み,まずこの治療法の適応となる患者群を知り,次いで2部の実際的の治療法に進むのがよいかもしれません。そしてまた1部に戻れば,また2部を繰り返し読みたくなります。そして3部については,認知療法や対人関係療法について知識や経験のある人が読めば,それぞれの治療法についてより理解が深まるものと思います。
CBASPは治療困難な慢性うつ病の精神療法でありますが,内容からして応用範囲が広く,今後慢性うつ病だけでなく,適応がさらにひろがる可能性があります。したがいまして,気分障害の治療に携わる人はもちろん,精神療法に興味を持っておられる多くの精神科医や臨床心理士にお勧めしたい本です。
A5・頁360 定価5,775円(税5%込)医学書院
