MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


櫻山 豊夫 著
《評 者》安藤 高夫(東京都医師会理事)
医療の担い手と医療の受け手との 信頼を創造するために
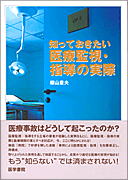 現在,国民が医療機関に求めるものは,安全かつ安心な医療,質の高い医療,わかりやすい医療の3つであると思う。とりわけ,毎日のように医療事故や感染症の記事が新聞や報道で流されることをみても,国民が安全かつ安心な医療に対する問題に最も関心があることがうかがえる。
現在,国民が医療機関に求めるものは,安全かつ安心な医療,質の高い医療,わかりやすい医療の3つであると思う。とりわけ,毎日のように医療事故や感染症の記事が新聞や報道で流されることをみても,国民が安全かつ安心な医療に対する問題に最も関心があることがうかがえる。
本書は,医学書院の雑誌『病院』で2001年1月から2004年3月まで連載された「事例による医療監視・指導」をまとめたもので,私も毎号楽しみにしていた記事であり,常に指針として参考にしてきた。著者が,高まる医療不信の中で,どうすれば医療事故を防止でき,また,医療を提供する側と医療を受ける側との信頼の創造ができるか,そして,そのような医療監視の方法を,日々模索してきたことを感じとれる書である。
著者の現場を大切にした患者および医療提供者側に立った考え,情報力,分析力,判断力,人間力,改善に対する情熱に深い感銘を受けた。
また,本書は,病院内部で自主点検できることが特徴で,それをチーム医療として行うことによって,病院全体の医療の質を上げることもでき,職員のモチベーション,さらには職員の一体感が増し,組織作りの一助にもなると思う。病院医療機能評価を受けるプロセスと似ているが,医療監視も含めペナルティではなく,安全予防の方法を標準化して,質の改善の取り組みを医療機関と一緒に担っていこうという,強い信念に基づいていることが誠に素晴らしいと感じた。
著者は,東京都が東京都医師会および東京都病院協会の協力のもと,医療安全推進委員会を設置した際の中心的役割を果たした医師で,現役の東京都福祉保健局の参事である。1996年のO-157流行に際しては,結核感染症課長として陣頭指揮にあたり,また,わが国ではじめての結核治療にDOTSを導入した。医務指導課長時代には,医療事故や院内感染の防止を行った。その後,東京都に患者の声相談窓口を設置し,2004年には,『立ち入り検査ハンドブック』も作成している。
本書は,医療機関の管理者にぜひ読んでもらいたい。医療監視を行う時のポイントを非常にわかりやすく,実際に起こった事例を通し解説している。読者にも記憶に残る多くの事例があるだろう。各章の最後に書かれた今回の事例から学びたいポイントの中に,非常に重要なことがまとめてあり,それだけを院内の標語として利用しても十分なほどである。
第1章「医療監視の実際」では,医療監視の目的と医療法の考え方,そして,立ち入り検査の留意点,また,緊急立ち入り検査に関しても述べている。行政を担当するものは,「医療の理念」に基づいて「良質かつ適切な医療を提供する体制が確保されるように努める」とされ,良質かつ適切な医療が提供されることを目的として医療監視を行っていると説いている。
第2章「事例から見た苦情対応」の中には,院内感染の事例とその対応,院内感染が疑われた時の病院の対応,さらには,インフォームド・コンセント,セカンドオピニオン,医療過誤を疑う相談事例までとりあげられている。
第3章は,「事例から見た医療事故の防止」で,医療事故を防止するための方法,事故発生後の報告などが述べられている。医療事故の防止も「あたりまえのことを丁寧に」と述べている。医療事故が発生した場合のクライシスマネジメント,あるいは,クライシスコミュニケーションについても組織管理が重要であると語る。院長は名誉職ではなく,自ら院内を巡回し,カンファレンスに参加することが大切と説いている。
第4章「事例から見た院内感染の実際」において,結核感染の防止,感染予防対策,管理体制,構造設備が言及されている。院内感染予防・防止の基本も「あたりまえのことを丁寧に」と述べている。東京都でも,『感染症マニュアル』(東京都新たな感染症対策委員会発刊)を作成している。東京都福祉保健局のホームページ上にも公開しており,必要に応じてダウンロードできる。また,都内の全病院,有床診療所に対して,『感染症マニュアル』と自己点検チェックリストを配布している。
そして第5章「医療関連各法が問題となった事例」においては,医療機器,医療法21条違反,診療録などの改ざん,医療の停止,無診察医療の禁止があげられる。
最後に著者は,医療監視は,医療法の医療提供の理念に基づき,医療の担い手と医療を受ける側との信頼関係がつくられ,良質かつ適切な医療が提供されることを目的として行われると結んでいる。法令遵守,コンプライアンスが叫ばれている現在,『感染症マニュアル』,『立ち入り検査ハンドブック』と併用して活用し,病院の運営に役立てたい書である。


福嶋 敬宜 編
福嶋 敬宜,二村 聡,太田 雅弘,入江 準二 執筆
《評 者》小菅 智男(国立がんセンター中央病院肝胆膵外科)
病理の素養を高めたい臨床医や 研究者と病理専門家との架け橋
 臨床医にとって病理診断は診療・研究の基本であり,ある意味では一般常識のように考えられている。しかし,多くの医師にとって,病理の知識は癌取扱い規約や症例報告などから得られた断片的なものの集合体でしかなかったりする。そのため,病理医の言葉を受け売りすることしかできなかったり,病理診断のニュアンスが理解できないで,臨床的な判断に困ったりすることが少なくない。病理に関する系統的な知識の欠如を痛感して教科書を開いてみても,どこから手をつけたらよいのかわからず,途方に暮れる――こんな経験をお持ちの方が少なくはないのではなかろうか。
臨床医にとって病理診断は診療・研究の基本であり,ある意味では一般常識のように考えられている。しかし,多くの医師にとって,病理の知識は癌取扱い規約や症例報告などから得られた断片的なものの集合体でしかなかったりする。そのため,病理医の言葉を受け売りすることしかできなかったり,病理診断のニュアンスが理解できないで,臨床的な判断に困ったりすることが少なくない。病理に関する系統的な知識の欠如を痛感して教科書を開いてみても,どこから手をつけたらよいのかわからず,途方に暮れる――こんな経験をお持ちの方が少なくはないのではなかろうか。
本書の編著者は米国へ留学する前の4年間を国立がんセンター中央病院の病理部で過ごした。カンファランスのたびに,私たち外科医の,時には非常識な質問に対してていねいに答えてくれ,はっきりしないことは一緒に考えてくれたりもした。また,国立がんセンター中央病院のレジデントはほとんど全員が病理をローテーションするため,日常的に病理の初心者を指導しなければならない環境にあった。
本書の特長は,編著者のそうした経験が色濃く反映されているところにある。読者として想定されているのは病理の素養を高めたいと考える臨床医や研究者であり,病理の専門家をめざす医師ではない。こうした人たちが,どんなところに興味を持ち,どんなところで壁にぶつかり,どんな疑問を持つのかといったことに焦点を合わせた書籍はほとんどない。本書は記載内容ばかりでなく構成にも配慮がなされており,読者は自分のレベルにあったところから読み進めていくことができる。また,今さら聞くのは恥ずかしいと考えるようなことでも,前のほうに戻ればたいていは書いてある。何しろ目次の最初のほうにあるのは「病理検査でわかること」とか「病理医はこんなふうに診断している」という項目である。また,最後のほうには「学会発表・論文投稿に役立つ病理写真の見せ方」などという項目まであり,まさに至れり尽くせりの感がある。もちろん,純粋に病理学的な内容についてもきちんと書かれており,最近の疾患概念の変化などについてもよくまとめられている。カラー印刷はわずか3ページにまとめられているため,見た目の派手さはないが,その分価格も抑えられており,入手しやすくなっている。
病理は臨床や研究の中で重要な位置を占めているにもかかわらず,病理医と「言葉の通じる」臨床医や研究者は意外に少ない。消化器疾患を扱う医師の数は膨大であるにもかかわらず,このような本がなかったことはある意味不思議である。本書が,数多くの「熱意ある素人」のよきガイドとなり,病理専門家との架け橋になってくれることを心から願うものである。


新日本監査法人医療福祉部 編
《評 者》武藤 正樹(独立行政法人国立病院機構長野病院副院長)
新しい病院会計準則に 対応するために必携の1冊
 2004年8月に病院会計準則が,20年ぶりに大改正された。病院会計準則は「病院の経営成績と財政状態を適正に把握し,病院経営の改善向上に資することを目的」として1965年に制定された。しかしその間,会計の世界でも,いわゆる「会計ビッグバン」のような大きな環境変化があった。こうした新しい環境変化に応じるために,病院会計準則も従来の貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)に加えて新たにキャッシュ・フロー計算書などを盛り込んだ見直しが図られることとなった。
2004年8月に病院会計準則が,20年ぶりに大改正された。病院会計準則は「病院の経営成績と財政状態を適正に把握し,病院経営の改善向上に資することを目的」として1965年に制定された。しかしその間,会計の世界でも,いわゆる「会計ビッグバン」のような大きな環境変化があった。こうした新しい環境変化に応じるために,病院会計準則も従来の貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)に加えて新たにキャッシュ・フロー計算書などを盛り込んだ見直しが図られることとなった。
さて,医療制度改革の波を受けて,病院を取り巻く制度環境も大きく様変わりをしている。特に2004年4月より全国154の国立病院・療養所が独立行政法人となった。独立行政法人化した国立病院機構病院では,施設会計が従来の官庁会計から企業会計へと変更された。そして今回の改正された病院会計準則の最初の適応病院となる。
ただ,こうした大きな会計制度の変更では,病院の現場の戸惑いも大きい。国立病院の場合,昨年を境に,それまでの現金主義の官庁会計の世界が,突然,発生源主義の企業会計のBS,PL,キャッシュ・フローの世界へと転換してしまったのだ。この戸惑いは,たとえてみれば,東西ベルリンの壁が崩れて,東ベルリンの市民が突然,西ベルリンに転がり込んだようなものだろう。
本書は,こうした意味では,独立行政法人化した国立病院機構病院の職員にとっては,新しい世界を旅する病院会計の手引書といっていいだろう。特に第5章の「病院特有の会計処理」は具体的で役に立つ。診療収入や購買関連,棚卸関連の仕訳処理ルールが豊富な例をあげて解説されているので,筆者のように会計の門外漢でも「なるほどー,こういうことか」と思って読めた。
今後,新病院会計準則は公的病院を中心に広がり,さらには医療法人病院にまで行き着くのだろう。そのとき本書は,病院の現場で働く多くの会計担当者の必携マニュアルとなるに違いない。


ECGブック
心電図センスを身につける
第2版
Making Sense of the ECG:A Hands-on Guide, 2nd Edition
Andrew R. Houghton, David Gray 著
村川 裕二,山下 武志 訳
《評 者》犀川 哲典(大分大教授・循環病態制御講座)
心電図を読むセンスを養うのに 格好の入門書
本書は“心電図の振れはどうして生じるのか”の章からはじまる17の章からなり,心拍数,調律,電気軸,P波,PR時間,Q波,QRS,ST,T波,QT時間,U波など,そしてホルター心電図,運動負荷,最後に心肺蘇生法まで付いている。各章ごとにまとめがあり要点がわかりやすく,かつ理解しやすい,心電図を読むセンスを養うのに「格好の入門書」である。要所要所でコラムあるいは囲みで異常心電図をみた時の対策について具体的記述があり,入門書でありながら実践的でもある。さらにこの本を読むことで知識の整理をし,より詳しい書物に挑戦しようかという気にさせてくれる本でもある。近年は心電図あるいは心電学に興味を持つ若い医師が少なくなり,他方で超音波検査に興味を持つ医師は増加している。しかし心臓,心機能を理解するうえでは心臓の興奮-収縮連関をよく理解することが何より重要であり,心電図検査と超音波検査は車の両輪とも言うべき心臓の検査である。その意味でも医学生,研修医,あるいは医員といった若い医師にぜひとも手にとって読んでほしい良書である。
本書は第1版も好評で10か国語に翻訳され,1997年には優れた医学書に与えられるアッシャー賞を受賞したと聞く。また,1998年の英国医学会推薦図書にもなっている。今回はさらなる好評を博するものと考える。また,訳が大変読みやすくわかりやすいと感じるのは評者のみではないと思う。訳者たちはかつて東大第二内科で一緒に心電図を勉強された先輩・後輩の間柄である。現在,心電学・不整脈領域で大変活躍している。気心の知れたお2人が,意欲を持って翻訳に取り組んでいること,加えて非常に気を配って訳していることによるものであろう。さらに随所に訳注を設けており,これも非常に貴重である。
心電図はわかりにくいと言わずに,ぜひ手にとって読んでいただき,センスを養ってほしいと思う心電図テキストである。


《Ladies Medicine Today》
婦人科内分泌外来ベストプラクティス
誰もが迷う99例の診療指針
神崎 秀陽 編
《評 者》藤原 浩(京大講師・産婦人科学)
豊かな臨床経験に裏打ちされた アドバイスで適切な診療方針を 組み立てることが可能に
 このたび医学書院から,関西医科大学産婦人科教授神崎秀陽先生の編集による『婦人科内分泌外来ベストプラクティス-誰もが迷う99例の診療指針』が刊行された。神崎先生は私が京都大学医学部附属病院で医師としての研修を開始した時の病棟の責任者であり,産婦人科医としての知識や患者さんに接すべき姿勢について一から直接ご教授いただいた恩師である。
このたび医学書院から,関西医科大学産婦人科教授神崎秀陽先生の編集による『婦人科内分泌外来ベストプラクティス-誰もが迷う99例の診療指針』が刊行された。神崎先生は私が京都大学医学部附属病院で医師としての研修を開始した時の病棟の責任者であり,産婦人科医としての知識や患者さんに接すべき姿勢について一から直接ご教授いただいた恩師である。
研修医時代に学び得た神崎先生の教えはきわめて明快で,納得のいくものであった。その一端を紹介すると,神崎先生は患者さんの診察に当たって必ず,「あなたならこの場合どのような根拠でどう判断し,どのように治療を計画しますか?」という質問をされた。私たちはこの基本的な質問にほとんど満足に答えられず,この体験は医師としての対応能力が不足している自分たちの現実を認識する貴重な経験となった。特に治療方針を決定する際には,患者さんの訴えとそこに潜む病態を正しく理解し,さらに患者さんの希望を加味したうえで医学の知識と経験をもとにバランスよく判断することの重要性を説かれていた。また,医師として責任を持てる医療を行うためには,医学知識や技術の習得はいうまでもなく,先輩諸氏が経験された貴重な症例の体験談にも耳を傾けるべきであることを強調されていた。
以上の薫陶を思い起こしながら本書を拝読すると,神崎先生の教えが随所に生かされた構成になっていることに気づく。本書は,主要な症例の全体像を読者が正確に捉えられるようになることを目的として,99例の代表的な事例を簡潔な形であげている。さらに,それらの患者の鑑別診断や治療方針の決定に必要なアドバイスを,読者が正確な医学情報に照らし合わせながら参照できるように工夫されている。また診療の概要,対処の実際,処方の実際および治療方針が筆者の臨床経験に裏打ちされた意見を含めて述べられているため,読者は具体的なイメージを持って内容を理解することができる。婦人科の内分泌系の疾患は外来での対応が重要なポイントとなるが,近くにすぐに相談できる相手がおらず,若手の医師が自分自身の判断で決定しなければならない状況が起こり得る。経験不足の医師にとっては,信頼できる先輩諸氏からの体験談が重要な情報となるが,これまでこれらの観点を重視してまとめた医学成書はほとんどなかった。この問題に対して本書では,臨床の経験から各筆者が絶対に抜かってはならないと考える重要な要点を「ここがポイント」の項でわかりやすくまとめている。いくつかの症状と訴えが重なったより複雑な症例に出会った場合でも,これらのポイントを組み合わせて考えることにより,いわゆる落とし穴にはまらない適切な診療方針を組み立てることが可能となる。この意味で本書は画期的な指針書といえる。
本書のもう1つの特徴として,婦人科内分泌学研究の面において世界的な業績を有する執筆者をそろえていることがあげられる。神崎先生は,研修医であった私たちに症例に関する質問をされたあと必ず自分の考えとその根拠を説明され,さらにはその疾患に関して何が未解決な問題点なのか,すなわち,われわれの世代が将来導き出すべき課題をあげられていた。「ぜひこの点を将来あなたたちが解明してください」と締めくくられていたのが印象的であったが,本書には臨床と研究の両面に造詣の深い執筆者からの症例を通した同様のメッセージが至るところに込められている。将来,生殖内分泌学の研究に携わる可能性のある若い医師にとって,本書は単なる臨床の指針書であるのみならず,先輩からの有意義なメッセージとの出会いをもたらす書籍でもある。
B5・頁296 定価5,250円(税5%込)医学書院
