MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


視床の神経生理学的研究の集大成
視床と精神医学汎性視床皮質投射系の役割
山口成良 著
《書 評》大熊輝雄(国立精神・神経センター名誉総長/大熊クリニック院長)
 視床は大脳の中央,扇のかなめに位置しているので,古くから脳機能の統合に重要な働きをするものと考えられてきたが,体性感覚の中継の他はその機能が明らかではなかった。本書の著者,山口成良博士が金沢大学精神医学教室で,秋元波留夫先生のもとで視床の研究をはじめられた1950年頃は,脳波の発見などに触発されて精神医学に神経生理学的研究が導入されはじめた黎明期であった。特に脳機能の神経生理学的研究の契機となったのは,汎性視床皮質投射系の発見,すなわち視床非特殊核の反復的電気刺激により両側大脳皮質の広汎な領域に漸増電位が誘発され,視床が大脳皮質を統合する機能を持つことが神経生理学的に実証されたことであった。
視床は大脳の中央,扇のかなめに位置しているので,古くから脳機能の統合に重要な働きをするものと考えられてきたが,体性感覚の中継の他はその機能が明らかではなかった。本書の著者,山口成良博士が金沢大学精神医学教室で,秋元波留夫先生のもとで視床の研究をはじめられた1950年頃は,脳波の発見などに触発されて精神医学に神経生理学的研究が導入されはじめた黎明期であった。特に脳機能の神経生理学的研究の契機となったのは,汎性視床皮質投射系の発見,すなわち視床非特殊核の反復的電気刺激により両側大脳皮質の広汎な領域に漸増電位が誘発され,視床が大脳皮質を統合する機能を持つことが神経生理学的に実証されたことであった。
視床と臨床精神医学との関連にも言及
本書は,わが国における優れた精神医学者であり,汎性視床皮質投射系研究の先駆者である山口成良博士が,1950年頃から長年にわたって金沢大学を中心に行った視床の神経生理学的研究の集大成であり,さらにその基礎の上に,視床と臨床精神医学との関連について論を進められたものである。すなわち,第1章では,金沢大学で行われた汎性視床皮質投射系に関する実験的研究が順を追って詳細に述べられ,これが本書の約3分の2を占めている。当時,教室主任であった秋元波留夫先生は実験てんかんの研究をしておられ,視床が体知覚の求心経路の中継核であるとすれば,それはてんかん発作の起始部位となり得るかもしれないと考えて,山口博士とともに無麻酔無拘束の動物での実験をはじめられたとのことである。金沢大学では,イヌ,ウサギ,ネコなどについて,急性実験だけでなく無拘束動物についての実験も行われ,その研究は世界でも例をみないほど体系的,包括的なものであり,本書の第1章を通読すると,現在の視床生理学の全貌を把握することができる。無拘束動物で視床汎性投射核を刺激すると,漸増電位とともに自然睡眠が出現するとの発見もこの研究の中から生まれた。
第2章は,その後経験されたクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)症例の視床の神経病理学的所見から,CJDに特徴的な周期性・同期性発射の発生機序を汎性投射系との関連から考察されたもので,いわば第1章の実験的研究の臨床的発展の1つである。
第3章では,古くから臨床的に知られている視床性失語,視床性痴呆などに関連して,視床が言語,認知,記憶,知能などの高次神経機能に果たす役割について,最近の文献を引いて展望が行われている。
第4章では,統合失調症と視床の関連が,最近急速に発展している画像診断学の所見を中心に展望されており,形態MRI,機能MRI,SPECTなどを用いた最新の研究成果が紹介されている。ここでは倉知正佳氏,地引逸亀氏ら金沢大学関係の方々の研究も多く引用されており,Carlssonの統合失調症における視床フィルター仮説にも言及されていて,統合失調症研究の全貌を理解するためにもきわめて有用である。
本書で視床の機能への理解を深めてほしい
最近私たちは,視床の形態については,CT,MRI画像などの観察の際にごく日常的に接しているが,視床の機能についての知識は必ずしも十分ではないと思われる。評者は精神医学者,神経学者,研修医の他,多くの方々が本書を一読され,視床の機能について,さらには脳の働きとこころについての理解を深められることを期待したい。実験動物の誘発電位などにはやや縁が遠い方は,場合によっては本書を「まとめ」,「統合失調症」,「高次神経機能」などの順に読まれれば,第1章がよりよく理解できるかもしれない。「視床と精神医学」は古くて新しい課題である。私事にわたって恐縮であるが,評者の亡父で精神医学者であった大熊泰治(本書の中でも引用していただいている)は,1934年(昭和9年,当時岡山医大助教授)の第33回日本神経学会(現在の精神神経学会)総会で「視床の研究」と題する宿題報告を行っている。亡父を知る方々によると,父はそれまで神経解剖学,神経病理学の研究を行ってきたが,これからは生理学の時代だと話していたとのことである。残念ながら父は志半ばにして早世したが,父がもし本書を読むことができたなら,視床研究が生理学的にはほぼ完成し,さらにそれを超えて神経画像学,受容体抽出にまで進展している現状を知って,どんなに感激することであろうかと思う。


他に類を見ない,体外式超音波を用いた消化管診断テキストが登場
消化管超音波診断ビジュアルテキスト春間 賢 編
畠 二郎,他 著
《書 評》千葉 勉(京大教授・消化器内科学)
先入観を打ち破く
 「消化管の超音波診断」と言うと,誰もがまず「超音波内視鏡」を考えるに違いない。しかし本書はそうではなく,消化管の「体外式」超音波による診断用テキストである! 超音波診断学の教科書は山ほどあるが,私が知る限り,「体外式」超音波を用いた消化管の診断テキストは,他に見たことがない。おそらくこれが日本,いや世界でも初めてのテキストではないだろうか?
「消化管の超音波診断」と言うと,誰もがまず「超音波内視鏡」を考えるに違いない。しかし本書はそうではなく,消化管の「体外式」超音波による診断用テキストである! 超音波診断学の教科書は山ほどあるが,私が知る限り,「体外式」超音波を用いた消化管の診断テキストは,他に見たことがない。おそらくこれが日本,いや世界でも初めてのテキストではないだろうか?
言うまでもなく,また編者の春間先生ご自身が述べておられるように,「体外式」超音波診断法の最大の特徴は,その手軽さと,患者さんに苦痛を与えない「非侵襲性」である。したがって,外来でちょっと見る手段として,また救急外来でのfirst lineの検査法として,CTなどと比較してもずっと簡便である。また内視鏡や,さらには透視検査と比較しても患者さんにとってはずっと楽であり,特にイレウスなど消化管透視が禁忌の人にも施行できる。ところが,消化器専門医の中でさえ,「消化管は管腔臓器であり超音波検査はあまり適していない」という先入観がなんとなく蔓延しているように思える。本書はそうした私たちの先入観を打ち破いて,体外式超音波検査が消化管のfirst lineの診断法として極めて有用であることを見事に示している。
症候ごとに分けられた項目で気軽に読める
本書の特徴は,とにかく読んでいておもしろいことがあげられる。また,項目が疾病ごとではなく,「胸やけ」「嘔吐・食欲不振」「下腹部痛」「便秘」などと各症候ごとに分けられているので,臨床の現場に即しており,そのためにかえって気楽に読める。おもしろいところを拾い上げてみても,アカラシアの固有筋層の肥厚とか,AGMLにおける層構造の保たれた全層性の肥厚,SMA症候群の十二指腸の見事な狭搾像,さらには一瞬,アニサキスそのものが見えるのでは,と思うようなアニサキスによる粘膜下層を中心とした肥厚など,盛りだくさんである。また,感染性腸炎では起炎菌が同定できない場合が多いが,本書では,サルモネラ腸炎として上行結腸の層構造の保たれた肥厚例が,またアメーバ腸炎やO157腸炎では,層構造が不明瞭な肥厚例が示されており,鑑別診断の一助となることが示されている。読者の方々も「そういえばそうだ」と思われるかもしれない! このように本書を読むと,「よし自分でも試してみよう」と思われる方がきっと多数おられるに違いない。
最後に,本書では,著者らが最も得意とする消化管運動異常に対する機能検査法としての超音波検査法の項目が設けられている。最近わが国でも,functional dyspepsiaや過敏性腸症候群など,機能性消化管運動異常に対する関心が深まるなか,本法は消化器病診断の新しい分野を切り開くものとして期待されているが,本書は,そうした将来をも見据えた著者らの考え方が伺える,一本筋の通った快著である。


肝疾患を診る機会のあるすべての医師に
肝疾患レジデントマニュアル柴田 実,関山和彦,山田春木 編
《書 評》上野文昭(大船中央病院・特別顧問)
臨床現場での疑問に即答してくれるマニュアル
 このたび上梓された「肝疾患レジデントマニュアル」は,実質的に5年前に刊行された「これからの肝疾患診療マニュアル」の改訂新版である。当時第一線で活躍中の比較的若手の臨床医によって執筆された肝疾患診療マニュアルは,実践的でユニークな内容により高い評価を得た,文字通り「これからの」マニュアルであった。改訂にあたって多くの執筆者が残り,新たに加わった執筆者も同年代の気鋭の肝臓臨床医である。5年の歳月を経て,自分で行うだけでなく教えることの責務が重くなったためであろうか,臨床現場での疑問に即答してくれるわかりやすく懇切丁寧なマニュアルに変貌を遂げている。
このたび上梓された「肝疾患レジデントマニュアル」は,実質的に5年前に刊行された「これからの肝疾患診療マニュアル」の改訂新版である。当時第一線で活躍中の比較的若手の臨床医によって執筆された肝疾患診療マニュアルは,実践的でユニークな内容により高い評価を得た,文字通り「これからの」マニュアルであった。改訂にあたって多くの執筆者が残り,新たに加わった執筆者も同年代の気鋭の肝臓臨床医である。5年の歳月を経て,自分で行うだけでなく教えることの責務が重くなったためであろうか,臨床現場での疑問に即答してくれるわかりやすく懇切丁寧なマニュアルに変貌を遂げている。
ベッドサイドの診断学から検査に飛ぶ前に,救急診療の項が新設されたのは健全な構成であり,救急診療に携わる機会の多い研修医にとって福音であろう。それに続く検査・IVR,疾患各論も5年間の進歩を盛り込みながらUpdateされている。冗長な文章を極力避け箇条書きに近いような文面も,図表の多さとともに見やすさをさらに倍化させている。また,画像写真の鮮明さは特筆ものであろう。もともと画像アトラスとして作成されたものならいざ知らず,このサイズの普通紙でもこれだけの画質が得られることは驚嘆に値する。また随所に挿入された囲み記事が興味深い。本書に無機的な実用書としてだけではなく知的好奇心を満足させる書籍としての価値を付加している。
すぐに解答を得られるが悩み考え学ぶ姿勢も忘れたくない
さて批判すべき点を探すのが難しい。本書の明快さと親切さは,若手医師が困った時にすぐに解答を得ることができるという点で,もちろん美点であろう。しかし逆説的に言うならば,研修医の教育という観点からはこれが欠点かもしれない。優れたエキスパートが即座に教えてくれるという上意下達型の問題解決により,悩み考え学習するという姿勢がスポイルされる危惧もあろう。しかし本書の目的から考えればそこまで配慮する必要性がないのは当然のことである。総じて言えば,本書は十分に新しくそして必要な知識が網羅されている魅力的な肝疾患診療マニュアルである。本書をお奨めしたい対象は,研修医はもちろんのこと,肝疾患を診る機会のある実地医家,病院勤務医などが中心であろう。白衣のポケットに簡単に入るコンパクトなサイズでありながら,これだけ充実したマニュアルを完成した執筆者そして特に編者の熱意と努力に最大級の賛辞を贈りたい。


がんの臨床試験に関する重要項目が目白押し
米国SWOGに学ぶがん臨床試験の実践
臨床医と統計家の協調をめざして
Stephanie Green,Jacqueline Benedetti,John Crowley 著
福田治彦,新美三由紀,石塚直樹 訳
《書 評》垣添忠生(国立がんセンター総長)
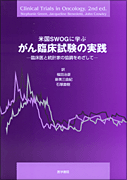 このたび医学書院より「米国SWOGに学ぶ がん臨床試験の実践」が刊行された。本書は,Stephanie Green(SG),Jacqueline Benedetti(JB),John Crowley(JC)三統計家による名著「Clinical Trials in Oncology, 2nd ed.」の訳書である。待望久しかった訳書が,それも2nd ed.が出版されてすぐに刊行されたことを喜びたい。
このたび医学書院より「米国SWOGに学ぶ がん臨床試験の実践」が刊行された。本書は,Stephanie Green(SG),Jacqueline Benedetti(JB),John Crowley(JC)三統計家による名著「Clinical Trials in Oncology, 2nd ed.」の訳書である。待望久しかった訳書が,それも2nd ed.が出版されてすぐに刊行されたことを喜びたい。
臨床試験では大きく立ち遅れている日本
わが国の医学研究のレベルは高く,疾病の本態解明や新しい現象の記述,その解明などで,世界の医学に多くの貢献をしてきた。ところが,薬物の効果や医療機器の評価など,患者を対象にした医学研究,いわゆる臨床試験の面では,従来大きく立ち遅れていた。その理由としては,大学に腫瘍学の講座がない,生物統計学者の絶対数が足りない,臨床試験を支える基盤が欠如していた……などいろいろあるだろう。しかし,世界的にもevidenceに基づいた医学,医療の展開の重要性が日々強まっている時,わが国のこれまでの事情がこのままであってよいはずはない。米国では,特に新薬の有効性や毒性などの評価に占める臨床試験の重要性は早くから認識されていた。全米にはいくつもの巨大な臨床試験グループがあるが,SWOG(Southwest Oncology Group)は中でも最も大きく,45年以上の活動の歴史を持つ。
原著者の1人SGが献辞の中で「過去45年以上にわたってSWOGの臨床試験に参加してくださったすべての患者さんへ:あなが方が私たちの試験に協力してくださったことは,がんとの戦いに対して計り知れない助けになりました」と述べている。この認識は重要である。つまり,患者の協力を得て,研究者とのパートナーシップのもとに,例えば抗がん剤やその組合せの有効性,安全性を評価する。そして,それらの積み重ねによって標準的な治療が次々と書き換えられていく。米国中心のがんの臨床試験のダイナミックな展開は,研究者のこの思想と,それを支える強固なインフラストラクチャーに秘密がある。
日本にもJCOGが発足
わが国においてもがんの臨床試験を遂行するためにデータセンターの必要性を痛感した下山正徳元国立がんセンター東病院長などが中心となり,厚生省,科学技術庁などの助成金を得て,JCOG(Japan Clinical Oncology Group)が発足した。そして,今やわが国を代表する臨床試験グループに成長した。本書は現在のJCOGの活動の事務局機能を支える福田治彦,新美三由紀,石塚直樹氏を代表として翻訳されたものである。また,本書に推薦の序を書いている東京大学医学部・生物統計学/疫学・予防保健学教授の大橋靖雄先生もまた,わが国に臨床試験を定着させるうえで大きく貢献された1人である。本書の目次に目をやると,統計的概念,臨床試験のデザイン,多群の試験,中間解析とデータモニタリング,データマネジメントと品質管理など重要項目が目白押しだ。眼から鱗が落ちる人も多いのではないかと期待する。
本書を,わが国でがん臨床に携わる医師,看護師はもちろん,製薬企業に働く皆さん,生物統計学に興味を持つ学生など,多くの方々に推薦したい。


不幸にして自殺が起きてしまったその後のために
自殺のポストベンション遺された人々への心のケア
高橋祥友,福間 詳 編
《書 評》広瀬寛子(戸田中央総合病院・看護カウンセリング室)
ポストベンションの実践から生まれた本
 編者のお一人の高橋祥友先生は精神科医として,これまでも数多くの自殺に関する著書を出版しており,自殺の実態・予防・危機介入など,自殺に関する研究・臨床・教育・啓蒙活動の第一人者である。現実には自殺予防のためにどれだけ努力しても自殺は完全には防げない。そのように不幸にして自殺が起きてしまった場合は,今度は遺された人々へのケアが課題となる。
編者のお一人の高橋祥友先生は精神科医として,これまでも数多くの自殺に関する著書を出版しており,自殺の実態・予防・危機介入など,自殺に関する研究・臨床・教育・啓蒙活動の第一人者である。現実には自殺予防のためにどれだけ努力しても自殺は完全には防げない。そのように不幸にして自殺が起きてしまった場合は,今度は遺された人々へのケアが課題となる。
本書は,そのような自殺した人の周りの遺された人々へのポストベンションに焦点を当ててまとめられた本である。著者らは,防衛医科大学校,自衛隊中央病院,陸上自衛隊衛生学校に所属し,自衛隊員の自殺が起きた場合に現場からの要請に基づいて,精神科医と心理職からなる2-3名のチームで出向き,ポストベンション活動を行ってきた。その実践から生まれた本である。
さて,「ポストベンション」という聞き慣れない言葉に戸惑っている方もいらっしゃると思うが,この意味は「事後対応」であるという。不幸にして自殺が起きてしまった後に,遺された人々に及ぼす影響を最小限度にするために,心のケアを行うことを指している。
各章に「要約」と「まとめ」を入れた頭の中を整理しやすい構成
本書の構成は以下の通りである。「第1章 ポストベンションとは何か」では,自殺の現状とリスクアセスメントを取り上げた後,ポストベンションの概要について述べ,「第2章 遺された人々に起こりうる反応」では,自殺が起きた後に個人と集団に現れる可能性のある反応について解説している。「第3章 職場で自殺が起きたとき:対応の原則」では,職場がすべきことと,外部から専門家が入る場合の職場に入る時の注意点などについて記している。ポストベンションには状況や対象者に応じて個別ケアと集団を対象としたケア(ディブリーフィング)をうまく組み合わせて行うことが重要であり,それぞれについて「第4章 個別のケア」と「第5章 グループに対するケア」で取り上げている。著書らは「ポストベンションは緊急事態を経験した人に対するファーストエイドであって,専門的な精神科治療の代替品ではない」から,「フォローアップのないポストベンションは,標準的なポストベンションとさえ言えない」という。そのような姿勢から「第6章 フォローアップ」が記述されている。「第7章 自殺予防教育」ではポストベンションの最終段階としての自殺教育について解説している。本書は主に職場で働く人たちへのケアとして書かれているが,「第8章 遺族への対応」では遺族へのケアについても触れられている。「第9章 ポストベンションの適応と禁忌」では,ポストベンション活動そのものが禁忌となる場合はないという立場で,実践するうえで遭遇する問題点を整理している。最後に「第10章 事例」では自衛隊の事例に止まらない広範囲の領域におけるポストベンションの事例について,ていねいに解説されている。
章立てはもちろんであるが,細部まで細やかな配慮がなされており,各章は「要約」ではじまって「まとめ」で終わるという,読者が頭の中を整理しやすい形に構成されている。
これまでの現実を認識し医療者にできる対応が理解できる
要請された専門家がポストベンションの導入に当たってどのように職場の人たちに説明するか,その説明文を具体的に記述してあるなど,痒いところに手が届く式の親切な記述である。しかし,だからといって,本書はマニュアル本ではない。著者らは何度も,その都度個別に対応することの重要性を警告する。また,この通りに行えば誰でも簡単にできるものではなく,精神科医を含めた外部の専門家が2名以上必要なことや,精神医学や心理学の専門家であってもトレーニングを受けなければできない,やってはいけないことがよくわかる。自殺が起きると,新聞やテレビではセンセーショナルに報道される。一方,そのような報道とは対照的に,現場ではできるだけその事実を隠そうとしてきた。病院でさえも入院患者が自殺すると,その事実は隠蔽される。他の患者はもちろん,周りの医療者に対してさえ事実が伝えられず,憶測ばかりが流れていく。こういう対応は間違っている,明らかになっている事実は淡々と伝え,隠さず取り組むことが大事だと本書は教えてくれる。
また,遺された人たちの中にさまざまな感情が起きることは自然である。そういう人たちが十分にケアされてこなかった現実があり,遺された人たちが専門家に助けを求めることの大切さや,自分たちができる対応について教えてくれる。
わが国でも自殺のポストベンションが受け入れられ,広がっていくことを願わずにはいられない。本書はまさに精神科医や心理職などの専門家だけではなく,看護師やMSWなどの医療スタッフ,引いては職場の管理職やメンタルヘルス担当者などにぜひ,読んでいただきたい1冊である。
A5・頁208 定価2,730円(税5%込)医学書院
