〔連載〕医者が心をひらくとき
A Piece of My MindJAMA(米国医師会誌)傑作エッセイ集より
|
(前回2507号)
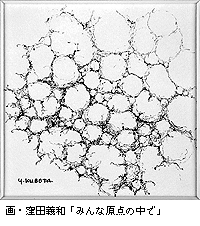 彼は75歳か80歳になっているし,もう開業もしていないが,この郊外のコミュニティでM医師のことを知っている患者や医師はいまでもたくさんいる。地元の新聞が最近彼についての記事を載せたが,記者は若き日のM医師の小児科医としての研修時代に焦点を当てていた。彼がインターンだった頃は,ポリオが猛威をふるい,ボストン中の病院が「鉄の肺」を使わなければならない患者であふれかえっていた。M医師は,フランクリン・デラノ・ルーズベルトがポリオにかかったときのことをいまでも覚えているし,ジョーナス・ソークとアルバート・サビンがワクチンの成功を報告したローマ会議にも出席していたという。
彼は75歳か80歳になっているし,もう開業もしていないが,この郊外のコミュニティでM医師のことを知っている患者や医師はいまでもたくさんいる。地元の新聞が最近彼についての記事を載せたが,記者は若き日のM医師の小児科医としての研修時代に焦点を当てていた。彼がインターンだった頃は,ポリオが猛威をふるい,ボストン中の病院が「鉄の肺」を使わなければならない患者であふれかえっていた。M医師は,フランクリン・デラノ・ルーズベルトがポリオにかかったときのことをいまでも覚えているし,ジョーナス・ソークとアルバート・サビンがワクチンの成功を報告したローマ会議にも出席していたという。
そして,小児科医であるM医師は,そうと企図したわけではないが,ある日,私のことを本当の医師に変えたのだった。いまとなっては遠い昔の話だが,私が内科医として開業して数か月しかたっていなかった頃のことだ。患者の1人が私に往診を依頼した。とても家を出られる状態ではないし,子どもの1人も病気ということだった。他の2人の子が最近水痘にかかったばかりなので,自分も水痘に罹ったらしいという。往診するのは気が進まなかったが,彼女は新しい患者だった(私の患者は皆新しい患者だった)し,彼女に気に入ってもらえば,友だちに私のことをよく言ってくれるかもしれないと私は期待した。
彼女の住まいは,忙しく車が行き交う道に面し,駐車は,違反になるどころか,危険でさえあった。自分の車を彼女の家の裏にあるスーパーマーケットの駐車場にあずけ,彼女の家のドアまでブロックを一周して歩いたことを,私はいまでも覚えている。彼女の家のドアには鍵はかかっていなかった。
患者は階上の部屋に寝ていた。確かに重そうに見えたが,体温は101度しかなかった(体温に華氏を使っていた時代だった)。口腔粘膜に水疱や膿疱はなく,呼吸器合併症の徴候も認められなかった。診断は水痘で間違いなかったが,病変は皮膚に限られていた。
3人の小さな子どものうち病気だったのは1人だけだった。親指を口にくわえた男の子が母親と同じ部屋の安楽椅子にちぢこまっていた。片腕にすり切れたテディ・ベアと毛布を抱え,もう一方の手で始終皮膚をかいていた。顔中に水痘の皮疹ができていたが,子どもは顔もかきむしっていた。私は子どものことを母親に聞いたが,後で小児科の医師が3人の子どもたちを診にくるという返事だった。M医師の名は有名だったし,彼が往診にくると聞いて私は少し驚いた。
他の2人の子どもは,母親のベッドの足元で「ピック・アップ・スティックス」*をして遊んでいた。それまで,「ピック・アップ・スティックス」が暴力的なゲームだと思ったことは一度もなかったが,この2人の子どもの遊び方を見ていて認識を新たにした。私は,おかあさんの肺と心臓の音を聞きたいから,2人に他の部屋で遊ぶように言った。肺はまったく正常で,心臓も,ごく軽度の頻脈があるもののリズムも正常で,心配すべき所見はなかった。
「ご主人はどちらにいらっしゃるんですか?」
と私は聞いた。
「ご主人にいてもらわないとだめですよ」
「ミルウォーキーです。会社の仕事で。あと3日しないと帰ってきません」
デラウェア州ウィルミントンは企業の街だった。街に数ある研究施設は,どこも大学院を出たばかりの若い研究者をたくさん雇い入れていた。彼らは国中いたるところからやってきた。私が,ウィルミントンで生まれたという人に初めて出会ったのは,この街に暮らして1年ほどたった後のことだった。手伝ってくれる母親とか姉妹がいないかなどと聞く必要はなかった。誰か助けてくれる人がいたとしたらもうとっくに来ていたはずだったし,誰も頼れる人がいないのは明らかだった。
「ご主人はあなたがご病気だということをご存じなのですか?」
と,私は聞いた。
「ええ,もう知らせました」
彼女が答えた。
「主人は,水痘なんて子どもしか罹らないと思っていた,ですって。私の両親が過保護に私のことを育てたせいだって。主人の言うとおりだわ」
「アスピリンを飲むように」
と私は勧めた(そう,アスピリンと言ったのだ。当時は当たり前だったし,誰もいけないことだなどとは知らなかった)。
「それと,フルーツ・ジュースとかで,たくさん水分を取るようにしてください。それから,たっぷり休むように」
子どもたちが部屋に戻り,また,暴力的な遊びを始めていた。
「この2人が最初にかかったんです」
と,彼女は言った。
「2人が,トミーと私にうつしたんですけれど,子どものときにかかっておけばよかった」
ドアにはさまったおもちゃを足でよけると,私は彼女の家を後にし,車に戻った。車を運転しながら,彼女に本当に必要なのは医師ではなくて配偶者か母親だと思うと,いい気持ちはしなかった。彼女に請求書を送るときにはやましく感じるだろうことがわかっていた。
気がかりだったので,私は,次の日も彼女の様子を見に行った。訪問看護婦を頼むことを彼女に勧めるつもりだった。
「本当によくなりました」
と彼女は言った。
「子どもたちのお昼に,まともなものを食べさせられましたし……,チキン・サンドイッチを作ったんです。昨日は,冷たいシリアルにマシュマロ・クリームをかけて食べさせたんですよ。トミーもとても元気になりました。M先生が,サンプルだからお金はいらないって,かゆみ止めのお薬を出してくださったので,トミーはかきむしるのをやめましたし,チキン・サンドイッチも食べたんですよ」
「M先生がしてくれたのはそれだけではなかったんです」
彼女は顔を輝かせながら言った。
「とてもすばらしいことをしてくださったんです」
彼女の口調に少しでも私を責める響きがあったのかどうか,私はいまでも自問することがあるが,彼女が私を責めていたとは思わない。
「診察が終わった後,M先生は裏のスーパーマーケットまで行って,いろいろなものを買ってきてくださったんです。ミルク,ジュース1クォート,バーベキュー・チキン,そしてバナナ。私,本当に驚いてしまって! でも,先生ったら,私にお金を払わせてもくれなかったんです。とてもすばらしいと思いません? 本当にすばらしい先生だわ」
私は,なぜ,彼女と子どもたちの夕飯の心配をしなかったのだろうか? 彼女たち一家がきちんと夕飯が食べられるようにするということを,私は考えなければならなかったはずだった。それなのに,そして,自分も母親の1人だというのに,私は,一家の夕飯のことに気が回らなかった。私は,成人の水痘例について自分が聞き,読んだ知識を思い出そうということに気を取られすぎていた。私にわかっていたのは,成人例は小児例より重症化しやすいこと,しかし肺炎や髄膜炎を起こしさえしなければ後遺症を残すことなく回復すること,だった。
M医師にも,そんなことはわかっていた。実際,水痘についての当時の彼の知識の広さは,私がこれからどんなに学んでもかなわないほどのものがあったろう。しかし,彼はそれだけでなく,子どもたちが空腹であること,そして母親が手助けを必要としていることを見てとり,子どもたちに夕飯を用意し,母親を手伝ったのだった。
そして,私は何もしなかったのだ。
患者の水痘は後遺症を残すことなく速やかに治癒したが,私には後遺症が残った。その後遺症のおかげで,私は,もっとまともな医師になることができた。何年か後に,私は,このときの話をM医師にしたことがあるが,彼は何も覚えていなかった。しかし,私はいまでも覚えているし,これからもこのときのことは絶対に忘れないだろう。
M医師は,やがて,「大きくなりすぎた」患者を私に紹介してくれるようになった。思春期に達したM医師の患者を受け持つことは嬉しかったし光栄に思っていた。しかし,M医師の名をもらい,ファースト・ネームやミドル・ネームがジョンとかジョアンナとかいう患者を受け持つのは例外だった。彼らを受け持つ責任は私には重すぎるように思え,私は憂鬱な気持ちにさせられた。というのも,M医師にはとてもかなわないということは,私には十分すぎるほどわかっていたからだ。
*細い棒を積み上げ,他の棒をくずさないようにして1本ずつ取っていくゲーム。
●本連載の単行本好評発売中本連載の元となっている『A Piece of My Mind』の日本語版『医者が心をひらくとき』(李啓充訳,上下巻各2000円+税)が,弊社より刊行されました。 |
