連載 クリニカル・クラークシップ
-新しい医学教育への挑戦 第2回
始動へ向けて

「いつ始めるのか。医学教育が社会に対して負っている責任を考えれば,それは今すぐにです」昨年11月,各大学の教育担当者が参集したクリニカル・クラークシップ(以下,クラークシップ)をテーマに開催された公開討論会の壇上で,黒川清氏(東海大医学部長)の言葉に力がこもった。東大教授を辞し,東海大医学部長に就任してから,わずか1年3か月でクラークシップの全面的導入を果たした黒川氏の言葉にはおのずと説得力があった。この日の講演後,黒川氏の元には共感を示すいくつもの手紙が届いたという。
不遇の時代続いたクラークシップ
日本でも以前から一部の教育者たちの間では,臨床能力を重視した効率的な教育方法として,クラークシップが注目されていた。しかし,医学生が一定の医行為を行なうこの実習法は,「医師でなければ医業をなしてはならない」という医師法の定めとの整合性が問題となり,大学側はその導入に長く消極的であった。卒前教育におけるクラークシップ導入の機運が高まったのは,1991年の厚生省臨床検討委員会最終報告以降のことである。この報告は,「医師法で無免許医業罪が設けられている目的は,患者の生命・身体の安全を保護することにある」のだから「医学生の医行為も,その目的・手段・方法が社会通念から見て相当であり,医師の医行為と同程度の安全性が確保される限度であれば,基本的に違法性はない」との見解を示すと同時に,「医学生の臨床実習において許容される基本的医行為」の例示も行なうなど,医師法との関係を明確にした。
これを受けて多くの大学でクラークシップの導入が検討されるようになったが,病床数の不足,マンパワー不足,教員の研究指向など,多くの問題があり決してスムーズな導入がなされたとは言えない。ある大学教員は,「クラークシップの全面的導入は日本の貧弱な教育環境では不可能」とすら言った。実際,ほとんどの大学では一部の診療科の実習にクラークシップを導入したに過ぎなかった。
しかし,1997年10月,東海大学はクラークシップを全面的に導入。大きな注目を集めることとなり,いま再び「クリニカル・クラークシップ」への関心が高まってきている。文字通り「すぐに」導入に踏み切った東海大でのクラークシップ準備過程を追ってみた。
始めなければ前に進めない
 1996年7月,東海大医学部長に就任直後の黒川氏は,医学教育の責任者を務める長村義之氏(副医学部長)らと話し合いを重ねていた。「ゴールが10だとすれば,2のレベルで結構だ。そのかわり少しずつ問題点をフィードバックしてレベルアップしていこう。初めは不完全に決まっているけれども,始めない限り前には進めない」。黒川氏の打ち出した方針は明快だった。長村氏はその「明快さ」に共感したという。
1996年7月,東海大医学部長に就任直後の黒川氏は,医学教育の責任者を務める長村義之氏(副医学部長)らと話し合いを重ねていた。「ゴールが10だとすれば,2のレベルで結構だ。そのかわり少しずつ問題点をフィードバックしてレベルアップしていこう。初めは不完全に決まっているけれども,始めない限り前には進めない」。黒川氏の打ち出した方針は明快だった。長村氏はその「明快さ」に共感したという。
早くも7月中に長村氏を委員長として「クリニカル・クラークシップ推進委員会」(以下,クラークシップ委員会)を組織した。医学部全体での導入を前提としているため,内科,外科の各部門・部署から約20名の委員を選出,召集した。
クラークシップの本質は,「アメリカで行なっている学生の臨床実地教育」であり,学生が診療チームの一員として実際の診療に参加しながら効率的に臨床医学を学ぶことにある。同委員会では,初めから,いかに学生を含めた医療チームを作るかという課題の検討に入った。若手の医師2名(シニアとチーフ)と学生2名の組み合わせ,側面からアテンディング・プリセプターと呼ばれる指導者が支援するというチームの雛形を作り,「各内科,各外科の医師数から算定し,それぞれ,『何チーム作ってください』と各部門・部署に依頼したが,『なぜそういうチームを作らなければいけないか』という共通の理解を確立するにはかなりの時間がかかった」と長村氏は振り返る。
学内での基盤作り
東海大にはクラークシップ導入を可能とする下地があったと言われている。以前から学生の交換留学制度や海外との定期的な教員間の交流を充実させてきたため,他校に比べ米国型の医学教育と接する機会が豊富で,留学経験者も多いこと。また,伝統ある多くの大学では「教授を頂点とした講座制が堅固で,新しいシステムを導入することができない」のに対し,学部開設から今日まで25年しか経っていない「若い」学部である東海大医学部は,「比較的,制度改革に対して抵抗が少ない」(黒川氏)ことがその理由だ。「しかし,以前から『臨床実習のあり方をどうするか』などの検討はされてきたが,『クリニカル・クラークシップ』という言葉を用い,それを医学部教育の根幹に据えようとしたのは,黒川医学部長が初めてだった」と,ある教員は振り返る。
クラークシップ導入の準備作業に携わった谷亀光則氏(腎代謝内科講師)も「米国への留学経験といっても,せいぜい3-6か月というような学生時代の短期留学経験であったり,『研究』での留学経験である場合が多く,米国で本格的な臨床研修を受けた人材は必ずしも多いとは言えない」と指摘する。実際,谷亀氏を含めてクラークシップ導入への準備作業を担った教員たちの中に,臨床留学の経験者が数多くいたわけではなく,また,そもそもクラークシップとはどういうものかの理解には当初かなりのばらつきがあった。
いったいクラークシップとは何か。それは何をどう行なうことなのか。学内で共通 の基盤作りが,まず求められたのだ。
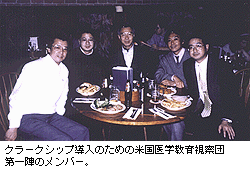
米国医学生の影となり……
「理屈で言っても実体験しなければわからない」黒川氏のアイデアは文字通り,1人でも多くの教員にクラークシップを実体験させることであった。8月の初旬にはクラークシップ委員会に属する5名の教員が召集された。松崎松平氏(内科教授)を団長とする米国医学教育視察団(以下,視察団)として米国の2大学へ派遣するためだ。米国への派遣を告げられたメンバーの1人である谷亀氏は「あまりに突然で驚いた」という。視察団は3名の内科医と2名の外科医で構成され,在日米軍病院で1年間のインターン経験がある団長の松崎氏を除いて,米国式の臨床研修を受けた経験のあるものはいなかった。派遣された5人には,その後の東海大クラークシップの導入に際して,その「核」となり,新しい教育法を現場に根づかせ,軌道に乗せるという役割が期待されており,責任は重大だった。谷亀氏らは急いで米国の臨床教育について勉強を始めたが,当時,日本語で書かれたものは赤津晴子氏の『アメリカの医学教育』(日本評論社刊)くらいしかなく,また,英書にはわかりやすく書かれた文献が見つからずに苦労をしたという。
「ともかく,米国の医学生の影となり,彼らの週間スケジュールに徹底的につきまとってやろう。これを学生にやらせるのであれば,まずは自分たちがそれをやってみなければ」谷亀氏は当時の心境をこう語る。視察団のメンバーは自らがクラークシップを「体で覚える」ために米国へ向かった。当初,出発日は8月下旬を予定していたが,先方との日程調整が遅れたため,9月30日にまでずれ込んだ。行き先はミシガン大とUCLA(カリフォルニア大ロサンゼルス校)であった(谷亀氏の談話を別掲)。
クラークシップ知る人材を蓄積
長村氏は「この視察団がクラークシップを始めるにあたってよい情報をくれた。実体験してきた人間が増えると,周囲のクラークシップへの理解は急速に進む」と指摘する。その後,同じような視察に教員・スタッフが次々と派遣され,これまでに30人以上が派遣されるに至っている。これらの視察を行なった教員・スタッフには,学内で報告会を行なうことが義務づけられており,本場で見て,体験してきた「クラークシップというものの考え方やあり方」について議論を重ね,その学内への浸透に貢献している。1996年11月,約3週間の米国医学教育の視察を終えた第1陣は,教員たちを前に報告会を開いた。新しく導入される教育システムとはどのようなものか,期待と不安を胸に会場には多数の教員が訪れた。視察団から「医療チームの構成と活動」,「学生の指導体制」,「ローテーションのあり方」,「学生のスケジュール」,「評価のあり方」等々,詳細な報告がなされたが,「内科の場合,毎朝7時半集合でカンファレンスが始まる。アテンディングは7時にくるため,学生はその1時間前には回診の準備を始めているのが常。外科の場合には5時半には準備を開始している」などの話には「大変だな」とため息が漏れたという。
視察団からの情報を得たクラークシップ委員会は,各部門・部署ごとのチーム作りをより具体的に進めた。「すぐに」始めなければならないが,課題は次々と現れる。
次回は個別の課題とその解決への取り組みを報告する。
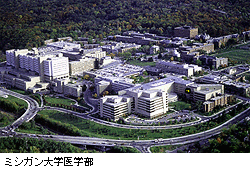
 | 総合内科のアテンディングラウンド(ミシガン大)
「アテンディングは病棟内や病室を回診しながら研修医や学生を指導する。かなり細かいことまで質問を交わすので回診時間は長くなる。アテンディングは決して研修医や学生を叱り飛ばしたりはしない。彼らはお互いに評価を行なうため,常に緊張感を保っているのだ」(谷亀氏) |
