DDW-Japan 1998 開催
消化器関連8学会が一堂に会す
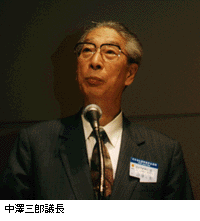 日本の消化器病学全体の発展を目的として,また関連する分野の学会を同時期に同会場で行なうメリットを掲げ,1993年9月に神戸市で開催されたDDW-Japan(Digestive Disease Week-Japan,日本消化器関連学会週間)は本年で6年目を迎え,さる4月15-18日の4日間,中澤三郎日本消化器関連学会合同会議議長(藤田保衛大),比企能樹運営委員長(北里大)のもと,横浜市のパシフィコ横浜を会場に開催された。
日本の消化器病学全体の発展を目的として,また関連する分野の学会を同時期に同会場で行なうメリットを掲げ,1993年9月に神戸市で開催されたDDW-Japan(Digestive Disease Week-Japan,日本消化器関連学会週間)は本年で6年目を迎え,さる4月15-18日の4日間,中澤三郎日本消化器関連学会合同会議議長(藤田保衛大),比企能樹運営委員長(北里大)のもと,横浜市のパシフィコ横浜を会場に開催された。
参加学会は,第29回日本膵臓学会大会(三重大 川原田嘉文会長),第55回日本消化器内視鏡学会総会(東医大 斉藤利彦会長),第34回日本肝臓学会総会(慈恵医大 戸田剛太郎会長),第84回日本消化器病学会総会(比企能樹会長),第33回日本胆道学会総会(昭和大 藤田力也会長),および部分参加の日本消化吸収学会,日本消化器外科学会,日本大腸肛門病学会の計8団体。
本DDWでは,合同企画によるシンポジウム(12題)やパネルディスカッション(9題)をはじめ,各学会長講演,特別講演,ワークショップが,一般演題等に加え企画された。本号では,これらの中からいくつかのトピックスを紹介する(関連記事掲載)。
パネル「H. pylori除菌後の諸問題」
 パネルディスカッション「Helicobactor pylori(以下H. pylori)除菌後に起こる諸問題」(司会=北大 浅香正博氏,大分医大 藤岡利生氏)では,H. pylori除菌治療により胃の形態的,機能的変化が起こることが明らかとなり,H. pylori感染症の病態研究には正確な除菌診断が要求されているとして,除菌の判定はいつ行なうのがよいのか,また除菌後に発生する十二指腸炎や食道炎,胃炎など,DDWでは初の試みとなったH. pylori除菌後の諸問題について,総勢12名が検討結果を発表した。
H. pylori除菌の判定はいつ行なうか
石塚淳氏(北大)は,「H. pylori除菌の判定は治療後1か月目でよいのか」を話題にあげた。H. pyloriの除菌診断は治療後1か月目に行なわれるのが一般的だが,石塚氏は1992年7月-97年12月に除菌診断が施行され除菌判定が可能だった386例を検討。312例(80.8%)が1か月後診断で成功との結果が出たものの,その後の観察で再陽性化したものがあったと報告し,「1か月目のみの判定では不十分。偽陰性が存在するため,正確を期するには1年後のUBT(尿素呼気検査,再陽性化全例が+であった)に加えた諸検査を行ない,総合的に判断する必要がある」と示唆した。
パネルディスカッション「Helicobactor pylori(以下H. pylori)除菌後に起こる諸問題」(司会=北大 浅香正博氏,大分医大 藤岡利生氏)では,H. pylori除菌治療により胃の形態的,機能的変化が起こることが明らかとなり,H. pylori感染症の病態研究には正確な除菌診断が要求されているとして,除菌の判定はいつ行なうのがよいのか,また除菌後に発生する十二指腸炎や食道炎,胃炎など,DDWでは初の試みとなったH. pylori除菌後の諸問題について,総勢12名が検討結果を発表した。
H. pylori除菌の判定はいつ行なうか
石塚淳氏(北大)は,「H. pylori除菌の判定は治療後1か月目でよいのか」を話題にあげた。H. pyloriの除菌診断は治療後1か月目に行なわれるのが一般的だが,石塚氏は1992年7月-97年12月に除菌診断が施行され除菌判定が可能だった386例を検討。312例(80.8%)が1か月後診断で成功との結果が出たものの,その後の観察で再陽性化したものがあったと報告し,「1か月目のみの判定では不十分。偽陰性が存在するため,正確を期するには1年後のUBT(尿素呼気検査,再陽性化全例が+であった)に加えた諸検査を行ない,総合的に判断する必要がある」と示唆した。
寺尾秀一氏(京都民医連第2病院)は「H. pylori除菌成功例の経過観察中に,除菌前には存在しなかった新たな病変の発症を経験した」と述べ,逆流性食道炎が約11%と比較的高頻度に発症すると報告。貝瀬満氏(東芝病院)は,消化性潰瘍瘢痕治癒後に行なった除菌治療1か月後,1年後の内視鏡検査(219例)での検討の結果,消化性潰瘍の再発は1年後で5.3%にみられ,その後も再発を繰り返すパターンがあると発表し,経過観察の必要性を強調した。
H. pylori除菌と胃酸の関係
飯島克則氏(東北大)は,H. pylori除菌後に発生する十二指腸びらん,逆流性食道炎の胃酸分泌能の変化について検討。「中高年齢の男性に発症が多くみられるH. pylori除菌後の急性十二指腸びらん,逆流性食道炎の原因として胃酸分泌の上昇が強く考えられる」と指摘した。また鈴木雅之氏(国立東京医療センター)は,「除菌後に出現する十二指腸びらんの原因として,胃内酸度の増加が考えられ,比較的粘膜萎縮の少ない患者に多く発症することが示唆された」と報告した。さらに春間賢氏(広島大)は,除菌後の逆流性食道炎の発生について,「胃酸分泌の亢進,食道裂孔ヘルニアの有無などの関与が考えられる」と述べた。谷中昭典氏(筑波大)は,まだ科学的に根拠が確立していない通常のH. pylori関連胃潰瘍とは異なる病態を呈する非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)起因性胃潰瘍への除菌の有用性を検討。その結果,NSAIDs胃潰瘍では,除菌後の胃酸分泌亢進を増幅し,通常のH. pylori関連胃潰瘍よりも高頻度に粘膜病変を出現させる可能性が高いことを示唆した。
総合討論の場では,欧米では1か月でよしとされている除菌の判定について,日本においては長期の経過観察が必要と合意。また,除菌後のH2ブロッカーの投与,および欧米に比べ使用率が圧倒的に低いPPI(プロトンポンプ阻害剤)の投与法に関しても話題となった。パネルの最後にあたって藤岡氏は,「21世紀初頭には,H. pylori除菌療法が保険点数化されるだろう。今秋にはH. pylori除菌をめぐる副作用や癌などの諸問題についてシンポジウムを開く予定もある」と述べ,今後も学会レベルでの検討されることを示唆した。
パネル「臨床試験をめぐる諸問題」
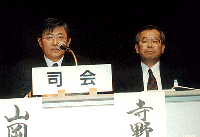 パネルディスカッション「臨床試験(新GCP)をめぐる諸問題」(司会=京大 山岡義生氏,獨協医大 寺野彰氏)では,本年4月より完全実施された新GCP(医薬品の臨床試験の実施に関する基準)での消化器領域の問題をめぐり,臨床試験担当医をはじめ,行政,製薬メーカー,被験者など,それぞれの立場から10人が登壇,フロアを交え白熱した議論が展開された。
パネルディスカッション「臨床試験(新GCP)をめぐる諸問題」(司会=京大 山岡義生氏,獨協医大 寺野彰氏)では,本年4月より完全実施された新GCP(医薬品の臨床試験の実施に関する基準)での消化器領域の問題をめぐり,臨床試験担当医をはじめ,行政,製薬メーカー,被験者など,それぞれの立場から10人が登壇,フロアを交え白熱した議論が展開された。
臨床試験の現場から
仁尾義則氏(島根医大)は,多施設での臨床試験には有効性の有無をめぐって格差が生じる現状を指摘。施設間格差の改善に向けて,複数の施設での定期的な技術研修とともに,臨床試験医資格制度の導入,施設認定の制度化などを提言。斉藤寿仁氏(東女医大)は,最近2年間の臨床試験で,患者に治験参加を拒否される率が25%であったことを報告。被験者へは交通費の支給,謝金を具体化する必要性を説いた。栗原稔氏(昭和大豊洲病院)は,治験責任医師,分担医師,協力者などの役割を明確にすることや,教育と訓練の必要性を強調。特に治験コーディネーターなどの治験協力者の教育の充実や体制の整備が急務であることを訴えた。上田慶二氏(都多摩老人医療センター)は,研修制度や実地医療機関における治験チームの確立,また研究会・学会の発足や治験広告の規制緩和などを提言した。中村孝司氏(帝京大市原病院)は,「治験コーディネーターの必要性を施設側は認識していない」と指摘,経済的基盤の視点からの必要性を強調した。
一方,新GCPの推進者となった厚生省の望月靖氏は,倫理性,科学性,信頼性を根拠とする新GCPのフローチャート図を提示しつつ今後の展望を語った。また,厚生省の新GCP普及定着総合研究班の主任研究者を務めた中野重行氏(大分医大)は,新GCPが日米欧での統一基準をめざした改正であったこと,患者中心の臨床試験のあり方を考慮したことなどを述べた。
薬学からは,柳川忠二氏(聖マリアンナ医大東横病院)が登壇。医師,看護婦,薬剤師の共通基盤となる臨床試験に関する研究会の設立を提言し,治験専任スタッフ育成の必要性を強調した。治験依頼者である内藤晴夫氏(エーザイ)は,製薬メーカーとしての立場から発言。治験における患者,医療機関,企業それぞれのメリットを述べ,治験実施体制の整備が急がれるとした。被験者を代表して,小出五郎氏(NHK解説委員)は治験の同意文書に関し,「被験者がいつでも医師,コーディネーターに相談できる体制の確約。金銭的,時間的損失がないこと」を明記すべきとの意見を述べた。


