新春
座談会
現代の感染症
 | ||
| 倉田 毅 国立予防衛生研究所 感染病理部長 | 〈司会〉吉倉 廣 東京大学・細菌学教授 |
岩本愛吉 東京大学医科学研究所 感染症研究部教授 |


日本の感染症対策の現状
 吉倉 岩本先生は東大の細菌学教室で基礎研究をされた後,東大医科学研究所(以下,医科研)でエイズも含めた感染症の臨床を,また臨床に関する研究もされているわけですが,移られてから何年になりますか。
吉倉 岩本先生は東大の細菌学教室で基礎研究をされた後,東大医科学研究所(以下,医科研)でエイズも含めた感染症の臨床を,また臨床に関する研究もされているわけですが,移られてから何年になりますか。
岩本 2年弱です。
吉倉 普通の病院で感染症が疑われて診断がつかないと医科研を受診しますが,印象が新しいところで,臨床の現場で気がついたことを話していただけると,日本の感染症がだいたいわかると思いますが。
岩本 まずは,スタッフの数が少ないという問題があります。それから,スタッフの数に応じて扱える疾患がある程度決まってしまうことがあげられます。
医科研の場合,対象となる感染症はHIV感染症と,それに付属する日和見感染症です。また,前身である伝染病研究所の伝統があるので,いろいろな形で日本に輸入されてくる感染症に注意をしていなければいけない。その基本はマラリアですが,マラリアを中心とした原虫疾患,下痢症,A型肝炎,チフスなどです。今年は,大腸菌による下痢症や,熱を主訴としたパラチフスを経験しました。
吉倉 それは輸入ではないのですね。
岩本 今言ったのは輸入例です。国内で下痢をして医科研に来られる方はあまりなく,海外からの帰国後,発熱や下痢で来院するのがパターンです。以前にはラッサ熱のような出血熱もあり,日本国内にある感染症以外に,時々日本に入ってくるものに注意しています。そういうことに興味を持っていこうと思うと,日本ではあまり起こっていないが地球上のどこかで起こっている感染症にもアンテナを立てていなければいけない。そこで,「国内にある感染症」と「時々日本に輸入されている感染症」,そして「すぐには日本に問題ないかもしれないが,世界で問題になっている感染症」の3つに分けて考えています。
感染症の教育
吉倉 大学の教育をみると,マラリア原虫を扱うのは寄生虫学講座ですが,その関連講座をだんだん減らす傾向にあります。そこで,大学における微生物の教育について,臨床現場にいて「これはまずい」という実感はありますか。それとも,基礎教育をすれば今のまま臨床の場で何とかやっていけるとか,その辺はどうですか。岩本 学生のうちからできるだけいろいろな感染症をみる機会を作り,感染症に興味を抱かせるようにする必要があると思います。2年前まで東大にいて,医学部の1年生に接する機会がありました。現在も感染症の系統講義を担当しております。そのときに,HIVはもちろんですが,輸入感染症のことも話して,医科研で症例を見るチャンスがあるので,できるだけ来てほしいと言っています。今年も夏に3,4人が見に来てくれたので,そういうことを地道にやっていこうと思っています。その中から感染症をやろうという人間が1人でも出てくればありがたいと思っています。
感染症のグローバリゼーション
 吉倉 世界中で,あるところから別のところへ容易に行ける状況で,感染症の「グローバリゼーション」(世界一体化)が問題になっているわけですね。そうすると,かつて見たことがないような病気に今から遭う可能性がある。そのことに関して,臨床的に専門家を育てることをどう考えたらよいですか。
吉倉 世界中で,あるところから別のところへ容易に行ける状況で,感染症の「グローバリゼーション」(世界一体化)が問題になっているわけですね。そうすると,かつて見たことがないような病気に今から遭う可能性がある。そのことに関して,臨床的に専門家を育てることをどう考えたらよいですか。
岩本 医科研では熱帯医学の研修を行なっております。全国から経験の深い先生方をお呼びし,3か月かけて10人の学生を相手に行なうものです。また,日本の感染症トレーニングの拠点を東南アジアあるいはアフリカに作って,現地で学ぶことを考えてもいいのではないかと思っています。今の状況では,特に熱帯地域が問題になるので,国内に輸入される感染症をみるだけでなく,現地がどういう状況なのかを若い人たちにみせる。その拠点の運営は現地の人で,日本が援助する形で。もしそういう研究所があれば,医科研の熱帯研修もそこから研究者を呼んだり,こちらから赴くなど,今の研修費用を交通費に使い替えてもいいのではないかと思います。
吉倉 国立予防衛生研究所(以下,予研)でもそういう計画を持っているそうですが。
倉田 国外でトレーニングを行なう話が1つあります。今の日本では専門家が育ちにくい。研究所の専門家は何とかなるにしても,フィールド研究ができる専門家が少ない。アメリカには熱帯医学の講座もあり,教育者も教育機関もたくさんあります。それでもまだ足りないというので,CDC(米疾病対策センター)は毎年200人を,MDと一部Ph.D.も入りますが,医師になりたてのところで採用して,徹底的にフィールドの疫学を勉強する機会を与えます。これがアメリカの大学病院や大きな総合病院の感染症およびCDCの中でも世界中の感染症に対応する人材のプールを作っているんです。
私はCDCで1981年4月以来20回以上にわたり仕事をしてきていますが,日本は,そういうキャパシティという意味で,人的にも経済的にも非常に貧しく,決して金持ちの国ではない。とても比較は不可能です。そこで厚生省では今年から,予算がどれだけとれるかわからないですが,エイズ結核感染症課が中心になって,若手の感染症専門家を養成することを考えています。もし予算が通れば,外国のフィールドのステーションへ,短期間,あるいは1年,2年単位で派遣しトレーニングするという考え方も出ています。
岩本 さっき先生がおっしゃったCDCの場合は,アトランタで行なわれているのですか。
倉田 アトランタで最初の教育を行なって,後は各地の州衛生部や研究室に行かせる。最低でも何か月間かは患者の診断をつけたり,研究室でもどうやって診断をつけていくのか,その得られた材料をどうやってリサーチに結んでいくかを学ぶトレーニングがなされるわけです。細菌やウイルスの研究室に行く人もいるし,寄生虫の人もいる。みんな2つぐらい経験しており,それが卒後の教育になります。学生時代は,感染症の教科書を見てわかるとおり,日本より徹底していますしね。
吉倉 その予研の制度は,何か名前がついているんですか。
倉田 名前はついていません。予研というより,厚生省のエイズ結核感染症課が中心になっています。その中で,厚生省および大学,地方衛生研究所などのいろいろな人を派遣してトレーニングする,あるいは協力体制を作る計画で,実施されれば大変意味ある制度と言えると思います。
吉倉 そういうもののセンターとなる研究所を作る話はないんですか。
倉田 エイズおよび感染症の研修研究センターを作る申請はしていますが,大きな補正予算でも通ればというままで,計画が止まっているんです。
感染症対策をとりまく環境
 吉倉 日本でも,各分野の感染症で立派な人材がいないわけではないが,それにしても臨床の場で,それから研究の場でも,人材はそう多いわけではないし,分野によってはみるべき人がほとんどいない。
吉倉 日本でも,各分野の感染症で立派な人材がいないわけではないが,それにしても臨床の場で,それから研究の場でも,人材はそう多いわけではないし,分野によってはみるべき人がほとんどいない。
1970年代の中頃,世界銀行のエバンスが,世界の経済状況と疾病とを関連づけて,経済状況がよくなれば,疾病は感染症から慢性疾患に移行し,先進国は感染症の部分がほとんど終わりになる,慢性疾患が20世紀から21世紀の問題だと言ったわけです。実際,われわれもそう理解したことがあります。80年代の初めに「感染症は終わった」という認識が出たために,感染症の医師も研究者も,ある意味では根絶されてしまった。
今ちょうど「ASM(American Society for Microbiology)ニュース」(1996年9号)を持っているんですが,アメリカのゴア副大統領が今回(1996年11月)の大統領選をにらんで,「今後,アメリカの保健の最大の問題は感染症であるから,CDCの予算を倍増する」との声明を発表しました。CDCのemerging disease対策の予算を1800万ドルから4400万ドルに拡大すると言っています。アメリカでは国力をあげて感染症対策をやろうという時代なんですが,一方,日本は財政的なサポートもないし,人もいない。大学で感染症関係のポジション,あるいは部局を作ろうとすると,人材がないから作ってもしょうがないじゃないかと,逆に悪循環になっているのです。
人材の育成
吉倉 考えなければならない問題は,人をどうやって育てるかだと思います。わが国の感染症の専門家の状況は,明治維新の後のようなもので,今から世界中に大学卒業したての人をどんどん送って,そこで育ててもらう以外にないのではないかというぐらい危機感を持っているんです。岩本先生,臨床のほうからみてどうですか。岩本 確かに危機感はすごくつのります。先程,倉田先生がおっしゃったトレーニングコースができた場合,5年ぐらいたったら同じ人がもう一度受けてもいいようなシステムを作り,何度もトレーニングが受けられる機会が作られてもいいのではないかと思います。
倉田 加えて,日本国内の問題は何とかなるから,外国から入ってくる問題に関しては現地に人を送り勉強してもらい,ふだんは国内で起こっている感染症を見るというのも必要かと思います。
国外でのトレーニングコースに派遣すると,優れた研究者の連携で,いわゆる水面下の情報が自然に入るようになるんです。政府が出す情報は,それが確定した後でなければ発表されないんです。WHOも同様です。しかし,日本にはそういう情報がなかなかこない。研究者網という仕事上のつながりがある人にしかそういう情報はこないのです。感染症対策の国際協力をCDCやパスツール研(フランス)同様にやることが求められるようになってきており,その基盤として専門家が必要ということです。
また,日米の「人口とエイズに対する合意」が3年ほど前にありましたね。その中で,日本は援助の話だけではなく,感染症のトレーニングコースを設立するなど,アジアにおける人材育成の中心になっていくべきだという話が加わってくるんです。しかし,それをカバーしていく人がいない。戦後に感染症をよくみた先生が皆引退され,人材が不足しているんです。
感染症に対する日本のとるべき対応
岩本 日本の感染症研究はそれぞれの分野でタコ壺になってしまっています。生物学から細菌学,寄生虫学まで,短い時間で,診断学や研究のトピックを話し合う機会がもっとあるほうがいいと思うんです。現実にも,最近日本でも問題になっている原虫クリプトスポリジウムは,神奈川で始まって,埼玉県で集団感染がありましたよね。
倉田 あれは大きな問題があるんです。飲み水の水源の近辺に物を廃棄する場所があったとか,とんでもない話と聞いています。
岩本 医科研でエイズで激しい下痢の人がいて,調べているうちに検査技師が2人ほどクリプトスポリジウムの診断をつけました。そして気をつけていると,だんだん症例が増えてきたのです。今,日本に専門家が少ないので,大阪市大の井関基弘先生のところに相談しています。
このように新しい寄生虫感染症が問題になってきても,ふだん寄生虫の専門家と会話をする機会があると,今何が問題になっているかがわかる。海外ではすでにミルウォーキー(米ウィスコンシン州)で1993年に40万人の集団感染がありました。そういう話を聞くと,感染症全般にいろいろな分野のことをまとめてディスカッションできる機会が,また興味を持つ人間が全体に増えることが必要なのかなと思います。特にエイズの臨床は,日和見感染症でウイルス,細菌から原虫と幅広く感染症全般を知る必要があるのです。海外派遣だけを考えていると,国内がどんどんしぼむことも考えられます。
吉倉 その辺,どうして学会がうまく機能しないんですかね。
岩本 アメリカのASMのように分科会があると,すごくいいと思うんですけれど。
吉倉 つい最近まで,感染症を国内問題としてとらえていて,グローバルな視野がなかったんですね。WHOのポリオの根絶計画で,西太平洋地区において日本がイニシアチブをとり,中国で2-3万人という大変なポリオ感染が,3年ほどでほとんどゼロになったわけです。そういう活動は本当に最近のことですね。
なぜ学会でうまくいかないかというと,グローバルな視野で感染症をとらえなかったことが,感染症の各分野が一緒になって現場で働くことにつながらなかったのではないかと思うのです。実際,今必要なのは,厚生省,文部省,外務省という省庁の壁を超えた国際的なスケールで,例えばCDCみたいなもの。しかし,CDCが世界中をカバーできるわけじゃない。西太平洋地区はどうしても日本がやらなければいけない。そういう視野で今から感染症をやらないとうまくないんじゃないでしょうか。
O157から見えてきた問題
吉倉 つい最近,腸管出血性大腸菌O157で大騒ぎしたのですが,倉田先生,このことについていかがでしょうか。倉田 O157の問題に関して,今まで新聞報道や厚生省が発表した資料の中で,CDCがコメントしている話と違う部分があるんです。CDCやアメリカの感染症の専門家の間では,O157感染の原因は牛肉と牛乳にあると認識されています。しかし,日本の公式発表では,感染源としての牛の追求がどこにも出てこない。
日本では,食物は市場に出てから消費者の口に入るまでは厚生省の責任ですが,市場に出る前は厚生省の管轄ではなく立ち入れない。屠殺場も農園も同じで,全部農水省の管轄です。しかし,牛のO157汚染率を調査したデータがあるかと言えばまったく出てきていないわけです。一方で原因とされたのがカイワレやカボチャサラダでしょう。O157がなぜカイワレにきたのかという話は,新聞報道や一般の人が見る情報にも,厚生省の文書にも出てこない。それでいいのかという話は当然出てきますよね。ここが世界の常識と違うところではないでしょうか。
学校や保管所に冷蔵庫がなかった話は人に聞いて驚いたのですが,ここには,厚生省は文部大臣の許可なしには入れないんです。一方,CDCは,人間に病気が起こった場合,調査チームはすべての規制を超越して即時に介入する権限があるんです。これは大統領も止めることができません。そういうことが日本にはないですね。もし今回のO157のような問題をすべて厚生省の責任とするならば,厚生省自体にあらゆる健康,疾病の問題に関してとことん調査立ち入りなどの権限を与えないと,肝心な原因はいつまでもわからない。
岩本 厚生省に与えるのか,超越するものを作るのか。
倉田 どちらでもいいのですが,とにかく問題が起こったときにはそれだけのことはやれないといけない。
先生方にお聞きしたいんですが,学校教育の場で集団感染が起こったときに,文部省は細菌学の先生方に調査にすぐ立ち会わせるような動きはあったんですか。
吉倉 まったくないですね。
倉田 ほかの先生からもないと聞いています。細菌専門の先生も調査しない,厚生省は当然許可なしには入れない。そういう話になってくると,一体だれが問題を解決するのか。カイワレは大丈夫だといって前厚生大臣が食べて見せた。でも,何が解決したから食べたということは,どこにも出ていない。また煮たばかりのカボチャに菌がいるはずがないんです。ではどこから菌がついたのか?そういうあいまいなままの状態が続くと,どこかで爆発が起こると思うのです。
輸入牛や,国産牛の牛肉の汚染はどのくらいあるんでしょうか? O157は火を通して,生で食べさえしなければよく,あとは扱いに気をつければいいのです。きちんと消費者に教育をしないと,何かあるとパニックになってしまうわけですね。
O157と行政
吉倉 赤痢菌と大腸菌は構造が非常に似ているんですね。しかし,赤痢の場合は伝染病予防法,厚生省では……。倉田 保健医療局エイズ結核感染症課の管轄です。
吉倉 食中毒の場合は食品保健課で,生活衛生局の管轄です。だから,役所での振り分けは,大学でいうとほとんど同じ菌でもラクトースを分解するかしないかで,片方は医学部,片方は農学部か工学部にいくというような話になる。
また食中毒の場合は,保健所単位で調査しますね。東京都でいうと,1つの区で発生した調査はその区の中だけで行なう。ですから,全体的な調査をする機構になっていないように思います。
そういうことからいうと,O157の話で,ある意味では厚生行政の病気がわかったと言ってもいいかもしれない。アメリカでは食中毒といわゆる経口伝染病は区別せず,同様に対応しているということです。
1988年に総務庁が行政観察で調理済みの食品について非常に詳しい調査をしました。そのうえで総務庁は10年も前から今回のような事件の可能性を言っているのです。下痢症を扱う人も,危ないと言い続けていたわけです。ですから,今始まったことではないんです。
全国食中毒事件録が厚生省食品衛生課から出ていて,どの県に食中毒発生が多いかがわかります。O157で騒がれた堺市も,まさに前から危ないと言われている場所なんです。ですから,行政の問題もあり,起こるべくして起こった感染症かもしれないと思います。
厚生行政の意思決定のメカニズム
感染症の「終焉」とエイズ
吉倉 非常に難しい問題があるので微妙なところですが,エイズの問題を避けるわけにいかないと思います。当時はゲイに関係しているというのでGRIDと言っていましたが,1980年頃からエイズが出現した。CDCは1980年から83年にかけて,エイズ感染者は同性愛者間,麻薬常用者に多く,これは血液感染ではないか,また,血友病の患者さんに発症したことから,「血液製剤の投与に関係があるかもしれない,エイズはウイルスによるのではないか」と一生懸命言ったわけです。
ピュリッツァー賞受賞のジャーナリストローリー・ギャレットは,著書『Coming Plague』の中で,CDCは必死になってエイズの血液からの感染の危険性を言っているが,それ以外の政府機関は一顧だにしなかった,と書いています。先程申し上げたように,80年代の初めはまさにエバンスが「感染症は終わった」と言った頃なんです。日本で厚生省の感染症対策課が「室」に格下げされたのも1985年でした。そういうことから言うと,エイズの発症と感染症が終わったという認識が不幸にもちょうど一致した時であり,それがエイズの広がった1つの原因じゃないかと思うんです。
1983年,何をすべきだったか
吉倉 血液製剤の行政について,1983年の時点で日本はどう対処すべきであったか。この年は,アメリカの科学アカデミーが血液製剤について徹底した調査をしているのですが,その中で,「1983年の段階では,ウイルスがエイズ発症の原因だと結論できる証拠がなかった」としています。日本の厚生行政は情報が確かでないと動けない。では,その情報が確かでないときに一体どうやったら正しい(あるいは国民の健康に悪い結果をもたらさないような)決断が下せるか,あるいは正しいかもしれない決断を下せるメカニズムを作るか,それが非常に大事だと思うのです。
今後も,従来わからなかった病原体が出現し,不確定な段階で,厚生行政の上で判断しなければいけない状況がくると思うんです。それに対して,一体どうすれば今回のエイズのようなことにならずに済ませることができるのか。例えば1983年にアメリカの議会で,推定として「輸血でHIVに感染する確率は100万回に1回」という今では考えられないような証言が出る(Dr. J. Bove, Blood Products Advisory Committe議長)。それが皆の頭にしみ込んで,一種の安心感というか自己満足というか,それによって的確な対応がとれなかった。どうしたらそういうことが防げるかを考えなければいけないのではないでしょうか。
特に新しく出現した感染症に関して,よくわからない状況にある場合,どうしたら正しい判断ができるのか。この辺について先生方の意見をお聞きしたいのですが,いかがですか。
倉田 私がエイズの問題を知ったのは予研に来るはるか以前ですが,初めてアトランタへ出血熱(ラッサ熱)の勉強に出かけたときです。4月初めにEISのミーティングがあり,部屋の入口にB5のサイズでタイプを打った紙が積んであった。それが,その年の6月にMMWR(Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC発行)に載ったもののもとなんです。
岩本 1981年ですね。
倉田 そうです。そのときに初めてCDCのミーティングでエイズが話題になった。当時発表されたのは,患者はゲイで,日和見感染を発症し,マルチプルな病原体による感染症で,調べてみたら免疫機能がかなり落ちると発症する,原因はまったくわからないがウイルスかもしれないと,要するに具体的な報告は何も出てこなかった。その翌年に,血友病の子供にHIV感染があるというので,これはおかしいと。共通項は血液しかないということで始まった話です。それを基盤にした話が1981年の6月にMMWRにまとめられ,その年の12月に正式な論文が出ているんです。
しかし,では,そういう問題が起こったときにどうするかということなると,非常に難しいですね。
実態とのギャップ
吉倉 1983年に,モンタニエ(フランス・パスツール研究所)によってHIVウイルスが分離されたが,サイエンスの世界に新しいことが発見され,それが定着するにはやはり時間がかかる。例えば,逆転写酵素が発見され,その考えが定着するには1年ぐらいはかかった。ケースによっては発表されたときは大発見だとされても,その中にはそれは間違いだったとなる場合もある。そういうことでいうと,サイエンスというのは保守的であることによって間違いをしない機構になっているんですね。ですから,1983年にウイルスが見つかったとされていますが,われわれもレトロウイルスの研究をしていて,その段階でモンタニエの論文を見て,これがエイズの原因だと確信を持ったかというと,少なくとも私はそういうことはなかった。やはり1984年に抗体のスクリーニングが可能になった頃から1985年にかけて,ゆっくりとサイエンスの世界にしみ透っていったと思うんです。また,加熱製剤についても,1988年のCDCの報告で加熱製剤のみを投与された患者で18人が感染したという事実がある。その辺に,いわゆるメディアと実態との間に超えられない,お互いに理解できないギャップがあるような感じもしますね。
岩本 昨年の秋ごろのMMWRが,当時のゴッドリーフの論文を再掲載していて,今読み直してみると,ひょっとしてサイトメガロウイルスが原因で免疫不全が起こってカリニ肺炎が起こるかもしれない,しかし,サイトメガロウイルスにしても変だ,というニュアンスですよね。
それが実際にHIVが発見されて,当時私自身は内科で血友病の患者さんもみていたのですが,血友病の方の中で新しい病気が起こっているという情報が,現場で仕事をしている人間の間にも少なかったように思います。また1984年に留学しており,その後の日本の流れはわかりませんが,抗体を持っている患者さんがたくさんいるということがわかったのはその頃ですね。それまでの病気だと抗体陽性はむしろプロテクションというイメージだから。
吉倉 特にB型肝炎の場合,そうなんですね。
岩本 そこでまた判断が難しかったと思うし,抗体があり,なおかつウイルスが存在するというのは,それに関し専門家の考え方の違いが起こりうる時期だったと思うのです。
吉倉 HIV感染の発症率がこれだけ高いというのは,だれも予想だにしなかったと思うんです。天然痘の発症率は50%で,ポリオになると100分の1~1000分の1。そういうことでいえば,発症率100%近い感染症というのは,かつて人類が経験しない病気なんですね。ただ,そういう病気は今後も出るかもしれない。行政の場では,科学的な判断の前に,行政的な判断で対策を立てなければいけない。どうやって行政的な判断を立てるか。
行政が正しい判断をするために
吉倉 岩本先生は診療の保険に入っておられるでしょう。岩本 個人的には入っていません。
吉倉 医療事故などのために,たいていの開業医は入ってますよね。例えば,1983年当時を考えてみる。厚生省が濃縮製剤の使用をやめると考えたとします。そうすると,その時点では,「もしもそれが間違っていたらどうするか」という話になるでしょう。その段階では,厚生省の決めたことが間違いになる可能性がある。それでもなおかつ厚生省が「やはり血液に関係があるようなので血液製剤の使用はやめましょう」と言えるメカニズムを作らないといけない。
実は,東大の医学部の学生にこの問題を提起したんです。面白い提案があり,1つは,薬害が起こったときの企業のリスクを非常に高めることが考えられると。第2の考え方はこうです。よくわからない段階で何かをするということは,企業にとっては無駄になるかもしれないので,その時点では非常に負担なわけです。そこで,わからないときに国が判断しなければならない場合には,ひとまず国がこのために企業に金を出す。もしも国の言うことが正しければ,企業から国の出した金を返してもらう。国が間違っていたら,国民の健康の保障のために出した金だから,それは国民が出していいだろうと言うのです。
これもやり方によっては問題も出るでしょうが,行政に携わる人が正しい,あるいはより高い安全性を含んだ決定ができるメカニズムを作らないと,うまくないのではないかなと思うんです。
倉田 確かに行政にも,厚生省の担当者は責任がありますが,今,厚生省にはそれを全部判断できる人はいませんし,機構もそのようになっていません。。CDCは必要な人は大学から呼び,そうでなければ全部CDCの中で判断して決めていく。それだけ人材は大勢います。何せ7000人いますからね。そのうちの半分が感染症対策です。3500人いると考えればいいんですよ。それに加えて,NIH(米国立衛生研究所),FDA(米食品医療局)の感染症専門家(研究を含む)はそれぞれ1000人,900人が大学以外にいます。日本はこれに対応する人員は予研の事務系を含み390人のみです。予算はエイズ関連の3000億円以外の分野で約5000億円(感染症研究で)あります。日本は,大学全部の微生物関連の研究者と予研の研究者を全部いれても1000人いるかいないかです。だから最初からケンカにならない。
また,日本の意思決定のシステムは,アメリカとはずいぶん違いますから,大学の先生が委員会にいて,大体の意見の方向や,サイエンスの経験から話し合い,その報告という恰好で決定が下される。つまりものを決めるときにどのようになっているかが明瞭ではない。
吉倉 HIV感染については,血液製剤,いわゆる生物製剤が日本では大きな問題になったわけですね。生物製剤は,厚生省薬務局の管轄ですが,一方,感染症は保健医療局と局が全然違う。こういうシステムになっていたのは生物製剤,生き物からとった製剤によって病気が起こるということを薬務行政の中に考えていない,つまり,現在の機構はかなり以前にできたので,製剤による感染を考えた行政機構ではない可能性がある。厚生省薬務局のメンバーは184人ぐらいですが,そのうち医師は6人ほどで,残りは薬系技官77人と事務官です(1996年9月1日現在)。その状況で当時は製剤使用の是非を判断したのではないかと思います。そういうことから言うと,対策を立てるときに,異った学問的,行政的背景のある複数の人が1つの決定の責任をとるメカニズムを作らないと,同じことが将来起こり得るんじゃないかと思います。
日本の医療システムと感染症
マスコミと感染症
吉倉 新しい感染症というと,エボラ出血熱やラッサ熱が浮かびますが,倉田先生は予研でラッサ熱の診断をされて,マスコミにずいぶんたたかれた経験があるわけですが,その辺についてちょっと話していただけますか。倉田 島田馨先生が医科研の教授の頃,1987年に私自身が医科研から予研に移った直後でした。その患者さんは水道関係の技術者で,2月に2週間ほど西アフリカのシオラ・レオネに滞在していた。そこはCDCがラッサ熱の研究チームを置いている場所なのです。患者は帰国して4日目までは何の症状もなく,それから発熱し,開業医から風邪薬をもらって1週間くらい自宅にいた。それでも熱が下がらないので,アフリカ帰りならと医科研へ行ったのです。まずマラリアを疑ったけれど原虫は発見されなかった。そのうち激しい下痢が始まり,腸管系の感染症が疑われ,抗生物質が投与されたけれども,まったく治らなかった。それが経緯です。
入院後1か月で軽快したけれど,理解できないということで,検体を予研に持ってきました。翌日の朝,血清をもう一度不活化して反応させたら,すべて陰性でしたが,ラッサウイルスに対して最後にとった血清だけが1000倍ぐらい出ているんです。もう1回やり直したら,また同じでした。そこで,二次血清やコントロール血清もみんな新しくして,日曜日に同じことを3回繰り返しても,結果は同じだった。
ところが,予研(当時,武蔵村山市内)にレベル4のキャビネットライン式の実験室があるのですが,完成直後に,当時の室長が議員会館に呼び出されて,「住民全員の合意があるまでそれを使ってはいけない」と政治家に圧力をかけられ,それと同時に武蔵村山市長から抗議を受けたんです。そんなことがあって,実験室は使用できず,すぐCDCに患者の血液を送り,結局,分離ウイルスは陰性ということで退院したんです。
しかし,同年7月末に患者に呼吸困難が出て,調べたら心臓の回りに心嚢液がたまっていて,抜いてみたら血性だった。4000例ぐらいのラッサ熱患者を調べた中に,そういう患者が7例いたんです。しかし,その血液からは一度もウイルスがとれたことがない。ただ,免疫グロブリンの高い液が貯留しているのがわかり,都立荏原病院で心嚢膜を剥いで外科的に治療され,それで治まったので退院されました。その材料は全部アメリカに送ったのです。
ところが,2年後の6月中旬,突然,「予研で違反検査が行なわれた」という記事が毎日新聞に載ったんです。予研の写真が載り,当時の大谷所長が「これは違反ではない」と反論しているコメントが載っていた。私は記者に会ったことも談話もとられていないんですが,勝手に「『答える必要がない』と倉田が答えた」と書いてあるんです。ラッサ熱の抗体チェックをしたことが,規定外検査という書き方ですが,記事の中で「違反」と書かれたのです。
私自身は,患者の診断をつけるためには,いかなることをやっても違反だと思ってはいませんが,そういうことがあって以来,日本では出血熱のことは,かなり危険なことであると認識されているようです。しかし,患者は世界中におり,そういうことは言っていられないのです。
ワクチンについても,マスコミは世界の動きとまったく異なったことを報道しています。日本におけるワクチン接種率の低下は異様です(「世界の状況」参照)。基本的には医学,医療記事を書いている人の多くがまったくの勉強不足です。このへんの教育もしないと,ワクチンもO157もウイルス性出血熱も,社会面でとんでもない活字が並び,それが一般化していくことになります。
ウイルス性出血熱をどうとらえるか
倉田 今,私が一番気にしているのは,クリミア・コンゴ出血熱についてです。これは鳥がダニを運び,そのダニが咬んだ哺乳動物では発症しないのですが,その血を吸ったダニが人間を咬むと,人間では病気が起きるわけです。これはどんどん広がってきていて,アフリカ全域から西アジア,モンゴル,中国の西部まできている。中国と日本の渡り鳥はわかりませんが,これは日本もある程度警戒しておく必要がある。その他は,そんなに心配することはないと思うんです。ウイルス性出血熱は,話題性はありますが,O157や結核などからすると,一般性という意味は非常に低い。だからCDCも「注意は必要だが日常的ではない」と別扱いなんです。実際の問題としては,対応さえ準備をしておけばいいので,赤痢やコレラなど,そういう日常性の問題とは少し違う。
吉倉 クリミア・コンゴ出血熱の話は,地球温暖化などと関係していて,対応を考えなければいけないですね。それからラッサ熱では,感染性が非常に高いと言われているけれども,通常の感染症に対する一般的な注意があれば……。
倉田 これらの疾患は,非常に大量の接触感染を出しているんですが,そのいずれの現場でも手袋などがまったく使われていないんです。ガウンも手袋もマスクもない。要するに,日本での一般的な医療でのバリアは,材料がないため行なえなかった。1995年にザイールのキクウィトでエボラ出血熱で244人死んでいますが,これも同様です。B型肝炎の患者を,手袋なしで血液にさわったり手術をすれば,全員感染すると思うのです。それと同じで,本当の問題とは少し違うと思います。
吉倉 診断がつくまではわからないですから,検体は外部に出しているわけですね。
倉田 検体は一般検査センターに出ていたんです。
吉倉 ウイルスを含んでいたかもしれない血清材料を送っていても,一般検査センターでは感染は起こっていない。ということは,逆に言うと,一般的な感染症に対する注意が大事だということだと思います。
マラリアの場合
岩本 輸入感染症ではマラリアが最も重要で,4種類あるマラリアのうち,熱帯マラリアだったら「これは緊急事態だ」という認識が絶対に必要です。2年ほど前,ある大学の植物学の教授が,海外から帰国後に発症した熱帯熱マラリアで亡くなられたことがありました。発熱の患者では特に渡航歴の問診が重要です。熱帯熱マラリアは世界のあちこちにありますが,特にアフリカ帰りでは注意が必要です。倉田 その症例は診断がつかなかったの?
岩本 マラリアの診断はついたけれども,治療前に脳マラリアで亡くなられたそうです。聞いたところでは,当の教授自身がマラリアを疑っておられたそうです。入院なさったのは金曜日か土曜日で,治療薬の手配が次の週に持ち越されたという話も聞きました。
昨年,医科研でマラリア陽性の赤血球数が一晩で100倍になった熱帯熱マラリアの患者さんを経験しました。この方はうまく治療できましたが,熱帯熱マラリアの場合,原虫が脳血管内皮に親和性を持つため,免疫のない患者では数日以内に死の転帰をとりうる緊急疾患だということがあまりにも知られていません。現在承認されている治療薬はファンシダールとキニーネだけで,あとは厚生省の研究班から入手する必要がある。入手ルートをつけておくことが必要です。
マラリアの場合,予防対策・情報もまったく貧弱です。やはり2年ほど前,予防薬としてファンシダールを処方された大学教授が,副作用のスティーブンス・ジョンソン症候群で失明され,研究生活がだめになったということもありました。
倉田 私が驚いたのは,海外へ行く人に「マラリアの予防はどうしました」と聞くと「必要あるんですか」と返事されることです。
吉倉 成田空港で出国手続きが終わったところに感染症予防のパンフレットがありますね。手続きした後では手遅れで,そこに書いてある薬なんか取り寄せようにもないんだから。
倉田 到着先の空港で求めたらというアドバイスもされているようですが,私が最近ヨーロッパの5か所の空港で抗マラリア薬を求めてみたのですが,ないか,あっても1箱しかないという状況でした。もし,急にそのままアフリカへ行かなければならないという事態が起こったら万事休すです。また,出国手続きした後に感染症予防の注意をするのであれば,同時に成田空港内で自由に必要な薬を購入できるようにすべきだと思います。
海外渡航者の医療をどうするか
倉田 海外旅行における一般的な注意として,アメリカのCDCが毎年更新している「Travelers Health」のようなものを日本もきちっと作っておかないといけない。吉倉 こういう高速大量輸送の時代で,特に人間の場合,空港などの検疫は効果が少ない。けれど,外から感染症が入ってくる危険性が昔より減ったかというと,むしろ増えている。そういうことを考えると,海外旅行者を対象とした医療をどうするかが問題です。
それは日本人だけでなく,来日する外国人も含まれる。日本にいる外国人は,観光ビザで働いている場合もあり,日本の医療機構になかなか近づけない。しかし,その人たちが感染症を持っている可能性もある。これをあまり言うと差別になりますが,そういう人を含めて,どうやって日本の医療システムの中で感染症をコントロールするか。各国でも結核患者は外国人のほうが本国人よりも多い。結核患者がほぼゼロといっているオランダでも外国人での結核患者は多いのです(表)。
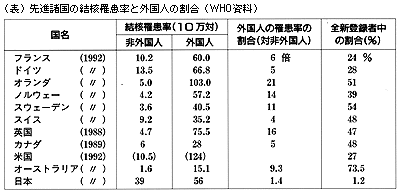
例えばアメリカでは,「旅行者外来」を数多く開いています。そういうことを日本では大学がやるのか,厚生省か,例えば国立国際医療センターがやらなければいけないのか。それに日本で1つだけでは間に合わないので,各都道府県にどうやって作るか。そのためには人材も育てなければいけない。
倉田 結局最初に戻るのですが,CDCのミッションステートメント(任務声明)を読むとおもしろいんです。CDCは何に対して責任があるかというと,「アメリカ国民が国内外において受ける不幸な事態を避けるためのあらゆる責任がある」とあります。その責任の1つである「Travelers Health」は,ある場所にはこの感染症があり,それを防ぐために何を気をつければよいかが全部書いてあるわけです。日本でも検疫所ではできるだけの努力はしてきていますが,海外に出ていく人は昔の特攻隊と一緒で,行った人は自分で努力しなさいという面が強かったですね。開発途上国の日本大使館へ行ってもそうです。日本の商社の人たちは,国内にそういう情報がないから,自己防衛せざるを得ず,その情報もすべてヨーロッパやアメリカから得ているわけです。日本からの情報はほとんど役に立っていない。最近,厚生省はこの辺の一般渡航者向けの感染症情報提供の準備をしています。
そういう意味では,厚生省も国際化しなければいけない。政治的な対応そのものを,ただ国際機関にお金を出すだけではなく,国民のために使う方向に変えて,それに日本の研究者,医師などいろいろな人が関与していかないと,輸入感染症というのはちょっとやそっとでは減らないと思います。
病院感染を引き起こす原因
吉倉 病院感染は,今始まったことではありません。しかし,黄色ブドウ球菌による感染MRSAでは死亡者も出て社会問題にもなりました。この原因としては,抗生物質の乱用と耐性菌の出現が指摘されていますが,本当のところは「細菌感染なら広域スペクトルの薬を投与すればなんとかなる」という感染症に対する侮りと誤解が原因ではないかと思っています。もう1つ忘れてならないのは,病院感染は医学の進歩と関わりがあることです。米国のCDCは「ベッド数の多い教育病院ほど病院感染の頻度が多くなる」と言っています。このような病院では,侵襲の大きい高度な治療が行なわれる。すると術後,血管,気管,腹部,膀胱などありとあらゆる所に管を差し込むことになります。これらの突っ込まれた管は感染の原因となりますが,先進医療には欠かせない。つまり,医療が進めば進むほど病院感染は問題になると言えます。
これに関係して,「大きい病院では感染症の管理が難しい」ことがあげられています。細菌などは,ほんのわずかな隙をついて広がるわけですから,これはよい指摘です。わが国では小さな病院を統廃合する政策が強力に推進されてきていますが,これも見直す必要があるかもしれないと思います。
アメリカやイギリスでは,各病院に感染対策担当者がおり,臨床微生物検査研究ユニットと一緒に病院感染に対処していますが,わが国ではわずかに委員会を作る程度で,人的・経済的サポートもない。感染対策専門医あるいは看護婦の養成など,今後取り組むべき問題がたくさんあります。
結核の問題
吉倉 数年前,結核による病院感染が新聞に報道されたことがあります。結核の死亡は戦前に比較すれば随分減ったわけですが,依然として大きな問題です。日本では年間5-6万人くらい新しい患者があり,年間4000人ほど亡くなっている。死亡率7%ぐらいになるわけですね。また,世界を見るとエイズの流行が結核の流行を再燃させている。タイで聞いた話ですが,エイズ患者の半数は結核だということです。エイズ患者の結核は空気を介して周囲の人に感染し,エイズよりもっとたくさんの人を危険に陥れているのです。その一方,結核の診断技術は確実に低下し,従来の抗結核薬の効かない菌が増加している。大変な問題だと思います。もう1つ,結核は外国人に多いということです。日本では,結核の罹患率は日本人10万に対し39人ですが,外国人ではこの数字が56人になります。結核がほとんどなくなったというオランダ,スウェーデン,英国などでは,外国人の発症頻度は本国人の10-20倍にもなる。これは,社会保障なども含め,外国人の医療をどうするか,という大きな問題につながります。
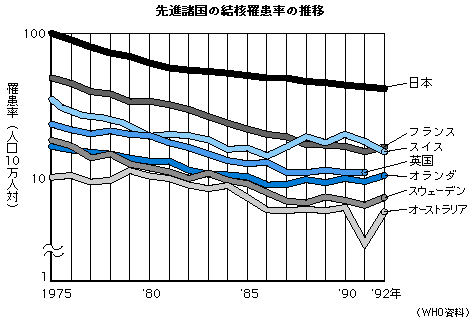
世界的に,エイズにせよ結核にせよ,感染症は社会的に弱い貧しい層に吹き寄せられるわけです。外国人に結核が多いのもその1つの現れです。日本はここ30年で年々豊かになり,貧しい者のいることを忘れてしまい,ついでに感染症という病気も忘れてしまったのではないかと思います。医学部の学生や教官からも,戦後しばらくはまだあった医療における社会的正義感が消えてしまっているような気さえします。ここでなんとかしなければいけない。特に,世界を見渡すとそう思います。医学はやはり貧しい人を忘れては困ると思います。
(おわり)
