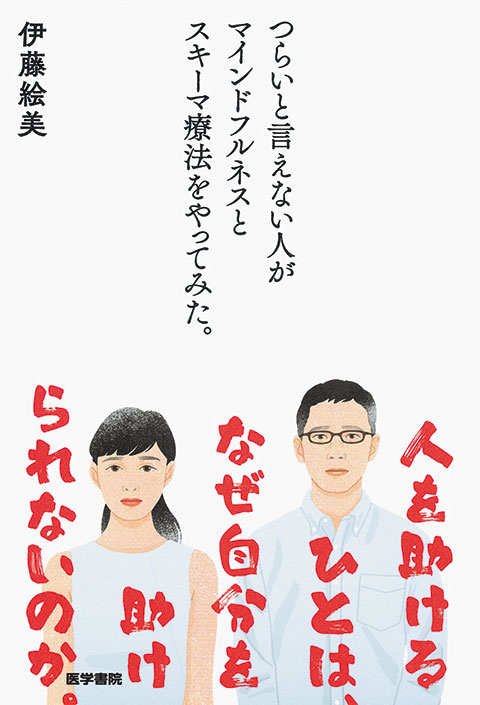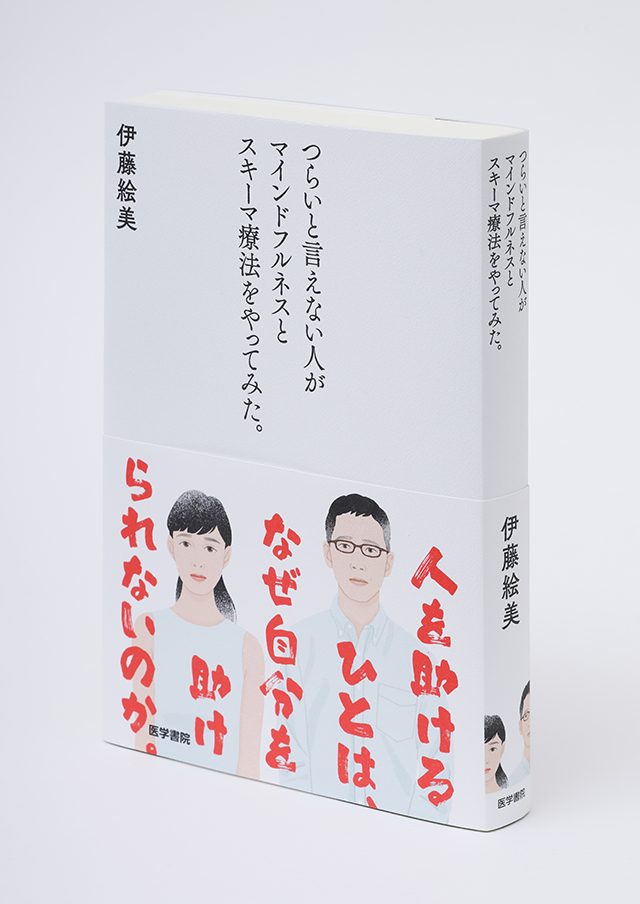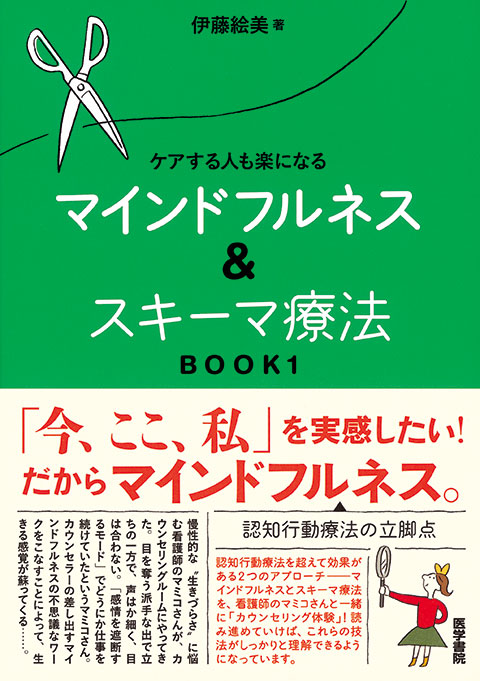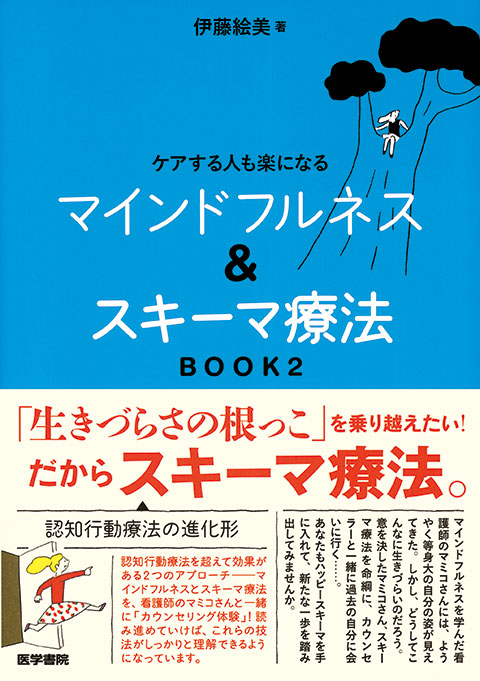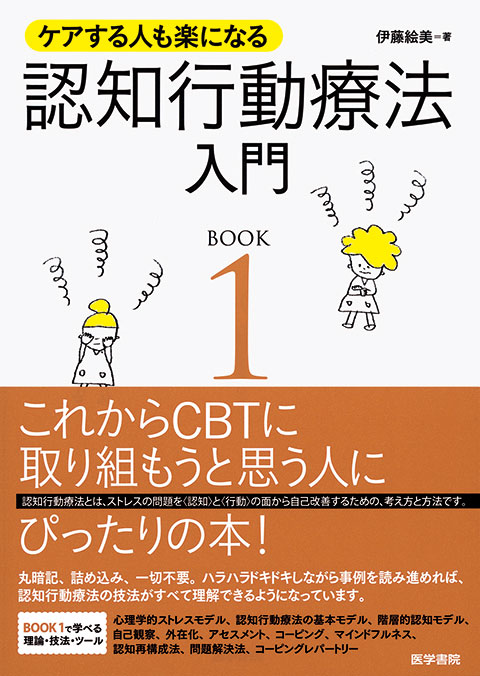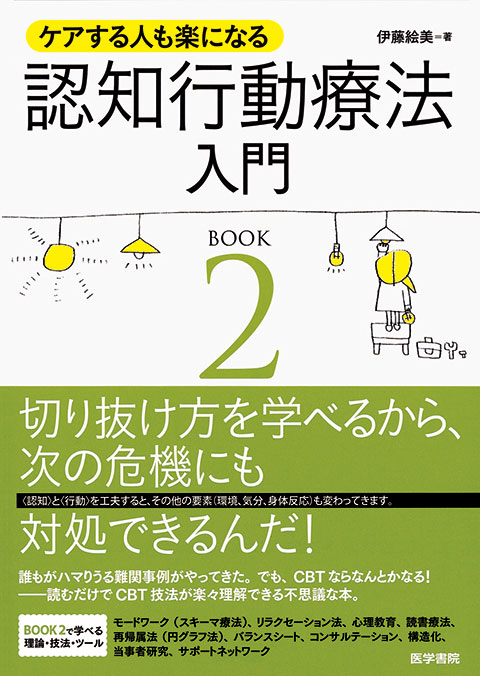つらいと言えない人がマインドフルネスとスキーマ療法をやってみた。
人を助けるひとは、なぜ自分を助けられないのか。
もっと見る
「感情を出す人をレベルが低いと見下す」“オレ様”開業医のヨウスケさん。「他人の世話ばかりしてしまう」“いい人”心理士のワカバさん。本書に登場するふたりは一見対照的ですが、意外な共通点があります。どちらも「つらいと言えない」のです。いえ、もしかして医師・看護師をはじめとする援助専門職は、みなこの“病”を持っているのかもしれません。そんな人たちが、マインドフルネスとスキーマ療法をやってみたら……。
●新聞で紹介されました。 《本書が出色なのは、「医師のヨウスケさん」と「心理士のワカバ」さんという、「自分を助けられない人助けのプロ」を主人公にしているところだ。……分厚い鎧を一枚ずつ剥いでいくそのプロセスは臨場感に満ちていて、思わず手に汗握ってしまう。解説書なのにドキドキハラハラ、実況中継を聴いているようで一気読み必至。》――伊藤亜紗(東工大准教授・美学者) (『読売新聞』2017年12月10日 読書欄 より)
| 著 | 伊藤 絵美 |
|---|---|
| 発行 | 2017年11月判型:四六頁:272 |
| ISBN | 978-4-260-03459-3 |
| 定価 | 1,980円 (本体1,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
私はなぜこの本を書いたのか―長いまえがき(抜粋)
皆様、こんにちは。伊藤絵美と申します。
私は臨床心理士で、「認知行動療法 Cognitive Behavior Therapy:CBT」という心理療法(セラピー)を専門に、臨床実践を長らく続けてきています。二〇〇四年からは東京都大田区にて「洗足ストレスコーピング・サポートオフィス」というカウンセリング機関を運営しており、多くのクライアントが認知行動療法を受けに通所されています。
(中略)
つらいと「感じられない」人びと
泣いたり笑ったりできれば、まだいい
さて、前著(『ケアする人も楽になるマインドフルネス&スキーマ療法』)でマミコさんの物語を書き終わったとき、私は考えました。「さて、次にどうしようか」。
マインドフルネスもスキーマ療法も私自身が自分のために体験するなかで、その絶大な効果を確信するに至っています。また臨床現場でも、実はBPD(境界性パーソナリティ障害)以外の障害や問題を抱えるクライアントにもマインドフルネスやスキーマ療法を提供することが増え、BPDに限らず、また精神的な障害の有無にかかわらず、多くの人に役に立つアプローチであることも経験的にわかってきました。もちろん客観的なエビデンスが、マインドフルネスについてもスキーマ療法についてもさらに積み重ねられています。
そこで、対象をBPDに留まらせず、BPD当事者ではない誰か他の人たちについて、マインドフルネスとスキーマ療法の物語を書いてみたいと思うようになりました。「BPDでなくても、マインドフルネスやスキーマ療法って、ものすごく助けになるんだな」ということを伝えたくなったのです。では、誰の物語を書けばよいのでしょうか。
そこで思い浮かんだのが、本書のテーマである「つらいと言えない人びと」です。
セラピストなら誰でも知っていることだと思いますが、何かが、あるいはどこかがつらいからセラピーを受けにきているのに、そのつらさをそのままの形でセラピストに伝えられない人たちがいます。もちろん先に書いたとおりBPDクライアントもそういう傾向が多かれ少なかれあるのですが、ていねいにセラピーを進めていけば、そしてクライアントの感情をしっかりと受け止める準備がセラピストに整っていれば、そのうちにさまざまな傷ついた感情を表出してくれるようになります。
クライアントがセッション中に自分の思いのまま泣いたり怒ったり怯えたりすることができるようになってくれると、セラピストとしての私は「あー、よかった。これでこの人と感情的につながれる」と思い、ホッとします。セラピーを仕事にしていない人からすると、目の前のクライアントが激しく泣いたり怒ったりするのは「大変なことなんじゃないか」と思うかもしれませんが、逆です。泣いたり怒ったりしてくれることが必要なのです。
「つらい」と言えない二つのタイプ
ところがBPDを抱える人以上に、はるかにそれができない人たちがいます。すなわち感情を感じられない、特に「つらい」「傷ついた」「怖い」「寂しい」「腹が立つ」といった、いわゆるネガティブな感情を感じたり、表現したりすることが本当に難しい人たち。
BPDの人たちはつらい感情を抱えていることを自ら知っているがゆえにそれを出すことを恐れるのですが、これらの人たちは、むしろ自分にそのような感情があること自体を知らない。
というか無意識レベルで「知らんぷり」しています。あるいは「感情なんか馬鹿馬鹿しい」「感情なんか必要ない」「感情なんかくだらない」「感情より理性が重要」というように、感情を見下し、感情なんかあたかも「ない」かのように信じて、生きてきた人。そういう人は自分の感情だけでなく、他人の感情も見下します。感情を出す人を「レベルの低い人」として見下すのです。
一方で、感情があることは知ってはいるのですが、あるいは感情を感じられないこともないのですが、自分の感情より他人の感情を優先する癖がついてしまっている人も、自らのネガティブな感情を認め、誰かに「つらいから助けて」と言うことができません。こういう人は他人のつらい感情には敏感で、「助けてあげたい」と思うのですが、他人の感情を優先してしまっているがゆえに、自分のつらい感情をつかまえることが非常に苦手なのです。非常に自己犠牲的です。
「感じる」とは生きていること
このような「自分のつらい感情に気づけない」「つらいから助けてと人に言えない」ということが一〇〇パーセント悪い、とは言いません。つらい感情に気がつかず、つらいと人に言えないまま、人生や生活や人間関係が特に破綻することなく、一生を過ごす人だって少なくないと思います。それも一つの生き方で、私がとやかく言うことではありません。
しかし心理学や心理療法を専門とする私にとって、やはりそれはヘルシーな生き方であるとは思えないのです。人間には必ず感情があります。生々しい感情やそれに伴う思考やイメージが日々わき上がってくるのが「生きている」ということです。それはネガティブな感情であってもポジティブな感情であっても同じことです。そのような感情を意識的にせよ無意識的にせよ抑え込んで生きる、「なかったこと」にして生きる、ということ自体に無理があると思うのです。そしてそういう人が実際にセラピーの場に姿を現すことが少なくないのです。
「つらいから助けてと人に言えない」人が、なぜセラピーに登場するのでしょうか。それこそそのような生き方に無理があって、何らかの不具合が生じているからです。その一人が本書の登場人物の一人である「ヨウスケさん」という四〇代の男性です。
つらいと言えない“オレ様”、医師のヨウスケさん
上から目線のややこしい人
ヨウスケさんは「背中の痛み」を訴えて、私のところにCBTを受けにきました。「え!? なぜ背中の痛みなのに心理療法?」「背中の痛みなら整形外科に行けばいいんじゃないの」と思われるかもしれません。もっともな反応です。
しかしヨウスケさんの背中の痛みは、整形外科的なものではないことがさまざまな検査や診察によって明らかになっていました。でも痛みは確実にあります。彼は痛みがつらくて処方薬やアルコールを乱用していました。
そんなヨウスケさんが藁をもすがる思いで、「疼痛性障害」にエビデンスがあると言われているCBTを受けに来所しました。そこからヨウスケさんの物語が始まります。
ヨウスケさんは典型的な「つらいと言えない人」でした。医師であるヨウスケさんは、臨床心理士の私(伊藤)に初めから「上から目線」でした。ヨウスケさんは最初、自分の感情に触れるどころか、背中の痛みを観察することも拒否します。心の痛みどころか身体の痛みを観察することすらも怖かったのです。でももちろん「怖い」と感じていることも自分で認めることができません。
そんなヨウスケさんと私は、紆余曲折のなかで、ようやくマインドフルネスのワークに、ついにはスキーマ療法にも取り組めるようになりました。そしてわかったことは「感じないようにしていた心の痛みが背中の痛みに置き換わっていた」ということです。ヨウスケさんはようやく自分の心の痛みに自ら向き合い、「つらいと言える人」に変わっていったのです。
自己愛性パーソナリティ障害とは
ヨウスケさんは精神医学的には「自己愛性パーソナリティ障害 Narcissistic Personality Disorder :NPD」と診断される可能性があります。自己愛性パーソナリティ障害(以下NPD)の特徴は「本当は心がうんとつらかったり心細かったりするのに、それを自分で認められず、つらさや心細さを隠したり、それらに対処したりするために、かえって不健全な自己愛で凝り固まってしまい、それによってさまざまな不具合が生じたり、対人関係がうまくいかなくなったりする」というものです。
こういう人は周囲にとってはいけ好かない「オレ様/女王様」として映ります。ですが、心のなかはつらさや心細さで本当はいっぱいなのです。しかしそのことを自分でも認められません。そのうちに何らかの不具合が身体や対人関係に生じます。しかしその不具合を素直に認めて誰かに「つらい」「助けて」とも言えません。「上から目線」で、「なんとかしろ」と要求するだけです。
なかなかややこしいですね。そしてヨウスケさんがまさにそのような「ややこしい」人だったのです。
BPDの次はNPD
実はスキーマ療法の世界では、BPDに効果があるのはすでに当然のことであり、次の治療的ターゲットとして、このNPDが注目されています。実際、私は仲間とともに、数年前に二回に分けて米国にスキーマ療法の短期研修を受けに行ったのですが、一回目のテーマがBPD、二回目のテーマがNPDでした。BPDよりさらに困難なケースとしてNPDに焦点を当て、NPDに対してどのようにスキーマ療法を適用していくか。このことを、講師によるレクチャー、講師や受講生たちとのディスカッション、受講生同士のロールプレイなどのワークを通じて学んだのでした。
ロールプレイの際には、クライアント役となってNPD当事者を演じる、ということを私自身何度もやりました。その経験を通じて、NPDを抱える人の苦しみ、すなわち「つらい」と言えず、相手に対して「上から目線」でしか接することのできない人の複雑な苦しみが、さらによく理解できるようになりました。
そして実はNPD傾向を持つ人が少なくないこと、臨床現場にもたびたび登場すること、そういうクライアントに対してセラピストが苦慮することが多々あることから、NPD傾向を色濃く持つヨウスケさんを本書に登場させることにしたのです。
つらいと言えない“いい人”、心理士のワカバさん
自分自身がおろそかになってしまう人
自分の感情を抑え込むもう一つのタイプとして先に挙げたのが、「自分の感情より他人の感情を優先して、他人の世話ばかりしてしまう人」でした。本書ではこちらのタイプの「ワカバさん」という、これもまた四〇代の女性が登場します。
「オレ様/女王様」的なヨウスケさんと違って、ワカバさんのような自己犠牲的な人はいわゆる「いい人」、それも「すこぶるいい人」として他人に映るので、たいていの場合、周囲の人たちから好かれ、頼りにされ、重宝されます。当事者もそれに応えてさらに自己犠牲的に他人のケアをしつづけることになります。
これの何がまずいのかと言うと、自分自身のケアが置き去りになってしまう、ということです。自分の心身がつらくても、それに気づかず、あるいは気づいても気づかなかったことにして、他人の世話ばかり焼いているうちに無理を重ね、何らかの不具合が生じてしまうのです。
このようなパターンから脱するためには、やはり自らのつらさを自分自身で認め、それを自分一人でなんとかしようとするのではなく、他者に手助けを求めることです。そして周囲の人が抱える問題を、「私がなんとかしなくちゃ」と思って解決しようとするパターンを手放し、「自分は自分」「他人は他人(すなわち自分ではない)」ということをしっかりと実感し、自分自身の人生を生きられるようになることです。
そのために役に立つのが、「今・ここの自分」をしっかりと感じるためのマインドフルネスや、自分の生き方の根っこやパターンを知り、それを乗り越えるためのスキーマ療法です。
多くの援助者に共通する特徴
ワカバさんは私と同じ臨床心理士で、CBTを学ぶためにスーパービジョンという教育的なセッションを求めて来所しました。すなわちセラピストとして、担当するクライアントのために、より効果的なセラピーを提供できるようになることを目的に、私のところにやってきました(「クライアントのため」というのが、すでに自己犠牲的ですね)。
CBTを私と一緒に学ぶうちに、ワカバさんは、「他人のため」ではなく「自分のため」にCBTを活用する必要性を感じ、それがひいてはマインドフルネスやスキーマ療法に展開していきました。最終的にはマインドフルネスやスキーマ療法を通じて、ワカバさんは、他人をケアする前に、自分自身をケアすると同時に、人に自分のつらさを伝えられるようになりました。そしてもう少し楽な気持ちでセラピストとして仕事ができるようになりました。
スキーマ療法を構築したジェフリー・ヤング先生(注:敬意を表して「先生」と呼びます)曰く、治療者や援助者はワカバさんのような特徴を持つ人が多いということです。本書の読者のなかには、治療者や援助者として仕事をしている人が少なくないと思います。ワカバさんのケースは、ワカバさんのようなクライアントの援助に役立てていただくのと同時に、もしご自身にワカバさん的な傾向があれば、ぜひ自分の生き方の見直しに役立てていただければと思います。
ヨウスケさんもワカバさんも一つのサンプル
一つだけ注意点を。本書ではNPD的なクライアントとしてヨウスケさんという医師を、そして自己犠牲的なクライアントとしてワカバさんという臨床心理士を、物語の主役に据えましたが、これらはあくまでもフィクションです。私がこれまでに経験した事例や学んだことを通じてつくり上げた物語です。
決して医師にNPDを持つ人が多いとか、臨床心理士はおしなべて自己犠牲的だ、と言いたいわけではありません。あくまでそれぞれ一つのサンプルとして、そして医師とか心理士とかそういうことを超えた汎用性の高いサンプルとして読んでもらえればと思います。
そしてマインドフルネスとスキーマ療法が、どんな人にでも大いに役に立ちうるツールであることを実感していただき、できれば読者の皆様自身も自分のために役立てていただけるとうれしいです。
二〇一七年九月吉日
伊藤絵美
皆様、こんにちは。伊藤絵美と申します。
私は臨床心理士で、「認知行動療法 Cognitive Behavior Therapy:CBT」という心理療法(セラピー)を専門に、臨床実践を長らく続けてきています。二〇〇四年からは東京都大田区にて「洗足ストレスコーピング・サポートオフィス」というカウンセリング機関を運営しており、多くのクライアントが認知行動療法を受けに通所されています。
(中略)
つらいと「感じられない」人びと
泣いたり笑ったりできれば、まだいい
さて、前著(『ケアする人も楽になるマインドフルネス&スキーマ療法』)でマミコさんの物語を書き終わったとき、私は考えました。「さて、次にどうしようか」。
マインドフルネスもスキーマ療法も私自身が自分のために体験するなかで、その絶大な効果を確信するに至っています。また臨床現場でも、実はBPD(境界性パーソナリティ障害)以外の障害や問題を抱えるクライアントにもマインドフルネスやスキーマ療法を提供することが増え、BPDに限らず、また精神的な障害の有無にかかわらず、多くの人に役に立つアプローチであることも経験的にわかってきました。もちろん客観的なエビデンスが、マインドフルネスについてもスキーマ療法についてもさらに積み重ねられています。
そこで、対象をBPDに留まらせず、BPD当事者ではない誰か他の人たちについて、マインドフルネスとスキーマ療法の物語を書いてみたいと思うようになりました。「BPDでなくても、マインドフルネスやスキーマ療法って、ものすごく助けになるんだな」ということを伝えたくなったのです。では、誰の物語を書けばよいのでしょうか。
そこで思い浮かんだのが、本書のテーマである「つらいと言えない人びと」です。
セラピストなら誰でも知っていることだと思いますが、何かが、あるいはどこかがつらいからセラピーを受けにきているのに、そのつらさをそのままの形でセラピストに伝えられない人たちがいます。もちろん先に書いたとおりBPDクライアントもそういう傾向が多かれ少なかれあるのですが、ていねいにセラピーを進めていけば、そしてクライアントの感情をしっかりと受け止める準備がセラピストに整っていれば、そのうちにさまざまな傷ついた感情を表出してくれるようになります。
クライアントがセッション中に自分の思いのまま泣いたり怒ったり怯えたりすることができるようになってくれると、セラピストとしての私は「あー、よかった。これでこの人と感情的につながれる」と思い、ホッとします。セラピーを仕事にしていない人からすると、目の前のクライアントが激しく泣いたり怒ったりするのは「大変なことなんじゃないか」と思うかもしれませんが、逆です。泣いたり怒ったりしてくれることが必要なのです。
「つらい」と言えない二つのタイプ
ところがBPDを抱える人以上に、はるかにそれができない人たちがいます。すなわち感情を感じられない、特に「つらい」「傷ついた」「怖い」「寂しい」「腹が立つ」といった、いわゆるネガティブな感情を感じたり、表現したりすることが本当に難しい人たち。
BPDの人たちはつらい感情を抱えていることを自ら知っているがゆえにそれを出すことを恐れるのですが、これらの人たちは、むしろ自分にそのような感情があること自体を知らない。
というか無意識レベルで「知らんぷり」しています。あるいは「感情なんか馬鹿馬鹿しい」「感情なんか必要ない」「感情なんかくだらない」「感情より理性が重要」というように、感情を見下し、感情なんかあたかも「ない」かのように信じて、生きてきた人。そういう人は自分の感情だけでなく、他人の感情も見下します。感情を出す人を「レベルの低い人」として見下すのです。
一方で、感情があることは知ってはいるのですが、あるいは感情を感じられないこともないのですが、自分の感情より他人の感情を優先する癖がついてしまっている人も、自らのネガティブな感情を認め、誰かに「つらいから助けて」と言うことができません。こういう人は他人のつらい感情には敏感で、「助けてあげたい」と思うのですが、他人の感情を優先してしまっているがゆえに、自分のつらい感情をつかまえることが非常に苦手なのです。非常に自己犠牲的です。
「感じる」とは生きていること
このような「自分のつらい感情に気づけない」「つらいから助けてと人に言えない」ということが一〇〇パーセント悪い、とは言いません。つらい感情に気がつかず、つらいと人に言えないまま、人生や生活や人間関係が特に破綻することなく、一生を過ごす人だって少なくないと思います。それも一つの生き方で、私がとやかく言うことではありません。
しかし心理学や心理療法を専門とする私にとって、やはりそれはヘルシーな生き方であるとは思えないのです。人間には必ず感情があります。生々しい感情やそれに伴う思考やイメージが日々わき上がってくるのが「生きている」ということです。それはネガティブな感情であってもポジティブな感情であっても同じことです。そのような感情を意識的にせよ無意識的にせよ抑え込んで生きる、「なかったこと」にして生きる、ということ自体に無理があると思うのです。そしてそういう人が実際にセラピーの場に姿を現すことが少なくないのです。
「つらいから助けてと人に言えない」人が、なぜセラピーに登場するのでしょうか。それこそそのような生き方に無理があって、何らかの不具合が生じているからです。その一人が本書の登場人物の一人である「ヨウスケさん」という四〇代の男性です。
つらいと言えない“オレ様”、医師のヨウスケさん
上から目線のややこしい人
ヨウスケさんは「背中の痛み」を訴えて、私のところにCBTを受けにきました。「え!? なぜ背中の痛みなのに心理療法?」「背中の痛みなら整形外科に行けばいいんじゃないの」と思われるかもしれません。もっともな反応です。
しかしヨウスケさんの背中の痛みは、整形外科的なものではないことがさまざまな検査や診察によって明らかになっていました。でも痛みは確実にあります。彼は痛みがつらくて処方薬やアルコールを乱用していました。
そんなヨウスケさんが藁をもすがる思いで、「疼痛性障害」にエビデンスがあると言われているCBTを受けに来所しました。そこからヨウスケさんの物語が始まります。
ヨウスケさんは典型的な「つらいと言えない人」でした。医師であるヨウスケさんは、臨床心理士の私(伊藤)に初めから「上から目線」でした。ヨウスケさんは最初、自分の感情に触れるどころか、背中の痛みを観察することも拒否します。心の痛みどころか身体の痛みを観察することすらも怖かったのです。でももちろん「怖い」と感じていることも自分で認めることができません。
そんなヨウスケさんと私は、紆余曲折のなかで、ようやくマインドフルネスのワークに、ついにはスキーマ療法にも取り組めるようになりました。そしてわかったことは「感じないようにしていた心の痛みが背中の痛みに置き換わっていた」ということです。ヨウスケさんはようやく自分の心の痛みに自ら向き合い、「つらいと言える人」に変わっていったのです。
自己愛性パーソナリティ障害とは
ヨウスケさんは精神医学的には「自己愛性パーソナリティ障害 Narcissistic Personality Disorder :NPD」と診断される可能性があります。自己愛性パーソナリティ障害(以下NPD)の特徴は「本当は心がうんとつらかったり心細かったりするのに、それを自分で認められず、つらさや心細さを隠したり、それらに対処したりするために、かえって不健全な自己愛で凝り固まってしまい、それによってさまざまな不具合が生じたり、対人関係がうまくいかなくなったりする」というものです。
こういう人は周囲にとってはいけ好かない「オレ様/女王様」として映ります。ですが、心のなかはつらさや心細さで本当はいっぱいなのです。しかしそのことを自分でも認められません。そのうちに何らかの不具合が身体や対人関係に生じます。しかしその不具合を素直に認めて誰かに「つらい」「助けて」とも言えません。「上から目線」で、「なんとかしろ」と要求するだけです。
なかなかややこしいですね。そしてヨウスケさんがまさにそのような「ややこしい」人だったのです。
BPDの次はNPD
実はスキーマ療法の世界では、BPDに効果があるのはすでに当然のことであり、次の治療的ターゲットとして、このNPDが注目されています。実際、私は仲間とともに、数年前に二回に分けて米国にスキーマ療法の短期研修を受けに行ったのですが、一回目のテーマがBPD、二回目のテーマがNPDでした。BPDよりさらに困難なケースとしてNPDに焦点を当て、NPDに対してどのようにスキーマ療法を適用していくか。このことを、講師によるレクチャー、講師や受講生たちとのディスカッション、受講生同士のロールプレイなどのワークを通じて学んだのでした。
ロールプレイの際には、クライアント役となってNPD当事者を演じる、ということを私自身何度もやりました。その経験を通じて、NPDを抱える人の苦しみ、すなわち「つらい」と言えず、相手に対して「上から目線」でしか接することのできない人の複雑な苦しみが、さらによく理解できるようになりました。
そして実はNPD傾向を持つ人が少なくないこと、臨床現場にもたびたび登場すること、そういうクライアントに対してセラピストが苦慮することが多々あることから、NPD傾向を色濃く持つヨウスケさんを本書に登場させることにしたのです。
つらいと言えない“いい人”、心理士のワカバさん
自分自身がおろそかになってしまう人
自分の感情を抑え込むもう一つのタイプとして先に挙げたのが、「自分の感情より他人の感情を優先して、他人の世話ばかりしてしまう人」でした。本書ではこちらのタイプの「ワカバさん」という、これもまた四〇代の女性が登場します。
「オレ様/女王様」的なヨウスケさんと違って、ワカバさんのような自己犠牲的な人はいわゆる「いい人」、それも「すこぶるいい人」として他人に映るので、たいていの場合、周囲の人たちから好かれ、頼りにされ、重宝されます。当事者もそれに応えてさらに自己犠牲的に他人のケアをしつづけることになります。
これの何がまずいのかと言うと、自分自身のケアが置き去りになってしまう、ということです。自分の心身がつらくても、それに気づかず、あるいは気づいても気づかなかったことにして、他人の世話ばかり焼いているうちに無理を重ね、何らかの不具合が生じてしまうのです。
このようなパターンから脱するためには、やはり自らのつらさを自分自身で認め、それを自分一人でなんとかしようとするのではなく、他者に手助けを求めることです。そして周囲の人が抱える問題を、「私がなんとかしなくちゃ」と思って解決しようとするパターンを手放し、「自分は自分」「他人は他人(すなわち自分ではない)」ということをしっかりと実感し、自分自身の人生を生きられるようになることです。
そのために役に立つのが、「今・ここの自分」をしっかりと感じるためのマインドフルネスや、自分の生き方の根っこやパターンを知り、それを乗り越えるためのスキーマ療法です。
多くの援助者に共通する特徴
ワカバさんは私と同じ臨床心理士で、CBTを学ぶためにスーパービジョンという教育的なセッションを求めて来所しました。すなわちセラピストとして、担当するクライアントのために、より効果的なセラピーを提供できるようになることを目的に、私のところにやってきました(「クライアントのため」というのが、すでに自己犠牲的ですね)。
CBTを私と一緒に学ぶうちに、ワカバさんは、「他人のため」ではなく「自分のため」にCBTを活用する必要性を感じ、それがひいてはマインドフルネスやスキーマ療法に展開していきました。最終的にはマインドフルネスやスキーマ療法を通じて、ワカバさんは、他人をケアする前に、自分自身をケアすると同時に、人に自分のつらさを伝えられるようになりました。そしてもう少し楽な気持ちでセラピストとして仕事ができるようになりました。
スキーマ療法を構築したジェフリー・ヤング先生(注:敬意を表して「先生」と呼びます)曰く、治療者や援助者はワカバさんのような特徴を持つ人が多いということです。本書の読者のなかには、治療者や援助者として仕事をしている人が少なくないと思います。ワカバさんのケースは、ワカバさんのようなクライアントの援助に役立てていただくのと同時に、もしご自身にワカバさん的な傾向があれば、ぜひ自分の生き方の見直しに役立てていただければと思います。
ヨウスケさんもワカバさんも一つのサンプル
一つだけ注意点を。本書ではNPD的なクライアントとしてヨウスケさんという医師を、そして自己犠牲的なクライアントとしてワカバさんという臨床心理士を、物語の主役に据えましたが、これらはあくまでもフィクションです。私がこれまでに経験した事例や学んだことを通じてつくり上げた物語です。
決して医師にNPDを持つ人が多いとか、臨床心理士はおしなべて自己犠牲的だ、と言いたいわけではありません。あくまでそれぞれ一つのサンプルとして、そして医師とか心理士とかそういうことを超えた汎用性の高いサンプルとして読んでもらえればと思います。
そしてマインドフルネスとスキーマ療法が、どんな人にでも大いに役に立ちうるツールであることを実感していただき、できれば読者の皆様自身も自分のために役立てていただけるとうれしいです。
二〇一七年九月吉日
伊藤絵美
目次
開く
私はなぜこの本を書いたのか―長いまえがき
第1章 ヨウスケさんと行ったマインドフルネス
1 ヨウスケさんとの出会い
2 背中の痛みのセルフモニタリングにトライするが……
3 マインドフルネスの練習を始める
4 夫婦関係の調整
5 ふたたびマインドフルネスのワークへ
6 ヨウスケさんの気づき
第2章 スキーマ療法を 通じてのヨウスケさんと家族の回復
1 自らのスキーマとモードについて知る
2 ヨウスケさんと家族の変化
第3章 慢性的な生きづらさを持つワカバさん
1 ワカバさんとの出会い
2 セルフモニタリングによって見えてきたこと
3 マインドフルネスのワークとそれによる気づき
4 「生きづらさ」への気づきとスキーマ分析
5 新たな生き方の模索と生活の変革
おわりに
Lecture
認知行動療法とは何か
マインドフルネスとは何か
スキーマ療法とは何か
Exercise
レーズン・エクササイズ
呼吸のマインドフルネス
歩くマインドフルネス
ボディスキャン
葉っぱのエクササイズ
シャボン玉のワーク
感情や思いを壺に入れるワーク
バーチャル味噌汁エクササイズ
香りのマインドフルネス
第1章 ヨウスケさんと行ったマインドフルネス
1 ヨウスケさんとの出会い
2 背中の痛みのセルフモニタリングにトライするが……
3 マインドフルネスの練習を始める
4 夫婦関係の調整
5 ふたたびマインドフルネスのワークへ
6 ヨウスケさんの気づき
第2章 スキーマ療法を 通じてのヨウスケさんと家族の回復
1 自らのスキーマとモードについて知る
2 ヨウスケさんと家族の変化
第3章 慢性的な生きづらさを持つワカバさん
1 ワカバさんとの出会い
2 セルフモニタリングによって見えてきたこと
3 マインドフルネスのワークとそれによる気づき
4 「生きづらさ」への気づきとスキーマ分析
5 新たな生き方の模索と生活の変革
おわりに
Lecture
認知行動療法とは何か
マインドフルネスとは何か
スキーマ療法とは何か
Exercise
レーズン・エクササイズ
呼吸のマインドフルネス
歩くマインドフルネス
ボディスキャン
葉っぱのエクササイズ
シャボン玉のワーク
感情や思いを壺に入れるワーク
バーチャル味噌汁エクササイズ
香りのマインドフルネス
書評
開く
2つの対人援助職を兼ねる看護教員だからこそ読みたい一冊(雑誌『看護教育』より)
書評者: 保田 江美 (国際医療福祉大学成田看護学部 講師)
つらいと言えない対人援助職の2人が,マインドフルネスとスキーマ療法によりいかにして幸せを手にしていくか!? 本書では,この2人と臨床心理士である著者とのやり取りが臨場感あふれる文章で描かれるとともにマインドフルネスやスキーマ療法,その基礎となる認知行動療法(CBT)についてわかりやすく解説されている。さらに,今日から実践できるマインドフルネスのエクササイズも多く紹介されている。
著者によれば,「つらいと言えない人」には,自分の感情をないものとし,感情を出す人を「レベルが低い」と見下す「オレ様/女王様」タイプと自分の感情より相手の感情を優先して,他人の世話ばかりしてしまうタイプの2つがあるという。本書では,前者のタイプであるオレ様医師のヨウスケさんと後者のタイプである真面目で隙のない臨床心理士のワカバさんの2人が登場する。
ヨウスケさんは,カウンセリングでもマウンティングをし続け,CBTの基本であるセルフモニタリング(自分の経験を自己観察する)を始めるや否や診察室から逃げるという荒業を敢行したくらい自分の内側の現象に目を向けることができなかった。看護職なら,ヨウスケさんのような人に一度は出会ったことがあるだろう。そんなヨウスケさんが著者とのやり取りのなかで,「今・ここ」に起こっていることを,「ふーん」「へー」「そっかぁ」とそのまま受け止めているうちに,その体験が遠ざかっていくというマインドフルネスのワークに徐々に積極的に取り組むようになる。いくつかのワークをとおして,ヨウスケさんは自身の核心に自ら迫っていく。さらには,スキーマ療法によって,自分の生きづらさの根っこを知り,その影響に目を向け,それを乗り越えていく。
ワカバさんもまた,CBTとマインドフルネス,スキーマ療法を行うことで,自分の生きづらさに気づき,他人のためではなく自分のために生きる「自分」を手にいれていく。著者がニューヨウスケさんと命名したのびのびと生きる彼や自分を手に入れたワカバさんを導き出したマインドフルネスやスキーマ療法の効果に私は驚き,二人が幸せになっていくプロセスにほっこりすらし,一気に読み進めた。
職務上,感情をコントロールする看護職には,ワカバさんのようなタイプが程度に差こそあれ,多いのではないだろうか。看護教員は看護職であり,教職でもある。私たちは2つの対人援助職の役割を担っているといえるだろう。本書は,対人援助職だからこそつらいと言えない生きづらさ,それに向き合うことの大切さに気づかせてくれる良書である。2つの対人援助職である私たちにこそ,今,マインドフルネスでまずは自分の内側をのぞいてみることが必要なのかもしれない。
(『看護教育』2018年3月号掲載)
書評者: 保田 江美 (国際医療福祉大学成田看護学部 講師)
つらいと言えない対人援助職の2人が,マインドフルネスとスキーマ療法によりいかにして幸せを手にしていくか!? 本書では,この2人と臨床心理士である著者とのやり取りが臨場感あふれる文章で描かれるとともにマインドフルネスやスキーマ療法,その基礎となる認知行動療法(CBT)についてわかりやすく解説されている。さらに,今日から実践できるマインドフルネスのエクササイズも多く紹介されている。
著者によれば,「つらいと言えない人」には,自分の感情をないものとし,感情を出す人を「レベルが低い」と見下す「オレ様/女王様」タイプと自分の感情より相手の感情を優先して,他人の世話ばかりしてしまうタイプの2つがあるという。本書では,前者のタイプであるオレ様医師のヨウスケさんと後者のタイプである真面目で隙のない臨床心理士のワカバさんの2人が登場する。
ヨウスケさんは,カウンセリングでもマウンティングをし続け,CBTの基本であるセルフモニタリング(自分の経験を自己観察する)を始めるや否や診察室から逃げるという荒業を敢行したくらい自分の内側の現象に目を向けることができなかった。看護職なら,ヨウスケさんのような人に一度は出会ったことがあるだろう。そんなヨウスケさんが著者とのやり取りのなかで,「今・ここ」に起こっていることを,「ふーん」「へー」「そっかぁ」とそのまま受け止めているうちに,その体験が遠ざかっていくというマインドフルネスのワークに徐々に積極的に取り組むようになる。いくつかのワークをとおして,ヨウスケさんは自身の核心に自ら迫っていく。さらには,スキーマ療法によって,自分の生きづらさの根っこを知り,その影響に目を向け,それを乗り越えていく。
ワカバさんもまた,CBTとマインドフルネス,スキーマ療法を行うことで,自分の生きづらさに気づき,他人のためではなく自分のために生きる「自分」を手にいれていく。著者がニューヨウスケさんと命名したのびのびと生きる彼や自分を手に入れたワカバさんを導き出したマインドフルネスやスキーマ療法の効果に私は驚き,二人が幸せになっていくプロセスにほっこりすらし,一気に読み進めた。
職務上,感情をコントロールする看護職には,ワカバさんのようなタイプが程度に差こそあれ,多いのではないだろうか。看護教員は看護職であり,教職でもある。私たちは2つの対人援助職の役割を担っているといえるだろう。本書は,対人援助職だからこそつらいと言えない生きづらさ,それに向き合うことの大切さに気づかせてくれる良書である。2つの対人援助職である私たちにこそ,今,マインドフルネスでまずは自分の内側をのぞいてみることが必要なのかもしれない。
(『看護教育』2018年3月号掲載)