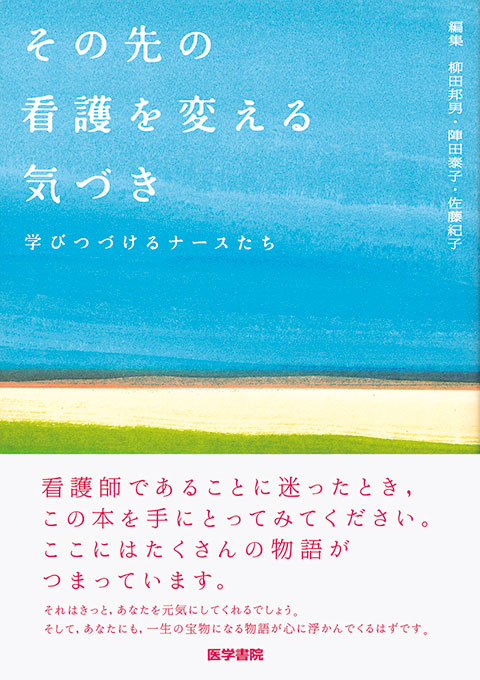患者の目線
医療関係者が患者・家族になってわかったこと
医療者と患者・家族のふたつの目線で、なっとくのケアを探そう
もっと見る
患者の本当の声を聞くことから始まる「患者が主人公」の医療。それがわかっていても、なかなかできないのが現実である。本書では、医師、看護師、看護教員、医療ジャーナリストなど、20名の医療関係者が、自身の患者・家族体験をもとに〈医療者のおかれている事情〉と〈患者・家族としての本音〉のふたつの“目線”から、「なっとくのケア」へのヒントを医療者に向けて語りかける。
| 編 | 村上 紀美子 |
|---|---|
| 発行 | 2014年04月判型:B6頁:268 |
| ISBN | 978-4-260-02021-3 |
| 定価 | 1,980円 (本体1,800円+税) |
- 販売終了
- 電子版を購入( 医書.jp )
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
プロローグ 患者の目線で話してみませんか
医療の主人公は患者です。その第1歩は、患者の本当の言葉を聞くことから始まるのでしょう。
それはわかっていても、病院の仕事の現実を考えると、「患者さんの話を聞き出すと長くなって、予定の業務が終わらない」「患者さん全員の話は聞けないし、不公平に思われそう」「患者さんはデリケートなので、怒らせたり傷つけたりしそうで怖い」「患者さんの話を聞いたら解決しないといけない気がする。でもそこまで責任がもてない」など、気になることがたくさん浮かんで、患者さんの話を聞くことをためらってしまいます。
それなら、医療関係者に、自分が患者や家族になったときの体験を聞けば、〈医療者のおかれている事情〉と一緒に〈患者・家族としての本音〉もわかるでしょう。それも、普通の人がよくかかる病気こそ、患者数が圧倒的に多いわりに見過ごされがちなので、大切にしたいのです。
このような趣旨でご相談し、月刊『看護管理』で「患者の目線-医療関係者が患者・家族になって」の連載が始まりました。執筆陣は、普通の人がよくかかる病気で患者・家族経験をされていた医師、看護師、看護教員、医療関係の行政マンやジャーナリストなど大勢に、編者の周辺でお声をかけました。しかし、ご自身やご家族の病気経験というきわめてプライベートなことを、ご自分がショックを受けた姿や気弱に落ち込んだ姿も隠さずリアルに、という不躾なお願いでしたから、「今はまだ書くことができない」というお返事も多かったのです。それでも、約3年間で33回、19人の方からすばらしいお原稿が届きました。心からお礼申し上げます。
そこには、ご自身の専門性をベースに患者や家族として経験したことを深く吟味して、医療関係者の目線のときには気づかなかったけれど、患者や家族の目線になって初めてわかったことが描かれています。「医療者の言動は、患者・家族にどう見えているのか」「患者・家族の言動や判断の背後で揺れている心理やコミュニケーションの機微」、さらにその先へ進めて「医療関係者の目線で、さてどうするか」、そして「こんなふうになったらいいな!」のアイデアや夢も生まれました。
そして、このシリーズを「まとめて読みたい」「患者さん理解の教材になりそう」などの声が届き、このたび1冊にまとめるチャンスをいただきました。
単行本にまとめるに当たって、執筆者のみなさんは、加筆修正を加えてくださっています。また、これらの貴重なドキュメンタリーレポートから何を学びとるかは、読む方の年齢や立場、関心や抱えているテーマによって、さまざまに異なると思います。そんな学びの一例として、編者の「この経験から学ぶ」を、それぞれのレポートの末尾に加えました。社会学を学び、日本看護協会の調査研究と広報部門で長く働いたのちに、フリーランスになって国内外の取材を続け、2人の子育てと90歳前後の親3人の遠距離介護中という立場での学びです。何かの手がかりになれば幸いに思います。
第1章「患者の目線 医療者の目線」では、患者さんの数が多く日常的によく遭遇する病気(コモンディジーズ)である盲腸、子宮筋腫、三叉神経痛、耳鼻科の軽手術と術後のフォローなどを取り上げています。
これらは「医療者の目線」で見れば、診断・治療法が確立しており、安全に実施さえすれば命の危険は少ない、と思われやすい病気です。とはいえ、「患者の目線」からは、自分の人生と家族の暮らしをかき乱す大事件です。読むほどに、コミュニケーションや手当て、心理面の配慮の重要性を再認識させられます。
第2章「がんとともに歩む」は、日本人の半数がかかる、がんを取り上げます。
がん健診で要精検となり確定診断が出るまでの、不安が膨らむ重苦しい日々、告知のショックから病気治療に立ち向かう力を取り戻すための支え、職場に復帰し、がんサバイバーとして過ごす年月、そして最期の日を予期しながら過ごす日々が綴られています。治療についての支えとともに、人としての心理的・社会的な支えが求められています。
第3章「迷いのなかで選ぶ看取り」は、人生を締めくくる日々についての経験です。
死期が近づいた状態での胃ろうや人工呼吸器の選択(これは諸外国ではほとんど行なわれません)、患者に付き添う家族へのグリーフケア、本人が「蘇生処置はしない(DNR)」と希望したときに救急車を呼ぶとどうなるか、病院での親しい人と心通う穏やかな看取りケアも描かれます。
多死社会に突入し、在宅やホスピス、介護施設での看取りが増えてくるとしても、病院で亡くなる人の数自体は多いと予想されます。これらの経験は、病院での穏やかな看取りケアパスウェイを見直すときの貴重な参考になるでしょう。
第4章は「患者と家族の物語」です。
ここで登場するのは、14回もの手術、腰痛の激しい痛みのなかでの病院探し、がん闘病の5年間の歳月です。それぞれの病を得てからは、病気以前とは違う暮らしへのギアチェンジが必要になることがあります。医療者と患者の相性やコミュニケーションの問題も気づかされます。
第5章では「なっとくのケア」を探します。
入院、妊娠出産、骨折治療のギプス、難病での入院や在宅ケア場面で、現実的な事情や制約のなかで、医療関係者と患者・家族の双方がなっとくできるケアを探します。「なっとくのケア」は、ふとした場面でにじみ出るようであり、勇気を出してつくっていくものでもあるようです。
本書を通して、患者や家族になったときの経験を振り返ることは、医療関係者のみなさんが今日も病院を訪れている患者や家族の暮らしや思いを想像する糸口になるでしょう。また、ご自身のなかにある「患者の目線」に気づくかもしれません。
「患者の目線ではどんなふうに見えているのかな」と、目線をときどき切り替えてみると、違った光景が見えてきそうです。いつもの「医療者の目線」と「患者の目線」を行ったり来たりすることで、両方から見てなっとくできるケアが探せそうな予感がします。あなたの職場のミーティングやカンファレンスで、研修や学校の教室で「患者の目線ではどうなのか」と、視点を切り替えて話し合ってみませんか。
患者・家族であり、医療関係者の友人として 編者 村上紀美子
医療の主人公は患者です。その第1歩は、患者の本当の言葉を聞くことから始まるのでしょう。
それはわかっていても、病院の仕事の現実を考えると、「患者さんの話を聞き出すと長くなって、予定の業務が終わらない」「患者さん全員の話は聞けないし、不公平に思われそう」「患者さんはデリケートなので、怒らせたり傷つけたりしそうで怖い」「患者さんの話を聞いたら解決しないといけない気がする。でもそこまで責任がもてない」など、気になることがたくさん浮かんで、患者さんの話を聞くことをためらってしまいます。
それなら、医療関係者に、自分が患者や家族になったときの体験を聞けば、〈医療者のおかれている事情〉と一緒に〈患者・家族としての本音〉もわかるでしょう。それも、普通の人がよくかかる病気こそ、患者数が圧倒的に多いわりに見過ごされがちなので、大切にしたいのです。
このような趣旨でご相談し、月刊『看護管理』で「患者の目線-医療関係者が患者・家族になって」の連載が始まりました。執筆陣は、普通の人がよくかかる病気で患者・家族経験をされていた医師、看護師、看護教員、医療関係の行政マンやジャーナリストなど大勢に、編者の周辺でお声をかけました。しかし、ご自身やご家族の病気経験というきわめてプライベートなことを、ご自分がショックを受けた姿や気弱に落ち込んだ姿も隠さずリアルに、という不躾なお願いでしたから、「今はまだ書くことができない」というお返事も多かったのです。それでも、約3年間で33回、19人の方からすばらしいお原稿が届きました。心からお礼申し上げます。
そこには、ご自身の専門性をベースに患者や家族として経験したことを深く吟味して、医療関係者の目線のときには気づかなかったけれど、患者や家族の目線になって初めてわかったことが描かれています。「医療者の言動は、患者・家族にどう見えているのか」「患者・家族の言動や判断の背後で揺れている心理やコミュニケーションの機微」、さらにその先へ進めて「医療関係者の目線で、さてどうするか」、そして「こんなふうになったらいいな!」のアイデアや夢も生まれました。
そして、このシリーズを「まとめて読みたい」「患者さん理解の教材になりそう」などの声が届き、このたび1冊にまとめるチャンスをいただきました。
単行本にまとめるに当たって、執筆者のみなさんは、加筆修正を加えてくださっています。また、これらの貴重なドキュメンタリーレポートから何を学びとるかは、読む方の年齢や立場、関心や抱えているテーマによって、さまざまに異なると思います。そんな学びの一例として、編者の「この経験から学ぶ」を、それぞれのレポートの末尾に加えました。社会学を学び、日本看護協会の調査研究と広報部門で長く働いたのちに、フリーランスになって国内外の取材を続け、2人の子育てと90歳前後の親3人の遠距離介護中という立場での学びです。何かの手がかりになれば幸いに思います。
第1章「患者の目線 医療者の目線」では、患者さんの数が多く日常的によく遭遇する病気(コモンディジーズ)である盲腸、子宮筋腫、三叉神経痛、耳鼻科の軽手術と術後のフォローなどを取り上げています。
これらは「医療者の目線」で見れば、診断・治療法が確立しており、安全に実施さえすれば命の危険は少ない、と思われやすい病気です。とはいえ、「患者の目線」からは、自分の人生と家族の暮らしをかき乱す大事件です。読むほどに、コミュニケーションや手当て、心理面の配慮の重要性を再認識させられます。
第2章「がんとともに歩む」は、日本人の半数がかかる、がんを取り上げます。
がん健診で要精検となり確定診断が出るまでの、不安が膨らむ重苦しい日々、告知のショックから病気治療に立ち向かう力を取り戻すための支え、職場に復帰し、がんサバイバーとして過ごす年月、そして最期の日を予期しながら過ごす日々が綴られています。治療についての支えとともに、人としての心理的・社会的な支えが求められています。
第3章「迷いのなかで選ぶ看取り」は、人生を締めくくる日々についての経験です。
死期が近づいた状態での胃ろうや人工呼吸器の選択(これは諸外国ではほとんど行なわれません)、患者に付き添う家族へのグリーフケア、本人が「蘇生処置はしない(DNR)」と希望したときに救急車を呼ぶとどうなるか、病院での親しい人と心通う穏やかな看取りケアも描かれます。
多死社会に突入し、在宅やホスピス、介護施設での看取りが増えてくるとしても、病院で亡くなる人の数自体は多いと予想されます。これらの経験は、病院での穏やかな看取りケアパスウェイを見直すときの貴重な参考になるでしょう。
第4章は「患者と家族の物語」です。
ここで登場するのは、14回もの手術、腰痛の激しい痛みのなかでの病院探し、がん闘病の5年間の歳月です。それぞれの病を得てからは、病気以前とは違う暮らしへのギアチェンジが必要になることがあります。医療者と患者の相性やコミュニケーションの問題も気づかされます。
第5章では「なっとくのケア」を探します。
入院、妊娠出産、骨折治療のギプス、難病での入院や在宅ケア場面で、現実的な事情や制約のなかで、医療関係者と患者・家族の双方がなっとくできるケアを探します。「なっとくのケア」は、ふとした場面でにじみ出るようであり、勇気を出してつくっていくものでもあるようです。
本書を通して、患者や家族になったときの経験を振り返ることは、医療関係者のみなさんが今日も病院を訪れている患者や家族の暮らしや思いを想像する糸口になるでしょう。また、ご自身のなかにある「患者の目線」に気づくかもしれません。
「患者の目線ではどんなふうに見えているのかな」と、目線をときどき切り替えてみると、違った光景が見えてきそうです。いつもの「医療者の目線」と「患者の目線」を行ったり来たりすることで、両方から見てなっとくできるケアが探せそうな予感がします。あなたの職場のミーティングやカンファレンスで、研修や学校の教室で「患者の目線ではどうなのか」と、視点を切り替えて話し合ってみませんか。
患者・家族であり、医療関係者の友人として 編者 村上紀美子
目次
開く
プロローグ 患者の目線で話してみませんか
第1章 患者の目線 医療者の目線
患者・家族の心配は医療者の想像を超えて ●勝原 裕美子
術後の痛みは当たり前? ●三輪 恭子
痛みを緩和する手当てと希望につながる言葉 ●阿保 順子
コミュニケーションの優先度をもっと高めて ●藤野 泰平
第2章 がんとともに歩む
妻が、がん!? 医師の夫の胸中は…… ●西村 元一
[コラム] マギーズがんケアリングセンター-心理・社会面の相談支援で病院を補完
“医学知識をもった友人”のような心理・社会的な相談支援 ●及川 由利子
がんサバイバーナースの10年 ●高田 芳枝
看護観察と申し送りで私は見守られていた ●上野 創
腑に落ちる人生 腑に落ちる死 ●池田 省三
第3章 迷いのなかで選ぶ看取り
延命処置の選択を迫られて ●阿保 順子
自宅で安らかな最期を迎えたい、しかし実際は…… ●高木 美穂
抜管してよかった 物語としての人生の看取り ●中村 順子
一瞬のまなざしとひと言で看取る家族は救われる ●望月 正敏
がんで逝く人、送る人 ●池田 朝子
第4章 患者と家族の物語
クリニカルパスに前のめりの関心を添えて ●榊原 千秋
激痛のなか、治療を求めて右往左往 ●村上 紀美子
あなたの立場で一緒に考える告知 ●村田 みやび
第5章 なっとくのケアへ
マニュアルを超えた援助の極意 ●藤原 瑠美
意外と言えない自分の希望 遠慮してしまうわけは? ●斎藤 元子
[コラム] 不本意なバッドニュースを患者・家族と話し合う英国の知恵
助産師は最高の水先案内人 妊産婦が主体的になれる健康教育 ●大久保 菜穂子
一人暮らし高齢者が骨折 ギプス内の耐えがたいかゆみ ●村上 紀美子
今一度、見直しませんか? 人生と医療・介護 ●森山 美知子
エピローグ 自分が患者・家族になった経験を大切に
初出一覧
第1章 患者の目線 医療者の目線
患者・家族の心配は医療者の想像を超えて ●勝原 裕美子
術後の痛みは当たり前? ●三輪 恭子
痛みを緩和する手当てと希望につながる言葉 ●阿保 順子
コミュニケーションの優先度をもっと高めて ●藤野 泰平
第2章 がんとともに歩む
妻が、がん!? 医師の夫の胸中は…… ●西村 元一
[コラム] マギーズがんケアリングセンター-心理・社会面の相談支援で病院を補完
“医学知識をもった友人”のような心理・社会的な相談支援 ●及川 由利子
がんサバイバーナースの10年 ●高田 芳枝
看護観察と申し送りで私は見守られていた ●上野 創
腑に落ちる人生 腑に落ちる死 ●池田 省三
第3章 迷いのなかで選ぶ看取り
延命処置の選択を迫られて ●阿保 順子
自宅で安らかな最期を迎えたい、しかし実際は…… ●高木 美穂
抜管してよかった 物語としての人生の看取り ●中村 順子
一瞬のまなざしとひと言で看取る家族は救われる ●望月 正敏
がんで逝く人、送る人 ●池田 朝子
第4章 患者と家族の物語
クリニカルパスに前のめりの関心を添えて ●榊原 千秋
激痛のなか、治療を求めて右往左往 ●村上 紀美子
あなたの立場で一緒に考える告知 ●村田 みやび
第5章 なっとくのケアへ
マニュアルを超えた援助の極意 ●藤原 瑠美
意外と言えない自分の希望 遠慮してしまうわけは? ●斎藤 元子
[コラム] 不本意なバッドニュースを患者・家族と話し合う英国の知恵
助産師は最高の水先案内人 妊産婦が主体的になれる健康教育 ●大久保 菜穂子
一人暮らし高齢者が骨折 ギプス内の耐えがたいかゆみ ●村上 紀美子
今一度、見直しませんか? 人生と医療・介護 ●森山 美知子
エピローグ 自分が患者・家族になった経験を大切に
初出一覧
書評
開く
妊産婦に寄り添う時の助産師の目線は (雑誌『助産雑誌』より)
書評者: 内木 美恵 (日本赤十字看護大学大学院講師)
本書を読み終えて,私のなかにはいくつかのフレーズが残った。「看護師は遠慮なく何でも聞いてくださいと言うが,患者はなかなか聞けない」「医療主導ではなく,患者と家族の希望や意思を尊重する」。これらは基礎教育や卒後教育で常に耳にしているフレーズばかりだ。しかし本書を読みながら,実際に実践できているのかという疑問が浮かんだ。そして同時に,私が助産師として産婦人科病棟で働いていた時のこと,自分が入院した時のことを思い出していた。
私が病院で助産師として働き始めたころは,妊婦や患者などを対象に「遠慮なく何でも聞いてください」というフレーズをよく使った。しかし,対象が本当に何でも聞ける雰囲気をつくり,何に困っているかを想像し,対象の表情からも問題を読み取ろうと努めていたかというと,必ずしもそうではなかった。本書にもあったが,治療の優先や,業務が増えて煩雑になることへの懸念,出産をしていない私が答えてもいいのかといった不安が頭をよぎり,口先だけでこのフレーズを使っていたこともあったと思う。加えて,経験が浅いことで対象の生活を察しようにも想像がつかず,個別性を考えた看護やアドバイスが難しかった。対象の住居構造や家族構成,過ごし方,仕事や趣味まで考えて説明したり,アドバイスしたりできるようになったのは,自分が病気を体験したり,さまざまな対象へのケアや妊産婦指導を経験したりしてからだった。
対象や家族から教えてもらった個々の思いや生活環境からくる健康問題,そして私の看護に対するフィードバックに気づいてからは,対象の個別性に視点を置き,より実生活に則したアドバイスをしようと努めるようになった。
さらに,対象が何でも気軽に聞ける雰囲気は,対象の生活や価値観を中心に置かなければ実現できない。対象のライフスタイルや仕事,人生で大事にしていることに目を向けて医療の提供を考えたい。本書のなかにある「医療者の説明が腑に落ちた」という言葉は,医療者の一方的な意見ではなく,対象が納得いく治療や医療の方向性が見出せたからこそ出てくる。医療者が対象の上に立って指示したり,説き伏せたりするのではなく,対象とともに考える姿勢をもち続けたい。
また,助産師の対象である産婦は陣痛を感じて出産にいたるが,苦しみの先にうれしい結果がある痛みは,病気にはない。助産師は,妊産婦がもっている産む力を最大限に引き出し,つらい痛みを乗り越えお産へと支援することが役割である。本書の「助産師はお産の水先案内人」という言葉に助産師への期待が込められている。
2015年4月にWHOが帝王切開率の上昇に警鐘を鳴らしていた。お産の水先案内人として,妊産婦の力を引き出しつつ,対象の目線で痛みや苦痛に寄り添う看護を心がけたい。本書は私にとって,あらためて自分の看護を振り返るきっかけをつくってくれた。
(『助産雑誌』2015年8月号掲載)
「なっとくのケア」を探索する手立てが得られる (雑誌『保健師ジャーナル』より)
書評者: 村嶋 幸代 (大分県立看護科学大学理事長・学長)
“目から鱗〈うろこ〉”がたくさん詰まった本である。執筆者20人は,かなり名前の通った医療関係者,もしくは看護・介護・福祉に関わる研究者や編集者・行政職である。その人たちが,実名で,「自分・家族の医療体験」を書いているのだから,とても説得力がある。面白く,思わず「なっとく」してしまうエピソードや教訓があふれている。
個々の体験談の後には,毎回,編者の村上紀美子氏による「この経験から学ぶ」が付いている。温かく,かつ,的確にポイントが解説されており,学ぶべきことが多い。
第1章「患者の目線 医療者の目線」は,日常的によく遭遇する盲腸,子宮筋腫などの手術と術後のフォローが扱われている。これらの疾患は「医療者の目線」からは診断・治療法が確立しており,危険は少ないと思われやすいが,「患者の目線」からは“自分と家族の大事件”である。両者の視点の違いとともに,患者・家族が乗り越えていくためには,医療者側の配慮がとても重要だとわかる。
第2章「がんとともに歩む」では,日本人の約半数がかかるがんが取り上げられている。健診で要精検となり,確定診断が出るまでの不安な日々,治療に立ち向かう力を取り戻す過程,がんサバイバーとして,また,最期の日を予期しながら過ごす日々が綴られており,各々の過程における「支え」の重要性が示されている。イギリスのマギーズがんケアリングセンターの機能や役割も紹介されており,日本でも必要だと認識させられる。
第3章「迷いのなかで選ぶ看取り」は,人生を締めくくる日々についての経験が語られる。胃ろうや人工呼吸器の選択,家族へのグリーフケア,また,病院での穏やかな看取りケアも描かれている。「最期の時を本人と家族に返す」「患者の話したひと言をメモにして家族に伝える」など,医療者として必要な,貴重な行動規範が示されている。
第4章は「患者と家族の物語」である。14回もの手術体験,激しい痛みの中での病院探しなどが語られている。病気以前とは違う暮らしへの対応策,医療者と患者との相性やコミュニケーションの問題にも気づかされる。
第5章「なっとくのケア」では,入院,妊娠出産,骨折治療のギプスなど現実的な事情や制約の中で,医療関係者と患者・家族の双方が「なっとくできるケア」を探すプロセスが丁寧に描かれている。「私たちの仕事は高齢者の望みをかなえること」として,気働きすることの重要性が指摘されている。
このように,いずれの文章にも平易な言葉の中に重要な事項が指摘されていて,読んでいてとてもためになる,楽しい本である。
本書は,今まで患者と対置している存在と考えられることの多かった「医療関係者」が,患者・家族になることによって2つの目線をもつことができ,そこで得られた知見から「なっとくのケア」を探索する手立てを得ることのできる大変素晴らしい本である。自分のこと,家族のことを正直にわかりやすく書いてくださった執筆者たちに感謝したい。
職場でのカンファレンスや勉強会の素材として,また,これから保健・医療・福祉分野で働くことを希望する学生の教材として,ぜひ活用されることをお薦めする。
(『保健師ジャーナル』2014年12月号掲載)
医療者が,一歩立ち止まって明日の仕事に向かうために
書評者: 松本 武敏 (秋津レークタウンクリニック・内科)
本書には,編者である村上紀美子氏の幅広い人脈によって,珠玉の原稿が集められています。そして,天国に旅立たれた方の貴重な一筆も含まれています。
編者は,日本看護協会の広報部長を経験されたフリーランスの医療ジャーナリストです。その編者が「患者・家族であり,医療関係者の友人として」厳しくも温かい配慮をしながら,医療者へのフィードバックを目的として,医療関係者に個人的体験をリアルに書いてほしいと著者らに依頼しました。そうして,月刊『看護管理』に約3年間にわたりリレー形式で掲載されたものがこの本のもとになっています。書籍化に当たり,加筆されるとともに,編者が「この経験から学ぶ」を付け加えています。
実は,2012年4月に,膵臓がんの父を自宅で看取った私にも,原稿を書く話をいただきました。しかし,文章を書くことが好きな私でも当時は「今はまだ書くことができない」とお返事するしかありませんでした。ゆえに,執筆された方々の思いを理解していますし,たとえ医療者であっても,「患者」や「患者の家族」になった場合に,こんなに悩んだり苦しんだりするという現実の奥深さ,内容の持つ価値に,思わずページをめくってしまいました。柳田邦男氏の言うところの2.5人称のアプローチを,普段の仕事で大切にされている方々が,実際に1人称や2人称の経験をつづったという意味でも切実な一書です。
本書は,第1章「患者の目線 医療者の目線」から始まります。夫の心臓の弁置換術の説明の際に用いるブタの弁に関して「そのブタは元気だったか」という妻の問いは,真剣そのものです。子宮筋腫の術後の痛みも,医療者には当たり前でも患者となればそうはいきません。術後の予防的な疼痛コントロールの提案は一考に値します。
第2章「がんとともに歩む」では,がんと突然告げられた妻とともに不安になる夫の胸中,怒涛の1か月は他人事ではありません。また,サバイバーナースの乳がん体験では,何気ない医療者のひと言が,患者さんにとっては傷つく場面が盛り込まれています。介護保険創設に向けた運動をされ,今は天上におられる,池田省三氏の「腑に落ちる人生 腑に落ちる死」では,ケアがはらむ「傾斜関係」について考えさせられました。
第3章「迷いの中で選ぶ看取り」では,気管挿管を抜管するサポートを通して,看取りを本人と家族に返す視点を看護師が訴えます。また一瞬のまなざしとひと言で,看取る家族が救われる経験を看護雑誌編集者が記しています。
第4章「患者と家族の物語」では,医療者が患者さんの人生の物語に,ほんの少しだけ「前のめりの関心」をもつ必要性が述べられています。夫の肺がんを経験された妻からは,医療者が行う説明の重みがひしひしと伝わってきて,本当の意味でのインフォームド・コンセントを自分が果たしてどのようにしてきたのか反省も含めて考えさせられます。
第5章「なっとくのケアへ」では,マニュアルを超えた援助の極意が紹介されています。
医療者の方々が,一歩立ち止まって明日の仕事に向かうためにも,ぜひ,一読されることをお薦めします。
書評者: 内木 美恵 (日本赤十字看護大学大学院講師)
本書を読み終えて,私のなかにはいくつかのフレーズが残った。「看護師は遠慮なく何でも聞いてくださいと言うが,患者はなかなか聞けない」「医療主導ではなく,患者と家族の希望や意思を尊重する」。これらは基礎教育や卒後教育で常に耳にしているフレーズばかりだ。しかし本書を読みながら,実際に実践できているのかという疑問が浮かんだ。そして同時に,私が助産師として産婦人科病棟で働いていた時のこと,自分が入院した時のことを思い出していた。
私が病院で助産師として働き始めたころは,妊婦や患者などを対象に「遠慮なく何でも聞いてください」というフレーズをよく使った。しかし,対象が本当に何でも聞ける雰囲気をつくり,何に困っているかを想像し,対象の表情からも問題を読み取ろうと努めていたかというと,必ずしもそうではなかった。本書にもあったが,治療の優先や,業務が増えて煩雑になることへの懸念,出産をしていない私が答えてもいいのかといった不安が頭をよぎり,口先だけでこのフレーズを使っていたこともあったと思う。加えて,経験が浅いことで対象の生活を察しようにも想像がつかず,個別性を考えた看護やアドバイスが難しかった。対象の住居構造や家族構成,過ごし方,仕事や趣味まで考えて説明したり,アドバイスしたりできるようになったのは,自分が病気を体験したり,さまざまな対象へのケアや妊産婦指導を経験したりしてからだった。
対象や家族から教えてもらった個々の思いや生活環境からくる健康問題,そして私の看護に対するフィードバックに気づいてからは,対象の個別性に視点を置き,より実生活に則したアドバイスをしようと努めるようになった。
さらに,対象が何でも気軽に聞ける雰囲気は,対象の生活や価値観を中心に置かなければ実現できない。対象のライフスタイルや仕事,人生で大事にしていることに目を向けて医療の提供を考えたい。本書のなかにある「医療者の説明が腑に落ちた」という言葉は,医療者の一方的な意見ではなく,対象が納得いく治療や医療の方向性が見出せたからこそ出てくる。医療者が対象の上に立って指示したり,説き伏せたりするのではなく,対象とともに考える姿勢をもち続けたい。
また,助産師の対象である産婦は陣痛を感じて出産にいたるが,苦しみの先にうれしい結果がある痛みは,病気にはない。助産師は,妊産婦がもっている産む力を最大限に引き出し,つらい痛みを乗り越えお産へと支援することが役割である。本書の「助産師はお産の水先案内人」という言葉に助産師への期待が込められている。
2015年4月にWHOが帝王切開率の上昇に警鐘を鳴らしていた。お産の水先案内人として,妊産婦の力を引き出しつつ,対象の目線で痛みや苦痛に寄り添う看護を心がけたい。本書は私にとって,あらためて自分の看護を振り返るきっかけをつくってくれた。
(『助産雑誌』2015年8月号掲載)
「なっとくのケア」を探索する手立てが得られる (雑誌『保健師ジャーナル』より)
書評者: 村嶋 幸代 (大分県立看護科学大学理事長・学長)
“目から鱗〈うろこ〉”がたくさん詰まった本である。執筆者20人は,かなり名前の通った医療関係者,もしくは看護・介護・福祉に関わる研究者や編集者・行政職である。その人たちが,実名で,「自分・家族の医療体験」を書いているのだから,とても説得力がある。面白く,思わず「なっとく」してしまうエピソードや教訓があふれている。
個々の体験談の後には,毎回,編者の村上紀美子氏による「この経験から学ぶ」が付いている。温かく,かつ,的確にポイントが解説されており,学ぶべきことが多い。
第1章「患者の目線 医療者の目線」は,日常的によく遭遇する盲腸,子宮筋腫などの手術と術後のフォローが扱われている。これらの疾患は「医療者の目線」からは診断・治療法が確立しており,危険は少ないと思われやすいが,「患者の目線」からは“自分と家族の大事件”である。両者の視点の違いとともに,患者・家族が乗り越えていくためには,医療者側の配慮がとても重要だとわかる。
第2章「がんとともに歩む」では,日本人の約半数がかかるがんが取り上げられている。健診で要精検となり,確定診断が出るまでの不安な日々,治療に立ち向かう力を取り戻す過程,がんサバイバーとして,また,最期の日を予期しながら過ごす日々が綴られており,各々の過程における「支え」の重要性が示されている。イギリスのマギーズがんケアリングセンターの機能や役割も紹介されており,日本でも必要だと認識させられる。
第3章「迷いのなかで選ぶ看取り」は,人生を締めくくる日々についての経験が語られる。胃ろうや人工呼吸器の選択,家族へのグリーフケア,また,病院での穏やかな看取りケアも描かれている。「最期の時を本人と家族に返す」「患者の話したひと言をメモにして家族に伝える」など,医療者として必要な,貴重な行動規範が示されている。
第4章は「患者と家族の物語」である。14回もの手術体験,激しい痛みの中での病院探しなどが語られている。病気以前とは違う暮らしへの対応策,医療者と患者との相性やコミュニケーションの問題にも気づかされる。
第5章「なっとくのケア」では,入院,妊娠出産,骨折治療のギプスなど現実的な事情や制約の中で,医療関係者と患者・家族の双方が「なっとくできるケア」を探すプロセスが丁寧に描かれている。「私たちの仕事は高齢者の望みをかなえること」として,気働きすることの重要性が指摘されている。
このように,いずれの文章にも平易な言葉の中に重要な事項が指摘されていて,読んでいてとてもためになる,楽しい本である。
本書は,今まで患者と対置している存在と考えられることの多かった「医療関係者」が,患者・家族になることによって2つの目線をもつことができ,そこで得られた知見から「なっとくのケア」を探索する手立てを得ることのできる大変素晴らしい本である。自分のこと,家族のことを正直にわかりやすく書いてくださった執筆者たちに感謝したい。
職場でのカンファレンスや勉強会の素材として,また,これから保健・医療・福祉分野で働くことを希望する学生の教材として,ぜひ活用されることをお薦めする。
(『保健師ジャーナル』2014年12月号掲載)
医療者が,一歩立ち止まって明日の仕事に向かうために
書評者: 松本 武敏 (秋津レークタウンクリニック・内科)
本書には,編者である村上紀美子氏の幅広い人脈によって,珠玉の原稿が集められています。そして,天国に旅立たれた方の貴重な一筆も含まれています。
編者は,日本看護協会の広報部長を経験されたフリーランスの医療ジャーナリストです。その編者が「患者・家族であり,医療関係者の友人として」厳しくも温かい配慮をしながら,医療者へのフィードバックを目的として,医療関係者に個人的体験をリアルに書いてほしいと著者らに依頼しました。そうして,月刊『看護管理』に約3年間にわたりリレー形式で掲載されたものがこの本のもとになっています。書籍化に当たり,加筆されるとともに,編者が「この経験から学ぶ」を付け加えています。
実は,2012年4月に,膵臓がんの父を自宅で看取った私にも,原稿を書く話をいただきました。しかし,文章を書くことが好きな私でも当時は「今はまだ書くことができない」とお返事するしかありませんでした。ゆえに,執筆された方々の思いを理解していますし,たとえ医療者であっても,「患者」や「患者の家族」になった場合に,こんなに悩んだり苦しんだりするという現実の奥深さ,内容の持つ価値に,思わずページをめくってしまいました。柳田邦男氏の言うところの2.5人称のアプローチを,普段の仕事で大切にされている方々が,実際に1人称や2人称の経験をつづったという意味でも切実な一書です。
本書は,第1章「患者の目線 医療者の目線」から始まります。夫の心臓の弁置換術の説明の際に用いるブタの弁に関して「そのブタは元気だったか」という妻の問いは,真剣そのものです。子宮筋腫の術後の痛みも,医療者には当たり前でも患者となればそうはいきません。術後の予防的な疼痛コントロールの提案は一考に値します。
第2章「がんとともに歩む」では,がんと突然告げられた妻とともに不安になる夫の胸中,怒涛の1か月は他人事ではありません。また,サバイバーナースの乳がん体験では,何気ない医療者のひと言が,患者さんにとっては傷つく場面が盛り込まれています。介護保険創設に向けた運動をされ,今は天上におられる,池田省三氏の「腑に落ちる人生 腑に落ちる死」では,ケアがはらむ「傾斜関係」について考えさせられました。
第3章「迷いの中で選ぶ看取り」では,気管挿管を抜管するサポートを通して,看取りを本人と家族に返す視点を看護師が訴えます。また一瞬のまなざしとひと言で,看取る家族が救われる経験を看護雑誌編集者が記しています。
第4章「患者と家族の物語」では,医療者が患者さんの人生の物語に,ほんの少しだけ「前のめりの関心」をもつ必要性が述べられています。夫の肺がんを経験された妻からは,医療者が行う説明の重みがひしひしと伝わってきて,本当の意味でのインフォームド・コンセントを自分が果たしてどのようにしてきたのか反省も含めて考えさせられます。
第5章「なっとくのケアへ」では,マニュアルを超えた援助の極意が紹介されています。
医療者の方々が,一歩立ち止まって明日の仕事に向かうためにも,ぜひ,一読されることをお薦めします。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。