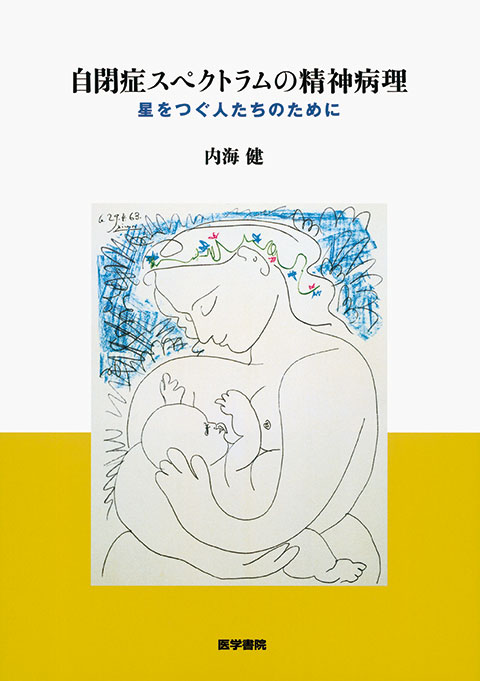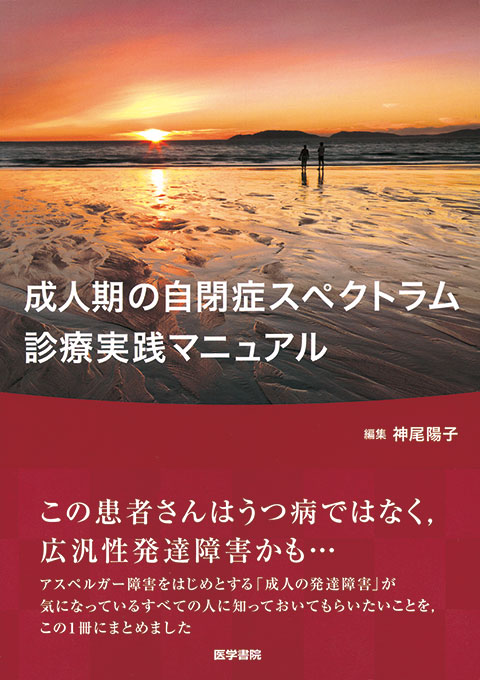自閉症スペクトラムの精神病理
星をつぐ人たちのために
青年期・成人期の「自閉症スペクトラム」(ASD)を対象とした臨床論
もっと見る
精神科医が日々の診療場面で出会う青年期・成人期の「自閉症スペクトラム」(ASD)を対象とした臨床論。障害の受容、適応、さらには共生をいう前に、あたかも異星人であるがごとくこの星に棲むための苦労を重ねている彼らがどのような世界に棲んでいるのか、そもそもの経験の成り立ちについて、もう少し突っ込んで考えてみることはできないだろうか——精神科臨床の基本ともいうべき精神病理学のテイストを下地にまとめられた書。
| 著 | 内海 健 |
|---|---|
| 発行 | 2015年11月判型:A5頁:304 |
| ISBN | 978-4-260-02408-2 |
| 定価 | 3,850円 (本体3,500円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
本書は,精神科医が日々の診療場面で出会う青年期・成人期の「自閉症スペクトラム」(ASD)を対象とした臨床論である.ほとんどの事例が,仕事や学業など,一定の社会的な営みにたずさわっている.
振り返ってみると,90年代の後半から,こうした事例に散発的に遭遇するようになり,それがみるまに,一群のまとまりをもつようになった.当初は随分と当惑したものだが,あらためて概念を学び,それを臨床経験によって肉付けしていくことによって,少しずつではあるが,かかわるポイントがみえてきたように思う.
青年期・成人期のASD 1 には,「小児自閉症」というゆるぎのないプロトタイプがある.その意味では,他の疾患と比較して,安定した臨床概念であるようにみえる.確かにそうした一面はあるが,他方で,「小児自閉症」と「成人ASD」の間には,大きな隔たりがあるのもまた事実である.
そもそもの自閉症概念は,孤立が最も顕著となる3歳から5歳の男児をプロトタイプとして組み立てられている.そこから導かれた症候学を,そのまま成人例や女性例にあてはめるには無理がある.
他方で,ちょっとしたそれらしき特性,たとえば「鉄道マニア」であるとか,「空気が読めない」といったようなことがあるだけで,ASDと見立てるのは乱暴な話である.過剰診断という以前に,そもそも当事者に役立たない診断など,単なるスティグマにすぎない.
成人例を診ることの利点は,彼ら彼女たちが自らについて語るということにある.そればかりか,書く能力に秀でていることさえある.実際,ドナ・ウィリアムズ(Donna Williams),グニラ・ガーランド(Gunilla Gerland),藤家寛子,森口奈緒美らの自伝からは,ありふれた解説書のたぐいを読むよりも,はるかに学ぶところが多い.これはかつての精神疾患にはなかったことである.こうしたことばをもつ成人事例と,ことばをもたないコアの「自閉症」との間を行き来することによって,より豊かな臨床概念がもたらされるはずである.
筆者は自閉症児の療育にたずさわった経験はない.しかし,偶々〈たまたま〉ではあるが,これまで彼らの生きる現場を肌で感じる機会に事欠くことはなかった.加えて,カナー(Leo Kanner 2 )とアスペルガー(Hans Asperger 3 )のすぐれた古典がある.いまだにこの二つの論考以上に,自閉症児を生き生きと描き出したものはない.
自閉症を考える際には,「脳」と「発達」という二つの柱がある.これらが重要であることはいうまでもない.ただ,その際,発想が窮屈にならないように気をつけなければならない.「脳」ということばを聞いただけで思考停止に陥るようでは,臨床家として終わっている.
生き物としてみた人間は,実に多くの欠陥を抱えている.そもそもの出発点で,およそ生命体としてはありえないくらいに,未成熟な状態で産み落とされる.ようやく生後9か月になって,オランウータンの生まれたばかりの赤ちゃんと同じ程度の身体能力が備わる.
これほどまでに無力な状態で産み落とされる生物は他にない.それゆえ,人間の個体間には,他の生物にはみられない関係が結ばれることになる.その結果として産み出されるのが,関係の起点となる「こころ」であり,関係の総体としての「社会」である.種として生き延びるためには,こうしたものを作り上げるよりないのである.より正確にいえば,「こころ」や「社会」などといったものを創発した(でっちあげた)がために,たまさか生き延びることができたのである.
人間の脳もさまざま欠陥を抱えている.そもそも,単独では作動できない.他者や環境といった<外部>をなかに含み込んでいる.他者からの働きかけがないと,うまく機能しないのである.さらに言語という奇妙なシステムを,認識と行動を制御するために不可欠のものとして,実装しなければならない.
発達もまた,自然には展開しない.他者とのかかわりのなかで,こころや社会といった自然にはないものを取り込んでいかなければならない.そして家族,学校,会社といった,さまざまな制度に適応しなければならないのである.
こころや社会というものは,一定のものではない.時代や文化で大きく変わる.ヨーロッパではつい最近まで神が生きており,こころの問題はもっぱら神やその代理人たちに預けられていた.いちいち考えなくともよかったのである.日本の伝統文化のなかでは,こころは人間の専有物ではなく,およそ自然のいたるところに感じられていた.今でもそう感じられなくもないだろう.
定型とされる発達も,その時代や文化によって大きく異なる.たとえば,「青年期」という,今ではあたりまえとなっている発達区分ができたのは,20世紀の初頭である.それまでは児童期が終わると,すぐに成人期に接続していた.さらにその前になると,「児童」という概念すらなく,働けるようになると,すぐに大人扱いされたのである.他方,今や,青年期は30歳,さらには40歳にまで延長されようとしている.近い将来,大多数が万年青年となれば,「青年期」そのものが解消されてしまうかもしれない(図,本サイトでは省略).
それゆえ,現時点で定型とされる発達の様式もまた,偶々のものでしかない.それに適応できぬ個体,そこからはずれる個体が,一定の割合で存在しても,何ら不思議なことではない.
ことばももたぬ中核の自閉症と比較するなら,成人ASDの精神病理ははるかに軽い.だが,それはかならずしも,彼ら彼女たちの方が生きやすいことを意味しない.むしろ適応という視点では,周囲から「障害」とみなされる程度の事例の方が,より安定した生活を営むといわれたりもする.
他の精神疾患にもみられることだが,病理が軽い事例の方が,生きる上での苦悩や困難が,かえってハードなものとなりうる.さらに成人ASDの場合,彼ら彼女たちに固有の問題がある.それは,他者の存在に気づき,自己にめざめるという,天変地異とでもいうべきカタストロフが,いずれふりかかってくるということである.
これは,定型者にとっては,自分の知らぬ間にすませた課題である.気がついたときにはすでに自分は自分である.それゆえ困難に対して共感も届かないし,モデルを提供することもできない.しかも「発達」という観点から,歓迎すべきこととしてすまされてしまいかねない.だが,そんなことでは,それが混乱や哀しみや緊張に満ちたものであることは,想像もつかないだろう.
本書がめざすのは,ASDの精神病理を明らかにする試みをとおして,彼らの抱える苦悩や困難にかかわるポイントを見出すことである.脳も発達も,この作業にはなかなか歯がたたない.人間という奇妙な生き物が発明したこころや社会といったものを,自明のものとせず,問い直す作業が必要である.それによってこそ,彼ら彼女たちの立ち会っている事態を理解し,有効な手だてを工夫する端緒が与えられるだろう.
本論に入るにあたって,本書の構成について,簡単な見通しを示しておこう.
第1章から第3章までは,「心の理論」仮説に含まれる根本的な誤りを検討しながら,ASDの精神病理のミニマムを提示する.要約すれば,それは「まなざし」,「呼びかけ」,「抱きかかえ」といった他者からの志向性に対して応答しないことである.そしてこの応答によって立ち上がるのが,まさに「自己」である.最初から自己を想定していては,ASDの世界へアプローチするための鍵は与えられない.
第4章では,生後9か月目頃に訪れる,乳児の世界の大規模な組み替えについて,それを「9か月革命」と銘打って示す.本書における発達論がこの章に集約されている.現在のこころの発達は,一個の「自己」にまとめあげることを自明の前提として求める.これは物理的,生理的な個体化ではなく,他者からの志向性によって切り出される象徴的個体化である.その端緒となるのが生後9か月目頃であり,乳児の世界は劇的に変化する.その地点でASDはつまずくのであり,精神病理の原点がそこにある.
第5章から第8章では,「自他未分」という出発点から導き出されるASDの世界を提示する.ローナ・ウィング(Lorna Wing)の「障害の三つ組」でいえば,5章が想像力,6章から8章が対人相互性に関するものとなる.想像力の障害は,通常,物に対する執着,常同的な行動,変化への抵抗などの,いわゆる「こだわり」の強さによって説明されているが,想像力の本来の機能に立ちかえって検討を加えた.そこには「こだわり」も包摂される.対人相互性の障害については,反転性がないこと(6章),地続きであること(7章),影響を受けやすいこと(8章)に分けて解説している.
第9章では,これらの考察を踏まえて,いわゆるASDの認知行動特性を,(1)経験を大域的〈おおまか〉に束ねることの障害,(2)文脈からのデカップリングの障害の二つに大別して,系統的に整理した.
第10章と第11章では,言語について,やや突っ込んだ考察を加えた.というのも,多くのASD論において,言語観そのものが,百年以上前の素朴な,out-of-dateの水準にあり,その点から論じ直さなければならなかったからである.言語を出来あがったシステムではなく,つねにあらたに行われる行為としてとらえることによって,ASDの言語の特異性に迫る試みである.「障害の三つ組」でいえば,コミュニケーションの障害がこの部分にあたる.加えて,第11章では,言語と身体感覚の関連から,感覚過敏についても触れた.
第12章は,ASDが自己にめざめることにともなう問題を取り上げた.通常は「二次障害」とされることが多いが,単に併発ととらえるのではなく,ASDの本来のあり方と,自己のめばえという構造変動のなかから,どのように理解できるかという視点から論じた.
第13章は,成人ASDの診断で問題となる,統合失調症と境界性パーソナリティ障害との鑑別を取り上げ,それをとおして,ASDの輪郭をより鮮明にすることを心がけた.とりわけ境界性パーソナリティ障害との鑑別に関しては,女性例に特化して論じた.この部分にかぎらず,女性例を重視しているのが本書の特色の一つかもしれない.
終章では,ここまでの論考を踏まえながら,成人ASDの臨床場面でのかかわりについて,その原則と,筆者なりのいくつかの工夫(デバイス)を紹介した.
全体的にみると,狭義の成人ASDを論じたのは,第12章以降ということになる.だが,本書のほとんどの論述が,成人例の臨床をとおして得られたものである.それに関連して,具体性を確保するため,成人例の短い事例報告をvignetteとして,多数紹介した(掲載にあたって,本人の承諾を得ていないものについては,複数の例を複合して改変するという手続きをとった).
本書全般をとおして,定型と呼ばれるものを相対化する視点をたずさえるようにこころがけた.大半の治療者は定型者の側にいる.これはいたしかたないことである.だが,自分の拠ってたつ地盤を不易なものであると考えているかぎり,ASD者の立ち会っている苦悩には届かない.この相対化は,堅苦しくいえば,臨床家としての倫理である.
同時に,彼ら彼女たちの,定型者にはないすぐれたところ,魅力的なところに出会うためにも,必要な心がけでもある.それは精神病理学の原点にほかならない.
本書は,精神科医が日々の診療場面で出会う青年期・成人期の「自閉症スペクトラム」(ASD)を対象とした臨床論である.ほとんどの事例が,仕事や学業など,一定の社会的な営みにたずさわっている.
振り返ってみると,90年代の後半から,こうした事例に散発的に遭遇するようになり,それがみるまに,一群のまとまりをもつようになった.当初は随分と当惑したものだが,あらためて概念を学び,それを臨床経験によって肉付けしていくことによって,少しずつではあるが,かかわるポイントがみえてきたように思う.
青年期・成人期のASD 1 には,「小児自閉症」というゆるぎのないプロトタイプがある.その意味では,他の疾患と比較して,安定した臨床概念であるようにみえる.確かにそうした一面はあるが,他方で,「小児自閉症」と「成人ASD」の間には,大きな隔たりがあるのもまた事実である.
1 本書で対象となるのは青年期・成人期のASDである.以後,略して「成人ASD」と記載する.また,特にことわりがないかぎり,単に「ASD」と記載されていても,青年期・成人期の事例を指す.
成人ASDのほとんどの事例は,かつて小児自閉症と診断されたことがない.その当時は見逃されていたという考え方もあるが,それだけで説明できるわけでもなさそうである.そもそも事例というものは,中心から周縁に行くにしたがって変化に富み,多様となる.場合によっては,出発点とはおよそ似つかわしくないものとなる.そもそもの自閉症概念は,孤立が最も顕著となる3歳から5歳の男児をプロトタイプとして組み立てられている.そこから導かれた症候学を,そのまま成人例や女性例にあてはめるには無理がある.
他方で,ちょっとしたそれらしき特性,たとえば「鉄道マニア」であるとか,「空気が読めない」といったようなことがあるだけで,ASDと見立てるのは乱暴な話である.過剰診断という以前に,そもそも当事者に役立たない診断など,単なるスティグマにすぎない.
成人例を診ることの利点は,彼ら彼女たちが自らについて語るということにある.そればかりか,書く能力に秀でていることさえある.実際,ドナ・ウィリアムズ(Donna Williams),グニラ・ガーランド(Gunilla Gerland),藤家寛子,森口奈緒美らの自伝からは,ありふれた解説書のたぐいを読むよりも,はるかに学ぶところが多い.これはかつての精神疾患にはなかったことである.こうしたことばをもつ成人事例と,ことばをもたないコアの「自閉症」との間を行き来することによって,より豊かな臨床概念がもたらされるはずである.
筆者は自閉症児の療育にたずさわった経験はない.しかし,偶々〈たまたま〉ではあるが,これまで彼らの生きる現場を肌で感じる機会に事欠くことはなかった.加えて,カナー(Leo Kanner 2 )とアスペルガー(Hans Asperger 3 )のすぐれた古典がある.いまだにこの二つの論考以上に,自閉症児を生き生きと描き出したものはない.
2 Kanner, L. : Autistic Disturbances of Affective Contact. Nervous Child 2 : 217-250, 1943
3 Asperger, H. : Die 'Austistischen Psychopathen' im Kindesalter. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 117 : 76-136, 1944
もう一つの利点は,適応が改善していくということである.小さな工夫の積み重ねが,意外なほど役に立つ.その前提となるのが,彼ら彼女たちの精神世界を理解することである.3 Asperger, H. : Die 'Austistischen Psychopathen' im Kindesalter. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 117 : 76-136, 1944
自閉症を考える際には,「脳」と「発達」という二つの柱がある.これらが重要であることはいうまでもない.ただ,その際,発想が窮屈にならないように気をつけなければならない.「脳」ということばを聞いただけで思考停止に陥るようでは,臨床家として終わっている.
生き物としてみた人間は,実に多くの欠陥を抱えている.そもそもの出発点で,およそ生命体としてはありえないくらいに,未成熟な状態で産み落とされる.ようやく生後9か月になって,オランウータンの生まれたばかりの赤ちゃんと同じ程度の身体能力が備わる.
これほどまでに無力な状態で産み落とされる生物は他にない.それゆえ,人間の個体間には,他の生物にはみられない関係が結ばれることになる.その結果として産み出されるのが,関係の起点となる「こころ」であり,関係の総体としての「社会」である.種として生き延びるためには,こうしたものを作り上げるよりないのである.より正確にいえば,「こころ」や「社会」などといったものを創発した(でっちあげた)がために,たまさか生き延びることができたのである.
人間の脳もさまざま欠陥を抱えている.そもそも,単独では作動できない.他者や環境といった<外部>をなかに含み込んでいる.他者からの働きかけがないと,うまく機能しないのである.さらに言語という奇妙なシステムを,認識と行動を制御するために不可欠のものとして,実装しなければならない.
発達もまた,自然には展開しない.他者とのかかわりのなかで,こころや社会といった自然にはないものを取り込んでいかなければならない.そして家族,学校,会社といった,さまざまな制度に適応しなければならないのである.
こころや社会というものは,一定のものではない.時代や文化で大きく変わる.ヨーロッパではつい最近まで神が生きており,こころの問題はもっぱら神やその代理人たちに預けられていた.いちいち考えなくともよかったのである.日本の伝統文化のなかでは,こころは人間の専有物ではなく,およそ自然のいたるところに感じられていた.今でもそう感じられなくもないだろう.
定型とされる発達も,その時代や文化によって大きく異なる.たとえば,「青年期」という,今ではあたりまえとなっている発達区分ができたのは,20世紀の初頭である.それまでは児童期が終わると,すぐに成人期に接続していた.さらにその前になると,「児童」という概念すらなく,働けるようになると,すぐに大人扱いされたのである.他方,今や,青年期は30歳,さらには40歳にまで延長されようとしている.近い将来,大多数が万年青年となれば,「青年期」そのものが解消されてしまうかもしれない(図,本サイトでは省略).
それゆえ,現時点で定型とされる発達の様式もまた,偶々のものでしかない.それに適応できぬ個体,そこからはずれる個体が,一定の割合で存在しても,何ら不思議なことではない.
ことばももたぬ中核の自閉症と比較するなら,成人ASDの精神病理ははるかに軽い.だが,それはかならずしも,彼ら彼女たちの方が生きやすいことを意味しない.むしろ適応という視点では,周囲から「障害」とみなされる程度の事例の方が,より安定した生活を営むといわれたりもする.
他の精神疾患にもみられることだが,病理が軽い事例の方が,生きる上での苦悩や困難が,かえってハードなものとなりうる.さらに成人ASDの場合,彼ら彼女たちに固有の問題がある.それは,他者の存在に気づき,自己にめざめるという,天変地異とでもいうべきカタストロフが,いずれふりかかってくるということである.
これは,定型者にとっては,自分の知らぬ間にすませた課題である.気がついたときにはすでに自分は自分である.それゆえ困難に対して共感も届かないし,モデルを提供することもできない.しかも「発達」という観点から,歓迎すべきこととしてすまされてしまいかねない.だが,そんなことでは,それが混乱や哀しみや緊張に満ちたものであることは,想像もつかないだろう.
本書がめざすのは,ASDの精神病理を明らかにする試みをとおして,彼らの抱える苦悩や困難にかかわるポイントを見出すことである.脳も発達も,この作業にはなかなか歯がたたない.人間という奇妙な生き物が発明したこころや社会といったものを,自明のものとせず,問い直す作業が必要である.それによってこそ,彼ら彼女たちの立ち会っている事態を理解し,有効な手だてを工夫する端緒が与えられるだろう.
本論に入るにあたって,本書の構成について,簡単な見通しを示しておこう.
第1章から第3章までは,「心の理論」仮説に含まれる根本的な誤りを検討しながら,ASDの精神病理のミニマムを提示する.要約すれば,それは「まなざし」,「呼びかけ」,「抱きかかえ」といった他者からの志向性に対して応答しないことである.そしてこの応答によって立ち上がるのが,まさに「自己」である.最初から自己を想定していては,ASDの世界へアプローチするための鍵は与えられない.
第4章では,生後9か月目頃に訪れる,乳児の世界の大規模な組み替えについて,それを「9か月革命」と銘打って示す.本書における発達論がこの章に集約されている.現在のこころの発達は,一個の「自己」にまとめあげることを自明の前提として求める.これは物理的,生理的な個体化ではなく,他者からの志向性によって切り出される象徴的個体化である.その端緒となるのが生後9か月目頃であり,乳児の世界は劇的に変化する.その地点でASDはつまずくのであり,精神病理の原点がそこにある.
第5章から第8章では,「自他未分」という出発点から導き出されるASDの世界を提示する.ローナ・ウィング(Lorna Wing)の「障害の三つ組」でいえば,5章が想像力,6章から8章が対人相互性に関するものとなる.想像力の障害は,通常,物に対する執着,常同的な行動,変化への抵抗などの,いわゆる「こだわり」の強さによって説明されているが,想像力の本来の機能に立ちかえって検討を加えた.そこには「こだわり」も包摂される.対人相互性の障害については,反転性がないこと(6章),地続きであること(7章),影響を受けやすいこと(8章)に分けて解説している.
第9章では,これらの考察を踏まえて,いわゆるASDの認知行動特性を,(1)経験を大域的〈おおまか〉に束ねることの障害,(2)文脈からのデカップリングの障害の二つに大別して,系統的に整理した.
第10章と第11章では,言語について,やや突っ込んだ考察を加えた.というのも,多くのASD論において,言語観そのものが,百年以上前の素朴な,out-of-dateの水準にあり,その点から論じ直さなければならなかったからである.言語を出来あがったシステムではなく,つねにあらたに行われる行為としてとらえることによって,ASDの言語の特異性に迫る試みである.「障害の三つ組」でいえば,コミュニケーションの障害がこの部分にあたる.加えて,第11章では,言語と身体感覚の関連から,感覚過敏についても触れた.
第12章は,ASDが自己にめざめることにともなう問題を取り上げた.通常は「二次障害」とされることが多いが,単に併発ととらえるのではなく,ASDの本来のあり方と,自己のめばえという構造変動のなかから,どのように理解できるかという視点から論じた.
第13章は,成人ASDの診断で問題となる,統合失調症と境界性パーソナリティ障害との鑑別を取り上げ,それをとおして,ASDの輪郭をより鮮明にすることを心がけた.とりわけ境界性パーソナリティ障害との鑑別に関しては,女性例に特化して論じた.この部分にかぎらず,女性例を重視しているのが本書の特色の一つかもしれない.
終章では,ここまでの論考を踏まえながら,成人ASDの臨床場面でのかかわりについて,その原則と,筆者なりのいくつかの工夫(デバイス)を紹介した.
全体的にみると,狭義の成人ASDを論じたのは,第12章以降ということになる.だが,本書のほとんどの論述が,成人例の臨床をとおして得られたものである.それに関連して,具体性を確保するため,成人例の短い事例報告をvignetteとして,多数紹介した(掲載にあたって,本人の承諾を得ていないものについては,複数の例を複合して改変するという手続きをとった).
本書全般をとおして,定型と呼ばれるものを相対化する視点をたずさえるようにこころがけた.大半の治療者は定型者の側にいる.これはいたしかたないことである.だが,自分の拠ってたつ地盤を不易なものであると考えているかぎり,ASD者の立ち会っている苦悩には届かない.この相対化は,堅苦しくいえば,臨床家としての倫理である.
同時に,彼ら彼女たちの,定型者にはないすぐれたところ,魅力的なところに出会うためにも,必要な心がけでもある.それは精神病理学の原点にほかならない.
目次
開く
はじめに
1章 「心の理論」のどこがまちがっているのか?
心の理論/「サリー-アン問題」のどこが問題なのか?/
心が読めること,心というものがわかること/直観でわかること,推論してわかること
-ASD者がわからないのはサリーではなく,アンである/
推論だけで作動するシステム/「心の理論」による代償/事後的な「こころ」
2章 なぜ他者のこころは直観できるのか?
他者というあり方の両義性/われわれは他者にいつ出会うのか/
「志向性」というもの/私から他者に向かう直観は挫折する/
理論説とシミュレーション説/直観のベクトルを反転せよ/
他者の側面図から正面図へ/了解は応答のなかに含まれる
3章 まなざしの到来
顔(おもざし)/視線触発/まなざし/ひとみしり-自己が触発されるとき/
他者が置いたしるし<φ>/<φ>は経験を超えたものであること/
<φ>をめぐる病理/φのまとめ
4章 9か月革命
自他未分という原点/象徴的個体化/9か月目からの再編/
他者は志向性を軸にまとまりあがる/sympathyとempathy/
指さしと共同注意/心的距離/距離の未形成/「みえる」と「みる」/
ハイマートとしての「みえる」/9か月革命のまとめ
5章 現前の呪縛-想像力の問題
奥行きのない世界/みえているのがすべて/余白の乏しさ/
自分はどこにいるのか/動かない大地/壊れない母/想像的身体/
抱えられること/現実と想像
6章 反転しない世界
一方通行路/呼びかけと応答/人称の混乱/固有名/反響しない世界
7章 地続きの世界-sympathyとempathy
「同一性保持」という現象/自と他/親と子/夢と現実/
sympathyとempathy/場違いなsympathy/私心なき傍若無人
8章 「司令塔」のない自己-被影響性について
文脈からのデカップリング/文脈のわからなさ/染まりやすさ/
規則に染まること/解離現象/対処としての解離/距離のめばえ
9章 認知行動特性
φの二つの機能/経験を束ねることの障害/
文脈からのデカップリングの障害/まとめ
10章 ことばの発生
9か月革命の完成/ASDは言語を道具として用いている/
ことばは道具ではない/言語はカタログではない/
シニフィアンによる切り取り/自閉症の原初的ことば/
成人ASDのことばの二つの様態/
バナナを受話器とみなすこと-「振り」と「ごっこ遊び」/言語ゲーム
11章 私的言語と感覚過敏
エコラリアから始まる/取り残されたことば/私的言語への傾き/
葛藤がみえない/「痛いの?」/ぼくはおなかがすいていたのだ/
差異のざわめき/感覚過敏について/疲れやすさ/「ことばのまえ」という故郷
12章 自己へのめざめ
孤立のなかへのめざめ/抑うつ/パニック/トラウマ/もう一人の自己/
他者へのめざめ/プロテスト/まとめ
13章 鑑別診断-統合失調症と境界性パーソナリティ障害
統合失調症との鑑別/BPD(境界性パーソナリティ障害)との鑑別
終章 臨床デバイス
いくつかの原則/関与のためのデバイス
あとがき
索引
1章 「心の理論」のどこがまちがっているのか?
心の理論/「サリー-アン問題」のどこが問題なのか?/
心が読めること,心というものがわかること/直観でわかること,推論してわかること
-ASD者がわからないのはサリーではなく,アンである/
推論だけで作動するシステム/「心の理論」による代償/事後的な「こころ」
2章 なぜ他者のこころは直観できるのか?
他者というあり方の両義性/われわれは他者にいつ出会うのか/
「志向性」というもの/私から他者に向かう直観は挫折する/
理論説とシミュレーション説/直観のベクトルを反転せよ/
他者の側面図から正面図へ/了解は応答のなかに含まれる
3章 まなざしの到来
顔(おもざし)/視線触発/まなざし/ひとみしり-自己が触発されるとき/
他者が置いたしるし<φ>/<φ>は経験を超えたものであること/
<φ>をめぐる病理/φのまとめ
4章 9か月革命
自他未分という原点/象徴的個体化/9か月目からの再編/
他者は志向性を軸にまとまりあがる/sympathyとempathy/
指さしと共同注意/心的距離/距離の未形成/「みえる」と「みる」/
ハイマートとしての「みえる」/9か月革命のまとめ
5章 現前の呪縛-想像力の問題
奥行きのない世界/みえているのがすべて/余白の乏しさ/
自分はどこにいるのか/動かない大地/壊れない母/想像的身体/
抱えられること/現実と想像
6章 反転しない世界
一方通行路/呼びかけと応答/人称の混乱/固有名/反響しない世界
7章 地続きの世界-sympathyとempathy
「同一性保持」という現象/自と他/親と子/夢と現実/
sympathyとempathy/場違いなsympathy/私心なき傍若無人
8章 「司令塔」のない自己-被影響性について
文脈からのデカップリング/文脈のわからなさ/染まりやすさ/
規則に染まること/解離現象/対処としての解離/距離のめばえ
9章 認知行動特性
φの二つの機能/経験を束ねることの障害/
文脈からのデカップリングの障害/まとめ
10章 ことばの発生
9か月革命の完成/ASDは言語を道具として用いている/
ことばは道具ではない/言語はカタログではない/
シニフィアンによる切り取り/自閉症の原初的ことば/
成人ASDのことばの二つの様態/
バナナを受話器とみなすこと-「振り」と「ごっこ遊び」/言語ゲーム
11章 私的言語と感覚過敏
エコラリアから始まる/取り残されたことば/私的言語への傾き/
葛藤がみえない/「痛いの?」/ぼくはおなかがすいていたのだ/
差異のざわめき/感覚過敏について/疲れやすさ/「ことばのまえ」という故郷
12章 自己へのめざめ
孤立のなかへのめざめ/抑うつ/パニック/トラウマ/もう一人の自己/
他者へのめざめ/プロテスト/まとめ
13章 鑑別診断-統合失調症と境界性パーソナリティ障害
統合失調症との鑑別/BPD(境界性パーソナリティ障害)との鑑別
終章 臨床デバイス
いくつかの原則/関与のためのデバイス
あとがき
索引
書評
開く
ASD臨床のための貴重な道標
書評者: 徳田 裕志 (高田馬場診療所院長)
人は誰しも何らかの障碍を担うものではあるが,自閉症スペクトラム障碍(以下ASD)的特質を負って世にすむことも大いなる労苦を伴う。その心的世界,精神/神経機能上の偏倚,現実世界との折り合えなさ,生活上の困苦を深く理解し,必要な支援を紡ぎ出そうと努めることは,精神科医を含め支援者達の職責である。ASDの臨床が混乱している昨今であるが,本書はそのための貴重な道標となってくれる。広く知られるようになった妙な言葉「心の理論」を解き明かし,眼差しや面差し,呼びかけという他者からの志向性によって自己が立ち上がることの障碍を活写する。言語が道具であらざるを得ないことや語用論的障碍について,言語というものの根源的意義から問い直す。その他,パニックやタイムスリップ現象,特異な時間体験,文脈やカテゴリー化の困難,感覚過敏などASDに伴う諸症候について精神病理学的視点より考察する。そして,それらを踏まえて臨床上の実際的具体的工夫を示唆してくれており,明日の臨床に役立つものである。評者自身の精神的資質や日頃の臨床と照合しつつ,格闘して読んだ。
あくまで評者の臨床感覚以上のことではないが全面的には肯えなかった点として,統合失調症は定型発達の病でありASDとは全く別であると明瞭に言い過ぎているように思う。ASD概念の事始めより,統合失調症との区別は大問題であった。自閉症の名付け親Kannerも迷ったし,統合失調病質の子どもについて述べたWolffとアスペルガー症候群を提唱したWingが対立した経緯もある。想定される本質的病理は異なるのだが,臨床上は鑑別が難しいことも多いように思われる。診断名を付けねばならないという陥りがちなこだわりから離れて,いわば安全感喪失の病たる統合失調症的要素と,ASDを含めた神経発達性の要素とが,別の方向への軸としてどちらもスペクトラム的な濃淡を持って同一個人の中に存在するという捉え方をすることは一つの解決であると思う。
もう一点は,ASDと診断されればこれが優先されるとしていることである。スペクトラム(程度の問題)として理解することに支障をきたしかねず,表層的に解してしまうと筆者の意図から逸して最近のASD診断濫用の傾向を助長する可能性への危惧を抱いたので一応記しておく。
また,具体例を記した多くのVignetteはとてもわかりやすいが,読者はここに示される特徴があるからといってASDと即断することのないように願いたい。個々の症候の有無で判断してはならず,現象学的態度(見聞きし学んだことは括弧に入れて素の心で目の前の事象に向き合うこと)を忘れてはならないのである。筆者も指摘し憂えているように,単なるスティグマとなってしまっているような状況を散見するので,肝要なのは診断をすることではなく適切な理解と関与であるという初心に立ち戻り,本書によって深められたものを糧として今日も臨床に勤しみたい。
開眼の衝撃を与える一冊
書評者: 神尾 陽子 (国立精神・神経医療研究センター児童・思春期精神保健研究部部長)
本書は成人自閉症スペクトラム障害(ASD),それも高い言語能力を持つ患者,あるいはASDと診断されるほど極端ではないが強いASD特性を持つ成人患者(閾下ASD)を対象としている。発達障害への感度が上がった今日なお,言語を流ちょうに話すASD(閾下ASDも)の人々は幼児期に「発達の遅れ」というわかりやすい要素がないがために,周囲に理解されない長い孤独の時間を過ごし,社会に居場所を求めて苦闘している。そして精神科臨床にはこうした成人ASDが一定の割合で潜在する。診療時間を十分に取れない精神科医にとって,通常の医師-患者関係を築きにくいこうした一群の患者の深刻なニーズはわかるものの,どのように彼らの訴えを理解し,対応するのがよいかはすぐにでも知りたいところであるだけに,ASDの精神内界に迫る本書はその先鞭を付けた待望の一冊と言える。精神病理学者として多数の名著を世に送ってきた著者の手になる初のASD論である本書は,精神病理学をベースとしているが精神病理学だけに閉じられていない点で全ての読者にとって読みやすくかつ刺激的な内容となっている。発達障害に苦手な印象を抱いている精神科臨床医には開眼の衝撃を与え,また発達障害の知識を持つ読者には自らの臨床経験に立ってその前提を批判的に検討することを促すに違いない。
第1章で取り上げられたのは,「定説化」している自閉症の「心の理論」仮説である。この心理学的仮説は1980年代に脚光を浴びたのち主役の座から降りたものの今なおASDの脳画像研究などでは前提とされることが少なくないが,著者はこれを正面から批判的に検証し,自閉症仮説以前に,そもそも人が他者を理解する際の仮説として間違っている,と一蹴する。先ず自己ありきという「心の理論」仮説に対して,他者からの志向性に対して立ち上がってこない自己をASDの問題の本質と捉え,既成の発達心理学の発達論や自閉症の症候論を広く展望した上で他者に対する了解,という観点から論を展開する。そしてASD者は発達過程のいずれかの時点で自己にめざめるが,そのめざめこそが成人ASD者の固有の問題を形作る,とする。このような議論は,著者の視線がASD者,定型発達者双方に向けられ,これまで見る側であった定型発達のありようを容赦なく問い直し相対化した結果,生まれたものである。成人ASD者のエビデンスのピースをつなぎ合わせることができないでいた評者の立場からは,文献を展望した上でご自身の豊富な臨床経験を素材として内海先生ならではの論考を加えてこうした精神病理学的臨床論を提示してくださったことに心から感謝したい。女性ASDのアンメット・ニーズの奥底に光を当てたという点も,本書の試みは新しい。これを機に精神医学においてASD,そして発達障害をめぐる架橋的な治療論が活発となることを期待する。
本書の利点として「はじめに」に次のような文章がさりげなく書かれている。「適応が改善していくということである。小さな工夫の積み重ねが,意外なほど役に立つ。その前提となるのが,彼ら彼女たちの精神世界を理解することである」。(p.2)このくだりこそが本書の価値を一番表しているかもしれない。
精神病理学的考察がもたらす臨床力
書評者: 熊木 徹夫 (あいち熊木クリニック院長)
本書は,青年期・成人期の「自閉症スペクトラム」(成人ASD:以下ASDとする)を対象とした精神病理学的考察である。ASDについては,過去にも重要な著作が刊行されている。それは,カナーやアスペルガーを始めとする医師・研究者の著作,ASD者の自伝,過去の傑物の病跡などである。しかし内海は言う。「ASD者の棲む世界・経験の成り立ちを洞察するためには,“こころ”や“社会”を自明のものとせず,定型者を相対化して,問い直さなければならない。それによりはじめて,治療者も必要な心的距離が了解でき,治療における適切な“温かみ”が活かされる」のだと。
その言葉に偽りはなく,本書の大部分は定型者の徹底的な相対化に割かれている。その相対化は,著者自身の思考・体験にまで及んでいる。その上で,ASD者が発達過程でどのように“系統分離”したのか,わかる仕掛けになっている。「まなざし」という他者からの志向性に触発され,「9か月革命」が起こる。そこで登場するのが,〈φ(ファイ)〉である。φはその触発の痕跡であり,「自他未分」の世界に劇的な変化を与える。φ自体は,他者からの志向性をキャッチするセンサーとして機能する。まずsympathy(共鳴)が,empathy(共感)と対象認識(すなわち,こころとものの世界)に分かたれる。そしてさらに,「自己」「他者」「“ここ”という場所」「こころ(志向性のあるところ)」が立ち上がる。このプロセスの記述は精緻であるだけでなく,畳みかけるようなダイナミズムに満ちており,息をのむ迫力で,誰しも“外からの傍観者”たりえない。
一方,ASD者にはこのφの到来はなく,「自他未分」のまま進んでいくという。これが言葉という「暴力」が支配的な一般社会で生きていくのにどれほどの齟齬をきたすか,どれほどその存在をぐらつかせるか。それだけではない。ASD者が自他未分の世界から一歩踏み出すと,「反響することのない世界に取り囲まれた孤独」「消え入ってしまいたくなるほどの強烈な羞恥」(p.114)が待つという。これらが,ASD者の自伝・症例・病跡の解析を踏まえながら丁寧に語られていく。真にASD者に寄り添うとは,こういうことなのだ。
それにしても,何たる洞察力か。定型者においては,言葉の指示作用が世界を分節する,すなわちシニフィアン(意味するもの)がシニフィエ(意味されるもの)を生み出す。とするなら,ASD者に成り代わり,彼らを理解し救済するため,鮮やかな手さばきで誰にも真似できない世界の分節を行う内海健とは何者か。本書の最大の功績は,先述の〈φ〉の発見にあり,これぞ発達理論におけるミッシングリンクであろう。これもまた,内海の内なるφが果たしたことだと考えると,とても不思議な思いにとらわれる。
いずれにせよ,言葉,そして精神病理学的考察がもたらす臨床力を痛感させられる一書であり,われわれ精神科医のみならず,他の臨床家・教育者・福祉従事者,そしてASD者の親などが,この豊饒の海からくみ上げられる知見は数知れない。
書評者: 徳田 裕志 (高田馬場診療所院長)
人は誰しも何らかの障碍を担うものではあるが,自閉症スペクトラム障碍(以下ASD)的特質を負って世にすむことも大いなる労苦を伴う。その心的世界,精神/神経機能上の偏倚,現実世界との折り合えなさ,生活上の困苦を深く理解し,必要な支援を紡ぎ出そうと努めることは,精神科医を含め支援者達の職責である。ASDの臨床が混乱している昨今であるが,本書はそのための貴重な道標となってくれる。広く知られるようになった妙な言葉「心の理論」を解き明かし,眼差しや面差し,呼びかけという他者からの志向性によって自己が立ち上がることの障碍を活写する。言語が道具であらざるを得ないことや語用論的障碍について,言語というものの根源的意義から問い直す。その他,パニックやタイムスリップ現象,特異な時間体験,文脈やカテゴリー化の困難,感覚過敏などASDに伴う諸症候について精神病理学的視点より考察する。そして,それらを踏まえて臨床上の実際的具体的工夫を示唆してくれており,明日の臨床に役立つものである。評者自身の精神的資質や日頃の臨床と照合しつつ,格闘して読んだ。
あくまで評者の臨床感覚以上のことではないが全面的には肯えなかった点として,統合失調症は定型発達の病でありASDとは全く別であると明瞭に言い過ぎているように思う。ASD概念の事始めより,統合失調症との区別は大問題であった。自閉症の名付け親Kannerも迷ったし,統合失調病質の子どもについて述べたWolffとアスペルガー症候群を提唱したWingが対立した経緯もある。想定される本質的病理は異なるのだが,臨床上は鑑別が難しいことも多いように思われる。診断名を付けねばならないという陥りがちなこだわりから離れて,いわば安全感喪失の病たる統合失調症的要素と,ASDを含めた神経発達性の要素とが,別の方向への軸としてどちらもスペクトラム的な濃淡を持って同一個人の中に存在するという捉え方をすることは一つの解決であると思う。
もう一点は,ASDと診断されればこれが優先されるとしていることである。スペクトラム(程度の問題)として理解することに支障をきたしかねず,表層的に解してしまうと筆者の意図から逸して最近のASD診断濫用の傾向を助長する可能性への危惧を抱いたので一応記しておく。
また,具体例を記した多くのVignetteはとてもわかりやすいが,読者はここに示される特徴があるからといってASDと即断することのないように願いたい。個々の症候の有無で判断してはならず,現象学的態度(見聞きし学んだことは括弧に入れて素の心で目の前の事象に向き合うこと)を忘れてはならないのである。筆者も指摘し憂えているように,単なるスティグマとなってしまっているような状況を散見するので,肝要なのは診断をすることではなく適切な理解と関与であるという初心に立ち戻り,本書によって深められたものを糧として今日も臨床に勤しみたい。
開眼の衝撃を与える一冊
書評者: 神尾 陽子 (国立精神・神経医療研究センター児童・思春期精神保健研究部部長)
本書は成人自閉症スペクトラム障害(ASD),それも高い言語能力を持つ患者,あるいはASDと診断されるほど極端ではないが強いASD特性を持つ成人患者(閾下ASD)を対象としている。発達障害への感度が上がった今日なお,言語を流ちょうに話すASD(閾下ASDも)の人々は幼児期に「発達の遅れ」というわかりやすい要素がないがために,周囲に理解されない長い孤独の時間を過ごし,社会に居場所を求めて苦闘している。そして精神科臨床にはこうした成人ASDが一定の割合で潜在する。診療時間を十分に取れない精神科医にとって,通常の医師-患者関係を築きにくいこうした一群の患者の深刻なニーズはわかるものの,どのように彼らの訴えを理解し,対応するのがよいかはすぐにでも知りたいところであるだけに,ASDの精神内界に迫る本書はその先鞭を付けた待望の一冊と言える。精神病理学者として多数の名著を世に送ってきた著者の手になる初のASD論である本書は,精神病理学をベースとしているが精神病理学だけに閉じられていない点で全ての読者にとって読みやすくかつ刺激的な内容となっている。発達障害に苦手な印象を抱いている精神科臨床医には開眼の衝撃を与え,また発達障害の知識を持つ読者には自らの臨床経験に立ってその前提を批判的に検討することを促すに違いない。
第1章で取り上げられたのは,「定説化」している自閉症の「心の理論」仮説である。この心理学的仮説は1980年代に脚光を浴びたのち主役の座から降りたものの今なおASDの脳画像研究などでは前提とされることが少なくないが,著者はこれを正面から批判的に検証し,自閉症仮説以前に,そもそも人が他者を理解する際の仮説として間違っている,と一蹴する。先ず自己ありきという「心の理論」仮説に対して,他者からの志向性に対して立ち上がってこない自己をASDの問題の本質と捉え,既成の発達心理学の発達論や自閉症の症候論を広く展望した上で他者に対する了解,という観点から論を展開する。そしてASD者は発達過程のいずれかの時点で自己にめざめるが,そのめざめこそが成人ASD者の固有の問題を形作る,とする。このような議論は,著者の視線がASD者,定型発達者双方に向けられ,これまで見る側であった定型発達のありようを容赦なく問い直し相対化した結果,生まれたものである。成人ASD者のエビデンスのピースをつなぎ合わせることができないでいた評者の立場からは,文献を展望した上でご自身の豊富な臨床経験を素材として内海先生ならではの論考を加えてこうした精神病理学的臨床論を提示してくださったことに心から感謝したい。女性ASDのアンメット・ニーズの奥底に光を当てたという点も,本書の試みは新しい。これを機に精神医学においてASD,そして発達障害をめぐる架橋的な治療論が活発となることを期待する。
本書の利点として「はじめに」に次のような文章がさりげなく書かれている。「適応が改善していくということである。小さな工夫の積み重ねが,意外なほど役に立つ。その前提となるのが,彼ら彼女たちの精神世界を理解することである」。(p.2)このくだりこそが本書の価値を一番表しているかもしれない。
精神病理学的考察がもたらす臨床力
書評者: 熊木 徹夫 (あいち熊木クリニック院長)
本書は,青年期・成人期の「自閉症スペクトラム」(成人ASD:以下ASDとする)を対象とした精神病理学的考察である。ASDについては,過去にも重要な著作が刊行されている。それは,カナーやアスペルガーを始めとする医師・研究者の著作,ASD者の自伝,過去の傑物の病跡などである。しかし内海は言う。「ASD者の棲む世界・経験の成り立ちを洞察するためには,“こころ”や“社会”を自明のものとせず,定型者を相対化して,問い直さなければならない。それによりはじめて,治療者も必要な心的距離が了解でき,治療における適切な“温かみ”が活かされる」のだと。
その言葉に偽りはなく,本書の大部分は定型者の徹底的な相対化に割かれている。その相対化は,著者自身の思考・体験にまで及んでいる。その上で,ASD者が発達過程でどのように“系統分離”したのか,わかる仕掛けになっている。「まなざし」という他者からの志向性に触発され,「9か月革命」が起こる。そこで登場するのが,〈φ(ファイ)〉である。φはその触発の痕跡であり,「自他未分」の世界に劇的な変化を与える。φ自体は,他者からの志向性をキャッチするセンサーとして機能する。まずsympathy(共鳴)が,empathy(共感)と対象認識(すなわち,こころとものの世界)に分かたれる。そしてさらに,「自己」「他者」「“ここ”という場所」「こころ(志向性のあるところ)」が立ち上がる。このプロセスの記述は精緻であるだけでなく,畳みかけるようなダイナミズムに満ちており,息をのむ迫力で,誰しも“外からの傍観者”たりえない。
一方,ASD者にはこのφの到来はなく,「自他未分」のまま進んでいくという。これが言葉という「暴力」が支配的な一般社会で生きていくのにどれほどの齟齬をきたすか,どれほどその存在をぐらつかせるか。それだけではない。ASD者が自他未分の世界から一歩踏み出すと,「反響することのない世界に取り囲まれた孤独」「消え入ってしまいたくなるほどの強烈な羞恥」(p.114)が待つという。これらが,ASD者の自伝・症例・病跡の解析を踏まえながら丁寧に語られていく。真にASD者に寄り添うとは,こういうことなのだ。
それにしても,何たる洞察力か。定型者においては,言葉の指示作用が世界を分節する,すなわちシニフィアン(意味するもの)がシニフィエ(意味されるもの)を生み出す。とするなら,ASD者に成り代わり,彼らを理解し救済するため,鮮やかな手さばきで誰にも真似できない世界の分節を行う内海健とは何者か。本書の最大の功績は,先述の〈φ〉の発見にあり,これぞ発達理論におけるミッシングリンクであろう。これもまた,内海の内なるφが果たしたことだと考えると,とても不思議な思いにとらわれる。
いずれにせよ,言葉,そして精神病理学的考察がもたらす臨床力を痛感させられる一書であり,われわれ精神科医のみならず,他の臨床家・教育者・福祉従事者,そしてASD者の親などが,この豊饒の海からくみ上げられる知見は数知れない。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。