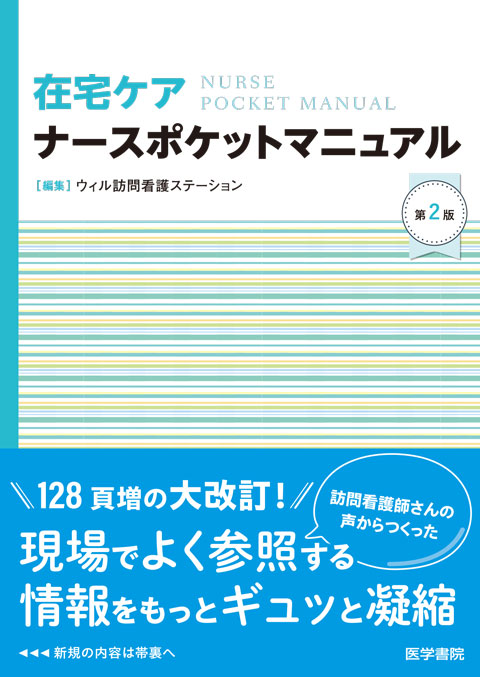在宅ケアの不思議な力
もっと在宅ケアを! 誰もが希望をもって生きられる1冊
もっと見る
「在宅ケアって何だろう?」と思う方には、在宅ケアの真髄を。「在宅ケアに取り組むことになった」方には、今日から動ける確かな指針として。そして「これまで在宅ケアを積み重ねてきた」方は、在宅ケアをもっと広めたくなることでしょう。「最期のかけがえのない時間を、これなら納得して過ごせそう」と、読んだ誰もが希望をもって生きられるようになる1冊です。
●本書を推薦します!
《これは、人がその人らしく生き抜くのを支える新たなケアのあり方を構築してきた熱い実践の手記だ》-柳田邦男氏(ノンフィクション作家)
三〇代に経験した姉のがん死。秋山さんのモチベーションは鮮烈だ。看護教師から在宅ホスピス看護師へ。さらにメディカルタウン構想や日本版マギーズセンター構想へ。発想の柔軟さとフットワークの強靭さで、活動の輪を広げていくエネルギーは凄い。医療人が看護の新境地と自らの人生を切り拓いた記録として感銘深く読んだ。
| 著 | 秋山 正子 |
|---|---|
| 発行 | 2010年02月判型:B6頁:192 |
| ISBN | 978-4-260-01047-4 |
| 定価 | 1,540円 (本体1,400円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
プロローグ
一九八九年(平成元年)八月二六日消印の姉からの手紙、これが二歳年上の姉、光子の直筆では最後の手紙となりました。几帳面な姉のきれいな文字が並ぶその文面は、「残暑お見舞い申し上げます。連日暑い事ですね。少々夏バテぎみです」に始まっています。
その三か月後、「光子ががんだって言われて……、それも手遅れの肝がんで、あと一か月」と姉の夫からの電話で聞かされました。双子のようにお揃いの服を着て育った私には、晴天の霹靂としか言いようがありませんでした。
九人きょうだいの末っ子の私とすぐ上の光子の二人は、「おまけのように生まれた」と母は笑いながら話し、きょうだいを幼少のときに亡くし一人っ子だった父は「子どもは多いほうがいい」と、私たち二人をあちこちへ連れ歩いてくれました。昭和三〇年代から四〇年代のはじめの頃、父の大好きなデパートで食べるホットケーキと映画鑑賞は、一人で行くには少々照れくさく、子ども連れで大義名分が立ったようです。上の兄や姉からは「下の二人には甘い」と言われつつ、おとなしい姉光子とお転婆でよく動き回る末っ子の私は育ちました。
その姉が四一歳で逝ったあと遺してくれたもの、それは、育ちざかりの二人の大事な子どもだけではありませんでした。
仕事中心で家庭をかえりみず、有給休暇など取ったことのなかった義兄が、初めて会社を休んで妻の看病にあたった。そのことが職場の人たちの知るところとなり、亡くなったあと、会社に介護休暇制度が導入されます。
介護休暇制度のきっかけとなった姉夫婦の日々に興味を抱いたノンフィクション作家の柳田邦男さんが取材に見え、毎日新聞の連載『「死の医学」への日記』に「妻の在宅ホスピス」として紹介されました。現在は新潮文庫『「死の医学」への日記』に所収されています。
柳田さんの新聞連載に挿絵を描かれていた伊勢英子さんは、その頃お父様の画家伊勢偉智郎さんが肺がんになり、がんセンター東病院で闘病中でした。姉光子の記事で在宅ホスピスという選択肢があることを知ったことは、お父様の在宅での看病につながります。
そして、姉の何よりの遺産は、私を在宅ケアの道に導いたことでした。
亡くなって一年ほどしたときに、『家庭で看取る癌患者――在宅ホスピス入門』のなかで「姉の死から看護者として学んだこと」を書く機会をいただきました(このときの文章を本書の第一章に、メヂカルフレンド社の許諾を得て掲載しています)。
二〇年経った今読み返し、ここから今の私の活動のすべてが始まっていると感じています。私は姉の在宅ケアを経験して、その人が生きてきた生活の場が療養の場になり、かけがえのない時間を、家族や親しい人に囲まれて過ごせるのは、在宅ホスピスにほかならないと知りました。そして、そこに出向いていく看護があるはずなのに、まだまだ実践者が少ない状況を変えていきたいと、自分の進む道を在宅ケアに定めようと思ったのでした。
『家庭で看取る癌患者』のなかに、姉光子が在宅で過ごすためにつくられた医療・看護・介護をめぐるチームの連携図を入れました。当時、京都に住んでいた私が、神奈川に住む姉のために、義兄と電話で連絡を取り、補助しながら地域のサービスを組み立てていった成果です。つくりなおした図を三四~三五ページに入れました。
二〇年経って今、この図を見るにつけ、在宅ケアは利用者・家族を中心にチームケアで推進するのだという基本が、ここにすでに表われていたのだと気が付きます。
当時の私が、離れて暮らす家族の立場で、必死に地域の情報を集めフォーマルサービス、インフォーマルサービスをつなげた結果がここに集約されています。遠く離れているため、日々の看護ができないもどかしさが、この連携を組み立てるにはよい作用をしています。直接看護できないことを他の人に委ねよう、任せてお願いしよう、自分のできることをできるだけしようという、今でいう遠距離介護です。とても多くの方々に助けていただきました。
当時、私は看護学校の教員をしていたこともあって、新聞記事の医療欄に目を通し、気になる記事は切り抜いていました。そうしたなかで、二四時間の連絡体制を取り、必要時には往診をする仕組み、がん患者も診ているというライフケアシステムの記事を読み、白十字診療所をお訪ねして、義兄とともに佐藤智(あきら)先生にお目にかかれたのも、本当に幸運でした。
在宅ケアに至るまでの、私の臨床経験は産婦人科が中心です。第二次ベビーブームの真っ最中の産科は、今にして思えば戦場のようでした。多忙を極めるなかに、新しいいのちの誕生に寄り添い、生まれなかったいのちをいとおしみ、婦人科のがん患者さんの抗がん剤や放射線治療のつらさに寄り添い、多くの経験をしました。その後の看護学校でも母性が中心ですが、大学病院の実習指導では、医学の発展に伴う取り組みのなかの内科・外科病棟を、学生とともに学ぶ機会に恵まれました。
「看護はすべての健康レベルの人が対象であり、どんな場所でも展開できる」と、基礎教育で学んだものです。健康に生まれてくる子どもや、健康破綻をきたす危険は高いが自然な経過である妊産婦、つまり周産期への看護としてのかかわりは、その後私が病院を飛び出して看護の場を広げていく糸口であったのかもしれません。学生実習の一環として新生児訪問を実施できていたことも、家庭での療養現場に近づいていくきっかけでした。
その後、実際に在宅ケアの道を歩むには、もっと勉強が必要ではないかと考え、施設ホスピスの草分けとして有名な淀川キリスト教病院の訪問看護室で研修させていただきました。ここでの経験は、東京に移ってから在宅ケアを始める際、大変役に立ちました。
姉からの大いなる遺産、在宅ケアへの道を歩いてきました。これからも歩み続けたいと思っています。
現在の私は、訪問看護ステーションの統括所長として、がんのみならず、高齢者や難病などさまざまな方へのターミナル(終末期)ケアに、一五人のスタッフとともにかかわらせていただいています。さらに同じく統括部長を務めるヘルパーステーションの同じ方向をめざすスタッフたち、そしてボランティアの方々とも一緒です。
在宅ケアには思いもよらない不思議な力があります。必死になったときに見えた“この人の力”を信じて頼み、そのことに感謝して次へ進む。このことは、患者さんを抱え込むことなく、もっと自在に在宅ケアを行なうヒントにつながるかもしれません。
在宅ケアはチームケアが原則。でも、それがうまくいっていないことも多く、ギクシャクとした人間関係を、緩めて、ほぐして、またつなぐことを、日々しています。
これまで経験してきたなかで、考え、感じてきたことを少しずつまとめることにしました。
できるだけ平易にと心がけた文章のため、旧知のことや、まわりくどいと思われる表現になったかもしれませんが、在宅ケアが多くの方に知ってもらえる機会となれば幸いです。とくにターミナルにある利用者やそのご家族へのケアは、これから大切になります。ターミナルケアは難しい、怖い、できれば避けたい、と思っている方も多いのではないでしょうか。でもそんなに臆病にならずに、ここはお互いの知恵を集めて、人生の最後の時間にかかわらせていただく幸せを感じられるようになっていきたい。そんなふうに考えています。
一九八九年(平成元年)八月二六日消印の姉からの手紙、これが二歳年上の姉、光子の直筆では最後の手紙となりました。几帳面な姉のきれいな文字が並ぶその文面は、「残暑お見舞い申し上げます。連日暑い事ですね。少々夏バテぎみです」に始まっています。
その三か月後、「光子ががんだって言われて……、それも手遅れの肝がんで、あと一か月」と姉の夫からの電話で聞かされました。双子のようにお揃いの服を着て育った私には、晴天の霹靂としか言いようがありませんでした。
九人きょうだいの末っ子の私とすぐ上の光子の二人は、「おまけのように生まれた」と母は笑いながら話し、きょうだいを幼少のときに亡くし一人っ子だった父は「子どもは多いほうがいい」と、私たち二人をあちこちへ連れ歩いてくれました。昭和三〇年代から四〇年代のはじめの頃、父の大好きなデパートで食べるホットケーキと映画鑑賞は、一人で行くには少々照れくさく、子ども連れで大義名分が立ったようです。上の兄や姉からは「下の二人には甘い」と言われつつ、おとなしい姉光子とお転婆でよく動き回る末っ子の私は育ちました。
その姉が四一歳で逝ったあと遺してくれたもの、それは、育ちざかりの二人の大事な子どもだけではありませんでした。
仕事中心で家庭をかえりみず、有給休暇など取ったことのなかった義兄が、初めて会社を休んで妻の看病にあたった。そのことが職場の人たちの知るところとなり、亡くなったあと、会社に介護休暇制度が導入されます。
介護休暇制度のきっかけとなった姉夫婦の日々に興味を抱いたノンフィクション作家の柳田邦男さんが取材に見え、毎日新聞の連載『「死の医学」への日記』に「妻の在宅ホスピス」として紹介されました。現在は新潮文庫『「死の医学」への日記』に所収されています。
柳田さんの新聞連載に挿絵を描かれていた伊勢英子さんは、その頃お父様の画家伊勢偉智郎さんが肺がんになり、がんセンター東病院で闘病中でした。姉光子の記事で在宅ホスピスという選択肢があることを知ったことは、お父様の在宅での看病につながります。
そして、姉の何よりの遺産は、私を在宅ケアの道に導いたことでした。
亡くなって一年ほどしたときに、『家庭で看取る癌患者――在宅ホスピス入門』のなかで「姉の死から看護者として学んだこと」を書く機会をいただきました(このときの文章を本書の第一章に、メヂカルフレンド社の許諾を得て掲載しています)。
二〇年経った今読み返し、ここから今の私の活動のすべてが始まっていると感じています。私は姉の在宅ケアを経験して、その人が生きてきた生活の場が療養の場になり、かけがえのない時間を、家族や親しい人に囲まれて過ごせるのは、在宅ホスピスにほかならないと知りました。そして、そこに出向いていく看護があるはずなのに、まだまだ実践者が少ない状況を変えていきたいと、自分の進む道を在宅ケアに定めようと思ったのでした。
『家庭で看取る癌患者』のなかに、姉光子が在宅で過ごすためにつくられた医療・看護・介護をめぐるチームの連携図を入れました。当時、京都に住んでいた私が、神奈川に住む姉のために、義兄と電話で連絡を取り、補助しながら地域のサービスを組み立てていった成果です。つくりなおした図を三四~三五ページに入れました。
二〇年経って今、この図を見るにつけ、在宅ケアは利用者・家族を中心にチームケアで推進するのだという基本が、ここにすでに表われていたのだと気が付きます。
当時の私が、離れて暮らす家族の立場で、必死に地域の情報を集めフォーマルサービス、インフォーマルサービスをつなげた結果がここに集約されています。遠く離れているため、日々の看護ができないもどかしさが、この連携を組み立てるにはよい作用をしています。直接看護できないことを他の人に委ねよう、任せてお願いしよう、自分のできることをできるだけしようという、今でいう遠距離介護です。とても多くの方々に助けていただきました。
当時、私は看護学校の教員をしていたこともあって、新聞記事の医療欄に目を通し、気になる記事は切り抜いていました。そうしたなかで、二四時間の連絡体制を取り、必要時には往診をする仕組み、がん患者も診ているというライフケアシステムの記事を読み、白十字診療所をお訪ねして、義兄とともに佐藤智(あきら)先生にお目にかかれたのも、本当に幸運でした。
在宅ケアに至るまでの、私の臨床経験は産婦人科が中心です。第二次ベビーブームの真っ最中の産科は、今にして思えば戦場のようでした。多忙を極めるなかに、新しいいのちの誕生に寄り添い、生まれなかったいのちをいとおしみ、婦人科のがん患者さんの抗がん剤や放射線治療のつらさに寄り添い、多くの経験をしました。その後の看護学校でも母性が中心ですが、大学病院の実習指導では、医学の発展に伴う取り組みのなかの内科・外科病棟を、学生とともに学ぶ機会に恵まれました。
「看護はすべての健康レベルの人が対象であり、どんな場所でも展開できる」と、基礎教育で学んだものです。健康に生まれてくる子どもや、健康破綻をきたす危険は高いが自然な経過である妊産婦、つまり周産期への看護としてのかかわりは、その後私が病院を飛び出して看護の場を広げていく糸口であったのかもしれません。学生実習の一環として新生児訪問を実施できていたことも、家庭での療養現場に近づいていくきっかけでした。
その後、実際に在宅ケアの道を歩むには、もっと勉強が必要ではないかと考え、施設ホスピスの草分けとして有名な淀川キリスト教病院の訪問看護室で研修させていただきました。ここでの経験は、東京に移ってから在宅ケアを始める際、大変役に立ちました。
姉からの大いなる遺産、在宅ケアへの道を歩いてきました。これからも歩み続けたいと思っています。
現在の私は、訪問看護ステーションの統括所長として、がんのみならず、高齢者や難病などさまざまな方へのターミナル(終末期)ケアに、一五人のスタッフとともにかかわらせていただいています。さらに同じく統括部長を務めるヘルパーステーションの同じ方向をめざすスタッフたち、そしてボランティアの方々とも一緒です。
在宅ケアには思いもよらない不思議な力があります。必死になったときに見えた“この人の力”を信じて頼み、そのことに感謝して次へ進む。このことは、患者さんを抱え込むことなく、もっと自在に在宅ケアを行なうヒントにつながるかもしれません。
在宅ケアはチームケアが原則。でも、それがうまくいっていないことも多く、ギクシャクとした人間関係を、緩めて、ほぐして、またつなぐことを、日々しています。
これまで経験してきたなかで、考え、感じてきたことを少しずつまとめることにしました。
できるだけ平易にと心がけた文章のため、旧知のことや、まわりくどいと思われる表現になったかもしれませんが、在宅ケアが多くの方に知ってもらえる機会となれば幸いです。とくにターミナルにある利用者やそのご家族へのケアは、これから大切になります。ターミナルケアは難しい、怖い、できれば避けたい、と思っている方も多いのではないでしょうか。でもそんなに臆病にならずに、ここはお互いの知恵を集めて、人生の最後の時間にかかわらせていただく幸せを感じられるようになっていきたい。そんなふうに考えています。
目次
開く
プロローグ
第一章 家庭で看取るがん患者-在宅ケアにかかわるきっかけ
第二章 訪問のなかで考えること-いのちに寄り添うケアを
音楽や言葉のもつ力
人生最後のすごい仕事!-認知症も穏やかな経過に
救急車を呼ぶということは、どういうことなのか?
もうちょっとそばにいてくれないかしら?-一人暮らしを貫いて
いのちの自然な終わり-最期の時間の過ごし方
動かさないと動けなくなる-廃用症候を防ぐ
「聞き書き」との出合い、そして明治の母の看取り
第三章 あなたの思いを聞かせてください-喪の作業とグリーフケア
看取りにまつわる個人的な体験から
グリーフケア-個人的な経験を話すことが、人を動かす
悲しみに、仕事としてかかわる
語ること、表現することの大きな力
最期の大事な「時」を迎える準備
「看取りの語り部」になって安心の地域と人生の再生
第四章 まちをつくる-健やかに暮らし、安心して逝くために
病気は家庭で治す-ライフケアシステムのめざしたこと
足元の現実と地域のネットワーク-問題解決へのコミュニケーション
「まち」をつくる
誰もが自分の力を取り戻せる相談窓口-イギリスのマギーズセンターを参考に
エピローグ/初出一覧/著者プロフィール
第一章 家庭で看取るがん患者-在宅ケアにかかわるきっかけ
第二章 訪問のなかで考えること-いのちに寄り添うケアを
音楽や言葉のもつ力
人生最後のすごい仕事!-認知症も穏やかな経過に
救急車を呼ぶということは、どういうことなのか?
もうちょっとそばにいてくれないかしら?-一人暮らしを貫いて
いのちの自然な終わり-最期の時間の過ごし方
動かさないと動けなくなる-廃用症候を防ぐ
「聞き書き」との出合い、そして明治の母の看取り
第三章 あなたの思いを聞かせてください-喪の作業とグリーフケア
看取りにまつわる個人的な体験から
グリーフケア-個人的な経験を話すことが、人を動かす
悲しみに、仕事としてかかわる
語ること、表現することの大きな力
最期の大事な「時」を迎える準備
「看取りの語り部」になって安心の地域と人生の再生
第四章 まちをつくる-健やかに暮らし、安心して逝くために
病気は家庭で治す-ライフケアシステムのめざしたこと
足元の現実と地域のネットワーク-問題解決へのコミュニケーション
「まち」をつくる
誰もが自分の力を取り戻せる相談窓口-イギリスのマギーズセンターを参考に
エピローグ/初出一覧/著者プロフィール
書評
開く
在宅ケアの新たな力にチャレンジ (雑誌『訪問看護と介護』より)
書評者: 石田 昌宏 (日本看護連盟幹事長)
◆不思議な力って?
在宅ケアの不思議な“力”ってなんだろう。
秋山さんは訪問看護をすることによって,その人がその人らしく生き抜く姿をたくさんみてきた。そしてそれを支えてきた。
ラジオ体操の音楽,尋常小学校のときに習った歌,若いころの流行歌,そんな音楽が生きる喜びを支えていること。在宅で死ぬことを「こうやって死ねたらいいとお手本を見せている」と語り,ターミナル患者が周囲に生きる意味を伝えていること。最愛の人が亡くなったとき,慰められることがかえってつらく感じるときもあること。
人の気持ちが揺さぶられるこのような場面に,必ず看護師がそっと寄り添っている。そう,精一杯生きる力を引き出し,どんなになっても明るく暮らし続ける力を支えるのが,在宅ケアの“力”だ。
そう,そう思っていた。そうとしか思っていなかった。
ところが秋山さんは今,一人ひとりの人との出会いによって,在宅ケアの“力”を昇華させ,新たな“力”にチャレンジしている。それは「まちづくり」だ。
◆看護は幸せを運ぶ
自分の家で看護を受けることができるのは,まだまだ少数の人たちでしかない。そもそも訪問看護の力を知らないから,自分の家で看護を受けることすら思いつかない。だから,自宅で看護を受けられること,そして「看護って素敵なんだよ」と伝える努力をしていくことが大切だ。
看護を受けると人は幸せになる。絶対にそうだ。だから堂々と臆することなく看護を語ればいい。
しかし,語り続けることも大変だ。
できれば誰もが肩ひじ張って努力しなくても,自然と看護を受けられる「まち」があればいい。
健康が気になったら,ちょっと相談。それだけですべてのケアがぶぁーって広がっていくわけだ。一人ひとりの生きざまに合わせて,いつでもどこでもケアが展開される「まち」に住んでみたいと思いませんか?
◆一人ひとりの生き方が「まち」をつくる
秋山さんは,きっとそんな「まち」をつくってくれる。秋山さんの発見した在宅ケアの不思議な“力”をもってすれば,それは必ずできる。この本を読んだらそんな気がしてきた。
訪問看護師として一人ひとりに寄り添っているうちに,いつの間にか「まちづくり」にチャレンジしている秋山さん。温かなまちは,そこに暮らす一人ひとりの素敵な生き方でできているんだなあと思う。
◆在宅ケアをあきらめない
全国をまわっていると,「高齢化もすごく進んで,帰り先のない患者さんも多いです。なんとかしたいと思っても,どうしようもないんです」という話をよく耳にする。
病院や施設の看護師たちも一生懸命患者さんや家族のことを考えて看護の仕事をしている。家族も何とかしたいと思っている。しかし毎日の生活を考えると症状が重く,医療的ケアに手が必要な患者さんをそう簡単に家で受け入れるわけにいかないと悩んでいる……。
在宅ケアをあきらめたくない気持ちが心の片隅から離れない。
確かに今のままでは難しい。けれど何か方法があるはずだ。ちょっと視点を変えて,まず看護を信じること。そして地域の訪問看護を見つめなおしたらその方法がわかるのではないだろうか。
(『訪問看護と介護』2010年6月号掲載)
人が生きようとする力を信じ,それに寄り添う看護 (雑誌『看護管理』より)
書評者: 宇都宮 宏子 (京都大学医学部附属病院地域ネットワーク医療部看護師長)
著者である秋山正子さんと私との出会いは,かれこれ16年以上前まで遡る。京都府看護協会の訪問看護養成研修で,彼女は在宅ホスピスの講義を担当し,一方の私は訪問看護師を始めて3年目頃で,研修生として参加していた。その後,私は秋山さんをはじめ,すでに活躍していた宮崎和加子さん,山崎摩耶さんたちを目標に,京都での訪問看護に看護師人生をかけようと決意し,日々訪問看護を重ねていた。そうしているうちに,地域で利用者をただ待つのではなく,病院から在宅へ移行させる医療・看護をマネジメントすることの重要性に気がついた。
◆どちらのケアが,よりクオリティオブライフを保てるか
在宅医療を知らない病院の医師や看護師が,「帰りたい」と願う患者に,独居であるとか,医療依存度が高いとか,家族が拒否しているという理由で,帰すことを諦めている。しかし,生活の場に戻れる医療・看護を提供しなければ,そうした高齢者や病気をもった人たちが増える一方であることも事実だ。誰のための医療なのかを患者・家族が主体的に考え参加できる医療のあり方をさらに追求するため,私は2002(平成14)年に病院に戻って以来退院調整看護師としてさまざまな課題に取り組んできた。秋山さんとはそうした思いを共有し,いまでは研修会や講演・執筆活動で協力し合う関係である。
本書には,患者本人や家族が在宅ケアを望んでも,なかなか思うようにならない現状のなかで,お姉さんの事例をはじめうまくいった事例を挙げ,その要因を“どちらのケアが,よりクオリティオブライフを保てるか”の見極めが早い段階でできたこと,そのために整えなければならない実際的な条件を充足するよう,一つひとつ問題解決を図っていったことが大きいと書かれている。まさに「患者の生活を考える,そのためのマネジメントを行なう」退院支援・退院調整が大きなカギを握っているということだ。
◆看護の果てなき夢と希望を与えてくれる
私はいま,全国で退院支援・在宅移行をテーマにした講演や退院調整看護師養成研修に走り回り,これまで京都大学病院で培ったシステムや考え方を伝道している。急性期ではとかく,医師からの指示待ち,そして指示通りにいかに動くかといった“診療の補助”が優先される。そんななかで,日々オンゴーイングで患者・家族と向き合い,対応に悩む病棟看護師や医師たちとチームカンファレンスを行ない,「患者にとってどうすることがよいのか」を考え行動してきたことを一人でも多くの人に知ってもらいたいからだ。
秋山さんが看護師としてどう考え,何をしてきたのか,そしてどのような言葉でそれを伝え,患者の語りを引き出してきたのか,さらに患者が病気をもって生きることに寄り添う看護をするという,本来あるべき看護の姿が本書を通じてみえてくる。そして,人が自分の人生を生きようとするときの力,家や地域といった環境がもつ力,長い歴史のなかで人が蓄積してきた魂の力など,いろいろな力が合わさって伝わり,共鳴し,家族や友人,そして私たち医療者,ケア提供者,患者に関わるすべての人に,“人間ってすごいなぁ”と,力を与えてくれる。
がんになっても老いても最期まで暮らせるまちづくりをめざす私たちに,果てなき夢と希望を与えてくれる一冊である。
(『看護管理』2010年5月号掲載)
書評者: 石田 昌宏 (日本看護連盟幹事長)
◆不思議な力って?
在宅ケアの不思議な“力”ってなんだろう。
秋山さんは訪問看護をすることによって,その人がその人らしく生き抜く姿をたくさんみてきた。そしてそれを支えてきた。
ラジオ体操の音楽,尋常小学校のときに習った歌,若いころの流行歌,そんな音楽が生きる喜びを支えていること。在宅で死ぬことを「こうやって死ねたらいいとお手本を見せている」と語り,ターミナル患者が周囲に生きる意味を伝えていること。最愛の人が亡くなったとき,慰められることがかえってつらく感じるときもあること。
人の気持ちが揺さぶられるこのような場面に,必ず看護師がそっと寄り添っている。そう,精一杯生きる力を引き出し,どんなになっても明るく暮らし続ける力を支えるのが,在宅ケアの“力”だ。
そう,そう思っていた。そうとしか思っていなかった。
ところが秋山さんは今,一人ひとりの人との出会いによって,在宅ケアの“力”を昇華させ,新たな“力”にチャレンジしている。それは「まちづくり」だ。
◆看護は幸せを運ぶ
自分の家で看護を受けることができるのは,まだまだ少数の人たちでしかない。そもそも訪問看護の力を知らないから,自分の家で看護を受けることすら思いつかない。だから,自宅で看護を受けられること,そして「看護って素敵なんだよ」と伝える努力をしていくことが大切だ。
看護を受けると人は幸せになる。絶対にそうだ。だから堂々と臆することなく看護を語ればいい。
しかし,語り続けることも大変だ。
できれば誰もが肩ひじ張って努力しなくても,自然と看護を受けられる「まち」があればいい。
健康が気になったら,ちょっと相談。それだけですべてのケアがぶぁーって広がっていくわけだ。一人ひとりの生きざまに合わせて,いつでもどこでもケアが展開される「まち」に住んでみたいと思いませんか?
◆一人ひとりの生き方が「まち」をつくる
秋山さんは,きっとそんな「まち」をつくってくれる。秋山さんの発見した在宅ケアの不思議な“力”をもってすれば,それは必ずできる。この本を読んだらそんな気がしてきた。
訪問看護師として一人ひとりに寄り添っているうちに,いつの間にか「まちづくり」にチャレンジしている秋山さん。温かなまちは,そこに暮らす一人ひとりの素敵な生き方でできているんだなあと思う。
◆在宅ケアをあきらめない
全国をまわっていると,「高齢化もすごく進んで,帰り先のない患者さんも多いです。なんとかしたいと思っても,どうしようもないんです」という話をよく耳にする。
病院や施設の看護師たちも一生懸命患者さんや家族のことを考えて看護の仕事をしている。家族も何とかしたいと思っている。しかし毎日の生活を考えると症状が重く,医療的ケアに手が必要な患者さんをそう簡単に家で受け入れるわけにいかないと悩んでいる……。
在宅ケアをあきらめたくない気持ちが心の片隅から離れない。
確かに今のままでは難しい。けれど何か方法があるはずだ。ちょっと視点を変えて,まず看護を信じること。そして地域の訪問看護を見つめなおしたらその方法がわかるのではないだろうか。
(『訪問看護と介護』2010年6月号掲載)
人が生きようとする力を信じ,それに寄り添う看護 (雑誌『看護管理』より)
書評者: 宇都宮 宏子 (京都大学医学部附属病院地域ネットワーク医療部看護師長)
著者である秋山正子さんと私との出会いは,かれこれ16年以上前まで遡る。京都府看護協会の訪問看護養成研修で,彼女は在宅ホスピスの講義を担当し,一方の私は訪問看護師を始めて3年目頃で,研修生として参加していた。その後,私は秋山さんをはじめ,すでに活躍していた宮崎和加子さん,山崎摩耶さんたちを目標に,京都での訪問看護に看護師人生をかけようと決意し,日々訪問看護を重ねていた。そうしているうちに,地域で利用者をただ待つのではなく,病院から在宅へ移行させる医療・看護をマネジメントすることの重要性に気がついた。
◆どちらのケアが,よりクオリティオブライフを保てるか
在宅医療を知らない病院の医師や看護師が,「帰りたい」と願う患者に,独居であるとか,医療依存度が高いとか,家族が拒否しているという理由で,帰すことを諦めている。しかし,生活の場に戻れる医療・看護を提供しなければ,そうした高齢者や病気をもった人たちが増える一方であることも事実だ。誰のための医療なのかを患者・家族が主体的に考え参加できる医療のあり方をさらに追求するため,私は2002(平成14)年に病院に戻って以来退院調整看護師としてさまざまな課題に取り組んできた。秋山さんとはそうした思いを共有し,いまでは研修会や講演・執筆活動で協力し合う関係である。
本書には,患者本人や家族が在宅ケアを望んでも,なかなか思うようにならない現状のなかで,お姉さんの事例をはじめうまくいった事例を挙げ,その要因を“どちらのケアが,よりクオリティオブライフを保てるか”の見極めが早い段階でできたこと,そのために整えなければならない実際的な条件を充足するよう,一つひとつ問題解決を図っていったことが大きいと書かれている。まさに「患者の生活を考える,そのためのマネジメントを行なう」退院支援・退院調整が大きなカギを握っているということだ。
◆看護の果てなき夢と希望を与えてくれる
私はいま,全国で退院支援・在宅移行をテーマにした講演や退院調整看護師養成研修に走り回り,これまで京都大学病院で培ったシステムや考え方を伝道している。急性期ではとかく,医師からの指示待ち,そして指示通りにいかに動くかといった“診療の補助”が優先される。そんななかで,日々オンゴーイングで患者・家族と向き合い,対応に悩む病棟看護師や医師たちとチームカンファレンスを行ない,「患者にとってどうすることがよいのか」を考え行動してきたことを一人でも多くの人に知ってもらいたいからだ。
秋山さんが看護師としてどう考え,何をしてきたのか,そしてどのような言葉でそれを伝え,患者の語りを引き出してきたのか,さらに患者が病気をもって生きることに寄り添う看護をするという,本来あるべき看護の姿が本書を通じてみえてくる。そして,人が自分の人生を生きようとするときの力,家や地域といった環境がもつ力,長い歴史のなかで人が蓄積してきた魂の力など,いろいろな力が合わさって伝わり,共鳴し,家族や友人,そして私たち医療者,ケア提供者,患者に関わるすべての人に,“人間ってすごいなぁ”と,力を与えてくれる。
がんになっても老いても最期まで暮らせるまちづくりをめざす私たちに,果てなき夢と希望を与えてくれる一冊である。
(『看護管理』2010年5月号掲載)
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。