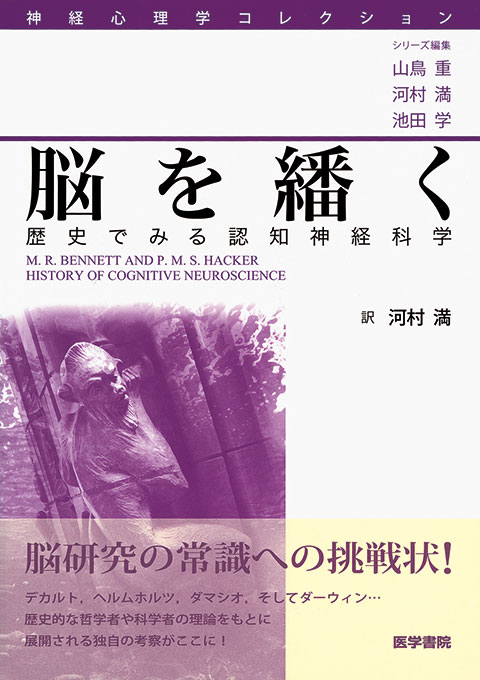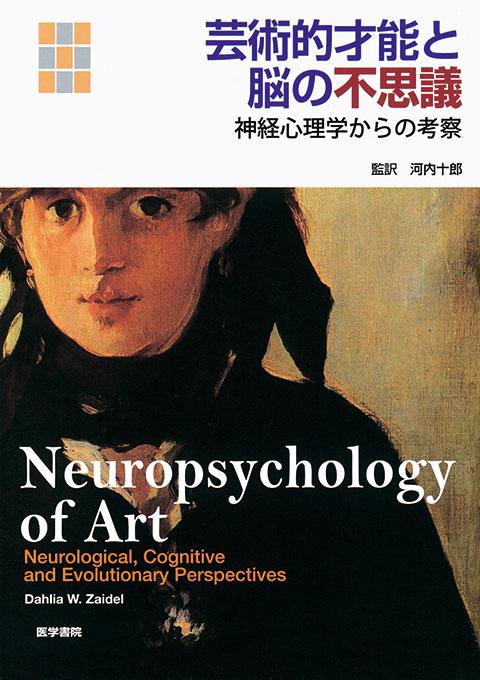脳を繙く
歴史でみる認知神経科学
脳研究の常識へ疑問を投げかけ、独自の考察を展開する衝撃の書
もっと見る
認知神経科学について「歴史」を切り口に解説するもの。認知(記憶など)、言語、運動といった神経心理学領域で扱われる一通りのテーマについて、過去から現在までの歴史的な流れが押さえられる。用語や人名などを網羅的に収載しているため、教科書的・辞書的に使うことも可能。神経内科医・精神科医はもちろん、初学者やコメディカルが神経心理学領域を理解するためのサブテキストとしても有用な1冊。
*「神経心理学コレクション」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 神経心理学コレクション |
|---|---|
| 著 | M. R. Bennett / P. M. S. Hacker |
| 訳 | 河村 満 |
| シリーズ編集 | 山鳥 重 / 河村 満 / 池田 学 |
| 発行 | 2010年11月判型:A5頁:432 |
| ISBN | 978-4-260-01146-4 |
| 定価 | 5,280円 (本体4,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
訳者 序/まえがき/序
訳者 序
『脳を繙〈ひもと〉く―歴史でみる認知神経科学』は,神経心理学コレクション・シリーズの節目に,今までとは装丁の雰囲気も変えて出版されます。表紙に帯がついたのが一番大きな違いです。表紙のサルのレリーフは本書の歴史的な内容を意味し,合成した海の写真は脳の複雑で謎の多い構造を深海になぞらえて表現しているのかもしれません。
神経心理学コレクション・シリーズの第1巻は,「神経心理学の挑戦」で,およそ10年前,2000年5月に発刊されました。対談形式が特徴で,当時仙台の山鳥 重先生と東京の私とが,まず仙台,次に東京で長時間対座してお話ししたことをよく覚えています。当時はまだボイスレコーダーはなく,編集の樋口 覚さんが細い帯状のテープが入ったレコーダーを机の真ん中に3台も置き,話が盛り上がったときに中断しなくてもよい準備をしてくれました。最近では対談・鼎談内容の正確性を期すために必ず同席する速記者も当時はいませんでした。
シリーズの全体編集は,山鳥 重先生,彦坂興秀先生,故田邉敬貴先生,それに私で,日本神経心理学会・日本高次脳機能障害学会総会時に定期的に編集会議を開き,次の企画を決めました。10年間で約20冊が発刊され,どの本も好評であったのは幸運でしたが,その最大の理由は,時代を先取りすることのできる優れた著者を豊富に獲得できたからであると思います。山鳥・彦坂・田邉先生は皆互いに共通しない,広い人脈を持っていましたし,ユニークで魅力のあるテーマを発案する能力がひときわ高かったのです。
神経心理学コレクションを全部集めている読者もかなりいます。その中の一人が私の大学の学生であったのは,私にとって何より幸せな思い出として残っています。7年前,彼が大学2年生のときに突然,「コレクションを読んで脳研究に興味を持った。お会いしたい」というメールをくれました。その彼も来年4月には臨床研修を修了して,私の教室の大学院に入学する予定です。
ところで,この『脳を繙く―歴史でみる認知神経科学』はかなり難解な本です。第一,「繙く」を「ひもとく」とちゃんと読めた人は少ないのではないでしょうか.私は本書を早朝起床してすぐに読むことを日課として課しました。お昼過ぎや夜ではついうとうとしてしまうからです。英文には難解な表現はあまりないのですが,かなり広い知識がないと内容理解に至らないので大変苦労しました。本の内容や出版の目的は筆者らの「序」やケニー先生の「まえがき」に書かれているように,脳科学全体にわたる主要な研究を網羅的に取り上げ,整理し,研究内容を歴史的に位置づけ,批判的に考察する,という雄大なものです。読者は,得意でない領域を理解するのには相当骨が折れると思います。さらに,著者らのスタンスはかなり挑戦的であると私には感じられます。常識となっている理論や有名科学者の考察に対してもずけずけと問題点を指摘し,批判するのが著者らの姿勢です。それは,デカルト,ヘルムホルツ,シェリントンなど歴史的な哲学者,科学者に対しても同様です。脳研究に関連したことに影響を与えた,アリストテレス以来の多くの人々の意見が引用されています。従来のほとんどすべての学説に対して懐疑的で,過激な表現にびっくりしてしまうことも随所にあります。こんな本は読んだことがありません。
若い柔軟な脳を持った人たちには,最初から通読するのをお勧めします。多くの知識が得られ,独自の視点を持つことの大切さが理解できるでしょう。脳研究をすでに開始した年長者にとっては,研究を拡大したり,深めたりしたいときに該当部分を選んで読むのが最良の読み方であると思います。引用文献は厳選されて取り上げられています。神経科学に興味を持つ一般の方にも読んでほしいと思います。どんな立場の読者も共通して感じなければいけないのは,脳研究には揺るぎのない科学哲学が必要である,という著者からの強烈なメッセージです。
神経心理学コレクションは,本書から新しい編集体制が敷かれ,次のステップに向かう予定です。編集者として山鳥 重先生と私が残り,新たに池田 学先生が加わります。
この節目の第1巻として,10年前と同様に,次の時代を先取りした挑戦的な本を読者に送りたいと考えます。
2010年9月
河村 満
まえがき
マックス・ベネット(Max Bennett)とピーター・ハッカー(Peter Hacker)の『神経科学の哲学的基盤』(Blackwell, 2003)は,近年,心に関する哲学に最も重要な貢献をなすものであった。この著書は,認知科学の主張するところを徹底的かつ綿密に検証することによって哲学的心理学を時代遅れのものとし,認知科学という新しい専門分野の何人かの最も著名な提唱者たちの著作がいかに広く哲学的混迷に冒されているかを明らかにした。われわれが通常用いている思考,意図,推理といった概念を,民族心理学の遺物としてしりぞける人々は,ベネットとハッカーによれば,心の神経学的基礎を探究する科学者なら誰しもがその上に腰を据えなければならない木の枝をみずから鋸で切り落とすのに熱中しているということになる。
多くの高い声価がこうした疑わしい主張のうえに築かれてきたのであるならば,ベネットとハッカーの著書が,とりわけ認知科学に肩入れする哲学者たちの側からの敵対的な反応に出くわしたのは当然であった。最も著名なふたりの研究者,ダニエル・デネット(Daniel Dennett)とジョン・サール(John Searle)が,2005年にニューヨークで開催された米国哲学協会の学術集会において辛辣な批判を細部にわたって展開した。このときの質疑応答は,『神経科学と哲学』と題して2007年にコロンビア大学出版局から出版されたが,この書こそ,ベネットとハッカーがその批判者たちよりはるかに立ちまさっていることをあまねく世に知らしめるものとなった。けれども読者の間では,これらの著者は認知神経科学における専門的研究作業に十分精通しているとはいえないのではないかという疑念が依然尾を引いて残った。
本書はこのような疑念を最終的に払拭するものとなるはずである。ここでは広く歴史的背景をふまえ,認知神経科学という専門分野を確立したとされる19世紀のヘルムホルツ(Helmholtz)以降の研究論文が詳しく解説されている。各章で著者らは,まず最初に関連領域の研究を記述し,次に研究者たちが自らの研究結果に付した解釈を批判的に分析し,最後に哲学的混迷を脱した用語でその研究の結論の再記述を行っている。
このようにして著者らは,例えば1例をあげるなら,ガザニガ(Gazzaniga)とル・ドゥー(Le Doux)が脳の2つの半球はそれぞれ独自に心を所有していると主張するうえで根拠とした交連切開術後の機能障害を記述し,この主張をメレオロジカル*な誤謬であるとしてしりぞけている。人間というものは,その一部分ではなく,1個の全体的存在としてのみ心を持ちうるというのである。次に著者らは,研究の諸結果を,脳梁を介しての神経信号の伝達は人間が視覚的に提示されたものを知るための必要条件であるというように,潤色のない言葉で再記述している。
さらにもう1つ別の例をあげるなら,側頭葉損傷患者の記憶力検査をもとに,多数の研究者が,記憶は過去の体験の神経的表象が海馬に貯蔵されることによると結論したが,ベネットとハッカーは,これには表象(representation)という概念についての誤用が含まれることを明らかにする。これまでの研究が明らかにしたことといえば,ある種の神経構造もしくはシナプス連結の力がなければ,人は,例えばヘースティングズの戦いの日付を思い出すことはできないだろうということにすぎない,と著者らは主張するのである。
このような研究諸結果のベネットとハッカーによる再記述に対して読者は最初,研究結果の持つすべての魅力を取り去って,いわば天然色ではなくモノクロームで表現したものだという印象を抱くかもしれない。しかし,実際には,これらの再記述は,そのような魅力よりも実体をはるかに正確に伝えるものであって,単に認知神経科学の物語の紹介にかかわるだけでなく,この科学の構想それ自体に重要な影響を及ぼすものなのである。
ベネットとハッカーによれば,神経生理学の研究者の陥りやすい誤謬は,論理的にいって動物全体にのみ帰すべき状態や活動を,脳の諸部分および脳の処理過程に帰着させてきた点にある。意識する,思考する,信じる,知覚する,仮定する,認識する,想起するといった心理学的属性を人間のある部分に帰着させるのは無意味だと著者らは主張するのである。
このような帰着のさせ方は,2つの異なる仕方で,説明の試みを挫折させる。一方で,それは,実際には何も説明されていないのにあたかも説明がなされたかのような幻想をもたらす。人間には自由に使える貯えられた表象があり,それが想起を可能にするという考えは,あらかじめ記憶というものを前提としており,それを説明することはできない。というのも,そのような記録をわれわれが利用することができたとしても,われわれはそれらをどのように読み取るべきかをやはり想起しなければならないからである。他方で,メレオロジカルな誤謬もまた,異なる神経経路で伝達された情報が統合された対象をどのようにして知覚することを動物に可能にするか(結合の問題)といった擬似問題にすぎない問いを生み出す。本書の批判的スタンスは,もとより神経科学的研究になんら脅威を及ぼすものではない。ただ,解答のありえない無用の問題を回避し,実験結果を逸脱する誇大宣伝を抑制しようとするものである。
この哲学と生理学との関係における歴史の背景には,ふたりの知的巨人が屹立している。アリストテレス(Aristotle)とデカルト(Descartes)である。生理学にアリストテレスがもたらした影響はきわめて望ましくないものであったし,デカルトがもたらした影響は非常に望ましいものであった。哲学では両者の立場はちょうど逆になる。脳の機能の多くをアリストテレスは誤って心臓に帰した。幸いガレノス(Galen)によって脳にその正常な位置が与えられるまでにそれほど長い時代を要さなかった。しかしデカルトのほうは神経生理学に実質的な貢献を果たしたのであって,ベネットの言葉を信じるなら,生物学的説明は作用因(efficient causation)の観点からなされなければならないというデカルトの主張は,17世紀以降の神経生理学上のすべての進歩の基盤となった。だがその一方で,デカルトの哲学的二元論は心の哲学を五里霧中の状態にさまよわせることになったので,その影響は長く尾を引き,現代に至っても唯物論者の中にはデカルト的自我(エゴ)を信じ,端的に自我というものを心ではなく脳と同一視する人々がいる。ベネットとハッカーは,アリストテレスの全体的存在としての人間(ユニタリ・ヒューマンビーイング)の概念に繰り返し言及しているが,この概念については近年ウィトゲンシュタイン(Wittgenstein)も重要な再記述を行っている。
本書では,神経生理学的研究の知見が,独特な,従来とは異なる視点から紹介されているが,これは,斬新な経験的探究や新しい実験的作業のゆえにそうなったのではなく,心と脳の間の関係を探るうえで不可欠の諸概念の論理言語学的分析の結果そうなったのである。このような探究の方式は多くの生理学者に馴染みのないものであろうが,これこそがこの研究プロジェクトに必須のツールなのである。「われわれの物語に教訓があるとすれば」とベネットとハッカーは述べている,「それは,神経科学者は自らの実験に注ぐのと同じくらい細心の注意を,概念の一貫性と明晰性を確保することにも注がなければならないということである」。
アンソニー・ケニー
大英学士院院長,1989~1993
* 訳注:mereology:部分と全体の形式論理的関係を研究する学問分野。
序
神経科学は,神経系の働きを解明し,その知識を,認知症や統合失調症などの病気による苛酷な苦難から人類を救済するための方策の設計に役立たせることをめざす。この課題を遂行するにあたって認知神経科学者はまた,脳の諸機能をも明らかにしようとする。われわれが知覚や記憶のような心理的機能を十分に果たしうるためには,脳が正常に機能するということが不可欠なのである。細胞神経科学者や分子神経科学者は,例えばニューロンとその軸索における活動電位の伝達にみられるメカニズムを研究し,この電位の変化がどのようにして軸索終末からシナプスで接合するニューロンへ伝達物質を放出するかを探究する(この主題の展開に関しては,Bennett, 2001参照)。認知神経科学者はとりわけ,シナプスの回路がどのように作動して脳におけるその機能を果たすかに関心を寄せる。それぞれ1万以上のシナプスを有する数千から数百万のニューロンからなるこのような回路網は,脳のさまざまな部位にみられるものであって,われわれが,例えば新しい出来事をおよそ1分間以上記憶にとどめ(海馬),視覚化できる(網膜と一次視覚野V1)ためには,それらが正常に機能していなければならない。
過去20年間,神経科学研究では海馬の作用のメカニズムが大きな焦点になってきた。海馬でみられるニューロンのタイプとそれらの空間的配置およびシナプス連結を最初に記載したのはラモニ・カハル(Ramon y Cajal)であった。海馬の機能を理解するためによく用いられるアプローチとして,この問題に対する工学的アプローチを踏まえながら,神経シナプス回路網の表象と考えられているものを開発するやり方がある。ブラインドリー(Brindley, 1967)は,海馬における,したがってそのシナプス回路網の表象における,ある種のシナプスは修正可能であると考えなければならないことを示唆した。彼がこの言葉で意味したのは,シナプスは軸索終末における活動電位の到達を受けてその特質を恒常的に変化させることができ,したがって海馬では「神経系の条件づけと記憶のメカニズムが修正可能なシナプスを用いて情報を貯蔵する」(p361)ということである。のちにマー(Marr, 1971)は,「古皮質(海馬)の最も重要な特性は,単一種類の記憶の課題を遂行する能力にある」(p23)と示唆した。さらに彼は,海馬の特定部位におけるシナプス連結のパターンは,もし興奮性シナプスの効力が修正可能であり,また大きなニューロンの膜電位がシナプス回路網の全体的活動を規制する抑制性介在ニューロンによって設定されているとすれば,自動連想記憶として機能しうることを明らかにした。工学的用語で組み立てられたマーの説は,きわめて大きな影響力を持った。例えば,海馬における神経回路網の表象がどのように作動するかについてのある報告では,「記憶の想起は,想起される記憶と重なり合う一定の組み合わせの錐体ニューロンの発火で始まり」,次いで「さまざまに異なる組み合わせの錐体ニューロンの発火が別個の同期的な歩調で起こり」,ついには貯蔵されたニューロンの記憶パターンが回復されることが示唆された(Bennett et al., 1994, p167)。
過去ほぼ半世紀にわたって,脳の各部分が神経回路網という工学的仕組みで説明されてきたが,それに伴って認知神経科学に1つの大きな動向が生じた。すなわち,通常ヒトが持つもの(場合によっては他の動物が持つもの)とされる心理学的属性を調べ,それらの属性を,複雑性と修正可能性がさまざまな度合いで異なる工学的仕組みで説明される以前ないしは以後の神経シナプス回路網に還元してとらえるという動向である。本書でわれわれは,脳内の特異的なシナプス回路網もしくは回路網の集合は,見ること(第1章),注意すること(第2章),想起すること(第3章),理解し,思考し,思考を言語に変換すること(第4章),情動を持つこと(第5章)が可能であるという主張を検証する。われわれのアプローチは,これらの考えの歴史的な発展を明らかにすることであり,また,それらを生み出すもととなったさまざまな実験結果の解釈を調べることによって,これらの考えがどのようにして認知神経科学の主流とみなされる専門領域に組み込まれるに至ったかを明らかにすることである。概念の分析を行うことによってわれわれは,例えば『すべての視覚行動は脳の提示する疑問への答えを探求する持続的過程とみなすことができる。網膜からの信号はこれらの答えを伝える「メッセージ」を構成する』(p119)とするJ・Z・ヤング(J.Z. Young, 1978)のような著名な神経科学者の解釈で何が誤っているかを明らかにできたと考える。ブレークモア(Blakemore, 1977)は,後頭極の視覚野皮質は「脳が知覚という仮説を組み立てる論拠となる」ニューロンを所有していると主張する(p91)。ゼキ(Zeki, 1999, p2056)は,われわれが色を見るためには,「脳が対象の物理的特性(それらの反射率)に対して与える解釈,つまり反射率の特性について速やかに知識を獲得することを脳に可能にする解釈」が必要であると論じている。ガザニガら(Gazzaniga et al., 2002)は,「右大脳半球は言語を理解することはできるが,統語法(シンタクス)を理解することはできない」とし,「右大脳半球の推理能力はきわめて限られている」(p414)と考えている。脳のシナプス回路網は心理学的属性を有しているという考えを精細に吟味するのが本書の中心的課題である。
われわれは先に上梓した共著『神経科学の哲学的基盤』において,最近の重要な神経科学理論,例えば知覚,記憶,情動に関する理論には概念上の問題があることを明らかにした。神経科学者と哲学者双方の意識の性質に関する最近の著作についても批判的評価を行った。本書が前共著『神経科学の哲学的基盤』と異なるのは,ここではわれわれが,ほぼ前世紀全体を通じて脳の機能と人間の心理学的属性との間の関係に関してさまざまな説を生むもととなった諸実験についての調査を紹介している点である(したがって多数の図解も用いた)。加えて本書は,われわれにとって,前共著に対してポール・チャーチランド(Paul Churchland),ダニエル・デネット(Daniel Dennett),ジョン・サール(John Searle)らの研究者から向けられた哲学的批判に,とりわけ脳と意識という主題(第7章)に関して,応答する機会ともなった。
認知神経科学者の実験的活動に前共著よりもはるかに詳しく言及した本書が,こうした研究者の関心と批判的反応を喚起することをわれわれは願っている。このようなやり方によって,哲学者の間だけでなく,神経科学者の間でも,われわれの心理学的能力の使用と関連づけて認知神経科学が脳の機能について何を明らかにできるかという問題をめぐって対話が可能になるであろう。哲学者と認知神経科学者双方の実験的観察およびその解釈についての持続的な批判的・分析的評価を通じて初めて,この主題は誇張を免れて真に実りあるものとなるであろう。
訳者 序
『脳を繙〈ひもと〉く―歴史でみる認知神経科学』は,神経心理学コレクション・シリーズの節目に,今までとは装丁の雰囲気も変えて出版されます。表紙に帯がついたのが一番大きな違いです。表紙のサルのレリーフは本書の歴史的な内容を意味し,合成した海の写真は脳の複雑で謎の多い構造を深海になぞらえて表現しているのかもしれません。
神経心理学コレクション・シリーズの第1巻は,「神経心理学の挑戦」で,およそ10年前,2000年5月に発刊されました。対談形式が特徴で,当時仙台の山鳥 重先生と東京の私とが,まず仙台,次に東京で長時間対座してお話ししたことをよく覚えています。当時はまだボイスレコーダーはなく,編集の樋口 覚さんが細い帯状のテープが入ったレコーダーを机の真ん中に3台も置き,話が盛り上がったときに中断しなくてもよい準備をしてくれました。最近では対談・鼎談内容の正確性を期すために必ず同席する速記者も当時はいませんでした。
シリーズの全体編集は,山鳥 重先生,彦坂興秀先生,故田邉敬貴先生,それに私で,日本神経心理学会・日本高次脳機能障害学会総会時に定期的に編集会議を開き,次の企画を決めました。10年間で約20冊が発刊され,どの本も好評であったのは幸運でしたが,その最大の理由は,時代を先取りすることのできる優れた著者を豊富に獲得できたからであると思います。山鳥・彦坂・田邉先生は皆互いに共通しない,広い人脈を持っていましたし,ユニークで魅力のあるテーマを発案する能力がひときわ高かったのです。
神経心理学コレクションを全部集めている読者もかなりいます。その中の一人が私の大学の学生であったのは,私にとって何より幸せな思い出として残っています。7年前,彼が大学2年生のときに突然,「コレクションを読んで脳研究に興味を持った。お会いしたい」というメールをくれました。その彼も来年4月には臨床研修を修了して,私の教室の大学院に入学する予定です。
ところで,この『脳を繙く―歴史でみる認知神経科学』はかなり難解な本です。第一,「繙く」を「ひもとく」とちゃんと読めた人は少ないのではないでしょうか.私は本書を早朝起床してすぐに読むことを日課として課しました。お昼過ぎや夜ではついうとうとしてしまうからです。英文には難解な表現はあまりないのですが,かなり広い知識がないと内容理解に至らないので大変苦労しました。本の内容や出版の目的は筆者らの「序」やケニー先生の「まえがき」に書かれているように,脳科学全体にわたる主要な研究を網羅的に取り上げ,整理し,研究内容を歴史的に位置づけ,批判的に考察する,という雄大なものです。読者は,得意でない領域を理解するのには相当骨が折れると思います。さらに,著者らのスタンスはかなり挑戦的であると私には感じられます。常識となっている理論や有名科学者の考察に対してもずけずけと問題点を指摘し,批判するのが著者らの姿勢です。それは,デカルト,ヘルムホルツ,シェリントンなど歴史的な哲学者,科学者に対しても同様です。脳研究に関連したことに影響を与えた,アリストテレス以来の多くの人々の意見が引用されています。従来のほとんどすべての学説に対して懐疑的で,過激な表現にびっくりしてしまうことも随所にあります。こんな本は読んだことがありません。
若い柔軟な脳を持った人たちには,最初から通読するのをお勧めします。多くの知識が得られ,独自の視点を持つことの大切さが理解できるでしょう。脳研究をすでに開始した年長者にとっては,研究を拡大したり,深めたりしたいときに該当部分を選んで読むのが最良の読み方であると思います。引用文献は厳選されて取り上げられています。神経科学に興味を持つ一般の方にも読んでほしいと思います。どんな立場の読者も共通して感じなければいけないのは,脳研究には揺るぎのない科学哲学が必要である,という著者からの強烈なメッセージです。
神経心理学コレクションは,本書から新しい編集体制が敷かれ,次のステップに向かう予定です。編集者として山鳥 重先生と私が残り,新たに池田 学先生が加わります。
この節目の第1巻として,10年前と同様に,次の時代を先取りした挑戦的な本を読者に送りたいと考えます。
2010年9月
河村 満
まえがき
マックス・ベネット(Max Bennett)とピーター・ハッカー(Peter Hacker)の『神経科学の哲学的基盤』(Blackwell, 2003)は,近年,心に関する哲学に最も重要な貢献をなすものであった。この著書は,認知科学の主張するところを徹底的かつ綿密に検証することによって哲学的心理学を時代遅れのものとし,認知科学という新しい専門分野の何人かの最も著名な提唱者たちの著作がいかに広く哲学的混迷に冒されているかを明らかにした。われわれが通常用いている思考,意図,推理といった概念を,民族心理学の遺物としてしりぞける人々は,ベネットとハッカーによれば,心の神経学的基礎を探究する科学者なら誰しもがその上に腰を据えなければならない木の枝をみずから鋸で切り落とすのに熱中しているということになる。
多くの高い声価がこうした疑わしい主張のうえに築かれてきたのであるならば,ベネットとハッカーの著書が,とりわけ認知科学に肩入れする哲学者たちの側からの敵対的な反応に出くわしたのは当然であった。最も著名なふたりの研究者,ダニエル・デネット(Daniel Dennett)とジョン・サール(John Searle)が,2005年にニューヨークで開催された米国哲学協会の学術集会において辛辣な批判を細部にわたって展開した。このときの質疑応答は,『神経科学と哲学』と題して2007年にコロンビア大学出版局から出版されたが,この書こそ,ベネットとハッカーがその批判者たちよりはるかに立ちまさっていることをあまねく世に知らしめるものとなった。けれども読者の間では,これらの著者は認知神経科学における専門的研究作業に十分精通しているとはいえないのではないかという疑念が依然尾を引いて残った。
本書はこのような疑念を最終的に払拭するものとなるはずである。ここでは広く歴史的背景をふまえ,認知神経科学という専門分野を確立したとされる19世紀のヘルムホルツ(Helmholtz)以降の研究論文が詳しく解説されている。各章で著者らは,まず最初に関連領域の研究を記述し,次に研究者たちが自らの研究結果に付した解釈を批判的に分析し,最後に哲学的混迷を脱した用語でその研究の結論の再記述を行っている。
このようにして著者らは,例えば1例をあげるなら,ガザニガ(Gazzaniga)とル・ドゥー(Le Doux)が脳の2つの半球はそれぞれ独自に心を所有していると主張するうえで根拠とした交連切開術後の機能障害を記述し,この主張をメレオロジカル*な誤謬であるとしてしりぞけている。人間というものは,その一部分ではなく,1個の全体的存在としてのみ心を持ちうるというのである。次に著者らは,研究の諸結果を,脳梁を介しての神経信号の伝達は人間が視覚的に提示されたものを知るための必要条件であるというように,潤色のない言葉で再記述している。
さらにもう1つ別の例をあげるなら,側頭葉損傷患者の記憶力検査をもとに,多数の研究者が,記憶は過去の体験の神経的表象が海馬に貯蔵されることによると結論したが,ベネットとハッカーは,これには表象(representation)という概念についての誤用が含まれることを明らかにする。これまでの研究が明らかにしたことといえば,ある種の神経構造もしくはシナプス連結の力がなければ,人は,例えばヘースティングズの戦いの日付を思い出すことはできないだろうということにすぎない,と著者らは主張するのである。
このような研究諸結果のベネットとハッカーによる再記述に対して読者は最初,研究結果の持つすべての魅力を取り去って,いわば天然色ではなくモノクロームで表現したものだという印象を抱くかもしれない。しかし,実際には,これらの再記述は,そのような魅力よりも実体をはるかに正確に伝えるものであって,単に認知神経科学の物語の紹介にかかわるだけでなく,この科学の構想それ自体に重要な影響を及ぼすものなのである。
ベネットとハッカーによれば,神経生理学の研究者の陥りやすい誤謬は,論理的にいって動物全体にのみ帰すべき状態や活動を,脳の諸部分および脳の処理過程に帰着させてきた点にある。意識する,思考する,信じる,知覚する,仮定する,認識する,想起するといった心理学的属性を人間のある部分に帰着させるのは無意味だと著者らは主張するのである。
このような帰着のさせ方は,2つの異なる仕方で,説明の試みを挫折させる。一方で,それは,実際には何も説明されていないのにあたかも説明がなされたかのような幻想をもたらす。人間には自由に使える貯えられた表象があり,それが想起を可能にするという考えは,あらかじめ記憶というものを前提としており,それを説明することはできない。というのも,そのような記録をわれわれが利用することができたとしても,われわれはそれらをどのように読み取るべきかをやはり想起しなければならないからである。他方で,メレオロジカルな誤謬もまた,異なる神経経路で伝達された情報が統合された対象をどのようにして知覚することを動物に可能にするか(結合の問題)といった擬似問題にすぎない問いを生み出す。本書の批判的スタンスは,もとより神経科学的研究になんら脅威を及ぼすものではない。ただ,解答のありえない無用の問題を回避し,実験結果を逸脱する誇大宣伝を抑制しようとするものである。
この哲学と生理学との関係における歴史の背景には,ふたりの知的巨人が屹立している。アリストテレス(Aristotle)とデカルト(Descartes)である。生理学にアリストテレスがもたらした影響はきわめて望ましくないものであったし,デカルトがもたらした影響は非常に望ましいものであった。哲学では両者の立場はちょうど逆になる。脳の機能の多くをアリストテレスは誤って心臓に帰した。幸いガレノス(Galen)によって脳にその正常な位置が与えられるまでにそれほど長い時代を要さなかった。しかしデカルトのほうは神経生理学に実質的な貢献を果たしたのであって,ベネットの言葉を信じるなら,生物学的説明は作用因(efficient causation)の観点からなされなければならないというデカルトの主張は,17世紀以降の神経生理学上のすべての進歩の基盤となった。だがその一方で,デカルトの哲学的二元論は心の哲学を五里霧中の状態にさまよわせることになったので,その影響は長く尾を引き,現代に至っても唯物論者の中にはデカルト的自我(エゴ)を信じ,端的に自我というものを心ではなく脳と同一視する人々がいる。ベネットとハッカーは,アリストテレスの全体的存在としての人間(ユニタリ・ヒューマンビーイング)の概念に繰り返し言及しているが,この概念については近年ウィトゲンシュタイン(Wittgenstein)も重要な再記述を行っている。
本書では,神経生理学的研究の知見が,独特な,従来とは異なる視点から紹介されているが,これは,斬新な経験的探究や新しい実験的作業のゆえにそうなったのではなく,心と脳の間の関係を探るうえで不可欠の諸概念の論理言語学的分析の結果そうなったのである。このような探究の方式は多くの生理学者に馴染みのないものであろうが,これこそがこの研究プロジェクトに必須のツールなのである。「われわれの物語に教訓があるとすれば」とベネットとハッカーは述べている,「それは,神経科学者は自らの実験に注ぐのと同じくらい細心の注意を,概念の一貫性と明晰性を確保することにも注がなければならないということである」。
アンソニー・ケニー
大英学士院院長,1989~1993
* 訳注:mereology:部分と全体の形式論理的関係を研究する学問分野。
序
神経科学は,神経系の働きを解明し,その知識を,認知症や統合失調症などの病気による苛酷な苦難から人類を救済するための方策の設計に役立たせることをめざす。この課題を遂行するにあたって認知神経科学者はまた,脳の諸機能をも明らかにしようとする。われわれが知覚や記憶のような心理的機能を十分に果たしうるためには,脳が正常に機能するということが不可欠なのである。細胞神経科学者や分子神経科学者は,例えばニューロンとその軸索における活動電位の伝達にみられるメカニズムを研究し,この電位の変化がどのようにして軸索終末からシナプスで接合するニューロンへ伝達物質を放出するかを探究する(この主題の展開に関しては,Bennett, 2001参照)。認知神経科学者はとりわけ,シナプスの回路がどのように作動して脳におけるその機能を果たすかに関心を寄せる。それぞれ1万以上のシナプスを有する数千から数百万のニューロンからなるこのような回路網は,脳のさまざまな部位にみられるものであって,われわれが,例えば新しい出来事をおよそ1分間以上記憶にとどめ(海馬),視覚化できる(網膜と一次視覚野V1)ためには,それらが正常に機能していなければならない。
過去20年間,神経科学研究では海馬の作用のメカニズムが大きな焦点になってきた。海馬でみられるニューロンのタイプとそれらの空間的配置およびシナプス連結を最初に記載したのはラモニ・カハル(Ramon y Cajal)であった。海馬の機能を理解するためによく用いられるアプローチとして,この問題に対する工学的アプローチを踏まえながら,神経シナプス回路網の表象と考えられているものを開発するやり方がある。ブラインドリー(Brindley, 1967)は,海馬における,したがってそのシナプス回路網の表象における,ある種のシナプスは修正可能であると考えなければならないことを示唆した。彼がこの言葉で意味したのは,シナプスは軸索終末における活動電位の到達を受けてその特質を恒常的に変化させることができ,したがって海馬では「神経系の条件づけと記憶のメカニズムが修正可能なシナプスを用いて情報を貯蔵する」(p361)ということである。のちにマー(Marr, 1971)は,「古皮質(海馬)の最も重要な特性は,単一種類の記憶の課題を遂行する能力にある」(p23)と示唆した。さらに彼は,海馬の特定部位におけるシナプス連結のパターンは,もし興奮性シナプスの効力が修正可能であり,また大きなニューロンの膜電位がシナプス回路網の全体的活動を規制する抑制性介在ニューロンによって設定されているとすれば,自動連想記憶として機能しうることを明らかにした。工学的用語で組み立てられたマーの説は,きわめて大きな影響力を持った。例えば,海馬における神経回路網の表象がどのように作動するかについてのある報告では,「記憶の想起は,想起される記憶と重なり合う一定の組み合わせの錐体ニューロンの発火で始まり」,次いで「さまざまに異なる組み合わせの錐体ニューロンの発火が別個の同期的な歩調で起こり」,ついには貯蔵されたニューロンの記憶パターンが回復されることが示唆された(Bennett et al., 1994, p167)。
過去ほぼ半世紀にわたって,脳の各部分が神経回路網という工学的仕組みで説明されてきたが,それに伴って認知神経科学に1つの大きな動向が生じた。すなわち,通常ヒトが持つもの(場合によっては他の動物が持つもの)とされる心理学的属性を調べ,それらの属性を,複雑性と修正可能性がさまざまな度合いで異なる工学的仕組みで説明される以前ないしは以後の神経シナプス回路網に還元してとらえるという動向である。本書でわれわれは,脳内の特異的なシナプス回路網もしくは回路網の集合は,見ること(第1章),注意すること(第2章),想起すること(第3章),理解し,思考し,思考を言語に変換すること(第4章),情動を持つこと(第5章)が可能であるという主張を検証する。われわれのアプローチは,これらの考えの歴史的な発展を明らかにすることであり,また,それらを生み出すもととなったさまざまな実験結果の解釈を調べることによって,これらの考えがどのようにして認知神経科学の主流とみなされる専門領域に組み込まれるに至ったかを明らかにすることである。概念の分析を行うことによってわれわれは,例えば『すべての視覚行動は脳の提示する疑問への答えを探求する持続的過程とみなすことができる。網膜からの信号はこれらの答えを伝える「メッセージ」を構成する』(p119)とするJ・Z・ヤング(J.Z. Young, 1978)のような著名な神経科学者の解釈で何が誤っているかを明らかにできたと考える。ブレークモア(Blakemore, 1977)は,後頭極の視覚野皮質は「脳が知覚という仮説を組み立てる論拠となる」ニューロンを所有していると主張する(p91)。ゼキ(Zeki, 1999, p2056)は,われわれが色を見るためには,「脳が対象の物理的特性(それらの反射率)に対して与える解釈,つまり反射率の特性について速やかに知識を獲得することを脳に可能にする解釈」が必要であると論じている。ガザニガら(Gazzaniga et al., 2002)は,「右大脳半球は言語を理解することはできるが,統語法(シンタクス)を理解することはできない」とし,「右大脳半球の推理能力はきわめて限られている」(p414)と考えている。脳のシナプス回路網は心理学的属性を有しているという考えを精細に吟味するのが本書の中心的課題である。
われわれは先に上梓した共著『神経科学の哲学的基盤』において,最近の重要な神経科学理論,例えば知覚,記憶,情動に関する理論には概念上の問題があることを明らかにした。神経科学者と哲学者双方の意識の性質に関する最近の著作についても批判的評価を行った。本書が前共著『神経科学の哲学的基盤』と異なるのは,ここではわれわれが,ほぼ前世紀全体を通じて脳の機能と人間の心理学的属性との間の関係に関してさまざまな説を生むもととなった諸実験についての調査を紹介している点である(したがって多数の図解も用いた)。加えて本書は,われわれにとって,前共著に対してポール・チャーチランド(Paul Churchland),ダニエル・デネット(Daniel Dennett),ジョン・サール(John Searle)らの研究者から向けられた哲学的批判に,とりわけ脳と意識という主題(第7章)に関して,応答する機会ともなった。
認知神経科学者の実験的活動に前共著よりもはるかに詳しく言及した本書が,こうした研究者の関心と批判的反応を喚起することをわれわれは願っている。このようなやり方によって,哲学者の間だけでなく,神経科学者の間でも,われわれの心理学的能力の使用と関連づけて認知神経科学が脳の機能について何を明らかにできるかという問題をめぐって対話が可能になるであろう。哲学者と認知神経科学者双方の実験的観察およびその解釈についての持続的な批判的・分析的評価を通じて初めて,この主題は誇張を免れて真に実りあるものとなるであろう。
目次
開く
訳者 序
まえがき
序
カラーグラフ
第1章 知覚,感覚と皮質機能-ヘルムホルツからシンガーへ
1 錯視と認知科学者による解釈
2 視覚のゲシュタルト法則
3 分離脳交連切開術-2つの脳半球は独立して機能する
4 皮質ニューロンの特異性
5 視覚野皮質モジュールを連結する多様な経路
6 心像と表象
7 対象認識における経路の性質と位置および地図
8 「地図」という用語の誤用
9 結合の問題と40Hzの振動
10 心像と撮像法
第2章 注意,意識性と皮質機能-ヘルムホルツからポスナーへ
1 注意の概念
2 注意の精神物理学
3 注意の神経科学
4 注意と脳の構造の関係
5 結論
第3章 記憶と皮質機能-ミルナーからカンデルへ
1 記憶
2 記憶と知識
3 記憶の理解に対する神経科学の貢献
第4章 言語と皮質機能-ウェルニッケからレヴェルトへ
1 心理言語学と言語の神経解剖学
2 ウェルニッケ/リヒトハイム理論
3 心的辞書とそのユニット-トリースマン
4 言葉の認識と音読に関するモジュール研究-モートン
5 流暢発話のモジュール研究-レヴェルト
6 言語理解に関する機能的神経解剖学
7 発話に関する機能的神経解剖学
8 言語に関する心理言語学的説明を実証する機能的神経解剖学
第5章 情動と皮質・皮質下機能-ダーウィンからダマシオへ
1 はじめに
2 ダーウィン
3 情動の表出に関する認知理論と前認知理論
4 扁桃体
5 眼窩前頭皮質
6 神経回路網-視覚における扁桃体と眼窩前頭皮質
7 情動体験の起源
第6章 運動作用と皮質・脊髄機能-ガレノスからブローカおよびシェリントンへ
1 脳室学説-ガレノスからデカルトへ
2 皮質学説-ウィリスからデュ・プティへ
3 脊髄精神,脊髄共通感覚,および反射の概念
4 皮質における機能の局在
5 チャールズ・スコット・シェリントン-脊髄と大脳皮質におけるシナプスの統合作用
第7章 認知神経科学の概念的前提
1 概念の明晰化
2 2つのパラダイム-アリストテレスとデカルト
3 アリストテレスの原理とメレオロジカルな誤謬
4 メレオロジカルな誤謬は本当にメレオロジカルか
5 メレオロジカルの原理の理論的根拠
6 心理学的属性の局在
7 言語人類学,自動人類学,隠喩と敷衍的使用
8 クオリア
9 頭蓋に具現された脳
10 認知神経科学
文献
索引
まえがき
序
カラーグラフ
第1章 知覚,感覚と皮質機能-ヘルムホルツからシンガーへ
1 錯視と認知科学者による解釈
2 視覚のゲシュタルト法則
3 分離脳交連切開術-2つの脳半球は独立して機能する
4 皮質ニューロンの特異性
5 視覚野皮質モジュールを連結する多様な経路
6 心像と表象
7 対象認識における経路の性質と位置および地図
8 「地図」という用語の誤用
9 結合の問題と40Hzの振動
10 心像と撮像法
第2章 注意,意識性と皮質機能-ヘルムホルツからポスナーへ
1 注意の概念
2 注意の精神物理学
3 注意の神経科学
4 注意と脳の構造の関係
5 結論
第3章 記憶と皮質機能-ミルナーからカンデルへ
1 記憶
2 記憶と知識
3 記憶の理解に対する神経科学の貢献
第4章 言語と皮質機能-ウェルニッケからレヴェルトへ
1 心理言語学と言語の神経解剖学
2 ウェルニッケ/リヒトハイム理論
3 心的辞書とそのユニット-トリースマン
4 言葉の認識と音読に関するモジュール研究-モートン
5 流暢発話のモジュール研究-レヴェルト
6 言語理解に関する機能的神経解剖学
7 発話に関する機能的神経解剖学
8 言語に関する心理言語学的説明を実証する機能的神経解剖学
第5章 情動と皮質・皮質下機能-ダーウィンからダマシオへ
1 はじめに
2 ダーウィン
3 情動の表出に関する認知理論と前認知理論
4 扁桃体
5 眼窩前頭皮質
6 神経回路網-視覚における扁桃体と眼窩前頭皮質
7 情動体験の起源
第6章 運動作用と皮質・脊髄機能-ガレノスからブローカおよびシェリントンへ
1 脳室学説-ガレノスからデカルトへ
2 皮質学説-ウィリスからデュ・プティへ
3 脊髄精神,脊髄共通感覚,および反射の概念
4 皮質における機能の局在
5 チャールズ・スコット・シェリントン-脊髄と大脳皮質におけるシナプスの統合作用
第7章 認知神経科学の概念的前提
1 概念の明晰化
2 2つのパラダイム-アリストテレスとデカルト
3 アリストテレスの原理とメレオロジカルな誤謬
4 メレオロジカルな誤謬は本当にメレオロジカルか
5 メレオロジカルの原理の理論的根拠
6 心理学的属性の局在
7 言語人類学,自動人類学,隠喩と敷衍的使用
8 クオリア
9 頭蓋に具現された脳
10 認知神経科学
文献
索引
書評
開く
型破りな脳科学の入門書
書評者: 酒井 邦嘉 (東大大学院准教授・言語脳科学)
型破りな脳科学の入門書である。本の帯には,「脳研究の常識への挑戦状!」とある。確かに,原題の“History of Cognitive Neuroscience”(認知神経科学の歴史)からは想像もつかない,過激な本であると私も思う。それ故,類書にない面白さがこの本にはある。同時に,本気で自分の脳を使って,脳という奥深い書物を「繙く(ひもとく)」ことを読者に強要せずにはいられない本でもある。一読をお勧めしたい。
本書の構想は,「脳科学全体にわたる主要な研究を網羅的に取り上げ,整理し,研究内容を歴史的に位置付け,批判的に考察する」というものである。その一方で,巷ではちょっと不思議にも思えるくらいもてはやされてきた用語である「ワーキング・メモリー(作動記憶)」に関してはたった1か所,「ミラー・ニューロン」に至っては全く記述や議論がみられない。どちらの概念に対しても,特に言語への安易な適用に対して常に懐疑的な私には,むしろこれは適切な判断であると言えるのであるが,もしもこれらの点について徹底的に議論してもらえたら,盲信されている概念に対する多くの誤解が解けたことであろう。
本書は,最終章の「認知神経科学の概念的前提」を除けば,すべての章に「ヘルムホルツからシンガーへ」といった具合に,そのテーマに貢献した有名な研究者の始点と終点を示す副題が添えられている。しかし,「○○へ」という側に置かれた現代の神経科学者は,「○○から」という側の往年の科学者を上回る貢献をしたとは,残念ながら思えないのである。そのような比較が容易にはできないくらい,ヘルムホルツやウェルニッケは偉かったのである。脳神経科学の歴史において,その未来を信じ,そして今なおその進むべき道を照らし続けているのだから。
本書の内容に少し踏み込むと,「歩くあるいは話すといった後天的能力」(p. 115)というように,人間の本能に対して誤解を招く記述もみられる一方で,ダプレットとブックハイマーのfMRI実験に対する批判(pp. 192-196)は,正鵠を射ている。また,私自身の主張を取り上げてこき下ろしている部分(pp. 149-151)は,残念ながら根本的な誤謬に満ちている。むしろ,そんな危険を冒してまで脳科学のテーゼに斬り込んでいった勇気を讃えるべきであろう。
著者たちは,「神経科学者は自らの実験に注ぐのと同じくらい細心の注意を,概念の一貫性と明晰性を確保することにも注がなければならない」と述べている。しかし,私はそうは考えない。物理学の世界では,「熱」という概念の本質については何ら考察することなく,「熱力学」という厳然たる理論体系が成立し得るのだ〔W・パウリ(著),田中實(訳)『熱力学と気体分子運動論』(講談社,1976)を見よ〕。一つの学問領域の中に,一貫していなかったり明晰でなかったりする概念が紛れ込んでくるのは,やむを得ないことであり,むしろその健全な発展の一過程を示すものでもある。それまでは予想もつかなかった角度から,その現象の本質的な意味が見いだされて初めて,「概念」というものは科学者に雄弁にその本質を語り始める。脳神経科学はまだその段階に達していないのだから,過信はむしろ禁物であろう。今の神経科学に必要なことは,ただ一つのみ。証明も反証もできないような概念化をしたり,それを批判したりする暇があったら,何か新しい実験をすべきなのだ。
こんな本を読みたかった!
書評者: 村井 俊哉 (京大教授・精神医学)
「こんな本は読んだことがありません」と,訳者の河村満教授は序文で述べています。私もまったく同意見ですが,さらに「こんな本を読みたかった!」と付け加えたいと思います。
原書タイトルの“History of Cognitive Neuroscience”や,目次を眺めただけでは,認知神経科学の主要な発展が網羅的に整理されている百科事典的な書物を想像してしまいそうになります。そんな本ならおそらく他にいくつも出版されているでしょう。本書も確かに情報量は豊富ですが,アンソニー・ケニーのまえがきにも記されているように,この本の狙いは,網羅的知識の提供とはまったく別のところにあります。
本書では,認知神経科学の歴史上の主要な業績・仮説が順に紹介されていきますが,そのような業績に対する賛否両論の併記という穏便な方法をとらず,本書の著者,マックス・ベネットとピーター・ハッカーは,なんらの遠慮・躊躇もなく,古今の学説の矛盾点を批判していきます。どうして彼らにそのような思い切ったことができたのでしょうか?
それは著者らが,明晰で一貫した「概念分析」という方法論に立脚し,その統一的視点で,本書を書き上げたからなのです。彼らの方法は,分析哲学の文献になじみのない読者にとっては,最初は何をめざしているのかわかりづらいかもしれません。しかし,著者らが立脚している方法は,哲学についての特別な知識を必要としない,筋道立ったものの考え方です。論理的にものごとを考える力と,論理的にものごとを考えることを楽しめる知的センスを備えた読者であれば,しばらく読み進めるうちに著者らの視点を共有し,最後には,この本で最も難解な最終章の議論にもついていくことができるでしょう。
その最終章は,著者らの見解に対するダニエル・デネット,ジョン・サール,ポール・チャーチランドからの批判への再反論で構成されています。現代の「こころの哲学」を代表するこの3名への再反論は,この本で最も刺激的な部分です。私自身はフォーク・サイコロジー(常識心理学)の用語を従来の意味からあえて逸脱して用いるデネットらに共感しており,自分自身も「脳が記憶し,思考し,判断する」といった言い回しを意図的に用いることがあります。しかし,そのような言い回しを「メレオロジカルな誤謬(全体と部分を取り違える誤謬)」として批判するベネットとハッカーの批判は極めて強力です。「こんな議論が聞きたかった!」と思い,また,できればこの本を多くの読者に読んでいただき,共にこういう議論ができる人たちが増えてくれるのを願います。
脳の中には,世界を映しだす鏡があり,それを見ている小人(ホムンクルス)がいる。このようなイメージで脳について考えることは,古めかしい愚かなことだ,とこの領域にかかわる研究者の多くは,自信を持って答えるでしょう。しかし,ホムンクルスのイメージはあまりに強力で,私たち研究者は,いつの間にか無意識のうちに,その誤謬に自らの言説を汚染されてしまっているのかもしれません。
本書の性格上,確実に意味が追える翻訳が極めて重要になりますが,正確な意味を原書で確認してみようなどという気がまったく起きないほど訳文は信頼でき,訳者には心より敬意と感謝の意を表したいと思います。
書評者: 酒井 邦嘉 (東大大学院准教授・言語脳科学)
型破りな脳科学の入門書である。本の帯には,「脳研究の常識への挑戦状!」とある。確かに,原題の“History of Cognitive Neuroscience”(認知神経科学の歴史)からは想像もつかない,過激な本であると私も思う。それ故,類書にない面白さがこの本にはある。同時に,本気で自分の脳を使って,脳という奥深い書物を「繙く(ひもとく)」ことを読者に強要せずにはいられない本でもある。一読をお勧めしたい。
本書の構想は,「脳科学全体にわたる主要な研究を網羅的に取り上げ,整理し,研究内容を歴史的に位置付け,批判的に考察する」というものである。その一方で,巷ではちょっと不思議にも思えるくらいもてはやされてきた用語である「ワーキング・メモリー(作動記憶)」に関してはたった1か所,「ミラー・ニューロン」に至っては全く記述や議論がみられない。どちらの概念に対しても,特に言語への安易な適用に対して常に懐疑的な私には,むしろこれは適切な判断であると言えるのであるが,もしもこれらの点について徹底的に議論してもらえたら,盲信されている概念に対する多くの誤解が解けたことであろう。
本書は,最終章の「認知神経科学の概念的前提」を除けば,すべての章に「ヘルムホルツからシンガーへ」といった具合に,そのテーマに貢献した有名な研究者の始点と終点を示す副題が添えられている。しかし,「○○へ」という側に置かれた現代の神経科学者は,「○○から」という側の往年の科学者を上回る貢献をしたとは,残念ながら思えないのである。そのような比較が容易にはできないくらい,ヘルムホルツやウェルニッケは偉かったのである。脳神経科学の歴史において,その未来を信じ,そして今なおその進むべき道を照らし続けているのだから。
本書の内容に少し踏み込むと,「歩くあるいは話すといった後天的能力」(p. 115)というように,人間の本能に対して誤解を招く記述もみられる一方で,ダプレットとブックハイマーのfMRI実験に対する批判(pp. 192-196)は,正鵠を射ている。また,私自身の主張を取り上げてこき下ろしている部分(pp. 149-151)は,残念ながら根本的な誤謬に満ちている。むしろ,そんな危険を冒してまで脳科学のテーゼに斬り込んでいった勇気を讃えるべきであろう。
著者たちは,「神経科学者は自らの実験に注ぐのと同じくらい細心の注意を,概念の一貫性と明晰性を確保することにも注がなければならない」と述べている。しかし,私はそうは考えない。物理学の世界では,「熱」という概念の本質については何ら考察することなく,「熱力学」という厳然たる理論体系が成立し得るのだ〔W・パウリ(著),田中實(訳)『熱力学と気体分子運動論』(講談社,1976)を見よ〕。一つの学問領域の中に,一貫していなかったり明晰でなかったりする概念が紛れ込んでくるのは,やむを得ないことであり,むしろその健全な発展の一過程を示すものでもある。それまでは予想もつかなかった角度から,その現象の本質的な意味が見いだされて初めて,「概念」というものは科学者に雄弁にその本質を語り始める。脳神経科学はまだその段階に達していないのだから,過信はむしろ禁物であろう。今の神経科学に必要なことは,ただ一つのみ。証明も反証もできないような概念化をしたり,それを批判したりする暇があったら,何か新しい実験をすべきなのだ。
こんな本を読みたかった!
書評者: 村井 俊哉 (京大教授・精神医学)
「こんな本は読んだことがありません」と,訳者の河村満教授は序文で述べています。私もまったく同意見ですが,さらに「こんな本を読みたかった!」と付け加えたいと思います。
原書タイトルの“History of Cognitive Neuroscience”や,目次を眺めただけでは,認知神経科学の主要な発展が網羅的に整理されている百科事典的な書物を想像してしまいそうになります。そんな本ならおそらく他にいくつも出版されているでしょう。本書も確かに情報量は豊富ですが,アンソニー・ケニーのまえがきにも記されているように,この本の狙いは,網羅的知識の提供とはまったく別のところにあります。
本書では,認知神経科学の歴史上の主要な業績・仮説が順に紹介されていきますが,そのような業績に対する賛否両論の併記という穏便な方法をとらず,本書の著者,マックス・ベネットとピーター・ハッカーは,なんらの遠慮・躊躇もなく,古今の学説の矛盾点を批判していきます。どうして彼らにそのような思い切ったことができたのでしょうか?
それは著者らが,明晰で一貫した「概念分析」という方法論に立脚し,その統一的視点で,本書を書き上げたからなのです。彼らの方法は,分析哲学の文献になじみのない読者にとっては,最初は何をめざしているのかわかりづらいかもしれません。しかし,著者らが立脚している方法は,哲学についての特別な知識を必要としない,筋道立ったものの考え方です。論理的にものごとを考える力と,論理的にものごとを考えることを楽しめる知的センスを備えた読者であれば,しばらく読み進めるうちに著者らの視点を共有し,最後には,この本で最も難解な最終章の議論にもついていくことができるでしょう。
その最終章は,著者らの見解に対するダニエル・デネット,ジョン・サール,ポール・チャーチランドからの批判への再反論で構成されています。現代の「こころの哲学」を代表するこの3名への再反論は,この本で最も刺激的な部分です。私自身はフォーク・サイコロジー(常識心理学)の用語を従来の意味からあえて逸脱して用いるデネットらに共感しており,自分自身も「脳が記憶し,思考し,判断する」といった言い回しを意図的に用いることがあります。しかし,そのような言い回しを「メレオロジカルな誤謬(全体と部分を取り違える誤謬)」として批判するベネットとハッカーの批判は極めて強力です。「こんな議論が聞きたかった!」と思い,また,できればこの本を多くの読者に読んでいただき,共にこういう議論ができる人たちが増えてくれるのを願います。
脳の中には,世界を映しだす鏡があり,それを見ている小人(ホムンクルス)がいる。このようなイメージで脳について考えることは,古めかしい愚かなことだ,とこの領域にかかわる研究者の多くは,自信を持って答えるでしょう。しかし,ホムンクルスのイメージはあまりに強力で,私たち研究者は,いつの間にか無意識のうちに,その誤謬に自らの言説を汚染されてしまっているのかもしれません。
本書の性格上,確実に意味が追える翻訳が極めて重要になりますが,正確な意味を原書で確認してみようなどという気がまったく起きないほど訳文は信頼でき,訳者には心より敬意と感謝の意を表したいと思います。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。