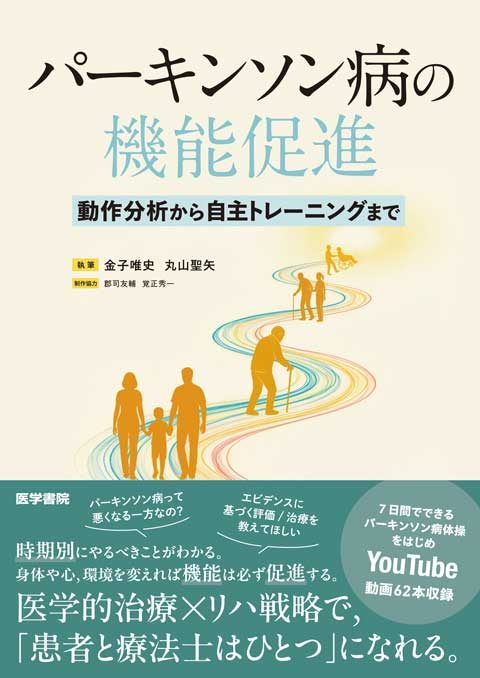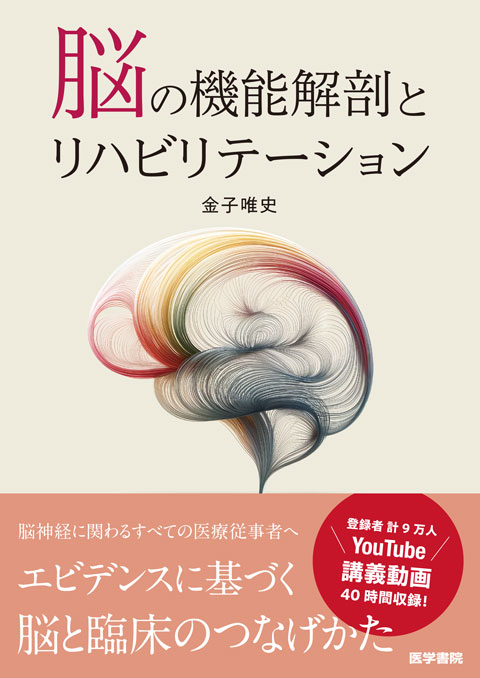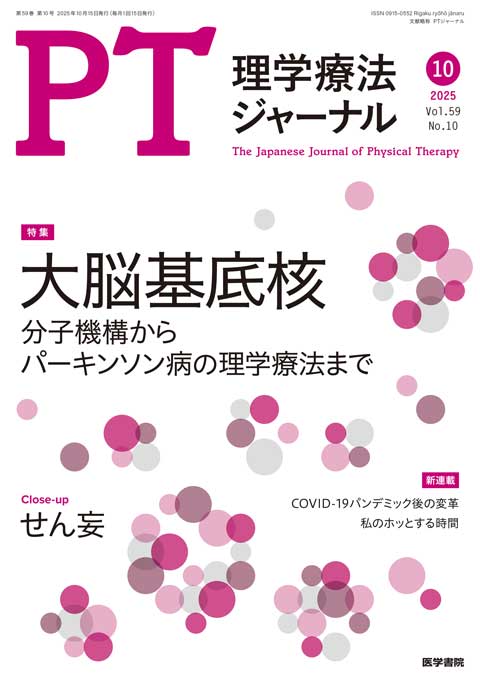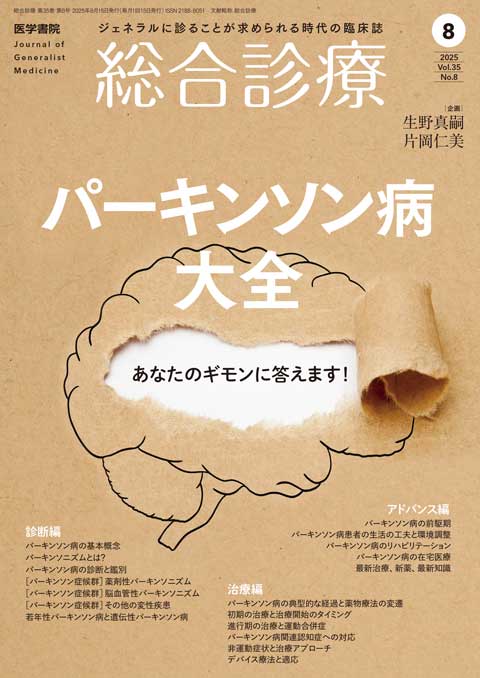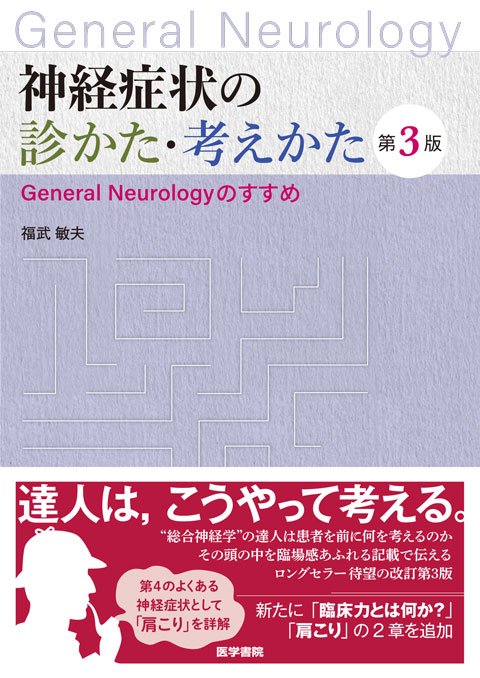パーキンソン病の機能促進
動作分析から自主トレーニングまで
パーキンソン病の対象者に向けて「時期別」に療法士ができること全部
もっと見る
有病者が多い進行性の難病であるパーキンソン病。専門的な知識を有するリハビリテーション療法士が益々求められるなか最適な実用ガイドが登場。病気の進行時期に応じた最新知見と具体的アプローチ法を提示。エビデンスに基づいた運動療法から生活管理法まで幅広くサポート。パーキンソン病体操をはじめとしたYouTube動画とリンクするなど患者家族が参考になる情報も多数収録。患者と療法士が一体となり機能を促進できる。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はじめに
忘れがたい光景があります.新人療法士として順天堂大学医学部附属順天堂医院の門を叩いてから間もない,20年前のことです.
私が担当したMさんは,ジスキネジア(不随意運動)が激しく,ご自身の意思とは裏腹に,身体が絶えず波のように揺れ動き,寝返りもままならない状態でした.なす術もない私の前で,当時の技師長はMさんの身体にそっと触れ,1枚のシーツを用いて,驚くほど繊細な感覚入力を始めました.すると,荒れていた波が凪ぐようにMさんの動きが次第に治まり,ベッドサイドをご自身の足で数歩,確かに踏み出したのです.その後の薬物調整でも目覚ましい効果を上げ,Mさんはご自宅の中を見守りで歩けるまでに回復されました.
「難病」「進行性」──その重い言葉によって閉ざされていた未来に,確かな光が差し込み,希望という名の余白が生まれた瞬間でした.「介入次第で,機能は促進できる」「身体は,変わることができる」.この驚きと感動が,私の臨床家としての揺るぎない土台となっています.本書が目指すのは,まさにあの日のような「現実が変わる一手」を必要とするすべての人の手に届けることです.
パーキンソン病とともに生きる方は,日本に約29万人,診断に至らない方々を含めれば,その数はさらに増えるといわれています.これほど多くいるにもかかわらず,リハビリテーションの現場では「機能維持」や「環境調整」が目標の中心となり,本来もつ可能性に蓋がされてしまうことが少なくありません.国家試験で学ぶ「4大徴候」の知識だけでは,目の前の1人ひとりがもつ複雑で多様な現実には,到底太刀打ちできないのです.
こうした状況を変えたい一心で,私たち STROKE LABでは,最新の学術研究と臨床現場の知見を束ね,記録し,検証を重ねてきました.
本書の企画から5年.症例の検討,動画の制作,パーキンソン病体操の検証,その1つひとつの積み重ねが,ようやくこの1冊へと結実したといえます.この道のりには,共著者である丸山聖矢氏の存在が不可欠でした.私が文献と経験から抽出した専門的介入という原石を,彼がもつ「誰もが理解できる言葉で体系化する力」によって磨き上げ,両者を滑らかに融合させてくれたのです.
本書は,非運動症状が中心の時期から,進行の各段階に応じて戦略を更新できるよう,「時期別」に構成されています.ページを開けば,今日から臨床で使える具体的な手立ての多さと,動作分析・介入の深さを専門職の皆様にも実感していただけるはずです.本書が果たすべきは,患者さん・ご家族・療法士というチームが,同じ地図と羅針盤を手にし,同じ未来をみることのできる道標となることです.
最後に,本書の編集に携わってくださった医学書院の北條立人氏に深く感謝申し上げます.デザイン制作をご支援いただいた郡司友輔氏,覚正秀一氏,パーキンソン病体操企画をサポートしてくださった石井 俊氏,編集をサポートしてくださった西坂拳史朗氏,嘉数匡晃氏,中村謙志氏,片平雄大氏,山川翔太郎氏にも心より御礼申し上げます.
本書が,現場の「明日の一歩」を少しでも軽くしますように.
2025年10月
STROKE LAB 代表取締役 金子唯史
目次
開く
1 パーキンソン病の基礎知識
ゼロから知る! 症状進行の全体像
過去からの学びと洞察
障害の程度を把握する
パーキンソニズムとの違い
遺伝や環境は関係するのか?
ドーパミン作動性ニューロンとは?
薬物療法の進歩
外科的治療──脳深部刺激療法(DBS)を理解する
非侵襲的治療
リハビリテーションの効果
未来への展望
大脳皮質-基底核ループ
3つの大脳皮質-基底核ループ
引用文献
2 パーキンソン病の診断の流れ
おおまかな診断の流れ
画像診断をもう少し詳しく知りたい
診断基準をもう少し詳しく知りたい
引用文献
3 時期別の症状/運動前症状(前駆症状)
日中の症状だけではない! 睡眠障害を理解する
便秘症状とパーキンソン病との関係を理解する
精神面にも注意! うつ病・気分症を理解する
においがなくなる!? 嗅覚障害を理解する
むずむず脚症候群を理解する
引用文献
4 時期別の症状/初期症状
疲労の問題を理解する
感覚障害を理解する
疼痛を理解する
アパシーを理解する
ジストニアを理解する
固縮を理解する
振戦を理解する
寡動・無動を理解する
仮面様顔貌を理解する
引用文献
5 時期別の症状/中期症状
排尿障害を理解する
起立性低血圧を理解する
サルコペニアを理解する
ジスキネジアを理解する
認知機能障害を理解する
遂行機能障害を理解する
視空間処理を理解する
幻覚・妄想を理解する
注意障害を理解する
引用文献
6 時期別の症状/後期症状
姿勢異常を理解する
運動障害性構音障害を理解する
嚥下障害を理解する
姿勢不安定性を理解する
引用文献
7 動作分析
寝返り・起き上がりの問題
立ち上がりの問題
上肢のリーチの問題
把握の問題
歩行戦略
引用文献
8 症状から学ぶ
腰痛が改善し,長距離歩行が可能に!
ピサ徴候の改善とともに腕の振りも改善!
すくみ足が改善し,歩きがスムーズに!
転倒恐怖感が軽減し,腰痛も改善!
歩行スピードが2倍に変化!
着替えの時間が大幅に短縮!
脳血管性パーキンソニズムの歩行改善
引用文献
9 STROKE LAB式 パーキンソン病体操
バランストレーニング
筋力トレーニング
柔軟トレーニング
四つ這いトレーニング
歩行トレーニング
嚥下・表情筋トレーニング
姿勢変換トレーニング
ピーナッツボール体操──上肢編
ピーナッツボール体操──下肢編
引用文献
10 評価
診断基準を理解する
4大徴候の評価
統一パーキンソン病評価尺度(UPDRS)
MDS-UPDRS
Timed Up and Go Test(TUG)
Freezing of Gait Questionnaire(FOG-Q)
Falls Efficacy Scale International(FES-I)
Mini-Balance Evaluation Systems Test(Mini-BESTest)
Berg Balance Scale(BBS)
6-min walk test(6MWT):6分間歩行テスト
10-m walk test(10MWT):10m歩行テスト
Parkinson's Disease Questionnaire-39(PDQ-39)
EuroQol 5-dimensions 5-levels(EQ-5D-5L)
16-item Parkinson’s Fatigue Scale(PFS-16)
Parkinson's Disease Sleep Scale-2(PDSS-2)
Parkinson's Disease-Cognitive Rating Scale(PD-CRS)
Montreal Cognitive Assessment(MoCA)
各種の嚥下評価(MWST/MDT-PD/SDQ/FEES/VFSS)
肩関節の評価
引用文献
11 お役立ちアイディア
介助方法を理解する
栄養管理のポイント
オメガ脂肪酸の役割を理解する
蛋白質は味方になる?
ビタミンは摂取すべきか?
ミネラルの力
公的支援制度を理解する
マインドフルネスを理解する
楽々クッキング!
楽しくショッピング!
安全な自宅内での生活
快適な入浴と排泄
運動イメージの重要性
引用文献
索引