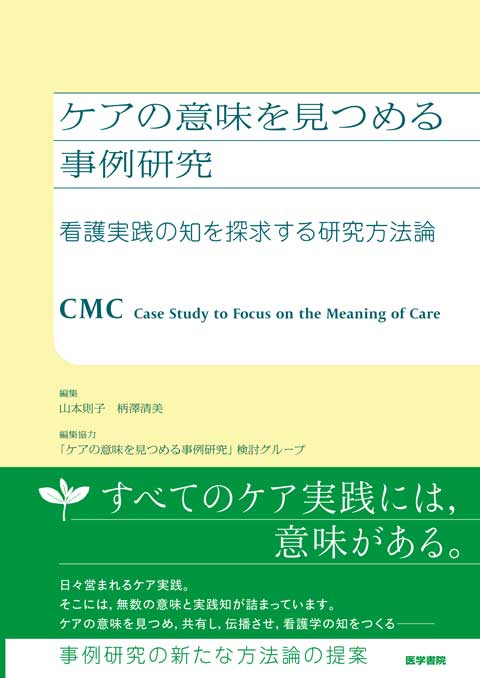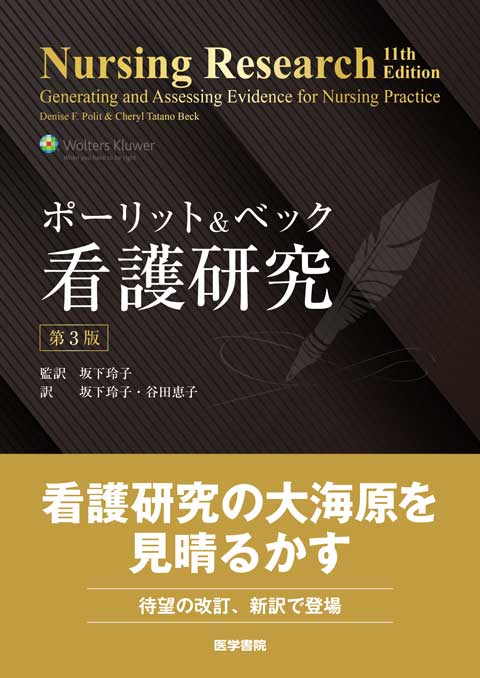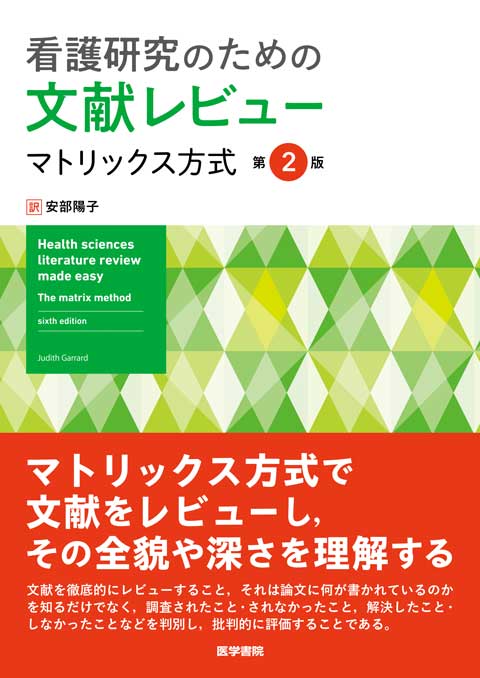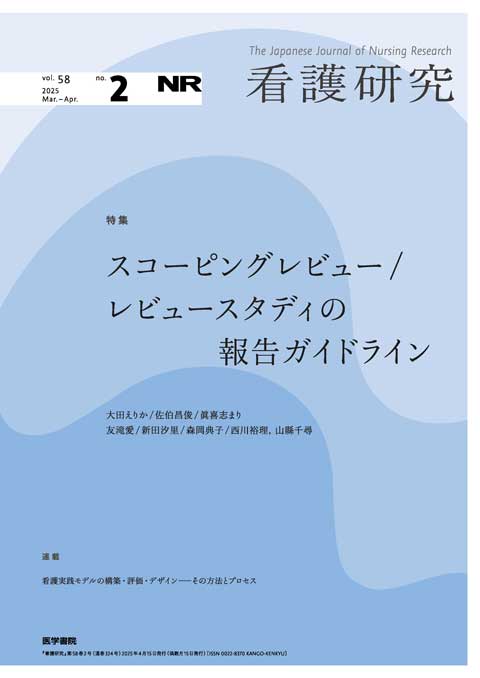ケアの意味を見つめる事例研究
看護実践の知を探求する研究方法論
看護職者必携! 日々の看護実践の知を明らかにする事例研究の新たな方法論の提案
もっと見る
現場で営まれるケア実践は、ナースの技と知が詰まった宝の山。しかし多忙な現場では、その知は暗黙知のまま日々の中に埋もれがちです。本書は、そうした実践知を独自の研究方法論により可視化して広く共有し、その知を看護学に位置づける道しるべです。研究するのはナース自身。ナースによるナースのための研究方法論です。自身の実践の意味を明らかにしたい。多くの実践から学んで活かしたい。その願いを叶える1冊です!
| 編集 | 山本 則子 / 柄澤 清美 |
|---|---|
| 編集協力 | 「ケアの意味を見つめる事例研究」 検討グループ |
| 発行 | 2025年03月判型:B5頁:224 |
| ISBN | 978-4-260-05711-0 |
| 定価 | 3,300円 (本体3,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
本書は,「ケアの知」を共有可能にするための過去12年ほどの活動の集大成です.ですが,この取り組みは「ケアの意味を見つめる事例研究(Case Study to Focus on the Meaning of Care:CMC)」検討グループメンバーそれぞれが,ケアのもつ「人を動かす力」,ケアのやりとりを通じてケア実践者とケアの受け手の双方が変容してゆく姿に驚き,すぐれたケアの営みの価値をぜひ共有したいと願ったときから始まっていたともいえます.事例研究方法を開発するぞ,という強い決意というよりは,日ごろの意識の底辺を流れるかすかな思いに動かされ,事例研究に取り組んだことがきっかけになりました.その事例研究の取り組みは,予想を超える多くの方々──看護職をはじめケアに日々取り組んでいる方々や,看護・ケアをとても大切に思っている研究者の皆さん──の共感をいただきました.そこからは,CMCを大事に思ってくださる方々の言葉に突き動かされ,自ら関心をもち集まってきた人たちでできた検討グループの力で,CMCは徐々に形になってきました.
そのようなわけですので,この本は,まずなによりも,看護をはじめとするケアの実践をとても大事に思っている方々に向けて書かれています.ケアは,少子超高齢社会,多死時代を迎えた現代および今後の社会にとって,最も大切な営みの1つだと思います.にもかかわらず,ご自身の実践の価値に気づかないまま日々の仕事に追われる方々,自分のケアに満足できないけれど何をどう学んだらよいかわからない方々が,とても多いように思われます.そのようなケアの実践者の皆さんに,自分たちのケアの素晴らしさに気づき,その素晴らしいケアを,周囲の同僚,後輩や,ケアの受け手である方々にも共有可能な形で表してほしいと思って本書を書きました.そうすることで,自分のケア実践に自信と誇りをもって,ケアの仕事をしていきましょう,というメッセージでもあります.
一方,素晴らしいケアの姿に導かれてCMCを進め,学会誌への投稿と査読の経験を重ねていくうちに,自分たちがとても大きなチャレンジをせざるを得ないことに気づき始めました.CMCは,特にケア実践の学問領域に関わる研究者の皆さんに,科学のあり方そのものを見直そうと主張しています.それは,開発グループの個人的な信念や思いなどではなく,私たちが共有したいと願うケア実践自体が,そのように主張してくるのです.ケア実践が私たちの学問の中心的な関心である以上,いつかは実証主義科学を偏重するあり方を変更しなければなりません.これは,世界全体がこれまでの実証主義科学による発展の限界を実感している現代においては,ケア実践のみならず他の多くの学問領域でも不可避なことであり,その端緒はすでにあちこちでみられてもいます.ですが,ケアを実践する私たちだからこそ,科学の進化の必要性にいち早く気づき,新たな研究方法を探求し,他領域の方々に紹介できるようにも思います.
本書の構成と主な読者対象
本書は,私たちが開発に取り組んできたCMCの方法に基づいて,ケア実践の事例研究に取り組むことに関心をもつ人たち(ケア実践者や研究者など)と,事例研究論文の査読にあたる人たちを第一の読者として想定しています.本書の構成は,以下の通りです.
第1部 「ケアの意味を見つめる事例研究」とは──どう生まれたか 何をめざしているか
・1章 すぐれた実践を共有可能にする
CMC開発の経緯と,CMCの考え方について説明します.CMCが何を目的・ゴールにしているのか,という根本の部分をまず理解していただけると,なぜこのような方法をとらなければならないと私たちが考えるのかがわかり,CMCを研究方法として使っていただきやすいと思います.
第2部 「ケアの意味を見つめる事例研究」の進め方
・2章 「ケアの意味を見つめる事例研究」にとりかかる
CMCを始めるのはどんなときか,どんなケア実践事例を選ぶか,どのようなチームでCMCに取り組むかなど,CMCを始める準備に関して解説します.
・3章 意識化/言語化
CMCの第一歩として,自分のケア実践について振り返り,意識化し,それを言語化するプロセスについて解説します.
・4章 メタファー化
CMCの特徴であるメタファーを用いたケア実践のキャッチコピー創り,「見出し」創りから,ケア実践をまとめて可視化する「表」創りまでを解説します.「表」ができれば,学会発表はすぐそこです.この章では,ポスターを中心とした学会発表までの道のりについても解説します.
・5章 再ナラティブ化(文章化)
CMCらしい論文の書き方について解説します.CMCの論文形式は,これまでの実証的な研究論文とはかなり様相が異なります.
・6章 研究計画書の作成と倫理的配慮
CMCを行う際の研究計画書の書き方と,倫理審査の申請書の書き方をまとめています.個別事例を扱うCMCでは,倫理的配慮が特に重要で,いまなお私たちも詳細に検討を進めています.
第3部 「ケアの意味を見つめる事例研究」の学術性
・7章 「ケアの意味を見つめる事例研究」の学術性と査読
論文が書けたら,学会誌への投稿が次のステップです.CMCの学術性については,査読の過程で様々な意見を得ます.本章では,査読に対応するために,CMCの学術性とはどのようなものかについて,私たちの考えを述べています.特にCMC論文を査読される人たちにはぜひ読んでもらいたい章です.
・8章 看護学と科学と普遍性
CMC検討グループのメンバーである2人の哲学研究者が,検討グループでこれまでに積み重ねてきた討議をもとに,看護学と科学について検討した内容を報告します.哲学分野の用語が多く使われているので,少し読みにくく感じるかもしれません.しかし,ケア実践に資する学術的視点について考えるうえで非常に重要なので,ぜひご一読ください.
第4部 「ケアの意味を見つめる事例研究」の活用と展開
・9章 「ケアの意味を見つめる事例研究」を現場で使う
最後の章では,CMCに実際に取り組んだ感想や,現場での様々な活用の事例を紹介します.「CMCに取り組んでみたいけれど,できるかな?」と不安に思う方や,実際に取り組んだ経験について知りたい方は,まず最初にこの章からお読みいただけるとよいかもしれません.
CMCが,ケア実践事例を通じて「ケアの知」を多くの皆さんと共有するためのツールとなること,そのような取り組みがケアの世界をより元気にしてゆくこと,
そしてこれからのケア実践の科学のあり方を見直すきっかけになることを,執筆者一同心より願っています.
ここに至るまでにお世話になりました多くの方々に感謝して,皆さんに本書をお届けします.できることならば多くの方のご意見・ご教示をいただき,さらなる進化をめざしたいと思います.なにとぞよろしくお願い申し上げます.
2025年2月
編集 山本則子
目次
開く
第1部 「ケアの意味を見つめる事例研究」とは──どう生まれたか 何をめざしているか
1章 すぐれた実践を共有可能にする──「ケアの意味を見つめる事例研究」の挑戦
「ケアの意味を見つめる事例研究」にたどりつくまで
ケア実践の知はどのようなものか
共有可能な実践知を生むための事例研究のポイント
「ケアの意味を見つめる事例研究」のアウトライン
「ケアの意味を見つめる事例研究」の3つの特徴
「ケアの意味を見つめる事例研究」の方法論的背景
「ケアの意味を見つめる事例研究」の学術性──「厳密性」とは
第2部 「ケアの意味を見つめる事例研究」の進め方
2章 「ケアの意味を見つめる事例研究」にとりかかる
事例研究を始めるのはどんなときか
どんな実践事例を選ぶか──いくつかの前提条件
取り上げる事例の特徴とポイント
事例研究はチームを組んで進める
3章 意識化/言語化──ワークシートの記述と「問われ語り」
意識化/言語化のプロセス──データとなる事例の記述の第一歩
「問われ語り」の実施──ワークシートを充実させ,データとなる記述を厚くする
4章 メタファー化──キャッチコピー創りから「見出し」創り,「表」創りを経て学会発表へ
「ケアの意味を見つめる」ことに「メタファー」を利用する
実践の意味を見つめキャッチコピーで表してみる
「見出し」創りから「表」創りへ──「大見出し」「小見出し」と実践の往還から事例の全体像を構築する
「表」が完成したら学術集会で発表しよう
5章 再ナラティブ化(文章化)──事例研究論文を執筆する
論文の構成と執筆の方法・注意点
緒言(はじめに)
方法
結果
考察
論文の投稿
論文を書くためのTips
まとめ
6章 研究計画書の作成と倫理的配慮
研究計画書の構成
研究計画書作成の意義
倫理的配慮
第3部 「ケアの意味を見つめる事例研究」の学術性
7章 「ケアの意味を見つめる事例研究」の学術性と査読
「ケアの意味を見つめる事例研究」論文の位置づけ
看護実践の事例研究の学術性
おわりに
8章 看護学と科学と普遍性──「ケアの意味を見つめる事例研究」から考えるケアの知
看護学と科学
看護に求められる知「フロネーシス」
「ケアの意味を見つめる事例研究」の普遍性
事例研究の「普遍性」について──河合の事例研究論から
実践を読むことの現象学的解明──鯨岡の「エピソード記述」の論述に基づいて
物語について──ブルーナーの議論から
事例記述の方法について
まとめと課題
第4部 「ケアの意味を見つめる事例研究」の活用と展開
9章 「ケアの意味を見つめる事例研究」を現場で使う
CMCに取り組んだ経験
1.「見えた」「伝わった」私たちの看護
2.事例研究の出会いからチャレンジまで
──小さな看護実践に光を当ててその意味を見つめたこと
3.事例研究を通して自分の中にコアとなる看護観を見出す
4.実践を論文にまとめることの醍醐味
組織でCMCを使う
1.事例検討から始める事例研究──ラダー研修(さいたま赤十字病院)
2. 専門看護師による事例研究(東京女子医科大学)
3. 退院カンファレンスにおける活用(台東区立台東病院)
4. 訪問看護における活用(ケアプロ訪問看護ステーション東京)
あとがき
索引
COLUMN
ワークシートへの記述の例
よい「問い手」になるために
書評
開く
現代医療への新しいアプローチとなる画期的な書
藤沼 康樹(医療福祉生協連家庭医療学開発センター長)
◆医師の症例報告と看護の事例研究へ
医師にとって「事例研究」といえば,これまで客観的な症例報告が主流であった。医学的に興味深い症例について事実を淡々と記述し,担当医の感情や意思決定過程,患者とのやりとりなどは「主観的で普遍性がない」として排除されてきた。
しかし近年,総合診療や家庭医療の専門医認定では状況が変わりつつある。医師自身がどのように意思決定したか,チームはどう連携したか,自分の感情とどう向き合ったかといった記述が求められるようになった。つまり,医師として自身の医療実践の意味を表現することが重視され始めている。
◆本書の画期的な取り組み
本書は,看護師が患者に行うケアの意味を,個別事例の深い検討を通して明らかにし,学術的な論文に昇華させようとする野心的な試みである。事例検討自体は医療現場で日常的に行われており,私たちにもなじみ深いものだ。しかし本書では,このなじみ深い手法を認識論・方法論的に洗練させ,参加した看護師や論文の読者の内面に変化(Transform)を起こそうとしている。
具体的には,ワークシートの設定,「問われ語り」という独特な対話手法の導入,創造的なメタファーの活用,そして全体を豊かなナラティブで再構成する-という体系的なプロセスが示されている。
◆「触発性」という核心概念
特に注目すべきは,哲学的考察に裏打ちされた理論的基盤の確かさである。中でも「触発性」という概念は極めて新しく,重要だ。事例研究に「触発性」が不可欠だという考え方は,個別性を方法論的に追求することで,逆にその個別性が内側から破られ,社会性を獲得するという逆説的なプロセスを含んでいる。これは柄谷行人が『探究II』(講談社,1989)で展開した,固有名を通じて単独性と社会性を結び付ける論考と正確に対応していると感じた。
◆現代医師に与える意義
現代日本の医師は,「多疾患併存」「未分化健康問題」「慢性疾患下降期」「心理社会的複雑困難事例」「生きづらさをめぐるメンタルヘルス」など,不確実性の高い問題に直面している。もはや医学知識や技術の提供者にとどまらず,「ケアの担い手」「癒やし手」としての役割が求められる時代である。
その意味で,本書が提示する事例研究の手法は,医師にとっても豊富な学びの源泉となるだろう。患者の個別性を深く見つめることで普遍的な意味を見出すこの方法論は,現代医療が直面する複雑な課題への新たなアプローチを示唆している。そうした問題に取り組んでいる地域の医師たちに一読を勧めたいと思う。
(「看護研究」 Vol.58 No.5 掲載)
世界観の変容から世界線の移行へ
酒井 郁子(千葉大大学院看護学研究院 教授/千葉大医学部附属病院総合医療教育研修センター)
山本則子氏は2000年代の数年間,千葉大学看護学部の准教授として在籍されていた。同時期に私も准教授として在籍し,学生の授業評価や学術推進の仕組みづくりを共に行った。「田んぼのあぜ道を爆走するポルシェ」という異名は,私が彼女の仕事ぶりを評して付けたものだ。それ以来,折に触れ多くの対話を重ねてきたが,その中で彼女は何度か,「この事例研究の仕事は本来,千葉大が取り組むべきだった」と語っていたことを今も忘れない。
本書『ケアの意味を見つめる事例研究』は,看護の実践知と学術知の架け橋という次のステージを明確に示す1冊である。第1部,第2部では,実践に内在する意味を掘り起こし,事例研究という方法論によって,その意味を可視化・言語化する営みが丹念に展開される。そして本書の価値は,「事例研究の方法」を分かりやすく解説するだけにとどまらない。特に注目すべきは,第3部の第7章,第8章において,事例を学術的に洗練させ,査読に耐えうる論述とし,研究論文として社会に開示するための具体的な方法を提示している点である。
経験の描写にとどまらず,その背後にある意味を問い,他者と共有可能な知へと昇華する。この営みは,実践と研究の境界を越える知的挑戦であり,看護師の語りを学術的・社会的に意義あるものとして位置づけ直すものだ。特に第7章では「事例研究の査読はどうあるべきか」について踏み込み,研究者と査読者双方の視点を踏まえながら,触発性・新規性をどう評価するかという問いに誠実に応えている。
そして第4部第9章では,事例研究を通じて看護観を見いだし,語り直し,実践への意味づけがどのように変化するのかが,実践者自身の言葉で記されている。読んでいて,看護の実践と学びが生き生きと往還するような手応えを感じた。
本書を通読して,私の中で2つの伝えたいことが浮かんだ。
1つ目は,「良き実践の意味」を問うことの持つ触発性についてである。山本氏は,事例研究の意義を「世界観の更新」として捉えている(121頁)。ここでいう世界観の更新とは,当たり前だった価値観を揺るがし,こうあるべきと思っていた構造に亀裂が入り,実践や判断の基盤が再構築されるようなことだ。つまり,読者は同じ物理的現実に生きていながら,意味の世界において別の次元に立ち上がる。この動きを,私は「世界線が変わる」と表現したい。実践の語りを読むことで,読者は新しい世界線にジャンプし,異なる意味世界でケアを捉え直すことができる。ケーススタディとは,ただの記録ではなく,読者を別の世界線に誘う力を秘めた装置なのだ。たぶん,読者の数だけ異なる世界線が生まれているはずである。
2つ目は,こうした「意味を見つめる事例研究」が,過去の実践の語りを起点とする回顧的・解釈的営みと一見みえるが故に,事例研究の読者が触発されなければ,世界線の移行は生じず,次の事例に相対した時に,これまでの世界で行われてきた看護をなぞってしまうことが生じるのではないか,という問いである。特に看護計画の「評価」が問われる設計型(前向き)事例研究では,「思ったとおりの効果が得られた。この看護目標は達成された」で終わってしまうリスクがある。
そうならないために,事例研究の触発性を高めるには,「メタファーを生み出す力」が必要となる。この力はたぶん1人で伸ばせるものではなく,実践について語り,メタファーを引き出すパートナーが必要だろう。
看護実践について語り合う―当たり前のことだが,当たり前にできているかを自らに問いかけるとともに,メタファーを生み出す力をどう伸ばすかについて論述することは,山本氏の次の仕事であるようにも思った。
(「看護管理」 Vol.35 No.9 掲載)