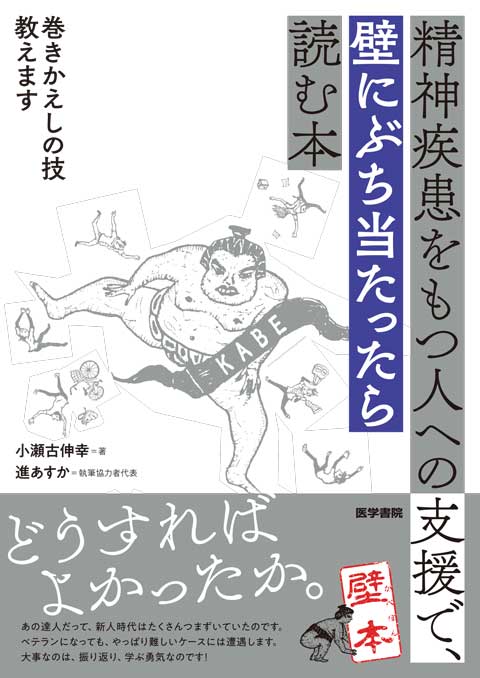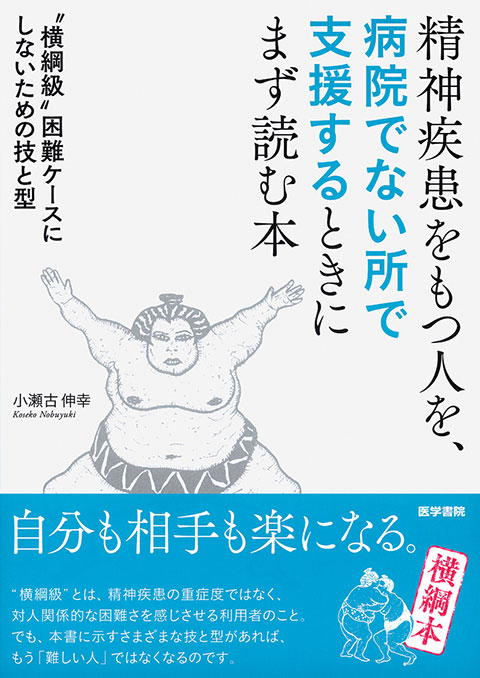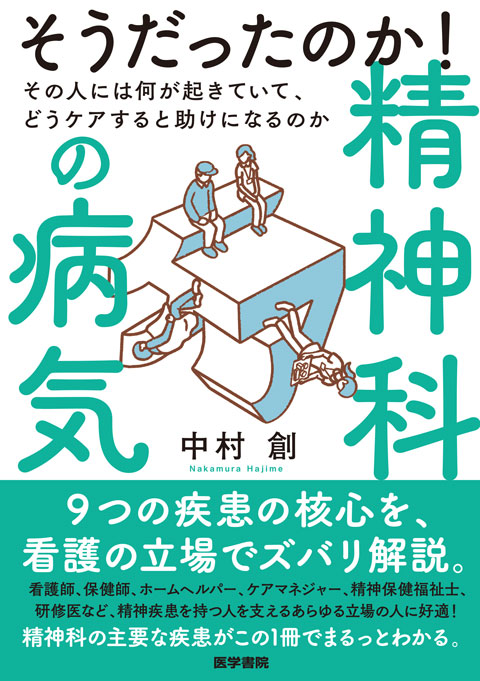精神疾患をもつ人への支援で、壁にぶち当たったら読む本
巻きかえしの技教えます
そんな考え方があったんだ! 地域の困難事例に「あんな手・こんな手」を提案。
もっと見る
どうすればよかったか──。あの達人だって、新人時代はたくさんつまずいていたのです。ベテランになっても、やっぱり難しいケースには遭遇します。大事なのは、振り返り、学ぶ勇気なのです! 本書では著者とその同僚が、自分たちがつまずき苦戦してきた事例を(恥をしのんで)公開します。そして「今ならこうやって巻きかえす」という考察・提案を記します。地域で支援・ケアを提供する人に必携の書「壁本」があなたの孤独を癒します。
更新情報
-
2025.05.23
- 序文
- 目次
序文
開く
はじめに
壁にぶつかっているのは、あなただけではない!
小瀬古伸幸
この本ではトライ&エラーの多かった私をさらします
精神科訪問看護は、精神疾患をもつ人を、その人の自宅で支援する仕事です。
精神科訪問看護を職業にしている人で、新人時代からベテランになるまで、利用者や家族との間で一度たりとも「失敗」や「困難」と感じる経験をしたことのない人なんているでしょうか。稀にはいるかもしれませんが、ほとんどの人は一度や二度どころではなく、何度も痛い経験を積んできていると思います。かく言う私もその一人です。
私は2019年に最初の書籍『精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援する時にまず読む本──“横綱級”困難ケースにしないための技と型』(通称:横綱本)を出しました。この本は、私が管理者になり、困難と言われるケースにある程度「パターン」が見えるようになった頃に、私がどのようにケアを組み立て何を考えて訪問しているのかを解説した本でした。
そこには、私がそうなるまでの、イタく苦しい体験はほとんど書きませんでした。そんなものは読者にとって学びにならないし、自分の恥をさらすだけだと思っていたからです。
すると、この本を出したとたんにちょっとだけ困ったことが起きました。私がまるで「最初から当たり前にできた」かのような誤解を与えてしまったのです。私が講演会で、こぼれ話として自分がつまずいた体験(「壁」体験)を語ったとき、ある参加者からこう言われました。「小瀬古さんでもうまくいかなかったケースがあったんですね。勇気づけられました」。
当然ですが、私も、最初から横綱級ケースと向き合えたわけではありません。特に新人時代は多くのトライ&エラーがありました。同僚に比べてもエラーは多いほうだったのではないかと思います。こうやって進めようと計画を頭に描き、利用者に話す際の根拠となるエビデンスを頭に叩き込んでから向かっても失敗しました。スッキリ解決しなかったり、中途半端に終了したり、なぜあのときあんな対応をしてしまったのかと後悔したり、何が悪かったのかを明確にできず、モヤモヤした思いが残ってしまったケースもありました。
そしてそこに葛藤が残っているからこそ、ずっと「どうしたらよかったのか」を考え続けてきました。だからこそ今の私がある、とも言えます。
なぜなら体験の共有が他人の役に立つと思うから
今回、この葛藤が残る新人時代の「壁」体験をまとめて本にすることにしました。
今ならこうするのに、と思う事例も多くありますが、私がつまずいてきたことは、おそらく多くの新人さんにとってもつまずきやすいポイントではないかと思いますし、「本を出すような人間でさえ、新人時代はこんなに派手につまずいてたし、ベテランになっても苦戦することがあるんだ」と思えば、皆さんもつまずいたときに落ち込みが浅くて済むかもしれません(うまくいかないときって、自分だけがそうなんだと錯覚しますからね)。また、事例を読んで「自分が同じ立場だったらどうするだろう」とシミュレーションすることもできると思います。
しかし、単に新人時代の私の「壁」体験を紹介するだけでは、読んだ皆さんにとっては答えがなくて気持ち悪いだけになってしまいますので、現時点の私が事例を振り返って思うこと、どうしたらよかったかという考察も、「こんな手もある」という形で事例の後ろに付けることにしました。
そして、とてもありがたいことに、私の企画の趣旨に賛同してくれた同僚や仲間が、同じように後悔の残る自分の「壁」体験を提供してくれることになりました(みんな、協力してくれてありがとう!)。
うまくいかなかった事例を書くというのは、ある程度自分の恥をさらすことでもあるので、その覚悟で書いてくれた同僚や仲間には深く感謝しています。それだけみんな、精神科訪問看護にはつまずきがつきものだとわかっているし、だから自分の事例を挙げることで他の訪問看護師に参考にしてもらいたいと思ってくれたのだと思います。さらに、今でも「どうしたらよかったんだろう」と悩んでいる事例に対してなんらかの答えがほしいと真摯に思っているからだと思います。それが向上心ですよね。
同僚や仲間が提供してくれた事例に対する考察・提案は、私のスーパーバイザー兼みのりの知恵袋である進あすかさんにお願いしました。
というわけで、今回のこの本は6人の仲間の協力を得て完成できた本なのです。おかげで「壁」体験の種類もさまざまになりましたし、特に新人さんが陥りがちな事例がほんとうによく網羅されていて、精神科訪問看護の必読書と言える本になれたと思います。
なお、本書の担当は、『横綱本』でも担当してくれた石川誠子さんです。石川さん、今回もありがとう!
「壁」体験は、自分の価値観を見つめ直す機会です
私は、「壁」体験とは、看護師としての自分の価値観(「なぜ自分はこう思い、こうしたんだろう」)を見つめ直す機会をくれるものだと思っています。再現性を持って看護をするためには、自分が「あれっ?」と思った違和感に対して、何が起こっていたのかをきちんと言語化し、意味付けする必要があります。どうしたらよいのかを考えて、向き合い続ける必要がある。それにより、次に同じような利用者、家族、状況に出会った時に、この経験を活用できるからです。だから「壁」体験を振り返ることには意味があります。
なお、本書の「壁」体験は(あくまで主観に基づくものではありますが)初級者編~上級者編の順になるよう並べました。
事例のあとの考察・提案は、読者の皆さんにとって腑に落ちる部分もあれば、違う視点が見えることもあると思います。その違和感も含めてメモを書き入れながら読んでみるのもよいと思いますし、さらには職場の皆さんで同じ事例を読んで、意見を出し合ってみるのもよいのではないでしょうか。
さあ、この切磋琢磨の旅に、みんなで一緒に出かけましょう。
注)事例においては個人が特定されないよう、性別、年齢を変更したり、他の事例と組み合わせるなど、さまざまに改変を加えました。
目次
開く
はじめに
一章 医療的な必要性が感じられないことを要求する
壁1 ハグを求めてくる人 〈パニック症、50代女性〉 ──こんな手もある
壁2 対話を拒否。命令口調で代理行為を強いてくる人 〈アルコール依存症、うつ病、40代男性〉 ──こんな手もある
壁3 「面白い話」を要求。スタッフ1人をこき下ろし、1人を褒める人 〈双極症II型、40代男性〉 ──こんな手もある
二章 「やりたいこと・望み」が出てこない
壁4 すべてを指示してもらいたがるので、「それはあなたが決めること」と伝え続けた結果、入院になった人 〈統合失調症、30代男性〉 ──こんな手もある
壁5 「リストカット」「オーバードーズ」以外に気持ちを紛らわす方法が見つからず、救急搬送になった人 〈ボーダーラインパーソナリティ症、20代女性〉 ──こんな手もある
三章 激しい感情を露わに突然攻撃してくる
壁6 人を試し、失望すると激昂し、支援者を拒否する人 〈双極症、60代前半男性〉 ──こんな手もある
壁7 発言を悪意に受け取り、支援者を非難。聞く耳を持たない人 〈統合失調症、覚せい剤使用、40代後半男性〉 ──こんな手もある
四章 家族からの要求と期待が大きく、一筋縄ではいかない
壁8 家族は支援者を頼り、長時間の面接を要求。利用者と支援者はなぜかうまくかみ合わない 〈利用者:双極症(混合状態)の20代前半男性、父親:60代後半〉 ──こんな手もある
壁9 家族の望みを明確にせず開始。1週間で終了を申し出てこられた 〈利用者:パニック症の70代女性、長男:うつ病の40代〉 ──こんな手もある
五章 アルコール依存症で、身体状態が悪化している
壁10 「節酒」を選択したが、自覚以上に身体状態が悪かった人 〈アルコール依存症、40代女性〉 ──こんな手もある
壁11 断酒する気は一切なし。救急車を呼ぶも、乗車を拒否した人 〈アルコール依存症、COPD、60代男性〉 ──こんな手もある
六章 自閉スペクトラム症と本人の特性から、支援が定着しない
壁12 支援を求めるが、猜疑心が高まると混乱し、支援を切ってしまう人 〈自閉スペクトラム症、40代女性〉 ──こんな手もある
七章 激しさ、不安定さで支援者を翻弄するボーダーラインパーソナリティ症をもつ人たち
壁13 働くための支援が始まったら、見捨てられ不安が大きくなった人 〈ボーダーラインパーソナリティ症、20代後半女性〉 ──こんな手もある
壁14 特定のスタッフを激しくこき下ろし、休職に追い込んでしまった人 〈ボーダーラインパーソナリティ症、軽度知的発達症、40代後半女性〉 ──こんな手もある
壁15 頻回の電話、引き留め、中傷でスタッフを追い詰めてしまった人 〈ボーダーラインパーソナリティ症、40代女性〉 ──こんな手もある
経験の伝承
相手の話したい内容を、相手のペースに合わせて話そう
先輩の言葉を「自分だったらどう言うか」と考えてみる
会話の「終結」までシミュレーションしてから向かおう
「現状維持」で良いのか? 良くないのか?
精神科訪問看護には2つの段階(時期)があります
利用者さんの「やりたいこと」の見つけ方
あとがきに代えて
執筆者・執筆協力者一覧