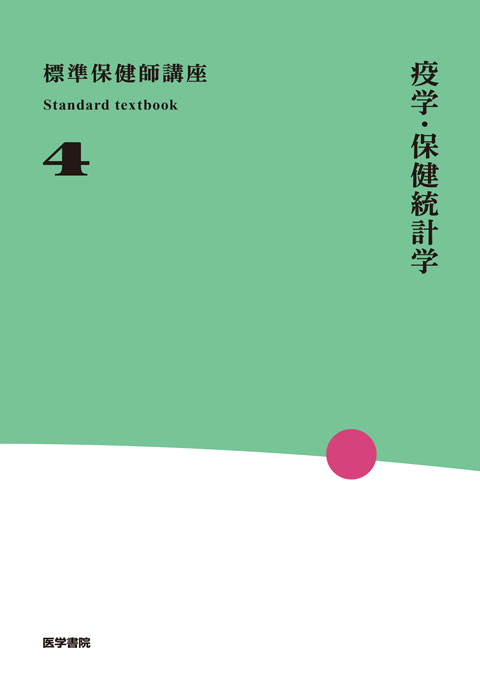疫学・保健統計学 第4版
もっと見る
◎本巻は、保健師国家試験出題基準(令和5年版)の次の内容に対応しています。
◎公衆衛生看護を実践するうえで必要となる、疫学・保健統計の適用場面を具体的に解説します。
◎各章に豊富な演習問題を設けています。
*「標準保健師講座」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 標準保健師講座 4 |
|---|---|
| 執筆 | 尾崎 米厚 / 金城 文 / 原田 亜紀子 / 森本 明子 / 宮松 直美 |
| 発行 | 2025年01月判型:B5頁:240 |
| ISBN | 978-4-260-05682-3 |
| 定価 | 3,300円 (本体3,000円+税) |
- 増刷中
- 改訂情報
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 付録・特典
序文
開く
はしがき
標準保健師講座の特色
少子高齢社会のなか,保健師活動では予防の重要性が強くうたわれ,健康な地域づくりが重要な課題となっています。さらに,在宅看護の需要の拡大から療養支援には生活の視点が重要になっています。公衆衛生看護学は,保健師だけでなく看護師にとっても必要不可欠なものです。多くの看護職が公衆衛生看護の志向をもつことが求められています。
いま保健師教育の場は,これまでの3年制の看護学に1年制の保健師教育を付加する養成所や短期大学専攻科における養成に加え,看護学に統合された4年制大学および大学院修士課程など多様化しつつあります。なかでも多くの4年制大学では,公衆衛生看護学について限られた時間内で講義や臨地実習をしており,教員が信頼して学生に読ませることのできるテキストが必要とされています。また,看護師と保健師の2つの国家試験を受験する大学生には,保健師国家試験に向けて短時間で効率よく,自己学習できるテキストが求められています。
本講座は,教員や学生のニーズにこたえ,標準的な保健師教育のための教科書として,保健師に求められる基本的な知識と技術を修得することを目ざし企画されました。
本講座の特色は,改定された保健師国家試験出題基準の項目をすべて網羅したかたちで,保健師として押さえておくべき内容をコンパクトにまとめたことです。
本来,保健師の仕事は,応用が必要で創造的なものですが,基本がおろそかでは,応用的な課題に対応できないといえます。そこで「理念や理論を押さえたうえでの基本の理解と,実践能力ゆたかな専門職の教育」を本講座のねらいとしました。
本講座は『公衆衛生看護学概論』『公衆衛生看護技術』『対象別公衆衛生看護活動』『疫学・保健統計学』『保健医療福祉行政論』の全5巻からなる構成です。
本講座の執筆者は保健師として現場経験豊富な看護大学教員や,地域保健に詳しい公衆衛生医師らで構成しました。
本書の概要
本書は保健師国家試験出題基準の「疫学」(1.疫学の概念,2.疾病頻度の指標,3.曝露効果の指標,4.疫学調査法,5.スクリーニング,6.疾病登録,7.生活習慣の疫学,8.主な疾患の疫学,9.公衆衛生看護と疫学)および「保健統計学」(1.統計学の基礎,2.人口統計,3.保健統計調査,4.情報処理)の全項目に対応しています。
疫学および保健統計学は,疾病や健康関連の現象を理解し,根拠に基づく対策を提示し,その評価を行うために重要な学問であり,保健福祉政策の立案,および実践への具体的現実的な手段を提供するために不可欠なものです。本書は,皆さんに疫学と保健統計学の理念・理論・方法などの基本と,それが社会でどのような意味をもつのか,どのように役だつのかという実践のなかでの活用方法をお伝えすることを目標に執筆されました。
疫学と保健統計学はいま,大きな転換の時期にあります。これまでの伝統的な疫学は,各種疾患の危険因子を同定し,危険因子修正のための効果的介入方法を検討することに焦点をあててきました。しかしながら近年では,情報技術の進歩により蓄積されたビッグデータを活用することで,従来ではとらえにくかった病気の発生メカニズムや流行パターンをより詳細に理解し,それに基づいた効果的な予防策や介入方法を提案することが可能となるなど,疫学の応用領域が大きく広がっています。
したがって本書では,伝統的な疫学手法を網羅し,各種健康事象のリスク評価や,保健医療政策の立案と評価などの実践的アプローチのための基本的知識の習得を目ざすとともに,今後,国民の健康増進のために重要となりうる新たな視点についても述べています。
本書は,各章のおわりに保健師国家試験をもとにした問題や予想問題を演習問題として掲載していますので,試験対策におおいに役だつことでしょう。しかしながら,私たちの願いは,本書を読んだ皆さんが国家試験に合格されることだけではなく,疫学と保健統計学の魅力にふれ,その重要性を理解し,さらには楽しんで学んでくださることにあります。疫学と保健統計学は,単なる試験のための知識ではありません。健康な社会を築くための基盤であり,その理解と実践は国民の福祉と健康の向上において重要な役割をもちます。
本書を活用されたみなさんが,公衆衛生看護を担う保健師として活躍されることを願っています。
2024年11月
著者ら
目次
開く
1章 疫学の概念 (宮松直美)
A 疫学の紹介
1.疫学の定義
2.疫学の発展
3.歴史に学ぶ疫学の原理
B 曝露と疾病発生
1.曝露と危険因子
2.診断基準
▪ 演習問題
2章 集団の健康状態の把握 (尾﨑米厚・金城文)
A 疾病の頻度の指標
1.疾病の頻度を測定する前提としての疾病分類
2.割合
3.率
B 曝露効果の指標
1.相対危険
2.寄与危険
▪ 演習問題
3章 疫学的研究方法 (森本明子)
A 因果関係の立証
1.因果関係の立証
2.多要因原因説
B 対象集団の選定
1.母集団と標本
2.標本抽出法
C 研究デザイン(研究方法)
1.観察研究
2.介入研究
3.システマティックレビューとメタアナリシス
4.研究方法によるエビデンスのレベル
D 誤差
1.偶然誤差と系統誤差
2.精度と妥当性
E 偏り(バイアス)
1.選択バイアス
2.情報バイアス
F 交絡因子とその制御方法
1.交絡因子の概念
2.研究計画段階での交絡因子の制御方法
3.解析段階での交絡因子の制御方法
4.年齢調整
G 研究における倫理
1.ニュルンベルク綱領,ヘルシンキ宣言
2.わが国における倫理指針
▪ 演習問題
4章 疾病の予防とスクリーニング (尾﨑米厚・金城文)
A スクリーニング検査の目的・要件・評価
1.スクリーニング検査の目的
2.スクリーニング検査の要件
3.スクリーニング検査の評価
4.わが国におけるスクリーニングの例
▪ 演習問題
5章 疾病登録
A 疾病登録の意義と目的 (原田亜紀子)
B がん登録 (尾﨑米厚・金城文)
1.院内がん登録
2.地域がん登録
3.がん登録に関する指標
4.がん登録等の推進に関する法律
C 循環器疾患の登録 (原田亜紀子)
1.循環器疾患登録の根拠
2.循環器疾患登録の現状
3.今後の課題
▪ 演習問題
6章 おもな疾患・生活習慣の疫学 (尾﨑米厚・金城文)
A 感染症の疫学
1.流行
2.アウトブレイク時の流行調査の基本
3.おもな感染症の疫学
B 非感染性疾患の疫学
1.がんの疫学
2.心疾患の疫学
3.脳血管疾患の疫学
4.糖尿病の疫学
5.難病の疫学
6.精神疾患の疫学,自殺の疫学
7.事故の疫学
8.環境要因による疾患の疫学
9.その他の重要疾患の疫学
C 母子保健,学校・産業保健の疫学
1.母性関連疾患の疫学
2.小児疾患の疫学
3.学校保健の疫学
4.産業保健の疫学
D 生活習慣の疫学
1.栄養・食生活
2.身体活動,運動
3.休息,睡眠
4.飲酒
5.喫煙
6.歯・口腔
▪ 演習問題
7章 疫学と公衆衛生看護 (宮松直美)
A 社会疫学
1.社会疫学の歴史と発展
2.健康の社会的決定要因と健康格差
B 政策疫学
1.健康課題に対する保健医療政策のプロセス
2.国・地域での政策疫学の実例
3.健康課題に対する政策決定への疫学のかかわりとデータの利活用
C 臨床疫学
1.診療ガイドライン策定への貢献
2.決定分析
▪ 演習問題
8章 保健統計学の基礎 (尾﨑米厚・金城文)
A データの種類と分布
1.データと尺度の性質
2.保健活動における尺度
3.代表値と散布度
4.確率分布
B 関連の指標
1.相関と回帰
2.クロス集計
C 統計分析
1.点推定と区間推定
2.検定,帰無仮説,統計学的有意性
3.割合に関する推定と検定
4.平均に関する推定と検定
5.相関に関する検定
6.ノンパラメトリック検定
7.多変量解析
D 統計調査の表現・解釈
1.データの表現
2.統計にだまされないために
▪ 演習問題
9章 人口統計の基礎 (尾﨑米厚・金城文)
A 人口静態統計
1.わが国の人口
2.年齢別人口
3.世界の人口
B 人口動態統計
1.出生と人口再生産
2.死亡
3.死産,周産期死亡
4.婚姻と離婚
C 生命表
1.平均寿命
2.健康寿命
▪ 演習問題
10章 保健統計調査 (原田亜紀子)
A 基幹統計
1.国勢調査
2.人口動態調査
3.国民生活基礎調査
4.患者調査
5.医療施設調査
6.学校保健統計調査
7.社会生活基本調査
B その他の統計調査
1.感染症発生動向調査
2.食中毒統計調査
3.国民健康・栄養調査
4.地域保健・健康増進事業報告
5.身体障害児・者等実態調査
6.衛生行政報告例
7.福祉行政報告例
C 医療経済統計
1.国民医療費
2.介護サービス施設・事業所調査,介護保険事業状況報告
D 疾病・障害の定義と分類
1.国際疾病分類
2.国際生活機能分類
E 活用可能なデータベース
1.レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)
2.国保データベース(KDB)システム
3.介護保険総合データベース(介護DB)
▪ 演習問題
11章 保健医療情報の管理・活用 (原田亜紀子)
A 情報処理の基礎
1.保健医療情報
2.ヘルスデータサイエンスの3要素
3.データの電子化
4.データベース
5.データの品質と情報セキュリティ
6.レコードリンケージ
B 保健医療情報に関する法令・指針・原則
1.個人情報の保護に関する法律
2.住民基本台帳法
3.倫理指針
4.まもるべき原則
C 保健医療情報の収集
1.既存の統計資料
2.公的機関のウェブサイト
3.文献検索
▪ 演習問題
付録
国家試験対策の手引き (尾﨑米厚・金城文)
索引
付録・特典
開く
章末問題解答
章末問題の解答は次のとおりです。
第8章「保健統計学の基礎」演習
●Microsoft Excelを用いた演習には,以下のファイルをご利用ください。
●EZRを用いた演習には,以下のファイルをご利用ください。