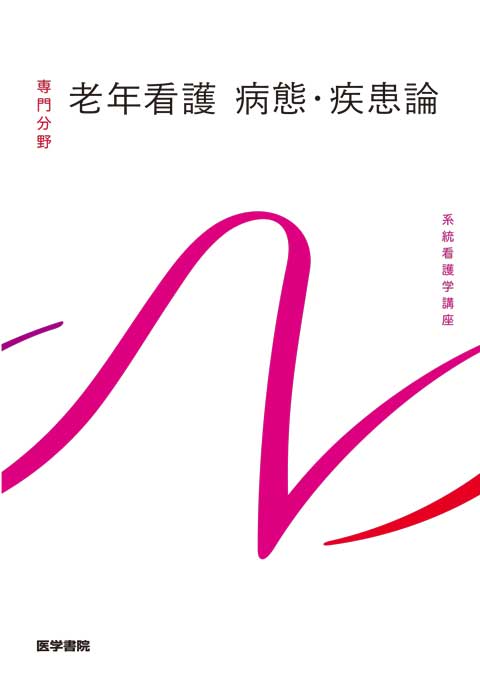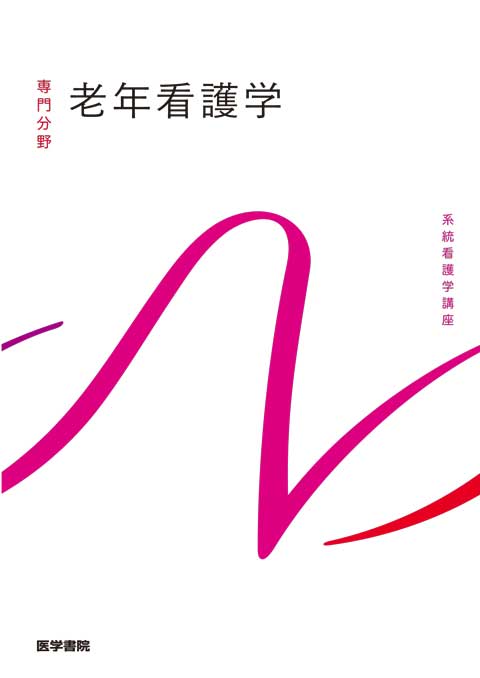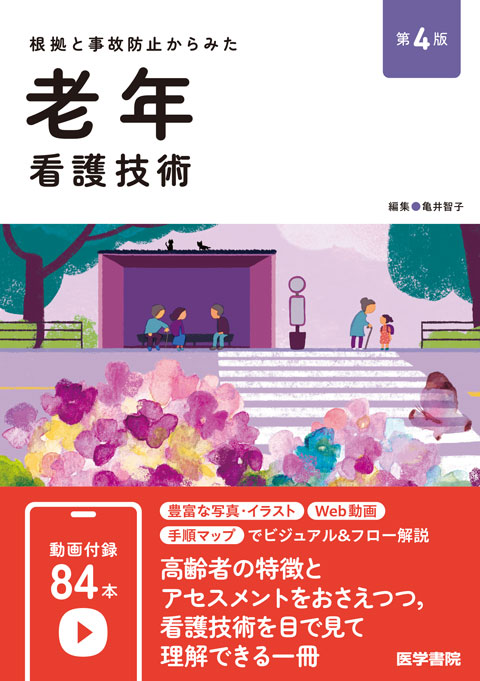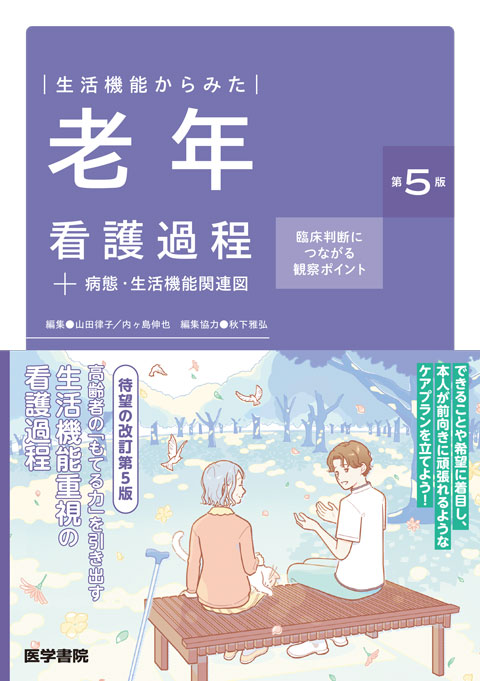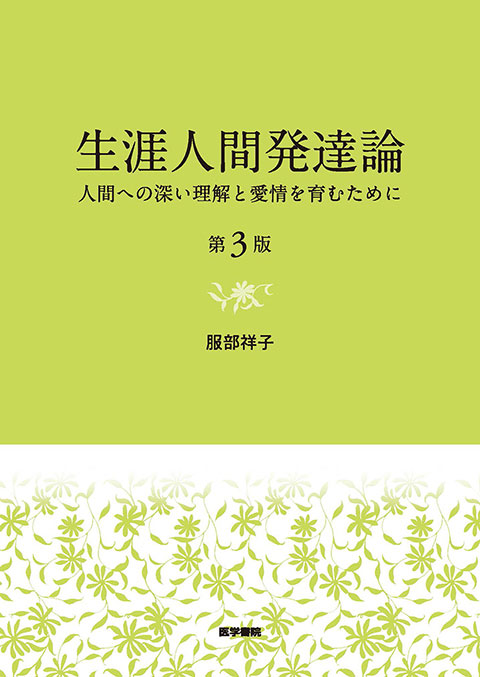老年看護 病態・疾患論 第6版
もっと見る
- 高齢者の生理的特徴、高齢者に特徴的な症候(老年症候群)と病態生理、高齢者の観察・面接・総合機能評価の方法、高齢者に多い疾患など、高齢者の医療実践に欠かせないエッセンスをまとめたテキストです。
- 看護のための老年医学・高齢者医療の概説書として、最適の1冊です。本講座の『老年看護学』との併用で効果を発揮します。「超高齢社会」時代のなかで、高齢者の身体的特徴をふまえたケア実践ができる看護師が育ちます。
- 高齢者は多くの症候や疾患を併存します。臓器ごとに課題に対応する一般的な医療モデルに基づいて看護を行うべきではありません。個々の症状や疾患をみるのではなく、状態を総合的にとらえて看護を行う必要があります。
- 第6版では、次世代の著者にご参画いただき、老化研究や高齢者医療の最新動向を盛り込んだほか、看護に役立つ高齢者アセスメント、高齢者の病態や症状に関する説明を強化しました。
- 「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 系統看護学講座-専門分野 |
|---|---|
| 執筆 | 鳥羽 研二 / 秋下 雅弘 / 石井 正紀 / 海老原 覚 / 清水 聰一郎 / 前田 圭介 / 山口 泰弘 |
| 発行 | 2025年02月判型:B5頁:312 |
| ISBN | 978-4-260-05683-0 |
| 定価 | 2,640円 (本体2,400円+税) |
- 増刷中
- 改訂情報
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はしがき
発刊の趣旨
本書は「系統看護学講座 専門分野 老年看護学」とともに,看護基礎教育カリキュラムにおける専門分野「老年看護学」に対応したテキストである。
わが国における高齢者医療の重要性は増すばかりである。2024年の日本人の平均年齢は50歳をこえる。モナコなどの小さな国を除けば,世界一の高さといってよい。たとえば,アメリカ人の平均年齢は39歳であり,インドにいたっては30歳と若い。全人口に占める65歳以上人口の割合を示す高齢化率も同様に世界トップレベルであり,3人に1人が高齢者という構造となっている。さらに,65歳以上人口は約50年後に4割まで達すると予想されている。
このような未曽有の高齢化に医療が対応するには,大学医学部への老年医学講座の設置の拡大などにより,高齢者診療を専門的に学んだ医師の養成が急務である。あわせて,患者に最も身近な存在である看護師が,高齢者に多い病気や症状,それに伴う生活上の諸問題や悩みへの理解を深めることも急務であろう。
高齢者医療の要諦は,臓器別医療からの全人的医療への転換である。たとえば,医療においては,呼吸器内科や循環器外科,消化器内科,耳鼻咽頭科,眼科など,臓器別の専門医療が存在する。しかし高齢者は,複数の疾患をあわせもつ「多病」の状態が一般的であり,とくに75歳以上は平均5つ以上の疾患をもつ。個々の診療科で治療を行っても問題が解決しない場合が多く,非効率的な医療提供になるおそれや,投薬が増えて多剤併用におちいるおそれもある。また,高齢者の「元気になりたい」「苦痛をやわらげたい」などのニーズに寄り添うものにもならないだろう。高齢者の生理的特徴や加齢に伴う生活機能の低下,個別的な生活状況を踏まえ,臓器別ではなく総合的に高齢患者を診療する専門医療が必要なのである。
看護も同様であり,高齢者医療ではとくに,臓器別(診療科別)の看護をこえた,全人的看護が重要になる。本書は,高齢者への全人的看護の参考になるよう,老年医学の視点から,高齢者の生理的特徴,疾患・症状・治療・リハビリテーションなどを解説するものである。
改訂の経緯
発刊の趣旨で述べた内容の核心部分は,すでに,この本の生みの親である前日本老年医学会理事長の佐々木英忠先生が,初版(1999年1月発行)のはしがきに書かれている。
本書は第2版まで佐々木先生の単著であった。第3版から,急速な認知症患者の増加に対応し,高齢者の多様な症候を記述したいという佐々木先生のお考えにより,東北大学の荒井啓行教授と当時杏林大学教授だった鳥羽が加わり,認知症と認知症に伴う行動・心理症状や,老年症候群について大きく加筆した。第4版からは東京大学の秋下雅弘教授が加わり,高齢者の疾患および薬物療法について,最新の知見を盛り込んでわかりやすく解説していただいた。第5版では,高齢者への多投薬がさまざまな問題を引きおこすことが明らかになりポリファーマシー(多剤併用)として社会に認知されたことをふまえ,第5章「高齢者と薬」を秋下先生に新設いただいた。また,医療と介護の一体化が課題となり,「科学的介護」の発展が求められている状況をふまえ,東北大学の海老原覚先生に加わっていただき,第6章「高齢者のリハビリテーション」を新設いただいた。
改訂の趣旨
今改訂は,いわゆる「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になる「2025年問題」の年に行った。2025年を目途に構築を目ざすとうたわれた地域包括ケアシステムの整備も不十分であるが,私たちは65歳以上の人口が約4000万人と最大になる「2040年問題」に向けて準備していかなければならない。人口減少とそれに伴う働き手不足もとまらないなかで,限られた医療資源を効率的に使うためには,高齢者への深い理解に基づいた専門医療がますます必要になる。加えて,ビッグデータの活用,ロボットやAIなどの新しい技術の利用も欠かせない。
そこで今改訂では,第1章「高齢者の生理的特徴」,第3章「高齢者の健康状態の把握と総合機能評価」,第4章「高齢者の疾患の特徴」において,老年医学研究と高齢者診療の第一線で活躍され,未来を担うと嘱望されている石井正紀先生,清水聰一郎先生,前田圭介先生,山口泰弘先生(五十音順)にご参画いただいた。
第1章については,近年,世界的に老化に関する研究が進み,多くの新しい知見が示されているため,内容の刷新を行った。
第3章は,高齢者のアセスメントに関する内容であり,看護上とくに重要であろう。いまも第一線で日々高齢患者の診療に勤しまれている新規ご参画の先生方に,新たにご執筆をいただいた。
第4章は,高齢者に多い疾患を解説する本書の重要な章である。超高齢社会を乗り切るための方策の1つは健康寿命の延伸であり,血管疾患やがん,認知症,糖尿病,フレイル,腰痛,難聴や視力障害といった感覚障害などが健康寿命を阻害する要因であることが明らかになっている。とくに認知症患者は現在,全国で600万人をこえ,その予備軍ともいうべき軽度認知障害(MCI)の高齢者も急増中である。
そこで,認知症診療のエキスパートである清水聰一郎先生をはじめ,新規ご参画の先生方に,最新の内容をご執筆いただくこととした。認知症については,その重要性を鑑み,前版よりも内容を大きく拡充いただくよう依頼した。
そのほか,前版以前からご参画いただいている先生方にも,最新の知見や現状に基づく内容の更新をお願いした。
これらにより,前版よりもさらに内容が充実し,これから迎える未曽有の高齢化に対応できる知見を盛り込んだテキストになったと確信している。
本書が老年看護をこれから学ぼうとする看護学生や,卒後しばらく経過して新しい知識を吸収したいという看護師のお役に立つことができれば幸いである。
2025年1月
著者を代表して
鳥羽研二
目次
開く
序章 「超高齢社会」における高齢者医療 (鳥羽研二)
A 高齢者の定義
1 何歳以上が「高齢者」か
2 WHOの区分と「高齢者」の現状
B 超高齢社会の到来と高齢者医療
1 どのような高齢者が増えるのか
2 どのような社会になるのか
3 「超高齢社会」に適合した医療へ
C 高齢者医療の要点
1 地域・在宅医療における要点
2 急性期医療における要点
3 慢性期医療における要点
4 人生の最終段階における医療の要点
5 高齢者医療の目標設定
D 高齢者医療における老年看護への期待
1 患者に寄り添い「強み」に着目する看護
2 高齢者医療で発揮すべき看護の力
第1章 高齢者の生理的特徴 (鳥羽研二・清水聰一郎・山口泰弘・前田圭介)
A 老化のとらえ方
1 老化を知る意義
2 老化を理解するために必要なこと
B 老化とは
1 加齢と老化
2 老化の定義
3 老化現象
4 寿命と老化
C 老化の原因
1 生物の進化に伴う遺伝的要因
2 生活習慣やストレスなどの環境要因
D 認知・知覚機能の老化
1 脳の老化
2 感覚機能の老化
E 呼吸・循環機能の老化
1 呼吸機能の老化
2 循環機能の老化
F 消化・吸収・代謝機能の老化
1 消化・吸収機能の老化
2 肝機能の老化
3 高齢者の糖代謝
4 高齢者の薬物代謝
5 高齢者の水代謝
6 高齢者の電解質代謝
G 排尿機能の老化
H 免疫機能の老化
1 免疫と老化
2 老化による免疫機能低下の促進要因
I 運動機能の老化
1 加齢に伴う運動機能・身体活動量の変化
2 骨・関節機能の加齢変化
第2章 老年症候群 (鳥羽研二)
A 老年症候群の特徴
1 老年症候群とは
2 老年症候群の分類
B おもに急性疾患に付随する症候
1 意識障害
2 せん妄
3 熱中症
4 脱水症
5 発熱
C おもに慢性疾患に付随する症候
1 腰背痛
2 やせ(るいそう)
3 手足のしびれ
4 浮腫
5 睡眠障害
6 うつ状態
D 日常生活動作(ADL)の低下と密接な関連をもつ症候
1 転倒・骨折
2 排尿障害(尿失禁)
3 便秘
4 嚥下障害
5 閉じこもり
6 寝たきり
E フレイル
1 フレイルとは
2 フレイルの基準
3 フレイルの下位分類と概念の拡大
4 フレイルの原因
5 フレイルの類似概念
6 フレイルの治療と予防
第3章 高齢者の健康状態の把握と総合機能評価 (鳥羽研二・前田圭介・秋下雅弘・石井正紀・清水聰一郎)
A 高齢者のフィジカルアセスメント
1 高齢者のフィジカルアセスメントにおける心構え
2 高齢者のフィジカルアセスメントのポイント
B バイタルサイン測定・身体測定
1 体温測定
2 血圧測定
3 身長測定
4 体重測定
C 高齢者の栄養評価
1 低栄養の評価と診断
2 過栄養(肥満)の評価と診断
3 栄養素摂取不足の評価と診断
D 高齢者の検査
1 高齢者の画像検査
2 高齢者の生理機能検査
3 血液検査
E 訪問場面での健康状態の把握
F 高齢者総合機能評価
1 高齢者総合機能評価(CGA)とは
2 高齢者総合機能評価(CGA)による評価
3 高齢者総合機能評価(CGA)の展開例
第4章 高齢者の疾患の特徴 (鳥羽研二・清水聰一郎・秋下雅弘・山口泰弘・前田圭介)
A 高齢者の疾患の特徴
B 認知症
C 脳血管障害
D パーキンソン病
E うつ状態
F 循環器系の疾患
1 虚血性心疾患
2 心不全
3 不整脈
4 高血圧症
5 動脈硬化症
G 呼吸器系の疾患
1 高齢者肺炎
2 肺結核
3 肺非結核性抗酸菌症
4 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
5 喘息
6 特発性肺線維症
7 肺がん
8 肺血栓塞栓症
H 消化器系の疾患
1 逆流性食道炎
2 胃・十二指腸疾患
3 腸疾患
4 肝胆膵疾患
5 消化器腫瘍
6 急性腹症
I 内分泌・代謝系の疾患
1 甲状腺疾患
2 糖尿病
3 脂質異常症
4 水・電解質異常
J 自己免疫疾患
1 関節リウマチ(RA)
2 リウマチ性多発筋痛症(PMR)
3 巨細胞性動脈炎(GCA)
4 ANCA関連血管炎
5 皮膚筋炎(DM)
6 強皮症(SSc)
K 血液の疾患
1 貧血
2 骨髄異形成症候群
3 白血病
4 悪性リンパ腫
5 多発性骨髄腫
L 腎・泌尿器系の疾患
1 腎不全
2 慢性腎臓病(CKD)
3 薬剤性腎障害
4 尿路感染症
5 前立腺疾患
M 運動器の疾患
1 大腿骨頸部骨折
2 変形性膝関節症
3 椎間板ヘルニア
4 腰部脊柱管狭窄症
5 変形性脊椎症
6 骨粗鬆症
N 皮膚の疾患
1 褥瘡
2 皮膚瘙痒症
3 湿疹
4 薬疹
5 帯状疱疹
6 白癬
7 疥癬
8 そのほかの高齢者によくみられる皮膚の疾患
O 感覚器の疾患
1 加齢変化と感覚器疾患
2 緑内障
3 糖尿病網膜症
4 加齢黄斑変性
5 白内障
6 難聴
7 鼻炎
8 嗄声
9 味覚障害
P 感染症
1 インフルエンザ
2 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
3 ノロウイルス関連胃腸炎
4 クロストリジウム-ディフィシレ感染症
5 結核菌感染症
6 高齢者施設における感染対策
7 ワクチン療法
第5章 高齢者と薬 (秋下雅弘)
A 高齢者の安全な薬物療法
1 高齢者の薬物療法の原則
2 高齢者で注意すべき薬物有害事象
3 高齢者で注意すべき薬物相互作用
B 高齢者で注意すべきおもな薬物
C 服薬管理能力のアセスメントと服薬支援
1 服薬管理能力のアセスメント
2 服薬支援
第6章 高齢者のリハビリテーション (海老原覚)
A 高齢者におけるリハビリテーション
1 高齢者におけるリハビリテーションの特徴
2 高齢者の包括的リハビリテーション
3 各期における高齢者リハビリテーションの特徴と実際
B 内部障害リハビリテーション
1 呼吸リハビリテーション
2 心臓リハビリテーション
C 肢体不自由リハビリテーション
1 脳卒中後のリハビリテーション
2 運動器疾患のリハビリテーション
D 廃用症候群のリハビリテーション
1 認知症リハビリテーション
2 フレイル・サルコペニアとリハビリテーション
E 非薬物療法としてのリハビリテーション
1 物理療法・アロマセラピー
2 ロボットの活用
終章 高齢者の在宅医療とエンドオブライフケア (鳥羽研二)
1 高齢者の在宅医療における現状と課題
2 人生の最終段階における在宅医療
3 高齢者の在宅医療における看護師の役割への期待
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。