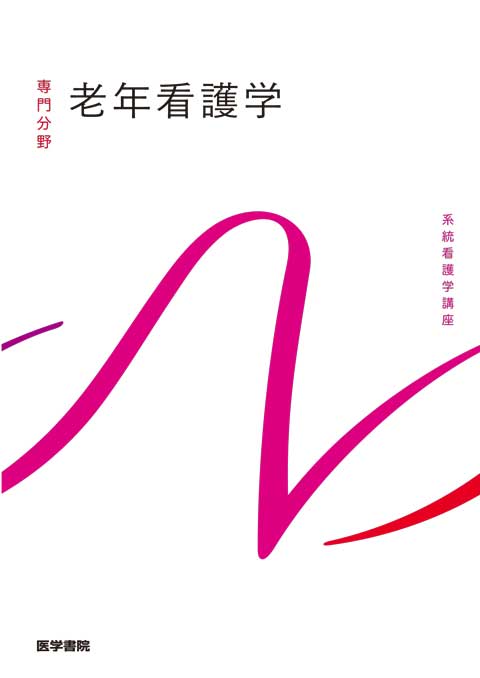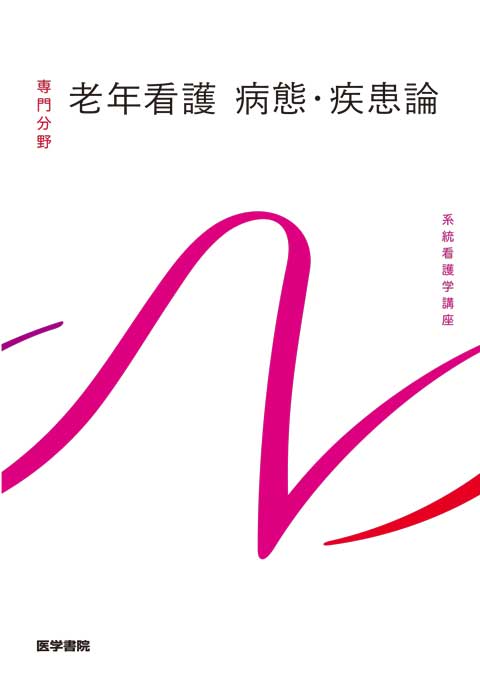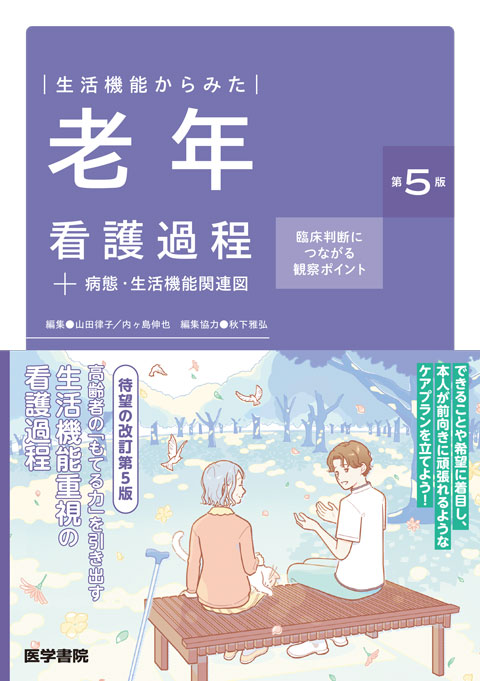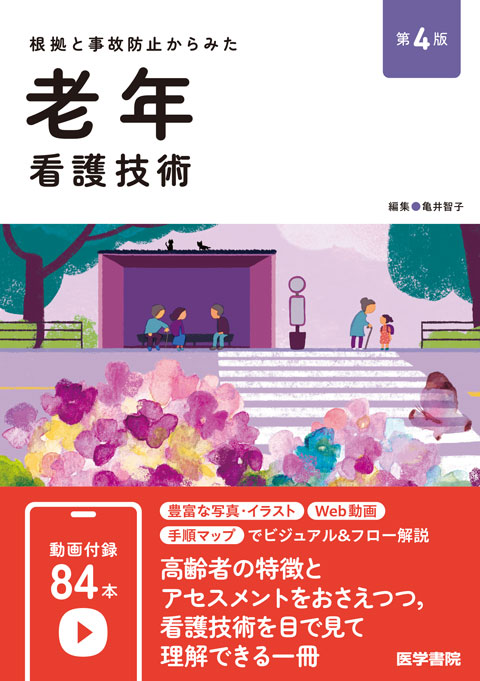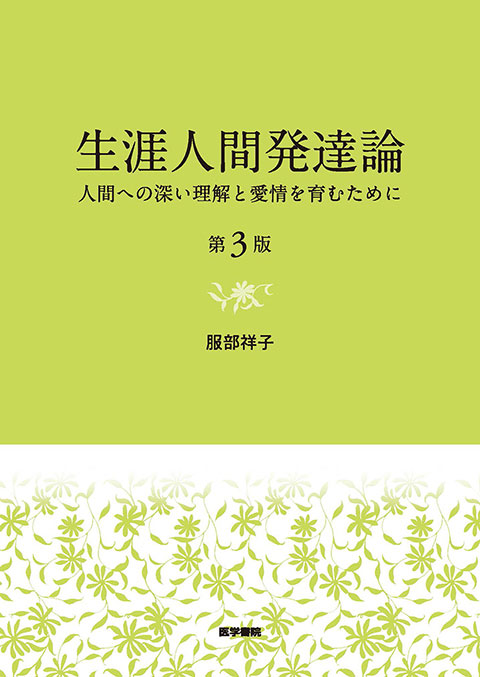老年看護学 第10版
もっと見る
- 第10版では新しい国家試験出題基準に対応し、目次・構成および内容を見直しました。
- 地域包括ケアはもちろんのこと、地域共生社会の実現を見すえた看護師の役割などについても言及しました。
- 加齢による身体的・心理的な変化についての記述を増やし、高齢者をより深く理解できるようにしました。また、オーラルフレイルなど近年注目される事項についても新しく盛り込みました。
- 自宅や施設における看取りが増えていることをふまえ、「場所別のエンドオブライフケア」の内容を充実させました。
- 「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はしがき
2017(平成29)年12月に第9版の「はしがき」を書いてから7年が経過した。この間の最大のできごとは,2020(平成2)年に始まった新型コロナウイルス感染症の大流行である。緊急事態宣言が発出されるなか,オンラインによる授業や,臨地実習の見合わせへの対応など,教育をとめないために知恵を絞る日々を過ごした。一方,高齢者はさらに困難な状況にみまわれた。自宅で日常を暮らす高齢者は,外出の見合わせや,子や孫の帰省の差し控えなどによって,親しい人との交流に大きな制約を受けた。さらに病院や施設で療養生活を送る高齢者においては,面会の中止,食堂での食事やレクリエーション,行事の見合わせなど,ここでも人との交流は最小限に制約された。平均寿命ののびをとめるほどの打撃から,その後少しずつ日常を取り戻し,現在はまだその途上にある。
2020年10月に保健師助産師看護師学校養成所指定規則が一部改正され,2022(平成4)年4月の新入生から新カリキュラムによる教育が始まった。老年看護学に関しては,臨地実習の単位の一部を各教育機関の裁量で自由に設定できるようになった。そのため,この改正によりいままで以上に教育機関が掲げるポリシーにそった講義・演習・実習が組みたてやすくなった。感染症流行下で必死に開発したシミュレーション教育やオンラインの活用を,さらに発展させていくことも期待されている。
本書の構成は,これまでの版を踏襲し,第1章から第3章を総論,第4章から第9章を各論とし,看護師国家試験出題基準を網羅するような目次だてとしている。また,第9版発刊以降に示された新しい概念や法律・制度についても触れている。
第1章では,老いを生きる高齢者その人に焦点をあて,老化理論や発達課題をわかりやすく紹介した。第2章では,現在の超高齢社会の様相を,統計資料を用いて提示するとともに,身体拘束や高齢者虐待などの倫理的課題,ならびに介護保険や成年後見制度など高齢者の自立と権利をまもるための社会制度について解説した。これらを受けて,老年看護の基本的な考え方,および老年看護に関連の深い理論を第3章で示した。
第4章以降の各論では既習の内容をふり返りつつ,加齢変化・病・障害を合わせもつ高齢者の心身をどのようにとらえ,それに基づいてどのように生活を整えるか,という学びを得られるよう書き進めた。第4章では,器官系統別の加齢変化とアセスメントの方法を具体的に解説した。第5章では,移動・食事・排泄・清潔といった生活行為と,それらが繰り返し展開される生活リズム,生活を円滑に進めるために不可欠なコミュニケーション,生きる基盤でもあるセクシュアリティについて,高齢者に特有の不具合と援助技術を解説した。さらに第6章では,高齢者に特有な症状や疾患・障害に応じた看護,第7章は健康状態や受療状況に応じた看護,第8章はエンドオブライフケア,第9章は場の特徴をふまえた看護,家族支援ならびに多様なニーズに対応するために不可欠な多職種連携について解説した。
今回の改訂では,高齢者や認知症の高齢者の方たちに対する否定的なイメージを読者に与えてはいないか,という点を心にとめながら執筆・校正作業にあたった。それは,2024(平成6)年1月に「認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し,相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進すること」を目的とする「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され,自分たちも,高齢者・患者・認知症の高齢者の方々とともに共生社会をつくっていく一員である,という意思をもつ看護職を送り出す責務を強く実感したためである。果たして,そのような内容や記述になっているのか,心もとない部分もあるが,どうぞ忌憚のないご意見を賜り,ともに本書を育てていくことができたなら,本書の執筆に携わった者として望外の喜びである。
2024年12月
著者を代表して
北川公子
目次
開く
第1章 老いるということ,老いを生きるということ (北川公子・竹田恵子)
A 老年看護学を学ぶ入り口
1 高齢者への深い関心
2 老年観
B「老いる」ということ
1 加齢と老化
2 加齢に伴う身体的側面の変化
3 加齢に伴う心理的側面の変化
4 加齢に伴う社会的側面の変化
C 老いを生きるということ
1 高齢者の定義
2 発達と成熟
3 健康と生活
第2章 超高齢社会と社会保障 (菅原峰子・舩橋久美子・内ヶ島伸也)
A 超高齢社会の統計的輪郭
1 超高齢社会の現況
2 高齢者と家族
3 高齢者の健康状態
4 高齢者の死亡
5 高齢者の暮らし
B 高齢社会における保健医療福祉の動向
1 高齢者にかかわる保健医療福祉の制度としくみ
2 地域共生社会と看護活動
C 高齢者の権利擁護
1 高齢者に対する差別と権利擁護
2 高齢者虐待
3 身体拘束
4 権利擁護のための制度
5 高齢者の権利擁護に対する老年看護への期待
第3章 老年看護のなりたち (北川公子)
A 老年看護の発展と定義
1 老年看護学教育の発展
2 老年看護の定義
B 老年看護の役割
1 注目すべき4つの視点
2 老年看護の6つの役割
C 老年看護における理論・概念の活用
1 老年看護における理論の活用
2 老年看護に役だつ理論・概念
D 老年看護に携わる者の責務
第4章 高齢者のヘルスアセスメント (三重野英子・小野光美・長瀬亜岐・若濱奈々子・内ヶ島伸也)
A ヘルスアセスメントの基本
1 ヘルスアセスメントの枠組み
2 高齢者総合機能評価(CGA)
B 身体の加齢変化とアセスメント
1 皮膚とその付属器
2 視聴覚とそのほかの感覚
3 循環器系
4 血液・造血器系
5 免疫系
6 呼吸器系
7 消化器系
8 代謝系
9 泌尿生殖器系
10 神経系
11 運動系
第5章 高齢者の生活を整える看護 (小薮智子・竹田恵子・山田律子・陶山啓子・小岡亜希子・三重野英子・末弘理惠・舩橋久美子・植田恵・宮林佐知)
A 日常生活を支える基本的活動
1 基本動作と環境のアセスメント
2 転倒やその他の事故のアセスメントと看護
3 フレイルと廃用症候群のアセスメントと看護
B 食事・食生活
1 食事・食生活の意義
2 高齢者に特徴的な変調
3 食事・食生活のアセスメント
4 食事・食生活の支援
C 排泄
1 排泄援助の基本
2 排泄のアセスメント
3 高齢者におこりやすい下部尿路症状とケア
4 高齢者におこりやすい排便機能障害による症状とケア
5 日常生活動作(ADL)能力に応じたケア
D 清潔
1 清潔の意義
2 高齢者に生じやすい清潔に関する健康課題
3 清潔のアセスメント
4 清潔の援助
E 生活リズム
1 高齢者と生活リズム
2 高齢者に特徴的な生活リズムの変調
3 高齢者の生活リズムのアセスメント
4 高齢者の生活リズムを整えるための看護
F コミュニケーション
1 高齢者とのコミュニケーションとかかわり方の原則
2 コミュニケーション能力のアセスメント
3 高齢者の状態・状況に応じたコミュニケーションの方法
G セクシュアリティ
1 高齢者のセクシュアリティ
2 高齢者ケアの場における性に関する問題
3 セクシュアリティのアセスメントと看護
第6章 健康逸脱からの回復を促す看護 (北川公子・若濱奈々子・高岡哲子・三重野英子・末弘理惠・長瀬亜岐・菅原峰子・蛯名由加里・荒木亜紀・初見温子・岡本聡美・山田律子)
A 回復プロセスと看護
1 健康逸脱から回復への段階
2 老年期における回復のとらえ方
B 症候のアセスメントと看護
1 発熱
2 痛み
3 瘙痒(かゆみ)
4 脱水
5 嘔吐
6 浮腫
7 倦怠感
8 褥瘡・スキン-テア
C 身体疾患のある高齢者の看護
1 脳卒中
2 心不全
3 糖尿病
4 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
5 パーキンソン病・パーキンソン症候群
6 感染症
7 肺炎
8 前立腺肥大症
9 骨粗鬆症
10 変形性関節症
11 骨折
D 認知機能障害のある高齢者の看護
1 うつ
2 せん妄
3 認知症
第7章 治療を必要とする高齢者の看護 (蛯名由加里・長瀬亜岐・小薮智子・竹田恵子・濱吉美穂・山地佳代)
A 検査を受ける高齢者の看護
1 高齢者が受けることの多い検査
2 検査を受ける高齢者への援助
B 救命救急を必要とする高齢者の看護
1 救急外来を受診する高齢者の特徴
2 救命救急場面における看護師の役割
C 薬物療法を受ける高齢者の看護
1 加齢に伴う薬物動態の変化
2 高齢者に特徴的な薬物有害事象
3 老年症候群と薬物有害事象
4 薬物療法における援助
D 手術を受ける高齢者の看護
1 手術を受ける高齢者の特徴
2 術前の看護マネジメント
3 術後の看護マネジメント
4 高齢者に特徴的な手術
E リハビリテーションを受ける高齢者の看護
1 高齢者のリハビリテーション
2 経過別リハビリテーション
F 入院治療を受ける高齢者の看護
1 治療を担う医療施設の状況
2 入院に伴う環境の変化と高齢者への影響
3 高齢者の入退院支援と看護
G 外来を受診する高齢者の看護
1 外来医療と高齢者の受診状況
2 外来を受診する高齢者の看護
第8章 エンドオブライフケア (北川公子)
A エンドオブライフケアの概念
1 エンドオブライフケアとは
2 高齢者のエンドオブライフケア
B エンドオブライフケアの構成要素
1 生が終わるときへの準備支援
2 意思決定への支援
3 苦痛を緩和するケア
C エンドオブライフケアの場
1 自宅におけるエンドオブライフケア
2 居住系施設におけるエンドオブライフケア
3 介護保険施設におけるエンドオブライフケア
第9章 生活・療養の場における看護 (北川公子・高岡哲子・松岡千代)
A 地域における高齢者への看護
1 社会参加の現状と支援
2 介護予防と生活支援
3 世代や分野をこえて支え,支えられる地域共生社会
B 保健医療福祉施設および居住施設における看護
1 介護保険施設における看護
2 地域密着型サービスにおける看護
3 サービス付き高齢者向け住宅における看護
C 高齢者を含む家族の看護
1 家族の健康と生活
2 家族への援助
D 多職種連携実践による活動
E 災害に伴う高齢者の看護
1 災害における高齢者の脆弱性
2 災害フェーズと高齢者支援
3 看護職に求められる役割
付章 看護過程の展開 (北川公子・松岡千代)
A 看護過程の考え方
1 看護過程の基本
2 高齢者の特徴をいかした看護過程の考え方
B 事例展開の実際
1 事例の状況設定
2 事例の展開
C 実習におけるヒヤリ・ハット
1 老年看護実習でおこりやすいヒヤリ・ハットとその要因
2 リスクの意識づけと事故の予防
巻末資料 認知症の評価尺度 (山田律子)
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。