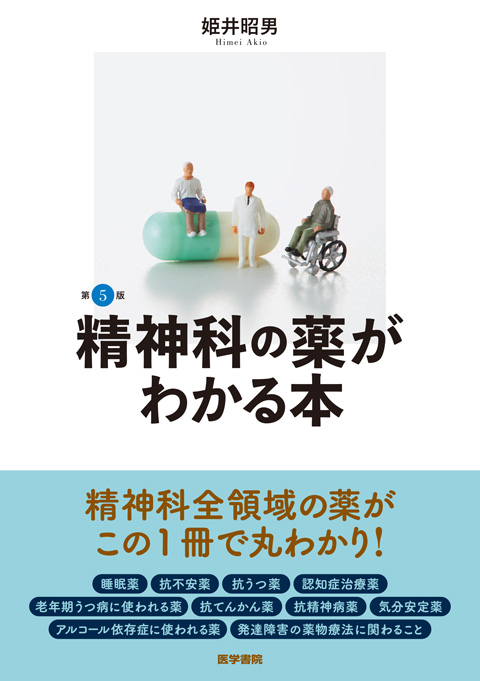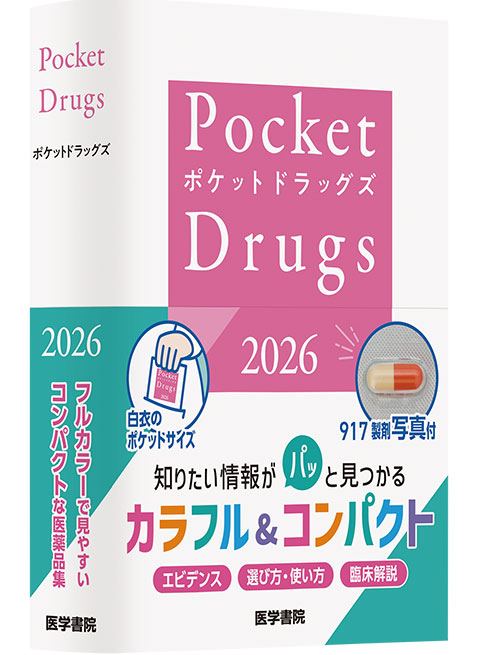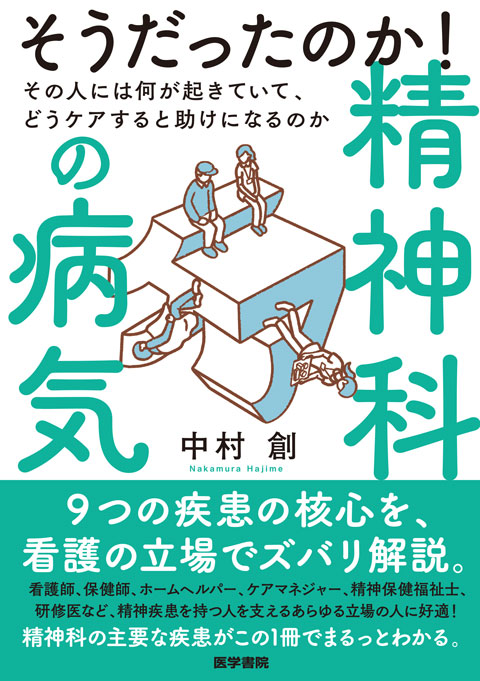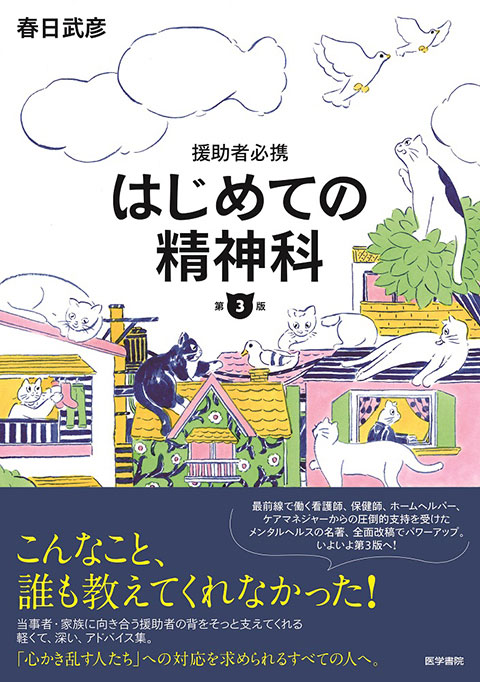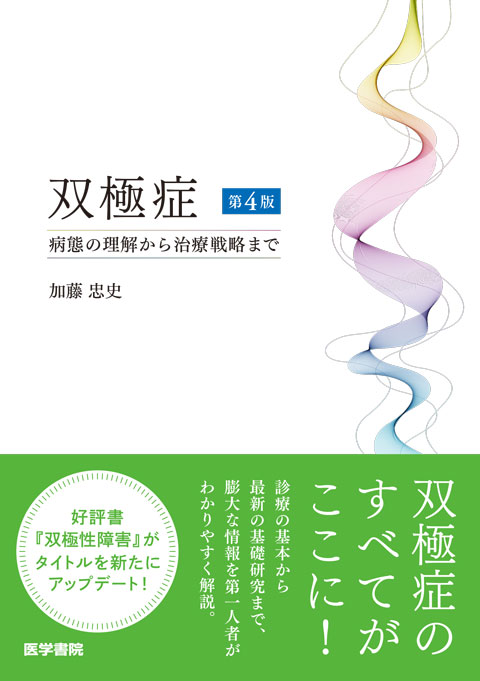精神科の薬がわかる本 第5版
精神科全領域の薬がこの1冊で丸わかり! ざっと広くのことを知りたい方へ。
もっと見る
精神科全領域の薬に関する最新かつ正確な情報を、第一線で診療を行う著者が厳選して紹介。精神科を専門とする医師、研修医、精神科看護師はもちろん、精神科以外の科の医療者で「精神科の薬」を使用する機会のある方にとっても有益な1冊。第5版では、なぜその薬が効くのかを知ることで、「精神科の薬」の誤用と乱用を防ぐことに注力しています。
| 著 | 姫井 昭男 |
|---|---|
| 発行 | 2024年02月判型:A5頁:240 |
| ISBN | 978-4-260-05377-8 |
| 定価 | 2,530円 (本体2,300円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第5版によせて なぜその薬が効くのか(作用機序)を知ることで、「精神科の薬」の誤用・乱用を防ぐ
近年メンタル不調者の増加が著しく、精神科・心療内科は予約が取れず、診療のキャパシティ自体が飽和状態にあり、受診さえできない地域もあります。また団塊の世代が後期高齢者となり、認知症がこの5年でこれまで以上に多くなることが予測されます。
現在の年齢で40歳以降は、精神科への偏見が残っている世代であるため、受診の敷居が高く、また、基礎疾患がありその人の“かかりつけ医”がいる場合には、メンタル不調であっても、まずかかりつけ医に相談する傾向があります。このような背景から、これからの時代は、精神科を専門としない医師も、精神科治療についての最低限の知識が必要になると思われます。本書は、そのような近い将来に備え、薬の使い方にとどまらず、精神科のベーシックな知識の学び直しができる内容を盛り込んでいます。
これまでの第1~4版では、完全に解明されていない仮説であっても、論理的で否定する意見がないものについては採用し、可能な限り新しい知見に基づいた「精神科の薬」の解説を心がけてきました。今回の改訂でもその理念に変更はなく、現時点で最新かつ矛盾のない薬理学的説明を執筆の下地としています。
さらに第5版では、章立ての大きな枠組みはこれまでを踏襲しながらも、新しい考え方の導入を試みました。これまでの『精神科の薬がわかる本』では、いわゆる適応症に沿った「精神科の薬」について解説してきましたが、精神薬理学のグローバルな考え方が、薬剤の主たる作用機序を基本として、疾病(適応症)に対してではなく、精神症状に対してどのように作用しているかで薬剤を分類するという方向に向かっていることから、今回の改訂ではその流れを意識しています。
以上、本書が、精神科治療薬がよりよく使用されるためのベーシックな教科書となること、また、これまでの版と同様に、精神科初学者、精神科認定看護師、多忙な臨床医の皆さまの薬理学的知見習得と知識の整理の一助となることを願っています。
2023年12月
姫井昭男
目次
開く
第5版によせて
第1章 精神科の治療における「精神科の薬」の役割
1 メンタル不調の原因
2 脳と精神活動
3 神経伝達物質に関連するトラブルと対応
4 メンタル不調を速やかに治療する重要性
第2章 「睡眠薬」と「抗不安薬」がわかる
1 マイナートランキライザー
2 「睡眠薬」がわかる
3 「抗不安薬」がわかる
4 新しい作用機序の睡眠薬
5 処方薬依存
第3章 「抗うつ薬」がわかる
1 「うつ」への対症療法に使用される「抗うつ薬」
2 「うつ」の治療薬の副作用
3 「うつ」の非薬物療法
「うつ」の治療に対するQ&A
第4章 「老年期メンタル不調に使う精神科の薬」がわかる
1 老年期の心身の変化
2 認知症のタイプと治療
3 認知症の周辺症状(BPSD)
4 老年期の「うつ」と認知症
5 「せん妄」の治療(薬物療法と生活リズム改善指導)
6 脳梗塞後遺症・頭部外傷後遺症の治療
認知症治療薬へのQ&A
第5章 「抗精神病薬」がわかる
1 抗精神病薬とは
2 定型抗精神病薬の特徴
3 非定型抗精神病薬の特徴
4 治療効果を低下させる副作用
5 治療効果を向上させるための剤形選択
抗精神病薬へのQ&A
LECTURE 薬剤特性の相補的組み合わせによる治療効果の向上と副作用の低減
第6章 「その他の精神科の薬」がわかる
1 気分安定薬
2 「アルコール依存症」に対する薬物療法
3 発達障害の薬物療法
その他の精神科の薬へのQ&A
索引
あとがき
PLUS ONE
神経伝達物質とその受容体は「鍵」と「鍵穴」
対症療法に用いられる神経伝達物質
精神症状と前頭葉機能
コンピュータの要素で精神活動をなぞらえてみる
非ベンゾジアゼピン系睡眠薬への過信
睡眠薬の諸問題
ベンゾジアゼピン系薬剤処方の留意点
ベンゾジアゼピン系薬剤の薬理と依存形成
そもそもの「行き違い」からはじまる処方薬依存
処方薬依存は低覚醒状態を継続するための手段か
ハームリダクション(Harm Reduction)という考え方
すべての責任は処方した医師にあるのか?
「うつ」に治療効果を示すその他の薬
SSRI、SNRIの薬理学的作用機序
NaSSAの薬理学的作用機序
トラゾドン
中止後発現症状(中断症候群)
SSRIによる中止後発現症状(中断症候群)を防ぐために
ボルチオキセチン
サポートは回復期にこそ必要
超高齢社会における「うつ」の精査と治療
周辺症状(BPSD)の発現機序
抗てんかん薬の薬理作用
老齢期に肥満になりやすい理由:活動エネルギーと「ミトコンドリア」
肥満が認知症の発症や進行を助長
生活習慣と健康格差
せん妄予防とメラトニン
NMDAグルタミン酸機能低下説と新しい精神病症状治療薬
抗コリン薬(抗パーキンソン病薬)
悪性高熱
ダントロレンナトリウムの作用機序
ハロペリドールデカン酸エステル注射剤
双極性障害II型ケースの増加
炭酸リチウムの薬理作用(仮説)
気分変動発生の原因と抑止
アルコール摂取によるグルタミン酸神経系とGABA神経系への影響
グルタミン酸神経系とGABA神経系の力関係
アルコール依存症の離脱症状における「うつ」の鑑別