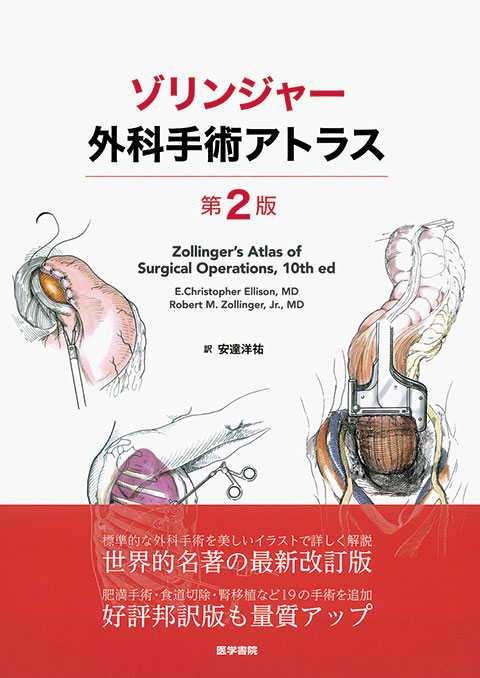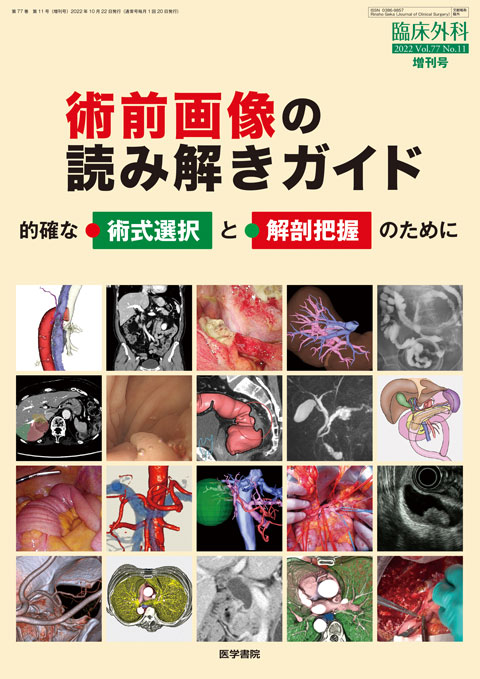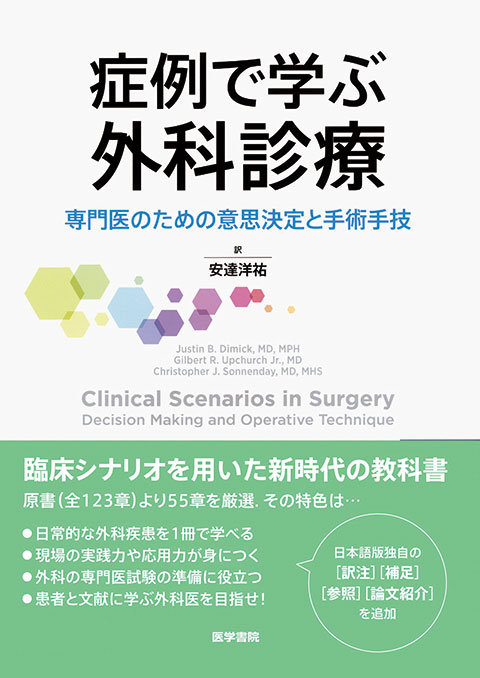肛門疾患診療の教科書[Web動画付]
エキスパートが伝授する診断・治療
豊富な経験とエビデンスに基づく本邦トップランナーの診かたと技法
もっと見る
痔核、痔瘻、裂肛、直腸脱の診かたと技法を本邦のトップランナーが解説するスタンダードテキスト。肛門の解剖から診断、治療・手術、合併症のリカバリーまで、豊富な経験とエビデンスに基づき詳述する。押さえるべきポイントを図、写真、動画を織り交ぜ、明瞭に示す。専門医をめざす初学者はもとより、一般・消化器外科医、ベテラン肛門科医まで、肛門疾患診療に携わるすべての方に有用な頼れる1冊。
| 編集 | 辻 順行 |
|---|---|
| 発行 | 2023年10月判型:B5頁:164 |
| ISBN | 978-4-260-05295-5 |
| 定価 | 8,800円 (本体8,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
序文
開く
序
現在,日本人の3人に1人は「痔主」であるとされ,疾患の中で最も頻度が高い疾患である.しかし,大学病院で肛門科の指導医が所属している施設は稀有であり,多くの場合,民間の専門病院に教育が委ねられている.また,肛門疾患に関する解説本は多く出版されているが,日本のトップランナーとして活躍し,十分な臨床実績と治療哲学を持つ肛門科の指導医による執筆本は少ない.
そこで,肛門の三大疾患である「痔核,痔瘻,裂肛」と「直腸脱」を対象として,その分野のトップランナーと目される指導医による考えと経験に基づいた解説本を企画した.
具体的には,肛門の解剖から始まり,疾患の診断法,陥りやすいピットフォール,鑑別疾患とその鑑別方法,さらに保存療法から手術へと至る各疾患のアルゴリズムを掲載し解説している.また,手術に関しては基本術式から始まり,トップランナーの指導医ならではの手術のポイント,合併症,合併症発生時のリカバリー法にも触れ,予後については短期的な結果ではなく,数年以上経過した成績を記載し,さらに国内外で行われている優れた手術法についても解説を加えた.共同執筆として,大阪中央病院の齋藤徹先生,奈良の錦織病院の錦織直人先生,福岡のくるめ病院の野明俊裕先生,熊本の大腸肛門病センター高野病院の高野正太先生に執筆をお願いした.
なお,各章の最後には,さまざまな症例を提示し,その疾患の診断法や治療法についても解説しており,経験豊富な専門医から研修医まで,幅広い医療関係者が理解しやすい解説本となっている.
筆者は,これまで日本大腸肛門病学会を中心に,大腸から肛門の疾患を学び,日本大腸肛門病学会の試験作成委員や作成委員長を経験してきたが,作成時に適切な解説本がなく難渋した.その経験から今回の解説本を企画したが,この本は単なる知識の羅列ではなく,文献の引用に頼らずに執筆者の血と汗の結晶による解説本であると自負している.肛門の三大疾患と直腸脱症例に関し,専門医には手術や診断,合併症発生時の手引書として,研修医には実際の臨床で困ったときの辞書として,明日からの実臨床に役立てて頂ければ幸いである.
2023年10月吉日
辻 順行
目次
開く
I. 肛門管の局所解剖と生理
1. 肛門の解剖
A 肛門と肛門管
B 肛門部の上皮
C 肛門管を構成する筋組織
D 肛門周囲間隙
E 肛門管の血流
F 肛門の神経
2. 肛門の生理
A 肛門の持続的閉鎖
B 排便に必要な動きとメカニズム
II. 肛門診察の実際
1. 診察設備と器具
A 診察台
B 診察時のライト
C 手袋
D 肛門鏡
E 診察用の潤滑剤
2. 診察の流れ
3. 問診
A 出血
B 痛み
C 脱出
D 腫脹
E 発熱
F 下着の汚れ
G 狭窄感
H 排便習慣
4. 診察の体位
A 左側臥位(シムス体位)
B 砕石位
5. 視診
6. 指診
A 裂肛
B 痔瘻,肛門周囲膿瘍
7. 肛門鏡検査
A ストランゲ型肛門鏡
B ケリー型肛門鏡
8. その他の検査
A 肛門エコー検査
B 怒責検査
C MRI(magnetic resonance imaging)検査
D 排便造影検査
E 直腸肛門内圧検査
F DP 3D-CT(dynamic pelvic 3D-CT)検査
III. 痔核
A. 外痔核
1. 診断・分類
2. 治療
B. 内痔核
1. 診断・分類
2. 治療法アルゴリズム
3. 保存的治療
4. 外来処置
5. 手術
A 結紮切除
B 硬化療法-ALTA療法
C ACL法
D 分離結紮法
6. 成績
A ゴム輪結紮法
B PAO
C LE
D ALTA療法
E ACL法
F 分離結紮法
7. 最近海外を中心に施行されている治療法
A MuRAL法
8. 症例提示
IV. 痔瘻
1. 痔瘻の発生と原因菌
2. 痔瘻の分類
A 隅越分類
B Parks分類
3. 痔瘻の診断
A 問診
B 視診
C 指診
D 内視鏡検査
E 肛門エコー検査
F MRI検査
G 瘻管造影
4. 痔瘻に対する治療法
5. 成績
A 低位筋間痔瘻
B 高位筋間痔瘻
C 坐骨直腸窩痔瘻
6. 最近海外を中心に施行されている治療法・
A LIFT法
B fibrin glue
C advancement flap repair
7. Crohn病に合併する痔瘻
A 臨床的特徴
B Crohn病の診断
C Crohn病による痔瘻の治療
D 若年者の痔瘻──Crohn病との関係
8. さまざまな病態を呈する痔瘻の症例
A 複数痔瘻
B 狭窄を伴う痔瘻
C 二次口を多数認める痔瘻
D 肛門のトーヌスが低下している痔瘻
V. 裂肛
1. 成因
2. 分類
A 時期による分類
B 成因による分類
3. 診断方法
A 視診,指診
B 肛門鏡診
4. 治療
A 保存的治療
B 手術療法
5. 各術式と成績
A 肛門拡張術
B 側方内肛門括約筋切開術(LIS)
C 肛門形成術
D その他の形成術
E 薬物による肛門括約筋弛緩
F ガイドラインに掲載されていない手術──裂肛切除
6. 裂肛に対する最先端治療
A 幹細胞移植
B 仙骨神経刺激療法
C 脛骨神経刺激療法
7. 症例提示
VI. 直腸脱
1. 病態・分類
2. 診断
A 問診
B 視診,触診
C 怒責検査
D 排便造影,骨盤内多臓器造影
E 直腸肛門内圧検査
F 腹部CT
3. 治療法アルゴリズム
4. 術式選択
5. 手術
A 経会陰手術
B 経腹手術
6. 成績
A 経会陰手術
B 経腹手術
7. 症例提示
索引
書評
開く
魅力あふれる新世代のバイブル的書籍
書評者:黒川 彰夫(『日本臨床肛門病学会雑誌』前編集委員長/黒川梅田診療所院長)
本邦においては,大腸疾患についての専門書や教科書は多く見られるが,肛門疾患に関する成書は非常に少ないのが現状である。日常診療では頻度の高い極めてありふれた疾病であるにもかかわらずである。結果,卒後研修のころから一般的に「痔」と呼んで軽んじて扱う傾向にある。その原因は,以前から肛門専門医の間で論じられてきたように,大学の医学教育や卒後研修の中で「肛門病学」が体系立て指導されていない点にあるのみならず「肛門病学」の存在すら認められていない点にあるのではないだろうか。
過去にいくつかの専門書や教科書の分担執筆に携わった者として,今回の辻順行先生の編集された『肛門疾患診療の教科書』は,驚きや感動を感じた点があまた認められた。
まず,第一に斬新な手法で手術の動画を採用していることである。執筆者が自らの手術手技を半永久的にこのような形で示し残すことは,学会やセミナーなどでの発表・供覧とは趣も度量も随分異なると思われる。分担執筆者の若手の登用の意味はここにあるように思えた。いずれにしても,普く読者にとっては,各執筆者の動画を見ることによって二次元から奥行きが加わった三次元の状態をリアルの世界として感じ取ることができるであろう。したがって,これから肛門疾患について勉強しようとする医師たちはもちろんのこと,自らの手技を再確認,再考しようとしている医師たちにとっても,それぞれの日常診療に大変参考になる書籍となると考える。各分野でこのような形式の専門書が増えてきていることは,小生のような老兵にとっては隔世の感がある。しかし,日常診療においては実際の診療や手術などを経験し,自己研鑽に励んで生の感性を養うことも非常に大切であると考える。
辻先生との出会いは30余年前になるが,若手のリーダーとしてその頃から学会活動や論文執筆などで頭角を現していた。痔瘻の診断に経肛門的超音波検査が有用であるという学会発表や論文で注目を集めたのを鮮明に記憶している。その後,彼はさまざまの苦難を乗り越え,ついに2023年11月に第78回日本大腸肛門病学会学術集会を開催し,大成功を収めたのである。わが事のように嬉しく感じたのと時を同じくして本書が発刊されたのである。編集者でもある先生が「序」で述べておられるように,まさに執筆者の血と汗の結晶の表れとして本書が出版されたように私も感じながらこの書評を著わしたのである。
本書が,これから肛門病学を学ぼうとしている外科の先生だけではなく,内科や産婦人科の先生方にも教科書として日常診療に利用されることを期待している。
付録・特典
開く
![肛門疾患診療の教科書[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8216/9743/0895/112203.jpg)
![「おしりの病気」アトラス [Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/3516/0459/0138/107242.jpg)