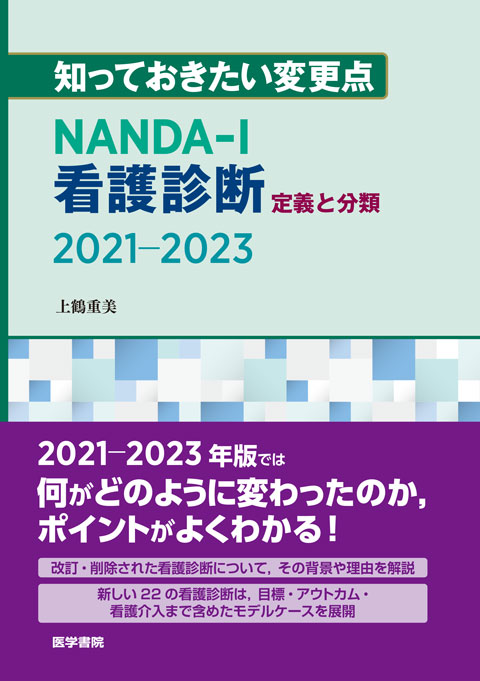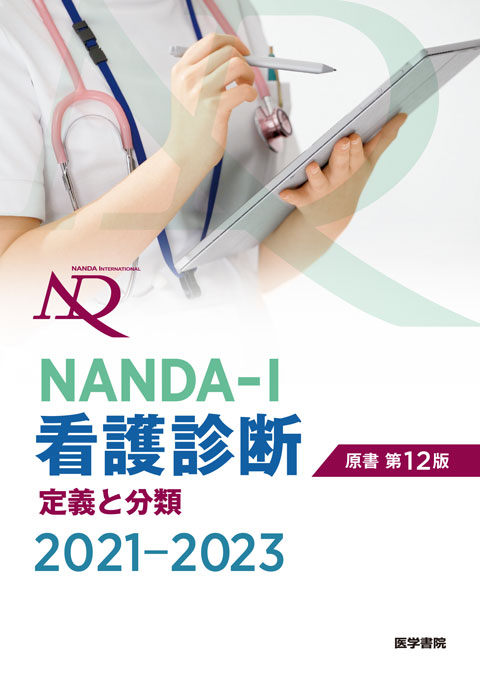知っておきたい変更点 NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023
2021-2023年版では何がどのように変わったのか、ポイントがすぐにわかる!
もっと見る
『NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023』の変更点のうち、おさえておくべき事項を、日本の状況をふまえながらコンパクトに解説。加えて、看護診断の活用に役立つ2つのモデル(看護実践の3部構造モデル・臨床推論モデル)も紹介。新しい22の診断は、モデルケースを使い、臨床推論モデルに則って、目標・アウトカム・介入までを含んだ展開例を提示。原著編者・日本語版訳者による確かな解説で知識をアップデート!
| 著 | 上鶴 重美 |
|---|---|
| 発行 | 2022年02月判型:A5頁:128 |
| ISBN | 978-4-260-04808-8 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
- 販売終了
- 電子版を購入( 医書.jp )
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
本書は,初めて看護診断を学習する方に向けた解説書ではありません。以前から看護診断をお使いの方々に, 『NANDA-I 看護診断――定義と分類2021-2023 原書第12版』では何がどのように変わったのか,変更点を効率よく把握していただけるようにまとめています。看護診断の基本を学習する必要のある方は,まずは『NANDA-I 看護診断――定義と分類2021-2023 原書第12版』をお読みください。看護診断の基本やNANDA-I 看護診断分類法の理解に役立ちます。
2021-2023年版のNANDA-I 看護診断分類には,今回も多くの改訂や追加があり,より一層洗練されたものになりました。たくさんの変更点があるということは,看護の知識がつねに進化し続けているという証しでもあります。また,NANDA-Iが看護診断用語集に最新の知識を確実に反映させていることも意味しています。
本書では,『NANDA-I 看護診断――定義と分類2021-2023 原書第12版』の「2021-2023年版の最新情報」(pp.3-20)の項目をより詳しく解説しています。掲載されていない変更点や訳語の変更についても,原書編集者・日本語版翻訳者の立場から解説しています。さらに,新たに追加された診断のうち,22の看護診断については,イメージしやすいようにモデルケースを使って,目標・アウトカム・介入を含んだ展開例もご紹介しています。
2021-2023年版の変更点についての理解がより深まること,教える立場の方々にお役立ていただけること,現場に最新の看護診断が確実に浸透することを願っています。
2022年1月
上鶴重美
目次
開く
はじめに
院内情報システム(電子カルテを含む)における『NANDA-I 看護診断』利用ライセンス取得案内
第1章 何がどう変わったか
改訂版の全般的な特徴
エビデンスの強化
診断の焦点の強調
診断手がかり用語の統一
ハイリスク群の修正
日本語訳の一貫性強化
看護診断名への年齢軸の追加
診断手がかり用語のコード化
看護診断が追加された:29診断
新規の診断の焦点を基に新たに追加された看護診断:12
既存の診断の焦点を基に新たに追加された看護診断:15
変更された診断の焦点を基に新たに追加された看護診断:2
看護診断名が変わった:4診断(英語は17診断)
英語の診断名と日本語訳の両方が変わった看護診断:15
英語の診断名のみ変わった看護診断:2
日本語訳のみ変わった看護診断:28
看護診断が改訂された:67診断以上
看護診断が削除された:6診断
看護診断の全般的な定義が少し変わった
英語版のみの変更点:2か所
日本語版のみの変更点:3か所
ヘルスプロモーション型看護診断の定義が変わった
エビデンスレベルの判定基準が変わった
第2章 課題と今後の取り組み
エビデンスの強化にむけて
他にも改訂すべき看護診断がある
「診断の焦点」は人間の反応か?
症状か看護診断か?
適切な看護診断の粒度(細かさ)は?
日本独自の妥当性検証の必要性
第3章 看護診断の活用に役立つ2つのモデル
看護実践の3部構造モデル
看護実践における看護診断の位置づけ
第1領域:医学診断に基づく看護実践
第2領域:看護診断に基づく看護実践
第3領域:施設内手順に基づく看護実践
看護診断は共同問題とは違う
臨床推論モデル
看護過程の原動力としての看護診断 臨
臨床推論モデル(1):問題焦点型看護診断
問題焦点型看護診断:診断推論
問題焦点型看護診断:目標・アウトカム推論
問題焦点型看護診断:看護介入推論
問題焦点型看護診断:評価推論
問題焦点型看護診断:統合
臨床推論モデル(2):リスク型看護診断
リスク型看護診断:診断推論
リスク型看護診断:目標・アウトカム推論
リスク型看護診断:看護介入推論
リスク型看護診断:評価推論
リスク型看護診断:統合
臨床推論モデル(3):ヘルスプロモーション型看護診断
ヘルスプロモーション型看護診断:診断推論
ヘルスプロモーション型看護診断:目標・アウトカム推論
ヘルスプロモーション型看護診断:看護介入推論
ヘルスプロモーション型看護診断:評価推論
ヘルスプロモーション型看護診断:統合
第4章 クイックマスター! 新看護診断22
逃走企図リスク状態
運動習慣促進準備状態
非効果的健康維持行動
健康自主管理促進準備状態
非効果的家族健康自主管理
非効果的家事家政行動
非効果的乳児吸啜嚥下反応
機能障害性尿失禁
混合性尿失禁
排便抑制障害
非効果的リンパ浮腫自主管理
血栓症リスク状態
思考過程混乱
家族アイデンティティ混乱シンドローム
悲嘆促進準備状態
非効果的ドライアイ自主管理
小児転倒転落リスク状態
乳頭乳輪複合体損傷
小児褥瘡リスク状態
新生児低体温
小児発達遅延リスク状態
乳児運動発達遅延リスク状態
書評
開く
臨床推論モデルにも注目したい,待ちに待った1冊
書評者:木村 瑞恵(釧路赤十字病院看護部 看護師長)
当院が看護診断に取り組み始めて今年で9年目になります。導入してから5年ほどが経過した2018年頃は,まだ正確な看護診断ができない状況に頭を悩ませていました。そんな時に出会ったのが,『知っておきたい変更点 NANDA-I看護診断 定義と分類 2018-2020』です。その中で「臨床推論モデル」を知り,目からうろこが落ちる思いでした。このたび発行された『知っておきたい変更点 NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023』は,先述した2018-2020年版の改訂版です。『NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023』の変更点を解説しつつ,「臨床推論モデル」もアップデートされた,待ちに待った1冊です。
正確な理解につながる分かりやすい解説
第1章では,追加や削除,改訂された看護診断に関して,根拠を基に分かりやすく解説されています。
第2章では,看護診断は常に進化し続けていることが強調されています。この章では,「症状か看護診断か?」の項に注目しました。というのも,当院は「急性疼痛」「慢性疼痛」を看護診断することが多いのですが,疼痛という症状そのものを看護介入で解決することは難しいと常々考えていたからです。2021-2023年版も「急性疼痛」「慢性疼痛」で変わりありませんが,本書で提案されている「非効果的疼痛コントロール」に将来変更されると,対象者の行動変容に介入できると納得しました。
第3章では,私が感銘を受けた「臨床推論モデル」について詳しく記載されています。「臨床推論モデル」は,看護診断を真の看護過程の原動力として活用するための優れた思考過程です。当院では看護診断を使うことは定着してきましたが,看護診断と看護計画が連動していないことが多々あります。このままでは看護診断をしても,絵に描いた餅になってしまうと悩んでいた時に,この「臨床推論モデル」と出会いました。
このモデルは,看護過程に含まれる4つの臨床推論(診断推論,目標・アウトカム推論,看護介入推論,評価推論)から成り立っています。今回の改訂版では,診断の根拠となる診断指標に対しては対症的ケア,診断の原因となる関連因子に対しては根治的ケアで介入することが,より分かりやすく記載されています。
当院の取り組みとして,各部署の看護診断の推進者に対して臨床推論モデル研修を実施し,事後課題として,実際の患者に対して臨床推論モデルを活用した看護計画の立案を設定しました。提出された事後課題を見ると,当院の現状がよく分かり,適切な看護診断なくしては「臨床推論モデル」を活用できないことを実感しました。
第4章では,新たに追加された看護診断について,モデルケースを挙げ,臨床推論モデルで展開しています。モデルケースによって,新たに追加された看護診断のみならず,臨床推論モデルの理解も深まります。
看護の力が試される時代に看護診断を
高齢者は特にこれといった疾患がなくても活動量が減って歩行障害を起こし,セルフケアができなくなることがあります。このように医学では解決できないことも多く,高齢化に拍車がかかる今,看護の力が試される時代になっています。看護独自の力でアウトカムを出すために,看護診断は強力なツールです。本書は改訂されたNANDA-I看護診断を理解するための優れた1冊です。
学生に伝えたい看護診断の理解に役立つ2つのモデル
書評者:和智 幸江(横浜市病院協会看護専門学校教務課長)
本書と本講義動画は,看護を実践する人はもちろんのこと,看護を学ぶ人,教える人にとって看護診断の理解を深めるために役立つものです。
『NANDA-I看護診断 定義と分類』は3年ごとに改訂されますが,今版はエビデンス強化,診断手がかり用語の統一などにより,多くの看護診断が改定されていて理解に難儀します。本書は,変更のポイントとその理由をわかりやすく解説しています。本書の著者であり,NANDAインターナショナル前理事長の上鶴重美先生による講義動画『〔講義動画 NANDA-I看護診断 徹底解説〕特別編 知っておきたい変更点 NANDA-I看護診断 定義と分類 2021-2023』を併せて視聴すると,何がどう変わったのかをさらに整理して理解できます。看護診断の開発過程において,それぞれの看護診断がどのように誕生し変更されてきたのか,それぞれの看護診断に内在する課題などを知ることで,本来どのような事象に対応した看護診断なのかが明確になります。また,看護診断を提案した各国の社会文化的背景や医療の問題に触れ,さらに関心が深まります。
本書では看護診断の理解に役立つ2つのモデルを紹介しています。その1つ「看護実践の3部構造モデル」は,看護実践を「医学診断に基づく看護実践」「看護診断に基づく看護実践」「施設内手順に基づく看護実践」の3つの主な領域に分けて説明し,看護師独自の判断に基づく看護介入の根拠としての看護診断の位置付けを明示しています。私は,看護独自の機能とは何かを問い,常にそこに立ち戻って看護を考えてほしいという願いを込めて,看護過程の授業でこのモデルを学生に紹介しています。
もう1つは,「臨床推論モデル」です。私は上鶴先生の主催する看護ラボラトリーのセミナーで初めてこのモデルに出合いました。先生はこのモデルを説明する時に,看護診断を“湖を走る船のエンジン”と例えました。このモデルは,“アセスメントから看護診断の過程が根拠(診断指標・危険因子・関連因子)を持ってなされていれば,おのずと目標やアウトカムそして看護介入が導きだされる。つまり,看護診断は看護過程の原動力となっている”ということを合点させてくれます。以来,私は,このモデルを使って看護過程と看護診断の関係を学生に説明しています。本書では,臨床推論モデルを看護診断の3つのタイプ(「問題焦点型看護診断」「リスク型看護診断」「ヘルスプロモーション型看護診断」)ごとに説明しています。このモデルを使ってタイプごとに看護診断と看護過程の関係を理解していくと,看護過程を学び始めたばかりの学生も“なるほど”とうなる必須の思考ツールになります。
さらに,本書では,新しく誕生した22の看護診断を,モデルケースを使って解説しています。私はこのモデルケース付きの解説を読みたくて本書の出版を心待ちにしておりました。本書では,前述の「臨床推論モデル」を使ってアウトカムや介入も含めてモデルケースを解説しているのでさらに理解しやすくなっています。
本書は,看護診断を基本から学びたい人にとっても役立つ1冊です。看護診断の構造的な理解を助けてくれること間違いなしのお薦めの良書です。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。