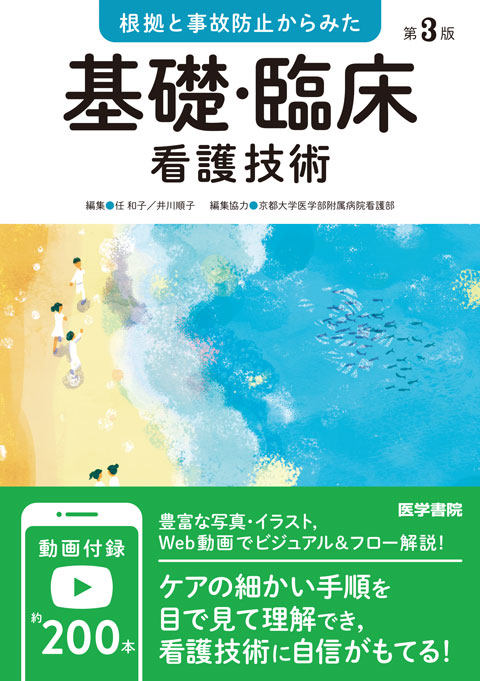根拠と事故防止からみた
基礎・臨床看護技術 第3版
基礎教育と臨床とを橋渡しする看護技術テキスト
もっと見る
本書は基礎看護技術の内容はもちろん、臨床現場で実際に行われている看護技術をも幅広く網羅し、基礎教育と臨床とのギャップを可能な限り埋めようと、根拠、コツ、注意点など現場で押さえておきたい情報を豊富に掲載している。また、写真と動画で看護技術の細かい手順を目で見て理解できる。今回の改訂では、学生の到達目標をはじめ最新の情報にアップデート。動画約200本がインターネット上でいつでも閲覧可能。
| シリーズ | からみた看護技術 |
|---|---|
| 編集 | 任 和子 / 井川 順子 |
| 編集協力 | 京都大学医学部附属病院 看護部 |
| 発行 | 2021年10月判型:A5頁:864 |
| ISBN | 978-4-260-04790-6 |
| 定価 | 6,050円 (本体5,500円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
2025.12.26
-
正誤表を追加しました
2022.03.29
- 序文
- 目次
- 付録・特典
- 正誤表
序文
開く
はじめに
医療技術の進歩や,医療安全に対する意識の高まり,インフォームド・コンセントの概念の普及などにより,療養生活支援の専門家としてベッドサイドで働く看護師に求められる知識・技能レベルは顕著に上がっています.そのため,臨床現場をとりまく切実な状況に対応し,療養生活支援の専門家として看護師が活躍するために,基礎教育と臨床現場が協働することが不可欠となっています.
本書はタイトルを「基礎・臨床看護技術」としたように,基礎教育と臨床現場のシームレスな連携をより一層促進することを目的に企画されたテキストです.
厚生労働省の「看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書」および「看護師教育の技術項目の卒業時の到達度について」(厚生労働省通達)に準じて構成しており,基礎教育で修得すべき技術項目を網羅的に盛り込んでいます.また,同じく厚生労働省の「新人看護職員研修ガイドライン」の「看護技術についての到達目標」も視野に入れており,活用範囲は学生時代だけではなく就職してからも,どのような医療機能の病床や配属部署であっても幅広く活用できるものとなっています.
本書の第一の特長は,臨床の第一線で最新のエビデンスを日々取り入れて看護ケアの質を改善している看護師と,基礎教育で看護技術を教授し病院実習でベッドサイドに出向いて学生指導をしている看護教員が話し合い,両者ともに納得できる水準にしている点です.
第二の特長は,タイトルにあるように「根拠と事故防止」の視点から,手順の根拠を説明するとともに,「Safety Check」欄を設けていることです.
そして,第三の特長は,ビジュアル化です.実際に普及している設備や物品を採用し,写真を取り入れ,イラストも多く使用しています.また,約2~3分の動画を192本収載し,インターネット上でいつでもどこでも閲覧が可能です.さながら実体験しているように,看護師の視線で写真や動画を撮影するといった工夫もしています.何度も繰り返し自己学習することで,適切な動作が身につきます.
今回の改訂では,最新の情報に更新し,読者の方々からのご意見も可能な限り反映いたしました.
本書は,基礎教育における看護技術の演習や実習,新人看護師の研修ばかりではなく,中途採用者の研修や病院の看護手順を作成する際にも活用できると考えます.みなさんに使っていただいて,新しいエビデンスを加えながら末永く愛されるテキストになることを願っています.
2021年9月
著者を代表して 任 和子
目次
開く
はじめに
本書の構成と使い方
動画一覧
動画の使い方
第1章 環境調整技術
1 病床環境の調整
2 ベッドメーキング
3 リネン交換
第2章 食事援助技術
1 栄養状態および食欲・摂食能力のアセスメント
①栄養状態のアセスメント
②水分・電解質バランスのアセスメント
2 食事介助
①実施前の評価
②食事摂取の介助
3 摂食・嚥下訓練
①実施前の評価
②間接訓練
4 経腸栄養法
①栄養剤の種類と特徴
②経鼻経管栄養法
③胃瘻からの栄養法
第3章 排泄援助技術
1 排尿・排便のアセスメント
2 自然排尿および自然排便の介助
①トイレにおける排泄援助(移動が可能な場合)
②床上排泄援助
③おむつによる排泄援助(おむつ交換)
④失禁のケア
3 導尿
①一時的導尿
②持続的導尿
4 排便を促す援助
①グリセリン浣腸
②摘便
5 ストーマケア
①ストーマ装具の交換方法
②ストーマからの導尿の実際
第4章 活動・休息援助技術
1 体位
2 体位変換
3 移動(歩行介助)
4 移乗・移送
①車椅子への移乗と移送
②ノーリフト
③ストレッチャーへの移乗と移送
5 廃用症候群予防
①廃用症候群リスクのアセスメント
②他動・自動運動(関節可動域訓練)
6 睡眠・覚醒の援助
第5章 苦痛の緩和・安楽確保の技術
1 体位保持(ポジショニング)
2 罨法・体温調整
第6章 清潔・衣生活援助技術
1 入浴・シャワー浴
①入浴
②シャワー浴
2 全身清拭・寝衣交換
①全身清拭(ベッドバス)
②寝衣交換
3 陰部洗浄
4 洗髪
5 部分浴
6 口腔ケア
①全面介助もしくは一部介助
②義歯の清掃と管理
7 整容
①ひげ剃り
②爪切り
③眼・耳・鼻の清潔
④フットケア
第7章 呼吸・循環を整える技術
1 酸素吸入療法
①酸素供給システム
②酸素の投与方法
2 吸引
①口腔・鼻腔内吸引
②気管吸引
③持続吸引(胸腔ドレナージ)
3 排痰ケア
①体位ドレナージ
②スクイージング
③その他の手技(咳嗽介助,ハフィング)
4 吸入(気道内加湿法)
5 人工呼吸療法
①人工呼吸器の準備
②人工呼吸器装着患者のケア
③人工呼吸器離脱後の患者ケア
6 末梢循環促進ケア
第8章 創傷管理技術
1 創傷管理
①創傷の観察
②創床環境の調整
③創傷処置(創洗浄と創保護)
④テープによる皮膚障害
⑤包帯法
2 褥瘡予防
①褥瘡発生リスクのアセスメント
②褥瘡発生リスクに対する予防ケア
第9章 与薬の技術
1 経口与薬
①内服薬
②口腔内薬
2 外用薬
①吸入
②点眼
③点鼻
④点耳
⑤経皮的与薬
3 直腸内与薬
4 注射・点滴静脈内注射・輸液
①注射器と注射針
②注射剤の準備
③皮下注射
④皮内注射
⑤筋肉内注射
⑥静脈内注射(ワンショット)
⑦輸液の準備(ミキシング・プライミング)
⑧点滴静脈内注射
⑨輸液ポンプの操作
⑩シリンジポンプの操作
⑪点滴静脈内注射における混注方法
5 中心静脈内注射・輸液
①中心静脈カテーテルの管理
②中心静脈カテーテル刺入部位の消毒
6 輸血管理
①血液製剤の種類と適応
②輸血の準備
③援助の実際
7 意を要する薬
①抗菌薬の用法と副作用の観察
②インスリン製剤の用法と注意事項
③カリウム製剤やキシロカインなどの致死的な薬
④麻薬の主作用と副作用の観察
⑤薬剤の管理
第10章 救命救急処置技術
1 心肺蘇生法
①BLSとALS
②一次救命処置(BLS)
③気管挿管の介助
④二次救命処置(ALS)
2 止血法
3 院内急変時の対応
①援助の実際
②救急物品(救急カートに常備される薬剤と資器材)の準備
第11章 症状・生体機能管理技術
1 身体計測
2 バイタルサイン
3 血液検査
①血液検査でわかること
②静脈血の採血
③動脈血採血の介助(血液ガス分析)
④血糖測定
4 尿検査
①尿検査でわかること
②尿の採取
③尿試験紙検査法
5 便検査(採便法)
6 喀痰検査(喀痰の採取)
7 生体検査時の援助
①心電図モニタ
②12誘導心電図(ECG)
③SpO2モニタ(パルスオキシメーター)
④その他検査における教育・注意事項
8 侵襲的処置の介助
①上部消化管内視鏡検査の介助
②下部消化管内視鏡検査の介助
③胸腔穿刺の介助
④腹腔穿刺の介助
⑤腰椎穿刺(ルンバール)の介助
⑥骨髄穿刺の介助
第12章 感染防止の技術
1 標準予防策(スタンダードプリコーション)の実施
①手指衛生
②個人防護用具
2 感染経路別予防策
3 洗浄・消毒・滅菌
①医療器材の取り扱い
②洗浄
③消毒
④滅菌
4 無菌操作
①滅菌物の取り扱い
②ガウンテクニック(滅菌ガウンの着用法)
5 感染性廃棄物の取り扱い
6 針刺し防止策
第13章 安全確保の技術
1 誤薬防止
2 患者誤認防止
3 転倒・転落防止
①リスクアセスメント
②具体的対策(環境整備)
4 抗がん剤曝露の防止
5 放射線曝露の防止
第14章 死の看取りの技術
1 臨終の見まもり
2 死後のケア
①死亡確認後の援助
②死後の処置
③患者のお見送り
④悲嘆ケア
資料
資料1 臨地実習において看護学生が行う基本的な看護技術の水準
資料2 看護師教育の技術項目と卒業時の到達度
資料3 新人看護職員研修:研修内容と到達目標
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。