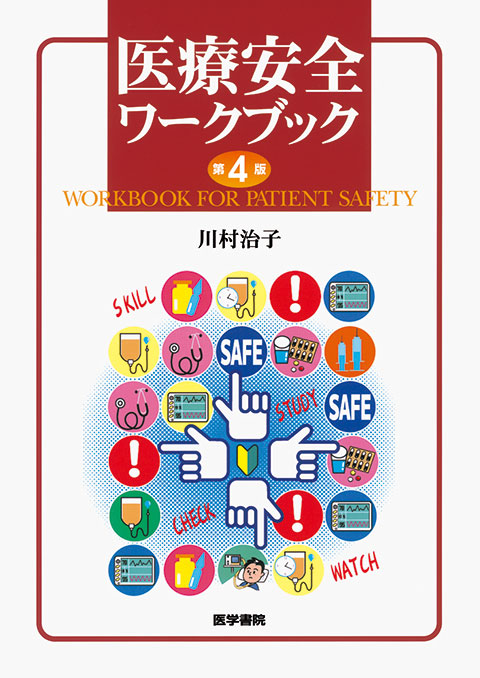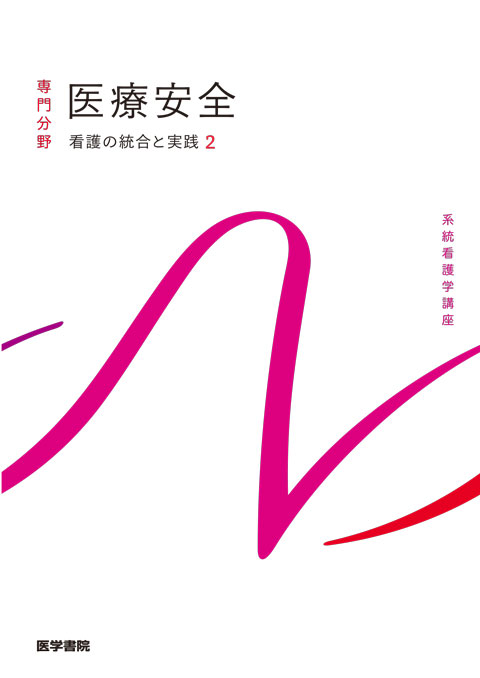医療安全ワークブック 第4版
看護師に必須の知識に絞り、根拠から解説! 患者の安全を守るための定本第4版
もっと見る
看護教育の中では抜け落ちてしまいがちだが、知らないと患者に重大な結果を招きかねない必須知識に絞り、その根拠からわかりやすく解説した医療安全の定本第4版。着実に進む医療安全対策を踏まえて記述を見直すとともに、後発医薬品を含む新たな薬剤や電子カルテでの問題など、UNIT1を中心に今日の看護現場の状況に即した内容にアップデート! 薬剤・機器の写真なども最新かつよりわかりやすいものに刷新。
| 著 | 川村 治子 |
|---|---|
| 発行 | 2018年11月判型:B5頁:258 |
| ISBN | 978-4-260-03588-0 |
| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第4版出版によせて
2004年の初版から14年,そして2013年の第3版から5年,このたび第4版を発行することができました。おかげさまで本書はこれまで,10万人を超える看護学生,臨床の若い看護師および教育担当者の皆さんに読んでいただけました。本当にありがたく思っています。この場をお借りして,心から御礼を申し上げます。
医療事故が社会問題化したのは,1999年のY大学病院の手術患者取り違え事故がきっかけでした。当時,来る日も来る日も医療事故がメディアを賑わせ,医療従事者にとっては,緊張と焦燥の日々が続きました。あれからもう20年です。看護職員の約半分が入れ替わった計算になります。
最近,当時話題になったものと同じ重大事故の報道を再び見聞きすることがあります。時が流れて人が変われば,また同じ事故が繰り返されるのではないかと不安になります。
本書の初版は,厚生労働省の補助金により,全国約200の急性期病院から収集した看護師のヒヤリ・ハット1万事例をもとに,その貴重な経験知を共有するために2004年に出版されました。とくに,UNIT1の「知らねばならない“危険”の知識」では,卒後2年以内の看護師の診療の補助業務の事例をもとに,若年看護師がおかしやすい間違いに的を絞って,“どこで,どのような間違いが,なぜ起き,どう防ぐのか”を具体的に学んでもらうものでした。以来,加筆・変更を加えながら版を重ねてきました。
今回の第4版での主な加筆・変更点は,UNIT1,UNIT2,UNIT4です。
まず,UNIT1の「知らねばならない“危険”の知識」では,取り上げた診療の補助業務やセクションの構造は変わっていませんが,ここ5~6年間に(公財)日本医療機能評価機構で収集された重要事例や発出された医療安全情報をもとに,第3版で触れていなかった注意点を加筆しました。また,ラベルが変更された注射薬やQ & Aに用いた注射薬の写真を一新,挿入事例もできるだけ新しいものに変更しました。また,どの部署に配属されても糖尿病患者に遭遇しやすいことを考慮して,インスリンや経口糖尿病薬における最近の進歩も盛り込みました。そのほか,今後発生の増加が危惧される抗血栓薬の術前の投与中止忘れ,術後の再開忘れの事故も取り上げました。
UNIT2の「看護業務に必要な計算ドリル」では計算問題の数値を一新し,UNIT4の「コミュニケーション・トレーニング」では,進行がん患者の自力排泄にこだわる心理への配慮をテーマにしたシーン「ベッドサイドでの排泄を求める看護師と進行がん患者との会話」を加えました。
第4版も,看護師の卒前・卒後の医療安全学習に少しでも役立ちますよう,心から願っています。
2018年10月 川村治子
2004年の初版から14年,そして2013年の第3版から5年,このたび第4版を発行することができました。おかげさまで本書はこれまで,10万人を超える看護学生,臨床の若い看護師および教育担当者の皆さんに読んでいただけました。本当にありがたく思っています。この場をお借りして,心から御礼を申し上げます。
医療事故が社会問題化したのは,1999年のY大学病院の手術患者取り違え事故がきっかけでした。当時,来る日も来る日も医療事故がメディアを賑わせ,医療従事者にとっては,緊張と焦燥の日々が続きました。あれからもう20年です。看護職員の約半分が入れ替わった計算になります。
最近,当時話題になったものと同じ重大事故の報道を再び見聞きすることがあります。時が流れて人が変われば,また同じ事故が繰り返されるのではないかと不安になります。
本書の初版は,厚生労働省の補助金により,全国約200の急性期病院から収集した看護師のヒヤリ・ハット1万事例をもとに,その貴重な経験知を共有するために2004年に出版されました。とくに,UNIT1の「知らねばならない“危険”の知識」では,卒後2年以内の看護師の診療の補助業務の事例をもとに,若年看護師がおかしやすい間違いに的を絞って,“どこで,どのような間違いが,なぜ起き,どう防ぐのか”を具体的に学んでもらうものでした。以来,加筆・変更を加えながら版を重ねてきました。
今回の第4版での主な加筆・変更点は,UNIT1,UNIT2,UNIT4です。
まず,UNIT1の「知らねばならない“危険”の知識」では,取り上げた診療の補助業務やセクションの構造は変わっていませんが,ここ5~6年間に(公財)日本医療機能評価機構で収集された重要事例や発出された医療安全情報をもとに,第3版で触れていなかった注意点を加筆しました。また,ラベルが変更された注射薬やQ & Aに用いた注射薬の写真を一新,挿入事例もできるだけ新しいものに変更しました。また,どの部署に配属されても糖尿病患者に遭遇しやすいことを考慮して,インスリンや経口糖尿病薬における最近の進歩も盛り込みました。そのほか,今後発生の増加が危惧される抗血栓薬の術前の投与中止忘れ,術後の再開忘れの事故も取り上げました。
UNIT2の「看護業務に必要な計算ドリル」では計算問題の数値を一新し,UNIT4の「コミュニケーション・トレーニング」では,進行がん患者の自力排泄にこだわる心理への配慮をテーマにしたシーン「ベッドサイドでの排泄を求める看護師と進行がん患者との会話」を加えました。
第4版も,看護師の卒前・卒後の医療安全学習に少しでも役立ちますよう,心から願っています。
2018年10月 川村治子
目次
開く
第4版出版によせて
初版はじめに
UNIT1 知らねばならない“危険”の知識
■注射
SECTION 1 医師の指示を正しく読み取る
2 不完全になりやすい口頭指示と指示受け
3 誤りやすい書き写し,転記ミスに要注意
4 注射の指示変更,その指示受けミスに要注意
5 注射薬のラベルの意味が理解できますか?
6 注射薬のさまざまな単位,1mL中の薬剤成分量もさまざま
7 1規格とは限らない注射薬,規格間違いも要注意
8 2つのキシロカインの不思議
9 似た輸液ボトルの間違い,輸液ボトル名の語尾の違いはなぜ?
10 インスリンの間違いは重大,正しい知識を身につけよう
11 点滴準備は1患者単位で,中断時には「済」と「未」を分ける工夫を
12 患者や注射の取り違えは意外と起こりやすい?
13 ちょっと待って! そのカリウムの側管注
14 危機を救うカテコールアミン,間違えば危機に!
15 ワンショット静注時には注入速度に注意しよう
16 複数チューブ挿入患者で投与経路を間違えない
17 正しく使おう三方活栓
18 点滴の滴数計算と滴数調節の間違いを防ごう
19 静脈穿刺時の神経損傷に気をつけよう
20 呼名応答のみでの確認は患者間違いの危険
21 三方活栓部のはずれで大出血,睡眠中でも接続部の確認を
22 点滴や静注時の皮下漏れ注意の薬剤と重大な漏れを知っておこう
23 遅れていたら速めて遅れを取り戻そう…それ,大丈夫?!
24 病棟ストック薬の入れ間違いが次の注射ミスにつながる
■ポンプ
SECTION 1 輸液ポンプに正しくチューブを装着しよう
2 “押し子はずれ”はシリンジポンプでの重大エラー
3 流量設定を間違えないようにしよう
4 フリーフローは最悪! ポンプのドアを開けるときは三方活栓を閉じよ
5 三方活栓開放忘れで閉塞アラーム,いきなり開放は厳禁
6 複数のポンプ,複数輸液ライン使用時の危険性を知っておこう
7 ポンプ操作間違いに関連する重要薬剤を知っておこう
■内服
SECTION 1 内服薬処方せんを正しく理解しよう
2 類似名称の内服薬に注意しよう
3 外用薬の間違いに注意しよう
4 鎮痛・解熱・抗炎症薬の頓用時に注意しよう
5 血糖降下薬(糖尿病薬)の与薬に注意しよう
6 内服与薬エラーが起きやすい状況を知っておこう
■輸血
SECTION 1 最悪の医療事故,血液型不適合輸血について知ろう
2 血液型の間違いで輸血事故,血液型判定用採血は最も危険な採血
3 血液製剤の取り違えで輸血事故,取り違えが起きる箇所はさまざま
4 患者間違いで輸血事故,血液製剤をつなぐそのときがクリティカルポイント
5 不適合輸血が起こったら…早期発見のためのサインを知っておこう
6 血液製剤によって保存方法と有効期限が違います
■経管栄養
SECTION 1 経管栄養での肺への誤注入と誤嚥を防ごう
2 胃管注入物の静脈内誤注入は重大事故,投与経路間違いに要注意
■チューブ類の管理
SECTION 1 チューブ留置患者への対応の原則を理解しよう
2 中心静脈ラインの接続部はずれ,閉塞,切断に注意
3 看護ケアによる気管チューブ・カニューレの抜け・はずれに注意
4 胸腔内は陰圧,胸腔ドレナージの取り扱いを誤らないように
■検査
SECTION 1 採血業務を安全・適切に行なおう
2 生体検査の準備や検査中・後の観察を的確に行なおう
3 検査移送・検査中のトラブルや転落を防止しよう
■酸素
SECTION 1 医療ガスと酸素ボンベについて
2 換気不全の慢性呼吸不全患者に酸素過流量吸入は危険
■その他
SECTION 1 ME機器による感電事故を防ごう
2 MRI検査に金属類の持ち込み禁!
UNIT2 看護業務に必要な計算ドリル
SECTION 1 ウォーミングアップ
STEP 1 重量の単位を理解する
2 容量の単位(液量の単位)を理解する
3 投与速度の単位,ガンマ(γ)も知っておこう
SECTION 2 指示薬剤量を液量「mL」に換算して取り出す
STEP 1 液状注射薬の指示量を液量に換算して取り出す
2 粉状注射薬の指示量を液量に換算して取り出す
3 小児用量を希釈して取り出す
SECTION 3 注入速度(流量,滴数)計算
STEP 1 輸液セット別に滴数を計算する
2 輸液セットの変更により滴数を変更する
3 輸液ポンプへの変更で滴数から時間流量を計算する
4 指示から滴数,流量を計算する
5 投与量,投与速度指示から流量を計算する
SECTION 4 酸素ボンベの残量,使用可能時間を計算する
STEP 1 酸素ボンベの残圧から残量を計算する
2 残圧と酸素吸入量からボンベ使用可能時間を計算する
UNIT3 リスクセンストレーニング
SCENE 1 患者の自力行動中の転倒・転落
2 認知症患者の危険行動
3 摂食嚥下障害患者への食事介助中の危険
4 ベッドから車椅子への移乗介助中の転倒の危険
5 小児のベッドからの転落の危険
6 廊下歩行中の転倒の危険
7 入浴中の患者の転倒,溺水,熱傷の危険
8 検査台からの転落の危険
9 排泄介助中の危険
10 ナースステーションでの認知症患者待機の危険
UNIT4 コミュニケーション・トレーニング
SCENE 1 末期がんの妻への処置を求める夫と看護師の会話
2 抗がん薬投与中の夫の悪化を心配する妻と看護師の会話
3 乳幼児を連れた面会家族と看護師の会話
4 排泄ケアで訪室した看護師と患者の会話
5 退院を翌日に控えた高齢患者と看護師の会話
6 急死した患者の家族と看護師の会話
7 内視鏡検査に関する外来看護師と患者の会話
8 ベッドサイドでの排泄を求める看護師と進行がん患者との会話
文献
UNIT1 解答と解説
UNIT2 解答と解説
あとがき
INDEX
初版はじめに
UNIT1 知らねばならない“危険”の知識
■注射
SECTION 1 医師の指示を正しく読み取る
2 不完全になりやすい口頭指示と指示受け
3 誤りやすい書き写し,転記ミスに要注意
4 注射の指示変更,その指示受けミスに要注意
5 注射薬のラベルの意味が理解できますか?
6 注射薬のさまざまな単位,1mL中の薬剤成分量もさまざま
7 1規格とは限らない注射薬,規格間違いも要注意
8 2つのキシロカインの不思議
9 似た輸液ボトルの間違い,輸液ボトル名の語尾の違いはなぜ?
10 インスリンの間違いは重大,正しい知識を身につけよう
11 点滴準備は1患者単位で,中断時には「済」と「未」を分ける工夫を
12 患者や注射の取り違えは意外と起こりやすい?
13 ちょっと待って! そのカリウムの側管注
14 危機を救うカテコールアミン,間違えば危機に!
15 ワンショット静注時には注入速度に注意しよう
16 複数チューブ挿入患者で投与経路を間違えない
17 正しく使おう三方活栓
18 点滴の滴数計算と滴数調節の間違いを防ごう
19 静脈穿刺時の神経損傷に気をつけよう
20 呼名応答のみでの確認は患者間違いの危険
21 三方活栓部のはずれで大出血,睡眠中でも接続部の確認を
22 点滴や静注時の皮下漏れ注意の薬剤と重大な漏れを知っておこう
23 遅れていたら速めて遅れを取り戻そう…それ,大丈夫?!
24 病棟ストック薬の入れ間違いが次の注射ミスにつながる
■ポンプ
SECTION 1 輸液ポンプに正しくチューブを装着しよう
2 “押し子はずれ”はシリンジポンプでの重大エラー
3 流量設定を間違えないようにしよう
4 フリーフローは最悪! ポンプのドアを開けるときは三方活栓を閉じよ
5 三方活栓開放忘れで閉塞アラーム,いきなり開放は厳禁
6 複数のポンプ,複数輸液ライン使用時の危険性を知っておこう
7 ポンプ操作間違いに関連する重要薬剤を知っておこう
■内服
SECTION 1 内服薬処方せんを正しく理解しよう
2 類似名称の内服薬に注意しよう
3 外用薬の間違いに注意しよう
4 鎮痛・解熱・抗炎症薬の頓用時に注意しよう
5 血糖降下薬(糖尿病薬)の与薬に注意しよう
6 内服与薬エラーが起きやすい状況を知っておこう
■輸血
SECTION 1 最悪の医療事故,血液型不適合輸血について知ろう
2 血液型の間違いで輸血事故,血液型判定用採血は最も危険な採血
3 血液製剤の取り違えで輸血事故,取り違えが起きる箇所はさまざま
4 患者間違いで輸血事故,血液製剤をつなぐそのときがクリティカルポイント
5 不適合輸血が起こったら…早期発見のためのサインを知っておこう
6 血液製剤によって保存方法と有効期限が違います
■経管栄養
SECTION 1 経管栄養での肺への誤注入と誤嚥を防ごう
2 胃管注入物の静脈内誤注入は重大事故,投与経路間違いに要注意
■チューブ類の管理
SECTION 1 チューブ留置患者への対応の原則を理解しよう
2 中心静脈ラインの接続部はずれ,閉塞,切断に注意
3 看護ケアによる気管チューブ・カニューレの抜け・はずれに注意
4 胸腔内は陰圧,胸腔ドレナージの取り扱いを誤らないように
■検査
SECTION 1 採血業務を安全・適切に行なおう
2 生体検査の準備や検査中・後の観察を的確に行なおう
3 検査移送・検査中のトラブルや転落を防止しよう
■酸素
SECTION 1 医療ガスと酸素ボンベについて
2 換気不全の慢性呼吸不全患者に酸素過流量吸入は危険
■その他
SECTION 1 ME機器による感電事故を防ごう
2 MRI検査に金属類の持ち込み禁!
UNIT2 看護業務に必要な計算ドリル
SECTION 1 ウォーミングアップ
STEP 1 重量の単位を理解する
2 容量の単位(液量の単位)を理解する
3 投与速度の単位,ガンマ(γ)も知っておこう
SECTION 2 指示薬剤量を液量「mL」に換算して取り出す
STEP 1 液状注射薬の指示量を液量に換算して取り出す
2 粉状注射薬の指示量を液量に換算して取り出す
3 小児用量を希釈して取り出す
SECTION 3 注入速度(流量,滴数)計算
STEP 1 輸液セット別に滴数を計算する
2 輸液セットの変更により滴数を変更する
3 輸液ポンプへの変更で滴数から時間流量を計算する
4 指示から滴数,流量を計算する
5 投与量,投与速度指示から流量を計算する
SECTION 4 酸素ボンベの残量,使用可能時間を計算する
STEP 1 酸素ボンベの残圧から残量を計算する
2 残圧と酸素吸入量からボンベ使用可能時間を計算する
UNIT3 リスクセンストレーニング
SCENE 1 患者の自力行動中の転倒・転落
2 認知症患者の危険行動
3 摂食嚥下障害患者への食事介助中の危険
4 ベッドから車椅子への移乗介助中の転倒の危険
5 小児のベッドからの転落の危険
6 廊下歩行中の転倒の危険
7 入浴中の患者の転倒,溺水,熱傷の危険
8 検査台からの転落の危険
9 排泄介助中の危険
10 ナースステーションでの認知症患者待機の危険
UNIT4 コミュニケーション・トレーニング
SCENE 1 末期がんの妻への処置を求める夫と看護師の会話
2 抗がん薬投与中の夫の悪化を心配する妻と看護師の会話
3 乳幼児を連れた面会家族と看護師の会話
4 排泄ケアで訪室した看護師と患者の会話
5 退院を翌日に控えた高齢患者と看護師の会話
6 急死した患者の家族と看護師の会話
7 内視鏡検査に関する外来看護師と患者の会話
8 ベッドサイドでの排泄を求める看護師と進行がん患者との会話
文献
UNIT1 解答と解説
UNIT2 解答と解説
あとがき
INDEX
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。