MEDICAL LIBRARY 書評特集


大野 博司 著
《評 者》田中 和豊(済生会福岡総合病院・臨床教育部長)
感染症診療のトライアングルを視覚化
 現在日本の医療界の「感染症ブーム」は,ばい菌の無法地帯とも言える日本で,病める人々をばい菌の魔の手から解放すべく立ち上がった正義感あふれる英雄たちによって作られた。そのきら星のごとく現れた英雄たちの一人が,今回『感染症入門レクチャーノーツ』を執筆された大野博司先生である。大野博司先生は,自主的に学生向けにセミナーを開催するなど精力的な活動をされることで有名な若手医師期待のホープである。彼の初の単独執筆となるこの本はまさに彼の努力の「結晶」である。
現在日本の医療界の「感染症ブーム」は,ばい菌の無法地帯とも言える日本で,病める人々をばい菌の魔の手から解放すべく立ち上がった正義感あふれる英雄たちによって作られた。そのきら星のごとく現れた英雄たちの一人が,今回『感染症入門レクチャーノーツ』を執筆された大野博司先生である。大野博司先生は,自主的に学生向けにセミナーを開催するなど精力的な活動をされることで有名な若手医師期待のホープである。彼の初の単独執筆となるこの本はまさに彼の努力の「結晶」である。
あまたある感染症関係の書籍の中で,本書の最大の特徴は,「微生物-抗菌薬・薬理学-臨床感染症」のトライアングルを意識しながら,それを視覚化したことである。著者考案の「微生物ガイド(臨床で重要な微生物を6つに分類したダイアグラム)」と「抗菌薬マップ(その6つの分類の,それぞれどこにどういった抗菌薬が効くかを示した図)」は非常に有用である。「微生物ガイド」は例えてみれば敵の布陣である。また,「抗菌薬マップ」はわれわれの持っている個々の武器の特性を示している。このように敵の布陣と武器の特性を視覚化することによって,感染症との闘いをまるで将棋や囲碁のように理詰めで行うことが可能になる。まさに孫子が言ったように“敵を知り,己を知れば百戦危うからず”なのである。この視覚化以外に,ともすれば羅列に終わってしまう百科事典的な感染症の知識も簡潔にポイントをついてよくまとまっていて,見たい図表や調べたい知識がすぐ探せるのも本書の魅力である。Chlamydia→chlamidophila,pnuemocystis carinii→pneumocystis jiroveciなど微生物の名称の変更などの最新の知識も網羅されている。このため,人をあざ笑うかのようにお笑い芸人並みにコロコロと名称を変更する微生物にもついていける。また,本書では随所にColumnがあり,そこには仕事や人生に対する筆者の真摯な態度が見受けられる。医療者はばい菌や傷病を退治することに専念するあまりに,ともすると知らないうちに自分自身が病院・家庭や社会の「ばい菌」扱いされがちである。著者はこのような愚を犯してしまわないことを十分に心がけている「人間的な」医師なのである。
この本の出現で,いままでやりたい放題やってきたばい菌たちも,身の危険を感じ恐れおののいて悲鳴をあげている姿が目に浮かぶ。ばい菌さん,ご愁傷さま。ただひとつ,この本は講義ノートであるので,何も知らない初学者が通読しても理解するのは難しいかもしれない。その意味で1冊目の本というよりは,ある程度勉強したものが知識を整理するのに用いる2冊目以降の本かもしれない。その欠点を補うにはやはり評判の高い著者自身の講義を聴くのがいいだろう。私もこの本を持って著者の講義を早く聴いてみたいと思っている。
A5変・頁328 定価3,990円(税5%込)医学書院
|
Message From
「出すぎた杭は打たれない」 松村 理司(洛和会音羽病院院長) 『感染症入門レクチャーノーツ』著者大野博司氏の素顔卒後2年目の研修医の大野博司君が,私の前任地の市立舞鶴市民病院を訪ねてきたのは,2002年の夏であった。“大リーガー医”の見学のためである。医学生時代に,来日中であったカリフォルニア大学サンフランシスコ校医学部の一般内科の泰斗であるローレンス・ティアニー先生の鑑別診断力に接し,痺れてしまったとの由であった。「心臓外科医の道は辞めました。ともかくティアニー先生に追いつき,追い越したい」との青雲の志も耳にした。そのときに大野君は,ティアニー先生共著の『Essentials of Diagnosis & Treatment』を持ち合わせていたが,それへの実にびっしりとした書き込みを覗いた私は,彼の「医学書読破力」を確信した。「書く力」は未知数だったが,2003年春に舞鶴に異動してきた彼は,書く機会もほしいという。私たちの共著『診察エッセンシャルズ』(日経メディカル開発)の骨子は,その後の約半年に及ぶ大野君の不眠不休の持続力に負うところが大きいが,「医学書執筆力」もかなりは実証されたといえる。「スーパーレジデント」の呼び声は,偽りではなかったようだ。 私たちの縁は続き,2004年春に他の数人の研修医とともに洛和会音羽病院に異動してくることになった。「出る杭は打たれる」というが,「出すぎた杭は打たれない」ともいう。入職当時にいささか感じられた大野君に対する前者の雰囲気は,2年半後の今日,ほぼ雲散霧消したように感じられる。最大の理由は,臨床現場で彼がとことん働いてきたからである。総合診療医として,感染症医として,トラベルクリニックで,透析室で,そしてICU/CCUで。私が慣れない院長業にもたもたしている深夜に,よく大野君に襲われたものである。「先生,ICUナースの○○さんや透析室クリニカル・エンジニアの△△君が辞めるなんて,大きな損失ですよ。何とか手を打たないとだめじゃないんですか」。 感染症学は,大野君の最も得意とするところである。舞鶴でも音羽でも,サマーセミナーやらウインターセミナーやらが開かれ,各地の研修医や若手医師が混じり合うように接してきた。手ごろな開催場所や多少の資金を提供させられてきたが,互いに切磋琢磨する青年の客気ほど私のような熟年を鼓舞するものも少ない。 本書を散読させてもらったが,「です・ます調」の平易な説明は新鮮だった。コラムでの私語の表白にも驚いたが,若き大野ファンには魅力的なのだろう。肝腎の中身については,読者諸氏の今後の交流に委ねたい。 実用的な医学書が,現場で汗する卒後6年目の若手医師によって書かれる時代を迎えた。隔世の感を禁じ得ない。 |


《コアテキスト3・4》
疾病の成り立ちと回復の促進
疾病各論[1][2]
下 正宗,前田 環,村田 哲也,森谷 卓也 編
《評 者》田中 文彦(帝京大助教授・臨床検査学)
基礎・臨床医学を総合的に学習し専門技能を磨く礎を作る
 私は平成18年度より医療技術学部・臨床検査学科(新設)の学生さんたちの教育を担当することになった。看護師,臨床放射線技師などと並んで,臨床検査技師は昔からいわゆるパラメディカルスタッフと呼ばれていた職種である。文字通りには医師の傍に(para-)侍る小間使いという意味合いが強い。最近ではこれをコメディカルスタッフ,すなわち医師とともに(co-)作業するスタッフと呼んでいる。
私は平成18年度より医療技術学部・臨床検査学科(新設)の学生さんたちの教育を担当することになった。看護師,臨床放射線技師などと並んで,臨床検査技師は昔からいわゆるパラメディカルスタッフと呼ばれていた職種である。文字通りには医師の傍に(para-)侍る小間使いという意味合いが強い。最近ではこれをコメディカルスタッフ,すなわち医師とともに(co-)作業するスタッフと呼んでいる。
近年の医療の発達はめざましいものがあり,医師だけですべての診断,検査,治療,リハビリテーション,予防など責任をもって遂行することは不可能になった。医師でない者が遂行すれば危険と法的に見なされる,いわゆる“医行為”だけでも最近は大変な重圧であり,高度な専門知識を持ったコメディカルスタッフによる支援の必要性はますます高まっている。
そのような時代の流れを受けて,従来は各種コメディカルスタッフを養成する機関は3年制の専門学校がほとんどだったが,それらは次第に4年制の大学に移行しつつある。私が就任したのもそういう4年制大学の臨床検査学科である。
しかし一言に高度な専門知識を持ったコメディカルスタッフの養成と言っても,では教科書として何を使うか,就任前から頭を痛めていた。医学部の学生さんであれば6年間かけてじっくり育てることができるから,解剖学,組織学,生化学,生理学,微生物学,病理学など各教科についてそれぞれ1冊ないし数冊の国内外の教科書や参考書を紹介できるが,4年制の大学ではそれだけの教育期間の余裕はない。
一方,従来の専門学校用の教科書では,やはり“パラメディカルスタッフ”と呼ばれていた時代の名残で,“医師のお手伝いさん”の教育だから,この程度のことを知っておいてくれればいいだろうというコンセプトが見え隠れしてしまう。決してそれらの著者が執筆に手を抜いたわけでないことはわかるのだが,これからのコメディカルスタッフにとっては「この程度でよい」という医学知識の限界はない。医学部の学生が将来医師として活動するために学習する基礎医学の基盤と同等の範囲の広範な知識を,コメディカルスタッフの学生さんたちも身につけておいてもらわなければ,卒業後に医師と対等のレベルで協調していくことは難しい。
このような教育目的のために執筆されたのが,「コアテキスト」シリーズということである。本シリーズは「看護師国家試験出題基準」に構成を準拠して,全4冊でその中の医学・生物学分野をまとめ上げたものであるが,幸い医療・看護系職種の国家試験出題基準は似通った構成をとっているので,本書は医療系の職種を目ざす異なる領域の学生の教科書として汎用しうるものとなっている。第3巻と第4巻は,各種の疾病(疾患)扱った巻である。
編集者の4人は私と同業の病理医であり,名前を見れば,ああ,この人か,とすぐわかる仲間である。病理医は普段は主として病理標本の作製や鏡検によって病理診断(いわゆる最終診断)を行っているが,モチベーションの高い病理医の関心は決して単なる病理学,形態診断学の範囲に限定されることなく,生化学,生理学,微生物学などの領域にまで広がっているものだ。編集者たちは間違いなくそのようなモチベーションの高い病理医である。
したがって本書は,膨大な数の疾患を単に診断病理学的に整理してあるばかりでなく,基礎医学各科の知識と有機的に組み合わせて解説してあり,むしろ狭義の病理学の記述は控え目でさえある。だから学生さんたちは“病理学”の講義にありがちな臓器や組織標本の写真の羅列に辟易することなく,まだ基礎医学各科が現在のように細分化されていなかった時代に“病理学者”の知的好奇心を刺激し続けていた命題,「病気とは何ぞや?」について,最新の現代的視点から総合的に学習することができると思われる。
医学部の学生は,解剖学を1クール,組織学を1クール,生化学を1クール,病理学を1クール,といった形で各個学習した後,自分でそれらの知識を再統合して基礎医学全般を身につけ,それから臨床医学へと進んでいくのだが,本シリーズはこの過程をほぼ一括して学ぶことができ,教育年限が医学部よりも2-3年短いコメディカルスタッフの学生さんが将来医師と協同して作業していくうえで必要な医学知識を集中的,効率的に身につけるために,またとない教材であると推薦に値するものである。さらに執筆陣には臨床の第一線の医師も加わっているので,卒業後も多様なコメディカルスタッフの実践の場で,臨床医が何を求めているのかを的確に把握する能力を飛躍的に向上させることも可能である。コメディカルスタッフの種別は多様であるが,それぞれの分野の専門技能を磨いていく土台となる基礎・臨床医学の知識が本書には満載されている。
もちろん本書はあくまで教科書であり,これを読破すれば一生こと足れりという種類のものではないが,各職種の国家試験合格後も手元に置いて,さらに高度な専門知識を吸収するための土台にしたり,学生時代の知識の復習の一助とすればよいと思われる。告白するが,私もまた,学生時代に学習したままその後の医師としての人生でほとんど遭遇することのなかった疾患について,それらに関する知識を本書でブラッシュアップさせていただいた。厚く御礼申し上げます。
《コアテキスト3》
B5・頁400・定価3,360円(税5%込)医学書院
《コアテキスト4》
B5・頁448・定価3,465円(税5%込)医学書院


森川 昭廣,内山 聖,原 寿郎 編
《評 者》小島 勢二(名大大学院教授・小児科)
教科書としてだけでなく臨床現場でも役立つ書
 小児科学は,すべての臓器別分野が対象となるほか,小児の特徴である胎児,新生児から思春期までを含む成長と発達という時間軸からの視点も重要である。さらに,小児保健や精神疾患・心身医学的側面も含まれる。このように,広範な分野を対象としているにも関わらず,各大学において小児科学へあてられる講義時間は限られている。とりわけ,医学教育にチュートリアル授業が導入されてからは,講義時間の削減は顕著である。評者が所属する名古屋大学においても,小児科学にあてられる講義時間はわずか15時間にすぎない。学生は,自学自習が原則であり,膨大な小児科学の内容を欠けることなく簡潔にまとめた教科書が必須である。本書は,このような目的に適しており,1991年に第1版が出版されて以来,今回第6版と改訂を重ねていることは,わが国の医学生に広く支持されていることを反映した結果であろう。
小児科学は,すべての臓器別分野が対象となるほか,小児の特徴である胎児,新生児から思春期までを含む成長と発達という時間軸からの視点も重要である。さらに,小児保健や精神疾患・心身医学的側面も含まれる。このように,広範な分野を対象としているにも関わらず,各大学において小児科学へあてられる講義時間は限られている。とりわけ,医学教育にチュートリアル授業が導入されてからは,講義時間の削減は顕著である。評者が所属する名古屋大学においても,小児科学にあてられる講義時間はわずか15時間にすぎない。学生は,自学自習が原則であり,膨大な小児科学の内容を欠けることなく簡潔にまとめた教科書が必須である。本書は,このような目的に適しており,1991年に第1版が出版されて以来,今回第6版と改訂を重ねていることは,わが国の医学生に広く支持されていることを反映した結果であろう。
本書は,疾患の記載については,(1)定義・概念,(2)病因・病態,(3)臨床症状,(4)診断,(5)治療,と統一されており,その内容も簡潔で理解しやすい。図や表が多数含まれていることも理解の一助になるであろう。付属のカラーページも充実しており,麻疹・水痘といった発疹性疾患の皮膚所見から,急性白血病の骨髄像まで鮮明な画像が多数掲載されている。
従来の内容に加えて,今回の第6版には新たに国試対策や臨床現場での参考となるように「やってはいけないこと」,学生の教科書レベルを超えた知識として「アドバンス」,さらに最新情報の入手の便宜を図るために「参考となるホームページ」が追加された。医師国家試験にも取り入れられるように,それぞれの疾患や病態における「禁忌」に関する知識は,医学生にとって最重要である。本書にはこのような「禁忌」事項が「やってはいけないこと」と別枠で記述されているので,記憶にも残りやすく優れた工夫である。「アドバンス」には,教科書レベルを超えた内容ではあるが,最近のトピックスや実際の診断で必要な知識が記載されている。学生時代に通読した教科書は,研修医,さらに他科に進んだ医師にとっても,卒業後,臨床の現場で手に取る機会があるであろうが,そのような場合にこの「アドバンス」の項目は役立つであろう。
教科書の欠点は,日進月歩の医学の世界において,記載された内容がややもすると古くなりがちな点であるが,その対極にインターネットによる情報入手がある。最近の学会や患者会のホームページには,診療ガイドラインなど実際の診療に役立つ最新情報が掲載されている。第6版には,各章の最後に「参考となるホームページ」として,関連した学会,患者会や疾患データベースのホームページが記載されており,これらのホームページごとアクセスすることで最新情報が入手できるようになっている。
このように,『標準小児科学 第6版』は,学生向けの教科書として立場を継承すると同時に,卒業後にも役立つように新たな工夫が盛り込まれており,従来にも増して利用価値が高い。以上の理由から,わが国を代表する小児科学の教科書の1つとして,本書を医学生諸君に強く推薦する。


高橋 三郎,染矢 俊幸,塩入 俊樹 訳
《評 者》西村 良二(福岡大教授・精神医学)
精神医学・問題に関わる医療・教育・福祉関係者に
 客観性の点で優れた操作的診断分類DSMは本邦でも普及しつつあるが,わが国の精神科の臨床家は必ずしもこの診断分類のみに頼っているわけではないことも指摘されている。その理由の1つとして,まだ多くの臨床家が伝統的な診断分類に対してある種の魅力を感じていることがあげられよう。伝統的な診断分類に対しては,患者との間に生じる初診時の情動体験やラポールの形成を含めた診断面接の進め方が,その後に続く治療に結びつくという思いがあるからに違いない。たしかに,伝統的診断分類法には,優れた先輩の診断法をじっくりと見て,考え,それを取り入れ,自分のものにしていくという営みがあり,また診断の後の治療の進め方についても,師匠の手法の実際を見ておぼえていくといった修練ともいえるものがあった。米国精神医学会(American Psychiatric Association:APA)は,操作的診断分類DSMのケースブックの一連の出版を通じて,わが国の臨床家たちも感じていたこの種の“もの足りなさ”を補っているように思える。
客観性の点で優れた操作的診断分類DSMは本邦でも普及しつつあるが,わが国の精神科の臨床家は必ずしもこの診断分類のみに頼っているわけではないことも指摘されている。その理由の1つとして,まだ多くの臨床家が伝統的な診断分類に対してある種の魅力を感じていることがあげられよう。伝統的な診断分類に対しては,患者との間に生じる初診時の情動体験やラポールの形成を含めた診断面接の進め方が,その後に続く治療に結びつくという思いがあるからに違いない。たしかに,伝統的診断分類法には,優れた先輩の診断法をじっくりと見て,考え,それを取り入れ,自分のものにしていくという営みがあり,また診断の後の治療の進め方についても,師匠の手法の実際を見ておぼえていくといった修練ともいえるものがあった。米国精神医学会(American Psychiatric Association:APA)は,操作的診断分類DSMのケースブックの一連の出版を通じて,わが国の臨床家たちも感じていたこの種の“もの足りなさ”を補っているように思える。
さて,本書は,APAから出版された『Treatment Companion to the DSM-IV-TR Casebook』(2004)の翻訳書である。本書では興味深い34症例があげられ,それぞれの症例に対して,その分野の専門家が治療法を語るという形式をとっている。例えば,強迫性障害にはジュディスL.ラポポート博士,性的サディズムにはマイケル・ストーン博士,境界性パーソナリティ障害にはジョン・ガンダーソン博士など,わが国でも名が知られた専門家が,鑑別診断も含めて,どのように診断を進め,いかに対応するか,さらには治療プランまでを語っている。あたかも直接の指導をしてもらっているかのようである。こうして,本書には,臨床家をとらえて放さない魅力,すなわち,“人を知るという生きた感情”を体験できる楽しみがある。
実際の面接では,ラポールを育成しながら,情報を得,まだ理解できない部分も焦らず治療経過のなかで明らかにしていこうという側面がある。こうした,今までのDSMに関する書物にはあまり見られなかった側面が本書には盛り込んである。
ところで,APAは,DSMの21世紀システムとして,さらに軸を増やして8軸にすることを検討しているという。新たな3軸とは,「治療動機と意味」,「行動の生物学的・遺伝的要因」,「心理社会的治療,薬物療法についての治療プラン」の3つであるらしい。そうすると,本書はそれへ向けての一歩なのかもしれない。
それはともかく,読者は,本書を読んでDSM診断分類が身近に思えるのではないだろうか。本書は訳がこなれていて読みやすいし,読んでいるとケースカンファレンスに参加している臨場感がわく。このようにすばらしい本書は,精神科医,精神医学に関わるすべての臨床家,精神科看護スタッフ,作業療法士,心理士,精神科ソーシャルワーカーは言うまでもなく,精神的問題に関わる教育関係者,福祉関係者の人たちにもお薦めしたい1冊である。


AO法骨折治療Hand and Wrist
[英語版DVD-ROM(Win版)付]
田中 正 監訳
金谷 文則 訳者代表
《評 者》三浪 明男(北大大学院教授・整形外科学)
AOの治療概念に則した整形外科医座右の書
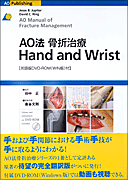 Dr. Jesse B. JupiterとDr. David C Ring著「AO Mannual of Fracture Management」が田中正先生監訳,金谷文則先生,別府諸兄先生,吉田健治先生訳によって『AO法骨折治療Hand and Wrist』として医学書院より出版されることとなりました。
Dr. Jesse B. JupiterとDr. David C Ring著「AO Mannual of Fracture Management」が田中正先生監訳,金谷文則先生,別府諸兄先生,吉田健治先生訳によって『AO法骨折治療Hand and Wrist』として医学書院より出版されることとなりました。
AO(Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthes)が1958年にMaurice Mullerとスイスの外科医グループにより設立されて以来,AOは安全確実な手術原理の確立,信頼性の高い内固定材料の開発などにより骨折治療の改革と治療成績の向上をめざしてきています。また,AOは従来の骨折治療に対する考え方を一新すべく,一次性骨癒合を可能とする骨折部の安定性(rigid fixation)とそれによって隣接関節の早期自動運動を行い,術後拘縮のリスクを軽減することに努めてきています。AOグループは治療結果を的確に評価し,それらを他の整形外科医の指導に実習という形でとり入れてきています。これらの考えは現在の骨折治療の根幹を形成するまでに浸透していると考えます。
Jupiter先生は日本からの多くの手の外科医を指導されておられますし,日本にも頻繁にお越しですのでご存じの先生も多いと思いますが,現在American Society for Surgery of the Hand(ASSH)の主要メンバーであるとともにAO Education BoardのChairmanであり,教育法に関しては定評のあるところで,本書にもその特徴が随所に見られます。
監訳者の田中正先生が記載されているように,本書は手関節,手指におけるすべてのタイプの外傷を取り上げているわけではありません。しかし,症例に基づいた教育方法という観点から,臨床例を通して骨折治療法を学べるようになっています。骨折症例の提示に始まり,術後計画をどのように立てるべきか,手術進入法はどうすべきか,安定した固定性を得るためにはどうすべきか,術後療法をどのようにすべきかについて順を追って解説されていますので大変わかりやすい構成となっています。フルカラーの豊富な写真や図が多数用いられており,大変わかりやすく編集されていることと,各項目の最後には必ずPitfallsとPearlsが簡潔に記載されており,合併症とその回避法について説明されていることも本書の重要な特徴と思います。
本書の前に翻訳されたAO法骨折治療(AO Principles of Fracture Management)と同様に,本書でも固定手技だけではなく手術進入法もビデオ化されており,さらにDVDを解説付きで見ることができ,読者にとって非常にわかりやすくなっています。
手関節,手指の骨折はよく遭遇する外傷であり手の外科を専門とする医師,一般の整形外科医にとって,本書は非常にわかりやすく,AOの治療概念に則した最新の固定手技の習得に役立つものと思います。
日常治療においてすべての整形外科医にとって座右の書であることを力説したいと思います。
A4・頁360 定価25,200円(税5%込)医学書院
