MEDICAL LIBRARY 書評特集


ポートフォリオ評価とコーチング手法
臨床研修・臨床実習の成功戦略!
鈴木 敏恵 著
《評 者》郡 義明(天理よろづ相談所病院総合診療教育部)
読んだ者にエネルギーを与える実践書
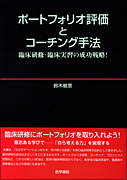 著者はポートフォリオの重要な点は,「気づき」を促す場を提供することと,教育の成果(成長の軌跡)が研修医自身にも指導医にも評価可能な点であると述べている。
著者はポートフォリオの重要な点は,「気づき」を促す場を提供することと,教育の成果(成長の軌跡)が研修医自身にも指導医にも評価可能な点であると述べている。
医学教育にとって,知識や技術の習得が重要なことは論を俟たないが,さらに重要なことは,学び続ける意志,学び取る能力である。こうした能力の獲得向上には,内省的な振り返りを通した「気づき」が欠かせない。ポートフォリオは,そのような気づきを促す格好の媒体となりうると著者は強調している。内省と言えば失敗から学ぶことがまず頭に浮かぶが,著者は一歩進めてもっとポジティブな面をとらえようとする。振り返りの中で,自らの成長を確認することで,さらに前進しようとする力が湧いてくるというのだ。
考えてみれば,優れた研究者や臨床家は,このような作業を目には見えなくとも頭の中で実践してきたに違いない。その“技”を誰にでもわかりやすく利用できるようにしたものがポートフォリオなのかもしれない。
実際の教育現場を見ると,いまだに教育は理論や信念に基づいて行われていることが意外と多い。その最大の原因は教育方法の実効性を証明することが困難なためである。しかし,ポートフォリオでは,あらかじめ評価の観点を設定することで評価が可能だと著者は述べている。
タイトルはポートフォリオ評価となっているが,本書では評価だけでなく,実際にどのように活用すればよいか具体例を多数挙げているので実践の場で活用しやすい。
また,昨今,企業でも注目されているコーチング手法についても紹介している。そのエッセンスは「静かな誘い水にも似たコーチングの問いは,頭の中に起きている思考の紡ぎを助けます。それは,余分な糸くずが混ざった糸の絡みが自然に解け,すっと1本の糸が自ら浮かびあがり,解決させるかのようです。その1本の糸は,本人の中にはじめからあるものであり,決して他者が教えたり,与えたりするといったものではない」という文章の中に凝縮されている。対話コーチングのポイントやコツがわかりやすく説明されており,現場での指導に大いに役立つであろう。コーチングの手法は,臨床教育の場にもっと利用されるべきものである。
本書には,随所に「成長は真摯な自己評価と共にある」,「人は皆,自己成長する潜在力を持っている」といった力強いメッセージがこめられている。そこには常に人間の可能性を信じて疑わない著者の前向きな姿勢が現れている。本書がノウハウ本を超えて,読んだ者にエネルギーを与える所以である。研修医や指導医が待ち望んでいた実践の書である。


佐藤 光源 監訳
《評 者》平安 良雄(横市大大学院教授・精神医学)
標準化された精神科医療を習得・実践するために
 米国精神医学会は精神科領域において最もよく経験する10の疾患や病態に関する治療ガイドラインを,臨床現場で手軽に用いられるようにまとめたクイックリファレンスを発行した。本書は東北福祉大学大学院の佐藤光源教授の監訳によって翻訳された日本語版である。
米国精神医学会は精神科領域において最もよく経験する10の疾患や病態に関する治療ガイドラインを,臨床現場で手軽に用いられるようにまとめたクイックリファレンスを発行した。本書は東北福祉大学大学院の佐藤光源教授の監訳によって翻訳された日本語版である。
わが国の精神科医療においてこれまでしばしば指摘されてきたことに,診療医または診療施設間の診断や治療方針,家族への対応などにばらつきが大きいという問題があった。この原因として,医師の教育・研修・生涯教育に一定の基準がないこと,さらに,特定の疾患に対して標準化された治療ガイドラインの必要性が十分に理解されていないことなどがあった。ガイドラインに対しては,賛否両論があり,精神疾患の多様性を公式にのっとった治療方針で解決することはできないというのが反対理由の1つである。しかし,この反論はガイドラインの趣旨を誤解していると思う。
本書に目を通していただければ,前述の反論が的外れであることがよく理解できる。ガイドラインは一定の公式に基づいて治療することを意味するのではなく,多様な精神疾患の病態をさまざまな角度から評価し,診断し,治療方針を立て,治療効果を評価し,さらに,個々の患者さんに応じた支援や疾患管理教育の方針を,エビデンスに基づいてもれなく合理的に進めていく手法を提供するものである。したがって,ガイドラインを用いることで,誰が治療をしても同じプロセスを経て疾患や病態が評価され,基準に基づいた治療方針が策定されることになる。治療の実践に関しては,それぞれの施設の環境や地域の社会資源によって当然違いは出るが,ガイドラインを1つの理由として治療環境の整備を行政などに働き掛ける材料とすることもできる。
また,本書は評価・診断から治療そして社会資源を用いた介入までを簡潔にまとめてあるので,クリニカルパス策定などにも参考となる。医師が治療方針を作成するうえで,急性期の治療のみならず,安定期から社会復帰を見据えた治療計画を考慮する習慣をつけることができる。精神科医療の特徴であるチーム医療にも対応した治療の流れが明確で,学生・研修医をはじめコメディカルスタッフにも理解がしやすく,教育的にも有効である。ぜひ,本書を活用し,国際的な治療ガイドラインを理解,実践することで,患者さんや社会に標準化された精神科医療を提供するきっかけとしていただきたい。


聖路加国際病院呼吸療法チーム 執筆
蝶名林 直彦 編
《評 者》田中 一正(昭和大教授・医学疾病学 山梨赤十字病院内科(呼吸器)非常勤医師)
呼吸療法チーム医療をめざすすべての医療従事者に
 誰が誰のためにどのようにNPPVを安全に行うか,刻々とバイタルサインの変化する中でNPPVをどう具体的に行うか,そのための指導書として,本書は実に簡潔に編纂されています。また,NPPVの適切な対応とは何か?等,実践の中から湧き出たさまざまな問題点も本書では,見事に解き明かしてくれています。
「これはどうするの?」,「え~っとどうだったっけ?」,「ちょっと調べてよ!」
誰が誰のためにどのようにNPPVを安全に行うか,刻々とバイタルサインの変化する中でNPPVをどう具体的に行うか,そのための指導書として,本書は実に簡潔に編纂されています。また,NPPVの適切な対応とは何か?等,実践の中から湧き出たさまざまな問題点も本書では,見事に解き明かしてくれています。
「これはどうするの?」,「え~っとどうだったっけ?」,「ちょっと調べてよ!」
これらは,現場の毎日の会話の中にある疑問と不安のやり取りです。 「こうでいいのよ!」つい,知ったかぶって言ってしまった。「うまくいかないのは私のせいじゃない」患者さんの状態や体つきが悪くて合わないのだ。先生の指示がおかしいから……,思うことはみな同じです。でもいちばん困っているのは,あなたではなく患者さん。経験不足で自信のない先生とNPPVを試したことはあるけど指示されたことだけをやっていたあなた,この本の中で症例を振り返ってみませんか。こうしてあげられれば……,こういう方法もあったんだ!経験と知識が結びついてこそ,よりよい医療に結びつくのではないでしょうか。
そんな気持ちで本書を読んでみると,急性期NPPVのための施設とチームワークでは「何を,なんのためにモニターするか」「患者状態の観察で注意するポイントと対処法」「挿管のタイミング」という表題で書が進み,さらに,「慢性期に移行する場合」「クリティカルパスによるNPPV導入の実際」「長期導入例のモニタリング」と呼吸器疾患患者の急性期から慢性期の流れに沿ってその時々のポイントが記されています。
さらに,呼吸ケアの実際としてまずマスクフィッティング維持のコツが解説されています。それぞれの出会う場面場面で何が患者さんとのコミュニケーションで最も大事か,そのためには何をすべきか,を大切にされる聖路加国際病院の呼吸療法チームの姿勢が注がれた良書となっています。
経験豊富な先生も,これから必要に迫られてNPPVの指示を出す先生も,在宅でご家族と一緒に看取る先生も,ぜひご一読していただきたい本です。
チーム医療をめざしたいあなた! 本書をテキストに勉強会を始めてみませんか。医師とともに患者さんのために一緒に読んでみたい本です。あなたの病院にも呼吸療法チームの産声が上がりますよ。


日本頭痛学会 編
《評 者》高倉 公朋(東女医大学長)
エビデンスに基づく頭痛治療を行うための必読書
 頭痛は脳神経疾患を診断・治療している医師にとって,もっとも普遍的な症状であるが,その原因と病態がさまざまであるため,診断と治療法が医師により異なっていたり,時に治療上不適切な投薬が行われていることも少なくない。しかし,最近頭痛の分類と診断が国際頭痛学会が定めた分類に従って行われるようになり,わが国の臨床現場でも,頭痛の診断と治療が標準化されつつある。頭痛の分類は国際頭痛学会が1988年に提案した国際頭痛学会分類初版が基本になっているが,その改定が2004年に行われたので,頭痛の分類は,今後,国際頭痛学会分類第2版(2004)に準じて行われることになった。
頭痛は脳神経疾患を診断・治療している医師にとって,もっとも普遍的な症状であるが,その原因と病態がさまざまであるため,診断と治療法が医師により異なっていたり,時に治療上不適切な投薬が行われていることも少なくない。しかし,最近頭痛の分類と診断が国際頭痛学会が定めた分類に従って行われるようになり,わが国の臨床現場でも,頭痛の診断と治療が標準化されつつある。頭痛の分類は国際頭痛学会が1988年に提案した国際頭痛学会分類初版が基本になっているが,その改定が2004年に行われたので,頭痛の分類は,今後,国際頭痛学会分類第2版(2004)に準じて行われることになった。
本書は慢性頭痛の診断と治療のガイドラインをまとめた書で,日本頭痛学会の主な会員の方々によって執筆され,頭痛に関して本邦の権威である坂井文彦先生と間中信也先生が中心となって編集されている。わが国の慢性頭痛治療レベルの向上と標準化に貢献するところが大きい。
頭痛は一次性と二次性頭痛に大別されるが,本書は一次性頭痛の分類,診断と治療法の解説に重点が置かれている。一次性頭痛の中では片頭痛が臨床的には,もっとも多いので,本書では片頭痛を中心に解説している。片頭痛とともに緊張性頭痛,群発頭痛およびその他の一次性頭痛については,従来よりも明確な診断基準が示されている。
片頭痛の薬物治療は最近,著しく進歩しており,トリプタン系薬剤の有効性が広く認められるようになっている。片頭痛急性期治療には,アセトアミノフェン,非ステロイド系抗炎症薬,エルゴタミン製剤,トリプタン系薬剤,制吐剤などが用いられているが,本書では,それぞれの系の薬剤の特徴,使用法と有効性が詳細に解説されており,実地臨床での医師の薬剤選択に適切な指針を与えている。
二次性頭痛について,その原因はさまざまであるが,「誤診すると死につながる頭痛」を見落とさないことに重点を置いて解説されている。くも膜下出血が重要な疾患であるが,髄膜炎,片頭痛,脳梗塞,高血圧症頭痛,緊張性頭痛などとの鑑別の要点や,救命・救急室での頭痛の診断・治療法,頭痛の簡易診断の手順,さらに病診連携で患者の経過を追うことの重要性など臨床に直接役立つ内容が要領よくまとめられている。
本書には,小児の一次性頭痛の疫学・診断と治療法,ならびに頭痛の遺伝子解析についても最近の知見が紹介されている。
本書は頭痛の診断と治療に関する現在の国際的な基準をまとめており,エビデンスに基づく頭痛の治療を行うためには必読の書である。


相馬 一亥 監修
上條 吉人 執筆
《評 者》白川 洋一(愛媛大教授・救急医学)
救急医療の現場で役立つ急性中毒診療の指南書
 本書の著者である上條吉人氏の名前は思い出せなくても,よく通るテノールの声と,10m先にいるマムシでも射すくめてしまいそうなギョロ目を知らない者は,臨床中毒学の関係者のなかにはいないだろうと思う。さまざまな学会や研究会の場で,鋭い質問を浴びせられてタジタジとなった経験を持つのは,おそらく,私ひとりではないはずだ。それだけ多くの経験を積んだ臨床家であり,同時に,深く勉強している臨床研究者でもあることは万人の認めるところだろう。昨年から,日本中毒学会の機関誌である『中毒研究』誌の編集委員としてもご活躍中のホープである。そんな上條氏の書いた急性中毒の本が面白くないわけがないではないか(実際に面白い)……と,それだけで私の感想はほとんど尽きてしまいそうである。
本書の著者である上條吉人氏の名前は思い出せなくても,よく通るテノールの声と,10m先にいるマムシでも射すくめてしまいそうなギョロ目を知らない者は,臨床中毒学の関係者のなかにはいないだろうと思う。さまざまな学会や研究会の場で,鋭い質問を浴びせられてタジタジとなった経験を持つのは,おそらく,私ひとりではないはずだ。それだけ多くの経験を積んだ臨床家であり,同時に,深く勉強している臨床研究者でもあることは万人の認めるところだろう。昨年から,日本中毒学会の機関誌である『中毒研究』誌の編集委員としてもご活躍中のホープである。そんな上條氏の書いた急性中毒の本が面白くないわけがないではないか(実際に面白い)……と,それだけで私の感想はほとんど尽きてしまいそうである。
簡単に中身を紹介すると,第1章「初期対応の考え方」では常法どおり,中毒物質の推定法,合併症,治療原則を述べている。記述はきわめて簡潔かつ正確であり,新しい知見もきちんと盛り込まれている。第2章では重要な40の中毒物質をとりあげて解説しているが,この選択には著者の臨床的センスがよく現れている。特に中毒メカニズムに重点をおいた記述や「イラスト」の使い方はすばらしい。
第3章「急性中毒と精神医学」と第4章「向精神薬の致死的副作用」の存在理由は,著者が精神医学の研鑽を積まれたあとで救急医学に加わったという経歴を知らなければ,理解できないかもしれない。しかし,今や,重い急性中毒患者の大部分が自殺企図であるという事実を知れば,この2つの章の重要性は納得されるであろう。
このように本書は,構成,内容ともにかなりユニークであり,著者である上條氏と監修者である相馬教授の豊富な臨床経験あるいは臨床教育の経験が巧みに反映されている。
ただ,個人的には,気に入らない点がひとつだけある。本書の題名に付いた「イラスト&チャートでみる」という余計な修飾である。「イラスト」だとか「チャート」だとか「マニュアル」とかの文言が表紙に書かれていると,私はその本を手に取らないことにしている。人々が忙しくなって深くモノを考える暇がなくなったためか,近年,薄っぺらな内容の本がとみに増えた。そのような本を読んでいると,かえって,限りある人生の時間を無駄にしているように思えてならない。
題名に文句をつけてしまったが,本書は決して内容の薄っぺらな本ではない。中身が濃いことは保証する。


WM感染症科コンサルト
岩田健太郎 監訳
《評 者》大曲 貴夫(静岡県立静岡がんセンター・感染症科)
感染症の疫学から診断・治療法まで網羅
 私たちが医師になった10年前と比べ,最近は感染症診療に関する良書が出版されるようになった。これから感染症診療を学ぶ若い先生方はよいリソースに囲まれていてうらやましい限りである。私も縁あって今では感染症臨床の教育に携わっているが,教える側としても良質なテキストが増えるのは非常に喜ばしい。
私たちが医師になった10年前と比べ,最近は感染症診療に関する良書が出版されるようになった。これから感染症診療を学ぶ若い先生方はよいリソースに囲まれていてうらやましい限りである。私も縁あって今では感染症臨床の教育に携わっているが,教える側としても良質なテキストが増えるのは非常に喜ばしい。
日本の感染症診療の変化に大きな影響を与えた英文書籍のきわめつけは,マニュアルであればSanford「熱病」であり,テキストであればMandellの教科書であろう。これらを使用している方は多いはずである。
しかしこうした地位の確立された書物にも限界はある。例えばSanford「熱病」はあくまで個別の臓器別,病原体別の治療について書かれたマニュアルであって,各疾患のマネジメントの全体像までは示してくれない。つまりは特定の感染症の疫学,病態生理,特徴的所見,診断方法,個別の治療法,そして予防までを系統立てて示してくれるわけではない。よって各疾患の個別の情報を得るにはMandellなどの分厚い成書を読む必要が出てくる。ところがこれには結構な時間がかかる。しかも時間をかけて読んだのに知りたかった肝心の全体像が見えてこない……という経験をしたのは筆者だけではないはずである。感染症の成書はたしかに個々の感染症について詳細な知識を与えてくれるのだが,結果的に全体像や重要なポイントが把握しにくい場合がある。自分のあまり明るくない分野のトピックについて勉強する際には,まずは全体像を掴ませてくれる書物が欲しいところである。
ここに今回,岩田健太郎先生が監訳されて,あの『WM(ワシントンマニュアル)感染症科コンサルト』の日本語版が出版された。早速手にとって読んでみた。「1.感染症科コンサルトの仕方」,「2.発熱」に始まり,臓器毎の感染を中心とした感染症診療上の重要なトピック,骨髄移植の感染,固形臓器移植患者の感染などの特殊な領域,旅行医学や予防接種,バイオテロリズムなどの周辺領域の話題まで広くカバーしてある。個々のトピックの内容も感染症の疫学から診断方法,治療法まで網羅してある。記載は簡潔ですっきりしていて読みやすい。
この『WM感染症科コンサルト』は感染症診療上の重要なトピックの全体像を示してくれる。これならば忙しい診療の間にも読めるし,成書の内容の重み付けや咀嚼に時間を取られることもない。また日本の読者にとっては,本書は北米の感染症診療がどのように行われているかを教えてくれる。医療のあり方は各国・地域で違うわけで,その観点からは北米の診療内容=世界の標準とは言い切れない点はある。しかし大筋では差はないであろう。感染症診療の標準を知るという観点からも,本書は有用である。本書の記載内容と本邦における現状に違いがある点については,脚注で指摘してあるが,ここも評価できる。
A5変・頁512 定価5,880円(税5%込)MEDSi
http://www.medsi.co.jp/
