MEDICAL LIBRARY 書評特集


中村 恭一 著
《評 者》柳澤 昭夫(京府医大教授・計量診断病理学)
「胃癌の構造」を解き明かす胃癌理解の必読書
 本書は1982年に出版された『胃癌の構造』の全面改訂版である。“初版出版によせて”において中村先生の恩師で,当時,癌研究所所長であった菅野晴夫先生が“本書はヒト胃癌に関する最も重要な成書として長く歴史に残ることになるであろうことは疑いない”と述べておられる。『胃癌の構造』はまさに菅野先生が予想されたように,20年以上にわたって「初版印刷時の鉛板がすり減って印刷に耐えない状態」まで出版され続け現在にいたった。この事実は,この本がいかに多くの読者にとって重要な書であったかを裏付けるものである。さらに,今回の改訂は本書が胃癌に関する重要な成書として今後とも歴史に長く残ることを確信させるものである。
本書は1982年に出版された『胃癌の構造』の全面改訂版である。“初版出版によせて”において中村先生の恩師で,当時,癌研究所所長であった菅野晴夫先生が“本書はヒト胃癌に関する最も重要な成書として長く歴史に残ることになるであろうことは疑いない”と述べておられる。『胃癌の構造』はまさに菅野先生が予想されたように,20年以上にわたって「初版印刷時の鉛板がすり減って印刷に耐えない状態」まで出版され続け現在にいたった。この事実は,この本がいかに多くの読者にとって重要な書であったかを裏付けるものである。さらに,今回の改訂は本書が胃癌に関する重要な成書として今後とも歴史に長く残ることを確信させるものである。
今回の改訂版は,初版の総頁数が266頁であったのに対して,452頁と倍に近い。この頁数からわかるように,中村先生がいかに今回の改訂に力を注いだか,また今回の改訂が単なる改訂にとどまらないかが理解できる。このことは,先生自身が序文の「“胃癌の構造”事始め」で,この本の改訂には4年を費やしたと述べておられることからも裏付けられる。
中村先生は胃癌の組織発生に関する本を1972年,金芳堂書店より『胃癌の病理-微小癌と組織発生』として最初に出版されている。この本は表紙,裏表紙,背表紙と全面黒で装丁されていたことにより“黒本”と呼ばれて愛読され,胃癌を研究する研究者に限らず病理医,臨床医にとってもバイブル的役割を果たしていた。“黒本”出版10年後に刊行されたのが『胃癌の構造』である。この本は“黒本”で述べられていた理論をさらに体系的に著したものであり,特に胃癌の組織発生の章は過去の胃癌発生の学説の誤りを中村先生独特(中村流)の論調で理論的に説いており,読んでいて痛快さをも感じさせるものであった。
今回の改訂は,初版の『胃癌の構造』をさらに体系化したものである。前半は胃癌の発生に関して,先生が研究してきた「胃癌の構造」の幹としている胃癌の細胞・組織発生から導かれた過程が,早期胃癌,胃癌の発生母地病変および胃癌組織発生研究の歴史的考察から始まり,潰瘍と胃癌の因果関係,ポリープと胃癌,胃癌発生の場,組織発生,微小癌から導かれる組織発生,細胞発生とその初期における癌細胞の生体生着様式の順で明快に述べられている。さらに,“胃癌発生のまとめ”として,胃癌発生の全体像が読者によりわかりやすく理解できるように1つの章にまとめられている。先生が,今回の改訂でいかに「胃癌の構造」全体を理解しやすくするかに腐心されたかが伝わってくる配置である。
次に述べられている項目は,胃癌の組織発生の分析結果から発生した胃癌が,どのように成長し,どのような組織像,肉眼像を現し,臨床所見を呈するか,また,胃癌の発育速度はどうであるか,すなわち,発生した胃癌が成長するとどのように展開していくかの研究結果から得られた結論が述べられているが,これらの項目は実際に胃癌を病理組織診断する場合や,臨床の場で診断する場合,そこで観察される所見を理解するうえで大きな手助けを与えてくれるものであり,研究を離れた実際の診断においても有益なものである。
臨床的問題が多く予後の悪いLinitis plastica型癌においては,“臨床的頻度は低く,その道は「小道caminito」である”としながらも,大きく頁を割いている。先生が何故この癌に対してこのように頁を割いたか興味があるところであり,この癌に対する取り組み方が,先生の癌に対する基本姿勢であると推測される。すなわち,たとえ臨床的に見つけられた時点でどんなに予後が悪い癌であっても,その初期像,構造を明らかにすることによって早期発見は可能となる。いいかえれば,どんな難治性癌も絶対早期発見できる(どんな癌も治す)とする姿勢でもある。
最後に先生はエピローグにおいて,“「胃癌の構造」のフィルターを通してその癌の胃癌全体のなかにおける位置づけが,そして,その癌の生物学的振る舞いから,以後に起こる可能性のあることをある程度予測できます”と述べている。これは,前述したことと通じるものであり,「胃癌の構造」を知ることは臨床の場で胃癌を診断するうえでも重要であることを意味するものである。本書を読むことにより,この言葉の真意が容易に納得できる。
今回私が改訂された本書を手にした時,20数年前に出版された『胃癌の構造』初版を読んで,胃癌発生に対する疑問をたとえ人体材料であっても理論的に矛盾のない結論へと導く論法に感銘したと同時に,人体材料を基にした癌研究のおもしろさを知ったことや,中村先生と知り合った当時のことを懐かしく思い出した。それ以来,常に物事を理論的に矛盾のない結論へ導く姿勢(たとえお酒がはいっていても変わらない)に感服している。この20年の間に遺伝子をはじめとする分子生物学研究の進歩は目覚ましいものがあったにもかかわらず,初版で得られた結論は揺るぎないものであり,まったく変わることなく現在もなお支持されている。さらに今回,初版を幹に全面改訂されたことは,常日頃,物事を論理的にとらえる姿勢の賜物であることに改めて感心させられた次第である。
先生の書は常に研究者に限らず臨床家にとっても必読書となっている。これは書かれている結論がすべて人体材料を基にしたものであり,常日頃臨床をよく知り多くの臨床家と議論している結果といえる。本書は胃癌に関心を持つ多くの研究者に限らず,胃癌診断を行っている病理医,臨床医にとっても“胃癌”を理解するための必読書であること,また,癌を研究している多くの研究者に有益な示唆を与えることを確信し,一読を推奨する次第である。


シリーズ:医療安全確保の考え方と手法1
RCAの基礎知識と活用事例 [演習問題付き]
飯田 修平・柳川 達生 著
《評 者》岩崎 榮(横浜市病院経営局長)
医療安全確保の指南書
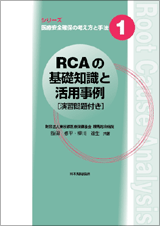 『RCAの基礎知識と活用事例』(RCA: Root Cause Analysis,根本原因分析)は,わが国の医療安全確保に関する初めての実用的な指南書である。従来この種の本は,とかく精神論で解説されたり総論的・教科書的なものが多かったように思われる。本書の出版によってこれまでの医療安全確保のあり方に一大インパクトを与えることになるであろう。それというのも,本書が医療における安全確保のための実践的な書として現場で使ってみて真に役立つものと確信しているからである。
『RCAの基礎知識と活用事例』(RCA: Root Cause Analysis,根本原因分析)は,わが国の医療安全確保に関する初めての実用的な指南書である。従来この種の本は,とかく精神論で解説されたり総論的・教科書的なものが多かったように思われる。本書の出版によってこれまでの医療安全確保のあり方に一大インパクトを与えることになるであろう。それというのも,本書が医療における安全確保のための実践的な書として現場で使ってみて真に役立つものと確信しているからである。
本書ではその書名からして,「活用事例」,「演習問題付き」と謳っており,そこに本書の特徴がある。医療現場での使用に利便性を高め,直接医療に携わる第一線の医療従事者一人ひとりにとっての実践の書である。そのために本書では総論を簡潔にまとめ,各論に重点を置く構成となっている。
しかも,本書は単なる実践の書ではなく,医療の質向上を目指す質管理の考え方・手法が巧みに取り入れられ,理論的にもきちっとした組み立て方がなされている。いわばTQM(Total Quality Management:総合的質経営)の質管理手法が用いられているのである。『TO ERR IS HUMAN/人は誰でも間違える-より安全な医療システムを目指して』(医学ジャーナリスト協会訳,日本評論社刊,2000年)は,わが国の医療界のみならず社会全般にも衝撃を与えたことは記憶に新しい。それ以来,医療安全確保への関心は高まったといっても過言ではない。しかし,残念ながら同書の真のねらいは十分に理解されないままである。
ことにマスコミを中心として国民もまた,「誰がやったのか」と事故の犯人探しにのみ興味を示すがゆえに,医療現場において日常的に真摯に懸命に取り組んでいる医療者が,かえって萎縮医療に傾くというジレンマに陥り苦悩しているのも事実である。
事故の隠蔽はあってはならないが,間違った告発主義のもとでは決して事故は減らせない。このような状況が続く限り,わが国では本当の意味での医療安全確保は確立し得ないであろうし,安全文化の醸成もままならない。
本書の総論では「社会が許容し得る安全対策」を提唱し,社会的合意形成が必要であるとし,そのためには,データに基づく合理的なわかりやすい説明が必要だと説いている。質管理手法や信頼性手法でいう手法を道具と考えるとわかりやすい。道具であれば,その特性に合わせた使い方をすればよいのである。総論から各論へと上手に導かれ,各論では,RCAの実施手順を著者の自院での事例を中心に演習問題を課し,事例の選定,分析チーム編成から始まり,RCA法による分析,分析後の取扱いにまで,こと細かに解説が加えられている。医療従事者すべての必読書として推薦したい。
B5・136頁 定価1,680円(税5%込)日本規格協会
http://www.jsa.or.jp/
