(前回よりつづく)
前回は,長座位からの立ち上がりを1人で行う,「バランス活用」の原理を使った「添え立ち」をご紹介しました。今回は,表面からは見えにくい,体の内部を有効に動かし,大きなチカラを出す「体幹内処理」の原理を利用し「添え立ち」をさらに技術として深めていきたいと思います。
武術遊び「骨盤崩し」
「体幹内処理」の感覚をつかむために,まずは武術遊び「骨盤崩し」をやってみましょう。図1を参考に,小さな動きから大きな「チカラ」が生み出せることを体感してください。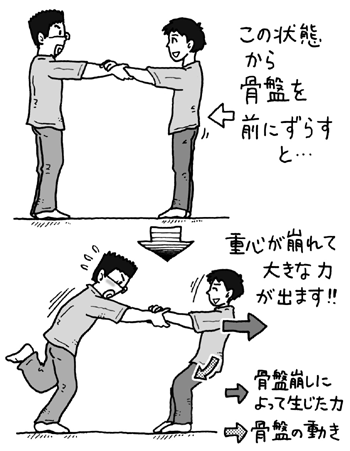 |
| 図1 武術遊び「骨盤崩し」 (1)向き合って,お互いが手を伸ばし,相手の手首を握る。 (2)はじめは腕力で相手を引いてみる。 (3)次に全身をリラックスさせ骨盤のみをわずかに前に突き出す。重心が崩れ,後ろに倒れそうになったら,そのチカラをそのまま受け手に伝える(腕力は使わない)。 ※受け手は引っ張られないように頑張らず,(2),(3)それぞれの違いを感じるようにしてください。(岡田) |
いかがでしたか? (2)の,腕力で引かれるほうは予想がつく力だったと思います。しかし,(3)の,骨盤をわずかに操作して得られた「チカラ」は予想外に大きなものだったのではないでしょうか。
もっとも,違いを実感できなかったという方も多いでしょう。「引っ張ろう」という意識が強いと,ついつい筋力に頼ってしまいます。そういう方はまず,1人で立って,骨盤のわずかな動きで起こるチカラを感じてみてください。
普通に骨盤を前に出しても重心が崩れる感覚はありません。しかし,全身の力を抜いた状態を維持したまま,骨盤だけを前に突き出すことができれば,後ろに引っ張られるように体勢が崩れていきます。「骨盤崩し」では,この「バランスが崩れるチカラ」を感じてほしいと思います。
人間は無意識のうちに「倒れない」ように身体をコントロールしています。違いを実感できなかった方の場合,骨盤を出した時に崩れたバランスが,瞬時に足腰の筋力によって回復しているのだと思われます。こうした無意識のバランスコントロールを意識的に「外す」ことによって,戦略的に身体のバランスを崩し,「筋力でないチカラ」を引き出すのがこの武術遊びの目的です。
このような「筋力でないチカラ」にとって,転倒しないようにバランスをとっている筋力は,いわばブレーキです。つまり,骨盤崩しによる「チカラ」は,筋力によるブレーキを外すことによって解放される「チカラ」ということができます。
体幹内の「動滑車」にスイッチを入れる
さて,今回の原理「体幹内処理」では,武術遊び「骨盤崩し」を「添え立ち」に応用する方法をご紹介します。この原理を利用すると,前回の「添え立ち」よりもさらに垂直に立ち上がらせているように見えるため,しばしば足腰の筋力で相手を持ち上げているように誤解されます。しかし,やってみればわかりますが,相当足腰を鍛えても,筋力で同じことをやるのは難しいのです。添え立ちの技術そのものは,前回ご紹介したとおりですが,今回は図2のように,立ち上がる瞬間に骨盤を操作することによって「チカラ」を引き出しています。これまでの技術は外から見て比較的理解しやすかったと思いますが,今回はほとんどが文字通り「体幹内」の骨盤を起点に行われているため,表面上は何をやっているか,どこが違うのかは非常にわかりにくいと思います。
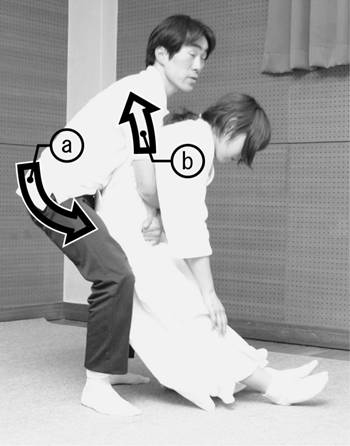 |
| 図2 骨盤の動きと全身の感覚の変化 体はまっすぐのまま,骨盤をわずかに下げて前方に出す(図中a)ようにする。すると,腕が上がり,脚が伸び上がる感覚が自動的に出てくる(図中b)ので,その感覚に合わせ,相手と一体になって立ち上がる。(「添え立ち」の方法については第6回参照のこと) |
どんな技術でもそうだと思いますが,技術が洗練されるにつれて無駄な動きがなくなり,表面上の動きがわかりにくくなっていきます。今回の場合,最大のポイントは骨盤の働きです。骨盤をほんのわずか,表からはほとんど気がつかないくらい動かすことで大きな「チカラ」が産み出されるのです。
第5回の「重心移動の原理」が「滑車」だとすれば,今回の「体幹内処理の原理」は,ちょうど複数の動滑車が動いているような感覚があります。滑車は力の方向をコントロールするだけですが,複数の動滑車を組み合わせることで相手の重さが半分,1/4……となるのは理科の授業で習った通りです。骨盤を前に出すと,それがスイッチとなって,身体の中に眠っていた動滑車が一気に動き出す。そういう感じをつかめれば,思いのほか楽に相手の身体が持ち上がってきます。逆にそういう感覚がつかめない時には,危険ですので無理に力で持ち上げないでほしいと思います。
微妙な角度を感覚でコントロール
この技術では,骨盤の角度のわずかなズレが,大きく効果を左右します。以前,身体障害者の方と街のバリアフリーを考える調査で,一日車椅子で過ごしたことがありました。その中で印象に残ったのが,普段,平らだと思っているような道が,意外にも角度がついていたということです。歩いていては気がつかないような坂道だったのですが,車椅子に乗ると,その角度を強く実感しました。
分度器上では小さな角度(おそらく1,2度)に思える差が,車椅子には大きな影響を与えてきます。それと同じように,骨盤の角度も少しずれるだけで,大きく効果が変わってくるのです。
骨盤の角度については具体的に何度くらい,ということは言えません。あくまでも,身体の内部の感覚によって調整するしかないのです。他人の決めた基準に従うのではなく,自分自身の中にある「感覚」を発見していく作業を楽しむことができると,意外に早く「体幹内処理」を実感できると思います。
「自分の身体」を探検する
ただし,こうした私の説明が本当に正しいのか,ということは実のところよくわかりません。そもそも身体の中でどのようなことが起こっているのかを正確に伝えることは不可能に近いですし,仮にもっとうまく説明できたとしても,習得するためには個人個人の感覚を頼りに練習するしかないだろうと思います。ですから,今回の解説,特に身体内部の感覚に関しては,あくまで私個人のものとしてご理解いただき,取り組みへの参考としていただきたいと思います。古武術介護は,やっていることは非常に具体的なのですが,方法論はどうしても抽象的になってしまいます。しかし,単純に「できる」「できない」ではなく,まずは自分自身の身体に向き合っていただければと思います。古武術介護を通して,他人によって規定された身体でなく,自分の身体を自分で探検し,発見する楽しさを実感してください。
今回は骨盤のわずかな動きによって,身体の内部を効率よく働かせる「体幹内処理」をご紹介しました。次回は原理その6「足裏の垂直離陸」を通して,介護への応用を考えたいと思います。
イラスト:海谷 和秀
(次回につづく)
岡田慎一郎氏講習会情報
◆新宿教室(tel:03-3344-1945)
|
岡田慎一郎氏プロフィール
介護福祉士,介護支援専門員。古武術の身体操法を応用した介護術を研究。岡田慎一郎氏への質問・講演依頼等は岡田慎一郎氏公式サイト(http://shinichiro-okada.com/)まで。
|
|||||||||||||||||
【関連情報】
●岡田慎一郎氏の最新刊 『DVD+BOOK 古武術介護実践編』 (動画配信中!)
●岡田慎一郎氏が最新技術を紹介する「こんな方法もあるかもしれない――介護発,武術経由の身体論」は,『看護学雑誌』で2008年1月号(Vol.72 No.1)より2010年3月号(Vol.74 No.3)まで連載。電子ジャーナル「MedicalFinder」からも検索・閲覧・購入できます。
●岡田慎一郎氏の公式サイトは こちら です。


